#驚きと感動を与えるワインづくり
Photo

1937年の創業の勝沼醸造さんの元へ 勝沼といえばこちらですよね 専用の試飲用のカードを作成して試飲しまくりました 売店がめちゃくちゃおしゃれ 働いている方々がとても楽しそうでした フランス醸造技術者協会主催の国際ワインコンテスト『ヴィナリーインターナショナル』にて数々の賞を受賞している実力派 良いワインは良いぶどうからとのこだわりを持ち、時間と手間を惜しまず、みずから良質なぶどう栽培に取り組んでいるとの事 #勝沼醸造 #勝沼 #山梨 #世界一高いワイン製造コストを肯定 #浸透膜濃縮装置 #氷結濃縮法 #日本ワインの先端 #世界に通じるワインづくりに挑戦 #醸造工程にこだわる #価格以上の価値 #驚きと感動を与えるワインづくり #イタリアン #ペペロッソ #日本ワインあります #オールドレンズ #OFFICINEGALILEOTEROG4cmf4 #OFFICINEGALILEO #TEROG #HEIF #HEIF422 #sony #α1 (勝沼醸造) https://www.instagram.com/p/CjAnF65vajo/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#勝沼醸造#勝沼#山梨#世界一高いワイン製造コストを肯定#浸透膜濃縮装置#氷結濃縮法#日本ワインの先端#世界に通じるワインづくりに挑戦#醸造工程にこだわる#価格以上の価値#驚きと感動を与えるワインづくり#イタリアン#ペペロッソ#日本ワインあります#オールドレンズ#officinegalileoterog4cmf4#officinegalileo#terog#heif#heif422#sony#α1
0 notes
Text
【SPN】庭師と騎士
警告:R18※性描写、差別的描写
ペアリング:サム/ディーン、オリキャラ/ディーン
登場人物:ディーン・ウィンチェスター、サム・ウィンチェスター、ボビー・シンガー・ルーファス・ターナー、ケビン・トラン、チャーリー・ブラッドベリー、クラウス神父(モデル:クラウリー)
文字数:約16000字
設定: 修道院の囚われ庭師ディーン(20)と宿を頼みに来た騎士サム(24)。年齢逆転、中世AU。
言い訳: 映画「天使たちのビッチナイト」に影響を受けました。ボソボソと書いてましたがちょっと行き詰まり、詰まってまで書くほどのものじゃないので一旦停止します。
◇
自分のことなら肋骨の二本や三本が折れていたとしても気づかないふりをしていられるが、部下たちを休ませる必要があった。
王国騎士の象徴である深紅のマントは彼ら自身の血に染められ、疲労と傷の痛みとで意識がもうろうとしている者も数名いた。何よりも空腹だった。狩りをしようにも、矢がなく、矢を作るためにキャンプを張る体力もない。
一度腰を下ろせばそこが墓地になるかもしれなかった。
辺境の村を救うために命じられた出征だった。王はどこまで知っていたのか……。おそらくは何も知らなかったのに違いない。そうだと信じたかった。辺境の村はすでに隣国に占領されていた。彼らは罠にかけられたのだった。
待ち構えていた敵兵に大勢の仲間の命と馬を奪われ、サムは惨めな敗走を余儀なくされた。
森の中を、王城とは微妙にずれた方向へ進んでいるのに、サムに率いられた騎士たちは何もいわなかった。彼らもまた、サムと同じ疑いを胸に抱いていたのだ。全ては王に仕組まれたのではないかと。
誰一人口には出さなかったが、森の中をさ迷うサムに行き先を尋ねる者もいなかった。
なけなしの食糧を持たせて斥候に出していたケビンが、隊のもとに戻ってきた。彼は森の中に修道院を発見した。サムはその修道院に避難するべきか迷った。森は王国の領内だ。もしも王が裏切っていた場合、修道院にまで手を回されていたら彼らは殺される。
だが、このままでは夜を越せない者もいるかもしれなかった。サムは未だ六人の騎士を率いていて、王国よりサムに忠実な彼らを何としても生かさなければならない。
サムはケビンに案内を命じた。
◇
ディーンは自分の名前を気に入っていたが、今ではその名前を呼ぶ者はほとんどいなかった。
修道院では誰もがディーンのことを「あれ」とか「そこの」とか表現する。もしくは彼自身の職業である「庭師」とか。彼自身に、直接呼びかける者はいない。なぜなら彼は耳が聞こえないし、口も利けないから。
ディーンは今年で二十歳になる……らしい。彼は子供のころに両親を盗賊に殺されて、もともと身を寄せる予定だったこの修道院に引き取られた。ただし支払うべき寄付金も盗賊に奪われたので、修道士としてではなく庭師として働いて暮らしている。
夜中、ディーンはフラフラになりながら修道院を出て、納屋に帰り着いた。家畜小屋の横の納屋が彼の住処だ。神父が彼に酒を飲ませたので、藁の下に敷いた板のわずかな段差にも躓いてしまった。
そのまま藁の中にうずくまって、眠ってしまおうと思った時だ。納屋の戸の下の隙間から、赤い炎の色と複数の人影がちらついて見えた。
ディーンは、静かに身を起こした。少し胸やけはするが、幻覚を見るほど酔ってはいない。ディーンがいる納屋は、修道院の庭の中にある。修道士たちをオオカミやクマから守る塀の、内側だ。修道士たちは夜中にうろついたりしないから、この人影は外部からの――塀の外、森からの――侵入者たちのものだ。
門番の爺さんは何をしていたのか。もちろん、寝ているんだろう、夜更かしするには年を取りすぎている。今までも修道院が盗賊被害には遭ったことはあるが、こんな夜中じゃなかった。オオカミにとってはボロを着ていようが聖職者のローブを着ていようが肉は肉。強襲も山菜取りも日差しの入る間にやるのが最善だ。
では何者か。ディーンはそっと戸を開けて姿を見ようとした。ところが戸に手をかける間もなく、外から勢いよく開けられて転がり出てしまう。うつ伏せに倒れた鼻先に松明の火を受けてきらめく刃のきっさきを見て、そういえば、神父に持たされたロウソクが小屋の中で灯しっぱなしだったなと気づく。
「こそこそと覗き見をしていたな」 ざらついて低い声がディーンを脅した。ディーンはその一声だけで、彼がとても疲れて、痛みを堪えているのがわかった。
「やめろ、ルーファス! 何をしている」
若い男の声がした。ディーンを脅している男は剣のきっさきを外に向けた。「こいつが、俺たちを見張っていた。きっと刺客だ。俺たちがここに来るのを知っていて、殺そうとしてたんだ」
刺客、という言葉に、側にいた男たちが反応した。いったい何人いるんだ。すっかりと敵意を向けられて、ディーンはひるんだ。
「馬鹿な、彼を見ろ。丸腰だ。それに刺客なら小屋の中でロウソクなんて灯して待っているわけがない」 若い声の男が手を握って、ディーンを立たせた。俯いていると首から上が視界にも入らない。とても背の高い男だった。
「すまない、怖がらせてしまった。我々は……森で迷ってしまって、怪我を負った者もいる。宿と手当てが必要で、どうかここを頼らせてもらいたいと思って訪ねた」
背の高さのわりに、威圧的なところのない声だった。ディーンが頷くのを見て、男は続けた。
「君は――君は、修道士か?」 ディーンは首をかしげる。「そうか、でも、ここの人間だ。そうだろ? 神父に会わせてもらえるかい?」 ディーンはまた、首をかしげる。
「なんだ、こいつ、ぼんやりして」 さっき脅してきた男――闇夜に溶け込むような黒い肌をした――が、胡乱そうに顔をゆがめて吐き捨てる。「おお、酒臭いぞ。おおかた雑用係が、くすねた赤ワインをこっそり飲んでいたんだろう」
「いや、もしかして――君、耳が聞こえないの?」 若い男が自分の耳辺りを指さしてそういったので、ディーンは頷いた。それから彼は自分の口を指さして、声が出ないことをアピールする。
男の肩が一段下がったように見えて、ディーンは胸が重くなった。相手が自分を役立たずと判断して失望したのがわかるとき、いつもそうなる。
彼らは盗賊には見えなかった。何に見えるかって、それは一目でわかった。彼らは深紅の騎士だ。王国の誇り高い戦士たち。
幼いころに憧れた存在に囲まれて、これまで以上に自分が矮小な存在に思えた。
「聞こえないし、しゃべれもしないんじゃ、役に立たない。行こう、ケビンに神父を探させればいい」 疲れた男の声。
抗議のため息が松明の明かりの外から聞こえた。「また僕一人? 構いませんけどね、僕だって交渉するには疲れ過ぎて……」
「一番若いしまともに歩いてるじゃないか! 俺なんか見ろ、腕が折れて肩も外れてる、それに多分、日が上る前に止血しないと死ぬ!」
ディーンは初めて彼らの悲惨な状態に気が付いた。
松明を持っているのは一番背の高い、若い声の男��、彼はどうやら肋骨が折れているようだった。肩が下がっているのはそのせいかもしれなかった。ルーファスと呼ばれた、やや年配の黒い肌の男は、無事なところは剣を握った右腕だけというありさまだった。左半身が黒ずんでいて、それが全て彼自身の血であるのなら一晩もたないというのも納得だ。女性もいた。兜から零れた髪が松明の炎とそっくりの色に輝いて見えた。しかしその顔は血と泥で汚れていて、別の騎士が彼女の左足が地面に付かないように支えていた。その騎士自身も、兜の外された頭に傷を受けているのか、額から流れた血で耳が濡れている。
六人――いや、七人だろうか。みんな満身創痍だ。最強の騎士たちが、どうしてこんなに傷ついて、夜中に森の中をゆく羽目に。
ディーンは松明を持った男の腕を引っ張った。折れた肋骨に響いたのか、呻きながら彼は腕を振り払おうとする。
「待って、彼、案内してくれるんじゃない? 中に、神父様のところに」 女性の騎士がそういった。ディーンはそれを聞こえないが、何となく表情で理解した振りをして頷き、ますます騎士の腕を引っ張った。
騎士はそれきりディーンの誘導に素直についてきた。彼が歩き出すとみんなも黙って歩き出す。どうやらこの背の高い男が、この一団のリーダーであるらしかった。
修道院の正面扉の鍵はいつでも開いているが、神父の居室はたいていの場合――とりわけ夜はそうだ――鍵がかかっている。ディーンはいつも自分が来たことを示す独特のリズムでノックをした。
「……なんだ?」 すぐに扉の向こうで、眠りから起こされて不機嫌そうな声が聞こえてほっとする。もう一度ノックすると、今度は苛立たし気に寝台から降りる音がした。「なんだ、ディーン、忘れ物でもしたのか……」
戸を開いた神父は、ディーンと彼の後ろに立つ騎士たちの姿を見て、ぎょっとして仰け反った。いつも偉そうにしている神父のそんな顔を見られてディーンは少しおかしかった。
ディーンは背の高い男が事情を説明できるように脇にのいた。
「夜半にこのような不意の訪問をして申し訳ない。緊急の事態ですのでどうかお許し頂きたい。私は王国騎士のサミュエル・ウィンチェスター。彼は同じく騎士のルーファス。彼は重傷を負っていて一刻も早い治療が必要です。他にも手当と休息が必要な者たちがいる」
神父は、突然現れた傷だらけの騎士たちと、さっき別れたばかりの庭師を代わる代わる、忙しなく視線を動かして見て、それから普段着のような体面をするりと羽織った。深刻そうに頷き、それから騎士たちを安心させるようにほほ笑む。「騎士の皆様、もう安全です。すぐに治癒師を呼びます。食堂がいいでしょう、治療は厨房で行います。おい」 目線でディーンは呼びかけられ、あわてて神父のひざ元に跪いて彼の唇を読むふりをする。
「治癒師を、起こして、食堂に、連れてきなさい。わかったか?」
ディーンは三回頷いて、立ち上がると治癒師のいる棟へ駆け出す。
「ご親切に感謝する」 男のやわらかい礼が聞こえる。「……彼はディーンという名なのか? あとでもう一度会いたい、ずいぶんと怖がらせてしまったのに、我々の窮状を理解して中へ案内してくれた……」
ディーンはその声を立ち止まって聞いていたかったが、”聞こえない”のに盗み聞きなどできるはずがなかった。
◇
明け方にルーファスは熱を出し、治癒師は回復まで数日はかかるだろうといった。サムは騎士たちと目を合わせた。今はまだ、森の深いところにあるこの修道院には何の知らせも来ていないようだが、いずれは王国から兵士が遣わされ、この当たりで姿を消した騎士たち――”反逆者たち”と呼ばれるかもしれない――がいることを知らされるだろう。俗世から離れているとはいえ修道院には多くの貴族や裕福な商家の息子が、いずれはまた世俗へ戻ることを前提にここで生活している。彼らの耳に王宮での噂が届いていないことはまずあり得なく、彼らがどちらの派閥を支持しているかはサムにはわからない。もっとも王が追っている失踪騎士を庇おうなどという不届きな者が、たくさんいては困るのだった。
出征の命令が罠であったのなら、彼らは尾けられていたはずだった。サムの死体を探しに捜索がしかれるのは間違いない。この修道院もいずれ見つかるだろう。長く留まるのは良策ではない。
かといって昏睡状態のルーファスを担いで森に戻るわけにもいかず、止む無くサムたちはしばらくの滞在を請うことになった。
修道院長のクラウス神父は快く応じてくれたが、用意されたのは厨房の下の地下室で、そこはかとなく歓迎とは真逆の意図を読み取れる程度には不快だった。彼には腹に一物ありそうな感じがした。サムの予感はしばしば王の占い師をも勝るが、騎士たちを不安させるような予感は口には出せなかった。
厨房の火の前で休ませているルーファスと、彼に付き添っているボビーを除く、五人の騎士が地下に立ち尽くし、ひとまず寝られる場所を求めて目をさ迷わせている。探すまでもない狭い空間だった。横になれるのは三人、あとの二人は壁に寄せた空き箱の上で膝を枕に眠るしかないだろう。
「お腹がすいた」 疲れて表情もないチャーリーが言った。「立ったままでもいいから寝たい。でもその前に、生の人参でもいいから食べたいわ」
「僕も同感。もちろんできれば生じゃなくて、熱々のシチューに煮込まれた人参がいいけど」
ガースの言葉に、チャーリーとケビンが深い溜息をついた。
地下室の入口からボビーの声が下りてきた。「おい、今から食べ物がそっちに行くぞ」
まるでパンに足が生えているかのように言い方にサムが階段の上に入口を見上げると、ほっそりした足首が現れた。
足首の持ち主は片手に重ねた平皿の上にゴブレットとワイン瓶を乗せ、革の手袋をはめたもう片方の手には湯気のたつ小鍋を下げて階段を下りてきた。
家畜小屋の隣にいた青年、ディーンだった。神父が彼を使いによこしたのだろう。
「シチューだ!」 ガースが喜びの声を上げた。チャーリーとケビンも控え目な歓声を上げる。みんなの目がおいしそうな匂いを発する小鍋に向かっているのに対し、サムは青年の足首から目が離せないでいた。
彼はなぜ裸足なんだろう。何かの罰か? 神父は修道士や雑用係に体罰を与えるような指導をしているのか? サムは薄暗い地下室にあってほの白く光って見える足首から視線を引きはがし、もっと上に目をやった。まだ夜着のままの薄着、庭でルーファスが引き倒したせいで薄汚れている。細いが力のありそうなしっかりとした肩から腕。まっすぐに伸びた首の上には信じられないほど繊細な美貌が乗っていた。
サムは青年から皿を受け取ってやろうと手を伸ばした。ところがサムが皿に手をかけたとたん、びっくりした彼はバランスを崩して階段を一段踏みそこねた。
転びそうになった彼を、サムは慌てて抱き止めた。耳元に、彼の声にならない悲鳴のような、驚きの吐息を感じる。そうだ、彼は耳が聞こえないのだった。話すことが出来ないのはわかるが、声を出すこともできないとは。
「急に触っちゃだめよ、サム!」 床に落ちた皿を拾いながらチャーリーがいう。「彼は耳が聞こえないんでしょ、彼に見えないところから現れたらびっくりするじゃない」
「ディーンだっけ? いや、救世主だ、なんておいしそうなシチュー、スープか? これで僕らは生き延びられる」 ガースが恭しく小鍋を受け取り、空き箱の上に並べた皿にさっさと盛り付けていく。階段の一番下でサムに抱き止められたままのディーンは、自分の仕事を取られたように見えたのか焦って体をよじったが、サムはどうしてか離しがたくて、すぐには解放してやれなかった。
まったく、どうして裸足なんだ?
修道士たちが詩を読みながら朝食を終えるのを交代で横になりながら過ごして待ち、穴倉のような地下室から出て騎士たちは食堂で体を伸ばした。一晩中ルーファスの看病をしていたボビーにも休めと命じて、サムが代わりに厨房の隅に居座ることにした。
厨房番の修道士は彼らがまるでそこに居ないかのように振る舞う。サムも彼らの日課を邪魔する意思はないのでただ黙って石窯の火と、マントでくるんだ藁の上に寝かせた熟練の騎士の寝顔を見るだけだ。
ルーファスは気難しく人の好き嫌いが激しい男だが、サムが幼い頃から”ウィンチェスター家”に仕えていた忠臣だ。もし彼がこのまま目覚めなかったら……。自分が王宮でもっとうまく立ち回れていたら、こんなことにはならなかったかもしれない。
若き王の父と――つまり前王とサムの父親が従弟同士だったために、サムにも王位継承権があった。実際、前王が危篤の際には若すぎる王太子を不安視する者たちからサムを王にと推す声も上がった。不穏な声が派閥化する前にサムは自ら継承権を放棄し、領地の大半を王に返還して王宮に留まり一騎士としての振る舞いに徹した。
その無欲さと節制した態度が逆に信奉者を集めることとなり、サムが最も望まないもの――”ウィンチェスター派”の存在が宮殿内に囁かれるようになった。国王派――この場合は年若き王をいいように操ろうとする老練な大臣たちという意味だ――が敵意と警戒心を募らせるのも無理はないとサムが理解するくらいには、噂は公然と囁かれた。何とか火消しに回ったが、疑いを持つ者にとっては、それが有罪の証に見えただろう。
自分のせいで部下たちを失い、また失いつつあるのかと思うと、サムはたまらないむなしさに襲われた。
ペタペタと石の床を踏む足音が聞こえ顔を上げる。ディーンが水差しを持って厨房にやってきた。彼は石窯の横に置かれた桶の中に水を入れる。サムは声もかけずに暗がりから彼の横顔をぼうっと眺めた。声をかけたところで、彼には聞こえないが――
床で寝ているルーファスが呻きながら寝返りを打った。動きに気づいたディーンが彼のほうを見て、その奥にいるサムにも気づいた。
「やあ」 サムは聞こえないとわかりつつ声をかけた。まるきり無駄ではないだろう。神父の唇を読んで指示を受けていたようだから、言葉を知らないわけではないようだ。
彼が自分の唇を読めるように火の前に近づく。
「あー、僕は、サムだ。サム、王国の騎士。サムだ。君はディーン、ディーンだね? そう呼んでいいかい?」
ディーンは目を丸く見開いて頷いた。零れそうなほど大きな目だ。狼を前にしたうさぎみたいに警戒している。
「怖がらないでいい。昨夜はありがとう。乱暴なことをしてすまなかった。怪我はないか?」
強ばった顔で頷かれる。彼は自らの喉を指して話せないことをアピールした。サムは手を上げてわかっていることを示す。
「ごめん――君の仕事の邪魔をするつもりはないんだ。ただ、何か困ってることがあるなら――」 じっと見つめられたまま首を振られる。「――ない?」 今度は頷かれる。「――……そうか、わかった。邪魔をして���めん」
ディーンは一度瞬きをしてサムを見つめた。彼は本当に美しい青年だった。薄汚れてはいるし、お世辞にも清潔な香りがするとは言い難かったが、王宮でもお目にかかったことのないほど端正な顔立ちをしている。こんな森の奥深くの修道院で雑用係をしているのが信じられないくらいだ。耳と口が不自由なことがその理由に間違いないだろうが、それにしても――。
水差しの水を全て桶に注いでしまうと、ディーンはしばし躊躇った後、サムを指さして、それから自分の胸をさすった。
彼が動くのを眺めるだけでぼうっとしてしまう自分をサムは自覚した。ディーンは何かを伝えたいのだ。もう一度同じ仕草をした。
「君の? 僕の、胸?」 ディーンは、今度は地下に繋がる階段のほうを指さして、その場で転ぶ真似をした。そしてまたサムの胸のあたりを指さす。
理解されてないとわかるとディーンの行動は早かった。彼はルーファスをまたいでサムの前にしゃがみ込み、彼の胸に直接触れた。
サムは戦闘中以外に初めて、自分の心臓の音を聞いた。
ディーンの瞳の色は鮮やかな新緑だった。夜にはわからなかったが、髪の色も暗い金髪だ。厨房に差し込む埃っぽい日差しを浴びてキラキラと輝いている。
呆然と瞳を見つめていると、やっとその目が自分を心配していることに気が付いた。
「……ああ、そっか。僕が骨折してること、君は気づいてるんだね」 ”骨折”という言葉に彼が頷いたので、サムは納得した。さっき階段から落ちかけた彼を抱き止めたから、痛みが悪化していないか心配してくれたのだろう。サムは、彼が理解されるのが困難と知りながら、わざわざその心配を伝えようとしてくれたことに、非常な喜びを感じた。
「大丈夫だよ、自分で包帯を巻いた。よくあることなんだ、小さいころは馬に乗るたびに落馬して骨を折ってた。僕は治りが早いんだ。治るたびに背が伸びる」
少し早口で言ってしまったから、ディーンが読み取ってくれたかはわからなかった。だが照れくさくて笑ったサムにつられるように、ディーンも笑顔になった。
まさに魂を吸い取られるような美しさだった。魔術にかかったように目が逸らせない。完璧な頬の稜線に触れたくなって、サムは思わず手を伸ばした。
厨房の入口で大きな音がした。ボビーが戸にかかっていたモップを倒した音のようだった。
「やれやれ、どこもかしこも、掃除道具と本ばかりだ。一生ここにいても退屈しないぞ」
「ボビー?」
「ああ、水が一杯ほしくてな。ルーファスの調子はどうだ?」
サムが立ち上がる前に、ディーンは驚くほどの素早さで裏戸から出て行ってしまった。
◇
キラキラしてる。
ディーンは昔からキラキラしたものに弱かった。
木漏れ日を浴びながら一時の昼寝は何物にも得難い喜びだ。太陽は全てを輝かせる。泥だまりの水だってきらめく。生まれたばかりの子ヤギの瞳、朝露に濡れた花と重たげな羽を開く蝶。礼拝堂でかしずいた修道士の手から下がるロザリオ。水差しから桶に水を注ぐときの小気味よい飛沫。
彼はそういったものを愛していた。キラキラしたものを。つまりは美しいもの。彼が持ち得なかったもの。
サムという騎士はディーンが今までに見た何よりも輝いていた。
あまりにもまぶしくて直視しているのが辛くなったほどだ。彼の瞳の色に見入っていたせいで、厨房で大きな音に反応してしまった。幸いサムは音を立てた騎士のほうに目がいってディーンの反応には気づかなかったようだ。
もう一度彼の目を見て彼に触れてみたかったが、近づくのが恐ろしくもあった。
ディーン何某という男の子がこの世に生を受けたとき、彼は両親にとても祝福された子供だった。彼は美しい子だと言われて育った。親というのは自分の子が世界で一番美しく愛らしいと信じるものだから仕方ない。おかげでディーンは両親が殺され、修道院に引き取られる八つか九つの頃まで、自分が怪物だと知らずに生きてこられた。
修道院長のクラウス神父は親と寄付金を失った彼を憐れみ深く受け入れてくれたが、幼い孤児を見る目に嫌悪感が宿っているのをディーンは見逃さなかった。
「お前は醜い、ディーン。稀に見る醜さだ」と神父は、気の毒だが率直に言わざるを得ないといった。「その幼さでその醜さ、成長すれば見る者が怖気をふるう怪物のごとき醜悪な存在となるだろう。無視できない悪評を招く。もし怪物を飼っていると噂が立てば、修道院の名が傷つき、私と修道士たちは教会を追われるだろう。お前も森に戻るしかなくなる」 しかしと神父は続けた。「拾った怪物が不具となれば話は違う。耳も聞こえなければ口もきけないただの醜い哀れな子供を保護したとなれば、教皇も納得なさるだろう。いいかね、ディーン。お前をそう呼ぶのは今日この日から私だけだ。他の者たちの話に耳を傾けてはいけないし、口を聞いてもいけない。おまえは不具だ。不具でなければ、ここを追い出される。ただの唾棄すべき怪物だ。わかったかね? 本当にわかっているなら、誓いを立てるのだ」
「神様に嘘をつけとおっしゃるのですか?」
まろやかな頬を打たれてディーンは床に這いつくばった。礼拝堂の高窓から差し込む明かりを背負って神父は怒りをあらわにした。
「何という身勝手な物言いだ、すでに悪魔がその身に宿っている! お前の言葉は毒、お前の耳は地獄に通じている! 盗賊どもがお前を見逃したのも、生かしておいたほうが悪が世に蔓延るとわかっていたからに違いない。そんな者を神聖な修道院で養おうとは、愚かな考えだった。今すぐに出ていきなさい」
ディーンは、恐ろしくて泣いてすがった。修道院を追い出されたら行くところがない。森へ放り出されたら一晩のうちに狼の餌食になって死んでしまうだろう。生き延びられたとしても、神父ですら嫌悪するほど醜い自分が、他に受け入れてくれる場所があるはずもない。
ディーンは誓った。何度も誓って神父に許しを請うた。「話しません、聞きません。修道院のみなさまのご迷惑になることは決してしません。お願いです。追い出さないでください」
「お前を信じよう。我が子よ」 打たれた頬をやさしく撫でられ、跪いてディーンを起こした神父に、ディーンは一生返せぬ恩を負った。
ぼんやりと昔を思い出しながら草をむしっていたディーンの手元に影が落ちた。
「やあ、ディーン……だめだ、こっちを向いてもらってからじゃないと」 後ろでサムがぼやくのが聞こえた。
ディーンは手についた草を払って、振り向いた。太陽は真上にあり、彼は太陽よりも背が高いことがわかって、ディーンはまた草むしりに戻った。
「あの、えっと……。ディーン? ディーン」
正面に回り込まれて、ディーンは仕方なく目線を上げた。屈んだサムはディーンと目が合うと、白い歯をこぼして笑った。
ああ、やっぱりキラキラしてる。
ディーンは困った。
◇
サムは困っていた。どうにもこの雑用係の庭師が気になって仕方ない。
厨房から風のように消えた彼を追って修道院の中庭を探していると、ネズの木の下で草をむしっている背中を見つけた。話しかけようとして彼が聞こえないことを改めて思い出す。聞こえない相手と会話がしたいと思うなんてどうかしてる。
それなのに気づけば彼の前に腰を下ろして、身振り手振りを交えながら話しかけていた。仕事中のディーンは、あまり興味のない顔と時々サムに向けてくれる。それだけでなぜか心が満たされた。
ネズの実を採って指の中で転がしていると、その実をディーンが取ろうとした。修道院の土地で採れる実は全て神が修道士に恵まれた貴重なもの――それがたとえ一粒の未熟な実でも――だからサムは素直に彼に渡してやればよかった。だがサムは反射的に手をひっこめた。ディーンの反応がみたかったのだ。彼は騎士にからかわれて恥じ入るような男か、それとも立ち向かってくるか? 答えはすぐにわかった。彼は明らかにむっとした顔でサムを見上げ、身を乗り出し手を伸ばしてきた。
サムはさらに後ろに下がり、ディーンは膝で土を蹴って追いすがる。怒りのせいか日差しを長く浴びすぎたせいか――おそらくそのどちらも原因だ――額まで紅潮した顔をまっすぐに向けられて、サムは胸の奥底に歓喜が生まれるのを感じた。
「ハハハ……! ああ……」 するりと言葉がこぼれ出てきた。「ああ、君はなんて美しいんだ!」
ディーンがサムの手を取ったのと、サムがディーンの腕を掴んだのと、どちらが早かったかわからかない。サムはディーンに飛びつかれたと思ったし、ディーンはサムに引き倒されたと思ったかもしれない。どっちにしろ、結果的に彼らはネズの根のくぼみに入ってキスをした。
長いキスをした。サムはディーンの髪の中に手を入れた。やわらかい髪は土のにおいがした。彼の唾液はみずみずしい草の味がした。耳を指で挟んで引っ張ると、ん、ん、と喉を鳴らす音が聞こえた。とても小さな音だったが初めて聞いた彼の”声”だった。もっと聞きたくて、サムは色んなところを触った。耳、うなじ、肩、胸、直接肌に触れたくて、腹に手を伸ばしたところでディーンが抵抗した。
初めは抵抗だとわからなかった。嫌なことは嫌と言ってくれる相手としか寝たことがなかったからだ。ところが強く手首を掴まれて我に返った。
「ごめん!」 サムは慌てて手を離した。「ご、ごめん、本当にごめん! こんなこと……こんなことするべきじゃなかった。僕は……だめだ、どうかしてる」 額を抱えてネズの根に尻を押し付け、できるだけディーンから離れようとした。「僕はどうかしてる。いつもはもっと……何というか……こんなにがっついてなくて、それに君は男で修道院に住んでるし――ま、まあ、そういう問題じゃないけど――ディーン――本当にごめん――ディーン?」
ディーンは泣いていた。静かに一筋の涙を頬に流してサムを見ていた。
「待って!」
またも彼の身の軽さを証明する動きを見届けることになった。納屋のほうに走っていく彼の姿を、今度はとても追う気にはなれなかった。
◇
夜、クラウス神父の部屋でディーンは跪いていた。
「神父様、私は罪を犯しました。二日ぶりの告解です」
「続けて」
「私は罪を犯しました……」 ディーンはごくりとつばを飲み込んだ。「私は、自らの毒で、ある人を……ある人を、侵してしまったかもしれません」
暖炉の前に置かれたイスに座り、本を読んでいた神父は、鼻にかけていた眼鏡を外してディーンを見た。
「それは由々しきことだ、ディーン。お前の毒はとても強い。いったい誰を毒に侵したのだ。修道士か?」
「いいえ、騎士です」
「騎士! 昨日ここに侵入してきたばかりの、あの狼藉者どものことか? ディーン、おお、ディーン。お前の中の悪魔はいつになったら消えるのだろう」 神父は叩きつけるように本を閉じ、立ち上がった。「新顔とくれば誘惑せずにはおれないのか? どうやって、毒を仕込んだ。どの騎士だ」
「一番背のたかい騎士です。クラウス神父。彼の唇を吸いました。その時、もしかしたら声を出してしまったかもしれません。ほんの少しですが、とても近くにいたので聞こえたかもしれません」
「なんてことだ」
「あと、彼の上に乗ったときに胸を強く圧迫してしまったように思います。骨折がひどくなっていなければいいのですが、あとで治癒師にみてもらうことはできますか?」
「ディーン……」 神父は長い溜息をついた。「ディーン。お前の悪魔は強くなっている。聖餐のワインを飲ませても、毒を薄めることはできなかった。お前と唯一こうして言葉を交わし、お前の毒を一身に受けている私の体はもうボロボロだ」
「そんな」
「これ以上ひどくなれば、告解を聞くことも困難になるかもしれない」
ディーンはうろたえた。「神父様が許しを与えて下さらなければおれは……本物の怪物になってしまいます」
「そうだ。だから私は耐えているのだ。だが今日はこれが限界だ。日に日にお前の毒は強くなっていくからな」 神父はローブを脱いで寝台に横たわった。「頼む、やってくれ、ディーン」
ディーンは頷いて寝台に片膝を乗せると、神父の下衣を下ろして屈み込んだ。現れたペニスを手にとって丁寧に舐め始める。
「私の中からお前の毒を吸い取り、全て飲み込むのだ。一滴でも零せば修道院に毒が広がってしまう。お前のためにもそれは防がなくてはならない」
「はい、神父様」
「黙りなさい! 黙って、もっと強く吸うんだ!」 神父は厳しく叱責したが、不出来な子に向けて優しくアドバイスをくれた。「口の中に、全部入れてしまったほうがいい。強く全体を頬の内側でこすりながら吸ったほうが、毒が出てくるのも早いだろう」
心の中でだけ頷いて、ディーンはいわれた通り吸い続けた。もう何度もやっていることなのに、一度としてうまくやれたことがない。いつも最後には、神父の手を煩わせてしまう。彼は自分のために毒で苦しんでいるのにだ。
今回も毒が出る前に疲れて吸う力が弱まってしまい、神父に手伝ってもらうことになった。
「歯を立てたら地獄行きだからな。お前を地獄に堕としたくはない」 神父は忠告してから、両手でディーンの頭を抱えて上下にゆすった。昨夜はワインを飲んだあとにこれをやったからしばらく目眩が治まらなかった。今日はしらふだし、神父がこうやって手を借してくれるとすぐに終わるのでディーンはほっとした。
硬く張りつめたペニスから熱い液体が出てきた。ディーンは舌を使って慎重に喉の奥に送り、飲み込んでいった。飲み込むときにどうしても少し声が出てしまうが、神父がそれを咎めたことはなかった。ディーンが努力して抑えているのを知っているのだろう。
注意深く全て飲み込んで、それでも以前、もう出ないと思って口を離した瞬間に吹き出てきたことがあったので、もう一度根本から絞るように吸っていき、本当に終わったと確信してからペニスを解放した。神父の体は汗ばんでいて、四肢はぐったりと投げ出されていた。
ディーンはテーブルに置かれた水差しの水を自分の上着にしみこませ、神父の顔をぬぐった。まどろみから覚めたような穏やかな顔で、神父はディーンを見つめた。
「これで私の毒はお前に戻った。私は救われたが、お前は違う。許しを得るために、また私を毒に侵さねばならない。哀れな醜い我が子よ」
そういって背を向け、神父は眠りに入った。その背中をしばし見つめて、ディーンは今夜彼から与えられなかった神の許しが得られるよう、心の中祈った。
◇
修道士たちが寝静まった夜、一人の騎士が目を覚ました。
「うーん、とうとう地獄に落ちたか……どうりで犬の腐ったような臭いがするはずだ」
「ルーファス!」 ボビーの声でサムは目を覚ました。地下は狭すぎるが、サムがいなければ全員が横になれるとわかったから厨房の隅で寝ていたのだ。
「ルーファス! このアホンダラ、いつまで寝てるつもりだった!」 ボビーが歓喜の声を上げて長い付き合いの騎士を起こしてやっていた。サムはゴブレットに水を注いで彼らのもとへ運んだ。
「サミュエル」
「ルーファス。よく戻ってきた」
皮肉っぽい騎士は眉を上げた。「大げさだな。ちょっと寝てただけだ」 ボビーの手からゴブレットを取り、一口飲んで元気よく咳き込んだあと、周囲を見回す。「それより、ここはどこだ、なんでお前らまで床に寝てる?」
「厨房だよ。他の皆はこの地下で寝てる。修道院長はあまり僕らを歓迎していないみたいだ。いきなり殺されないだけマシだけどね」
「なんてこった。のん気にしすぎだ。食糧をいただいてさっさと出発しよう」
「馬鹿言ってないで寝てろ。死にかけたんだぞ」 起き上がろうとするルーファスをボビーが押し戻す。しかしその腕を掴んで傷ついた騎士は強引に起きようとする。
「おい、寝てろって」
「うるさい、腹が減って寝るどころじゃない!」
サムとボビーは顔を見合わせた。
三人の騎士は食堂に移動した。一本のロウソクを囲んで、鍋に入れっぱなしのシチューをルーファスが食べるのを見守る。
「で、どうする」 まずそうな顔でルーファスはいう。もっともルーファスは何を食べてもこういう顔だから別にシチューが腐っているわけではない。例外が強い酒を飲む時くらいで、一度密造酒を売って儲けていた商売上手な盗賊団を摘発した時には大喜びだった(酒類は国庫に押収されると知ってからも喜んでいたからサムは心配だった)。
修道院にある酒といえば聖体のワインくらいだろう。ブドウ園を持っている裕福な修道院もあるが、この清貧を絵にしたような辺境の修道院ではワインは貴重品のはずだ。ルーファスが酒に手を出せない環境でよかった。しかし――サムは思い出した。そんな貴重なワインの匂いを、あのみすぼらしい身なりの、納屋で寝ている青年は纏わせていたのだった。
「どうするって?」
ボビーが聞き返す。ルーファスは舌打ちしそうな顔になってスプーンを振った。「これからどこへ行くかってことだよ! 王都に戻って裏切者だか敗走者だかの烙印を押されて処刑されるのはごめんだぜ」
「おい、ルーファス!」
「いいんだ、ボビー。はっきりさせなきゃならないことだ」 サムはロウソクの火を見つめながらいった。「誤魔化してもしょうがない。我々は罠にかけられた。仕掛けたのは王だ。もう王都には戻れない――戻れば僕だけでなく、全員が殺される」
「もとからお前さんの居ない所で生き延びようとは思っていないさ。だが俺とルーファスはともかく……」
「若くて将来有望で王都に恋人がいる私でも同じように思ってるわよ」 チャーリーが食堂に来た。ルーファスの隣に座って平皿に移したシチューを覗き込む。「それおいしい?」
「土まみれのカブよりはな」
「なあ、今の話だが、俺はこう思ってる」 ボビーがいった。「この状況になって初めて言えることだが、王国は腐ってる。王に信念がないせいだ。私欲にまみれた大臣どもが好き放題している。民は仕える主を選べないが、俺たちは違う。もとから誰に忠義を尽くすべきか知っている。もう選んでいる。もうすでに、自分の望む王の下にいる」
「その話、なんだか素敵に聞こえる。続けて」 チャーリーがいう。
「いや、まったく素敵じゃない。むしろ危険だ」 サムはいったが、彼の言葉を取り合う者はいなかった。
ゴブレットの水を飲み干してルーファスが頷いた。「サムを王にするって? それはいい。そうしよう。四年前にあの棒みたいなガキに冠を乗せる前にそうしとけばよかったんだ。野生馬を捕まえて藁で編んだ鞍に乗り、折れた剣を振りかざして、七人の騎士で玉座を奪還する!」 そしてまた顔をしかめながらシチューを食べ始める。「俺はそれでもいいよ。少なくとも戦って死ねる」
ボビーがうなった。「これは死ぬ話じゃない。最後まで聞け、ルーファス」
「そうよ、死ぬのは怖くないけど賢く生きたっていい」 チャーリーが細い指でテーブルを叩く。「ねえ、私に案がある。ここの修道院長に相談するのよ。彼から教皇に仲裁を頼んでもらうの。時間を稼いで仲間を集める。探せば腐った大臣の中にもまだウジ虫が沸いてないヤツもいるかもしれない。血を流さなくても王を変える手はある。アダムだって冠の重さから解放されさえすればいい子に戻るわよ」
「それよりウィンチェスター領に戻ってしばらく潜伏すべきだ。あそこの領民は王よりもサムに従う。俺たちを王兵に差し出したりしない」
「だから、それからどうするのかって話よ。潜伏もいいけど結局王と対決するしかないじゃない、このまま森で朽ち果てるか北の隣国に情報を売って保護してもらって本物の売国奴になる他には!」
「ちょっと落ち着け、二人とも。修道士たちが起きてくる。それから僕の計画も聞け」
「ろくな計画じゃない」
「ルーファス! ぼやくな」
「そうよルーファス、死にかけたくせに。黙ってさっさと食べなさいよ」
サムはため息を吐きそうになるのを堪えて皆に宣言した。「王都には僕一人で行く」
「ほらな」とスプーンを放ってルーファスが特大のため息を吐いた。「ろくな計画じゃない」
◇
行商売りの見習い少年と仲良くなったことがあった。同年代の子と遊ぶのは初めてだったから嬉しくて、ディーンは思わず自分の秘密をもらしてしまった。自分の口で見の上を語る彼に、少年はそんなのはおかしいといった。
「君は神父に騙されているんだよ。君は醜くなんかない、夏の蝶の羽のように美しいよ」
「神様の家で嘘をついちゃいけないよ」
「嘘なんかじゃない。ホントにホントだよ。僕は師匠について色んな場所へ行くけれど、どんなお貴族様の家でだって君みたいな綺麗な人を見たことがないよ」
ディーンは嬉しかった。少年の優しさに感謝した。次の日の朝、出発するはずの行商売りが見習いがいなくなったと騒ぎ出し、修道士たちが探すと、裏の枯れ井戸の底で見つかった。
井戸は淵が朽ちていて、遺体を引き上げることもできなかった。神父は木の板で封印をした。ひと夏の友人は永遠に枯れ井戸の中に閉じ込められた。
修道院は巨大な棺桶だ。
ディーンは二度と友人を作らなかった。
1 note
·
View note
Text
「子どもだと思ってからかわないで…」「大人をもてあそぶものじゃないよ、きみ」
「勇利、デートしないか?」
ヴィクトルにそう誘われたとき、いったいどういうつもりなのだろうと勇利はあきれてしまった。勇利は、デートだとか、色恋だとか、そういったことにはうとく、経験もなく、そんなことよりスケートのことで頭がいっぱいだという性質なのだ。それをヴィクトルも知っているはずなのにデートをしようとはどういう了見だろう。きっとヴィクトルのことだから、「好きな子はいるの?」「愛されたことを思い出すんだ」と言ったときのようなかるい気持ちなのだろう。あるいは、勇利はそういうことをしないから、体験させてそういった方面の情緒も伸ばそうとしているのかもしれない。ヴィクトルとしては親切のつもりなのだ。大きなお世話だからほうっておいて欲しいと勇利は考えた。ぼくが子どもだと思って……。
勇利はそっけなく断ろうとした。実際、「しません」と言うために口をひらきさした。しかし、その直前で思い直した。ヴィクトルのこれまでの傾向からして、一度断っても、これからさき、何度もそういうことを言ってくるだろう。そのたびに勇利はむっとすることになる。それなら、一度付き合って、そのあとは二度と誘ってこないようにしたほうがよい。そうしよう。勇利は決心し、おとがいをつんと上げて答えた。
「いいよ」
「本当かい? うれしいな」
ヴィクトルがにっこりした。まるで本当に喜んでいるみたいだ。勇利は感心してしまった。きっとヴィクトルのデートとは、誘うところからもう始まっているのだろう。相手をよい気分にさせるものなのだ。
「じゃあ明日、十時に」
ヴィクトルが待ち合わせ場所を指定した。一緒に住んでるのに外で会うわけ!? 勇利は声を大きくして反対しそうになったけれど、慌てて口をつぐんだ。きっとそういうものなのだろう。デートについて何も知りませんという幼さを示すことはない。当たり前のような顔をしていなければ。「やっぱり勇利は子どもだ。こういう子どもっぽさが心配なんだ」とあなどられてしまう。
「わかった」
勇利は落ち着きはらってうなずいた。ヴィクトルは���っぽい瞳で勇利をじっとみつめていた。ぼくにそこまでしなくていいのにと勇利は思った。
何を着ていくのかということは大きな問題だった。正直なところをいうと、勇利は、動きやすい服装がよかった。ジャージとまではいかなくても、簡単な、かるい服が希望だったのだ。しかしそれではいけない。ヴィクトルが「勇利は完璧だ。もう俺の助けはいらない」と思い、経験のためにデートに誘うなんて考えつかなくなるように、きちっとしたところを見せなければならない。そうでなかったらこのデートの意味がない。
勇利は衣装戸棚を開け、ヴィクトルがいつか買ってくれたスーツを出した。濃い色の、勇利にしっくりと合う上質な服だ。これならドレスコードのあるような店にだって入れる。どんなところへ連れていかれても、「ぼくこんなかっこうで」「場外れなんじゃ」と戸惑うことはないだろう。髪もきちんと上げておこう。眼鏡はないと不便なのでかけておく。これは我慢するしかない。
勇利は身なりを整え、姿見で確かめてみた。変ではない。たぶん。気持ちもしっかりしている。スケートのときもそうだが、衣装というものはずいぶん精神に影響を与えるのである。
「マッカチン、ヴィクトルとデートしてくるよ」
勇利はぴんと背筋を伸ばし、余裕をもって待ち合わせ場所へ向かった。初めてのデートにすこし不安はあるけれど、そんなことではヴィクトルに子どもと思われると気を引き締め、試合にのぞむような心構えになった。そういえばヴィクトルはすでに家にいなかったようだ。さきに出たのだろう。しかし、待ち合わせ場所についても、彼の姿は見当たらなかった。どうしたんだろ……。勇利は街路灯のそばに立ち、しずかにあたりを見渡した。やはりヴィクトルはいない。彼はたいへん華があり、いるだけでぱっと目立つので、現れたらすぐにわかる。どこかに寄り道でもしているのだろうか? まだ時間はあるので遅刻ではない。
表面的には落ち着きはらって、内心では失敗しないようにしないとと不安に思いつつ待っていると、どうも通りをゆく人がちらちら自分を見ているような気がしてきて、勇利はますます心配になった。何かおかしいだろうか? 鏡では普通に見えたのだけれど、見落としでもあっただろうか。どこか妙なのだろうか。ヴィクトルが靴までそろえて見立ててくれたのだから、ちぐはぐだということはないと思うのだが。もしかしたら、単純に不釣り合いなのかもしれない。こんな上等の服、勇利には似合わないのだ。
「勇利!」
どうしよう、とたまらなく不安になったとき、ヴィクトルが背後から現れて勇利の前に立った。
「待たせてごめんね。遅れちゃったかな。どうしたの? 不安そうな顔してるね」
ヴィクトルを見た瞬間、勇利は気持ちがすっと落ち着くのを感じた。ヴィクトルだ。今日もかっこうよい。彼もスーツを着ている。なんて似合うのだろう。世界一──いや、宇宙一すてきだ。このひととデートをするのだ。
勇利は、ヴィクトルと釣り合うようにふるまわなければ、ヴィクトルに子どもと思われないようにしなければ、という気持ちで、自然と背筋が伸び、凛とした表情になった。
「べつに不安なんかじゃないよ。大丈夫。どこかへ寄ってたの?」
勇利は平然として、かすかに微笑すら浮かべて尋ねた。ヴィクトルはにっこりして、手にしていた花束を差し出した。
「これをね……。勇利よりさきについていようと思ったのに、きみはどんな花がいいだろう、あれもいい、これも欲しいと見てたら時間がかかってしまって。ごめんね」
「どうもありがとう」
勇利はヴィクトルの上品な花束を落ち着きはらって受け取った。青い花をふんだんに使った、清楚で可憐な花束だった。失敗してはならないと一生懸命勉強したので、ロシアではデートのとき花束を渡すものだと彼は知っていた。しかし、思った以上にすごいことだという気がした。優美で品のある、愛情の感じられる花々だ。自分が特別な待遇を受けているかのようである。いかにもデートっていう感じ……。勇利はどきどきしてのぼせ上がりそうになった。いけないいけない。ヴィクトルに幼稚だと思われる。これくらいもらって当たり前という顔をしていなくちゃ……。
「綺麗だね」
勇利はほほえんでささやくように言った。ヴィクトルはうっとりした目で勇利をみつめた。
「勇利のうつくしさにはかなわないけどね」
出た! ロシア男の愛情表現! いやロシア人の特徴なのかは知らないけど! 勇利は、すごいな、とまた感心してしまった。本当のデートじゃないってわかってるぼくでもめろめろになりそう……。落ち着かなくちゃ。おおはしゃぎしてる場合じゃない。お世辞お世辞……。
「その服、着てくれたんだね。やっぱり勇利に似合うね。なんて綺麗なんだ。勇利のようにうつくしいひとはいない。一緒に歩くと、見蕩れて道に迷ってしまいそうだ。気をつけるよ」
「…………」
なに!? なんなの!? いくらデートでもちょっと言いすぎじゃないの!? 勇利は不安をおぼえた。ヴィクトル、ぼくにいい経験をさせようと思って気合い入れすぎなんじゃ……。そんなに気を遣わなくてもいいのに。今日一日、この調子で続けるつもりだろうか、と勇利は心配になった。これは、「これくらい言われて当然」という顔をしているのは大変そうだ。がんばらなくては……。勇利は改めて気を引き締めた。
「ありがとう。ヴィクトルが選んでくれたからだよ。貴方はぼくのことをよくわかってるからね。愛情を感じる」
勇利は花束に頬を寄せて微笑した。
「花も、ぼくに合うようにしてくれたんだね。すごくすてき。ありがとう。照れちゃうな」
「勇利……喜んでくれてうれしいよ……」
ヴィクトルはたまらないというようにささやき、勇利の腰を引き寄せて歩きだした。勇利はぎょっとした。なんでそんなにぴったりくっついて腰をしっかり抱くんだ! いやデートだからだろうけど! 当たり前なんだろうけど! こころの準備が……。気を引き締めたわりには内心でうろたえてしまった。普段からヴィクトルは接触過多なたちだけれど、デートだと思っているときにそうされると焦ってしまう。幼い証拠だ、と勇利はすこし落ちこんだ。ヴィクトルがデートでもして大人の世界を教えてやろうと思うのも無理はない。ちゃんと、二度とそんなことを思われないようにがんばらなければ……。
「どこへ行くの?」
「ないしょ」
ヴィクトルが片目を閉じて指を一本立て、にっこりした。勇利はとろんとした目つきになった。かっこいい……。あっと、だめだだめだ……見蕩れてる場合じゃない……夢中にならないようにしないと……。
ヴィクトルがまず勇利を連れていったのは、美術館の庭園だった。とくに何かがあるわけではないけれど、そもそもサンクトペテルブルクはどこを見ても情緒的でうつくしい風景なので、ただの庭とはいえ、すてきな場所だった。
「勇利をここに連れてきたくて」
ヴィクトルはベンチに座って優しく勇利に話しかけた。
「俺がよくひとりで──あるいはマッカチンと一緒に来る場所なんだ。考えごとなんかをしたいときにね。ごく普通のところだけれど、俺にとっては大切なんだ」
勇利はうなずいた。ヴィクトルの私的な時間を使うための場所なのだろう。
「ヴィクトルの特別なんだね。教えてくれてありがとう」
勇利はこころから言った。ヴィクトルは笑みを浮かべ、勇利の肩を抱き寄せた。勇利は、近い近い、と思ったけれど、デートだし、慌てるわけにはいかないし、気恥ずかしいながらも素直にうれしかったのでじっとしていた。すこしだけ照れて、膝に置いたヴィクトルの青い花束を撫でた。
「いままで何度も来たの?」
「そうだよ。ちいさなころからずっとだ。ここは静かに過ごすのにうってつけなんだ」
「ぼくに教えたからには、ぼくがここに入り浸るかもしれないよ」
勇利はいたずらっぽく言った。本当はそんなつもりはなかった。ヴィクトルのひとりの時間を邪魔したりしない。しかしヴィクトルは笑ってうなずいた。
「いいよ。ただし、そのときは俺も一緒がいいな。何か思い煩うことがあるときは俺が勇利を助けたいよ」
ヴィクトルがあまりに熱心な様子なので、勇利は、ヴィクトルは本気で言っているのではないかとあやぶんだ。少なくとも、彼はこのときヴィクトルの言葉を信じた。あとで思い上がりだと自分にあきれるだろうけれど。
「ここで勇利と過ごせたらなとずっと考えてたんだ」
ヴィクトルは優しくつぶやいた。
「本当に勇利に教えたかったんだ……」
勇利は、自分のためのデートにしては、あまりに熱烈すぎると感じた。それとも、こういうことも経験のうちなのだろうか?
「そういうことを言うと本気にするよ」
勇利はからかうように言った。
「いいよ」
ヴィクトルはこのうえなく誠実に答えた。
「俺は真剣だ」
「…………」
勇利はどきっとし、慌てて口をひらき、たわいないことをしゃべりだした。いささかつじつまが合っていないような気もしたけれど、構うものかと思った。本当にどきどきしてしまった。だめだめ……これはヴィクトルの気遣いのデートなんだから……。
昼食に誘われた店は、格式張ってはいないけれど、上品な印象の、しゃれたレストランだった。上流階級の者が隠れ家にするような、あたたかい、ちいさなところだ。落ち着いた雰囲気は勇利をなごませた。家庭的な料理を彼は楽しみ、ヴィクトルの話にほほえみながら耳を傾けた。食事が終わったときは大満足だった。
「美味しかった。ありがとう」
「あそこは好きな店なんだ。ほかにも勇利に味わってもらいたい料理があるから、またふたりで来ようね」
「そうだね」
そのときは「デート」ではないだろうけれど、ヴィクトルと楽しい時間を過ごせるのならまた来たい。勇利は素直にうなずいた。
午後は、美術館や博物館をめぐったり、川沿いの道を散歩したりして過ごした。
「車で出掛けようかとも考えたんだけど、もっと身近な場所がいいかと思って」
「うん。ぼくは家の近くをまだ知らないから、こういうのも楽しいよ」
「遠出はまた今度しよう」
勇利は黙って微笑した。次の機会などないことを彼は知っていた。
ヴィクトルはいつもどおり優しく、愉快な話をしてくれたけれど、普段より物静かで、しかし情熱的で、何か目つきに深い意味があらわれていた。勇利は感心してしまった。たとえ勇利のためだからと思ってしたデートでも、こんなふうにいかにも熱っぽくふるまうことができるのだ。ヴィクトルはすごい。本当に浮かれちゃいそうだな、と勇利は自分を戒めなければならなかった。いや──彼はすでに、本当のデートとしてヴィクトルとの時間を楽しんでいた。こころはどきどきしどおしだった。ヴィクトルをみつめるだけで頬が紅潮した。しかし同時に、頭の中では、ヴィクトルはそういうつもりではないとわきまえてもいた。ヴィクトルは「本物」を経験させようとしてくれてるんだ。だったらぼくだって本気になってもいいのかもしれない。今日一日だけとさえわかっていれば……。
「そろそろ夕食にしようか」
ヴィクトルは腕時計を確かめて言った。
「レストランを予約してるんだ」
「すごいところ?」
「そんなに緊張しなくていいよ。いまの勇利にふさわしい店だから」
「普段のぼくは?」
「普段は……」
勇利は笑いだした。いつもの自分がありふれて冴えないことくらいわかっていた。ヴィクトルも笑った。
「でも俺はいつもの勇利もいとしいよ。かわいいこぶたちゃん」
「いつものぼくとこぶたを同じように考えないでよ」
「そうだね。勇利はいつでもこぶたちゃんだ」
「どういう意味」
「いまもそうだ。俺のこぶたちゃんだ」
愛称のつもりらしい。まあいいけど、と勇利はくすくす笑った。ヴィクトルの「こぶたちゃん」は、あまくてとろけるような響きを帯びている。
連れていかれた店は、確かに昼間とはすこしちがう、格調高いところだった。この服でなければすっかり慌ててしまっていただろう。昼の店は上流階級の者の隠れ家だったけれど、ここは上流階級の者が堂々と通うレストランといったふうだった。品格があり、礼儀を心得ていなければ入れないようなところだ。勇利ひとりではとても食事できない。そう伝えるとヴィクトルは笑って答えた。
「勇利が来るのにふさわしい店だと思うけど、きみがこういうのを苦手にしているのはわかってる。あまり通いたくないってこともね。ただ、たまにはこんなところもいいさ。そのときは俺と一緒に来よう。いいだろう?」
注文はすべてヴィクトルにまかせた。ワインは口当たりのよいさわやかなものだったけれど、だからこそヴィクトルは注意を忘れなかった。
「飲み過ぎないで。俺のこころはダンスバトルを期待してるけど、ここではまずい」
「ぼくのこころだってまずいと主張してるよ」
「もししたくなったら言って。場所を変えよう」
「なりません」
きちんとした店で、しっかりした作法を要求されているにもかかわらず、勇利はちょっと緊張しながらもくつろいでいたし、とても楽しかった。ヴィクトルが優しく勇利をみつめ、機知に富んだ話をし、いかにもおまえが特別だというまなざしをしていたからかもしれない。これがデートか、と勇利は思った。ヴィクトル・ニキフォロフの一流のデートだ。確かに経験すれば自分が変わるかもしれない。なんてすてきな時間なのだろう。勇利はテーブルに飾ってあるヴィクトルの青い花をみつめた。でも、あとでさびしくなりそうだな、とすこしせつなくなった。
「デザートはアイスクリームでいい?」
ヴィクトルが尋ねた。勇利はにこにこした。
「あんまり食べたら太っちゃうかも」
「一緒に走るよ」
勇利はかるい笑い声をたてた。ヴィクトルがまっすぐに勇利をみつめた。
「なに?」
「綺麗だ」
「…………」
何なんだこのひとは、と勇利は思って目をそらした。頬が熱い。デートというのは、なんの脈絡もなく相手を褒めるものなのだろうか。知らなかった。勇利はすこし黙りがちになり、運ばれてきたアイスクリームをもくもくと食べた。
「急に静かになったね」
「ぼくはいつでも静かです」
「そうかもしれない。でも、最高ににぎやかなときもあるね」
「酔ったぼくのことは忘れて」
「忘れないよ」
ヴィクトルは瞳を熱意できらめかせてささやいた。
「一生忘れない」
「…………」
勇利は目を伏せた。
「……勇利」
「……なに」
「何か言ってくれ」
勇利は上目遣いでヴィクトルを見た。
「アイスクリーム美味しい」
ヴィクトルが笑いだした。
食事のあとは、川沿いの道をまた歩いた。ひろい川は昼間とはちがう顔を見せていた。美術館や博物館がきらきらと輝いて、まるでひかりの都のようだ。それも都会的なものではなく、しっとりとした、情緒のあるきらめきだった。それらを、川の水面がすっかり写し取っていた。
「楽しかったかい?」
「うん」
勇利はこっくりうなずいてから訊き返した。
「ヴィクトルは?」
「楽しかったけど、有頂天になって、なんだかずっと浮かれていたよ。記憶がさだかじゃない」
勇利はくすっと笑った。
「すごい口説き文句だね」
「口説き文句じゃない。本気で言ってる」
「そっか」
勇利は花束を持った手を後ろにまわしてかるく指をからませ、ヴィクトルよりさきに立って機嫌のよい足取りで歩いた。するとヴィクトルがすぐに追いついて二の腕をつかみ、勇利を振り返らせた。
「本当だ」
「…………」
ふたりは立ち止まってみつめあった。ヴィクトルの瞳はこわいくらいの真剣さで勇利を射すくめ、勇利の頬は自然と紅潮した。
「勇利が綺麗すぎて、かわいすぎて、あまりに可憐で、何を話しても愛らしくて、俺は楽しくて、胸が騒いで、もうこころの中はめちゃくちゃだったよ」
ヴィクトルは腕をつかんでいた指をすべらせて、勇利の手を取った。勇利はぼうっとなって手をひっこめたくなったけれど、動けなかった。
「いまもめちゃくちゃだ」
ヴィクトルがささやいた。勇利には、彼はめちゃくちゃに見えなかった。落ち着いて、すばらしくかっこうよく、ぞくぞくするほど男っぽく見えた。
「勇利」
ヴィクトルの瞳が熱狂的にきらめいた。彼はこのうえなく熱愛のこもった声でささやいた。
「きみのことが好きだ」
勇利はどきっとした。手足がふるえ出しそうだった。ものが言えなかった。きみのことが好きだ。ヴィクトルはそう言ったのだ。
「好きだ。──好きだ」
勇利はすっかりとりのぼせてしまった。デートをして愛の告白をされるなんて思っていなかった。こんな──こんなに緊張して、どきどきして、泣きたくなるものなのだろうか? 勇利の瞳はうるみを帯び、視線はヴィクトルの顔から離れなかった。ヴィクトルの胸に飛びこみたいと思った。抱きしめられたいと思った。ぼくも大好きと伝えたかった。
しかし勇利は思いとどまった。これはちがうのだ。そういうものではないのだ。本気にしたらヴィクトルが困る。そうだ。こういうのを上手くあしらえなければならないのだ。勇利がきちんとした一人前の受け答えをすることができれば、ヴィクトルは納得して勇利をもう子ども扱いしたりしないだろう。好きなひとはいるかとか、愛されたことを思い出せとか、デートをしようとか、そんなことは言わなくなるにちがいない。ヴィクトルにこういった方面を気にかけてもらわなくても、立派にちゃんとできるというところを見せなければ。
勇利はふいと顔をそらした。
「好きってなに?」
勇利がしとやかな口ぶりで尋ねると、ヴィクトルは目をまるくして瞬いた。
「え?」
「好きって言うけど、ヴィクトルはぼくとどうなりたいの?」
「どうって……」
「ぼくと何かしたいの? ぼくをどうしたいの? ぼくとどうにかなりたいの? ヴィクトルみたいなすてきなひとが? 何も知らない、子どもっぽいぼくなんかと?」
「勇利──」
「子どもだと思ってからかわないでよ」
勇利はヴィクトルをにらみつけた。ヴィクトルが慌てたように言いつのった。
「からかってなんかない! 俺は本気だ。勇利、俺は本当にきみのことを──なんていうか──その──あんまり好きすぎて上手く言えないんだが──、くそ、これじゃ俺のほうが子どもだ……」
「真剣にぼくのことが好きなの?」
「真剣だ!」
「だったらそんなんじゃぜんぜん足りない」
勇利は顔をそらすと、おとがいをつんと上げて拗ねたように言った。
「足りない……?」
「きみのことが好きだよなんて、それっきりで不足がないと思ったら大間違いなんだから!」
ヴィクトルが何か言いたげに口元を動かした。勇利はヴィクトルにぱっと向き直り、眉根を寄せて、澄んだ目で���をみつめた。
「もっとちゃんと愛情を見せて」
「…………」
「もっと情熱を見せてくれなきゃいやだよ。好きって言って終わりなの? それだけ? 本当に? ぼくのこと真剣に好きなのにおしまいなの?」
「…………」
ヴィクトルは何も言わなかった。勇利の頬は燃えるように熱かった。勇利はそっとヴィクトルの手からみずからの手を引いて取り戻し、もじもじしながらうつむいて花束を抱きしめた。ど、どうしよう。すごいこと言っちゃった。うわあ……。
そろそろ夢のさめる時間だった。いつまでもヴィクトルとこうしてはいられない。ヴィクトルはすてきなことを経験させてくれたし、勇利もそれにじゅうぶん──とはいかないまでも、なんとか応えられたのではないだろうか。すばらしい一日だった。
ヴィクトルが勇利に一歩近づいた。
「勇利──」
「……なんて」
勇利はつぶやいて顔を上げ、彼に笑いかけた。ヴィクトルが瞬いた。
「びっくりした? ぼくもなかなかちゃんとできるでしょ?」
「え?」
ヴィクトルがふしぎそうな表情をした。勇利はいたずらっぽく言った。
「なんだかとんでもないことを言っちゃったって自分でも思う。でも、あのヴィクトル・ニキフォロフをあしらえるんだから、そんなに子どもじゃないでしょ?」
「…………」
「ヴィクトルはぼくのこういう方面が心配でデートを教えてくれたんだろうけど……」
「えっ?」
「もういいよ。ありがとう。今日は楽しかった。ぼくちゃんとできてたでしょ? ヴィクトルも安心したよね?」
「……勇利。何を……」
「すごくいい体験をさせてもらったと思う。ぼく途中から……ううん、ほとんど最初から、本当にヴィクトルとデートしてる気になって……もう完全にその気になって、ずっとどきどきしてたんだー」
勇利は胸に手を当ててにっこりした。ヴィクトルは幾度も瞬いている。
「ヴィクトルはぼくにいろいろ教えてるだけのつもりだっただろうけど、ぼくはもうすっかりめろめろ……恥ずかしいけど。でもちゃんとヴィクトルのエスコートに応えられてたんだからいいよね? 合格でしょ? まさか告白までしてもらえるとは思ってなかった……」
勇利は頬に手を添え、ほうっと夢見るように息をついた。
「そこまでしてくれなくてよかったんだよ……ヴィクトル、すっごく真剣だったから、ぼくほんとにとろけちゃったよ。だけど、いくらぼくのためでも、あんなこと言うのはだめだよ。だってぼくはヴィクトルが好きなんだよ……」
勇利は恥じらいのほほえみをヴィクトルに向け、にっこりした。
「すごく好きなんだ……。あんなふうに言われたらぼく本気になるからね! ヴィクトル、困るでしょ?」
ああ、恥ずかしい。勇利はちょっとうつむき、それからまたにこっと笑った。
「でも今日はありがとう。本当に……」
「…………」
「帰ろっか」
勇利が歩きだそうとすると、ヴィクトルがさっと手を伸べ、さっきのように、ぐっと腕をつかんだ。勇利は驚いて彼を見上げた。ヴィクトルの瞳にはまじめなひかりが浮かんでいた。
「どうしたの……?」
彼はふいに、愉快そうに笑いだした。口元をふるわせ、肩も揺らして、くすくすと可笑しそうに笑った。
「な、なに……?」
「勇利、きみは……」
ヴィクトルはたまらないというように笑い続けた。
「俺がきみにデートを体験させるためにこんなことをしたと思ってるのか?」
「ちがうの?」
勇利はぽかんとした。
「ほかに考えられないじゃない。ヴィクトルがぼくを誘う理由なんてある?」
「理由ならある」
ヴィクトルが顔を近づけた。勇利はどぎまぎしてまっかになった。
「おまえが好きだ」
ヴィクトルの低い声が耳元をかすめた。勇利は今日彼と過ごした中で、いちばんぞくぞくっとした。ヴィクトルがほほえんだ。
「ああ、きみが好きだって言葉だけじゃよくないんだったね。そうだな。もちろんそれで不足がないとは思ってないさ」
ヴィクトルがぐいと勇利の腰を抱いた。身体がぴったりとくっついて、勇利はぐらぐらとめまいを感じた。な、なに。なんだ。なんだ。なんなの。なにこれ……。
「勇利。おまえはぼくとどうなりたいのと言ったね。どうしたいんだって……」
「ま、待って。待ってヴィクトル……」
「勇利としたいことはたくさんあるよ。まずは手始めに……」
「あ、あの……」
ヴィクトルが勇利のおとがいをすっと持ち上げた。彼と目が合い、青い瞳がすぐそこにあることに、勇利はますますくらくらした。倒れそうだ。いや、ヴィクトルが腰を支えてくれていなかったら倒れている。
「勇利……」
「こ、子どもだと思ってからかわないで……」
「俺はおまえを大人だと思っている。大人なのにいとけないからますます夢中になるんだ。勇利……」
「ヴィ、ヴィクトル──」
「おまえを愛してる」
くちびるが重なった。勇利は息もできなかった。一度ふれて、離れて、もう一度ふさがれたときには、腕全体で抱きしめられていた。それから熱っぽく甘噛みされて、くちびるを舐められて、舌が優しく入ってきて、激しく口内を愛撫されて、そして、そして──。
勇利は脚から力が抜けてしまった。
「勇利」
ヴィクトルは勇利がくずれないように抱いてにっこりした。勇利はぽーっとなって彼をみつめていた。目つきは完全にとろんとして、わけがわからない状態だった。勇利のくちびるは赤く濡れていた。
「愛と情熱を見せればいいんだったね」
「あ……あ……」
「本気になってくれるんだろ?」
「あの……」
「俺のことが好きなんだよね?」
「えと……」
ヴィクトルは勇利をしっかりとした自分の身体に寄りかからせ、腰を引き寄せてゆっくりと歩きだし、にこにこした。
「おまえには言いたいことがいろいろあるけど、今後の話もたくさんあるよ」
「そ、その……ぼく……」
「俺の愛と情熱はまだじゅうぶんじゃないだろう? そのこともふくめて、帰ってからじっくり相談しよう……」
「あ……」
な、なんだか大変なことになっちゃったみたい……。勇利はまったくなりゆきについていけなかった。完全に夢見ごこちで、何が起こっているのかわからない。ただ、ヴィクトルがあたたかいなとか、いい匂いだなとか、キスってあんな感じなんだ……すごい……とか、ヴィクトル……好き……とか……そんなことばかり考えていた。
「勇利」
ヴィクトルはいとおしそうに笑い、はしゃいだ様子で勇利の髪にキスした。
「大人をもてあそぶものじゃないよ、きみ」
1 note
·
View note
Text
新しい住人について
この冬、二人暮らしを始めた。 親元を離れて、一人暮らしの期間が長かったものだから、どうやって二人で暮らしていくのかということに不安があったけれど、始まってしまえばなんでもない。生活というのはその場の人間に合わさるように出来ているのだと、つくづく思う。 二十五歳で二人暮らし。順調な生活具合だ。世間一般に言うまっとうな人生、そういうものに似ている。 いつものようにすぎるはずだった日々に、あるいはなんてことのない生活に、人と人の化学反応が起きれば、そこには記憶が生まれていく。これがそのうち思い出になったりするのだろうと思うと、どこか面映ゆくなる。同居人の存在をそばで感じながら巡っていく日々は、いつかなんでもない映画のようになっていくのかもしれない。 大切なことを言うのを忘れていた。 同居人の名前は、ギブソン・レスポール・スペシャル、イエローという。 身長は62センチメートル。体重は3キログラム。 普段は大人しめの黒い衣服を脱ぐと、それはそれは眩しいばかりの肌が見える。光が反射してイライラするのでケースにしまいっぱなしだけれど、黒ずくめの人間が部屋にいるのは、それはそれで威圧感がある。不審者と一緒に暮らしていたら、こんな気分なんだろうか。 一緒に生活しているのに同じ食卓を囲まないなんて、と、この前の休日の夕食の際は、一緒にテーブルについてみた。 「いただきます」までは済ませたけれど、作ったキーマカレーを口に含んだ瞬間に耐えられなくなった。 傍から見たら、ギター眼の前に置いて、食事をつまらせるおかしな人間だっただろう。いや、実際にそれ以外の何者でもないのだけれど。 話しかけるようにしてみたこともある。観葉植物に話しかけるとよく育つみたいな噂と同じ要領でやれば、少しは二人暮らしらしくなると思ったのだ。 「元気?」 当然返事はなかった。 一緒に暮らしている人に元気かどうかは尋ねないということに気がついたので、やめた。 冗談はさておき。 今の私の部屋には、ギターがある。 それなりに重い、整理しづらい物体が、一人暮らしの1LDKに存在するときのことを考えてほしい。当然急に押し掛けてきた来客に寝床なんて用意していないから、どこかに重ねたり隠したりもできない。悩んだ末の結論として、ギターは作業机の隣、曖昧に空いていたスペースの観葉植物を押しのけて座っている。 本当に邪魔だ。 特に掃除をしているときは酷い。休日、掃除をしているときに動かない旦那さんを前にした奥さんというのは、こういう気分なのだろうかと思う。 でも旦那さんはホコリをかぶらないし、いくらものぐさでもどけと言ったら動くだろうし、まだマシな気がする。と、わざわざ動かして床のホコリを掃除して、少し乗っかったホコリを拭く度に思っている。週に1度は掃除をしているから、まあそこまでひどくなることはないのだけど。 すっかり習慣として身について、今では土曜日の朝が来ると勝手にハンディクリーナーを持ち出すこの体は、毎度こまった同居人にため息をつくことになるのである。これでいて、勝手に音楽の一つでも流してくれたら良かったのだけれど、残念ながらギターは勝手に鳴ったり、メロディを奏でたりしない。ただそこにあるだけで、自分を使う人が現れるまで、ただただ沈黙し続ける。果たして待ち人が誰なのか、その答えも分かってしまっているから、余計に気まずい。 つまるところケースから出されることもなく、ただオブジェとして置いていかれるだけのそのギターは、部屋の片隅を彩ることもなく、ただただのっぺりとした印象だけがそこに存在している。招く人もいないからよかったけれど、これで部屋に遊びに来る人がいたら「ギター弾くの?」と質問されることは間違いないだろう。なにせ見逃せない程度に大きいから。そのときのことを考えて、私は勝手に冷や汗をかいているわけだ。 彼女――もしかしたら彼かもしれないが、あまり男性と二人暮らしをしているとは考えたくないから、私はこのギターのことを女の子だと思うことにした――がやってきたのは、もう一ヶ月も前になる。 ある日の朝、突然彼女はやってきた。正確には「運ばれてきた」のだけど。 二日酔いが残る朝方に、インターフォンの音で起こされたと思ったら、寝ぼけている間に玄関に大きな箱が広がっていた。何も覚えがなくて開けたら、そこには彼女がどんと構えていたわけである。これにはびっくりした。なにせ箱の中身にも覚えがないとは思わなかった。調べてみたらたしかに深夜の購入履歴が残っていて、確かに注文はしていたらしい。全く記憶がないのだけれど。 その前の日は会社の送別会で、職場でも親しい年の近い人たちしかいなくて。大きな仕事が終わって、一段落ついて。つまり酔うためにはもってこいの条件だったわけである。質が悪いのは、無事に家についた途端平気だと思い込んで――何なら足りないと思いこんで――貰い物のワインを開けてしまったことで。あっという間に真っ逆さま。気がついたら見に覚えのないギターの解説ページと、注文を知らせるブラウザの履歴が、新品そのもののギターと一緒にニヤニヤと私に笑いかけていたわけである。 そのときすぐさま|追い出して《返品して》やらなかったのは、今思えば失敗だった。圧倒的に合理的なその行動を取らなかったのは、私がこの同居人にどこか責任のようなものを感じていたからかもしれない。買ってしまったのは事実なわけだし。高価なものを何度も行ったり来たりさせてしまったら悪いし。もしかしたらキャンセル料とか取られるかもしれないし。 そういった憶測と役に立たない感傷をいくつも並び立てて、調べもせずに考えるふりをしている間に、一般的な返却期間は過ぎていき、キャンセルのボタンが注文詳細から消える頃にはすっかりギターはこの部屋に馴染んでいた。日々目にするものへの慣れというのは恐ろしく、いつの間にかずっと前からそこにあるような、そんな顔をしているように私には見えている。 酩酊した私が丁寧なことに購入していたアンプとピックは機能していて、音は鳴る。それだけは一応確認した。それ以来、一度も触っていない。やらない理由はいろいろあって、例えば防音はどうだとか、教材をどうしようかとか。いくらでも正当な理由は並べられた。それでも置きっぱなしにしてしまっているということ――つまりやらない決断をすることが、やる決断をすることと同じぐらい難しいことを思い知らされているわけで。 一年ぶりに夏紀に出会ったのは、鳴らすこともないのにしまい込むことも出来ないそのギターを、まるで自分のように持て余していたときのことだった。 ★ 私も二十五年生きてきたわけで、様々なものの実在を確かめる経験があった。 嬉しくない誕生日だとか、 特別じゃないクリスマス。捨てられないCDとか、そういうものだ。大人たちが語るそういった哀愁の匂いが取れないものを子ども心に笑っていたはずの私は、いつのまにかその実在を確かめては、手触りの感触を記憶するようになってしまっていた。 「何をやっているのかよくわからない友人」なんてものが存在するということもわかったし、高校時代にあれだけ近かったはずの夏紀が、いつの間にかそういう立ち位置に落ち着いていることもあるのだとわかった。あの頃と気持ちの距離感は変わっていないはずなのに、彼女を取り巻くものだけはいつも移り変わっているから、好きだったバンドの数年ぶりの新譜に手を付けるときのような不安が、彼女を前にするとやってくる。 たまたま駅で見かけた彼女は、そのときはギターケースを背負っていて、それ自体は大学生の頃から見慣れた景色だった。土産屋の邪魔にならないような隅にいるのも彼女らしい。あの髪色も柔らかな目もあまり変わっていなくて、ただ違うのは、彼女が見たこともない女の子二人に囲まれているということだ。 囲い込まれていると言った方が正しいかもしれないその様子は、傍から見ると微笑ましいような、そうでもないような、しかしただ対等ではないことだけはわかった。夏紀を見つめる目にはそれぞれ羨望が乗っているのがよく見えた。駅を急ぐ人たちも、心なしか彼女たちを避けて通っているように見える。午後四時の京都駅に在っていい雰囲気じゃなかった。 話し込んで気づかない夏紀達の横をなんでもないように通りながら、彼女に気づかれないぐらいの距離に立って、様子を見守ることにした。頼まれてチケットを買った大学の同期のコンサートが、休日を無駄に過ごしてしまったと少しでも思ってしまうようなものだったから、このぐらいの時間のロスはいいだろう。後ろからじゃ彼女の表情は見えないが、別に見えなくてもよいぐらいには、親しいと自負している。 夏紀は渡されたCDにサインをしていて、それが彼女がやっているインディーズバンドのものなのだろうということには想像がついた。 (CDって持ち歩いているものなのかな) 素朴な疑問を持て余しているうちに、夏紀は一人になっていた。曖昧に手を振る方向にさっきまでいた女の子二人がいるのが見える。彼女たちが夏紀の方を振り向かなくなって十分経った所で、彼女の肩の力が抜けていくのが見えた。わかりやすい力の抜け方を見ながら、少しだけ生まれた悪戯心のまま、彼女の背中に近づく。夏紀がマスクを付け終わるのを待ちながら、花粉症だったかどうかまでは忘れてしまったことを思い出した。 「久しぶり」 後ろから声をかけると、力の抜けた肩が強張るのが見て取れる。俊敏な動きでこちらを振り向くと、私だとわかって安心したのか、少し大きく息を吐いたのがわかった。 「希美」 「お疲れ。どうしたの?」 私が省略した主語を恐らく理解した彼女は、しかしそれには答えず、腕時計で時間を確認した。大学時代からつけているものだとわかって、私はやっと本当に目の前の彼女が夏紀なのだと安心する。確か、優子からプレゼントで貰ったもののはずだ。 「このあと時間ある?」 曖昧な記憶が一致していくのを確かめている私に、夏紀は少し籠もらせた声で答えた。 「あるよ?」 「じゃあお茶しない?久しぶりだし」 「いいよ」 頷いた私に、夏紀は安心したように笑った。 「自意識過剰だってわかってるんだけどね」 そういいながら鬱陶しそうにマスクを外す夏紀は、至って健康体だった。花粉症じゃないという私のおぼろげの記憶はまちがっていなくて、つまりそれは変装のためのものだった。 「大変だね」 「ありがたいことなんだけどね」 そう言いながら力を抜いて椅子に寄りかかる彼女は、この至近距離で見ても、あまり変わったところを見つけられなかった。いつかの冬の彼女と同じように、夏紀はその髪の毛を下ろしていた。あのときからずっと変わっていないような気がして、すこし怖くなる。いつの間にかあの頃に取り残されてしまったような、そんな気がして、慌てて違うところを探す。彼女の目の前に置かれた紅茶とミルクレープを見出して、なんとか安心した。 「よくあるの?」 私の質問に、夏紀は苦笑いで答える。 「メジャーデビューもしてないバンドで、そんなによくあったら大変だよ」 「そうなの?」 「三ヶ月に一回もないはずなんだけど、ここのところ連続してて」 そういう彼女が嬉しく思っているのは、鈍いらしい私でもわかってしまう。友人の素直じゃない幸福をどう扱ってやろうかと考えていると、目線に意図が乗ってしまったらしい。夏紀は私から目線をそらして、取り繕うように紅茶を口にした。 「熱っ」 その様子に、からかう言葉を投げかけられるほどみっともなくはなかった。高校の頃よりずっと自覚的になった意地悪さを、私は急いでしまいこんだ。 「じゃあバンド続いてるんだ」 「お陰様で」 「なにそれ」 笑いながら、ひどく安心した。夏紀の席のとなりに立てかけられたギターは、生きているような、そんな感じがしている。同じようにケースに入っているはずなのに、私の家で黙ったままのあいつとは、あまりにも違う。 「久しぶりだね」 「一年ぶりぐらいだっけ」 「もうそんなになるのか」 「前、いつだったっけ」 「なんだっけなぁ」 夏紀が考え始めた隙を見て、頼んだカフェラテを口にする。てっきり甘いものだと思っていた舌が、苦味に驚いたのを隠しながら、自分の記憶を取り戻そうと躍起になる。 「前、みぞれが帰ってきた時じゃなかったっけ?」 「そんなになるっけ」 喫茶店のロゴの入ったカップをテーブルに戻しながら、夏紀の奥にいる家族のパスタを見つめる。カレンダーを出すのはなぜだか冷たい気がして、私は記憶の景色から季節を当てる。 「去年の1月だよ」 言葉にして引っ張り出すと、曖昧にぼやけていたはずの記憶が引きずり出された。 「思い出した。雪降ってて、優子が帽子被ってた」 「なんでそんな細かいとこ覚えてるの?」 「どうでもいいことってよく覚えてるじゃん」 夏紀の疑問を解決したふりをして、哀愁に浸るふりに勤しむ。 「もうそんなになるのかぁ」 「今年は私が都合つかなかったからね。そういえば、誕生日おめでとう」 誕生日はもう一週間前で、つまり今年ももう終わりだった。自分の部屋で一人で迎えたそれよりも、ずっと嬉しい気がした。 「ありがとう。もう25ですよ」 「私もですけど」 口を抑えて互いに笑い合う。特別じゃない誕生日も、祝われれば嬉しいもので、何気ない拾い物をした気持ちだった。目を細めて笑っていた夏紀は、ふと気がついたように私に向き直った。 「今日夜空いてる?ご飯奢るよ。大したことじゃなくて悪いけど」 「えっ、いやいいよ。ご飯は行きたいけど、夏紀の誕生日私何もしてないし。普通に食べに行こ」 「まあまあ、じゃあ来年覚えてればなんかしてくれればいいよ。こういうのはタイミングだし」 そうやって笑う夏紀は、本当になんでもないように人に与えるのが得意だ。一生敵わないんだろうな、なんて考えながら、それでも引き下がるわけにはいかない。私の曖昧なプライドもあるし、何よりなんか、悪いし。 「でも」 「ご飯以外でもいいんだけど、私ができることってギターぐらいしかないし」 そういいながら、夏紀は隣にあるギターケースを引き寄せた。その手に、あることを思いつく。 「じゃあさ、夏紀に頼みたいことがあるんだけど」
1 note
·
View note
Text
修道女たち
先日紫綬褒章を受賞したケラリーノ・サンドロヴィッチ(小林一三)さんの演劇を初めて観ました。初めての本多劇場。
以下ネタバレあるので、万が一これから観に行く人がいたら読まないほうがよいです。あとほぼメモなので雑です。
世の中まだまだ面白いものがいっぱいあるなあ、それにしてもこんなに面白いものがあるなんて。という思いが、言葉として、観劇中に自分の中にはっきりとくっきりと浮かび上がって来た。それくらい確かな「感動」が存在していた3時間でした。
観てる間は、なんだこれ、面白い、なんだこれ、っていう驚きと感動による語彙力の低下。完全に自分の全部持っていかれててわけがわからなくて。ドーパミンドバドバ出て来た。観終わってすぐには自分の中に出てくる感情の情報量の多さで頭の中がぐちゃぐちゃで。凄いものを見た後、その余韻を永遠に自分の中で反復、反響させるために、音楽も映像も情報として余計なものを何も入れたくなくなって何もしないことがあるんだけど、今回はそれでした。友達と別れてからも、イヤフォンだけ耳にさしてずっと電車に揺られて帰った。
一つの宗教の終わりと密かな継続の物語、修道女たちの群像劇。終わりは、修道女たちの死。布教をする、信仰の核となる人々が死んだことにより、宗教が大きく伝播する可能性は潰されてしまった。けれど彼女達が、毒が入っていることを分かってワインを飲んだとことは村人達を救ったし、そんな彼女達の行動は記憶として残り続ける。のちに緩やかに消失していくかもしれないけれど。
彼女達の宗教との関わり方は様々だ。宗教にすがりたいがために、多額の献金を払って短期間で修道女になった者。そんな母に連れられて様々な宗教を転々としてきて、宗教という者自体に辟易としている者。宗教の維持のために甘んじて献金を受け取る者。修道長であるが、実際は人の顔色ばかり伺って自分では判断を下せていない者。しかしそんな彼女達が、最終的には一様に信仰心に身を捧げる。しかしそれもまたそれぞれに理由があった。行動は同じでも思惑は違う。面白い
修道女達が死んだことを直接舞台上で見せずに事後報告的に言葉によって語られるの、授業でやったギリシャ演劇の話思い出した。言語の方が写実的だと考えられていた的なアレ
脚本のお話
会話をベースに、物語が進んで行く。説明台詞なんて全然なくて、でも緩急つけて物語が展開していく。何気ない会話から彼女達のコミュニティにおける各々の立ち位置や宗教の捉え方がジワジワ伝わってくるのがすごい。直接的なことはさして言っていないのに、伝わってくる。キャラもキャラクターも立ってた。作り込みがまーじで丁寧。ああ、この舞台上で繰り広げられる会話や場面は、彼女達の日常の一部を切り取ったものなんだろうなあ、っていうのがなんでか分かる。その背景に日常が見える。それぐらいの作り込み。親子の性格が似てるんだなあ、っていうのがわざとらしくなく分かったんだよ。関係性の描き方凄くないですか
あと、その時は面白くないなって思った小ネタがあとで響いてくる。回収が丁寧綺麗。追って面白ぶち込んでくる演劇らしさ。全部笑わせてくるの本当にずるい。
彼女達の信仰の一つである魂の列車の模型を作っていたら、一人だけ変な形のものを作ってしまう。その形がめちゃくちゃわざとらしく変な形で、一発系なギャグにしてはあんまり面白くないな〜って思ったら、その後その列車持ちながら超真面目に語り出すという。しかもその列車作った人が新人に作り方を教えることになるという。笑うってそんなの。
パンが例え話か本当のパンの話か問題とか
スタッフワーク的な演出のお話
じわじわ雰囲気持ってく演出やっぱ好きだなあ。明かりが暗いシーンでは、役者が次に移動する位置を徐々に徐々に明るくしていって、観客の視線を誘導する。同じ映像を、盛り上がりに伴って次第に色付かせていく。すごくゆっくりな変化だから、演出によってだんだん自分が引き込まれていっていることに気付けない。素晴らしか〜
オープニングアクトの映像よ、、、、立体感がすごいし、壁画が回ってるように見せる工夫とか。いつ舞台転換したんだ。全然わからなかった。映像演出場中に机はけあんまり気にならなかった。後半の死神のインも全然わからなかった。ハケる時はガン見したけど(笑)演出ってマジシャンだなあ〜観客の視線を巧みに操ってる。操られた。悔しい
暗転の使い方綺麗すぎーーーーーーーー!
紅茶甘い暗転、四角い照明の暗転
役者さんのお話
オーネッジ役の鈴木杏さん、凄い。白痴の女の子の役なのだけど、笑い方や褒められた時の反応一つ一つにその子の性格や障害が癖として表出していて、かつそれが面白くてこちらも笑ってしまうという(笑)祈りの言葉を意味もわからずにただただ読んでいる、というのをしっかり伝えられる台詞の言葉の運び方。死んだ修道女が乗り移った時の声色の変わり様よ。スチームボーイの主人公の声優さんやってたの親に言われて気づいた。。
林原めぐみさん声の出演ああああああああありがとうございますめちゃくちゃ色気あった
間がうまいんだなーーーちょっとギャグ混じりの会話劇って間が命だよね。すげー当たり前のことだけど。例えばちょっとズレたことを言ったときに、それに突っ込むまでの間でちゃんとお客さんに「………ん?」ってなる時間を与える、長すぎると不安になっちゃうし。まあそれを面白に昇華する手法も使われていたけれど。
字面だけで捉えたら面白い台詞でも、役者さんの話し方によって笑いの場は終わって、空気が変わりますよーっていうのがちゃんとわかる。隣の人ずっと笑っててすごい気になった(苦笑)このセリフ笑うの違うでしょ!ギャグゼリじゃないじゃん!言い方違うじゃん!って思ってましたとさ
ギッチョダ。
面白いものを作りたい。娯楽を作りたい。
2 notes
·
View notes
Text
初恋
怒りが、私は衝き動かしていた。全てがあかく染まって見えた。イルミネーションに彩られたクリスマスの街並みも、楽しいこと明るいもの以外は許そうとしない夜の喧噪も、自分たちこそが世界でいちばん幸福なのだと信じてやまない恋人たちも、別の女を抱いた日に私に触れた三十分前まで恋人だった男も、そんな男に夢を見た私自身も、何より他人の恋人に手を出して背中にルージュのサインを残した"シノ"が、私の怒りだった。
六本木五丁目の交差点を過ぎると、その場所があった。私は(男を追い出した手で)IDを提示して、歓迎を口にするセキュリティに(男を罵った口で)答えて、階段を(男を蹴り出した脚で)下り、情けなく涙を流した後の目でフロアを眺めた。なんてことのない、至って普通のナイトクラブ。散りばめられた光と音が十人並の欲望を世界にたった一つの宝石にさえ見せてしまうような、そういう場所。
私はシノを探す。ホールの上層、フロアを見渡すテーブル席で出会ったと、男は言っていた。場違いなワイングラスを傾けて、対面に座ると無言でグラスに真っ赤なワインを注いで差し出したと、そう言った。それ以上、聞こうとは思わなかった。それだけで充分だと思ったし、聞くほどに憎もうとする自分が、許せなかった。自分がこれほどに嫉妬深いいきものだと、知りたくなかった。あるいは嫉妬ではなく、見栄やプライド。いずれにしても、私が嫌うもの。自身ではなく他者への依存。私は、自分の足で立っていたかった。誰かに寄りかかって、一人では立てなくなって、自身の何もかもを委ねてしまうなんて、許せなかった。
私は、ハイチェアに腰を下ろす。卓上のグラスを取り上げると、「一杯いただける」と言う。真っ赤なサルモスを注いでから「どうぞ」と答えられて、私はグラスをかかげる。
「乾杯しない?」
「いいけど、何に?」
「あなたが奪った私の男に」
「……お名前は?」
「レイコ」
「そう……私は」
「シノ、そうよね」
「……ええ。会いにきてくれたのね、嬉しい」
「私もよ」
「出会いに」
グラスを重ねて、ワインを口に含んだ。顔にぶちまけてやろうと思っていたけれど、良い味だったからやめにした。
「ここにはよく?」そう訊ねる。シノはけだるそうに(絶えず、そういう造りをした女だった)唇を開く。喧噪が言葉をかき消して、私には離れては触れ合う唇の動きだけが映った。
聞こえない、とテーブルに身を乗り出して耳を寄せる。ちょうどフロアの音響が高鳴り、ミラーボールが無遠慮な光をばらまきはじめた。
いつまで待っても返事がないので、シノを見る。けだるそうな表情を崩さずにシノは、もう一度、とサインを送る。耳を近づけると今度は手で触れられて、やっと声が聞こえた。
「きれいなお耳、見とれちゃった」吐息の混じる、そういう声だった。シルクのブランケットか、蜘蛛の糸。いずれにしても、からめ捕られようとしていると本能が感じた。「このお店、ワインがおいしいの。すごく」
それきり声が離れてしまったので、私は体をハイチェアへ預け直してしな垂れた髪を耳にかける。そこが驚くほどの熱を持っていたので、隠せば負けだと思った。シノをじっと見ながらグラスを傾けると、ほとんど裸の全身をさらすような思いがした。「本当ね」
「でしょう? 他のお店とぜんぜん違う。こんな場所でわざわざ置いてるんだから、こだわりがあると思うの」
「確かめてみたら?」
「どうやって?」
「訊いてみる」
「いやよ、触りたくないの。私のせいで終わったら悲しいわ」
「臆病ね」
「そう。気付かれずにそっと見守っていたい」
矛盾した女だと思う。私の人生を踏み壊しておいてそう言うのだから、これは本心ではないのかもしれない。口から出るままに嘘をついているのか、けれど、もしかすると全てが本物かもしれない。瞬間の全てに真心で接する、そういう女か本当に頭がおかしいのか。
表層をなぞるような言葉を交わしながら、シノを眺めた。決して派手ではないが丁寧に造られたその顔は、墨色の髪を伴ってどこか高貴な印象さえ与える。ボディラインを丁寧になぞり、肩口までをあらわにしながら決してその印象が崩れないのは、振る舞いによるものだろう。たとえばグラスを傾ける仕草、目線の流し方や髪を梳かす指、あらゆる動作が滑らかで、洗練されていた。きっと、棺に入る時でさえその滑らかさは崩れないのだと思う。魂や、遺伝子にまで染み込んだその美しさ。
私は、ますますわからなくなる。
「ところで、昨日私を愛した男のことだけど」シノは言う。世間話の延長でするような、淀みのない声だった。「あの人とはどういう関係だったの?」
「恋人だった」私は答えた。言葉を詰まらせれば負けだと思った。「一年半、二十代の最後をあげたわ」
「待って、あなた今年で三十歳?」
「見えないって言ってくれる?」
「ええ。同い年だとは思わなかった」
「……私も、驚いてる」
「そう……そうね。ああ、嬉しい」
そう言って、シノはもう一度グラスを差し出す。乾杯と、言いたいのだろうけどそうする理由はこちらにはなかったので、掲げられたグラスをただ眺めた。シノはしばらくそのまま私を眺めて小さく笑うと、乾杯、と一人きりで言って、「それで、どういう関係だったの?」と続けた。
「言ったでしょう。恋人だった」
「愛し合ってた?」
「何が聞きたいの?」
「教えて。あなたたちは愛し合ってた?」
「答える理由がないわ」
「あなたは愛してた?」
「意味がわからない」私は中身の残ったグラスを置いて、立ち上がろうとする。全ては一瞬で覆された。何もかもが嫌になった。もう、うんざりだった。わざわざ足を運んだことを後悔していた。人の恋人を奪って、全てを壊して、その残骸をヒールで踏み荒らすこんな女に付き合って馬鹿馬鹿しいと、そう思った。テーブルから腕が離れようとせず、やっとシノの手に気付いた。
「……待って、お願い」信じられないくらい、弱い言葉だった。懇願する視線も、かろうじて服の袖をつまんでいる指先も、私の知らないシノだった。
知らない? まさか、私はまだこの女のことを何も知らないというのに。
「……謝るから、あなたが望むなら土下座もする。お金だって払う。許せないならぶってくれてもいい……顔はちょっと、イヤだけど」
「そんなこと、してほしくない」
「あなたが望むならなんでもする。だからお願い……まだ行かないで」
勝ち負けとは、一体なんだろうと私は思う。こんな状況、どう考えても私の勝ちだった。けれど、どれだけシノを見下ろしても、思い描いていたものが心を満たすことはなかった。私には、私の求めるものがわからなくなった。
シノを振り払って(彼女はとても悲しい顔をする)、その手でスタッフを呼んだ。サウザゴールドと告げて腰を下ろすと、シノは嬉しそうな、まるでローティーンの少女みたいな笑顔を見せる。私はそれでいくらか気分が良くなって、自分が思うより単純な人間だとはじめて知る。
「花を、贈ってくれたの」今度はためらいなく、私は話し出している。「誕生日とかクリスマス、記念日、そういうのと関わりのないなんでもない日にも、思いつきで花を買ってきてくれた。私は、枯らせるだけだからって言いながら、いつも小さなグラスに移してた」どうして、私は花瓶を買わなかったのだろう。そういえば、帰ったら残したままの花も処分しないと。「もらってるだけじゃ嫌だから、私は思いついたらお酒を買って帰るようにしたわ。ウイスキー、焼酎、お酒の趣味はぜんぜん合わなかったけど、テーブルに飾った花を眺めながらグラスを交わすのは、好きだった」
ちょうど、グラスが二つテーブルに届けられる。最後にあの人と飲んだお酒を、あの人を奪った女と交わす。乾杯と、聞こえないように言う。
「好きな仕草も嫌いな口癖も、好きでも嫌いでもないところだってたくさんあったけど、あの時間だけは心から愛してたって思う」
その味は最後の時と全く違っていて、何もかもが変わってしまったことを強く感じさせた。
私が言い終える頃、ミラーボールが回転を止めてフロアに青白い光が広がる。チルアウトだ。まだ夜が終わるには早く、そして夜は長い。少しだけ音を下げて、ダンスをやめて、そういう時間がある。私はもう一度グラスを傾けて、シノを眺める。そうして、消えてしまったミラーボールの光をその目に見つける。シノはグラスごと私の手を包み込むと、あやうくこぼれそうな水面がしずまるのさえ待たずに言った。
「約束する」手のひらの熱で揮発したアルコールが、銀色にまたたいた。「その人の倍、ううん、毎日だって花をあなたに贈るわ。お酒だって、そう。思いつきじゃなくて、ちゃんとあなたのために毎日。だからね、レイコ。私を愛して」
私は、ぽかんとして目の前の女を見つめた。言葉を失ったので負けだと、ぼんやり思った。これで一勝一敗。勝負はイーブン、また振り出しに戻りながら、その場所はまったく違う意味を持った。
冗談、そう言おうとして、冗談じゃないことはすぐにわかった。シノの目は、傾国の妖艶さとあかちゃんみたいな愛らしさを兼ね備えたその目は、かけらの嘘もなく私を見つめた。手のひらの熱やかすかなふるえ、その全てが私の人生をおかしくしてしまった女から発せられていること。私は、自分を強い女だと思っていた。自負も、経験もあった。けれど今、事実が強い女の堰をたやすく壊して、私は笑った。大声をあげて、周りの目も不安げなシノの視線も気にせずに笑う、それがあまりに心地良かったのでしばらくおさまらなかった。
「そう言って、あの人も落としたの?」ほとんどこぼれそうになった涙をぬぐいながら、私は言う。「ああ、怒ってない。ほんとよ」
「もっとシンプルだったわ」
「でしょうね。で、ここへは何の目的で?」
「おいしいお酒、と……バカにしない?」
「ええ、知りたいの」
「……運命の人を探して」
「そのために、男に抱かれるの?」
「……そう。こういう歳になると、素敵な人には恋人がいて当たり前でしょう。もう、私なんて目に入らないの。だから、恋人を奪えば少なくとも私に気付いてくれるって思って」
「成果は?」
「あなたでふたりめ。最初の人には頭からワインをかけられた」
「あなたって、掛け値なしのバカね」
「言わないで」
「それか、本当の天才」
「二回も言わないでよ」
そう言ってシノが小さくとがらせた唇を、私は眺めた。小さくて、肉付きがよくて、見れば見るほど綺麗なところばかりに気付く。
「つまり、女性が好きなの?」
「性別にこだわりがないの。レイコは?」
あまりにも自然に口説こうとしたので、しまったと、シノは言ってから思ったみたいだった。弱気やおそれは突然に現れて、みるみるその表情を曇らせていく。シノは頬を赤く染めて、小さくうつむく。私は、よく揃ったまつげの生んだ影を眺めながら、口を開いた。ミラーボールが強い光を放って、叩きつけるみたいな音楽が声を呑み込んでいった。チルアウトは終わった。私はシノの手を取る、不安げな視線を導くと、一緒になって席を離れる。ワイングラスを離そうとしないので、うばい取って(今日いちばんに悲しそうな顔をする)フロアへ続くステップへ踏み込むと、そうしないと聞こえそうにない爆音の中で耳に唇を、ほとんど触れるくらいに寄せて言う。
「ダンス」
聞こえる流行りの音楽は、あまり好きな類ではなかった。けれど、今は楽しめるような気がしていた。
「踊りましょう。それが良かったら、考えてみる」
シノが答える。唇を寄せるのに、声が小さいから吐息の感触だけがわかった。
聞こえない、と私は言う。そうしてフロアの喧噪に溶け合うと、私たちはまたたきの間に一つのいきものになる。
宝石箱から出てきたメモを、私はくしゃくしゃに丸めてゴミ袋へ放り込む。ルージュで書かれた電話番号はとっくに読めなくなっていて、その役割を果たす代わりに、私に一年前のことを思い出させた。
どうして連絡を取らなかったのか、どうして宝石箱の奥底なんかに後生大事にしまい込んでいたのか、今となってはもう何もわからない。全部、過ぎたことだ。あの日離れた男も、それからの一年も、シノさえも、遠くに眺める思い出だった。この部屋と一緒に別れを告げて、二度と出会うこともない。それでいい。そうやって、私はまた新しい人生を始める。
けれど、あの日のダンスだけは忘れられなかった。
だから私は、こんな道を選んだのかもしれない。
部屋を引き払うと、その足で事務所へ向かった。おとぎ話のお城みたいな外観を眺めて、初めて実感が胸に訪れた。私は今日、アイドルになる。三十一年を共にしたこの身体と心を武器にして、まだ知らない、知るだなんて夢にも思わなかった世界へ足を踏み入れていく。
エントランスを抜けて、受付で約束を告げる。案内された二十四階のフロア、その部屋の前で一度だけ深呼吸をして扉をノックする。返事を確かめると、私をこの場所へ導いてくれたプロデューサーの前に腰を下ろす。挨拶と世間話を終えて、契約書や同意書の分厚い束を広げだした彼は電話が鳴ると、失礼します、と私を残して行ってしまう。
ため息をついてやっと、緊張を知った。
けれど黙って座っていたところで落ち着くはずもないので、ローテーブルの書類に手を伸ばす。私のプロフィール。まだ写真さえ載らない、退屈な文字の羅列に意味を持たせるその日を考えると、胸が高鳴った。その隣には、同じような紙束が並んでいる。もう一人、同日に契約をする人がいると彼は言っていた。
好奇心、それだけだった。書類のいちばん上、プロフィールを見ると、束の間息が止まった。ノックが聞こえると、どうぞ、とひとりでに私は答えていた。
失礼します、と記憶と同じ声を聞く。記憶と同じ姿を見る。私は、シノを見る。シノもまた、レイコを見る。私たちは重ねた視線に、一瞬の時間にあの日のまぼろしを見る。ミラーボールと流行りの音楽、アルコールのにおいと触れ合った肌、一度きりのダンス。
音もなく扉を閉じて、シノは私の隣へ腰を下ろした。それから目の前のプロフィールを手に取って眺めると、私を呼んだ。
「礼子。高橋礼子っていうのね」
私は答える。勝負はまだ続いている。あの日からイーブンのまま、ずっと。
「花は、毎日用意してくれてる?」
シノは首を振って、小さく笑う。
「お花って、枯れちゃうでしょ。悲しくって、やめちゃった」
でも、��シノは肩にかけたままでいた鞄を下ろすと、手をもぐり込ませる。再び現れたその手には、ワインボトルが握られている。
「いつでも礼子に会えるように、これ」
私は、思わず笑った。それでこの女は本当にバカで、天才で、最高のひとだと思った。
私はもう一度、プロフィールを眺める。志乃。柊志乃。その名前を、彼女のことを呼ぶ。
「積もる話はあると思うけど、とりあえずよろしくね。志乃」
「末永く?」
「考えるわ」
「踊ってみる?」
「踊りながら考えましょう、二人で。時間はたくさんあるから」
やがてプロデューサーが戻ってくると、私たちは居ずまいを正す。ボトルは鞄に隠して、背筋を伸ばして、大人らしく契約にまつわる面倒な話にしっかりと耳を傾ける。
けれどその寸前、私たちは約束をした。「今夜、あのお店で」とても静かなこの部屋で唇を耳に寄せると、「ずいぶん仲良くなったみたいですね」と彼は苦笑いをした。女には色々あるの。そう答えると私たちはまるで少女みたいに笑って、ちゃんと恋を始める。
0 notes
Text
【パトリック・バーン】 2021/2/4 23:55 JST
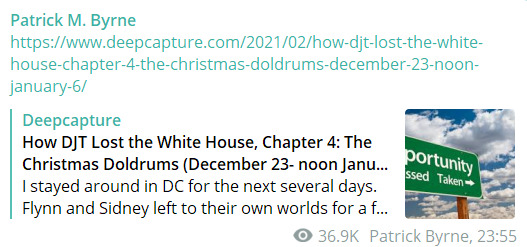
https://www.deepcapture.com/2021/02/how-djt-lost-the-white-house-chapter-4-the-christmas-doldrums-december-23-noon-january-6/
ディープキャプチャー
DJTはいかにしてホワイトハウスを失ったか 第4章:クリスマスのドルドラム(12月23日~1月6日正午
私はそれから数日間、DCに滞在した。フリンとシドニーは数日間、それぞれの世界に旅立ったが、マイクが旅立つ前に私たちは会話をした。この機会に、マイク・フリンについて少しお話したいと思います。私は現場で働いていた人たちからフリンが何をしていたかは知っていました。
※以下、4章の和訳。マール・ア・ラーゴ。激励会。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DJTはいかにしてホワイトハウスを失ったか、第4章:クリスマス・ドルドラム (12月23日~1月6日正午)
2021年2月4日 14分読む
私はそれから数日間、DCに滞在した。フリンとシドニーは数日間でそれぞれの世界へと旅立っていったが、マイクが去る前に我々は会話をした。この機会にマイク・フリンについて少しお話したいと思う。
現場で働いていた人から、フリンが沼の敵になるべく何をしたのかは知っていた。彼がイラクに到着したとき、空襲で得た物資は袋に束ねられ、「搾取」および分析のためバージニア州へ出荷され、また1、2ヶ月後に有益な情報が最前線の部隊へ戻された。フリンは起業家のように世界を見ており、プロセスを再設計することに着手した。搾取と解析をイラク内に基づいて行うことで、ループは18時間に短縮された。次の夜に人々が襲撃に出かけるときは前回の夜の働きから得た洞察を理解した状態だった。
最終的にループはとてもきつくなり、夕方とある場所での襲撃が、夜通しの調査によって、資料が作られ、夜明け時にまだ進行中の襲撃について報告するようになったのだ。私が知っていて信頼を置く、現場の人々が言うにはフリンという男には賞賛者もいれば、反感を持つ者もいた。反感を持つのは主に昔の少年のようなアプローチに慣れている人たちが中心で、彼が物事を揺さぶり、諜報機関の快適なやり方に現代的なアイデアを持ち込んでいることに不満を持っていたのだ。キャリアが進むにつれ、フリンのエスタブリッシュメントに対する分裂は伝説的なものとなったが、私の経験では、私が知っている明るくて元気で使命感のある連邦職員と思われる男女はフリンのことをよく褒めていたし、中道派はフリンを嫌っているように見えた。
しかし、マイク・フリンと一緒にいることで、彼のことを初めて知った。例えば、61歳のマイクは生涯民主党員として登録されていたが、アイリッシュ・カトリック系の、ボストン南部の北プロビデンスのジャック・ケネディ的な(現代の左翼的な「憲法をズタズタにしてしまおう!」というタイプではない)人物だった。彼は憲法に造詣が深く、私が知っている中では(私以外にも)数少ない、会話の中でフェデラリスト・ペーパーズを番号で引用する人物の一人である。アメリカの現代戦争について議論するとき、彼はチョムスキアンのような口調で、アフガニスタンとイラクでの戦争は15年前に終わるべきだったが、戦争を支援する企業に何千億、何兆ドルもの資金が流れ込み、その資金の流れから利益を得ている企業はとても太っていて、多くのロビイストを雇っていて、戦争を継続させるためにDCで戦っている、と話した。我々は冗談を言い合った、戦争はただの、「もう一つのワシントンがDCを、アイスクリームコーンが自分を舐めるようなのもの」だねと。
言い換えれば、『捕獲』。時々、私と同じように、全く異なる背景を持ちながらも、国家としての問題の根底にある争点を認識するようになった人に会う。その問題とは、強力なエリートたちが、政府の意思決定のサイクルを捉え、自分たちの私的な目的の方に変えてきたということだ。異なる経歴、異なる人生経験を持ちつつも、この国の何が間違っているのかという同じ根本的な分析に辿り着いた事実が、私の新しい相棒が正しい男であることを示してくれた。
「将軍、一体ここで何をしているんですか?」というような会話を何度も何度もした。
クリスマスは一人でDCにいたが、トランプの軌道の誰かから電話がかかってきた。電話の相手が言うには、フロリダに降りて、マール・ア・ラーゴの近くのどこかに行くべきで、それからトランプ氏ともう一度、10分程度の短い会談ができるように手配されているという。私はその時点までに、トランプ氏は健全な人々の話を聞いておらず、ある意味では大局を見落としていると完全に確信していたので、その招待状を受けて、DCからフロリダのマール・ア・ラーゴから数マイル離れたホテルへと向かった。私はチェックインし、連絡を待った。
ほどなく、実際にどれほど緊密な関係にあるのかは知らないが、トランプ氏と公に関係している有名な人物から電話がかかってきた。その電話に出ていたのは彼の同僚で、彼らは私に「マール・ア・ラーゴに行って、『アイリーン』(罪のない人を守るために別名にする)を呼んでくれ」と言っていた。アイリーンの苗字を聞いたら 「アイリーンを呼んで来い」と言われ、アイリーンの役職を聞いたら「アイリーンと言ってくれ」と言われた。「出来るだけ早くマール・ア・ラーゴに行って、アイリーンを呼んでくれ」。私は、そのようなやり方で仕事をするのは本当に嫌だ、行く前にもっと知りたいと答えた。するとまたしても断固として「マール・ア・ラーゴに行ってゲートに行ってアイリーンを呼んでくれ」との返事が返ってきた。「準備はできている」とのこと。不安を抱きながらも、自分の最高のヨガウェア(他のものはクリーニングに出していた)に身を包み、マール・ア・ラーゴに向けて出発した。Uberに電話してみると、乗っていたのは数年前の古ぼけてボロボロのトヨタカローラだった。
マール・ア・ラーゴの門に到着した私は、カローラを道へ送り出した。シークレットサービスの警備員に近づき、アイリーンに会いに来たと言うと、連邦捜査官はみな信じられないような顔をした。「アイリーンって誰?」彼らは尋ねた。「知らない」続けて「アイリーンに会いに行くように言われただけだ」「私は大統領と短い会議をする事になって」「呼ばれてここに来て」「アイリーンを呼んでくれと言われた」と答えた。「アイリーンって誰だ?」 と言われた。またしても私は知らないと答えるしか無かった。シークレットサービスの捜査官のせいではなく、彼らの混乱と義務感のせいで、会話はそこから急降下した。私はこの状況を助けられなかったのかもしないが、捜査官の一人が軽い中国訛りの女性であることに気付き、状況を落ち着かせてラポールを確立しようと、彼女と北京語でラップを始めた。かなりの時間話したが、他の捜査官の緊張感は増すばかりだった。その頃から、私は、この状況を打開して逃げ出し、電話で解決するのが最善の方法ではないかと考え始めもしたが、エージェントたちは許してくれなかった。
やがて、監督するエージェントがやってきた。彼は、一度会っただけで、相手にする人間ではないとすぐにわかるような人物だった。彼はまだきちんとしていたが、かなりの攻撃性を持っていた。「もう一度始めよう。我々はあなたの話を知りたい。あなたは誰で、ここで何をしているのですか?」
何から話せばいいのか分からず、私はこのように始めた。「20年前、オーバーストック・ドットコムという会社を始めました。私の名前は…」彼は「そうだ、君はパトリック・バーンだね」と笑いながら中断した。突然、私は、トヨタのカローラ、私のヨガの服、中国の....、を手に入れた。免許証を見せて、今度は全てが一致した。そして、フリンとシドニーと私の活動が注目されていることにも気がついた。それまでは自分たちがやっていることがどれだけ注目されているのかよくわかっていなかったが、ちゃんと意味をなしていたのだ。
いずれにしても、シークレットサービスのエージェントは親切になったので、私に頷き、何人かは私が敷地外に出て橋を渡り、別のUberに乗ることを許可してくれ、「あなたのしていることに感謝します」と言ってくれた。
私はさらに数日間、状況が改善されるのを待っていた。一度もなかった。��かし、その間、私はマール・ア・ラーゴの群衆の周辺にいたし、何百もの共和党のプー・バーの家族が休日のために集まって、周辺のホテルのほとんどを占拠していた。共和党の大物とその権力者たちの周辺で泳いでいるうちに、すべてのことの本質を感じることができた。そこには、イベントだけでなく、アイデアについても深い会話を交わすことができる、素晴らしい若者や知識人が何人かいた。私と同年代か少し上の女性で、フォーチュン50社の元役員で、定年退職した人がいたが、その人はとても強くて、有能で、知的だった。そして、私が見た限りでは、他の人たちは無法者だった。ピカピカの車に乗っている人、うるさくて不愉快な人、自己中心的な人、好事家、気取り屋、詐欺師、詐欺師、プラスチック・ファンタスティックの妻や夫やドイリーの子供たちは、自分たちが奪われたと感じるどんな話題においても公然とワインを飲んでいた。炎上していても小便したくなるような人間はほとんどいない。私が見なかったのは、信者、ビジョンを持っている人たち.... あるいは計画を持っている人もいなかった。
大晦日の前日、ジョージアの男から電話があった。フルトン郡(アトランタのある郡)では、郡の選挙活動が「イングリッシュ・ストリートの倉庫」と呼ばれる場所で行われていることはすでに知っていた。アンティファの女が500ドルで倉庫に潜入して写真を撮り、白紙の投票用紙を押収した。これらの投票用紙は、法医学的に検査された。私は、元旦に働いてくれる連邦政府認定の法医学文書検査官(この分野の古株)を2人手配して、大晦日にジョージア州に行った。
ジョージア州では、この取り組みに関わった何人かの人の家に泊まった。私が初めてジョバン・ピューリッツァー氏に会ったのはその時だ(私のサイバー仲間とジョバン氏の間には数週間前から連絡があったようだが)。また、マイクロソフトの上級セキュリティ専門家も同席していた。ジョージア州サバナでの集計作業で状況を把握していた人物だ。この人物によって、集計機には無線カードが入っていること、壁にはスマートサーモスタットがあり、そのサーモスタットは投票機に無線で接続されていたことが判明した。さらに調査すると、チャイナテレコムの誰かがインターネットを経由してスマートサーモスタットに接続し、投票機に接続していることが確認された。サイバーセキュリティの専門家は、選挙マシンの衝撃的な脆弱性、10年から15年前のOSソフトウェアで動作する傾向、そして一般的には技術がいかにスイス・チーズであるかについて、残りの時間を費やし語ってくれた。我々は真夜中まで脆弱性のカタログを作成していた。
元旦の午前3時にフリン将軍からメールが来た。彼はまだ仕事をしていた。彼はソーシャルメディアに公開された写真を送ってきた。マール・ア・ラーゴでは、ルディと側近たちが新年に沸き立っていた。ルディ、ドン・ジュニア、キンバリー・ギルフォイルがシャンパンを飲んだり、踊ったり、1999年のようにパーティーをしている写真がソーシャル・メディアを駆け巡っていた。またしてもフリンと私は呆れたような沈黙の瞬間を共有した。
元日は、連邦政府公認の法医学文書検査官の研究室にいた。彼の同僚が夜通し車を走らせそこまで運んでくれたのだ。検査官らは静かでプロフェッショナルだったので、私は彼らに仕事を任せた。1時間後、報告によると、投票用紙のうち2枚はある印刷所で印刷され、もう1枚は別の印刷所で別の用紙、別のインク、別の印刷方法で印刷されていた。郡が2つの異なる印刷所に投票用紙を注文した可能性は非常に低く、これは少なくとも1つの投票用紙が偽造であることを示していた。
ジョージアの男はアトランタの倉庫を監視していた。望遠レンズを持った奴らが撮影していた。許可を得て、発見したものに短い説明をつけてツイッターにあげた。数時間後、レンタルされたエンタープライズ社の引越しバンが倉庫に到着し、投票用紙のパレットがバンに移された。
次の日、隣の郡のシュレッダー会社は、裁断するので取りに来てほしいとの依頼の電話を受けた。呼んだトラックは、約3,000ポンドの投票用紙でいっぱいになった。支払いは「ドミニオン投票」からの人物によるカード払いだったと確認されている。裁断用トラックは走り去った。どういうメカニズムかは説明しないが、その裁断用トラックは妨害されて、作業が中断され、最終的に1万ポンドの裁断物が地元警察署の床に捨てられた、そうだから、証拠の連鎖があるのだろう。裁断物の約3,000ポンドは投票用紙だった(残り7,000ポンドは先客からのもの)。ドミニオン投票の従業員が注文した裁断方法は、通常の裁断(物を長い短冊状にする)ではなく、特別な方法(物を紙吹雪にする)でもなかった。それは、超超軍事級で採られている、投票用紙を裁断した後に砕いてドロドロにする方法だった。
アトランタのDHS(※国土安全保障省)の捜査官が到着し、指揮を執った。裁断された投票用紙の中には、完全に裁断されていないものもあった。実際、数枚はゴミ箱の壁にくっついていて丸ごと残っていた。さらに、私が聞いた話では、投票用紙箱の外面に残った領収書と出荷ラベルも発見された。これらの領収書と出荷ラベルは、中国南部にある中国の印刷屋から送られてきたものだった。DHSの捜査官がこれらをすべて入手したという(そして、その特定の仲介人は、中国の問題に精通していると聞く)。
その瞬間を「T=0」と呼ぶ。アトランタからの継続的な報告をもとに、次の2日間の展開をご紹介する。
・T + 6時間。ルディ・ジュリアーニが、何が起きているのか知らされる。
・T + 9時間。マーク・メドウズが、何が起きているのか知らされる。
・T + 18時間。FBIが引き継ぎのために現場に到着する。DHSは抵抗。
・T + 24時間。問題のDHS捜査官から政治的な圧力を受けていることに非常に不快感を抱いている、というメッセージを受け取る。私の理解が正しければ、マーク・メドウズ本人(ホワイトハウス参謀長)から電話があり、調査を手を引くように言われたという。私がただの傍観者としてそのメッセージを受け取っていたのか、それともDHSの仲介者が、私がそれについて何かできるかもしれないという誤った希望(例えば、大統領に知らせる)を抱き、意図的にそのメッセージを寄越したのかどうかは、はっきりとはわからない。
・T + 36時間。FBIが作戦の主導権を握る。FBIはシュレッダー会社を呼び戻し、1万ポンドを引き渡し、裁断を完了させ、その後、通常業務を続けるよう指示をした。すなわち、裁断された素材は、水と酸を混ぜて、溶け、再編成されてしまった。リサイクルペーパーとして。
上で話したような物語の様々な側面は写真やフィルムに記録されている。
その間、私はDCに戻っていた。私はまだトランプ氏ともう10分でも話をしようとしていた。もし、1月6日に負けるのを待ってから我々のプランを試しても、それは負け惜しみにしかならない、と繰り返し言っておきたかった。しかし、まだ数日の猶予が残っていて、もし彼が引き金を引くなら、問題のある6つの郡についての回答を得られるだろう。我々が1月6日前にそれを完了すれば、上院は情報に基づいた選択をしてくれるかもしれないし、1週間猶予を与えてくれるかもしれない等々……
ここで重要なサブストーリーを一つ挿入しておく。当時、ちょうど大統領に近しい様々な人たちと一緒に泳ぎ回っていた頃、トランプ氏の側近に非常に近しい人物からあることを聞かされた。それは、メラニアは政府高官から、もしトランプがもう一期務めるならJFKのようになるだろう、と通告されているのだと。シークレットサービスの誰かが「我々は守りきれないだろう」という意味で警告したのかもしれない。脅迫の中には、もう一人の家族も含まれていたそうだ。シークレットサービス自体がそんなことを言うとは信じがたいが、私にとってその情報源は、他の点は汚れのないものだったし、メラニアにこのようなことを言ったのが誰であれ(おそらくシークレットサービスか、おそらく他の誰か)、そのような主張を真面目に受け止めてもらえる人物だったのだ。メラニアはドナルドに対し、戦わないように、そしてシンプルに負けを認め家族と一緒にワシントンから出て行くようにと懇願していた。
フリンと私は再びDCで一緒になり、1月6日が近づいてくるのを、イライラした鷹のように見守っていた。私は何度かインタビューを受けたことがあるし、少数の演説でも次のように主張してきた「私たちは暴力を振るわないし、その点他の奴らよりも優れている。もし暴力をふるえば負けだ。」と。あまりにわかりきったことだと思っていた。
私は集会を企画する「ウーマン・フォー・トランプ」から、1月6日の朝、南芝生での講演に招待されていると知った。私は要点を2つに絞って話に備えた。第一に、被治者の同意する我々のシステムがいかに、自由で、公正で、透明性のある選挙に依存しているのか、ということ(11月の選挙はそうではなかった)。第二に、我々は暴力をふるわない、ということだ。(※追加注:『被治者の同意(consent of the governed)』とは、公権力・国家権力を行使する政府の正統性や道義性は、その権力が行使される対象である人民ないし社会によって同意される場合にのみ、正当化かつ合法化される、とういう政治的概念。)
非暴力についての要点を考えるにあたり、私はどちらの方法をとるか迷っていた。
・ジェリー・ガルシアとグレイトフル・デッドから非暴力に関する話をする(ディープ・キャプチャーにも書いたことがある:『ジェリー・ガルシアの対峙と「主立ったクソ野郎」について』)
・モルドバについての話をする。数年前に行ったことがあるのだが、バーテンが2009年の選挙の話をしてくれた。選挙の不正が原因で親プーチンの男が当選したが、人々はそれを知っていて抗議の声を上げていた。プーチンは、首都キシナウに何百人もの男たちを派遣していたが、彼らにはある任務があった。プーチンの男たちは、抗議が起こるたびに、抗議を暴力的なものにすることを目的として抗議に潜入し、政府の建物の前で抗議をするだけでなく、抗議をしたり、窓を割ったり、占拠したりしていたのだ。モルドバの人々はとても賢いのでプーチンの策略を知っていた。プーチンは、双方が、モルドバの中産階級という観客のために演じており、抗議者を挑発して実際に政府の建物を襲撃させることができれば、中産階級をうんざりさせ、大衆の支持を失うことになることを理解していた。モルドバの人々は、自分たちを律し、自分たちがそのような道に導かれることを拒み続けてきた...そして最終的には、政府は屈し、新たに公正な選挙が行われ、プーチンの取り巻きが大敗した。その話も書いた:『全米の民兵へのメッセージ、チンピラ左翼と工作員について[ランジェリーではない]』
ホワイトハウスの芝生の上で、どちらの話を使うか迷った。5日になって、私は群衆はジェリー・ガルシアが誰だか知らないかもしれないと判断したので、その話をオンラインで書き上げ、DCに到着した群衆に数回ツイートし、1月6日の朝、演説に使うと決めたモルドバの話について簡潔に説明するリハーサルをした。
マイク・フリンも講演すると知らされていたので、マイクと私は、お互いに何を言おうとしているのか、群衆は何を聞く必要があるのか話し合った。この機会がユニークで歴史的なものだと認識していたのだ。おそらく30分で、選挙を混乱させ、結果を変えてしまった可能性の高い不正行為を世界に向けて説明しなければならないだろう。我々はその挑戦に応えるために準備をした。サイバー忍者や科学者など、一緒に仕事をしていた彼らもまた、簡潔に説明できるよう備えていることは理解していたが、その中から誰がスピーチをするかは主催者側が決めることになっていた。
マイク・フリンと私は、1月6日の朝はこのような流れになると考えていた。演説は、ホワイトハウスの南芝生で行われる。マイク・フリンは「人々の将軍」として、この瞬間を歴史的な文脈に置いて話をする。私は、自由、公正、透明性のある選挙の基本的な意義について、それからモルドバの話をする。その後、2-3 人のサイバー忍者や科学者に交代し、それぞれが 5-10 分間ずつ話し、市民の良心を悩ませるべき不正の最も明らかな点を説明する。私は経験から、彼らのうちの一人が5分から10分も話せば、良識ある人は2020年11月の選挙について重大な疑念を持ち始めだすと知っていたが、3人が話し終えた後、世界中の視聴者の80%は2020年の選挙結果がなぜ無視されるべきなのかを理解するだろうと思った。
その日の夕方、私が話すと予想していた科学者の一人から電話がかかってきた。彼は、自分の講演枠がキャンセルされたと知ったので、DCには行かないということを知らせたかったのだそうだ。その科学者は非常に物腰が柔らかく、教授のような人で、心を開いて話を聞いてくれる人には説得力��あると思っていたため、私は戸惑った。11月3日の週に起こったことに深く懐疑的であるべきだと、何百万人もの視聴者を説得するために、彼よりも良い仕事ができる誰かを見つけたのだろうかと考えた。
1月6日の朝、フリンと私と他十数人でホワイトハウスの南側に歩いて行った。 特別な手配がないことに驚かされつつ、人ごみの中を必死で駆け抜けた。我々二人はスピーカーバッジを渡され、前方の特別席に着席して....その後、自分たちの講演がキャンセルされたことを知った。我々は控えめに言って途方に暮れ、我々と同じように状況をなんとか説明できる誰かがいるのだろうかと驚いていた…
ショーが始まり、すぐにフリンと私は絶望のあまり席に沈んでしまった。トランプの子供の一人が立ち上がり、ガールフレンド、あるいはボーイフレンドに「ハッピーバースデー」を歌った。ルディが立ち上がって、ジョー・フレージャーが投票したことについて、また話をした。別の弁護士が立ち上がって話した。ドン・ジュニアが立ち上がり、胸を膨らませてステージを闊歩し、共和党のブランドがトランプのブランドになったとか、トランプのブランドが共和党のブランドになったとか、ブランディングの話をしていた。その頃、フリンと私は目が合うと、互いに恐怖の表情を見て取った。後で判明するに、どちらも、この場を離れたいのかどうか尋ねており、互いに誤解したようだ。(※フリンの様子が?ステージが?)あまりにもひどかったので、主催者の中で分別のある人が心変わりし、フリン将軍にステージに立つかどうかを聞きに来たのだが、辞退した。悪ふざけが1時間以上続いた後、トランプ氏が登場し、選挙イベントや激励会と同じように話した。実際、全体は多かれ少なかれ、「私は権利を奪われた」を推す会だった。群衆に向けて、1時間後に投票を始める上院議員たちに向けて、自宅で視聴するアメリカ人に向けて、自由で公正で透明性のある選挙の先導者としてのアメリカに期待を寄せる世界に向けて。2020年11月の選挙で何が間違っているのか、そしてなぜ我々は徹底した調査を要する深刻な不正があったと信じているのか理由について、説明しようとする努力は全くなされなかった。大した努力は一切ない。
代わりに、激励会を行った。それだけ。「私は奪われた」トランプ激励会。
前列から離れることができた瞬間、私とフリン、そして私と一緒にいた全員が、出口に向かってダッシュした。感想を話し合ったとき、フリンは怒りを抑えるのがやっとの様子だった。これが全世界に状況を説明する最後のチャンスだったのに、トランプは激励会に利用したのだ。「彼はそれを理解していないだけだ」と、我々はホテルに向かって群衆の中を嵐のように駆け抜けながら、お互いに繰り返した。「彼は自分事ではないのだとわかっていない。彼はクソ激励会をした。彼は自分のことではないと理解していないんだ」と怒りと絶望の中で何度も何度も繰り返した。15分後、ホテルに戻ると、二人とも荷物をまとめ、二人とも胃が痛くなり、議事堂に向かい移動する群衆に合流しようと出発することはなかった。
※やたー訳したー。げそー。他の章はまだ途中。
※1/6あのトランプの演説を見て、私もなんでこんなダラダラ同じような話ばかりするのか?あきれて割と絶望していたので、このバーン氏の記事を読んで、ほんと胸のすく思いがした。似た思いをした人がいたのか…ウルウル。いやバーン氏らの方がショック深刻だったろうし、いずれにせよ現在進行形でいい結末ではないけれど。あー面白かった。ノンフィクションは続きます。いつか選挙不正の証拠の数々がきちんと白日の下にさらされますように。そして本になりますように。
0 notes
Text
#076 ナビゲーター(袋小路でやぶから棒に)
あの、すみません。まずは、あの、はい。お、お、落ち着いて。あ、すみますみすみすみません。とりあえずは、まずは、なにをおいても、こういう時は、ええ、絶対的、可及的、速やかに、落ち着くことが大前提かつ大事ですから。はい。とにかくまずは、深く、ふかく、ふか……げええっほんえふんげふんごめんなさいんんんっ。はい。深呼吸から……はあ、深呼吸から始めましょう。それから、すべてはそれからです。息をすう〜、はあ。すう〜、はあ、して。……そう、そーうですはいはい。はい。はい。よくできました〜。あっすみませんすみません。怒らないでください。馬鹿にしているわけではないんです。けっして、断じて、誓って、そんな失礼なこと、あなたにするわけないじゃありませんか。そう思いません? 思いますよね? よかったよかった。それでですね、まずはそのー。あっ、挨拶がまだでしたね。えと、おはようございます。あ違うか違いますね。はじめましてですねこういうときは。人と人がはじめて、こう、顔面を合わせると言いますか。初対面。そう、初対面、ですよね? 満員電車の中ですとか、信号待ちの間ですとか、もしかしたらもしかすると、偶然ばったり出会っていたのかもしれませんけど。あ、こういう場合――つまり、まだちゃんとした初対面の挨拶を交わすより以前に、あなたを見かけていた場合――も、ばったり、とか、偶然、って、使うんですかね? そこんところ、ちょっとよくわかんないんですけども。でも、そうですね、とりあえずは、はじめましてにしておきましょうか。しておいてください。どうか。どうか……。
えと、それでですね。あなたの頭には今、たくさんのハテナが浮かんでは消え浮かんでは消え――あ、消えてはいないですか。それは失礼しました――、していると思うんですよ。そりゃ思いますよ。思うことでしょう。誰だってこんな、非常時にはそういう思考回路が働くものです。誰だこいつら、と。なんでこんなに腰が低いんだ、と。そもそもなんで部屋にいるんだ、と。こんな早朝に、と。まだアラームが鳴る二時間も前なのに、と。得体の知れない輩に安眠を妨げられたぞ、と。今日は祝日なのに、と。小鳥のさえずりしか聴こえないくらい早朝じゃないか、と。チュンチュク鳴いてるあの小鳥はスズメだろうか、と。そうですおそらくスズメです。それにしても最近、スズメを見かけなくなりましたよね。なんでも年々スズメの数が減っているらしいですよ。ええ。ええ。本当ですとも。こんな所で嘘なんかついてなんになるんですか。こんな、高層ビルの裏の、袋小路の、ゴミ臭い、陽の当たらない場所で。……そうですとも、まだ寝ぼけてますね。大丈夫ですか? もう一度深呼吸しますか? コンコンコン、おーるーすーでーすーかー? いえいえ冗談ですってすみませんってばふふふ。ああ失礼。とにかく、今一度、辺りを見回してください。たっぷり、首を左右上下に、三往復くらい、動かしてみてください。首の運動には眠気をふきとばす効果もあります。そうしたら、けっして慌てずに、まずはこの文章に目線を戻しましょう。
これでようやくお分かりになりましたでしょうか。ああ、よかった。ホッとしました。とりあえず、ホッ、とさせてください。この仕事も、いろいろと気苦労が絶えないのです。ほら、その、あなたのように、イレギュラーな状況で浮空期に突入した場合、パニック障害を併発することもめずらしくないのです。ええ、ええ、ここだけの話。そうなんですよ。
まさか俺が。そう思ってますか? ついにきたか。そう思ってますか? なんでまたこんな時期に……。そう思ってますか? まあ、災難ですね、としか言いようがないですね。五年間、学生のころから付き合っている人と別れて、しかもその人には二年前から別の恋人がいて、つまりあなたは二年間浮気をされていて、しかも付き合っている人的にはあなたより浮気相手のほうが本命で要するにあなたは浮気されていたと言うよりあなたが付き合っている人にとっては浮気相手のようなもので、お荷物で、ただのヒモ野郎で、ノータリンで、……みたいなことを昨日の夜付き合っている人と付き合っている人の浮気相手に一方的にまくし立てられて、あなたは驚きすぎてなにも言い返せなくて、むしろ驚きを通り越してなにも感じなくて、なにも感じないのだから当然言うべき言葉も言いたい言葉もなにも浮かばずただあなたは「ふうん」という心持ちで冷蔵庫から缶チューハイ――夏みかん味の五〇〇ml――を取り出してグビグビ飲んで、飲んでいるうちにやっぱりなんだかムシャクシャするなあとぼんやり思い始めて、特に暴れもせず泣きわめきもせずに、無表情のまま付き合っている人の浮気相手の頭頂部に残りの缶チューハイをダバダバと注いで、付き合っている人も付き合っている人の浮気相手もなぜだかまったく動じずに「なにこいつ」といった眼をあなたに向けるだけで、缶チューハイを注ぎきったあなたは「ほいじゃ、俺はこれで」とでも言い出しかねないくらい気さくな身のこなしで玄関の百円ショップで買ったオレンジ色のサンダルを履いて、行きつけの、駅前のおでんの屋台にでも行こうかなと足を動かしはじめたはいいものの、途中でそっか今日日曜日だわおでん屋やってねーわってことに気づいてしばらく迷いながら歩いた結果駅前のカラオケ館に足が進んで、人生初の一人カラオケというものでもしてみようかという気持ちにだんだんなってきて、「一名で」なんて少しぶっきらぼうに、顔を横にぷいっとそむけそうなくらいそれはそれはぶっきらぼうな「一名で」を店員に向かって投げ捨てて、二〇一の札を笑顔の店員に渡されてあなたは仏頂面のまま二〇一号室までペチペチ――サンダル履いてますからね――歩いて、着いて、固いんだか柔らかいんだかはっきりしないソファーに体を沈めたあとに「別に俺、歌いたい曲ねえや」ってことに気づいてその言葉を実際に口に出して、何回か舌打ちしながらメニュー表をめくって少し迷った末にあなたは生ビールを頼んで、パリパリという音と共に今にも剥がれ落ちそうなくらい乾いた笑顔で店員がそれを運んできて、あなたは痙攣のような会釈だけして店員が去るのを待って、一息で飲んで、頼んで、飲んで、頼んで……、午前三時――つまり日付的には今日、ですね――の退出コールギリギリまでそれを繰り返して、千���足で、階段で二、三度転けそうになりながら、爪先立ちみたいな体勢で一階のレジまで歩いて、店員に番号札を渡してから「そういや俺財布持ってきてねーじゃん」ってことに気がついて、「やべ」と口から出かけて、千鳥足のまま操り人形みたいなぎこちない動きで右向け右をして、そのままダッシュで逃げて――お客様! おい! お客様! という声を後ろで聞きながら――この路地裏まで逃げて逃げて逃げて、倒れ込んで、眼を閉じて、そして眼を開けたら見知らぬタキシード姿のおっさんがいて、こんなあなたのプライベートな情報をペラペラと喋られているんですからね。ほんと、災難でした。いや、現在進行形で、残念ですね。ご愁傷さまです。あ、死んでないですね。しかしながらですね、もうちょっとクサい言い方をさせていただきますとあなた、あなたの心はもう死んでいるようなものです。あなたの半分、半身は、ご愁傷さまって感じですね。ほんと。ところでご愁傷さまってあなた、実生活で言われたことあります? 初めて言われたんじゃありませんか?
とりあえず、あなたは今、立ち上がっています。いますよね? まあ、地に足は着いていませんが――いえいえあなたの生き方がというわけではありません、ですからどうか、その握りこぶしを解いてください……そう、そう、ゆっくり、ゆっくりね――、とりえあず、〈立ち〉上がってはいます。ね。そうでしょう?
あなたみたいなケースはわりかしめずらしいのです。ですから、ええ、さきほどから再三、���をこれ以上ないというほどすっぱくして申し上げておりますが、どうか、落ち着いて、冷静に、行動なさることが肝要なのです。浮空期の初期段階に不慮の事故等で死亡してしまうケースはままあります。ですから、あなたのこれまでの人生の、常識の枠は一旦、外していただいて、どうか、説明委員会の言葉に耳を傾けていただきたい。いいですね? はい。いい返事です。そうしましたらまずは、説明委員会の名に恥じぬよう、簡単かつ簡潔に、ご説明のほう、させていただきます。
まずはそう、あなたの足元、ゆっくりと、再度確認してみましょう。はい、そうです。そうですね。浮いています。宙に浮かんでいますね。重力から解き放たれて。歩こうとしても足がスカスカッと空を切って歩けませんね。ええ。そうです。浮空期の間、通常の方法で――つまり、左右の足を交互に、前後に動かして体全体を前に押し進めるという方法のことですね――歩くことができません。ええ、ええ、仰りたいことはわかります。不便ですね。とーっても不便です。エスカレーターに乗ってもあなたの足の下で段差が動くだけです。エレベーターは……、ふふ……、ああ、いえ失敬。すべてを説明してしまっては興も冷めるというもの。わたくしども説明委員会は、過剰な説明は過剰な愛、を社訓――委員会の場合も社訓って言うんでしょうか――に掲げて日々浮空期の方々へのツボを押さえた適切かつ適度な説明――そう、それはほとんど愛――を心がけております。ああっ、そこそこ、その説明。あーちょうどいい、いやあいいわあ。きもちいい……。という声をいただくこともままあります。というわけで、あなたには、肝心要の部分のみ、ご説明させていただきます。あなたもこの宇宙の、この地球の、つまり、宇宙船地球号の乗組員である人間ならば、今、ご自分の体に起こっている現象、そしてその現象の名称、ある程度は理解しているはずです。なにしろ今は朝の七時。人間の脳みそが一番活発に動く時間帯です。もっとも、その三〇分前までに朝ごはんを食べていればの話ですが。あっ、そういえばタキシードの右ポケットに、あなたに会う前にコンビニで購入したおにぎり――焼きたらこ――が入っています。説明と、あなたの練習がてら、このタキシードの右ポケットから、自力で、おにぎりを取ってみてください。安心してください。取って食おうってんじゃないんですから――それに、取って食おうとしているのはあなたですよ――。さあ、指示通りに、体を動かしてみてください。まずはお尻の穴……肛門付近に力を入れてください。なかなか出てこないイケズな大便をひり出すように――もちろん、本当にひり出してはいけませんよ。そういう人、案外多いんです――。そして右人差し指の爪を甘咬みしてください。それが体を動かす方法です。車に例えると、肛門に力を入れることが、エンジンを吹かす行為、右人差し指の甘咬みが、エンジンとハンドルを操作する行為です。甘咬みしたまま手首を左右に動かすと、その動きに連動して……おお、そうそうそうです! その調子です! そのように、体が左右に回転します。そのまま手首を動かして、こちらに体を向けるようにして、はいはいその調子ですよ、そして、その状態で肛門に力を……そーうです! これで前進はわかりましたね。ちなみに後進――バック、ですね――したい場合は、おヘソの辺りに力を込めてください。腹筋を鍛えるような感じで……おおー、いいですね、いいですよ。はい、では、もう一度、前進して、近づいてみましょう。ちなみに力を入れれば入れるほど、スピードは速くなります。はい、これであなたとタキシードの距離は限りなくゼロになりました。ちょっと、その、気まずい距離感ですね。吐息がかかる距離、と、言いますか。恋人でないと許されない距離、と、言いますか。あっ、いえ、別にその気はありませんのでご安心を。では、右ポケットからおにぎりを取ってみてください。はい、よくできました〜! 何度も言うようですがバカにしているわけではありませんよ。なので、どうかその、怒髪天を衝くかのような肩の上下運動を辞めてくれませんか。ちなみにですね、浮空期の間は、自分の体重、身長以下の物なら、一度触れれば宙に浮かせる事ができます。ですから、その、おにぎりを口いっぱいに頬張るのを一旦中断していただいて――ええ、ええ、ほんと、すみません。お願いですからそんな怖い顔しないでください――その練習も、一応、やっておきましょう。万が一、ということがありますからね。その力が誰かの命を救う。なんてことが、無いとも限らないですから。例えばこの、二五階建てのビルが火事になって、逃げ遅れた人が外に面した窓ガラスに追いやられていたら、窓ガラスを割ってもらって、あなたはそこら辺にある――ああ、あそこにちょうどいいベニヤ板がありますね――ベニヤ板を触って、逃げ遅れた人がいる階まで浮かせて、エレベーターの要領でサラリーマンやOLの方々を救い出すことが出来ます。素晴らしいじゃありませんか。浮空期の特権です。もちろん多くの人から感謝されます。ありがとう。ありがとう。君がたまたまこんな路地裏で、酔いつぶれて寝ていたおかげで助かったよ。助かりました。握手。握手。さらに固い握手。そして感謝状の授与。嗅ぎつけたマスコミがあなたをネタに記事を書く。あなたは一躍有名人。街中でサインなんか求められたりして。ああ、はい。そうです。ええっ、サインですか。いやいやそんな。サインするほどの人間じゃあ……、ああ、そうですか……? じゃあ、まあ、はい。えっと、ここに? はい。はい。サラサラサラ、っと。あ、ちょっと、カメラはちょっと。恥ずかしいっていうかなんていうか。いやはは、まいったなこりゃ。そしていそいそと人混みをかき分けて目的の場所へ進むあなた。目的の場所――川沿いに最近オープンした小洒落たヴィーガンレストラン――には、ビル火災の中、果敢にも人々を救ったあなたのことが書かれている記事を読んだ元恋人。再会を喜ぶ二人。微笑みを交わす二人。まずはグラスワインで乾杯をしようではないか。注文をしようと手を上げたあなたを元恋人は優しく止める。ワインはちょっと。だって、私のお腹には、もう……。あなたの耳には聴こえないはずの、命の、微かだけれど確かな鼓動が聴こえてくる。そう、あなたと元恋人の――現、伴侶の――。……なんてことにもなるかもしれないのです。あ痛い。いたた。ごめんなさいごめんなさい。まだ一応、正式には、面と向かって、別れを告げられてはいなかったですね。元恋人ではありませんでしたすみません。すみませんってば。
えと、それで、なんでしたっけ。ああ、説明がまだ途中でしたね。触れた物を浮かせたい場合は、左人差し指の爪を甘咬みします。はい。そうです。甘咬みした瞬間から、物は浮きます。あとは、基本的な動作は先程の、体の操作と同じです。肛門に力を入れると前へ、おヘソに力を入れると後ろへ進みます。上へ上へと浮かせたい場合は、甘咬みしたまま腕を上げてください。上げている間、物は上昇し続けます。落下させたい場合は甘咬みをやめるか、腕を下げてください。その他、細かい動きはすべて、甘咬みしている間、左腕の動きと連動します。簡単でしょう? 最初のうちは微調整が難しいでしょうが、すぐに慣れるはずです。あなた、なかなか筋がいい。いや、本当ですよ。浮かせることすらままならない人も、最近は多いのです。……ああ、そうそう言い忘れていました。浮かせることができる物は、最後に触った物だけです。複数の物を同時に操作することは出来ません。気をつけてください。くれぐれも。
そうそう、これは最初に説明しておくべきでしたが――いやほんと、説明委員会失格ですね――。男性の生理と言われるくらいですから、女性同様、浮空期の前後、浮空期の間で心身に様々な変化が起こります。顕著に現れるのは性欲の減退ですね。浮空期の間、睾丸の機能は著しく低下します。常に射精直後のような状態になる、と言ったら、わかりやすいでしょうか。浮空期の間は女性を――ゲイセクシャルの場合ですと男性を――見るだけで苦痛に感じる人もいるそうです。いやはや、そこまでいくとちょっと理解し難いですね。とにかく、どんなにお盛んな人でも、浮空期の間は射精することが困難になります。ま、大体の人は射精をする気も起こらないので、大丈夫でしょう。
先程、常に射精直後のような状態になる、と説明しましたが、浮空期が近づいてくるにつれて、段々とそういった精神状態になっていきます。落ち着いて、冷静に、物事を判断できるようになる、ということですね。あなたは昨日、元――……失礼――恋人とその浮気相手に散々ひどいことを言われたにも関わらず、ある程度は平静を保てていました。今になって考えてみると、それは浮空期直前特有の症状だったのかもしれませんね。そして、安定した精神状態に移行してから大体三日後、夢精を合図に浮空期が始まります。……ええ。ええ。そうです。あ、気づいていませんでした? あなた、夢精したんですよ。この、高層ビルの裏の、袋小路の、ゴミ臭い、陽の当たらない場所で。あ、ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさいってば。
ちなみに浮空期は、月一回ペースでやってきて、およそ一週間で終わります。終わる時は夢精も何も起こりません。目が覚めたとき、体が地面にピッタリくっついていれば、それが終了の合図です。性欲も、精神状態も、通常に戻ります。もう、ビンビンの、グングンです。その、あなたの、スカイツリーに負けじとそそり勃つイチモツを、存分に振り回していただきたい! まあでも、今はとりあえず、精子が乾いてカピカピにならないうちに、ティッシュ――あ、ポケットティッシュ、持ってたんでさしあげます――で綺麗に拭き取ってください。大丈夫です。後ろを向いておきますから。どうかお気になさらずに、あなたのペースで、慌てることなく、精子と、そのぬめり気のあるパンツを処理してください。ここにはあなた以外誰もいない、誰も来ない。袋小路なのですから。栗の花の匂いが染み付いたパンツの一つや二つ、ポイ捨てしてしまっても何ら問題ありません。ええ、ええ。本当ですとも。さあ、一刻も早く――されどあなたのペースは乱さずに――その青いチェック柄の、ゴムが伸びきっていて、歩くと少しづつずり落ちてしまう、三年前に――そう、恋人と付き合い始めたころ、ユニクロで――買ったトランクスを、どうぞ、地面に叩きつけてください。そして、彼がトランクスを力の限り地面に叩きつけたのとほとんど同時に、今までピーチクパーチクしゃべり続けていたタキシード姿の男の隣にただただ突っ立っていただけのもう一人の男――もう一人の男は、ジーパンに半袖シャツというラフな格好だった――が、やぶから棒に、口を開いた。川城さん、も、いっすかね僕しゃべっても。いっすかね。やっぱり〈あなた〉とか言われたってピンと来ないっすよ正直言って。えっと、矢野さんでしたっけ? わかんないっすよね。いやいや、誰だよ。みたいな。そう思いません? ……あ、ちなみに自分、宇城っす。ままま、川城さん、ちょっとここからは、もうちょいわかりやすく、僕が説明しますんで。だ〜いじょぶっすよ川城さ〜ん。これでも自分、説明の成績はトップなんで。川城さんは僕の隣で、ドシンと構えてくれてればいっすから。はい。はい。
矢野は自分の体の感覚を取り戻しつつあった。この袋小路で、怪しげな説明委員会の男二人組に揺り起こされて、ついに自分が浮空期になったということを知らされてから、ずっと、自分の体を見知らぬ誰かに操られているような気分だった。歩く動作をしているのに、前に進まない。体の向きを変える���ともできない。これが浮空期か。タキシード姿の男、川城の説明を聞きながら、矢野は昨日の出来事や恋人の浮気相手のこと、サンダルで家を出たのに今は裸足だということ、雨が振りそうな雲行き、何枚も溜まっている公共料金の請求書のこと、などなど、とりあえず現時点でわかる限りの問題や不安、悩みを頭の中でリストアップしようとしてすぐにやめた。そんなこと考えてなんになるというのだろう。自分だって、恋人との生活に限界を感じていたはずだろ。職だってそろそろ本気で探さなくてはいけない。バイトでも内職でも、コンビニでも工事現場でもディーラーでも汚染処理でもなんでもいい、恋人とすっぱり縁を切るからには――やはり、そうするしかないのだろうか――、自分の時間を売ってお金に替える方法を、早いとこ見つけるしかない。それ以外のことを考えるのはやめよう。やめよう。
川城の説明通り、今の矢野には性欲がまったく無かった。まるで最初から存在していないみたいに、きれいさっぱり、消え去っていた。なるほどこれが生理か。矢野は、二八歳という、あまりにも遅咲き過ぎる自分の心身の変化を、戸惑いつつも楽しんでいた。浮空期は女性の生理と違い、始まる時期が人によって大きく異なる。五歳で浮空期が始まった宇城――今、川城の隣でしゃべり続け、言葉を書き連ね続けているジーパン姿の男――のような人もいれば、矢野のように成人してから浮空期が始まる人もいる。死ぬ間際、病院のベッドなどで始まるようなケースも極稀にだが、存在する。その点だけ見ると、生理というよりむしろ水疱瘡やおたふく風邪に近い。矢野は宙に浮かせっぱなしだったおにぎりを口に投げ入れ、というより口の中まで移動させ、ゆっくりと咀嚼した。
携帯を見ると不在通知が何件も届いていた。知らない番号だ。おそらく昨日行ったカラオケ館からだろう。なんでてきとうな番号をでっちあげなかったんだ。名前も、きっちり矢野とバカ正直に書いてしまった。いや、それよりも、なんであのとき逃げてしまったんだ。いやいや、そもそも、なんで恋人の部屋で自分はあんなに落ち着いているかのようにふるまってしまったんだ。なんで外に出たんだ。なんで財布を忘れたんだ。これもすべて浮空期の前兆がもたらした行動なのか。考えてもきりがない。どうせもう身元はわれているのだ。説明委員会の二人ですら知っている情報ばかりだ。自分があれこれ案じても何も変わらないのだ。矢野は携帯で一週間の天気を調べた。次に晴れるのは四日後か。ふん。
矢野は左人差し指を甘咬みし、携帯を宙に浮かせた。左腕を思い切り上げると携帯は物凄いスピードで上へ上へとグングン昇っていく。このまま昇り続けるとどうなるんですかね。甘咬みした状態で矢野が宇城に話しかける。まあ、大気圏は余裕で越えるっす。それでもさらに昇り続けたら、どうなりますかね。だんだん、空気が無くなっていくんじゃないっすか、詳しくは知らないっすけど。空気が無くなっても、さらにさらに、昇り続けたら、どうなりますか。宇宙まで行きますね。宇宙を進み続けたら、どうなりますかね。あーそれ、たしか、どっかで読んだか聞いたかしたんすけど、それで、どんどんどんどん進み続けて、何光年も先の宇宙まで進み続けて、そうやって浮空期の人たちが飛ばした物が星になって、星と星を人が繋げて星座にして、だから僕らがこうして星空を見て、おうし座だとかふたご座だとか言っているものは元々遠い昔の人々が宇宙に飛ばした貝殻とか、お椀とか、槍とか、弓とか、筆記具とか、パンケーキとか、ガラス瓶とか、綿棒とか、お相撲さんのマゲとか、レコードとか、煙草とか、パピルス紙とか、羊の毛とか、豆電球とか、画鋲とか、死んだ人の骨とか、貞操帯とか、トランペットとかで、だから、死んだ人がお星様になるっていうのはあながち間違いじゃないと思うんすよね。あれ、なんか、語っちゃいましたね。つまり、俺が今操作している携帯も、いずれは星になるんですね。あー、多分、そっすね、なると思います。矢野の左人差し指は唾液でふやけはじめていた。身元がわれているということは、きっと今頃、警察にも連絡がいっているだろう。早くも捜索が始まっているかもしれない。恋人の家に連絡が行っているかもしれない。いや、連絡では飽き足らず、実際に警察官が恋人の家に押し入っているのかもしれない。別れの瀬戸際でも迷惑をかけてばかりだ。昨日は恋人と恋人の浮気相手にひどい仕打ちをされたが、付き合い始めてから今までの五年間、ずいぶん恋人にひどい仕打ちをしてきた。喧嘩ではすぐに手をあげてしまうし、お金は勝手におろすし、酔って暴れて食器を割った数なんて数え切れない。もう恋人の部屋には戻れないし、戻りたくないし、警察から逃げ続けなければならない以上、職を見つけることすらままならない。財布も携帯も身分を証明するものもなにもない。あるのはポケットでくしゃくしゃになっている煙草とライターだけ。矢野はポケットから煙草を取り出し、火をつけた。吸って、吐いて、一呼吸置いてから甘咬みをやめてしまったことに気づいたが、遥か彼方まで昇っていった携帯は一向に落ちてこなかった。灰が落ちそうになっていることに気づいた宇城は矢野に素早く携帯灰皿を差し出す。ああ、悪いね。いいんすよ。心中、お察しするっす。煙草はまだ充分吸えるだけの長さで燃え続けていたが、矢野はそれを無理やり携帯灰皿に押し込んで、宇城に返した。宇城は渡された携帯灰皿を、また矢野の手のひらに戻す。いいっすよいいっすよ、その携帯灰皿はあげますんで。その灰皿見るたびに、なんとなくでいいんで、僕のこと、思い出してください。って、気持ち悪いっすね自分。よく言われるんすよ、お前は説明対象に情が移りやす過ぎる、って。ま、僕、携帯灰皿何個も持ってるんで、大丈夫っすから。矢野は口元を緩めて、ありがと、とぼそぼそ声でお礼を言った。携帯は落ちてこなかった。おそらく大気圏を越えて、地球の周回軌道にでも乗ったのだろう。それとも周回軌道すら超えて、いずれどこかの惑星にたどり着くであろう隕石やスペースデブリの一つとして宇宙空間を漂っているのだろうか。矢野にも、もちろん宇城にも川城にも、それは分からなかった。ぽつりぽつりと降り出してきた小雨に、傘をさすか否か、三人はそのことばかり考えていた。傘なんてないのに。
同時刻、矢野の恋人は住処である二階建ての軽量鉄骨アパートの部屋で、浮気相手と二人で、穏やかな寝息をたてていた。いや、眠っていたのは浮気相手だけで、恋人は一時間ほど前に目が覚めてから、どうにも寝付けずに、浮気相手の寝息を自分の前髪に当てたり、脇腹をくすぐったりして、再び眠気がやってくるのを待っていた。マヌケそうに口をぼんやりとあけて眠る浮気相手を見つめる恋人の表情は柔らかく、その表情からは、矢野と接するときの冷たさや無感情さをうかがい知ることは困難である。今夜はなにか好きなものを食べに行こう。朝目覚めた時にベッドの中で今日の夜のことを考えるのは恋人の幼少期からの癖みたいなもので、それが、二四時間のうちでもっとも愛おしい時間なのだと、以前、恋人は矢野に言ったことがあった。眠気は一向にやってこない。二度寝を諦めて、恋人は台所で細かく刻んだベーコンとタマネギを炒めた。昨日、矢野が部屋を出ていってから作り置いてあったなめこのみそ汁を温めている間、恋人は矢野が買い置きしていた煙草一カートンをまるまるゴミ���に捨てて、灰で底が見えなくなった灰皿を捨てて、毛先が開いた矢野の歯ブラシを捨てて、LOFTで買ったペアのマグカップを捨てて、ここぞというときに食べようと思っていた矢野のエクレアを食べて袋を捨てて、捨てて捨てて捨てて、ゴミ袋を二重固結びできつく結んで、玄関の隅に置いた。ベッドでは、浮気相手がフワフワと宙に浮いていた。ああ、今月もきたか。いっつも症状重いみたいだし、大丈夫かな。みそ汁からは湯気がもうもうとたちこめている。恋人はコンロの火を消してお椀にみそ汁を入れ、ベーコンとタマネギの炒めものを小皿によそい、ラップにくるんで冷凍保存してあったご飯をレンジで解凍して、一人きりの朝ごはんを堪能した。今日の夜はなにを食べに行こう。脂っこいものが食べたいかも。チキン南蛮とかいいかもしれない。かつ吉のトンカツもいいかもしれない。いやいやそれより、脂とかいいから、少し足を伸ばして、川沿いに最近オープンした小洒落たヴィーガンチレストランに二人で行くのもいいかもしれない。考えながら箸を動かしているうちにお椀も小皿もお茶碗もキレイに空になり、満足そうに唇の周りを舌で舐めてから、恋人は洗い物を始めた。
どこかで誰かと誰かが話している声がする。向かいの公園から犬の鳴き声が聞こえる。通り沿いにある中学校から野球部の掛け声と吹奏楽部がホルンやユーフォニウムやサックスやフルートを吹く音が聞こえる。携帯がさっきからずっと震え続けているけど私はそれを無視し続けている。冷蔵庫の稼働音がわからないくらい微かに部屋を揺らしている。数分前についたばかりの脂を洗い流す水の音が規則的に聞こえてくる。油は泡と共に水で洗い流され、食器棚に置かれていたときより綺麗になったお椀と小皿とお茶碗の、キュイキュイっという、清潔さの証明のような音が部屋に響く。私はベッドで浮かぶ木下が起きたらまずなにを話そうか、考えている。ヴィーガンレストランなんて、かっこつけ過ぎだ。今日の夜は、近所のスーパーで豆乳でも買って、豆乳鍋にしようか。私も木下も湯葉が大好きなのだ。脂っこいものが食べたいのかも、という気持ちは不思議と消えていた。台所のまな板置き場のそばに、矢野の携帯灰皿が置いてあるのを見つけて、私はそれをからにしたばかりのゴミ箱にシュートした。
木下の寝息は聞こえてこない。
洗い物を終えた私は濡れた手を拭くのも億劫になって、ポタポタと指から水が滴っている状態のまま、ベッドにもう一度もぐった。手についた水は布団やまくらに吸収されて私の手は潤いを失っていく。叩いても突っついても木下は起きる気配すら見せない。私はすぐにまた起き上がり、ベッドの上で体育座りをして、自分の膝に顔をうずめながら、隣で、空中で、ゆりかごに揺られているように漂いながら眠っている木下の、静かな寝息に耳を傾ける。
五年後、矢野の携帯は地球の周回軌道を外れ、凄まじいスピードで大気圏に突入し、地表にたどり着く前に跡形もなく燃え尽きてしまう。
0 notes
Text
国境がまだ閉じられていなかった2月16日、横浜の老舗のホールでソウルのドラッグ・クィーン、MOREさんとプロデューサーのコ・ジュヨンさんと一緒に作ったパフォーマンスのレビュー。正確に意図を汲んでいただいていて、うれしい。本当に本当に光栄だ。
국경이 아직 닫히지 않은 2월 16일 서울의 드래그 퀸, MORE와 프로듀서 고주영 씨와 같이 만든 공연의 리뷰.정확하게 의도를 길어 주시고 있고 기뻐서 눈물이 나온다.
http://choomin.sfac.or.kr/zoom/zoom_view.asp?type=OUT&zom_idx=514&div=03
去る2月9日から16日まで、日本の横浜に宿泊しながらTPAM2020(Performing Arts Meeting in Yokohama 2020)参加公演の数々を見ることが出来るという「あまり見慣れない」機会が与えられた。
公演観覧することを目的に海外に出て行ったことも、1日に一回以上の公演を毎日見ることも私には全て初めてのことだった。
不慣れなことだったので、普段よりも公演を見ることにより集中しようと努力した。しかし、目を閉じれば韓国で片付けられない数々の仕事と帰ってからやらねばならない仕事たちが頭の中でぐるぐる回り、インターネットで触れる韓国の事件とニュースは韓国にいる時よりもずっと大きく迫って来た。
その渦中に解決することができない悩みに向き合っている友人の日常が心配でもあった。そして、当時横浜にはコロナ19ウィルス感染の拡散防止を理由に3700余名の乗客と乗務員が隔離された旅客船が停泊させられていた。
とても近い所で起きていたけれど、一番非現実的に感じたことでもあった。私が歩いて通った道は穏やかで小綺麗で、公演は決められた場所で定時に始まり終わるというそんな繰り返しだった。私はぎこちない顔をして街を歩き公演を見て酒を飲んで睡眠を取る日々を送っていた。
振り返って見ると横浜での私の様子は見慣れないものではなかった。知らない建物の窓に照らされる私の顔をしばしばまるで違う人の顔のように錯覚するくらいだった。体も心もしっかり足を地面に踏みしめたいけど、実際にいざ自分がいたい場所がどこなのか、よくわからない気分。行かなければいけないのは何処なのか、そしてどこに行きたいのか。それらを確信出来ずにキョロキョロしながらを心許なく歩いているいつもの私の姿を、知らない場所でもっとはっきりと感じていた。
そんな状態で私はTPAM2020の最後の公演となる「ねじロール」と「オギヨディオラ」に出会ったのだ。それぞれ三十分あまりの二つのパフォーマンスが立て続けに上演されるこのプログラムは、TPAMディレクション(プログラムディレクター達によって紹介または企画されたプログラムが束ねられているセクション)の最後の公演でもあった。公演場所であるクリフサイドは外観から、廃業して随分経ったナイトクラブの気配をぷんぷん匂わせる場所だった。
ドアを開けると、年月を経た木と布の匂いが嗅覚を刺激した。過去の栄光が古いテーブルクロスとカーペットの染みの痕跡に記憶された場所だった。ロビーや階段にびっしり埋まった人々がいなくなってしまい今はもう空っぽになった空間が、ようやくブルースの音楽とともに「今にもマジで」ショーが始まりそうな空間だった。
客席の入場が始まると、観客達はロビーから相次いで階段を上り始めた。階段を上り切って到着した二階にはクリフサイドの一階のダンスホールとは区分された空間が設けられていた。ライブ公演を見ること、もしくは舞台に立つことには関心のない人々がそれぞれ集まってわいわいがやがやと酒を飲んでダンスを踊る物語を紡ぐ言葉を交わしそうな空間だった。
その空間で「オギヨディオラ」のパフォーマーであるモア・ジミンとアキラ・ザ・ハスラーが、ドラァグの扮装をし準備をしていた。二人のパフォーマーは、散らかった荷物衣装や小道具の間でまるでそこが自分の家であるかのように気楽な様子でメイクをしていて、観客たちはその姿を見ながら客席に通じる狭い通路に向かって相次いで歩いて行った。
私はその二人の姿を交互に眺めながら既に公演が始まっていたことにはっと気づいた。そして狭い通路の前に着くと、その通路の横のコンセントに携帯電話の充電器を差し込んだまま、しゃがみこんで座って、通話をする一人の男性の後ろ姿が見えた。「公演開始まであまり時間がないのにあの人はどんなに急な用があってああしているんだろ」
過去のどこかで、私も何回かは経験した、「緊迫した」行動も時空間を割るひとつのパフォーマンスのようだった。私は二階の狭い通路(下に一階のダンスホールが見下ろせるテラス)を通過して舞台(ダンスホール)が正面に見える一階のディナーテーブルに席を取った。
<ねじロール>
観客たちが席を取る時に生じる騒音と騒がしさは公演の開始時間が過ぎても続いた。おそらく舞台に設置されたスピーカーとサウンドシステムを通じて出て来る吃るような話し方の男性の声に神経が持っていかれるが、ぜんぜん無視もできるくらいの喧騒の中で観客たちのおしゃべりも継続された。
入場のさいに受け取った公演パンフレットをいじくり回す音と、バーに行ってドリンクチケットをビールやワインに変えてくる人たちが動く音で空間が散漫に満たされた。 <ねじロール>の梅田哲也(Umeda Tetsuya)と同僚のパフォーマーが舞台に登場して、サウンドシステムの前に座る動作も特別な気配もなく進行された。
二台の大型スピーカーの間に位置したサウンドシステムは、楽器を変形したものなのか変形して楽器になったものなのか分からない物体と、マイク、オーディオ・コンソール、そしてそれらを連結するラインで構成されていた。 パフォーマーが登場したから、もう何かが起きるのかなと思った瞬間、システムの合間に置かれている黒い旧式の電話機のベルが鳴った。 このベルは私がこの公演で明確に認知した二つの音のなかの一つだった。
ベルは鳴るが、受話器を取る人はいなかった。 梅田哲也が受話器を取り上げて、電話機の横に置いた。 まるで受信者はこの空間だとでもいうように。 そのため、さっきも流れたどもるような話し方の男性の声がもう少しよく聞こえるようだったが、依然として内容は分からなかった。 そして何を見なければならないのか聞かなければならないのか不明なこの状況を経験しているのは(おそらく)私だけではないようだった。
舞台の両側に見える、観客の視線もその焦点を失ったまま、それぞれ漂っていた。と、その時さっき通路にしゃがみ込むように座って電話をしていた男性が舞台の領域に歩いて入り、マイクの前に立ち泰然と通話を続けた。 やっと私はその人がもう一人のパフォーマーである捩子ぴじん(Neji Pijin)であり、これまで流れていた吃るような声の主人公であったいう事実を知ることになった。
若干の追加パフォーマンス(スプレームースを舞台の床にまいたり椅子の高さの構造物の上に立つアクション)がなかったわけではないが、彼は公演が終わるまで終始一貫してマイクを握り、言葉を「叫ぶ」行為を繰り返した。 そして他のパフォーマーたちによって作られた(あらかじめ計作ってあった)様々なサウンドが、彼の叫びをめぐって増幅された。 パフォーマンスが終わる頃に喉が裂けるほど繰り返して何かを訴えていた彼の声から「笛の音」がした。彼の声が裏返ったのだ。
その笛の音が私がこの公演ではっきりとはっきり認知した二番目の音だった。 最初に認知したベルの音が発信の始まりだったら、笛の音は重ねて滑ってしまう発信、あるいは、受信のずれを暗示するようだった。 彼の叫びのなかで、私がわかった内容は遂に一つもなかったが、後で彼が叫んだ言葉のなかに"Can you hear me?(私の話が聞こえるの?)"という言葉があったという事実を知ったとき、笑みがこぼれた。彼の数多くの叫びの中で、私は笛の音だけを受信したんだね。<ねじロール>は、対象と目的がなめらかに収束しない叫びと音をすべての空間にまき散らしながら終わった。 明確な受信させることは当初から発信する目的ではなかったというかのように。
<オギヨディオラ>
空間のあちこちにばら撒かれたエネルギーは、<オギヨディオラ>のパフォーマンスで一つずつ拾い集められた。 <ねじロール>の音が止むと、客席に入場した時から配備されていた、小道具や大道具たちが再び目に入って来た。サウンドシステムが置かれていた舞台の反対側、古いグランドピアノが置かれている空間(社交ダンスの交流の場だったクリフサイドで、ライブバンドの定位置だった空間)の両側に、約1.5×1.5メートルの段ボールに描かれた二つの山(mountain)がそびえ立っていた。 そしてグランドピアノの周辺には華やかな衣装やウイッグ、鏡などの小道具とバレーレッスンのためのバーが設置されていた。 私は前日に<オギヨディオラ>公演のために用意された練習室で、部分的にではあるけれど覗き見たパフォーマンスが、今日この空間でどのように実行されるのか期待しながら舞台まわりをもう一度ゆっくり見渡した。 その時、モアが舞台にフッと入ってきた。 ライブでドラァグクイーンの舞台を見るのははじめてだったので、彼が登場しただけで訳もなく胸騒ぎがし始めた。 彼は舞台にのぼり、精巧に描かれたラインと色が調和を成した自分の顔を鏡に映してみたり、靴や衣装といった小道具を手にするように動き、また舞台の外に出て行った。
ほどなく<オズの魔法使い>の挿入曲<Over the rainbow>の前奏が流れた。 そして白いショートカットのウイッグと白い木綿材質のオフショルダー・ドレスを着た、濃く厚いアイラインと彼のものよりさらに厚く赤い唇のアキラ・ザ・ハスラーが、はにかみながら舞台に登場してきた。 彼が歌の始まるポイントに合わせて唇を開いた瞬間、散漫だった空間の空気が彼の周辺に集まるのが感じられた。 彼のリップシンク、手ぶり、歩み、いたずらにスカートの下に隠しておいた、歌のラストに天井にバラバラに飛ばした半透明の黄色い風船まで私にはとても「リアル(real)」であるように感じられて、軽く狼狽するほどだった。
私は誇張されたジェスチャーや内容の公演をまっすぐに見ない方なのだが、アキラ・ザ・ハスラーのショーはもちろん、それに続くモア・ジミンの<It's oh so quiet-Bjork>の舞台も、動作や表情を一つも逃さないようにじっと見つめていた。モアの真っ赤な唇と同じくらい濃いチーク、白い巻き毛のショートカットのウイッグ、小さな白いドット柄が散りばめられた赤い水着。そして赤い靴、そのすべての扮装が本来彼の身体の一部であるかのように自然に感じられ、それでいて美しかった。 私が感じたリアルさと美しさは、舞台の特性を活用し、着飾った二人の華やかさに由来するものでもあったが、何より二人が表現しようとした感情、情緒そして歌の歌詞以上のドラマが、各自に与えられた3分弱の時間の中で、極めて具体的に作られたためだった。 私はにわかに二人の世界をそっとのぞいたような気さえした。
ⓒRody Shimazaki, TPAM - Performing Arts Meeting in Yokohama, 2020
各自のショーが終わるやいなや、すぐに次のパフォーマンスが続いた。 余韻を感じる間はなかった。二人はもうすでに一緒にやるショーを準備するかのごとく「突然」モアによるバレエのレッスンが始まった。バーを使って開始された「講習」は舞台の中央へとつながって行った。 プロのバレエダンサーであり、振付師のモアジミンが見せてくれる動作を真似するアキラ・ザ・ハスラーの姿はまるで大人の真似をしはしゃぐ子どものように見えたりもした。 二人の遊びは、チャイコフスキー(Peter I.Chaikovskii)の<白鳥の湖>の音楽に合わせて最高潮を迎えて、二羽の白鳥のように舞台裏に退場してショーはそのまま終わるかのように見えた。
しかし、すぐに二人は白とピンク色の白鳥の形をした浮き輪に乗って(正確に表現すると両足で引っ張って)オールを漕ぎながら舞台に出て来ると、客席の笑い声とともに異なる次元の遊びが再開された。その後に続いた二つの韓国語の歌に合わせた二人のパフォーマンスは、二人が一緒にドラァグショーを作る、その過程のように見えた。 観客の視線と流れる歌に合わせて二人はショーの場面を一つずつ作って行っていた。
"…天空の星も 大地の花も ひそやかに わが道を 生きてゆくように ふと気がつけば 河が微笑みかけている 私たちも 微笑みがこぼれる…"-<オギヨディオラ>
李尚恩の歌<オギヨディオラ>の穏かなメロディーに会場全体の雰囲気が敬虔になったのか、それともそっと互いに心を配るかのように、それぞれの船に乗って水路の上で出会った二人の動きは、終始一貫して軽くて愉快だった。 "オギヨディオラ"のフレーズがリフレインされると、二人はそれぞれの船から降りて一緒に通ってきた水の流れに白い布を広げた。 そして二人はまるで白い布の上に新しい水路を描くような感覚で空色の絵の具を塗り、撒いた。 そして空色の絵の具が塗られた川(水路)は2階のテラスの高さまで引き上げられて、舞台の正面であり、両側にそびえる山の間に(流れるように)置かれた。 そして間髪を入れずに二人のパフォーマーはすぐに始まる次のショーのために衣装をチェンジし、順次舞台の両脇に置かれた山(山の絵が貼りつけられた構造物)の上に上がった。 二人がそれぞれの峰に上がると、二つめの歌である楊姫銀(ヤン・ヒウン)の<私たちが登る峰は>のナレーションが始まった。
ⓒHideto Maezawa, TPAM - Performing Arts Meeting in Yokohama, 2020
モア・ジミンは明瞭な表情と口の動き、そして手振りで、自分が登った峰にまつわる話を聞かせ始めた。 その場に韓国語の歌詞を聞き分けることができる観客は多くても5人程度だったため、ほとんどの観客は英語/日本語の歌詞が書かれたパンフレットや、モアのジェスチャーを交互に眺めながら彼の話に耳を傾けた。それは孤独に自身の峰を登っている友達に手渡す励ましだった。 そんなふうに各自の峰で始まった慰めだが、「友達よ」のフレーズのリフレインが始まる頃には二人のパフォーマーは各自の山から降ろし、出会わせ、今度は共に他の山(2階のテラス)を登らせた。
歌がクライマックスに近づくと、二人のパフォーマーは、観客らが公演前に通って来ていた2階テラスの両側の通路を通り、先ほど二人が共に描いた水路の上に並んで立ってプラカードを広げた。 プラカードには、まさにそのときに流れていた歌詞の内容の文句が書かれていた。 "だから友よ 私たちが登る峰は すぐ今のここかもしれないよ"
公演は「まさに今ここ」に集まった人々の耳目を二人のパフォーマーが到着した地点に集中させ、終わった。
驚いたことに<オギヨディオラ>のすべてのパフォーマンスを見るのにかかった時間はわずか30分だった。 二人のパフォーマーは停泊するまで延々とオールを漕いで行かなければならない船頭のようにせっせと、そして休む間もなくパフォーマンスを遂行した。 プログラムディレクターと2人のパフォーマーが公演に込めようとしたメッセージと「こうすれば面白そうだ」と想像した要素が決められた時間内に舞台の上で一つずつクリアになった。 パフォーマンスを一つずつクリアする度にモアが息を切らしながら吐き出した息の音、まるで合いの手や囃し言葉のようだったハイトーンの「はっ!」という音が、私がいま見ているものが何なのかをその度に想起させてくれた。 <ねじロール>での「笛の音」がそうであったように。
ⓒHideto Maezawa, TPAM - Performing Arts Meeting in Yokohama, 2020
公演場で、不慣れな場所で、そして日常でも私はしばしば「まさに今ここ」という感覚を失ってしまう。それは私を取り巻く状況と関係が、たとえどこにいても私に影響を与えているためでもあるが、しきりに今ここにないもの、あるいは私が望んでいないことを欲する真似をするからでもある。 私は今ここに無いものについて話す時、不安な気持ちになり、今踏みしめている地面も,そばにいる人もリアルに感じられなくなったりする。 そんな私に見知らぬ場所での最後の公演であった<ねじロール>と<オギヨディオラ>は、足元に感じられた古いカーペットの感触、そして私が見ているものの表面と裏面を感じられる時空間をその瞬間、開いてくれた。
公演が終わって宿所に戻って、次の日に韓国に発つ準備をしながら李尚恩の"オギヨディオラ"をもう一度聴いてみた。 すると他のどの歌詞より"さあさあ 船を漕いで"というフレーズが耳にすっと入ってきた。 私が漕いできた、そしてこれから漕がなければならないオールのことについて、そして一緒にオールを漕いでいる人たちについて考えた。 私はまた見知らぬ気持ちに酔って、どこか分からないところをうろうろするだろうことは明らかだが、少なくともその瞬間だけはせっせとオールを漕いで向かうべきところがどこなのか、少し鮮やかにはっきりしたのだ。
テキスト: シン・ジェ (演出家・韓国)
0 notes
Link
突拍子も無い話ですが表題の通り、とあるご縁がきっかけで、きょろ(@kyoro353)とはとね(@hatone)夫婦を含む友人メンバー4人で、カリフォルニアのナパにほど近い「SUNSET CELLARS」(サンセット・セラーズ)というワイナリーを購入させて頂くことになりました。「ワイナリーって個人で買えるの!?」という感じだと思うんですが(僕も1年半前はそう思ってました)最終的に色々と頑張りまして、今年の10月から晴れてワイナリーの共同オーナーを務めさせて頂いています。まさか自分がワイナリーオーナーになる人生なんて思っても見なかった!! とは言え、私達は別にテレビゲームで大成功を収めた天才事業家でも、金銭的に成功した起業家やお金持ちでもありません。技術とモノづくり、そしてカリフォルニア・ワインが大好きな普通のエンジニアの夫婦です。 この記事では、ワインが大好きな普通のエンジニア夫婦が、いかにしてワイナリー経営を始めるに至ったのかをご紹介したいと思います。あわせて、自分たちがこれから取り組みたい事や、解決したいワインの問題なんかも所信表明としてまとめさせて頂ければ幸いです。 私達のワイナリーについて VIDEO まずはウチのワイナリー「SUNSET CELLARS」(サンセット・セラーズ)の紹介を軽くさせて頂きます。葡萄畑やワイナリーの雰囲気なんかは↑の映像をご覧ください(僕がドローンで撮影しました)カリフォルニア・ワインとして有名な産地であるNapa Valleyの東隣、Suisun Valleyという場所にある、年間生産数500ケースに満たない超小規模なマイクロ・ファミリー・ワイナリーです。 創業者はダグさんとカツコさんという老夫婦で、ダグさんは早稲田大学への留学生、カツコさんも日本生まれと、日本との縁があるお二人です。ワイナリーを創業したのは今から22年前の1997年。もともと半導体が盛んな時代のシリコンバレーで技術コンサルタントとして働きながら自宅のガレージでワインの自家醸造(カリフォルニアでは年間1人225Lまで自家醸造ができます)を趣味として続けた結果、50歳を越えてから「ちょっと余生はワイン造って生きるわ!」と一念発起。有名なワイナリーに弟子入りし、ついには自宅のガレージでワイナリーを起業してしまったという面白い創業秘話を持っています。シリコンバレーの人ってガレージで起業するの大好きですね。 創業者のタグさんとカツコさん お二人が造るワインの特徴は何と言っても爆発的な果実味。フルーツの味と香りを最大限に引き出すために、信じられないくらいの長期熟成を行います。今年の新リリースのヴィンテージ(収穫年)はなんと2010年。9年って!!…って感じです。それでいて「ワインなんて気軽に開けて楽しむものだ!」という強い信念から、採算度外視で一切売値に転嫁しない原価みたいな超お値打ち価格です。生産数も少ないので米国内でもお店では販売しておらず、テイスティングルームに直接来ないと買えません。絵に書いたような「田舎の頑固オヤジが地元の人のために造る最高のワイン」と言った感じです。ただ、その味や評価は対外的にも高く、カリフォルニア全州が対象の「California State Fair」とかではBarbera単品種のナパ地区最優秀賞(The Best)を何年も取り続けてる結構凄いワイナリーです。とにかく儲ける気がまったくない! 美味いワインを残したい!からの事業譲渡 今は元気にワインを造ってるお二人も御年70歳越え。10年後もワインを造れるかわからない…という状況から、ワイナリーの閉鎖を考えているという話が出てきました。日本でもよくある「酒造の後継者問題」です。私達のメンバーのFahとMioはもともとワイナリーの近所の住人で、長年通ってワイン造りも手伝っていたSUNSETのワインの長年のファンでした。閉鎖話に大変ショックを受け、悩んだ末に「自分たちでワイナリーを引き継がせてもらえないか?」と申し出たのが始まりです。 Mioは日本出身で普段は食品ビジネス経営の専門家、Fahはタイ出身でソムリエ上級資格を持つ生命科学者で、普段はDNA解析エンジニアとして働いています。能力は十分すぎる二人ですが、フルタイムの仕事を持つ彼らだけのリソースで、本業の片手間に労働集約的なワイン造りとワイナリー運営を行うことは物理的にも時間的にも大変難しいものがありました。同じような境遇の誰かの助けが必要です。そこで相談を受けたのが無類のワイン好きの私達エンジニア夫婦でした。 「ワイナリーを買うので一緒にやらないか?どうか助けてほしい!」 「えっ!?ワイナリーって個人で買えるの?!」 ここで冒頭の驚きと返事です。一方で相談を受けた瞬間に「なんかこの人生は本当にネタに尽きないなぁwww」という興奮と笑いがこみ上げました。 実はワインは私達夫婦が何より愛するものの1つです。カリフォルニアという場所に来たあと、夫婦で一緒に惚れ込み、隔週でワイナリーに通うような生活をしています。カリフォルニアのワインが大好きな理由は「ものづくり精神」を随所に感じる事で、それはシリコンバレーの空気と同じようなオープンでイノベーションを歓迎する空気と同じものです。具体的にはどのワイナリーもオープンで醸造家同士の情報交換や勉強会も活発、移民の国ならではの様々な出身国のバックグランドを持つワイン造りのスタイルが入り混じり、等級のような誰かから一方的に押し付ける価値観で縛られておらず、良いワインを作���ば弱小の小さなワイナリーでもちゃんと評価されるという、大変フェアで自由な場所です。そんなカリフォルニアのナパだけでも大小600以上のワイナリーがあり、1つ1つに個性と特徴があります。その上収穫年によって毎年味が変わるのですから、人生すべての時間とお金を使っても飲みきれません。好きな土地での出会う一期一会がワインの何よりの楽しみです。 SUNSETのワインを初めて飲んだ時の、頭がクラクラするような爆発的な果実味を今でも覚えています。古き良きナパの味、近年の薄味のワインの流行に完全に逆行する、いままで出会ったことのない種類の美味しさです。こんな素敵なワインの歴史が今閉じようとしている。私達もMioやFahと同じ様に、この味を残したいと強く思うようになりました。 想定外を「つくる側」でいたい しかしワインを飲むのと造るのでは全くの別物です。でも根っからのエンジニアである私達は、一度興味を持って大好きになってしまうと、いつも最後は作る側に回り���くなる欲求を抑えられなません。DIYや建築に興味が湧いた結果、家を実際に建てたくなって米国オフィスを物理的に自分で施工してしまったときもそんな感じでした。僕としてはワインに関係した仕事がいつかしたいなぁという夢もありました。 私達の夫婦には1つの価値判断基準があります。それは「悩んだら一番想定外の面白い選択肢を選ぶ」ということです。 ベイエリアの物価の高さに震えながら過ごす小市民な生活の私達ですが、ITやWebの業界に入って10年余、シリコンバレーに渡って年月ともなれば、知り合いにの中にも事業で成功したり、IPOやバイアウトで金銭的な成功を収めた人もポツポツと出始めます。そのような知人の中には頑張って得たお金を使って、今度は自分の好きなこと、たとえばレストランやバー、飲食店を買ったり始めたり、自分の夢を託したスタートアップに投資する人も出始めます。 でも自分の知る限り、ワイナリーを始めた人なんて身の回りに一人もいません。それこそ自分の中の「ワイナリーオーナー」のイメージは、裕福なダブルのスーツを着た年配の男性が、優雅にグラスを傾けてるような感じです。我が家みたいな普通のエンジニア夫婦がワイナリーのオーナーになるなんて、予想外すぎて自分でも面白いです。 もちろん私達は余ってるお金があるわけでもありません。だけど背伸びをして高級車を買うくらいなら、そのお金を出し合ってワイナリーをやってみたい!という人が4人も揃っているのです。これはもうチャレンジしない手は無いでしょう! 私達は決意を決め、4名共同でのワイナリーの事業譲渡を申し出てました。 エンジニア、ワイン造りを学ぶ 1年半前、将来の事業譲渡を目指してダグさんとカツコさんに弟子入りし、私達はワイナリーの運営メンバーになりました。「ワイン作りを学ぶにはどうしたらいいですか?」という最初の質問は「まずはガレージで失敗して来な!」と相手にされませんでした。さすが職人肌の頑固オヤジ。「実際に手を動かす気もない観光気分の若者」みたいな感じでしょう。 しかし私達も負けてはいられません。近くのファーマーズマーケットで葡萄を大量に買い込み、Youtubeで「ワイン 作り方 簡単」などと検索して自家醸造を開始。次第に文献を読んで発酵醸造学の専門知識を深く身につけて行きました。学生時代に愛読していた「もやしもん」を読んだときの興奮を思い出します。ワインそのものの知識も、体系的な物を持っていたわけではないので改めて勉強です。ワインのイロハを一番教えてくれたのは、何をおいても亜樹直先生の「神の雫」です。ワインのすべては神の雫から教わったレベルで素晴らしい教科書です。そして、アメリカでもワイン業界の人は結構みんな読んでるので、国を越えて話が通じるのです! フォークリフトも運転するよ! 葡萄の除梗(茎を取る)と破砕作業 手を紫に染めながらワインを自宅で作り、収穫や発酵、プレスダウンを手伝い、いろんなイベントや飲食店にワインを売って歩く姿を見て、老夫婦も次第に僕たちを信用してくれるようになりました。日本にワインを売りに行く時「いってらっしゃい」と初めて声をかけてもらったのは参加から半年後だったでしょうか。いまでもその時の嬉しさを覚えています。 亜樹直先生(樹林先生兄弟)にウチのワインをお渡しできたのは夢のような体験でした ワインの世界にはHackできる場所が沢山! ワイナリー経営や国際物流、日本での商流を知れば知るほどに、エンジニアの自分たちから見ると無駄で、レトロで、改善&最適化できそうな部分や未開の可能性未が多く目につくようになりました。たとえばマーケティングや生産、醸造工程、在庫の管理なども、小さなワイナリーの多くはデジタル化が全く出来ておらず、人力で無駄な部分が本当に沢山あります。 また国際物流、特に日本でのカリフォルニアワインの商流に関しては、改善や挑戦できる余地が沢山あることに気づきました。 私達のチームは各人がそれぞれが日本生まれであったり、日本にゆかりを持つ者たちです。愛を込めて造った美味しいワインを、どうにか日本の人達にも楽しんでほしいという想いから、ワインインポーターさんに相談へ伺いました。しかし生産数があまりに少ないため、そもそも取り扱ってもらえなかったり、少数のため値段を高くせざるを得ず、ワイナリーの卸価格の7倍という小売価格を設定する必要に迫られるなど、なかなか上手くは行きませんでした。 一般的に日本のお店で手に入るワインの値段はワイナリーの蔵出し価格の約4-8倍、飲食店での提供価格を考えると、レストランでで特別な日に1万円以上を出して開けたワインから得られるワイナリーの収益が1000円にも満たないことは一般的です。 もちろんコストがかさむのは複合的な原因があり、誰かが利益を独占しているわけでは決してありません。国際輸送や通関、保管、営業、在庫リスクなど、古典的なワイン物流に関しては多くのキャッシュアウトが発生します。一方でワイン造りは一朝一夕どころか、どんなに短くても2年以上の歳月が必要。ワイナリーの売上から膨大な原価や人件費を除けば、そこに殆どの利益は残りません。結果として日本で飲むことができるワインは、希少で高品質な代わりに大変高価なワインか、数を生産して利益を生み出せる大規模なワイナリーのものしか手に入れることが難しい状況にあります。 同時に、少量生産ワインが高価になる原因の大部分は「ワインが売れるどうかかわからない」という事に起因するということも分かってきました。原価・輸送・通関費を安くするためには一度に大量の買付が必要ですが、その内訳は一部の凄く売れる商品と、多くの売れない商品に別れます。売れるにしても在庫を捌くまでに時間が必要で、その間の冷蔵保管費用はコストとして全てのワインの価格に乗ってきます。 では売れた分だけ輸出入すればいいのかと言えばそうでもありません。今度は輸送規模やコスト、リードタイムの問題が発生します。空輸の場合の最小単位は1本ですが、SFO-TYOの輸送に1本7000円くらいかかります。1000円のワインが8000円です。数をまとめても劇的には安くなりません。一方リーファ(定温輸送)コンテナ船の輸送の最小単位は一般に1パレット(50ケース=600本)で、リードタイムは30日。これではオンデマンドな発注には全く対応できません。 カリフォルニアで一緒にワイン造り 日本の皆さん、特に自分の周りにいる友人のような、沢山のお金は無いけどロマンはあるぞ!という人に、リーズナブルに最高のカリフォルニアワインを届けたい。なによりダグが守ってきた「気軽に最高のワインを楽しむ」という無理難題をどう実現するかを色々と考えました。 その答えとして思いついたのは「小売や卸売を一切行わず、定期配送で私達のワインを買ってくれる個人やレストランに直販し、コンテナ輸送を使ってカリフォルニアから直接届ける」という方法です。事前に売れる数がわかれば、輸送や在庫リスク、保管コストを最小化でき、リードタイムを無視して必要な数だけを日本に送ればOK。販売数がパレットに満たない場合でも、各回スケジュールを上手く組み立てれば対応可能。必要最低限の間接経費だけで、日本の人にワインを届けることができます。要するに国際輸送を伴うサブスクリプション・モデルですが、販売予測の精度が如実に何倍もコストに反映されるワインに関しては相当有効な手段です。仲介業者を最低限しか挟まないのでコストも最小化できます。 ただこのモデルの一番の問題は、日本にもワインショップはじめ多くのワイン購入サブスクリプションがある中で、あえて私達のワイナリーだけのワインを楽しく、定期的に飲んで頂けるモチベーションやインセンティブの設計をどう行うか?という事です。そこで考えたのは、会員の方にカリフォルニアに実際に存在する私達の葡萄畑にある葡萄の木をプレゼントして「ツタ主」としてオーナーになって頂くというものです。それもよくある月の土地や、飲食店会員権のクラウドファウンディングのような単なるバーチャルオーナーシップではありません。葡萄のツタにはシリアル番号を付与し、テクノロジーを使って自分のツタの写真や葡萄畑の気温・湿度・土中水分量などの育成状況、収穫後は糖度の変化や発酵醸造過程、熟成過程などの様々な情報を会員向けWebやアプリを通してリアルタイムにお届けします。そして会員の皆様と一緒にワイン造りを行い、収穫から数年後には自分の葡萄から造られたワインが手元に届いて実際に飲めるというもので、名前を「Vine Owner’s Club」と名付けました。いわば「飲む株主」となって頂き、私達と一緒にワインを造りを楽しく飲みましょう!という試みです。 会員ページから自分のツタの状況を確認できます 私達のワインのような希少なクラフトワインは、一般商流で流通することは基本的に無く、ワイン専門店か取扱のあるレストランなどで出会うことが殆どかと思います。 ワインを楽しむために必要な値段を比べた場合、ワイン自体のコスト構造も含め、家で楽しめる「ツタ主」モデルのコストパフォーマンスはなかなかのです。 旧来の10,000円のワインより、ツタ主モデルの3600円の方がワインは、ワイナリーに2倍のお金を届けることが可能です。 ローカルのワイナリー体験を技術で届ける 実はこの根源のアイデアは、ワイナリーのある地域では古来からアナログに行われている仕組みです。日本でワインクラブやワインサブスクリプションと言えば「世界の色々なワインを飲みましょう!」というものが多いかと思います。いわばワインに出会う機会を買っているわけです。一方ナパなどのワイナリー地域では大小数多のワイナリーが、それぞれにワインクラブをやっています。そしてワインクラブに入れば無料試飲やパーティーへの招待はもちろん、購入するワインも大幅割引が適用され、樽からリリース前のワインを飲ませてくれるなど、本当に家族のような待遇を受けます。かくいう私も多数のワイナリーのクラブの会員です。なんでこんなにVIP待遇を受けるのか今まで不思議で仕方なかったのですが、生産者側に立つとクラブ会員の存在ほど心強いものはありません。 ワインは通常、リリースに2年以上の歳月が必要で、毎年新酒を出せる日本酒以上に生産に時間が必要です。そして2年後なんて、いったいどれだけのワインが売れるかなんてぶっちゃけ全くわからないわけです。どんなに大ヒットしても2年前に生産していなければ売れない(これがワインが値上がりする理由です)、一方で造りすぎると余剰在庫に悩まされお金が溶ける。クリック1つでいくらでもインスタンスが増えるクラウドの世界を体験した身からすると、信じられないほど対局にいるビジネスです。 だからこそ、買ってくれる人の顔を思い浮かべながら酒造りができるというのは、本当にありがたいことです。小さなワイナリーでは「あなたは〜なワインが好きだから、今年はあなたが好きそうなワインを仕込んだよ」なんて話をされることもあります。ワイナリーも消費者の顔を思い浮かべながらワインを造り、安く届ける。消費者はワインメーカーの顔を思い浮かべながら、安くて美味しいワインを飲む。これってお互いに結構幸せな体験なのです。 そんなローカルなワインクラブの体験を、テクノロジーを使って遠い日本の皆様にもお届けしたいと思っています。普通のファミリーワイナリーだとこんなシステムなんて開発する余裕ありません。私達がエンジニアだからこそ出来る取り組みです。人件費もかからないしね!すでに会員になってくれた皆さんの反応は上々で、おかげさまで楽しんで頂けているみたいで嬉しいです。バーチャルですけどツタは物理的なものなので「ご近所さん」なんて概念が生まれてるのも面白いですね。在りし日のジオシティーズのような面白さを感じます(笑) カリフォルニアのワイン農場のツタ主になった #0007 ✌️ ワインできるの楽しみ☺️ pic.twitter.com/vw1W7YROAN — Ryusuke Chiba (@metalunk) November 24, 2019 https://t.co/Pv2WHLJ5zT さんのブドウ…!!これから毎季節ここのワインが飲めるの本当に楽しみで楽しみで。 21番なのはアレかな、運命かな🤔 pic.twitter.com/Tsjr5IIPtE — Lain Matsuoka/松岡 玲音 (@lain_m21) November 24, 2019 「ツタ主」の募集は第1期100ツタ限定もしご興味のある方はぜひお気軽にご参加ください! Vine Owner’s Club 葡萄の「ツタ主」の皆様にカリフォルニアからワインをお届け https://sunsetcellars.jp/club 気軽にお声がけください! 以上少し長くなってしまいましたが、私達がワイナリー購入に至った経緯と想い、これから取り組みたい事についてまとめさせて頂きました。これから学ぶべき事や乗り越えなきゃいけない課題も山盛りですが、新米ワイナリーオーナーとして美味しく楽しいワイン造りに取り込んで行こうと思います。皆様、今後とも宜しくお願い致します! そしてエンジニアやスタートアップ界隈の皆さんには、ぜひ何かワインやお酒を絡めた面白いアイデアがあれば、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。言わば「みなさんの身内で好き勝手面白いことがっできるワイナリーが登場しました!」という事です。お声がけ頂ければDroidKaigiやiOSDCみたいな開発者会議でもスタートアップカンファレンスでも、どこでもワイン持って行きますのでお呼びください。企業やイベント向けのオリジナルワインも、小ロットでも全力でお作りします。 また、私も妻も引き続きメインの仕事はエンジニアとして大好きなものづくりに取り組んで行くつもりです。最近は平日シリコンバレーで頭を動かし、週末ワイナリーで体を動かしてワインを造る、みたいな生活をしています。人生楽しんでなんぼです。ものづくり、さけづくりに楽しんで取り組んでいこうと思います。日本にもプロジェクトや仕事の都合で良く訪れていますので、引き続きよろしくおねがいします! Cheers! 「SUNSET CELLARS」(サンセット・セラーズ) 共同代表 井上恭輔・大島孝子
0 notes
Text
Page 109 : 口止め
キリにやってきてから一週間程が経ち、少しずつザナトアの元での生活に慣れ始めていた。
元々ウォルタでは弟と二人で暮らしていた。最低限の家事は手慣れており、家事全般を受け持つようになっていた。
一日目のような重労働は十分に出来ないけれど、決まった時間にポケモン達に餌を与えに向かう。目立つのは鳥ポケモンだけれど、他にもポケモン達が住んでいると知るのに時間はかからなかった。
晴れている日には広大な草原でひなたぼっこをしている陸上ポケモン達。身体を地面に埋めて頭の葉を茂らせ光合成に勤しんでいるナゾノクサはいつの間にかここで群を成している。ここらを住処とはしないが恐らくトレーナーに捨てられて保護したのだという外来種の黒いラッタは他のどんなポケモンよりも美味しそうに餌を頬張る。美味しい牛乳を分けてくれるから重宝しているというミルタンクはキリの農場の主人が亡くなって譲り受けたポケモンだという。
小屋からそう遠くないところには小さな林が茂り、その中に大きな池がある。水ポケモン達の楽園だ。山から引いて��た水が貯められ、トサキントやケイコウオといった魚型のポケモンが優雅に泳ぎ、コアルヒーはこの場所と卵屋を行き来している。同じようにこの周囲を自由に飛び回っているヒノヤコマは、この池に住むハスボーと仲が良いらしくしばしば一緒にいる場面を見かけた。清らかな水で洗練された池の端で暢気に見守るように、いつもヤドンはしっぽを水面からぶらさげている。
餌をばらまけばあっという間に食いついてくる様子をじっくりと眺めながら、アランは額の汗を拭う。秋の日差しは柔らかく吹き抜ける風は軽いが、身体は膨らんだ熱を帯びていた。ポケットに入れっぱなしにしている懐中時計を確認すれば、そろそろ次の予定時刻が迫ろうとしている。
薄い木陰に背中から寝転ぶと、草の匂いがこゆくなり、池から漂う独特の鬱蒼とした香りと混ざる。林の中にぽっかりと作られた人工の池は、そこだけ空洞となったように直接陽が入る。少し離れれば木陰があり、水の放つ涼感が疲弊した身体に沁みるのだ。
木の根本から声がする。アランは起き上がり、座らせていたアメモースを引き寄せ、代わりに自分の背を幹に預けた。
アメモースを出来るだけボールから出してやれと進言したのはザナトアだ。ボールの中はポケモンにとって安寧の空間だが、出来るだけアメモースとアランの接触を増やすことが主な目的だった。
彼等の間にある溝は浅くはない。しかし彼女が今アメモースのトレーナーである限り、溝を抱えていても関わりを断つわけにはいかないのだった。
「今日、エクトルさんにも会おうと思うんだ」
ぽつりと告げると、アメモースは静かに頷く。
もう一時間程したら、湖のほとりまで向かう公共バスが近辺を通る。最大の目的はアメモースを一度病院に連れて行くことだが、ザナトアからはいくらか買い物を頼まれている。そのついでにエクトルと再会する心積もりでいた。
昨晩ザナトアが自室に戻った際に電話をかけた。依然休暇は続いているらしく、都合はつけられるとのことだった。
ザナトアの家で世話になっている旨を話すと、少しだけ驚いた様子だったけれど、それきりだった。そしてザナトアには彼との約束を伝えていない。何事もなく夕食に間に合うようには帰るつもりでいるのだろう。
ざわめく木漏れ日の下で暫し身体を休めてから、アランはゆっくりと立ち上がる。軽くなった餌袋を左手に下げ、右手でアメモースを抱えると、元来た道を戻った。
荷物を倉庫に戻した帰路の途中でザナトアに出会う。傍にはエーフィとフカマル。紺色の頭上にヒノヤコマが乗っていた。数日一緒に過ごすうちに、ヒノヤコマが数あるポケモン達のリーダーで、フカマルは気に入られている弟分という関係性が見えつつあった。
「行くのかい」
「はい」
やや驚いたようなザナトアは、もうそんな時間か、と息を吐く。
「わかった。買ってきてほしいものはメモに書いたよ。机の上に置いてある。よろしく頼んだよ」
「はい。行ってきます」
曇った表情を浮かべるエーフィを宥めるようにアランは頭を優しく撫でる。
「仕事、頑張ってね」
そう言われれば、エーフィは見送る他無いのだった。
ザナトア達に別れを告げ、アランはリビングへと戻り、そのまま奥の廊下へ向かい途中の右の部屋へ入る。脱衣所となったそこでそそくさと着替える。全身が汗ばんでいたが流すほどの時間は無い。旅のために見繕った服をさっさと着込み、パーカーは暑いので腰に巻き上げる。小さな尻尾を作るように首下で結っていた髪を慣れた手つきで直したところで、薄い傷がついた鏡を見据える。緊張した表情を浮かべた少女が、昏い眼で見つめ返していた。
再度リビングへ帰ってくると、先ほどは横たわっていたブラッキーがゆっくりと起き上がる。
「大丈夫?」
声をかけると、黒獣は深く頷いた。
アメモースだけを連れて行くのは心許ない。だが、最近のブラッキーはやはり不調だった。ついでに診てもらえばいいというザナトアの助言を受けて医者の目を通してもらうつもりでいた。
ダイニングテーブルの上に置かれたリストに目を通し、二つのモンスターボールと共に鞄に仕舞う。
裏口から出て、表の方へと家の周囲を沿っていき長い階段を降り始める。一昨日降った長い雨で、気温がまた一段階下がって秋が深まったようだった。丘を彩る草原もゆっくりと褪せていき、正面の小麦畑からは香ばしい匂いが風に乗ってやってくる。
一番下まで降りて、トンネルの方へと歩いてすぐに古びたバス停にぶつかった。錆だらけで、時刻表も目をこらさなければ読めない程日に焼けてしまっていた。
脇にぴったりとついて離れないブラッキーは、今一目だけ窺えばなんの不足も無く凛と立っていた。昼夜問わず横たわる姿とは裏腹に。
予定到着時刻より数分遅れて、二十分ほど待ってやってきたバスに乗り込み、運ばれていく間車窓からの景色を覇気のない表情で眺めている。途中で乗り込む者も降りる者もおらず、車内はアランと二匹のみのまま町中へと進んでいった。
山道を下っていくと、やがて目が覚めるように視界が広がる。木々を抜けて、穏やかな湖が広がった。波は立っておらず、美しい青色をしていた。水は天候によって表情を変える。静寂に満ちている時もあれば、猛々しく荒れる時もあり、澄んだ色をしている時もあれば、黒く淀んでいる時もある。
駅前のバス停で降りると、そそくさと歩き出す。キリの町は比較的ポケモンとの交流が深いが、ブラッキーに向けられる好奇の視線からは避けられない。抱いているアメモースを庇うように前のめりで歩く。
町の飾り付けは先週訪れた時よりも活気づいている。豊作を祈る秋の祭。水神が指定するという晴天の吉日の催しを、当然のようにキリの民は心待ちにしている。
ザナトアに紹介された診療所はこじんまりとしていたが清潔で、感じの良さがあった。院長でもある獣医はザナトアの知り合いといって納得する、老齢を感じさせる外見だったが、屈託のない笑顔が印象的な人物だった。フラネで診察中に暴れた経験があるので身構えたが、忘れもしないフラネでの早朝の一件以来良くも悪くも取り乱さなくなったアメモースは終始大人しくしていた。傷口は着実に修復へ向かっていて、糸をとってもいいだろうと話された。大袈裟な包帯も外され、ガーゼをテープで固定するだけの簡素なものへと変わった。アメモースにとっても負担は減るだろう。
抜糸はさほど時間がかからないそうであり、その間にブラッキーを預け精密検査を受けさせた。モンスターボールに入れて専用の機械に読み込ませて十数分処理させるらしい。画像検査から生理学的検査まで一括で行える、ポケモンの素質としてモンスターボールに入れることで仮想的に電子化されるからこそできる芸当だが、アランにはその不思議はよく理解できない様子だった。彼女にとって大事なのは、ブラッキーに明らかな変化があるか否かだった。
結論から言えば、身体にはなんの異常も認められなかった。
本当ですか、と僅かに身を乗り出すアランは決して安堵していないようだった。収穫と言うべきかは迷うだろう。気味悪さに似たざらつきが残っているようだった。見えぬ場所で罅が入っているような違和感を拭いきれない。
ただ、抜糸を済ませたアメモースが少し浮かれた顔つきで、いつも垂れ下がっていた触覚がふわりふわりと動いている姿には、思わずアランも情愛を込めるように肌を撫でた。
診療所を後にして、入り口付近で待っていたスーツ姿の男にすぐに気が付いた。待合室で二匹の処置を待っている間に連絡を入れていたのだった。
「案外、元気そうですね」
出会って早々、エクトルはそう告げた。
「そうですか?」
「以前お会いした際は見るに耐えない雰囲気でしたので」
はは、と苦笑する声がアランから出たが、表情は変わらない。
時刻は十五時を回ったところだ。夕食までには帰る必要があり、ザナトアから頼まれた買い物を済ませなければならない。とはいえ、頼まれているのは主に生鮮食品だ。そう時間はかからない。その旨を伝えると、
「では、お疲れのようですしお茶でも飲みましょうか」
無愛想な顔は変わらないが、落ち着き払った提案を素直にアランは受け取り、並んで歩き出した。
「アメモース、順調のようですね」
「なんとか」
腕の中で微睡んでいる様子は、エクトルと再会した頃の衰弱した状態と比較すれば目覚ましいほどに回復している。
そう、とアランは顔を上げる。
「ザナトアさんを紹介してくださって、ありがとうございました。今日はそのお礼を言いたかったんです」
「そう言えるということは、生活の方も順調でしょうか」
「……大変なことは多いですけど、少し慣れてきました」
「何よりです。失礼ながら、追い返されるだろうと」
アランは首を横に振る。
「皆のおかげなんです。私は全然。怒られるし、うまくいかないことばかりですし」
「追い出されなければ、十分うまくいっている方でしょう」
冷静な口ぶりには、お世辞ではなく実感を込めていた。
駅前近くの喧噪からやや離れて、住宅街に近付くほどに人の気配が少なくなる。低めに建てられた屋根でポッポが鳴いて、よく響く。無意識のうちに、アランの手は強張っていた。
「……キリに来たのは、アメモースをもう一度飛ばせるためだったんですけど」しんと目を伏せた先では、とうのアメモースがいる。「それについてはもう少し考えてみます」
「それがいいですよ」
すんなりと同意した。
アランはすいと顔を上げる。
「随分焦っていらっしゃるようだったので、安心致しました。一度立ち止まるのは、アメモースのためにも、ご自分のためにもなるのでは」
まじまじと見上げながら、少し間をとって、辛うじてアランは小さく頷いた。
会話が途切れ、不揃いな足音で町を進む。
真夏ほどではないとはいえ、日差しにあたれば薄らと汗が滲む。逆に日陰に入れば肌寒さが勝る。気温も徐々に低くなってきた。アランは腰に巻いたパーカーを羽織る。
「アイスクリームという時期でも無くなりましたね」
歩きながらぼんやりとした心地でエクトルは零す。
「あの時、エクトルさんいましたっけ」
エクトルの意図を掬い取ったのか、何気なく彼女は尋ねる。懐かしい思い出を語り出そうとするように。
「いえ。けどお嬢様から事の顛末は話していただいたので。あの時は失礼しました。驚かれたでしょう」
「そうですね……そうだった気もします」
「他に知る場所も殆どありませんから、仕方がありませんが。お嬢様はキリを知らない」
「でも、生まれも育ちもキリですよね」
「お嬢様からクヴルール家の掟については話を聞いていますよね」
高圧的に刺され、アランは口を噤む。
「ここで生まれここで死ぬと定められていても、この町のことを何も知らずに生きていく。皮肉なものです」
まあ、と自嘲気味にエクトルの口許は僅かに上がる。
「私も殆ど知りませんがね。――綺麗な場所ではありませんが、どうぞ」
不意に立ち止まり、道の途中の喫茶店の扉が開けられる。彼自身は身体つきが逞しいが、恭しい礼と滑らかな所作は一つ一つが画になるような美しさがあった。促されたアランは思わず空いた口を締めて、二匹のポケモンをボールに戻すと、緊張した動きで通されるままに中へと入る。
古めかしい店内は奥に細長い造りとなっており、長いカウンターが伸びている。今は客が他にいないようだった。カウンターを挟んだ向こうの棚には、ずらりと並ぶコーヒーの他にワインやカクテルの瓶が立ち並び、夜にはバーに変わるのだろう。まだ酒と縁遠いアランには関係の無い話だが。シックな内装に見とれるように、入り口で立ち止まったまま動かなかった。
「ここで立ち止まられても邪魔になります。奥へお進みください」
後ろから静かに囁かれ、慌てて奥へと進む。カウンターに立つのは外見の妙齢な男で、知人なのか、エクトルを見やるとまず目を丸くして、続けざまに気軽な雰囲気で手を挙げた。
カウンター席の更に奥は小さなスペースがあり、二人掛けのテーブルが二つだけある。いずれも空席だったので適当に右側を陣取ると、店員はにやつきながら、店員は水の入ったグラスを二人に差し出す。
「これはまた随分久しぶりだな。元気か? 油を売っていていい身分になったのか?」
「身分は変わりませんが、少々暇を頂きましたので顔を出すついでにと。クレアライト様、コーヒーはお飲みになれますか」
「えっと」
唐突に尋ねられ惑っていると、店員が笑う。
「なあんだ、子供かと思ったら違うのか、つまらんな。うちのコーヒーは美味いぞお」
「彼の仰ることはお気になさらず。好きなものをお選びください」
けらけらと肩で笑う店員を真顔で無視し、エクトルはメニューを差し出した。整然と並ぶドリンクの数々に目を泳がせながら、ミルクティーを選んだ。茶葉の種類は見当がつかないので、適当にお勧めを貰う。
店員が姿をカウンターの奥に消すと、エクトルは小さく息を吐いた。
「彼に代わって失礼をお詫び申し上げます。軽率な人間ではありますが口は堅いのでその点はご安心ください」
「はあ……」
アランが恐縮していると、エクトルは彼にしては幾分弛緩した雰囲気で水を含んだ。
どことなく緊張しながら室内を軽く見回す。カウンターをはじめ物は深い茶色で統制され、落ち着いたクリーム色をした漆喰の壁と似合っている。お世辞にも広いとは言えない限られたスペースだが、それがかえって隠れ家のような秘密裏な雰囲気を連想させた。細部まで店主の拘りが感じ取られる。ささやかなジャズ音楽が流れ、がらんとしていてもどこか寂しくはない空気感だった。
「お洒落な雰囲気ですね」
「創業者のセンスが良いんです」
ぽつりぽつりと言葉を交わすばかりで、会話はうまく繋がらない。沈黙の時間を多く過ごしているうちに、コーヒーと紅茶が一つずつ運ばれてきた。
「少女趣味だったっけ」
テーブルに置いて、一言。硬直したエクトルが、深い溜息を返す。
「ご冗談でもやめていただけませんか。彼女に失礼です。知り合い以上の何者でもありません」
「知り合いねえ」
アランは探るような目をしている彼の胸元を軽く見やる。白いシャツに黒いベストを羽織り、馴染んでいるような黒い名札には白文字の走り書きでアシザワと記されている。アーレイスでは聞き慣れない音感だった。
「しかし、あのお嬢さんはどうした。お付きがこんな所にいて女子と茶をしばいて噂になっても文句は言えねえな。しかもこの年の差はまずい」
「馬鹿馬鹿しいことを。そんな発想になるのは貴方くらいなものですよ。お嬢様は先日無事ご成人されて、私の役目は終わりました」
「ご成人」彼は目を丸くする。「いつのまにそんな時期になっていたっけか。あんなに可愛らしかった子がねえ、早いもんだ。美人に育ったんだろうなあ」
あっけらかんとした物言いにエクトルは返す言葉も無いように首を振る。
「貴方はそればかりですね。頭の固い他の関係者だったら――」
「あ、なんでも色目で見てると思うなよ。これでも話す相手は選んでるんだ。大体こんな噂話くらいどこでも立つだろうが。それより」
アシザワは前のめりになる。秘密の話でもしようとするような雰囲気だが、彼等の他に人はおらず、少々滑稽だった。
「役目は終わった。つまり、あのお嬢さんのお目付役が終わったってことか?」
「それが何か」
へえ、とアシザワは感心したような表情を浮かべる。
「良かったじゃないか。念願が叶って」
アランは顔を上げる。
正面に座るエクトルは静かにコーヒーに口をつけ、熱の籠もった溜息を吐き出す。
「もういいでしょう」
話を無理矢理切り上げるように一言零す。アシザワは明らかに変容した空気を察したようにアランを一瞥し、頷いた。
「悪い悪い。じゃ、ごゆっくりお過ごしください」
とってつけたように軽く会釈をすると、アシザワは足早にその場を去って行った。
小さな喧噪が終わり、後には気まずい空気が吹きだまりとなって残った。
「口が堅い、を訂正すべきですね」
溜息まじりにエクトルは言い、黒々と香りを浮かばせるコーヒーを飲む。アランもつられるように紅茶を飲んで、その後思い出したようにミルクを入れた。透明な飴色に細い白が混ざり、瞬く間に濁っていく。
「聞きたいことがあれば、答えられる範囲で応じますが」
「……いくつか」
「どうぞ」
「念願が叶ったというのは」
エクトルは思わず口許を緩ませる。誤魔化すような笑い方だった。
「本当に口が軽いことです」
「離れたかったんですか。クラリスから」
「そう簡単な話ではありません。温度差を感じる程度には、彼とも長く会っていません。確かに昔は嫌になったこともありましたが」
エクトルは目を伏せる。
「湖上でお嬢様を呼んでいた、貴方とは真逆ですね」
栗色の瞳が大きくなる。
その名を何度叫んだだろう。寂しさと怒りの混ざった感情を爆発させ、銀の鳥に跨がって、朝の日差しに照らされた湖上で喉が嗄れても呼び続けた。朝に読んだ手紙と、あっけない別れを受け入れられずに無我夢中で走り出した夏の終わりの出来事は、彼女の記憶にもまだ新しいはずである。
「クラリスに聞こえてい��んですか」
「いいえ」
間伐入れぬ即答に、アランは押し黙る。
「クヴルールの中心には誰も届かない。あの日お嬢様の耳に入っていたのは風の音のみ。私も後ほど知りました。湖上にエアームドと少女の姿があったと」
一呼吸置く間に流れる沈黙は、重い。
「やはり貴方だったんですね」
確信ではなかったが、彼にとっては確信に等しかったのだろう。エクトルですら今まで真相を知らなかったのなら、クラリスが知るはずもない。
アランは俯き、力無く肯いた。
「……神域に繋がる湖畔を守るように風の壁を施しています。ポケモンの技ですがね。誰も近付けぬように。キリの民は誰もが当たり前に知っていることです」
「そう……初めから届くはずがなかったんですね」
言葉に沈痛なものを感じたエクトルは黙り込み、重々しく肯いた。
「まさか、たったあの二日で、そこまでお嬢様に入れ込む方ができるとは考えもしませんでした。申し訳ございません」
「どうして謝るんですか」
決して怒りではない、純粋な疑問をぶつけるようにアランは問いかける。
「私が中途半端にお嬢様を許してしまったがために、無闇に無関係の貴方を危険に曝しました」
「違います。あれは私が勝手にやったことです」
「そう。貴方がご自分でそうされました。想像ができなかった。キリを知らず偶然立ち寄っただけ、それも訳のありそうな旅人なら何を告げたところで深く干渉はしてこないだろうと」
アランは眉根をきつく寄せる。
「何を言いたいんですか」
突き放すように言うと、エクトルは薄く笑った。
「見誤っておりました」
店内の音楽が切れ、本当の沈黙が僅かの間に訪れる。
「噺人は成人すれば完全に外界との関係を断ち、全てを家と水神様に捧げ、自由は許されない。クヴルール家の掟は他言無用。とりわけ未来予知、消耗品のように使い捨てられ続けてきたネイティオの件は禁忌。公となれば、いくらクヴルールとはいえ只では済まないでしょう。愛鳥を掲げる町ですから、尚更。それを他者に教えるなど、いくらキリの民でなくとも許されない。今回の件を他のクヴルールの者が知れば、お嬢様は代用のきかない立場ですので考慮はされるでしょうが、私の首は飛ぶでしょう」
アランは息を詰める。
「つまり、クラリスの元を離れたというのは」
「ああ」エクトルは軽く首を振る。「それとは関係ありません。このことを知る者はクヴルールで私とお嬢様の他にはおりません。先ほども言ったでしょう、役目を終えただけです。もし知られていれば、私は今ここにいませんよ」
平然と言ってのけるが、アランは一瞬言葉を失う。
「そんな恐ろしい口封じをする家なんですか」
直接的には言葉にしていないが、首が飛ぶとは形容でなく、言葉そのものの意味を示すのだというニュアンスを含めているのだとアランは嗅ぎ取っているようだった。
エクトルは短い沈黙を置く。
「程度によりますが。強い力を持てば、手は汚れるものです」
諦観を滲ませ悟ったように呟き、続ける。
「アシザワ……先程の店員に、貴方がお嬢様のご友人だということを伏せたのも念のためです。彼はキリの事情には驚くほど無関心ですがね」
「そんなことも?」
「本来、彼女は外界に関係性を持ってはいけない存在ですから」
また長い沈黙が流れていく。
場を持て余すようにエクトルがコーヒーを飲むのを冷めた表情でアランは見守る。
「口止めをしたいということですか」
エクトルの動きが止まる。
「それならそうと、はっきり言えばいいじゃないですか」
「口止め……そうですね。そう言っても良い」
アランの唇が引き締まった。
「貴方も、暫くキリに留まるつもりなら言葉は選んだ方が良いでしょう。これは警告です」
「だったら」
声が僅かに震えていた。
「初めからクラリスに何も言わせなければ良かったでしょう。外に関係を持つなと言っておきながら、学校に通わせたり……中途半端に許したということは、そもそもクラリスを止めることも出来たということですよね。何を今更」
「言ったでしょう、軽率だったと」
刺すように言い放つ。
「判断を誤ったのは私の責任です。だから出来る限りの協力は致します」
「ザナトアさんを紹介した��も、だからなんですね」
虚を衝かれたエクトルだったが、表情には出さない。ザナトアの存在は、彼にとって苦みのある、できるだけ触れたくない部分ではあった。
「クラリスの約束だけではなく。気が進まなかったけれど協力してくださった理由は、それですか。手は貸すから、余計なことは言うなと」
「一つは、確かに」
アランの唇が僅かに歪む。
「……これも、この時間も、口止めのつもりだと」
言いながら、手元のカップの縁をなぞる。
どこまでも深い黒い視線はあくまで凪いでいた。軽く首を振る。
「あまり警戒を強くされないでください。貴方は私を利用し、何事も無かったように過ごせばいいのです。ただ、一つ覚えておいて頂きたいのは」
強まった語気にアランは身を正す。
「私は貴方の身と、お嬢様の身を案じているのです」
辻褄合わせのように吐き出される言葉達に、アランは表情を変えなかった。
暫しの沈黙の間に、細い指先が持ち手を強く握り、また和らぐ。長い息と共に一口、渦巻いているだろう感情諸共流し込んで、温もった甘みのある吐息が小さく零れた。
「わかりました」
凜と言い放つ。
その直後のことだ。アランの顔が不意に、微笑んだ。
首都で訣別として笑いかけてから、意識していても強ばったまま動かなかった頬が解れた。凍っていた表情が溶けて、ふわりとした綿のように優しい微笑みが咲く。
「わかりました」
繰り返す。言い聞かせるように、或いは強調するように、しかし今度は随分と和らいだ口調だった。同じ言葉でありながら、全く色の異なる声を使っている。
「エクトルさんは、甘い人なんですね」
エクトルの肌が強張る。
「あの子、言ってました。本当は優しい人なんだって。その意味をちゃんと理解した気がします。……クラリスの望みをできるだけ叶えようとしてたんじゃないですか」
「クレアライト様、それは違う」
「エクトルさん」
咄嗟にエクトルは息を呑んだ。
ただ名前を呼ばれただけなのに、今までで最も意志の強い声だとエクトルは思った。有無を言わさず黙り込ませるだけの強い声。
「丁度良かったんです。私、クレアライトは捨ててるんです」
「……はい?」
僅かに動揺するエクトルとは対照的に、にこやかな顔を彼女は崩さない。
「クラリスと友達になり秘密を知ったラーナー・クレアライトはキリに居ない。そんな人間はここにいない――丸く収まりますよね」
「何を……」
「アラン。アラン・オルコット。今はそう名乗っています」静かに頷く。「これで踏ん切りがつきました」
驚きを隠さぬ顔で、エクトルは妙にさっぱりと笑うアランを凝視した。
< index >
0 notes
Text
彼について Ⅰ
彼について Ⅰ
「じゃ、ほかの子はみんなその子の代替品というわけ」
そう問いながら、代替品などという言葉がじぶんの口から滑り出したことに驚いたし、言ったそばから撤回したくなった。こんな卑俗的な単語をかれに当てはめるのではいけない。かれについて語るとき、ただしいと思って口にしたことさえ一瞬のあいだに嘘になるような気がした。このひとの前では、どうも自分が何か言うたび恥だけを上書きし続けているような、そんな呪いがたしかにあると思う。
〈テラス・メルツェル〉のロビーの一部はカフェとして職員のために開放されている。1階から最上階にあたる17階までの中央はひろびろとした空間で穿たれて吹き抜けになっており、円蓋からはたとえ外がどのような天候であれ、いつでも晴天に相当する光が差し込んだ。白を基調とした建造物の内部はつねに木洩れ日に似た陰翳で彩られ、一瞬一瞬のうちに光によって姿を変える。外部からの光を蓄え、常に一定の光量に変換するようプログラムされた円蓋展開型プラネタと広大な吹き抜けがあってなお行き届いた空調設備、つるりとした壁や床、柱の類。それらは清潔であるほど無機質で、どこまでも生のありかを否定しようとするようにみえた。最初のメルツェル・ドールが設計した神殿。じっさいにそうなのかどうかはわからないが、そのように謳われるこのテラス・メルツェルはたしかに、人間のためにつくられ生を持たないかわりいつまでも美しくある、メルツェル社の人形そのものなのだ。ここには自社の商品のホロ広告も展示もない。ドールは街中に溢れ、誰もがそこに刻まれた社名を知っているし、この建造物じたいが巨大な広告塔だった。
「お待たせいたしました。ほかにご注文は?」
「ありがとう。他にはないよ。そうだ、14時になったら報せてくれないかな」
「ええ。報せはどのように?」
「そうだなーーこの番号へ繋いでくれると助かる」
「かしこまりました。ごゆっくりどうぞ」
少女が注文しておいたヴァン・ショー……熱いワインを二人ぶん運んでくると、かれと少しの言葉を交わしてまた戻って行く。そのやりとりのなめらかさにだっていちいち感嘆する。まるで映画みたいだ。
「なるほど。そうやって通信先を渡すわけだ。勉強になるなあ」
「きみはなにか俺をかんちがいしてるんじゃないかな。それにご存知のとおりー」
「冗談だってば。知ってる」
ワインを口に含む。あたたかなアルコールは喉をくべるようで、たっぷりとしたシナモンのつよい香りがほどよい陶酔をうながした。
たとえばそう、彼女だって人形だ。
なめらかな動作、表情、擬似呼吸と機能的にはまったく意味のないまばたき……もはや一見して人間と区別がつかないけれど、首のうしろ、やわらかな人工皮膚にはネクタイピンほどの銀のプレートが嵌め込まれ、メルツェル社の名が刻まれている。高品質な、人間に近しい無生物。
メルツェル社は工業用のドールをつくらない。あるひとつの仕事のためにだけ特化してつくられたドールは存在しない。ひとりのドールが助手として事務作業をこなすこともあれば、いまのように給仕をすることもあるし、もちろん働かないこと、ただ所有者のそばにひかえるだけの場合もある。ドールたちは所有者となる人間に好みのパーツをえらばれ、設定されたパラメータ・カードを挿入された人工物ではあるけれど、同時にかれらの在り方はメルツェル社によって厳格に規定されていた。すなわち、メルツェル・ドールは娯楽と鑑賞のための美しい人形でなければならず、それ以外の平均された機械のような工業的な在り方、奴隷のような使用はみとめられない。それが何代にもわたって受け継がれてきたメルツェル社のコンセプトだった。ドールを購入して得るものは好きにする権利ではなく、ひとのように愛するための権利だ。
とはいえ、不正な利用が後を絶たないのだってまた事実だった。パラメータ・カードを規定された以上に従順なものに書き換えるパッチはいつになっても駆逐されない。本来存在しないはずの機能を付け加えるガジェットも。からだを弄られたドールの回収と保護も、この施設で行われている。
そういえば、かれはそのセクションで仕事をしているときいたことがある。お互いのセクションの詳細な業務内容を明かすことは職員どうしであっても禁じられているために、具体的にはなにを担当しているのか、それはわからないけれど。
そこでようやくロビーを行き交う人々の視線がかれへと注がれているのに気がついた。ある者は悟られないように、ある者は露骨に、そのすがたを注視する。セクションがちがえば会う機会のない人間は山といるし、ふだん別館にいるかれがこのカフェへ来ることも思えば珍しい。とはいえ、それだけでないのは一目瞭然だった。こぼれかかる銀の髪、美しいがいっそ禍々しい赤いひとみ、その輪郭を象るどの曲線にも意味のあると思わせる、生きた彫刻のような男。会話をしたならその隙のなさにまた驚くんだろう。
「そうそう、さっきのこたえだけどーー」
一度途切れてしまった会話をどうつなごうかと思案していたまさにそのとき、かれはひとくちワインに口をつけると、かちゃりとていねいにカップをおいてそう言った。ほとんど合図だったし、こういう所作こそ隙がないとおもわせる所以だということを、あらためて知らされる。まるでこちらの意図をなにもかも知っているかのような、意識的でさえないエスコート。
それからかれは大げさに、すっと肩をすくめてみせた。
「……まさか。代替品だなんておこがましいよ」
からりとした、重量を感じない調子のこたえ。抜群にひとを安心させる、負の成分を含まない声、そう、その効力は絶対だ。だからこそずるいのだ。ひとこと発するだけで空気を変えてしまう。かれの印象をよりよいものへ近づけ、悪意や嫉みは少なくともかれの声のあるあいだ消え失せる。人を信用させることにおいて一流だ。たぶん、それは生まれついて。フォーマルでありながら野性的であり、そこのところのバランスが完ぺきだった。最上級の信頼ーー同時にだれもそれ以上へは踏み込めない。踏み込もうとした人間がけしていないではなかったが、来る者を拒まずあまやかされただけだといつか気づいて引き返す。それをかれは追うこともなく、ただわらっているだけだ。傷はつかない。誰もかれを傷つけられない。
かれはいつも、自分に好意を向けてくる彼女たち(あるいは彼ら)に対して紳士的かつ柔和な姿勢を崩さないけれど、思うにそれはなんの熱も含んではいなかった。ほどよいタイミングで、ほどよい距離で、ほどよい位置でそこにいて、どんな瞬間に顔を覗いても牙がみえない。だれから見ても隙のない立ち居振る舞い。俳優のような整った在り方。理想の男(アニムス)。なのにどこかで、いちばん人の情や愛と呼ばれるものから程遠い場所に立っている気がしていた。それがどんなに美しいもので、高尚であるかを��れかが語ったとしても、かれがそこにあらわれるだけで途端に陳腐な虚構に成り下がってしまうみたいだった。
かれ自身は気づいていないかもしれないが、自分に好意を向けてくる人間へのかれの想いというのは、道端で戯れてくる猫に対するときのそれと同じなのかもしれない。拒絶はせず、甘えられればのどを撫でてやる。餌をねだれば与えてやる。けれどその行為には目に見えたそれ以上の意味は宿らない。一瞬の交錯がすぎると、結び目がほどけるみたいにそれぞれの日常へかえってゆく。なまえはつけない。そういう種類のいきものだ、「道端の猫」というのは。先週どこかで見かけたのと、一年前別の場所で見かけたのと、遠い昔旅行先で見かけたのとは、「道端の猫」という同じいきものにすぎない。おれたちがある猫を撫でるとき、いつかどこかで撫でてやった別の猫に後ろめたさを感じたりなんかしないように、かれにとっては自分に好意を寄せるどの人間も等しく平均的に映るのかもしれない。それはほとんど、無価値とイクォールだ。やさしいといえばそのように写りもするだろう。だけど決定的ななにかが欠落している。
何人がそれをうめたがり、やがてあきらめたのだろう?
だからといってだれかをもののように手ひどく扱うことなんかないのだって分かっている。やわらかな無関心は博愛と言い換える���とだってできるのだから。
代替品などという言葉をえらんだことにたいして、まちがえた、と思ったのはそういうことだ。
「さっきのは言い方がよくなかったよ。忘れてくれ」
「いや、せっかくだからきちんと答えておこう。その子の代わりとして他の誰かを扱ったことはない。
……というわけで、誤解は解いてもらえた?」
「……誤解、というか、ほんとうに言葉のあやなんだ。怒った?」
意味のない質問だった。ご機嫌とりみたいだ。かれがひとに対して怒ったりしないし、機嫌を損ねたりしないということを知っているのに。おれはじぶんが、せいいっぱいかれに親しくあろうとしている、ということをいやでも意識する。ときどきあるだろう。こちらだけが友人だと思っているのではないかと感じて、よけい砕けたじぶんを演じようとすることが。もうずっとそういうふうに振る舞っている。
「まさか、怒ったりしないよ。でもさ、きみやっぱり俺を何かかんちがいしてるんじゃない?」
くだけた笑いがかれから発せられる。どんな猜疑もあっけなくなかったものにするかろやかさが、そこにはある。かんちがい。そうかもしれないーーそれならどんなによいだろう。
「そうだな、それなら……あんたは優しすぎるだとかぬるすぎるとか彼女たちの言ったようなほんとにそういう理由で毎回振られてるだけで、それ以上もそれ以下もないのかも。そんなはずない、と思っているおれの穿った見方というやつで、おれが思うほどあんたは複雑ではないのかも」
「毎回振られる、ね。事実だけど本人のまえでそれをいうかなぁ、謝ってるんだか貶してるんだか。複雑、ねえ」
それってぜったいいい意味ではないでしょ、とかれは言う。屈託がなく、そのわりに上品で静かな表情、たぶん性別のない天使はこういうふうに笑うんだろうなと思った。
「悪かったってば。だけど、なんていうか意外で。そう、ほんとう失礼なんだけど、俺はあんたを人形なのかとすら思ってたくらいだしーーいや、知ってるんだけど、人間なんだってことは」
「嫌味?それは矛盾しているよ」
「そうなんだけど。でも、だいじにはするけど、好き、には見えなかったから。まるでそういう感情を知らないみたいだったから。それはたぶんほとんどの人間にとって屈辱だよ」
なんというか善人すぎてあんたは胡散臭いんだーー
すっかりかれに絆されかけ(そういうことにおいて天才だ)、軽口を叩こうと頬がほころびかけて、ぎくりとした。
……ぎくりとした?
それがじぶんのどんな感情なのか理解するまで、たっぷり数秒はかかったように思う。
紅い目は笑っている。
屈託がなく、そのわりに上品で静かな表情、天使。そう、博愛の目。けして拒絶ではない無関心の目。
ーーほんとうに?
混乱した。突然じぶんが、触れてはいけないものをさわろうとしてしまっているような、なにか大切なものをまちがえたような、そんなような気持ちになっていることに。この混乱の意味がわからなかった。
かれはなんと言っていた?
代替品だなんて、おこがましいよ。
背中にひやりと流れるものを感じた。
かれのせりふがべたりと耳にはりつき、こだました。声が蔓となって鼓膜へ飲食し、このからだをすっかり染め替えてしまうような感じ。
慄えがおこった。
代替品だなんて、おこがましいよ。
かれの発した声の記録をもういちどなぞる。耳の奥にひびくうつくしいテノール。
ふっと窓の外に視線を移した彫刻めいた輪郭に、なにかそらおそろしいものを垣間見た気がした。
彼女たちが・あの子の・代替品だなんて・おこがましいよ。
やわらかな微笑をかれはけして崩さない。
混乱でなくてはっきりとした恐怖だった。あざやかすぎてそうとわからかったくらいの。
かれのその浅く弧を描くように細めた、博愛の象徴みたいな目が、手にしたいという動的な感情を持ってたしかにだれかをみつめることがあるのだということに、恐怖した。いつも微笑むときに細められる静かで優美に見えた目が、意味を変えてゆく。変貌してゆく。なぜ気づかなかったのだろう。かれの目は笑ってなどいなかったのだ。かれがああやって目を細めるとき、目の前にある事象を透過して、「あの子」の像を結んでいたのだろう。だれのすがたに重ねるでもなく、そこにその子自身のすがたをたしかに見ているように。慈しむような視線、けれどそれは寵愛ではなく、昏い憎悪さえ孕んでいる。かれは誰にも踏み入れられない場所を見つめている。
無限に広がる湫。
脳みそをすうっと撫でられたような気がして、ぞわりと全身の毛が立った。
ーーあんた、誰かを手に入れたいとほんとうに願ったことはあるの。
そう聞いたのは、ないと答えられればやっぱりそうかと安堵できるだろうし、あると答えられればかれにも誰かに思いを寄せるということがあるのだ、かれもやはり平凡な一個人にすぎないのだと、そうくすぐったく笑いあうつもりだったからだ。じっさいは、さあ、と曖昧にされると思っていたし、それでもよかった。あまりにもとりとめのない会話のたった一部だった。だけどいざその目が誰かひとりに向けられるということをこうして知ると、なにかそれがおそろしくいびつで間違ったことのように感じられた。その視線は期待したような、じぶんたちが誰かを慕い、慈しみ、愛すときの目じゃなかった。そんな範疇をとっくに過ぎていた。丹念にみがかれたナイフ。ヴァン・ショーみたいな、熱と陶酔と、からだを蝕むアルコールの毒、静かすぎる熱情。
ーーあったよ。
過去形で語られたことにはどういう意味があるのだろう。かれはこんなにもいまだ鋭いものを抱えていて、あきらめただなんてそんなことがあるのだろうか。まるで手に入れたがったもののほうから消えてしまったみたいだ。
「具合が悪い?」
声をかけられて、はっとぼやけていた視界が集束した。なにかを言わなくては、とてもそこにいられなかった。意味のないことでもいい。絞りだすようにやっとのことでことばをはなとうとする。のどがからっからに乾いているのを声を出してはじめて気づいた。
「その子はいまはどうしている?
ーー亡くなったの?」
だけど、まただ、まちがえた。
あんた振られたの、そうとでもいえばもう少し冗談にも近づけられたのだろうに、もうおそい。かれはしばらくなにかを思い出すようにして、まっすぐにおれの目を射止めて、笑った。……ああ、そのとおりだ。笑ってなんかいない。
「さあ、どうだろう」
ひどく無責任なことばだったけれど、やわらかくけして突き放すようなものでなかったことにおどろいた。ほんとうに知らないというみたいで、それが事実におもえた。あるいはそんなことにはぜんぜん興味がないみたいだった。視線を逸らしてしまえれば楽だったろうに、不思議なくらいその赤い色に吸い寄せられる。そこには、蜜でもあるんだろうか。血の色のなかで誰かがみつめかえきている気がした。かれの瞳のなかに、ときどき子どもめいた無邪気な翳りが見える。
「ねえ、死はどこにあるんだろう?」
質問を質問で返すのはずるい。こっちはそれをもういちどは使えないから。答えずにはいられないから。死はどこにーーあるんだろう。どうしてそんなことを聞くのだろう。まるでそんなものどこにもないみたいに。
だけどふと、それが今月の機関誌の論文のタイトルだということを思い出した。死はどこにあるか。
「からだが……いや、主観が消えた瞬間にあらわれるもの……」
「……もうひとつ、聞いてみてもいいかな。他人の主観を、それがたしかにあるとどうやって観測するんだろう。反対に、からだのない主観がないとどうやって証明するだろう。たとえばきみが読む本の登場人物はものを思うだろうか。それが存在したり、消えたりするのを、そのひと以外にだれが観測できるだろう。たとえばからだがほろびて、閉じ込められていたその主観が外へとはなたれてまだそこにあるのだとしたなら、それでも死とよぶんだろうか」
かれが何を言いたいのか、わかるようでわからない。その内容じたいはかろうじて理解出来るけれど、意図はちっとも読み取れない。ただ完全にかれのことばに聞き惚れていた。それはどこかとおい国の詩の朗読、心地よい音楽のようだった。
おれ以外の世界のだれもが、かれでさえほんとうに心なんて持っていなくて、規定通りの演技をする人形のようだとしたなら、そしてかれから見ればおれだってそうで、かれの世界でおれがたしかに意識をもっているということを証明できないなら、だれもがだれかの世界ではそうなら。そうなら、ではない。じっさいにそうだ。心のありかは証明できない。メルツェル・ドールにだってそれはあるのかもしれない。本の登場人物にだって。
死はどこにあるんだろう。
生の死の境はどこにあるんだろう。
夢と、いま夢ではないと信じている景色の、境は?
「ときどき不思議に思わない?眠って起きたら、どうして昨日の自分といまの自分とが地続きだって感じられるのかって。それとこうも思うーーその証拠はどこにあるんだろう?まったくかたちの同じべつのからだに記憶と認識体系とをうつされたのだとしてだれがそうと気づくんだろう?主観の移植と複製。アカウントを別の端末に引き継ぐみたいにかんたんに、どんな器にもインストールできたなら。主観の創造ーー本や夢の登場人物だって、その認識体系を再現できたらからだを持つことだって可能かもしれない」
滑らかなことばたちににつよく惹かれながら、ひどいめまいをおぼえていた。三年前、かれはここへ突然あらわれた。メルツェルに手紙をすでに送ってあるといって通されたかれを案内したのはおれだった。
かれはここで何をするんだろうか?
しようと、しているんだろうか?
「現実に存在しないものを手に入れようとするとき、ひとはどうするか俺たちは知っているはずだよ。物語を残したい者は小説を書く。風景を表したい者は絵をえがく。美しいすがたを愛でたいのなら、人形をつくる」
「ーーなんの話を」
「象る、ということ。
ひとの夢からかたちをつくる方法は、ずっとそうだったよ」
それからすぐかれとおれとのあいだに通信モニターがたちあがり、少女のすがたで約束の時間を告げた。実体のないそれはだけどかれとのあいだを阻むやぶることのできない薄い膜、見えない壁のようにおもえた。いまの話さえ途方もないおとぎ話だったかのように、もう行かなくてはねと立ち上がったかれの彫刻めいた顔に浮かぶのはこんどこそ完ぺきな陰ひとつない微笑だった。
結局かれの手に入れようとしただれかが、どんな人物であってどのように関わってどのようにかれの前からすがたを消したのかーーあるいはかれのほうから去ることになったのかを、語られることはなかった。死や主観の移植なんて話はそれとはまったく関係のない話で、おれをはぐらかすためのただの気まぐれだったのかもしれない。
だけどときどきこんなことを夢想する。
その子はほんとうはどこにもいなくて、それさえすべてはかれの一夜の夢だったのかもしれない。かれの中でだけ生き、かれの中でだけすがたを消した、その子はいまはまだえがかれていない物語の人物なのかもしれない。夢の国のアリス。作家が文字を連ねるように、音楽家が五線譜を彩るように、かれはまだ見ぬだれかをあたらしい技法でたしかなものに象ろうとしているのかもしれない。
そうであればうつくしいと思った。
ただしくなかろうと真実でなかろうと、それがおれの中ではもっともかれにふさわしいような気がした。かれのからだを褥として夢はそだち、いつかかれをとおしてかたちを得る。かれは死をきらっているのでも、死者にとりつかれているふうにも見えなかったから。むしろ生のあざやかなにおいすらそこにはあって、手に入れられなかったということじたいがかれにとってはひとつも惜しむべきものではなく、神聖な事実なのではないかと思えた。
その子はかれの瞳の中でだけ住んでいる。博愛と無関心だけがあると思われたかれの瞳の中で、ただ一点の炎をくべつづけている。
象るということーー。
主観の移植、複製、創造ーー夢を捏ねてかれがなにかを生み出そうとする過程で、ひとのありかたはもしかしたら大きく捻じ曲げられてしまうのかもしれない。かれの目的がそうでなくたって、だって夢の人物ではなくひとにとってはそれは死をうしなうことだ。からだが時によってほころんでそれをだれも止められないのならば、いつかみんなからだを棄てるようになるかもしれない。人形のやわらかなつくりものの器に移住するかもしれない。あるいは物語の人物が読まれることによってひとびとのあいだを渡り歩くように、ひともいつかからだを持たず情報の海をゆきかう信号になるかもしれない。これから何百年も先、かれの技法によってまったく新しい命のありかたが定義され、ひとの意識は創作世界と物理世界のあいだでクラウドできるものになり、いつか現実と夢の境界はまざりあってうしなわれるのかもしれない。だけどかれは気にもとめないだろう。なぜだかそれが心地好いものに思えた。かれの技法によって変容することは暴力的な官能だと思った。そのような力を、ふるわれ��みたいとさえ思った。
三年前からの友人だ。少なくともおれはそのつもりだ。だけど、おれはこの男のことを、きっとまだ何も知らない。
1 note
·
View note
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」 令和2年(2020)6月23日(火曜日) 通巻第6552号
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
集中連載「早朝特急」(17)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
第一部 暴走老人 西へ(17)
第十七章 南モンゴル、ウィグル、チベット
▲中国の残虐はチベットで顕著に露呈した
チベットのラサへは成都から飛行機で飛んだ。空港で驚いたのは大型機が次から次へと中国各地から到着し、観光ブームの頂点に湧いていた。空港からラサ市内までは一時間半ほど。渓流や水たまり、でこぼこ道を越えるので四輪駆動でないと、安定しない。
ラサ市内であちこちを見たが、ようすにチベット族は差別を受けて、ろくな職場がないこと、仏教寺院はありきたりで、とても僧侶達が真剣に仏典を勉強しているとは思えず、ひどく俗化していたこと。ポタラ宮殿は偉容を誇るが、内部はそこら中に公安デスクがあり、警戒が厳しく、広場ではうっかりすると物乞いがまといつく、それもじつにしつこい。
市内にアメリカ人女性が経営するバアがあって、スコッチを飲んだが、一杯程度では高山病にかかることもなく、最終日にうっかり四杯呑んだら、一晩中頭が痛くて眠れない。嗚呼、これが高山病というやつか、と貴重な体験をした。
ひとことで言うとチベットは完全に漢族の支配下にはいってしまった、表向きの寺院とは無縁の俗世である。知識人も僧侶も、ほとんどが粛清されたか、外国へ逃げたからだ。
チベットはいかにして侵略され、自由が失われてしまったのか、これまでにも多くが語られた。
ダライラマ法王にはノーベル平和賞が授与され、そのダライラマに感激したハリウッド俳優のリチャード・ギアはチベット仏教徒になった。エディ・マーフェイは若き日のダライラマを助ける映画の主演を演じた。ブラッド・ピットはエベレスト登山の冒険野郎が、ダライラマにひかれてゆく物語の映画に主演した。
ダライラマが訪米すれば大統領が面談する。わが日本は仏教国であるにも拘わらず、歴代首相が面会したことはない。
日本はいつの間にかサムライ精神を忘却の彼方へ葬り去った。
▲このチベットの惨劇が明日の香港の運命を襲うかも知れない
香港と台湾は過去の出来事を学んだ。とくに香港は『国歌安全法』がいずれ言論の自由を封じ込めることになると不安を募らせ、「第二のチベット」か、或いは「第二のウィグル」になるのではないか、不安が増すのも中国共産党がいかなる凶暴性を発揮してきたかを知り尽くしているからだ。
沈黙を続ければ、静かに侵略はすすみ、自由社会は消え、中国共産党の奴隷に転落するという悲劇的な地獄を迎える。
悲劇は繰り返されている。南モンゴル、チベット、そして現在の進行中はウィグル族への血の弾圧だ。
ペマ・ギャルポ『犠牲者120万人 祖国を中国に奪われたチベット人が語る侵略に気づいていない日本人』(ハート出版)の行間にもチベット人の悲劇、
その懊悩と悲惨な逃避行のパセティックな思いが滲み出ている。温厚で信仰心熱きチベットは中国にあっという間に侵略され、中国に味方する裏切り者も手伝って、120万もの同胞が犠牲となった。ダライラマ法王は決死の覚悟でヒマラヤを越えてインドに亡命政府をつくった。その深い悲しみ、暗澹たる悲哀、血なまぐさい惨劇、しかしこのチベットの教訓こそが、香港、台湾、そして日本がいま直面している危機に直結する。
「日本人よ、中国の属国に陥落し、かれらの奴隷となっても良いのか」とペマ氏は訴える。
チベットは「寛容の国」だった。
それゆえに「寛容の陥穽」に嵌って邪悪な武装組織、つまり中国という暴力団の塊のような、ならず者によって滅ばされた。日本は平和憲法という、寛容な国家の基本法を押しつけられてから七十四年も経つのに、未だに後生大事に墨守している。それが国を滅ぼす元凶であること、左翼の言う「平和憲法」擁護には騙されてはいけないことをペマさんは力説している。
百万人の強制収容所問題で世界を揺らすウィグルの悲劇もチベットのパターンを踏襲している。
▲ウィグル自治区で何が起きたか
十数年前に新彊ウィグル自治区を旅し、ウルムチから列車でトルファンへ入った。
途中のハミ駅で熟した瓜を買った。じつに美味い。トルファンでは干しぶどう、これもまた絶品だった。当時、中国で売り出したばかりの「長城」をいうワインはフランスのワインとまでは行かないけれどもなかなか乙な味だった。
江沢民時代の新彊ウィグル自治区は外国人にほぼ全域が開放されていて、かなり自由に写真撮影もできた。
ウルムチやトルファン市内の屋台に溢れる羊肉、皆がイスラム帽をかぶり、女性はスカーフが多かったけれども、顔を隠しているわけでもなかった。
観光名所のベゼクリク千仏窟は、いかにイスラムが仏像を破壊したかの廃墟跡を意図的に見せているような気がした。岩だらけの高台には孫悟空ワンダーランドとかのテーマパークも出来ていた。
ウィグル自治区の各地でコルランの普及率を調べたが、何処にも、それこそ一ケ所にもコルランを売る書店もなければモスクの受付にもなかった。田舎へ行くとモスクは閉鎖されたところが多く、そのモスクの周囲は物静かで人影もなかった。
コルラン販売の監視とモスクの出入りがチェックされている様子は呑み込めた。
▲留学生がおびただしく行方不明になった
2017年頃からエジプト留学から帰国したウィグル族の若者が当局に拘束されて行方を絶った。家族が心配して心当たりを捜したが、杳として行方がしれない。同様な「事件」が頻発していると在日のウィグル人組織が騒ぎだした。
2018年にはドイツやトルコの海外ウィグル人組織が騒ぎ出し、議会が動き、国際団体が調査に乗り出した。ついに国連の人権委員会で取り上げられた。
なかには家族が偽りの電話を強要され、父親が病気とかで外国へ電話をかけて急いで留学先から帰ると、有無を言わせずに強制収容所に放り込まれ、そのまま一年以上。
合計八千名のウィグル族の若者の留学帰りが収容所で「再教育」という名の下に洗脳教育を受けていた。いずれもイスラム圏への留学という共通点があった。
もともとウィグル族はイスラム教を篤く信仰してきた。無神論の中国共産党は、それ自体が一神教であるから異教徒は許容できない。
この弾圧の中心人物は陳全国(政治局員)だ。
2016年8月29日、陳全国が新彊ウィグル自治区の党委員会書記に任命された。直前まで陳全国はチベット自治区の書記だった。つまりチベット弾圧の責任者だったから、ウィグル自治区にはいっても民衆の弾圧、暴力支配など得意技だった。
陳全国は1955年に河南省に生まれた。武漢の大学をでて軍隊に入隊し、共産党へ入党して頭角を現し、2010年に河北省省長に就任した。異例のスピード出世である。その後、習近平の覚え目出度くチベット書記に栄転した。現在はトップ25の政治局員でもある。
同じ頃、重慶特別市書記だった孫政才が唐突に解任され、新たに陳敏爾が任命された。孫政才の解任理由は「薄煕来の腐敗体質の残滓を重慶市から積極的に排除できず、そのままに旧幹部等をのさばらせ、自らも汚職に励んだ」などとする冤罪だった。要は共産主義青年団の「希望の星」だった孫を潜在的ライバル視してきた習近平にとって、将来の独裁に邪魔になるから排除したに過ぎない。
陳全国も陳敏爾も習近平の子飼い、イエスマン若しくは茶坊主、行政手腕が無能でも、おべんちゃらがうまければ出世街道を驀進できる。阿諛追従の才能だけは秀逸なのだ。下手に理論家だったり戦略論をぶったりすると無学な習近平から逆恨みされるのだ。
ウィグル自治区の悲劇は、このときから一層無惨になった。
2009年に勃発したウルムチ暴動で、漢族が武器を持って手当たり次第にウィグル族を虐殺し、多くのウィグルの若者は隣のカザフスタンへ逃げた。その数は数万人と言われるが、そのうちの一万人ほどがシリアの軍事訓練基地へ送られ、ISのメンバー入りした。
かれらは漢族への復讐心に燃える。中国の諜報機関はシリア政府、同時にISにも武器を提供して巧妙に近づき、かれらの動向の情報収集に躍起となった。テロリストとして訓練され、中国に帰ってくることを怖れたからだった。
ISをスピンアウトした過激派は「漢族に血の復讐を。中国人を血の川へ投げ込め」などと煽動するヴィデオを作成し、ユーチューブで配信した。びっくり仰天の中国共産党はあらゆる手段を講じてでもウィグル族過激派の撲滅排除に乗り出す。
陳全国は新彊ウィグル自治区の党書記となるや、「宗教活動を厳密に規制し、イスラム文化の表現をやめさせ、辻々には検問所を設け、顔識別とAI機器を駆使して手配者の逮捕を強化し、さらに砂漠に次々と強制収容所を設営し、拷問による改宗を強要した」(『TIME』、2018年8月27日号)。
▲再教育センターとは監獄である
そうやってイスラムを学んできたウィグルの若者の洗脳教育を始めた。「改宗」できない者は独房にぶち込み、イスラム教徒が忌み嫌う豚肉を与え、しかも独房の狭い牢獄に三人も五人も入れてストレスを溜めさせる。睡眠不足とし、洗脳の効果をあげようと急いだ。それでも「直ら���い」ケースでは家族も強制収容所に入れた。出所してすぐに死ぬという悲劇が相次いだ。
米国の偵察衛星が収容所の数が急増していることを突き止めた。また強制収容所ばかりか、再教育センターもつくられ、家族全員のDNAや血液が収集されデータベースに入力された。デジタル全体主義の支配システムである。
トランプ政権はこのような人道に悖る人権無視の民族浄化を黙ってみることはなかった。
衛星写真の証拠を楯にして、これを対中政治カードとする。ゲイ・マクドゥーガル国連人権差別撤廃委員は2018年8月10日、国連委員会で「200万人のムスリムが強制収容所で再教育を受けているという報告がある」と爆弾発言した。
マクドゥーガルは「なかには髭を貯えていた、ベールを被っていた」などの理由で拘束されているケースも報告されているとし、「ウィグル族の民族的アイデンティティの喪失が目的だ」と中国を非難した。
またウィグル女性は漢族の男性としか結婚できないという規則を強要しているとの情報があり、そうなるとユーゴスラビアでおきた「エスニック・クレンジンング」(民族浄化)という悪夢の再来である。あの時、セルビアは欧米社会から猛烈な非難を浴び、孤立を怖れたセルビア国民はミロセビッチ、カラジッチという民族の英雄を国際法廷に送り込んだ。
中国は国連報告をただちに否定し、「あそこは強制収容所ではない、あれは職業訓練センターであり、ウィグル人の教育向上と雇用機会の増大をはかる目的だ。漢族も収容されている。われわれが警戒して取り締まっているのはテロリスト、分裂主義者、過激な宗教活動家だけだ」などと平然と嘯いた。
これはチベットにおける120万人の無辜の民と僧侶の虐殺を「農奴解放」と言ってのけた嘘の論理の適用である(チベットに農奴はいなかった)。
またウィグルの動きに触発されて隣の青海省、四川省、甘粛省、陝西省、寧夏回族自治区などではモスクの監視が厳格化され、とくに後者の回族自治区のモスクは「改修」を詐っての取り壊しが計画されたため信者がモスクに座り込み開始した。
イスラムは国境なき連帯のコミュニテイィであり、ウィグル族への苛烈な弾圧は口コミを通じて世界のムスリムに拡大した。トルコはこの時、中国を激しく批判し、旅行制限をだしたほど対立的だった。
ムスリムの中国敵視は米国の対中国認識とはレベルの異なる、感情的エトスが含まれているのである。
▲日和見主義だった欧米が中国に強硬となった
習近平時代となって強烈なイスラムへの弾圧が強まった。陳全国の悪名は世界にとどろき、「悪代官」と呼ばれる。収容されているウィグル人は百万人ともいわれるのに、イスラム同胞をかかえる国々は中国の人権抑圧を批判しない。米国も911テロ事件以来、「東トルキスタン開放同盟」を「テロリスト」とうっかり認定してからこれまでは黙りを決め込んできた。
その日和見的態度をがらりと変えたのがトランプ政権だった。
ペンス副大統領が正式にイスラムに言及し、ウィグル族の不当拘束を避難する演説を行ったのは2018年十月だった。2019年七月には日本を含む22ヶ国が中国政府を批判する声明に署名した。トランプ大統領はウィグル族をふくむ少数民族の代表者をホワイトハウスに招いて実情を聞いた(19年7月17日)。
しかし奇妙なことにイスラム国家のサウジもエジプトもカザフスタンもキルギスも右の署名には応じなかった。イスラム国家とは言え、みな独裁政治であり、おなじ独裁の中国とはたいそう馬が合うのだ。
だからイスラムはテロリストだという中国の嘘宣伝を楯にイスラム同胞への惨い弾圧には目を瞑ってきた。
▲イスラムの影響を抜き取るのが収容所の目的なのだ
福島香織『ウィグル人に何が起きているのか』(PHP新書)はウィグルへの突撃取材を試みたルポで、エティガール寺院の現場報告から始めている。
「美しいミナレットが特徴で、一日五回行われる礼拝の時間にはアザーンが流れるとガイドブックには書いてあるのだが、(中略)流れていなかった。寺院の屋根には五星紅旗が翻る。宗教施設に国旗を掲げることは2018年二月以降、義務化されているのだが、これほど不自然な光景もない」。
しかも寺院前広場はゴーカートなど子供遊園地に化け、戦車の乗り物もある。目抜き通りを歩くと「路上にはゴミ一つ落ちておらず、清潔だ(中略)が、どこかよそよそしい、この作り話めいた空気は何だろう。青いジャージに赤いネッカチーフの小学生たちが、中国語の童謡を唱いながら歩いていた。ああわかった。テーマパークだ」
タクシーにのっても監視カメラ内臓のため運転手と会話は弾まず、車内には「社会の秩序を乱してはいけない」などのポスター、どこもかしこにも監視カメラだらけ。
「人々は正直で親切だ。だが、人を含めて全部作り物のようだった。彼らは昔ほど陽気ではなかった」
福島香織さんの観察の目は鋭く、さらに牧畜が行方不明となっている現実をみた。どこにも羊の姿はなかったのだ。町からも村からも消えていた。ウイグルは「巨大な監獄」だった。それも「21世紀で最も残酷な監獄社会」だ。
所内では漢語の強制、豚肉を食べさせ、ウイグル族の文化的背景、イスラム教の影響を抜き取り、漢族風に洗脳する目的だったことは述べた。
中国語を教え、中国の法律を叩き込み、そのうえ中国共産党の獅子吼する「愛国」教育を徹底させた。その一方で、縫製、メカニカルエンジニアリングからホテルの清掃のやり方など教育、訓練した。
反抗したウイグル族が相当数、拷問され、収容所内で死亡した。
こうした事実はその後、亡命に成功したウイグル族女性によって米国議会の公聴会証言で明らかとなった。米議会は超党派で中国への批判を強めた。
トランプ政権はウイグル弾圧に用いられたとして監視カメラ、顔面識別、AI技術を製造するハイクビジョンなど中国企業の28社を[EL]リストに加え取引停止とした。ペンス副大統領の二度に亘る対中批判演説にはこれらの裏付けがあった。
1 note
·
View note
Text
あれがヴィクトル・ニキフォロフ
普段から人々にもてはやされ、いろいろな相手に声をかけられるクリストフだが、それがバンケットとなると、試合の終わった開放感と、そう何度も会えるわけではない面々という状況が加わり、ますます誘われることが多かった。クリストフは笑顔で、やわらかく、気の利いたことを言って適当にあしらうが、こういうときに気になるのは、自分のことではなく、友人のヴィクトル・ニキフォロフのことだった。彼もまた人気が高く、試合で披露したプログラムのすばらしさもあって、いつでも多くの女性に群がられていた。今夜もそうで、彼はワインのグラスを傾けながら、押しの強い女性選手たちの話を、気取った微笑を浮かべて聞いていた。
クリストフは、自分の目の前にいる相手が、帰国までに食事をしましょうとか、次の出場試合も同じだからそのときでもいいとか言っているのを上手くはぐらかしながら、これはまだ楽なほうだと考えた。もちろん夜の誘いに積極的な者もいるので、そういうときは、失礼のないように断るのが難しい。それをたくみにできるのがいい男の条件だとクリストフは思っている。
しばらくすると、ヴィクトルが人々の輪から離れたところを狙って、そっと彼に近づいた女性があった。彼女はクリストフのそばでちょうどヴィクトルを呼び止めたので、彼女自身の言葉は聞こえなかったけれど、彼の答えは耳に届いた。ヴィクトルは、とにかく彼女を褒めてよい気分にさせ、手際よく、慣れた感じで誘いをかわした。相手を刺激しないよう、いい気持ちのままあきらめさせるのが、彼はじつに上手かった。クリストフはこの手腕については自分もなかなかだと思っているのだが、ヴィクトルの口ぶりには感心した。
「すごいね」
クリストフは、ヴィクトルがひとりになるとそっと寄っていき、ふくみ笑いを漏らして声をひそめた。
「あんなきざなせりふ、とても俺には口にできない」
「うそだろう。俺はクリスが言ってるのを聞いて勉強したんだけど」
「いつの話?」
ふたりは顔を見合わせて笑った。
「応じてあげればよかったのに」
クリストフは、ヴィクトルにまったくそんな気がないことをわかっていてからかった。
「興味ないんだ」
ヴィクトルは微笑を浮かべたままあっさり言った。
「どういう相手なら興味があるわけ?」
「さあね」
「好みは?」
「さあね」
「どうでもいいって感じだね」
「スケートのことで頭がいっぱいなんだ」
「スケートとは結婚できないよ」
「クリスは結婚したいと思ってるの?」
その質問にクリストフは驚いた。
「とくに具体的に考えてるわけじゃないけど、まあいずれはそういうこともあるかもしれないなという気はしてるよ」
「へえ」
ヴィクトルは簡単な返事をした。
「未来のことなんてわからないからね」
「そうだね」
ヴィクトルはうなずいたが、未来のことなんてわからないから俺もいつかは結婚するかもしれない、と思っているようには、クリストフには見えなかった。
「ヴィクトルは?」
こころみに尋ねてみたところ、ヴィクトルの答えは、クリストフの想像どおりだった。
「興味ないんだ」
「びーまいこーち!」
勇利が子どもみたいに叫んだ。その言葉にクリストフはびっくりし、しかしこのうえなく愉快に思い、ヴィクトルがどう思うだろうとそのことを考えた。
「びくとーる!」
完全に酔っぱらった勇利が、勢いよくヴィクトルに抱きついた。みんなが声にならない驚きをあらわにし、クリストフはおもしろいと思いながらも、すこし心配した。
クリストフは勇利が好きだった。勇利には才能があるし、彼のスケートは彼だけにしかできない、情緒的で気品高いものだ。試合ではなかなか成果を出せないけれど、クリストフは彼のスケートを気に入っていた。このたび、ようやくグランプリファイナルに出場できて祝福していたのに、結果が思わしくなく、精神的によわっていないかと気になっていた。だが、勇利はわかりやすくなぐさめてもらって喜ぶたちではないし、あまり踏みこむのはいいことではないかもしれないと判断し、自重していた。ところがこのバンケットで、勇利は、以前から大好きで夢中になってあこがれていたヴィクトルと楽しそうに踊り、おおはしゃぎだった。おもしろいことが好きなヴィクトルも、陽気に相手をしていた。これですこ���は勇利も元気になるかもしれないとクリストフはほっとしていたのだが、ここまでのことを言い出すとは思っていなかった。
酔った勢いというのもあるし、これまでのはしゃぎきった雰囲気を考えれば、勇利の望みは冗談として受け取られ、すぐに忘れられるだろう。ヴィクトルの対応もそういったものにちがいない。だがヴィクトルは、女性たちの誘いを断るように、慇懃に、あっさりと、うわべだけの綺麗な言葉で辞退するかもしれない。感受性豊かで繊細な勇利にはそれは通用しないのだと、クリストフは知っていた。勇利ははっきりと、手ひどく拒絶されたと感じ、今夜の楽しい思い出も台無しになるだろう。我に返り、青ざめ、ヴィクトルにずうずうしいことを言ってしまった、それ以前にあんな醜態を見せてしまったと後悔するにちがいない。クリストフはそれが心配だった。勇利はとてもよい友人で、クリストフは彼に仲間として親しみを感じており、だから、勇利が落ちこむようなことにはなって欲しくなかった。
クリストフははらはらしながらヴィクトルを見た。ヴィクトルがあの気取った調子で、きざなことを言い、やんわりと勇利を拒絶するのを覚悟した。いくら楽しくダンスを踊ったといっても、それと同じ具合で、ヴィクトルが勇利の頼みを喜ぶとは思えなかった。彼は、自分に特別な感情をことさらに向けてくる者には、いつだってきまった態度を取り、それ以上に何かを与えることはないのだ。
クリストフは息をつめた。勇利が傷つかないことを祈った。ヴィクトルがすこしでも優しい物言いをしてくれることをねがった。そして同時に、そんなことを言い出した勇利の勇気に敬意を表した。酒が入って精神が高揚しきったとはいえ、引っこみ思案で控えめな勇利が、これまでまったく近づけなかった遠い存在である皇帝をダンスに誘い、さらに「コーチになって」とまで言ったのである。やるじゃないか、という気持ちもあった。
クリストフはじっとヴィクトルをみつめた。ヴィクトルが口をひらくのを待った。だが、ヴィクトルは、いつまで経っても何も言わなかった。彼ははっとしたように息をのんだあと、硬直して、勇利に抱きつかれるままになっているのだ。それだけではない。ヴィクトルは、思いもかけないことを言われたというように興奮し、頬を上気させ、勇利をみつめる瞳は一等星のように輝いていた。
クリストフはあぜんとした。ヴィクトルがそんな反応をするとは思わなかった。これがあのヴィクトルだろうか? 好意を示されればきまりきった計算された言葉で断り、「興味がないんだ」とクリストフに向かって肩をすくめたヴィクトル・ニキフォロフだろうか?
「びくとる……」
勇利が完全にヴィクトルに寄りかかった。ヴィクトルはどぎまぎしながら勇利を抱きとめ、「大丈夫かい?」と尋ねた。その声ときたら! クリストフがいままで聞いたことがないほど優しい、甘い声だった。クリストフは、ヴィクトル、君そんな声でしゃべれるんだ、と笑いそうになった。
「だいじょぶ……」
勇利はつぶやき、彼もまたきららかに輝く黒い魅力的な瞳でヴィクトルをみつめた。ヴィクトルは動けないようだった。勇利から目をそらせないのだ。クリストフはあやうく噴き出すところだった。
「びくとる……」
「なんだい?」
「びくとる……」
「うん……」
「あのね……」
「なにかな……?」
ヴィクトルは、世界じゅうの何をおいても、どんなことをほうり出しても勇利の話を聞きたいと思っているかのように、熱心に勇利の口元に耳を寄せた。
「ぼく……」
ところがそこへ、日本のスケート連盟の役員たちがやってきた。彼らは勇利をさっとヴィクトルから引き離すと、彼に何度も謝った。ヴィクトルは目に見えてがっかりした。彼はあきらかにまだ勇利と話したがっており、抱きつかれたり甘えられたりすることを喜んでいるのだ。
勇利は腕を引かれ、身支度を整えさせられながら、それでもヴィクトルのことを見、「びくとる」と呼んでいた。ヴィクトルはいてもたってもいられない様子で、彼のそばに行きたそうだった。クリストフはヴィクトルの隣にすっと寄り、「ちょっと、君」と話しかけた。だがヴィクトルは返事をしなかった。彼は勇利の声しか耳に入らないのだ。勇利の言うことだけに全神経を集中させているのである。
勇利は、もう部屋へ戻ったほうがよいと言い聞かせられていた。クリストフには日本語はわからないけれど、たぶんそういうことだと察した。だが勇利はかなしそうにヴィクトルを見ており、彼のほうへ手を伸ばして彼を求めていた。
「ヴィクトルとまだ一緒にいたい……」
それも日本語だった。しかし、せつない響きはクリストフにも伝わった。クリストフにわかるのだからヴィクトルにわからないはずがない。彼は名前を呼ばれたのだ。
「失礼」
ヴィクトルはすばやく、勇利を支えている男性と勇利のあいだに割って入り、彼を守るように抱いて自分に寄りかからせた。
「よかったら俺が部屋まで送っていこう」
ヴィクトルの申し出に、相手は驚いたようだった。しかしヴィクトルはそれで話はついたというように勇利に向き直り、「ひとりで立てるかい?」「抱いていってあげようか?」と甘い優しさを帯びた声で尋ねた。クリストフはもう可笑しくてたまらず、我慢できなかったので、そっぽを向いて笑った。
クリストフは、部屋でふたりがどうするのか興味がないわけではなかったけれど、何か大人っぽいことをしそうというよりは、ヴィクトルがひたすら勇利の世話を焼きたがっているように思えた。そうする中で、それが勇利にとってよいことになりそうなら性行為もするだろうし、勇利がヴィクトルにくっついて離れなければ、ヴィクトルはひと晩じゅう、朝までだって添い寝をして髪を撫でてやるにちがいなかった。
「いいかい? 歩くよ。気分は悪くない?」
ヴィクトルは親切に勇利を気遣っていた。勇利のダンスと、勇利のせりふと、勇利の抱きつきは、ヴィクトルによい意味で深刻な衝撃を与えたようだった。勇利との時間はヴィクトルにとって貴重で、今夜これから始まる時間もまた、同じように貴重なのだろう。
ただ、クリストフには、いまから何が起こるのか、想像もつかなかった。
翌日、ロビーでヴィクトルに会ったので、クリストフは興味津々といった様子で彼に声をかけた。
「ヴィクトル、ゆうべはお楽しみだったようだね。勇利はどうだった?」
わざとあからさまな物言いをすると、驚いたことにヴィクトルは、照れたように笑って視線をそらしてしまった。クリストフは目をまるくした。さすがにヴィクトルも今日は我に返って、いつものとりすました、体裁のいい、落ち着き払った態度に戻っていると思っていたのである。ところがどうだ。ゆうべ勇利がかけた魔法は、どうやらまだとけていないようではないか。もしかしたら一生とけないのかもしれない。
「どうだったって……べつに……」
クリストフは声をひそめ、ヴィクトル、と呼んだ。
「まあそうなることだってあるだろうとは思ってたけど……」
ひそひそとささやいて質問した。
「抱いたの……?」
「……いや」
ヴィクトルは相変わらず照れくさそうに笑っていた。
「いや……、そういうことはしてないよ」
「本当に?」
「ああ」
ヴィクトルは誠実にうなずいた。
「でも、かわいかったんでしょ? だから送っていったんでしょ」
「かわいかったけど、セックスするとかしないとか、そういうことじゃないんだ」
ヴィクトルは真剣に説明した。
「そうじゃない」
「じゃあどうなの?」
ヴィクトルはしばらく黙りこんだ。彼はかなり長いあいだ考えこみ、ようやく口にした言葉はこうだった。
「……よくわからない」
クリストフはまた驚いた。
「彼って不思議な子だね」
「ヴィクトル……」
「なんていえばいいのか……わからないよ。とにかく魅力的だなって」
「ヴィクトル、大丈夫?」
クリストフはまじめに尋ねた。
「何が?」
「あたま」
「これまでにないくらい絶好調だ」
その一年後、クリストフはまたヴィクトルと勇利と一緒にバンケットに出席する機会があったのだけれど、ヴィクトルはまったく変わっていなかった。いや──変わったといえるのだろうか。去年より、彼の症状はひどくなっていた。じつはクリストフは、たとえヴィクトルと勇利が親しくなったとしても、一年も経てばヴィクトルも慣れるだろうし、精神が安定するだろうと踏んでいたのである。ところがそうはならなかった。ヴィクトルはますます大変なことになっていた。
「勇利、やっぱりあのネクタイはよくないと思う」
たまたま三人一緒になったホテルのエレベータの中で、ヴィクトルは熱心に言った。
「昼のうちに新しいのを買いに行こう」
「あれでいいよ」
勇利は落ち着いたものだった。
「いや、よくないよ」
「何がよくないの?」
「勇利にはもっと似合うものがある」
「べつに深く考えなくていいよ。ネクタイまで見てる人いないだろうし」
「俺が見てる」
「じゃあ見ないようにして」
「無理だ」
「どうして?」
「勇利が綺麗だからずっと見てしまう」
クリストフはあきれかえった。綺麗だからずっと見てしまう? これが夜のバーで、ふたりきりで、ヴィクトルが勇利をくどきにかかっているというのならまだわかる。だがちがうのだ。いまは真っ昼間で、第三者──クリストフ──もいるエレベータ内で、しかもヴィクトルは、ごく日常的な会話として、心底からそう思って率直に話しているのである。
「俺が勇利に似合うのを選んであげる」
「いいよ、もう、そんなの……。あんまり時間ないし」
「すぐきめる」
「いいって……」
そんな会話をしながら、ヴィクトルは勇利の手を握り、指や甲を撫で、薬指には指輪がきらきらと金色に輝いているのだった。左手は勇利のほっそりした腰にまわっているし、もう見ていられない。
「ほら、着くよ」
「今日の予定はなんだっけ」
「ぼくのネクタイよりそっち気にしてよ。それでもコーチ?」
「コーチだよ……」
ヴィクトルは勇利の髪にくちびるを寄せた。
「勇利、ネクタイは……?」
「ヴィクトルはぼくのネクタイなんて見てる暇ないと思うよ。復帰を発表したんだから、いろんな人が話しに来る」
「勇利のそばにいる」
「そうは言っても、できないんじゃないかな」
「そばにいる。勇利のコーチだから」
「はいはい……」
勇利はクリストフに「おさきに」とほほえんで声をかけ、さきにエレベータから降りた。ヴィクトルもそうした。クリストフはしばらくその場にどとまっており、溜息をついてつぶやいた。
「最悪だ」
今後、絶対あのふたりとは一緒にエレベータには乗らない。
バンケットでは、勇利は、去年ほどではないけれど、なかなかの酔っぱらいぶりだった。ヴィクトルも酔ってはいたけれど、彼はかなり正常で、酔うことより、勇利にくっついていることに忙しいようだった。そしてここでも、ヴィクトルは、去年よりいろいろと悪化していた。
「ヴィクトルー」
「なんだい」
「ヴィクトル、また一緒にいられるね……」
「そうだね」
「一緒にスケート、できるんだね」
「できるよ。ずっとそうしようね」
「ヴィクトルと、終わりにならなくて……」
勇利の黒い目がうるおいを帯びた。彼はヴィクトルに向かって清楚にほほえみかけた。
「よかった……。よかったよ……」
「…………」
ヴィクトルは感極まったようにくちびるをかみしめ、勇利を抱きしめて頬ずりをした。言葉もないらしい。その代わり、髪や額や頬にせわしなく接吻している。クリストフはやれやれと思った。だが、おもしろくて仕方ないのも事実だった。まったく、公式練習には出てこないし、なんだかわけありっぽくへだたりを取ってるし、それぞれ思いつめた顔で沈んでる様子だったのに、結局はこれ……。
「ヴィクトルは、去年のバンケットでぼくと踊ったって言ってたけど、どうだったの?」
勇利がヴィクトルのネクタイをいじりながら尋ねた。
「どうだったって、すごく楽しかったよ」
ヴィクトルは上機嫌で、にこにこして答えた。
「いきなり踊るし、ずうずうしいし、礼儀を知らないおかしなやつだって思った?」
「いや、かわいいって思った。すごくかわいかった」
「じゃあ、一年、生徒として取り扱ってみて、どう思った?」
「かわいいって思った。ものすごくかわいい」
「へえ……そうなんだ」
「うん、そうなんだ」
「ヴィクトルって、変わってるね!」
勇利がへらっと笑った。ヴィクトルもへらっと笑った。君も変わってるよ、とクリストフは思った。
「今年は、去年ほど楽しくない?」
「いや、すごく楽しい。たまらなく楽しいよ」
「でも踊ってないよ」
「踊るのも好きだけど、勇利といると俺は楽しいんだ」
「ふうん……」
「去年は勇利を部屋へ送っていったりもしたんだよ」
「そうなんだ。部屋でのぼく、どうだった?」
「どうだったって……」
ヴィクトルが高揚したように口ごもった。おいおい、とクリストフは思った。何もしなかったんじゃなかったのか?
「……かわいかったよ」
「どんなところが?」
「靴下が脱げないってじたばたしてるところが」
「それから?」
「水が飲みたい、飲ませて、って、水を飲みながら水の瓶を探してるところが」
「ばかじゃん」
「かわいかった」
クリストフは、本当に飲ませたんじゃないだろうな、と疑った。手を使わずに。
しかし、そんなふうに上機嫌のヴィクトルでも、勇利の言ったとおり、ずっと勇利にべったりというわけにはいかなかった。話をしなければならない相手もいる。ヴィクトルは勇利から離れるとき、クリストフを呼び、くれぐれもこの子に気をつけてやってくれと頼んだ。
「わかった。よく見てるよ」
「目を離さないでくれ。本当にあぶなっかしいんだから。勇利、いいかい、クリスの言うことをよく聞いて……勇利!」
勇利はふらふらとひとりで歩き出していた。ヴィクトルは慌てて彼を引き止めた。
「どこへ行くんだ!」
「ピチットくんと遊ぼうと思って」
「わかった。ピチットといてもいいから、クリスも一緒だ。もう飲むんじゃないよ」
「ヴィクトル、ぼくが飲むの好きじゃん」
「俺がいるときはね。いないときはだめだ」
ヴィクトルはいろいろと勇利を心配し、注意を与えたうえで、彼の額にキスをしてせわしなく歩いていった。勇利から離れなければならないのがかなり無念だということが、彼の足取りから見てとれた。クリストフは笑いをこらえた。
勇利はヴィクトルの言葉をおぼえておらず、平気な顔でシャンパンに手を出した。おもしろいのでクリストフはほうっておいた。しばらくするとヴィクトルが戻ってくるのが見えたが、彼は誰にも呼び止められなかった。こんなことは、一年前には考えられなかったことだ。女性たちはどうしてもヴィクトルに声をかけずにはいられなかったのだ。だがいまはそうしない。しても無駄だとわかっているのだろうと、クリストフはこっそり笑った。そのとおり、ヴィクトルはまっすぐ勇利のところまで帰ってきた。
「飲んでるじゃないか!」
「何が?」
勇利はまたひとつグラスをからにしたところだった。
「俺の言うことをぜん��ん聞かない……。まあ、戻ってきたからもう飲んでもいいけど」
ヴィクトルは溜息をつき、クリストフに「ありがとう」と礼を述べた。
「でも止めてくれたらよかったのに」
「おもしろかったからね」
「ヴィクトルー」
ますます酔った勇利は、ヴィクトルにくったりともたれかかった。ヴィクトルの頬が紅潮した。
「勇利、くらげみたいになってるよ」
ヴィクトルが勇利の髪を撫でた。いとおしくてたまらないといった様子だ。
「大丈夫かい? もう部屋に戻る?」
「うーん……。去年みたいに、ぼくを送ってくれる?」
「同じ部屋じゃないか」
「同じ部屋じゃなかったら送ってくれない……?」
勇利がきららかに輝く瞳でヴィクトルをみつめた。ヴィクトルは強く宣言した。
「そんなわけないだろ」
クリストフは噴き出した。
「ヴィクトル、去年の、そのときさ……」
勇利は目を伏せ、またヴィクトルのネクタイをいじりながらぽそぽそと話した。
「部屋で、ぼくに何か……した……?」
ヴィクトルがのぼせ上がったのがクリストフにはわかった。
「いや、してないよ」
ヴィクトルは真剣に断言した。
「してない」
「ほんと……?」
「指一本ふれてない」
「そうなんだ……」
「あ、本当に何もしてなかったんだね。ちょっとくらいは手を出したかと思った。意気地のない男だねえ」
クリストフがまぜかえすと、ヴィクトルは「君は黙っててくれ」ときっぱり言った。
「余裕がないね、色男」
「じゃあさあ……」
勇利が考えこむようにうつむいて、ますますヴィクトルのネクタイをいじった。
「今日も何も……しない?」
「…………」
ヴィクトルがこのときどういう顔をしたのか、見なくてもクリストフにはわかったし、彼が何を思ったのかも、きわめて簡単に想像できた。ヴィクトルは首をもたげると、クリストフに向かって「じゃあ俺たちはこれで」と口早に言い、勇利をエスコートして去っていった。しかし、彼はすぐにでも飛ぶように戻りたかっただろうけれど、勇利をせかしたりはせず、手つきも寄り添い方も口ぶりも、やはりひどく優しかったし、甘かった。
「ちょっと抱きつかれて、踊って、コーチになってって言われただけであんなになっちゃって……」
クリストフはつぶやいた。
「数ヶ月コーチをして一緒にいただけで、そんなになっちゃって……」
翌日、今日は去年のようにはヴィクトルに会えないだろうとクリストフは考えていたのだけれど、驚いたことに、ロビーでまた彼の顔を見ることができた。
「あれ? 勇利にくっついてるんじゃないのかい?」
いまごろベッドの中か浴室かで、いちゃいちゃとむつまじく過ごしていると思ったのに。
「ああ……」
ヴィクトルはひどく深刻な顔つきだった。
「朝起きたら、勇利が……」
クリストフは彼の向かいに腰を下ろした。
「なに? へたくそって怒ったの?」
「いや……、恥ずかしいからちょっと外に出ていてって……まっかになって言うものだから……」
「…………」
ヴィクトルが深刻な顔になっているのは、どうやら、ゆうべの勇利のかわいいところや、今朝のそういった恥ずかしげな態度を思い出し、いとおしすぎて、かえって何か哲学的な気持ちになるせいらしかった。ばかばかしい。
「よかったね」
ばかばかしいけれど、友人が好きなひとと結ばれたのだ。それもどちらも大切な友人が。クリストフは祝福を忘れなかった。こうなることを望んでいたのだ。
「クリス、俺……」
ヴィクトルが真剣な態度でつぶやいた。
「なんだい」
「結婚しようと思うんだ」
クリストフは目をまるくした。ちょっと言葉がみつからなかった。楽しそうに、陽気に話すいつものヴィクトルとはまるでちがう、このうえなく真摯な様子だった。
「勇利と結婚しようと思うんだ」
ヴィクトルはくり返した。
「勇利と……」
クリストフはしばらく黙っていた。こんなときなんて言えばいいのだろう? ヴィクトルは、以前は結婚なんてまるで頭になかったのだ。クリストフと結婚について話したことさえ、いまは忘れているだろう。彼はそういったことに興味がなく、好みの型もなく、結婚なんて自分からいちばん遠いことだと思っていたのである。クリストフが口にするまでは発想すらなかったはずだ。それが、勇利と知り合ってたった一年で、こんなふうに思いつめたように「結婚しようと思う」などと言い出すようになってしまった。これがあのヴィクトル・ニキフォロフだろうか?
「……それはおめでとう」
クリストフはほほえんだ。
「俺もうれしいよ。式はいつ?」
「まだぜんぜん考えてないんだ。でもするんだ」
「そうか」
そのとき、ヴィクトルのポケットの中で携帯電話が音をたてた。彼はすばやくそれを取り出し、画面をみつめて、ぱっと顔を輝かせた。ヴィクトル、そういう表情できるんだね、とクリストフはおもしろかった。
「部屋へ戻るよ」
「どうぞ」
「じゃあ、クリス、また」
エレベータへ向かうヴィクトルの足取りは、スキップでも始めそうなくらいかるかった。クリストフはたまらなく可笑しかった。完全にクリストフの知らないヴィクトルだった。ヴィクトルは途中で足を止め、また何かメッセージが入ったのか、もう一度携帯電話を見た。そのときのとろけきった目ときたら、もう……。
クリストフはつぶやかずにはいられなかった。
「あれが、ヴィクトル・ニキフォロフか……」
0 notes
Text
{:en}Yo-Ho Brewing are one of Japan’s biggest craft beer makers and in 2019, they have become central to the debate about what craft beer is. In the USA, there are very clear, but loose, definitions as to what makes a craft beer brewer. The UK is looser still, with some unique ideas about how the beer is served. However, in Japan there are no clear definitions as to what constitutes craft beer.
However, the white elephant in the room can not be avoided – Kirin’s investment and purchase of Yo-Ho Brewing’s shares. In September 2014, Kirin took a 33% stake in Yo-Ho Brewing – at the time, an unheard-of idea. This stake also allowed Yo-Ho Brewing to buy Ginga Kogen Beer a few years later, further blurring the definitions of independence and craft beer in Japan.
While a little apprehensive to the line of questioning, and also the image of Kirin, Yo-Ho Brewing did go on to explain the reasoning for the selling of a one-third stake of the company to a macro brewery, especially with the connotations and negative PR it has brought. Yo-Ho Brewing are adamant that the only effect Kirin have had on them is to improve their supply chain, with no changes to ingredients or the processes used in making beer.
Kirin Beer have helped Yo-Ho Brewing Company expand out from supermarkets, with appearances and collaborations with Lawson’s convenience store, such as the Boku Beer, as well as using the Tap Marche system too. Yo-Ho Brewing are going to be fighting a battle with this concept; however, their clear answers and openness to the amount Kirin have bought into goes against some bigger, well-known, breweries, from both the USA and UK that hid investments from their customers.
Yo-Ho was founded in 1996 by Keiji Hoshino. He first experienced craft beer in the United States while he was an exchange student, and by comparison quickly realised how bad most Japanese beer was. At the time most Japanese breweries were focussing on German style beers of pilsners, weizens, and alts, so Hoshino started Yo-Ho with the aim of being more like an American one than a Japanese one. Since then, their focus has been entirely on ale-like beers (ones that are bottom-fermented), since their first batch in 1997.
At the time of the deregulation, many breweries’ focus was on tourists as an additional source of income, rather than actual beer drinkers. Yo-Ho Brewing focussed on the latter rather than the former, and since then, their beers have won numerous awards both in Japan as well as overseas.
Many of the brewery’s current styles were developed by former head brewer Toshi Ishii, who was one of the first Japanese brewers to work overseas, gaining experience at Stone Brewing company – known for their aggressive IPAs. Ishii moved to Guam to open up Ishii Brewing Company. While the brewery may not be as well known as his former place of employment, Yo-Ho Brewing do encourage their brewers to learn on the job and also support them in opening their own breweries.
Yo-Ho Brewing is situated at the base of Mt. Asama in Nagano, and the mountain area also lent some ideas to the naming of the brewery. In Japanese, the brewery is called ヤッホー (ya-hoo), which is the sound people make when calling out across the area – yodelling made its way to Japan, it seems.
Mt. Asama also plays a strong factor in the beers too, with its hard mountain water being used for the production of the beers. While it undergoes basic cleaning and filtration to ensure it is safe to drink, the water itself retains the majority of its minerals from the soil. It would be relatively easy for a brewery the size of Yo-Ho Brewing to use soft water; however, the hard water adds to the depth of flavours of the beer – adding a sense of terroir to the range.
Terroir, a word often used with wines in the past, has now found its way into the beer market. This has not missed a brewery the size of Yo-Ho Brewing. In their high-tech laboratory, the brewers can experiment with using a variety of adjuncts from the area ��� such as fruits, herbs, spices, and bonito flakes. To coincide with the new tax rules that the Japanese government has introduced, Yoho launched Sorry Umami IPA, a previously limited-edition beer featuring umami extracts from katsuobushi bonito flakes.
Yo-Ho Brewing’s most popular beer is Yona Yona Ale, an American Pale Ale with pronounced citrus hop aromas, which saw a renewal due to the appeal of American pales ales in 2017 – the first renewal in a lineup that stood the same for almost 20 years. Aooni (“Blue Demon”), a 7% India pale ale that was inspired by Ishii-san’s experience with Stone Brewing, and Suiyōbi no Neko, released in 2012, is a Belgian witbier, with 99% malt content. It translates as “Wednesday Cat” and was meant to be aimed towards women, under the guise of it being an easy-drinking beer. It was classified as a happōshu because of its orange peel and coriander seed flavorings, and remains so due to an ingredient used to control the beverage’s clarity under the old tax laws. However, since the change in laws in 2018, it’s interesting to note that the happoshu label on the side has changed. Suiyōbi no Neko is now sold as beer.
Yo-Ho Brewing also make a range of beers for the local Karuizawa area under the name Karuizawa Kogen Beer. There are four different types of brews on the regular roster: The clear and smooth “Wild Forest,” “National Trust,” which is made from black malt, “Seasonal,” which changes its flavor each year, and other limited production ales. Part of the revenue from sales is donated to two volunteer groups, “Karuizawa Wild Forest” and “Karuizawa National Trust,” which help preserve the beautiful nature of Karuizawa and enhance its appeal through various activities.
With the help of Wonder Table, a company that operates a variety of restaurants in Japan, Yo-Ho Brewing have also expanded out into taprooms, with the Yona Yona Beer Works brand. The bars follow a tried and tested method of design, with all 8 locations (at the time of writing) offering up the same food and beer on tap. While the bars serve the main range of Yo-Ho Brewing on tap, there are also seasonal specials on that are not sold in cans or in bottles.
While some craft beer fans choose not to drink Yo-Ho Brewing due to their links to the big macro company that is Kirin, what they did Yo-Ho Brewing’s influence on craft beer in Japan cannot be underestimated.{:}{:ja}ヤッホーブルーイングは日本最大のクラフトビールメーカーのひとつであり、2019年にはクラフトビールとは何かという議論中で中心となりました。 アメリカでは、クラフトビールを醸造するものについて、非常にはっきりしながらも、ゆるい定義があります。英国はまださらにゆるく、ビールの提供方法に関するいくつかのユニークなアイデアがあります。しかし、日本ではクラフトビールについて明確な定義はありません。
しかし、厄介な避けられない問題 – キリンの投資とヤッホーブルーイングの株の購入-があります。2014年9月, キリンはヤッホーブルーイングの33%の株を取得しました – その際、それは今までに聞いたことのないアイデアでした。
ヤッホーブルーイングは、質問の流れやキリンのイメージを少し気遣いながら、マイクロブルワリーでありながら1/3の資本をキリンに売却することの理由、特にネガティブなイメージを受けることに対し、意味を説明しました。彼らは、急成長により自社でのビール製造が需要に追い付かなくなった為、製造の一部委託を主な目的として提携しました。キリンとの資本提携により、ビール市場の一層の活性化を見込んでおり、ビールづくりにおけるプロセスや原材料には変化がないと頑なに主張しました。キリンビールはヤッホーがスーパーマーケットを起点に拡大する手助けしました。Tap Marcheシステムにもヤッホーブルーイングのビールを組み込んでいます。
ヤッホーは1996年に星野佳路によって設立されました。彼は交換留学生である間にアメリカで最初にクラフトビールを経験し、これまで日本で飲んだことのない味に驚きました。1994年の酒税法改正以前、 下面発酵の それ以来、彼らの焦点は1997年の彼らの最初のバッチ以来、完全にエールビール(上面 発酵されるもの)に集中しています。規制緩和の当時、多くのビール醸造所は、実際のビールを飲む人ではな��、追加の収入源として観光客に焦点を当てていました。ヤッホーブルーイングは後者ではなく前者に焦点を合わせ、それ以来、彼らのビールは国内外で数多くの賞を受賞してきました。
かつてヤッホーブルーイングに在籍していたブルワーに、石井敏氏がいます。海外の攻撃的なIPAで知られる、ストーンブルーイングで働いた経験を持ち、最初の日本の醸造業者の1人です。石井はグアムに引っ越して、石井醸造会社を設立しました。醸造所は彼の元職場ほど知られていないかもしれませんが、ヤッホーブルーイングで醸造ついて学び、醸造所を自分自身で開いた人物として挙げられます。 ヤッホーブルーイングは長野県の浅間山のふもとに位置しており、そこは醸造所の名前をつける際にアイデアを与えました。日本語では、この醸造所はヤッホー (ya-hoo)と呼ばれています。これは、人々が山々からふもとに呼びかける(=ヨーデリング)ときに言う言葉です。山にある醸造所で美味しいビールができたよ、とお客様に伝える意味合いを持たせています。
浅間山から湧き出る硬水は、ビールづくりにも大きな役目を果たしています。その水は飲む安全を確証するために、基本的な洗浄と濾過を受ける間、水自体は土からのミネラルの大部分を吸収します。ヤッホーブルーイングのサイズの醸造所にとっては、軟水を使用するのは比較的簡単です。しかし硬水はビールの味の深さを増します – テロワール感を追加します。
テロワールは、過去にワインでよく使われていた言葉で、今はビール市場でも使用されています。これはヤッホーブルーイングのサイズの醸造所を見逃していません。彼らのハイテク研究室では、醸造者は地域からの様々な補助剤を使うことで実験することができます – 果物、ハーブ、スパイス、そしてカツオフレークのようなものです。日本政府が導入した新しい税法と適合させるために、ヤッホーはかつお節からのうま味抽出物を特色とする以前の限定版ビール、SORRY UMAMI IPA を発売しました。 .
ヤッホーブルーイングの最も人気のあるビールは、2017年にリニューアルを行った、シトラスなホップアロマで知られるアメリカン・ペール・エール、よなよなエールです。- 約20年同じように並んでいたラインアップの初めの新調です。石井さんのストーンブルーイングでの経験にインスパイアされた7%の淡いエールであるインドの青鬼と 、2012年に発売された水曜日のネコは、99%のモルト含有量を持つベルギーのウィットビールです。それは「水曜日のネコ」と言い換えて、それが飲みやすいビールであることを訴え、女性をターゲットにしています。それはオレンジの皮とコリアンダーの種子の風味のために発泡酒として分類され、そして古い税法の下でも飲料の透明度を管理するために使用される成分のためにそのままそう分類されています。2018年に法律が変更されて、特定の副原料を5%までなら使用して良くなりましたが、製法の面などにいまだ制限があり、「水曜日のネコ」は麦芽使用比率が高いにも関わらず発泡酒として売られています。
ヤッホーブルーイングはまた、軽井沢高原ビールという名前で地元の軽井沢地域向けに様々なビールを製造しています。通常のロスターには4種類のビールがあります。ブラックモルトから作られた「ナショナルトラスト」、クリアで滑らかな「ワイルドフォレスト」、、季節限定などの限定生産エール。売上の一部は軽井沢の美しい自然を守り、様々な活動を通しそのアピールを行う「軽井沢ワイルドフォレスト」と「軽井沢ナショナルトラスト」の2つのボランティア団体に寄付されています。
ヤッホーブルーイングは、日本で様々なレストランを運営しているWonder Tableの助けを借りて、YONA YONA BEER WORKSという名のタップルームも展開しました。バーは試行錯誤してデザインされた方法に従い、(執筆時点で)8か所すべてでビールをタップで提供しています。バーはタップでヤッホーブルーイングの主な範囲を提供していますが、さらに缶やボトルで販売されていない季節限定の物も含め、常時10種以上を提供しています。
クラフトビールファンの中には、大手マクロ企業であるキリンとの関連性から、ヤッホーブルーイングを飲まないことを選ぶ人もいますが、ヤッホーブルーイングが日本のクラフトビールに与えた影響は過小評価できません。
{:}
Yo-Ho Brewing Interview・ヤッホーブルーイングインタビュー {:en}Yo-Ho Brewing are one of Japan’s biggest craft beer makers and in 2019, they have become central to the debate about what craft beer is.
0 notes
Text
7月から今日まで
久しぶりに忙しい内容の生放送。朝冷蔵庫に忘れ物をして幸先が悪い。雨宮さんに試食を丸投げしてディスプレイする。放送開始後生肉を切りにいかなくちゃならず、インカムから聞こえる縁起のいいめだかを紹介する中継を聞きながら「おめだか様の手も借りてえ・・・」と思う。めだかには手も足もないというのに。猫に助けを求める時点で相当てんてこ舞いなのに、めだか。まあなんとか破綻せずにすんだ。かなり危なかった。試食入れ終わったの10秒切ってた。相変わらず想像力がない。帰って役所に行くつもりだったけど結局寝てしまった。19時に起きてデニーズにいく。1時に帰宅。流石に疲れてフラフラで寝る。
___
ちょっと余裕ある時間に起きてステーキ丼食べる。堀井さんの担当回を少し見て家を出る。 JAFNA。川畑さん仕事早い時はちゃっちゃとやってくれるからってそんなトゲのある言い方しなくても。今日はまあ普通。そんなに早くは終わりません。昼飯は例によってはしご。5回連続。だあろう。隣の人が食べてたシュウマイがうまそう。次はだんだんとシュウマイかな。 なんだか酷く疲れてしまい帰ったら寝るなと思ったのでプロントに入る。が、wifiがなく結局飲んじゃう。
___
朝雨がすごかったから小田急でツイート検索したら積み残しが凄そうだったのでケイクスにメールして1時間余計に寝た。カレー食べて11時半くらいに電車乗って12時半とかに出社した。パン祭り今日だったのにおにぎり弁当買っちゃった。なんだかんだ結構食べちゃう。全部めちゃうまかった。ロブションのクリームパンすごい。今度人に買っていこう。体力がガーーっとなくなって大変だった。結構やばい気分だったけど下北で一龍食べてブルーマンデーでES書く。興が乗ってきて、いい感じでまとめることができた。なによりやりきったことで得体の知れないエネルギーを得た。22:50くらいまでいたけど0時前に帰ってきた。下北沢は近い。
___
朝起きて学校に行って証明書を発行して図書館��いって本を読もうと思っていたのに結局14時まで寝てしまった。背中に痛みを感じつつシャワーを浴びて代々木八幡に行く。月一の散髪。着く直前に清水さんから連絡が来ていることに気がつく。早稲田に移動。証明書を入れるクリアファイルを忘れてどうしようか迷ったけどお父さんは週末しかいないので発行することに。ついでに成績証明書も取っておいた。なにかに使う気がするので。図書館で『舞踏会に向かう三人の農夫』を借りて少し読む。どうやら舞踏会とは戦場のことらしい。19時に合流してピカソ。桃のサラダと2本目のワインが美味しかった。牧舎に行って藤田さんの誕生日に乾杯する。気にかけてくれていて嬉しい。
___
13時まで寝てしまう。お父さんがご飯に誘い出してくれた。ロイホでハンバーグ。 煙草の吸いすぎで胸が痛くてあんまり長くものごとを考えられない。 少ししてヤマザキに買い物に行く。そうめんをゆでて食べてしばらくしてからデニーズに行く。日記を書いている。このあと帰ってお風呂に入って寝る。
___
リハをやって本番をやる。古野さんが最後だったのにうまく感謝を伝えられなかった。頼りにされていたと思うし、つくしたいという気持ちがあった。いい経験だった。江ノ島に撮影に行く。しゅんじに手伝ってもらいながら二日間で5カット。満足。でも提出時に5カット”以上”で、テーマが『早稲田の光』であることに気づいてしまった。まあいいか。電車の乗り継ぎを間違えてしゅんじを1時間も待たせてしまった。ふつうにおちこんだ。 木金は銀座で事務。久保さんいないので好き勝手やった。でも仕事はほとんどきちんと終わらせた。ウーバーイーツを初めて使った。tosirou(85)がお届けしてくれた。ビッグマックセット。帰りにオールスター見たくて代々木上原のビアバー行って5千円も使ってしまう。でも秋山が松坂からホームラン打つところみれたからいいか。今日はプール行ってそうめん食べた。音楽の日とかいうテレビの歌番組で宇多田ヒカルを見る。今日も美しかった。
___
引越しを手伝う。12時に渋谷につけるように起きて家を出た。セブンイレブンでサンドイッチとコーヒーを食べて電車に乗ったらお腹が痛くなって新百合で降りた。間に合うかなと思っていたらやっぱ13:30と連絡があってこの感じ懐かしいなと思った。下北で立ち読みして100均でメジャーを買って改めて渋谷に向かう。井の頭線に新しいエスカレーターができている。結局14時前に集合して天下寿司にいく。美味しい。元祖より美味しいし値段もそんなにしないし閉店間際は安くなるらしいしいい。カーテンを買いベッドを物色してから無印へ。ベッドを決めてハンズで壁美人を買う。ニトリに戻って鏡を買って再び戻る。楽しみだなあこれからの人生と言った友達が眩しかった。おれは全然楽しみじゃない。正気を保つので必死だ。
___
俊二と早稲田に行って図書館とコンタクトセンター。ふたりでメルシーを食べる。別れて松の湯にいく。体重が70kgになっていて驚く。ゴトーでチーズケーキ食べて帰る。ダイエットだと思い夜はツナ缶とレタス。那須の話が動き出す。
___
金曜日の夜からリンクス同期7人で那須に旅行に行った。1日で先に東京に戻って新木場でceroのtrafficに。SPANKHAPPYに間に合うか危なかったけど大丈夫だった。完全に整った。帰りにコンビニで煙草を吸うこともなく、石鹸を買い足し忘れたことにも苛立たず。おおらかなこころを取り戻した。
___
9時台に起きて朝ごはんを食べる。昼まで洗濯をして12時半に正ちゃんへラーメン食べに行く。しょうゆ味玉。アイス食べてCS見る。ずっと後手。点差以上の差を感じた。
___
ファミマで肉まん食って夜はサガミで味噌うどん。怒りの葡萄上巻読み切ってコンビニでコーヒーとチョコ。まじでおもしろい。怒りの葡萄。文章全体が煌めいてる。
___
多摩川に行ってお昼を食べる。川沿いを歩く。狛江高校の女子陸上部がいる。硬式の少年野球がいる。小さい子供とその親がいる。女の人二人組がいる。洪水を伝える石碑を見つける。おれにも伝わったよ、と思う。トイレに行きたいのとゴミを捨てたいのとで駅に向かって歩く。結局改札内にしかトイレもゴミ箱もなかった。なんて不便なところなんだろう。駅でガーベラを、セブンでロックアイスを買って帰る。裏庭で焼き鳥をするというので鶏肉を切って串に刺す。串に食材を刺すことを串を打つという。ビール飲んで焼き鳥食べる。日本シリーズを最後まで見てコンビニに行く。帰ってきて風呂に入ってウイスキーを一杯だけ飲む。2時に寝る。
___
俺を漢字一文字で表すと瓦らしい。瓦斯の瓦。青い炎。採用。9時に起きて着替えてコンビニまで散歩。なんとか振り絞ってES書いて履歴書も書き直してギリギリで家出る。走る。間に合って面接。可愛くて愛想がいいけどペラい感じの女の子が受け付けてくれる。なんか小説に出てきそうな絵に描いたようなベンチャー企業の若い女の子だ。面接はけっこう芯食ったと思う。終わって駅前でサンドイッチとカフェオレ。煙草。帰って授業の準備と授業。面接と演習で脳が興奮状態にある。
___
リハ。ADさんが有能でとても助かる。パターンいじってただけ。本屋とベローチェで時間潰す。ベローチェにZAZYがいた。魚金で飲み会。楽しかった。
___
本番。飯田さんへの手元大根の打ち込み浅かった。記憶ねえ。こういうとこだ。 オファーボックス整備。めっちゃオファーくる。去年の今頃からやっとけばよかった。
___
12時半まで寝てから掃除と洗濯をして、ツタヤに行って帰りにコンビニでタバコを吸ってあとは部屋で音楽を聴いたりSNSをみていた。今日は129円しか使わなかった。これで2千円浮かしたのでもう本が買える。 年金の督促が来てしまったので遡って猶予できるか確認しにいかなくちゃいけない。でもこれで最大でも九月までしか猶予にならないことは確実になったから少なくとも半年分は月16000円払わなくちゃならない。ばりキツイ。
___
11時前に起きてご飯を食べる。宇多田ヒカルのプロフェッショナルを見てからまほろ駅前狂騒曲をみる。真実は他者にはない。世界にもない。自分にしかない。思い出す作業に近い。なにか引っかかったら引き寄せくる。まほろは終盤急に大味になっていまいちだった。あのぬるっとした緊張感のなさと進行している狂気のギャップが悪い方にでてた。でも作品全体に横たわる空気はとても好きだ。映画終わってちょうどM-1始まったから見る。ここ3年はとても刺激的で、しかも笑いを通してなにか世の中の倫理観とか空気感がいい方向に転がっているような感覚がある。平場の志らくほんと嫌いなんだけど絶対上沼殺すマンになっててよかった。塙富澤志らくは審査基準を繰り返し述べていたのが番組全体に安定感と信頼感を与える結果になっていてとてもよかった。霜降り明星の漫才はボケ単体でもパワーがあるのにツッコミが全ワードハマっててすごかった。久々に背中痛くなるくらい笑った。92年93年生まれらしくて嬉しくなった。和牛が準優勝3回目と聞いて聖光学院かよと思った。ジャルジャル。もうジャルジャルが2本やっただけでいかにいい大会だったかということがわかる。その上で3位。いい塩梅。絶対結果を出そうとして、その過程についてまでも理想を描いて、突き詰めて、あの組み順で決勝に残って、ウケて、あの2組にああやって負けて、エンディングのあの表情。もう充分すぎるくらい見せてくれた。あなたたちが俺たちの幸福を願ってることは充分伝わった。あしたからも楽しく、幸せに、全員連れて行く漫才をつづけてください。ありがとう。
___
新バイトへの説明と本番、JAFNA。眠すぎて市民センターいけなかった。友達から結婚の報告を受ける。おめでたい。すすすっと生きていくのに全然悲壮感やさみしさを感じさせないコミーさん好き。
___
面接して面接。1本目はとてもうまく行ってその場で内定がでた。変に受け流しても体に良くない気がしたのでじんわり喜んだ。でも次があったので脚はわりと高速で回転させた。2本目は大失敗した。面接官の第一声を聞いた瞬間にこいつ冷たいな、見下してんな、しゃべりたくねえなと思った。終始全然響いてない感じで、締めの言葉が御足労ありがとうございましただったんでもう完全に終わったと思った。やべえどうしよう、まじでエンジニアか。これどっちだ?悲しいのか?迷いなくなってむしろいいのか?んんん??となりつつタリーズでなんかピザクロワッサンみたいなのとチャイミルクティー、煙草。ぼーっとして、ぼーっとしながらも猛烈な勢いでなんJ読み漁るいつものぼーっとするをして、ながらご飯、みたいなことだけど、して、体はねむいし頭は混乱してるから首がくんして寝ようとするけど次の瞬間には巨人のプロテクトリスト予想見て、いやどうせ若手が漏れてる、とか思った瞬間にはガクン。してるうちにメール。え、うわっ3時間で来た。常にお互い即レスという12月採用あるある第2位をやりながらここまできたもののさすがに今回はひらけず。再び広島スレを回遊したのち急にプロ野球が色褪せて見えたので、やっぱ一番面白いの自分の人生か、と思いつつ開いたら通ってて草。通ってて草。なにがあった?の答え一発目として上出来なやつだった。草ってリアルで使う人ほんと無理だったんだけどこの1年でちょっと大丈夫になった。3時間ふらふらだったけどまた別の種類のフラフラがきてフらふラだった。でも迷いは晴れない、とりあえず脳内に『まだ内定じゃない』をかけて戦闘モードを呼び戻す。
___
最後のJAFNA。文書保存箱の組み立て方がわかんなくて、何はともあれ検索だと思ったら動画でてきて5秒で解決した。10分くらいウンウン言ってたのに。ファイルの整理や会員向けの資料の封書をしているうちにお昼に。最後なので事務局長とお食事。勤務初日に行ったイタリアンと同じビルにある和食屋さんに行った。目の前の壁に白鵬の手型が飾ってあってベタだなと思った。なんかふつうにハンバーグとステーキ重で迷っていていや和食和食と穴子重にした。穴子って銀座の和食屋でのランチとして一番ちょうどいい気がした。うなぎだと鰻屋のパチモンみたいになるし。美味しかった。なんで留年したのかとかどんなバイトしてたのかとかを話した。通常初日にする話。一応就活終わりましたと報告しておめでとうな空気にしておいた。就留中社会性を保つために始めたバイト先が、まさか解散し、まさか最終勤務日の前日に内定をもらうとは、なかなかかけない筋じゃないですか、と言おうと思ったけど何かの拍子に忘れ、今思い出し、言わなくてよかったと思う。席を立つ時「ここに白鵬の手型あるの気づいてましたか」と聞いたら見るなり「思ったより小さいのね」と言うので笑ってしまった。小ささに気づくの早っ。確かに小さい気がするけど。驚きの焦点の切り替わり方が早すぎる。バナナジュースコリドールに移動。レトロポップ&たしかな品質に久保さんも気に入ってくれたようでよかった。今日はベースを豆乳に変えてレモンとナッツを追加した。めっちゃうまい。またポイントカード作るの忘れた。午後は封書を頑張る。60ちょい。また盛大に紙を無駄にしながらも印刷したりなんだり。春にやってたら絶対おわんなかったし間違いまくりだったけど今はわりとふつうなのでふつうに頭が働いていい感じにミスを未然に修正してくれた。おれは間違えるけど脳みそが助けてくれる感じがした。無意識がのびのびしてるのがちょうどいい時
___
9時に起きてラグビー。7時に兵藤から10時集合との連絡あったようだけどもう間に合わないと連絡。インスタみるも兵藤の気配がないのでたぶん朝まで起きてて今寝てる。三ツ沢上町から球技場まで歩く。とても立派な公園。球技場は球技場だけあって臨場感すごい。負けちゃった。けど生ラグビーはとても良いもの。早明戦以来だった。あれも冬。冬の晴れた日に熱く美しいスポーツを見るというのはなかなかいいものです。試合後横浜で飲む。みなさん暖かく受け入れてくれてありがたかった。
___
吉祥寺でワカサギ会議。ワカサギを釣りにくことが決まった。長野に。久しぶりに井の頭公園にいく。大道芸人がとてもすごくて見いってしまった。その後ローグでキルケニーとなんかIPAを飲む。トラファルガーより品があって気分が出る。店内禁煙になっていたのもいい判断なように思う。お釣りが合わないからとたくとにスタバでチャイラテを買ってもらう。甘いの忘れていた。全然美味しくない。帰宅後、ご飯がなんにもないので腹ペコの中日記を書く。チャイへの後悔と空腹からナイルレストランを思い出して無性に食べたくな���。
___
リハ。助手さんが有能で助かるというかおれが無能すぎて申し訳ない。でもなんとかなりそう。
___
本番。まあなんとかなる。もっと時間をかけて準備しなくては。やっぱりSEは向いてない、というか嫌、やりたくない、のかもしれないと思い始める。まさきくんとよっちゃんと会う。よしひろに彼女ができたの本当だった。なんだか胸が熱くなった。相手と自分にきちんと向き合って常によしひろにとって最良の選択肢を選んでほしいと願うし、そのための力になりたいと思った。
___
内定先の選定で無間地獄に落ちる。双六のルートを限界まで読み込んだところで結局ルーレット次第なので意味ない。意味ないことを意味ないで終わらせられなくてずっと困り続けてる。
___
本番。朝、あっきーとあめみーさん結婚の報を知りはい?となる。目が覚める。以降いつになく調子がいい。つつがなく進む。結構見えてる感じ。一回インカム聞き逃して変な感じになったけど。サンドラ・ブロックがキアヌ・リーブス好きだったと告白したという記事で、当時サンドラはキアヌの顔を見るとあはははってなっちゃうから真剣になるのが大変だったと書かれていて、その好きのこぼれ方はとてもいいなと思った。
___
9時に起きて10時から授業。途中11時からのも頼まれて12時に部屋に戻る。4時まで何をしようかと思っていると1時からもと言われて結局3時前にコメダに。グラコロバーガーとたっぷりウインナーコーヒー。おいしい。インヴィジブルを読む。佳境に入る。こういう視点の切り替えとても好きだ。夜はセブンの肉じゃがを2パック買ってきて食べた。美味しい。なんなら家のより塩分控えめでいいんじゃないかとすら思う。Spotifyはじめてみたけどとてもいい。
___
9:30に起きて10時から授業。一コマやって夕方まで間があったので下北へ服を買いに行く。せっかくなので一龍納めする。奥のほうに常連がいていつもよりずいぶんにぎやかだった。なんか年末っぽい。一番盛り上がって最古参と思われたおじさんが実は初めての来店だったらしく他の客にひかれていた。4時に帰宅。夕飯の準備をしてから2コマ。終わって炊事。ニラとケールと豚肉と卵の炒め物。ネギと里芋がいつのまにかお好み焼きのタネにされていたので味噌汁はインスタントにした。
___
インターン先に1ヶ月ぶりに出勤。新オフィスめっちゃ綺麗で笑ってしまった。編集部のみなさまに挨拶。なんだかんだ可愛がってもらってありがたいことです。鈴木くんと目黒。落ち着いたしいろいろ書こうねという話をする。なぜかダーツへ。楽しい。
___
昼飯に藤田へ。鴨南蛮。この商店街もそろそろ建て替えらしく西側はもう取り壊されたらしい。よく通った駄菓子屋俺たちのサンケイこと三景も閉まったらしい。ドキュメント72時間の年末スペシャルを見て泣いたりウンウン唸ったりする。デパート閉店の回が特によかった。6時ごろ出て下北で時間潰す。山角納めしようと思ったらすでにお納まりになっていた。仕方がないからひとりでジンギスカンを食べる。今ブルーマンデーでこれを書いていてこのあと渋谷に行く。
20181229
0 notes