#東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった
Photo

😙✨ 新刊の紹介ですー🥹 『東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった!』 ムギタロー著 ✨✨✨✨✨✨✨ イラストたくさん描いたよ😃 国とお金のこと、貿易のこと、などなど、イラストと図解たっぷりのフルカラーの内容です😌✏️ 本屋さんで探してみてね✨ #東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった #ムギタロー #経済#経済勉強 @sanctuary_books . #harupei#ハルペイ#doodle#draw#drawing#illustrator#illustration#japan#絵#雑貨#湘南#イラスト#イラストレーター#插畫#插畫家#ゆるい#茅ヶ崎 https://www.instagram.com/p/ChRq92gvLXo/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった#ムギタロー#経済#経済勉強#harupei#ハルペイ#doodle#draw#drawing#illustrator#illustration#japan#絵#雑貨#湘南#イラスト#イラストレーター#插畫#插畫家#ゆるい#茅ヶ崎
1 note
·
View note
Text
2022年12月9日

田中雄大選手 ブラウブリッツ秋田より完全移籍加入のお知らせ

運転60年超の原発、世界で実例なし 設計時の耐用年数は40年 配管破れ、腐食で穴...トラブル続発(東京新聞)
8日の経済産業省の有識者会議で議論を終えた原発活用の行動指針案は、運転期間の制限は維持した上で「最長60年」との現行規定を超える運転を可能にし、将来的な上限撤廃も視野に入れる。しかし、原発が60年を超えて運転した実例は、世界中に一つもない。国内では設備劣化によるトラブルが相次ぎ、原子力規制委員会も「未到の領域」の規制に手間取っている。(増井のぞみ)

国際原子力機関(IAEA)によると、既に廃炉になった原発を含め、世界最長の運転期間はインドのタラプール原発1、2号機の53年1カ月間。同原発から約1カ月遅れで運転を始めた米国のナインマイルポイント1号機とスイスのベツナウ1号機が続く。4基とも現役だ。
米国も日本と同じく運転期間を40年と規定するが、規制当局の審査をクリアすれば20年間の延長が可能で、延長回数に制限はない。80年運転を認められた原発も6基ある。英国とフランスは運転期間に上限はなく、10年ごとの審査が義務付けられている。
ただ、多くの原発は設計時、耐用年数を40年間と想定して造られた。老朽化が進むと維持管理コストも高くなり、事業者が長期運転よりも廃炉を選択するケースが多いとみられる。
国内では40年に満たない原発でも、劣化によるトラブルが起きている。
運転年数37年の関西電力高浜3、4号機(福井県)は2018年以降、原子炉につながる蒸気発生器内に長年の運転で鉄さびの薄片がたまり、配管に当たって傷つけるトラブルが相次ぐ。定期点検で6回も確認され、蒸気発生器を洗浄しても再発した。

高浜原発4号機の蒸気発生器内の配管(右下)に刺さった鉄さびの薄片(中央の三角形)=福井県で(関西電力提供)
さらに深刻なのは、点検漏れだ。原発の部品数は約1000万点に上るとされ、見落としのリスクはつきまとう。04年には、運転年数が30年に満たない美浜3号機で、点検リストから漏れて一度も確かめられなかった配管が経年劣化で薄くなって破れ、熱水と蒸気が噴出して5人が死亡、6人が重傷を負った。
東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)では、福島第一原発事故後まもなく停止した7号機タービン建屋の配管が11年間点検されず、腐食で穴が開いたことが今年10月に判明した。
井野博満・東京大名誉教授(金属材料学)は「劣化状況を調べる超音波検査は、配管の陰では測定が難しい。長期運転で劣化が進むと、点検漏れした時のリスクが増し、重大な事故につながる」と警鐘を鳴らす。

運転延長の可否を安全性の側面から審査する規制委は、60年超の原発をどのように規制するのかについて、具体策の検討を始められないでいる。
大きなハードルとなっているのは、原子炉が実際にどう劣化していくのか、データが不足していることだ。運転延長の審査で先行している米国とは、劣化具合のとらえ方が異なるという。山中伸介委員長は記者会見で「(60年超は)未知の領域。日本独自のルールをつくる必要がある」と、検討の難しさを認める。
規制が不透明なまま、60年超を可能にする仕組みだけが先行していく。井野氏は強調する。「日本は地震が多く、人口密度も高い。外国とは状況が違う。原発の運転は設計目安の40年を守るべきだ」

ベルギー、原子炉稼働10年延長で仏エンジーと合意(ロイター 2023年1月10日)
[ブリュッセル 9日 ロイター] - ベルギーのデクロー首相は9日、国内の原子炉2基(ドエル4号機とティアンジュ3号機)について、稼働時期を10年延長することでフランス電力大手エンジーと合意に達したと明らかにした。2025年に計画していた脱原発は、ロシアのウクライナ侵攻を受けたエネルギー戦略の変更により、覆されることとなった。
2機はベルギーの原子炉7基のうち、1985年に稼働を開始した最新のもの。25年に恒久的に停止する予定だったが、今回の合意を受けて必要な作業を行った後に26年11月に再稼働し、そこから10年間稼働を続けることとなった。
デクロー首相は閣議後の記者会見で、「稼働延長は、エネルギー安全保障のために極めて需要だ」と訴えた。ベルギーは、脱原発に伴い天然ガス依存を増やす計画だったが、ウクライナ侵攻を受けて方針の変更を余儀なくされた。
ベルギーの電力網運営会社は、2基の稼働を延長しなければ、26年の冬から27年にかけ、大幅な電力不足に直面すると警告していた。
ティアンジュ3号機は、昨年にすでに稼働を停止。稼働中の6基も、25年に停止の予定だった。
世界原子力協会によると、6基の発電容量は500万キロワットと、全体のほぼ5割を占める。
ファンデルストラーテン・エネルギー相によると、延長する2基は、政府とエンジーが折半出資する合弁企業が運営するという。

麻生氏「原発で死亡事故はゼロ」 飯塚市の会合で発言(西日本新聞 2023年1月17日)
自民党の麻生太郎副総裁は15日、福岡県飯塚市であった国政報告会で「原発で死亡事故が起きた例がどれくらいあるか調べてみたが、ゼロです」と述べた。関西電力美浜原発(福井県)で計11人が死傷した蒸気噴出事故などが起きており、発言の真意を問う声が上がりそうだ。
麻生氏は、国政課題の一つとしてエネルギー問題を挙げ、太陽光などの再生可能エネルギーは安定的な供給が難しいと指摘。その上で「(原子力は)最も安くて安全。原子力と原子爆弾の区別がついていない人もおられ、原発は危ないと言う人もいる」として、原発の活用を訴える中で「事故ゼロ」に言及した。
2004年8月の美浜の事故では、蒸気を浴びた点検準備中の作業員5人が死亡、6人が重軽傷を負った。東京電力福島第1原発事故では、収束作業に従事していた男性が肺がんを発症し死亡。その後、労災認定されている。(坂井彰太、坂本公司)

その原発は安全か、温暖化との闘いが耐用年数超える長期稼働を促す(ブルームバーグ 2023年1月26日)
カーボンフリー発電の魅力が一段と高まっている。二酸化炭素(CO2)排出の削減と気候変動対策の目標達成に必死で取り組む各国は、伝統的な化石燃料の不足にも直面。こうした矛盾した状況で導き出された回答は、原子炉の想定を超える長期稼働だ。
実際どれくらい長期にわたり、原子炉が運転され続けるのか。多くの原子炉が一般的な耐用年数である40年間を大きく超えて稼働し続ける方向だ。一部の原子炉については最長80年間の稼働を探るという動きもある。100年にわたり発電し続けることが可能かという研究すら行われ始めている。
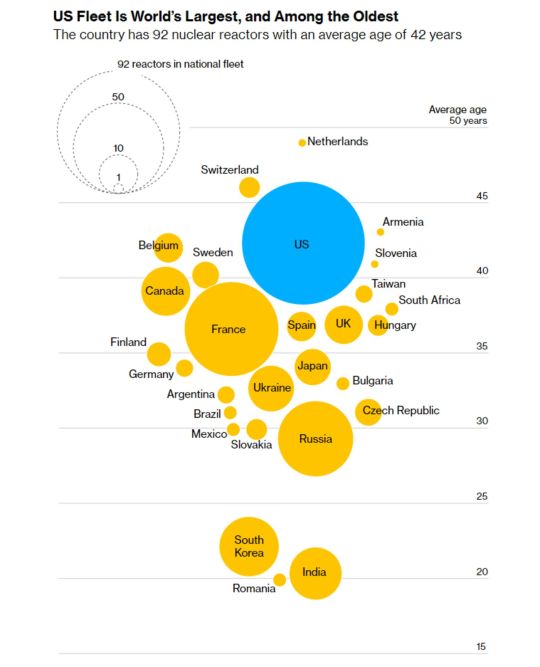
2030年までに世界で現在稼働している原子炉の3分の2が、設計または認可されていたよりも長期にわたり運転を続けることになる。
「これほど長期に及ぶ稼働は見込まれていなかった。100年前にできた原子炉の隣に住みたいとは思わないだろう」とブルーバーグNEFの原子力担当主任アナリスト、クリス・ガドムスキ氏は言う。米国人の平均寿命は77年だが、一部原子炉の一生はそれより長くなる。
リスク評価
数年前であれば、1世紀前に建設された原子炉での発電というのは考えられなかった。だが、米国と欧州連合(EU)は30年までに温室効果ガスの排出量を少なくとも50%減らすと表明。70カ国余りが炭素排出「ネットゼロ」の目標を掲げている。こうした状況で、早期の目標達成に向けた具体策を見いだすよう各国・地域に対する圧力は強まりつつある。世界はコントロール不能な気候変動と自然災害に見舞われ、CO2を排出しない電子力発電のリスク評価が喫緊の課題となっている。
英国は現在、発電全体の約15%を原子力で賄うが、50年までにこの比率を25%にまで引き上げたい考えだ。米国は老朽化が進む原子炉を維持するため60億ドル(約7800億円)を原子力関連の補助金に投じている。

フランスは原子力発電所を新設する計画。ベルギーやフィンランド、スロバキアなどは既存原発の延命を図る。ドイツは22年に閉鎖予定だった原子炉を使い続けており、11年の東日本大震災で東京電力福島第一原発の事故を起こした日本ですら原発の運転期間延長に向けて動いている。
過去数十年にわたり原発への批判や反対は、特に欧米で強く、閉鎖を余儀なくされた原子炉も多い。業界からの投資も細り、新規の原発建設は減少。今すぐ着工したとしても、大規模な原発建設には10年以上を要することが多々あり、30年までの炭素排出削減目標の達成には寄与しない。つまり原子力発電の復権は、老朽化しつつある原子炉なしではあり得ないということだ。
稼働の長期化に伴う最大のリスクは明白だ。老朽化が進む原発が適切に保守・修理されていない場合、事故の危険性は高くなる。公平を期して言えば、第2次世界大戦終結から10年の間に商業運転が始まった原子炉の事故はごくわずかしかない。だが、可能性が極めて低いとしても、いったん原発事故が起きれば大惨事となる恐れがある。

1986年のチェルノブイリ原発事故では直接的に数十人が死亡し、何百万人もの人々ががんの原因になり得る放射線にさらされた。ニューヨーク市の3倍という広大な土地が汚染され、何世紀にもわたりそこに住むことはできない。その25年後に起きた福島第一原発事故では10万人余りが避難を強いられた。復興には長い時間と巨額の費用が必要となる。
温暖化との闘い
原子炉運転の長期化は、未踏の領域だ。そのことはまた、安全性を巡り激しい議論が交わされてきた原子力発電のリスクを一段と高めることを意味する。
原子炉から出る廃棄物を処理する施設に絡むリスクもある。世界初の原子炉稼働から約70年たつが、多くの国が危険な放射能を何千年にもわたり帯び続ける廃棄物の最終処分場をまだ建設していない。
これら全てが、最近まで原子力発電が着実に減ってきた理由を説明している。90年代半ばには世界の発電の約18%が原子力だったが、今では10%程度だ。

ロシアがウクライナで2022年に始めた戦争が長期化し、その影響も顕著だ。原子力エネルギーを巡り激しい論争が続いていたドイツは、ロシアからの天然ガス供給が限定され一段と厳しい状況に追い込まれている。
米カリフォルニア州で昨年夏に起きた停電や欧州のエネルギー価格急騰で見られたように、風力・太陽光・水力発電は扱いにくい。こうした再生可能エネルギーと違い、原子力の有用性の一つは天候に左右されず夜間ですら24時間発電し続けることが可能なことだ。
専門家の多くは、原子力発電を増やさない限り50年までのネットゼロ目標の達成はほぼ不可能だとみている。低炭素電源は21年に世界の電力供給の約40%を占めたが、その比率は20年前と比べわずか4ポイント程度の上昇に過ぎない。再生可能エネルギーが普及したものの、原子力が減り、一部はガスプラントに代替されたが炭素排出を増やした。
国際原子力機関(IAEA)のグロッシ事務局長は長期稼働に耐える原子炉について、「地球温暖化との闘いを陰で支えるヒーロー」だと述べている。

【本日(12/9)の広島県内の感染状況】(広島県)
新型コロナ 広島県 3549人が感染 1人が死亡 9日発表(NHKニュース)
広島県では9日、新たに3549人が新型コロナウイルスに感染されていることが確認され、1人が亡くなったと発表されました。
感染が確認されたのは、広島市で1388人、福山市で734人、呉市で299人、東広島市で213人、尾道市で193人、三原市で130人、廿日市市で127人、府中町で70人、庄原市で61人、三次市で55人、府中市で52人、安芸高田市で33人、海田町で29人、竹原市と世羅町で28人、大竹市と江田島市で22人、熊野町で17人、神石高原町で12人、坂町と安芸太田町、それに北広島町で11人、大崎上島町で3人のあわせて3549人でした。
1週間前の金曜日より773人多く、県内での感染確認はのべ56万5591人となりました。
また県内では、患者1人が亡くなったと発表されました。県内で新型コロナウイルスに感染し、その後、死亡した人は900人となりました。
【新型コロナ 厚労省まとめ】228人死亡 12万7090人感染 (9日)(NHKニュース)
厚生労働省によりますと、9日発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め12万7090人となっています。また国内で亡くなった人は228人で、累計5万1290人となっています。
東京都 新型コロナ22人死亡 1万3556人感染確認 前週比2312人増(NHKニュース)
大阪府 新型コロナ 9人死亡 新たに7076人感染確認(NHKニュース)大阪府内の感染者の累計は234万2193人となりました。府内で感染して亡くなった人は合わせて6811人となっています。
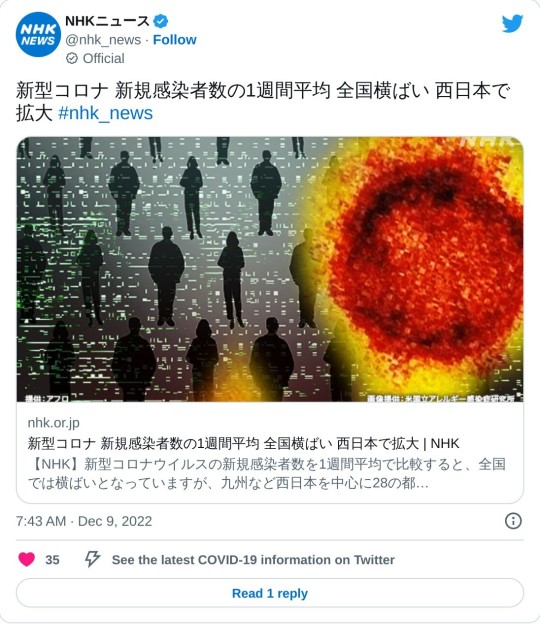
新型コロナ 新規感染者数の1週間平均 全国横ばい 西日本で拡大(NHKニュース)
新型コロナウイルスの新規感染者数を1週間平均で比較すると、全国では横ばいとなっていますが、九州など西日本を中心に28の都府県では前の週より多くなっています。
NHKは厚生労働省が発表した感染者数をもとに、1週間平均での新規感染者数の傾向について前の週と比較してまとめました。
全国 全国では、▽先月10日までの1週間では前の週に比べて1.30倍、▽先月17日は1.24倍、▽先月24日は1.08倍、▽今月1日は1.27倍と7週連続で増加が続いていましたが、▽8日まででは1.00倍(1.003倍)と、ほぼ横ばいとなり、一日当たりの全国の平均の新規感染者数はおよそ11万1000人となっています。
一方、九州や四国、関西など西日本を中心に28の都府県では前の週より多くなっていて、▽宮崎県では1.24倍、▽熊本県では1.19倍、▽愛媛県と兵庫県では1.17倍などと増加の幅が比較的大きくなっています。
一方で、▽北海道では0.79倍、▽山形県と長野県では0.85倍、▽岩手県では0.87倍などと、北海道や東北などでは減少傾向が見られています。
宮城県 人口当たりの感染者数が最も多いのは宮城県で、▽先月24日までの1週間は前の週の1.18倍、▽今月1日は1.17倍と7週連続で増加が続いていましたが、▽8日まででは0.93倍と減少に転じています。
一日当たりの新規感染者数はおよそ3285人で、人口10万当たりの感染者数は999.05人となっています。
1都3県
【東京都】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.06倍▽今月1日は1.37倍▽8日まででは1.01倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ1万2137人となっています。
【神奈川県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.10倍▽今月1日は1.26倍▽8日まででは1.02倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ7274人となっています。
【埼玉県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.07倍▽今月1日は1.34倍▽8日まででは1.07倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ6421人となっています。
【千葉県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.14倍▽今月1日は1.44倍▽8日まででは1.02倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ5102人となっています。
関西
【大阪府】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.10倍▽今月1日は1.29倍▽8日まででは1.08倍で、一日当たりの新規感染者数は5779人となっています。
【京都府】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.14倍、▽今月1日は1.40倍▽8日まででは1.09倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ1785人となっています。
【兵庫県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.10倍、▽今月1日は1.31倍、▽8日まででは1.17倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ3574人となっています。
東海
【愛知県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.13倍▽今月1日は1.36倍▽8日まででは0.94倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ6940人となっています。
【岐阜県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.06倍▽今月1日は1.33倍▽8日まででは0.97倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ2226人となっています。
【三重県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.22倍▽今月1日は1.13倍▽8日まででは1.09倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ1535人となっています。
その他の地域
【北海道】 ▽先月24日までの1週間は前の週の0.93倍▽今月1日は1.03倍▽8日までは0.79倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ6311人となっています。
【広島県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.15倍▽今月1日は1.02倍▽8日まででは1.08倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ3037人となっています。
【福岡県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.06倍▽今月1日は1.41倍▽8日まででは1.16倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ3581人となっています。
【沖縄県】 ▽先月24日までの1週間は前の週の1.17倍▽今月1日は1.47倍▽8日まででは1.15倍で、一日当たりの新規感染者数はおよそ579人となっています。
東邦大 舘田教授「変異ウイルスへの置き換わり 感染状況注視」
新型コロナウイルス対策にあたる政府の分科会のメンバーで、東邦大学の舘田一博教授は現在の感染状況について「一時期、増加傾向が目立っていた北海道や東北、北陸では、新規感染者数が前の週を下回った一方、九州など西日本では前の週を上回り、地域差がはっきり出ている。年末年始にかけて感染状況が各地域でどう推移するか、見ていく必要がある」と評価しています。
そのうえで「いま主流となっているオミクロン株の『BA.5』だけなら爆発的な感染拡大につながらないかもしれないが、別の『BQ.1』系統の新たな変異ウイルスへの置き換わりが、急激な感染拡大のリスクとなっている。『BQ.1』は東京都内などで徐々に増えていることが確認され、今月末から年明けにかけて、本格的に置き換わっていくとみられるので、そのときに感染状況がどうなるか注視しなければならない」と指摘しました。
そして「1日の感染者数は第7波のピーク時に比べてまだ少ないが、医療の現場では病床の使用率が高まって、院内感染も発生していると報告されていて、この状況が続くだけでもかなりの負荷となる。また、死亡者が1日に200人を超える日が続き、感染拡大が進めば、これまでのピークを超えるペースで増加すると見込まれる。高齢者や基礎疾患がある人はワクチンを打っていても、一定の頻度で重症化したり、死亡したりしてしまうので、年末年始の帰省などで、高齢者と会う機会がある人は、若い人であっても、▽ワクチンを接種すること、▽事前に検査を行うこと、▽体調管理の徹底、▽寒くても換気の徹底など基本的な感染対策を行い、感染を広げないような行動が重要だ」と話しています。
一方で新型コロナウイルスの感染症法上の扱いの見直しをめぐり、国は判断にあたって考慮する要素として▽「病原性」▽「感染力」▽「今後の変異の可能性」を挙げています。
これについて舘田教授は「新型コロナはワクチンや治療薬が普及し、検査キットも薬局やオンラインなどで購入できるようになり、死亡率はおよそ0.1%とインフルエンザに近づいているが、感染対策が徹底され、インフルエンザの感染者がほぼ出なくなった状況でも、コロナは広がり、感染力が高いウイルスであることは確かだ。しかし、全国で1年間に2000万人以上の感染が確認される中、『2類相当』の位置づけで就業制限や入院勧告、外出の自粛要請を続けたり、一部の医療機関しか診療できなかったりする状況が続くのは現実的ではない。『5類相当』への移行を目指す上で、医療だけなく、社会経済への影響も含めて議論を進めることが大事だ」と話していました。
0 notes
Text
日本に「見えない戦争」を仕掛け始めた中国
日本は「全政府対応型アプローチ」で備えよ
2020.11.16(月)
樋口 譲次
「新しい戦争」の形
21世紀の戦争は、国家が堂々と紛争の解決を軍事的手段に訴える分かりやすい従来型の戦争から、知らないうちに始まっている外形上「戦争に見えない戦争」へと形を変えている。
この「新しい戦争」の形を初めて実戦に採り入れたのはロシアである。
その実戦とは、2014年のロシアのクリミア半島併合と東部ウクライナへの軍事介入であり、西側では「ハイブリッド戦」と呼んでいる。
ハイブリッド戦は、『防衛白書』(令和2年版)によると下記のように説明されている。
軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にした現状変更の手法であり、このような手法は、相手方に軍事面にとどまらない複雑な対応を強いることになります。
例えば、国籍を隠した不明部隊を用いた作戦、サイバー攻撃による通信・重要インフラの妨害、インターネットやメディアを通じた偽情報の流布などによる影響工作を複合的に用いた手法が、「ハイブリッド戦」に該当すると考えています。
このような手法は、外形上、「武力の行使」と明確には認定しがたい手段をとることにより、軍の初動対応を遅らせるなど相手方の対応を困難なものにするとともに、���国の関与を否定するねらいがあるとの指摘もあります。
顕在化する国家間の競争の一環として、「ハイブリッド戦」を含む多様な手段により、グレーゾーン事態(純然たる平時でも有事でもない幅広い状況)が長期にわたり継続する傾向にあります。(括弧は筆者)
東西冷戦が終結して2000年代に入り、複数の旧ソ連邦国家で独裁的政権の交代を求めて民主化と自由を渇望する運動が起こった。
非暴力の象徴として花や色の名を冠した、グルジア(ジョージア)のバラ革命(2003年)、ウクライナのオレンジ革命(2004年)、キルギスのチューリップ革命(2005年)などがそれである。
また、アラブ諸国においても「アラブの春」と呼ばれた同様の運動が起こり、2010年から2011年にかけてチュニジアの民衆が蜂起した「ジャスミン革命」を発端として、エジプト、リビア、イエメンなどでも独裁・腐敗の政権が倒された。
シリアでは激しい内戦が最近まで続いている。
これらの民主化と自由を求める運動によって、かつての衛星国を失ったロシアでは、本運動は米国や欧州などの西側が介入・扇動し、旧ソ連邦国家やアラブ諸国住民の「抗議ポテンシャル」を活性化させた意図的な体制転覆あるいは陰謀であり、一種の戦争であるとの見方が強まった。
そして、ロシアもまた、このような脅威に晒されているとの認識が高まり、安全保障・国防政策上の中心的テーマとして急浮上したのである。
それを背景として、2013年2月に発表されたのが、ロシア連邦軍の制服組トップであるヴァレリー・ゲラシモフ参謀総長による「予測における科学の価値」(『軍需産業クーリエ』、2013年2月27日付)というタイトルの論文である。
ゲラシモフ論文は、「21世紀には近代的な戦争のモデルが通用しなくなり、戦争は平時とも有事ともつかない状態で進む。戦争の手段としては、軍事的手段だけでなく非軍事的手段の役割が増加しており、政治・経済・情報・人道上の措置によって敵国住民の「抗議ポテンシャル」を活性化することが行われる」と述べている。
そして、ゲラシモフ論文による21世紀の戦争では、非軍事的手段と軍事的手段との比率を4対1とし、非軍事的手段の役割の大きさが強調されている。
そのように、ゲラシモフは「戦争のルールが変わった」と指摘しており、いわば「新しい戦争」の到来を告げたのである。
その後、2014年にウラジーミル・プーチン大統領が承認した「ロシア連邦軍事ドクトリン」は、前年のゲラシモフ論文の考え方を踏まえて作成されたとみられている。
ロシアの2014軍事ドクトリンでは、政治的、外交的、法的、経済的、情報その他の非攻撃的性格の手段を使用する可能性が尽きた場合のみ、自国およびその同盟国の利益のために軍事的手段を行使するとの原則を固守するとし、最終手段としての軍事とその他の手段との連続性を示唆している。
そして、同ドクトリンでは「現代の軍事紛争の特徴および特質」と題して10項目を挙げ、ハイブリッドという言葉こそ使っていないが、ハイブリッドな戦い方が現代戦の特色であることを強調している。
「現代の軍事紛争の特徴および特質」を時系列的にまとめると、次のようになろう。
平・戦時の境目のない戦い→ハイブリッド戦/グレーゾーン事態
①軍事力、政治的・経済的・情報その他の非軍事的性格の手段の複合的な使用による国民の抗議ポテンシャル(相手国民への宣伝戦・心理戦による懐柔)と特殊作戦(リトル・グリーンメン)の広範な活用
②政治勢力、社会運動に対して外部から財政支援および指示を与えること
③敵対する国家の領域内において、常に軍事活動が行われる地域を作り出すこと(東シナ海:尖閣諸島~沖縄、南シナ海)
軍事活動への移行
④軍事活動を実施するまでの準備時間の減少
軍事活動
⑤グローバルな情報空間、航空・宇宙空間、地上および海洋において敵領域の全縦深で同時に活動を行うこと(マルチドメイン作戦)
⑥精密誘導型兵器および軍用装備、極超音速兵器、電子戦兵器、核兵器に匹敵する効果を持つ新たな物理的原理に基づく兵器、情報・指揮システム、無人航空機および自動化海洋装置、ロボット化された兵器および軍用装備の大量使用(技術的優越/先進的兵器)
⑦垂直的かつ厳密な指揮システムからグローバルな部隊および指揮システムネットワークへの移行による部隊および兵器の指揮の集中化および自動化
⑧軍事活動に非公式の軍事編成および民間軍事会社が関与すること
(以上、括弧は筆者)
つまり、「新しい戦争」の特徴・特質は、まず、純然たる戦時と認定しがたい条件の範囲内で、軍事的手段と非軍事的手段を複合的に使用し、相手の知らないうちに外形上「戦争に見えない戦争」を仕掛ける。
それによる可能性が尽きた場合には一挙に軍事活動へと移行し、最終的に最先端技術・兵器を駆使したマルチドメイン作戦による軍事活動をもって戦争の政治的目的を達成することにあると言えよう。
ロシアは、旧ソ連邦国家やアラブ諸国の民主化や自由を求める運動を西側による体制転換の脅威として非難しているが、むしろそれを逆手にとり、実際にウクライナやシリアで「新しい戦争」を展開しているのはロシアの方である。
そして、最近ロシアとの軍事的接近を強めている中国が、「孫子」の伝統と2人の軍人によって提唱された「超限戦」の思想と相まって、従来と形を変えた「新しい戦争」を描く「ロシア連邦軍事ドクトリン」に関心を示さないはずはないのである。
すでに始まった中国の対日“戦争”
習近平国家主席は、故毛沢東主席のほかに、ロシアのプーチン大統領をロール・モデルとしていると言われている。
クリミア半島併合などの実戦で採用された「ハイブリッド戦」に代表されるロシアの軍事ドクトリンは格好の教材である。
習近平主席は、中国のシンクタンクにその研究を命じ、それによって、中国の台湾統一戦略や尖閣諸島・南シナ海などへの海洋侵出戦略に大きな影響を及ぼしていると見られている。
そこで、中国がわが国に対して仕掛けている「新しい戦争」について、ロシアが挙げる「現代の軍事紛争の特徴および特質」に沿って分析してみることにする。
①「軍事・非軍事手段の複合的使用等」について
中国は、軍事や戦争に関して、物理的手段のみならず、非物理的手段も重視しているとみられ、「三戦」と呼ばれる「輿論(よろん)戦」、「心理戦」および「法律戦」を軍の政治工作の項目としているほか、軍事闘争を政治、外交、経済、文化、法律などの分野の闘争と密接に呼応させるとの方針も掲げている。(令和2年版『防衛白書』)
米国防省によると、輿論戦は、中国の軍事行動に対する大衆および国際社会の支持を得るとともに、敵が中国の利益に反するとみられる政策を追求することのないよう、国内および国際世論に影響を及ぼすことを目的としている。
心理戦は、敵の軍人およびそれを支援する文民に対する抑止・衝撃・士気低下を目的とする心理作戦を通じて、敵が戦闘作戦を遂行する能力を低下させようとする。
また、法律戦は、国際法および国内法を利用して、国際的な支持を獲得するとともに、中国の軍事行動に対する予想される反発に対処するものである。
中国は、海洋侵出の野望を実現するため海軍および海警局の先兵として海上民兵(リトル・ブルーメン)を活用している。
海上民兵は、普段、漁業などに従事しているが、命令があれば、民間漁船などで編成された軍事組織(armed forces)に早変わりし、軍事活動であることを隠すため、漁民などを装って任務を遂行する。
東シナ海の尖閣諸島や南シナ海で見られるように、海上民兵は、中国の一方的な権利の主張に従い、情報収集や監視・傍受、相手の法執行機関や軍隊の牽制・妨害、諸施設・設備の破壊など様々な特殊作戦・ゲリラ活動を行う。
同時に、係争海域における中国のプレゼンス維持を目的とし、あるいは領有権を主張する島々に上陸して既成事実を作るなど幅広い活動を行い、中国の外交政策や軍事活動の支援任務に従事している。
その行動は、「サラミ1本全部を1度に盗るのではなく、気づかれないように少しずつスライスして盗る」という寓意に似ていることから、「サラミスライス戦術」と呼ばれている。
「サラミスライス戦術」を行う海上民兵が乗船する漁船などの周りを海警局の艦船が取り囲み、公船の後方に海軍の艦艇が待機し、島や岩礁を2重3重に囲んで作戦する様子が、中心を1枚ずつ包み込んでいるキャベツの葉に似ているので、これを「キャベツ戦術」と呼んでいる。
そこには、前述の通り、計算尽の巧妙な仕掛けが潜んでいる。
まず、中国は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土である尖閣諸島を、中国の「領海・接続水域法」で自国領土と規定した「法律戦」に訴えつつ、妥協の余地のない「核心的利益」と主張している。
その虚構の上に、尖閣諸島周辺海域で漁船(海上民兵)を活動させ、その保護を名目に法執行機関(海警)を常続的に出動させている。
そして、「釣魚島は中国固有の領土である」という題目の白書を発表するとともに、いかにも尖閣諸島を自国領として実効的に支配しているかのように国際社会に向けた大規模な「輿論戦」を繰り広げている。
同時に、日本および日本国民に対しては力の誇示や威圧による士気の低下を目的とした「心理戦」を展開している。
このように、中国の日本に対する「戦争に見えない戦争」は、すでにこの段階まで進んでおり、中国の尖閣諸島奪取工作は危機的状況にまで高まっている。
そして、中国は、同島周辺地域で不測の事態が起きることを虎視眈々と窺っており、もしそのような事態が発生すれば、力による現状変更の好機と見て軍隊(海軍)を出動させ、軍事的解決に訴える態勢を整えているのである。
②「敵対国家内の政治勢力や社会運動に対する財政支援・指示」について
米有力シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)は2020年夏、「日本における中国の影響」についての報告書を発表した。中でも、中国の沖縄工作が注目される。
報告書は、中国が世界中で展開する戦術には、中国経済の武器化(取引の強制や制限)、 物語的優位性の主張(プロパガンダと偽情報)、エリート仲介者の活用、在外華人の道具化、 権威主義的支配の浸透などがあるとした。
こうした工作を中国は日本に対しても行い、表向きの外交から、特定個人との接触などの隠蔽、強制、賄賂による買収(3C=covert, coercive and corrupt)を用いているとしている。
特に、尖閣諸島を有する沖縄県は、日本の安全保障上の重要懸念の一つであり、米軍基地を擁するこの島で、外交、ニセ情報、投資などを通じて、日本と米国の中央に対する不満を引き起こしていると指摘する。
報告書は、中国共産党が海外の中国人コミュニティに影響を与えるために使用する多くの方法の一つが中国語メディアであり、ニュースメディアを通じた中国の影響力の最も重要なターゲットは沖縄だと指摘する。
この件については、日本の公安調査庁も年次報告書(2015・17年の『内外情勢の回顧と展望』)において、中国官製メディアの環球時報や人民日報が、日本による沖縄の主権に疑問を投げかける論文を複数掲載していることを取り上げ、沖縄で中国に有利な世論を形成し、日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるものとみられ、今後の沖縄に対する中国の動向には注意を要すると問題提起している。
そのように、中国が沖縄に「独立宣言」させる工作を進めている可能性があるとして懸念が広がっている。
③「敵対国家の領域内における軍事活動地域の創出」について
中国は、尖閣諸島周辺の日本の領海や接続水域に法執行機関である海警局の艦船を絶え間なく送り込み、同諸島の領有をかたくなに主張している。
この動きは、2019年から強まっており、今年、各国が新型コロナウイルスへの対応に迫られる中でもそ���攻勢はむしろ激化し、これまでとは違った危険な局面に入っていると見られている。
尖閣諸島周辺での中国公船等による接続水域内入域および領海侵入は、今年4月中旬から110日以上連続した。
そして、5月8日、日本の領海に侵入した中国海警局の2隻が、そこで漁をしていた日本漁船を追尾し続け、3日間にわたって領海への侵入を繰り返した。
この件について中国外務省の報道官は、「日本漁船が中国の領海内で違法な操業をしたため海域から出るよう求めた」と主張した。
すでに尖閣諸島は自国領であるとの前提に立ち、あくまで自国の海で主権を行使しているに過ぎないとうそぶく始末である。
中国では、2018年1月に人民武装警察(武警)部隊が、また同年3月には武警部隊の傘下に海警局が、それぞれ国務院(政府)の指揮を離れ、最高軍事機関である中国共産党中央軍事委員会(主席・習近平国家主席)に編入された。
この改編を通じ、海警局の法執行の強化および武警・人民解放軍と融合した軍隊化が図られた。
その結果、尖閣諸島周辺海域で行動する中国海警局の艦船は、準軍隊としての性格と役割を付与され、東シナ海を管轄する人民解放軍の「東部戦区」とともに一元的に作戦行動をとる体制が整ったことになる。
さらに、中国の立法機関である全国人民代表大会(全人代)は今年11月初め、海警局(海警)の権限を定めた「海警法」案の全文を発表し、国家主権や管轄権が外国の組織、個人に侵害されたときは「武器の使用を含めたあらゆる必要措置」を取れると規定した。
また最高軍事機関である中央軍事委員会の命令に基づき「防衛作戦などの任務」にあたることも明記された。海警局の艦船は、大型化し、軍艦並みの兵器を装備しており、法制定後は海軍との連携を一段と強めるとみられている。
前述の通り、海警局の艦船は、尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返しており、周辺で操業する日本漁船も「海警法」の対象となるのは間違いなかろう。
このように中国は、日本領域内の尖閣諸島ひいては南西諸島周辺を焦点に軍事活動を行う地域を意図的に作り出していると見ることができ、今後、不測の事態が生起すれば、一挙に軍事活動へとエスカレートさせる危機が迫っていると考えなければならない。
④「軍事活動への短時間の移行」について
中国は、東シナ海の尖閣諸島、南シナ海そしてインドとの国境で、領土的野心を露わにしている。
今年6月に中国とインドの国境付近で発生した両国軍の衝突は、中国が自国周辺の領有権主張を巡り、一段と強硬姿勢を取るリスクを浮き彫りにした。
また、その衝突によって、中国が国境付近の現状を変えるため、現場の比較的小規模な小競り合いを利用しごく短時間に軍事作戦へ移行することも明らかになった。
同じように、中国の尖閣諸島を焦点とする日本に対する軍事作戦は、「Short, Sharp War」(迅速開始・短期決戦の激烈な戦争)になると見られている。
そのシナリオの一例はこうだ。
米国がINF全廃条約の影響で、東アジアに対する中距離(戦域)核戦力による核の傘を提供できない弱点に乗じて、中国軍は日本を核恫喝してその抵抗意思を削ぐ。
同時に、対艦・対地弾道ミサイルを作戦展開し、それによる損害を回避させるべく米海軍を第2列島線以遠へ後退させるとともに、米空軍を北日本などへ分散退避させる。
その米軍事力の空白を突いて、中国軍は、海空軍を全力展開して東シナ海の海上・航空優勢を獲得し、その掩護下に海上民兵や日本国内で武装蜂起した特殊部隊などに先導されて尖閣諸島をはじめとする南西諸島地域に奇襲的な上陸作戦を敢行し、一挙に同地域を奪取占領する。
まさにその軍事作戦は、迅速に開始され短期決戦を追及する激烈な戦争、すなわち「Short, Sharp War」を追求している。
その際、米陸軍および海兵隊は、中国軍の侵攻に遅れまいと第1列島線への早期展開を追求するため、中国軍の侵攻と米地上部隊の展開が交錯する戦場でいかに主導権を握るかがカギである。
したがって、日本や第1列島線の国々は、米陸軍・海兵隊の受け入れをスムーズに行う体制を平時から整備することが重要である。
⑤「マルチドメイン作戦による戦争」について
中国は、日米などが新たな戦いの形として追求しているマルチドメイン作戦(MDO)という言葉を使用していないが、それに相当する概念を「情報化戦争」と呼んでいる。
中国は、2016年7月に公表された「国家情報化発展戦略綱要」などで表明しているように、経済と社会発展のための道は情報分野に依存しているとし、軍事的側面からは情報化時代の到来が戦争の本質を情報化戦争へと導いていると認識している。
そして、「情報戦で敗北することは、戦いに負けることになる」として、情報を生命線と考えるのが中国の情報化戦争の概念であり、そのため、従来の陸海空の領域に加え、敵の通信ネットワークの混乱などを可能とするサイバー領域や、敵のレーダーなどを無効化して戦力発揮を妨げることなどを可能とする電磁波領域、そして敵の宇宙利用を制限する宇宙領域を特に重視して情報優越の確立を目指している。
この際、中国の情報化戦争は、米国のような全般的な能力において優勢にある敵の戦力発揮を効果的に妨害する非対称的な能力を獲得するという意味合いもあり、新たな領域における優勢の確保を重視している。
前述の通り、「孫子」の忠実な実践者である中国は、情報化戦争の一環として政治戦や影響工作も重視している。
また、1999年に発表された中国空軍大佐の喬良と王湘穂による戦略研究の共著『超限戦』は、25種類にも及ぶ作戦・戦闘の方法を提案し、通常戦、外交戦、国家テロ戦、諜報戦、金融戦、ネットワーク戦、法律戦、心理戦、メディア戦などを列挙し、これらのあらゆる手段で制限なく戦うものとして今後の戦争を捉えており、中国の情報化戦争に少なからぬ影響を及ぼしていると見られている。
⑥「技術的優越の追求と先進的兵器の使用」について
中国は、2019年10月1日の建国70周年の軍事パレードで23種の最新兵器を公開し、軍事力を内外に誇示した。
その中で、超音速ミサイルや無人戦闘システム、電子戦などに力を入れていることが明らかになったが、パレードで公開された最新兵器はすべて実際に配備されていると説明されている。
その一部を紹介すると下記の通りである。
新型大陸間弾道ミサイル(ICBM)「DF-41」、極超音速滑空ミサイル「DF-17」、超音速巡航ミサイル「CJ-100/DF-100」、超音速対艦巡航ミサイル「YJ-12B/YJ-18A」、最新鋭ステルス戦略爆撃機「H20」、攻撃型ステルス無人機「GJ-11」、高高度高速無人偵察機「WZ-8」、無人潜水艇(UUV)「HSU001」など
中国は、全般的な兵力やグローバルな作戦展開能力、実戦経験でなお米国に後れを取っているとはいえ、今や自国からはるか遠くで作戦を遂行する能力を持ち、インド太平洋地域の紛争を巡る米軍および同盟国軍に対する接近阻止・領域拒否(A2/AD)能力を有する自国製兵器を幅広く取りそろえている。
中国は、米国に対する技術的劣勢を跳ね返すため、特に、海洋、宇宙、サイバー、人工知能(AI)といった「新興領域」分野を重視した「軍民融合」政策を全面的に推進しつつ、軍事利用が可能な先端技術の開発・獲得に積極的に取り組んでいる。
中国が開発・獲得を目指す先端技術には、将来の戦闘様相を一変させるゲームチェンジャー技術も含まれており、技術的優位性の追求を急速かつ執拗に進めている。
⑦「ネットワーク型指揮システムによる部隊指揮・兵器運用の集中化・自動化」について
中国は、建国以来最大規模とも評される「軍改革」を急ピッチで進めている。
軍改革は、2016年末までに、第1段階の「首から上」の改革と呼ばれる軍中央レベルの改革が概成した。
2017年以降は、第2段階の「首から下」と呼ばれる現場レベルでの改革を着実に推進し、そして「神経の改革」と呼ばれる第3段階の改革に着手している。
中国は、中央軍事委員会に習近平総書記を「総指揮」とし、最高戦略レベルにおける意思決定を行うための「統合作戦指揮センター」を新設した。
これをもって、習近平総書記が、統合参謀部や政治工作部などで構成される中央軍事委員会直属機関の補佐を受け、統合作戦指揮センターにおいて中国全軍を集中一元的に指揮する体制が整ったことになる。
また、中央軍事委員会/統合作戦指揮センターの直下に、従来、総参謀部が持っていた多くの作戦支援部門の機能を統合し、航空宇宙部、ネットワークシステム(サイバー)部、電子電磁システム部および軍事情報部から構成され、情報の戦いを一元的に遂行できる戦略支援部隊が編成された。
さらに、これまでの「七大軍区」が廃止され、軍全体で統合運用能力を高めるため、統合作戦指揮を主導的に担当する「五大戦区」、すなわち東部、南部、西部、北部および中部戦区が新編され、常設の統合作戦司令部がおかれている。
これに先立つ2014年7月、環球時報(電子版)は、中国軍が2013年11月、東シナ海に防空識別圏を設定したのに続き、「東海(東シナ海)合同作戦指揮センター」を新設したと伝えた。
合同指揮センターは、中国各軍区の海、空軍を統合し、東シナ海の防空識別圏を効果的に監視し、日本の軍事的軽挙妄動を防止するのが目的だと報じている。
このように、中国は、マルチドメイン作戦としての情報化戦争で「戦える、勝てる」(習近平総書記)よう、統合作戦遂行能力の向上と効率的な部隊・兵器運用に向けて、ネットワーク型指揮統制システムによる部隊指揮および兵器運用の集中化・自動化に注力している。
⑧「軍事活動への非公式の軍事編成および民間軍事会社の関与」について
中国は、2010年7月に国防関連法制の集大成となる「国防動員法」を制定した。
同法は、有事にあらゆる権限を政府に集中させるもので、民間の組織や国内外に居住する中国公民に対して、政府の統制下に服する義務を課している。
国防動員の実施が決定されれば、公民と組織は、国防動員任務を完遂する義務を負い、軍の作戦に対する支援や保障、戦争災害の救助や社会秩序維持への協力などが求められる。
同法は、日本国内で仕事をしている中国国籍保持者や留学生、中国人旅行者にも適用され、突発的に国防動員がかかった場合、中国の膨大な「人口圧」がわが国の安全保障・防衛に重大な影響を及ぼす。
そのことについて深刻に受け止め、有効な対策を練っておかなければならない。
また、同法は、国が動員の必要に応じ、組織および個人の設備施設、交通手段そのほか物資を収容しおよび徴収することができると定め、その際の徴用の対象となる組織や個人は、党政府機関、大衆団体、企業や事業体等で、中国国内のすべての組織と中国公民、中国の居住権をもつ外国人をも含むすべての個人としている。
つまり、本法律は、中国に進出している日本企業や中国在住の日本人をも徴用の対象としている点に注意が必要である。
コロナ禍によって、マスクをはじめとする薬や医薬品、医療機器など、日本人の生命や国家の生存に関わる生活必需品や戦略物資が不足した。
その原因は、中国でマスクを生産していた日本企業が中国の国防動員の徴用の対象となったことにあり、医薬品などを極度にまで中国に依存し、脆弱性を露呈した厳しい現実を決して忘れるわけにはいかない。
他方、中国は、2017年に軍隊と民間を結びつけ、軍需産業を民間産業と融合させる「軍民融合」政策を国家戦略として正式採用した。
その狙いは、軍の近代化のために民間企業の先進的な技術やノウハウを利用することにある。
中でも、最先端の軍民両用(デュアル・ユース)の技術を他国に先駆けて取得・利用することを重視していることから、民間セクターと軍事の壁を曖昧にし、あるいは排除して軍事分野に活用する動きを強めている。
そのため、国有企業と民間企業の相互補完的な関係づく��に取り組みつつ、米国の軍産複合体を目指すとともに、国有企業の規模・シェアの拡大と民間企業の縮小・後退を意味する「国進民退」を積極的に推進し、政府の官僚を「政務事務代表」としてアリババやAI監視カメラメーカーのハイクビジョン(海康威視)などの重点民営企業に駐在させ、政府官僚による民営企業の直接支配を始めている。
このような共産党一党独裁体制下での軍民融合は、軍事力の近代化・強化がすべてに優先する「軍国主義」化に拍車をかける危険性がある。
軍民融合政策と同時に警戒しなければならないのが、「国家情報法」である。
同法は、「国家情報活動を強化および保障し、国の安全および利益を守るため」(同法第1条)、国内外の情報工作活動に法的根拠を与える目的で作られた。
その第7条では「いかなる組織および国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助および協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない」と定め、国内外において一般の組織や市民にも情報活動を義務付けている。
つまり、中国は軍民融合政策と国家情報法を一体として運用しており、そのことは、日本の企業や研究者が意図せずして、あるいは気付かないうちに、人民解放軍によるドローンや人工知能(AI)などの民間の最先端技術や専門知識の取得を助け、新たなリスクを生み出す可能性があることを意味している。
このように、中国は、軍事活動に民間の組織や公民を動員する体制を敷き、また、軍の近代化のために民間企業の先進的な技術やノウハウを利用するため、民間セクターと軍事の境界を曖昧にし、あるいは排除して軍事分野に積極的に活用する動きを強めている。
以上、ロシアが挙げる「現代の軍事紛争の特徴および特質」に沿いながら、中国がわが国に対し仕掛けている「新しい戦争」の形について概要を説明した。
それから読み解けることは、中国は、ロシアの軍事ドクトリンとほぼ同じ軌道をたどった行動や工作を行っているということだ。
ロシアが、当初ウクライナで行ったこと、すなわち純然たる平時でも戦時でもない境目において、軍事的手段と非軍事的手段を複合的に使用し知らないうちに始められた外形上「戦争に見えない戦争」、それと同じあるいは更に厄介な戦争を、中国は日本に対しすでに仕掛けていることは疑う余地のない事実である。
もし、それによる可能性が尽きた場合には一挙に軍事活動へと移行し、最終的に最先端技術・兵器を駆使した情報化戦争をもって戦争の政治的目的を達成しようとすることも、ロシアのクリミア半島併合や東部ウクライナへの軍事介入と同じと見なければならない。
「全政府対応型アプローチ」で備えよ
「新しい戦争」の形である外形上「戦争に見えない戦争」の大きな特徴および特質は、軍事力を背景とし、軍事的手段と非軍事的手段を複合的かつ連続的に使用することにある。
したがって、わが国の防衛も、軍事と非軍事の両部門をもって構成されなければならない。
その軍事部門を防衛省・自衛隊が所掌することは自明である。
では、これまで説明してきた中国の非軍事的手段である「輿論(よろん)戦」、「心理戦」および「法律戦」の「三戦」、そして政治、外交、経済、文化などの分野の闘争、さらに常態化しているサイバー攻撃などに対しては、どの行政組織がどのように備えているのであろうか。
それ以前に、わが国が中国の「戦争に見えない戦争」の挑戦を受け危機的状況にあるとの情勢認識があるのか、ななはだ疑わしい。
そこでまず、「日中関係は完全に正常な軌道に戻った」や習近平国家主席の国賓来日など、誤った対中情勢認識に基づいた日中関係の推進は、直ちに是正されなければならない。
そのうえで、中国の複雑多様な非軍事的手段による脅威を考えると、政府内各省庁のそれぞれの任務所掌事務・機能を結集した「全政府対応型アプローチ」(all government approach)を取ることが何よりも重要である。
しかし、各省庁の縦割り行政では、効果的・実効的な対応は期待できないので、その弊害をなくし、政府が総合一体的な取組みを行えるよう、行政府内に非常事態対処の非軍事部門を統括する機関を新たに創設することが望まれる。
例えば、内閣府または総務省に「国土保全庁」(仮称)を設置するか、米国の「国土安全保障省」のように、各省庁の関係組織を統合して一体的に運用する「国土保全省」(仮称)を創設する選択肢もある。
そして、国家安全保障局(NSS)の補佐の下、国家安全保障会議(NSC)を国家非常事態における国家最高司令部とし、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣および防衛大臣(4大臣会合)を中核に関係閣僚をもって国家意思を決定し、最高指揮権限者(NCA)である内閣総理大臣が軍事部門の自衛隊および非軍事部門を集約する「国土保全庁」あるいは「国土保全省」に対して一元的に指揮監督権を行使するピラミッド型の有事体制を作ることが必要だ。
他方、わが国は「自然災害大国」であり、平成7(1995)年1月の阪神淡路大震災や平成23(2011)年3月に発生した東日本大震災をはじめ、ほぼ毎年全国各地で大規模自然災害が発生し、その都度、共助、公助の不足が社会的課題として指摘されてきた。
近い将来、南海トラフ地震や首都直下地震などによって国家的危機の発生が予測されている。
併せて、中国による広範なサイバー攻撃や高高度電磁パルス(HEMP)攻撃があれば、一般住民をも直接的・間接的に巻き込まずには措かないのである。
このように、国民保護や重要インフラ維持の国土政策、産業政策なども含めた総合的な対応を、いわば「国家百年の大計」の国づくりとして、千年の時をも見据えながら行っていくことが求められる。
つまり、わが国の安全保障・防衛を強化するためには、社会全体でわが国を守る仕組み・取組みが不可欠であり、国民の「自助、共助、公助」への責任ある参画を促し、それを「民間防衛」の組織へと発展させることが更なる喫緊の課題である。
一方、軍事部門を見れば、わが国は、戦後の「経済重視・軽武装」政策を引きずり、いまだにその充実強化が疎かにされている。
最大の課題は、列国と比較して防衛費が極端に低く抑え込まれていることだ。
日本は、中国の「情報化戦争」を念頭に、30防衛大綱で「領域横断(クロスドメイン)作戦(CDO)」を打ち出し、自衛隊の能力構築を始めた。
CDOでは、従来の陸上、海上、航空の活動領域が宇宙空間へと拡大し、さらにサイバー空間や電磁波空間といった新たな活動領域が加わった。
そのように、軍事活動の領域・空間が3つから6つへと一挙に倍増し、多領域・多空間に拡大して戦われるのが近未来戦の際立った趨勢である。
そのため、これまでの自衛隊の組織規模をスクラップ・アンド・ビルト方式で再編成するのには一から無理があり、従来の防衛力を基盤として、中国の新たな脅威に対抗できるCDO能力を付加的に強化するには、自衛隊の組織規模の飛躍的拡大や最先端のハイテク装備の取得が必須である。
また、CDO(米軍はマルチドメイン作戦:MDOと呼称)を前提とした日米共同作戦には、両軍のC4ISRをネットワーク化することが不可欠であり、そのような防衛力の整備には防衛費の倍増は避けて通れない。
米国は、中国との本格的かつ全面的な対決に踏み出し、そのため今後、世界の分断が進むと予測されている。
つまり、米中対立は、米中間に限られたものではなく、自由・民主主義を支持する国々と共産主義中国との対立であり、他ならぬ日本自身の問題である。
その対立が前提の世界において、日本が二者択一で同盟国の米国をさて置き、中国を選択することがあってはならない。
同盟が成り立つには、①価値の共有、②利益の共有、③負担の共有、そして④リスクの共有、すなわち戦略的利害の共有が必要である。
米国が中国との新冷戦を決意している時、日本が安全保障・防衛上の利益のみを享受し、新冷戦において生じる米国の通商や金融、テクノロジー、外交、それに安全保障・軍事などの負担やリスクを、中国との経済関係を重視するあまり、日本が共有する明確な姿勢を示さない場合、同盟は成り立つはずがない。
そのうえ、米国からは見放され、中国からは経済面で裏切られた上、安全保障上の敵対心を露わにされるのは必定である。
コロナ禍とともに戦後最大の安全保障の危機に直面している今こそ、日本は米国との同盟関係を一段と深化させ、米国と同じ構えで中国に備えることが強く求められるのである。
そして、日米同盟を基軸として、インド、オーストラリアの4か国(クワッド)に台湾などの周辺諸国やASEANなどを加えて、「自由で開かれたインド太平洋」構想(戦略)の下、インド太平洋版「NATO」へと発展させることが今後の大きな課題でもある。
16 notes
·
View notes
Link
沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が日本の領海のすぐ外側の接続水域を航行していて、接続水域内の航行は、22日で100日連続となりました。これは日本政府が尖閣諸島を国有化して以降、最も長く、海上保安本部が警戒を続けています。
第11管区海上保安本部によりますと、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海のすぐ外側にある接続水域を航行しています。
4隻は、22日午後3時現在、尖閣諸島の久場島の北東およそ39キロから東北東およそ41キロを航行しているということです。
尖閣諸島の沖合では、中国海警局の船がことし4月14日以降、22日で100日連続で接続水域内を航行していて、これは日本政府が8年前に尖閣諸島を国有化して以降、最も長くなっています。
また、この間には、領海に侵入して操業中の日本の漁船に接近する動きを繰り返すなどしていて、海上保安本部が領海に近づかないよう警告と監視を続けています。
官房長官「極めて深刻 きぜんとした態度で冷静に対応」
菅官房長官は、午前の記者会見で、「中国側による活動が継続していることは極めて深刻に考えており、中国側に対し、現場海域での海上保安庁の巡視船による警告のほか、外交ルートを通じて繰り返し厳重抗議をしている」と述べました。
そのうえで、「政府としては、領土、領海、領空は断固として守るという方針のもとに、引き続き、緊張感をもって、関係省庁と連携して情報収集に努めつつ、尖閣諸島周辺の警戒に万全を尽くしていきたい。同時に、中国側に対しては、引き続き、きぜんとした態度で冷静に対応していきたい」と述べました。
米国務省「尖閣諸島は日本の施政下」
アメリカ国務省の報道担当者は21日、NHKの取材に対し、「われわれの立場は変わらない。アメリカは尖閣諸島が日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条が日本の施政下にある領域に適用されると認識している」として、アメリカによる防衛義務を定めた日米安全保障条約の適用範囲だという立場は変わらないと強調しました。
日本政府 領有権の問題はそもそも存在しない
日本政府は沖縄県の尖閣諸島について、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配しているとして、尖閣諸島をめぐって解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないとしています。
尖閣諸島の周辺海域で中国海警局の船が日本の接続水域を航行した場合には、そのつど外交ルートを通じて申し入れを行い、領海に侵入した場合は、中国による一方的な現状変更の試みに厳重に抗議するとして、繰り返し退去要求を行っています。
そのうえで、日本政府は「東シナ海の安定なくして日中関係の真の改善はない」と、外交当局間などの協議を通じて日本の立場を主張するとともに、信頼醸成に向けて意思疎通を続けています。
軍の影響力を増す「中国海警局」
沖縄県の尖閣諸島の周辺海域で活動を活発化させている「中国海警局」は、ここ数年、機構改革などを重ねて軍の影響力を増し、体制を強化しています。
「中国海警局」は2013年の機構改革で、それまで複数の省庁に分散して行ってきた、海上での巡視活動にあたる組織を統合する形で誕生し、「国家海洋局」という政府組織に属していました。
その後、おととしの機構改革で、政府組織から軍の指揮下にある「武装警察」に編入され、トップに軍の出身者が就任したほか、人員や装備も増強したものとみられています。
さらに、先月の法改正では有事の際、軍の最高指導機関である「中央軍事委員会」か、その下部組織の「戦区」の指揮を受けると定められ、軍と同じ指揮系統のもとで一体的に運用することを明確化しました。
一連の機構改革などによって、中国海警局は軍との統合作戦運用能力を高め、軍隊に匹敵する性格を帯びるようになっています。
活動は長期的な国家戦略も
沖縄県の尖閣諸島周辺での中国の公船などの活動は、習近平指導部が描く長期的な国家戦略に基づいて進められているという見方もあります。
習近平国家主席は2017年の共産党大会で、来年の中国共産党創立100年を経て、中華人民共和国建国から100年となる2049年には「社会主義の現代化強国を築く」という目標を掲げました。
さらに「今世紀半ばまでに世界一流の軍隊を作り上げる」としていて、軍事力を含む国力を高め、アメリカを超える世界一の強国を目指しているとみられます。
同時に、海洋権益の確保やシーレーン=海上交通路の確保などを目的に「海洋強国」の建設を掲げ、海軍や空軍の装備を増強して遠方での展開能力の向上を図っています。
尖閣諸島は、中国が防衛ラインとみなし、太平洋と東シナ海を隔てる「第1列島線」のそばに位置することから、中国としては戦略的な観点からも、この海域での影響力を誇示し、領有権の主張を強めていくものとみられます。
中国 日本の実効支配を突き崩すねらいか
中国政府は沖縄県の尖閣諸島について「中国固有の領土だ」と主張し、日本政府が国有化した2012年9月以降、周辺海域での公船の活動を一気に活発化させ、接続水域での航行だけでなく、日本の領海への侵入を繰り返しています。
日中関係が改善に向かう中で、去年6月には、習近平国家主席の国賓としての日本訪問が合意されましたが、外交上の姿勢とは裏腹に尖閣諸島周辺での挑発的な動きを続けています。
ことし5月には、尖閣諸島沖の日本の領海に侵入した中国海警局の船が日本の漁船を追尾したほか、今月にも、一時、日本の漁船に接近しました。
これについて、中国外務省の報道官は「日本の漁船が中国の領海で違法に操業していたため、海域から出るよう求めた」と述べて、みずからの行動を正当化したうえで、逆に日本に対し「新たな争いごとを作り出さないよう求める」と一方的に主張しました。
さらに先月には、尖閣諸島周辺とみられる東シナ海の海底地形、合わせて50か所に名称をつけたと発表し、この中には中国が主張する「釣魚島」という呼称の一部を使った地名も含まれ、日本政府が中国側に強く抗議しています。
中国としては、尖閣諸島周辺での公船の活動を既成事実として積み重ねるとともに、パトロールや取締りと称した活動を繰り返して主権を行使しているかのようにアピールすることで、日本による実効支配を突き崩すねらいがあるものとみられます。
中国は去年、4年ぶりに発表した国防白書でも「島の海域でパトロールを行い主権を行使していく」と明記していて、みずからの領有権の主張については一切妥協しない姿勢を示しています。
中国の海洋進出に対抗する米
アメリカ政府は沖縄県の尖閣諸島について、日本の施政下にあり、アメリカによる防衛義務を定めた日米安全保障条約の適用範囲だという立場で一貫しています。
アメリカ政府のこうした立場は、トランプ政権になって以降も日米首脳会談などの場で確認されてきたほか、国務省は今月15日、NHKの取材に対し、尖閣諸島について「日本の施政下にあり、日本の施政下にある領域には日米安全保障条約第5条が適用されると認識している」とコメントしました。
また、エスパー国防長官は21日の講演で「中国の人民解放軍が、日本の施政下にある尖閣諸島の周辺水域に侵入する回数も時間も増えている」と述べ、中国の艦船が沖縄県の尖閣諸島の周辺で活動を活発化させているという認識を示し、警戒感をあらわにしました。
一方、南シナ海をめぐって、トランプ政権は、領有権争いの当事国どうしでの解決を促すとしてきた、これまでの立場を転換しました。
ポンペイオ国務長官は13日、中国が南シナ海のほぼ全域の権益を主張するのは「完全に違法だ」とする声明を発表。中国の違法な領有権の主張に対しては、フィリピンなど相手国の側を支援して対抗していく新たな方針を打ち出したのです。
アメリカが立場を転換した背景には、各国が新型コロナウイルスへの対応に追われるさなかにも、中国が南シナ海や東シナ海での軍事的な活動を活発化させているとの強い危機感があります。
中国海軍が今月上旬、南シナ海と東シナ海、それに黄海の3つの海域で、同じ時期に異例の軍事演習を実施したのに対し、アメリカ海軍も今月上旬、2隻の原子力空母を南シナ海に���遣し、軍事演習を実施。米中が同じ時期に同じ海域で大規模な軍事演習を実施するという異例の事態となりました。
さらに、アメリカ海軍は今月中旬にも再び南シナ海に2隻の原子力空母を派遣して軍事演習を実施しており、中国の海洋進出に対抗する姿勢を鮮明に打ち出しています。
中国船の活動に「執よう」の表現は初 防衛白書
防衛省は、ことしの防衛白書で、中国当局の船が沖縄県の尖閣諸島周辺の接続水域で活発に活動している状況を取り上げ「力を背景とした一方的な現状変更の試みを執ように継続しており、事態をエスカレートさせる行動は全く容認できるものではない」としています。
尖閣諸島周辺での中国当局の船の活動をめぐって、防衛白書で「執よう」という表現が用いられたのは、ことしが初めてで、防衛省は「たび重なる抗議にもかかわらず、活動を繰り返している実態を反映させた」としています。
尖閣諸島周辺で主に活動している中国海警局の船には、海上保安庁が対応していますが、過去には中国の潜水艦やフリゲート艦が、領海のすぐ外側の接続水域を航行したこともあります。
一方、中国はことし、空母を沖縄本島と宮古島の間の海域で初めて往復させるなど、太平洋側への進出も強めていて、防衛省は護衛艦や航空機などによる警戒を強化しています。
中国公船のこれまでの動き
尖閣諸島の周辺海域における中国公船の動きをまとめました。
海上保安庁によりますと、日本政府が尖閣諸島を国有化した平成24年9月以降、尖閣諸島の沖合では、中国公船による接続水域での航行や領海侵入が頻繁に確認されています。
中国公船の接続水域での航行を年別に見てみると、平成24年が91日、平成25年は232日、平成26年は243日、平成27年は240日、平成28年は211日、平成29年は171日、平成30年は159日となっていて、平成27年からは減少傾向にありましたが、去年は一転して急増し、282日と過去最多となりました。
また、今回のケースを除くと、これまでの連続航行した日数で最も長かったのは、去年4月から6月にかけて続いた64日でした。
24時間体制で警戒・監視
中国が海洋進出を強める中、海上保安庁は体制を強化して警戒・監視を行っています。
尖閣諸島の周辺海域の警備を巡っては海上保安庁は大型の巡視船12隻を専従としているほか、複数の航空機も運用することで24時間体制で警戒・監視にあたっています。
また、海上保安庁では所有する船や職員も増やしています。
大型の巡視船は平成24年度の51隻から昨年度は67隻に増やしたほか、ことしの定員はおよそ1万4300人で、平成24年と比べると1600人ほど増えています。
中国は尖閣諸島以外でも領有権を主張
中国は沖縄県の尖閣諸島のほかにも、みずからの領有権を主張する動きを強め、周辺国との対立を深めています。
このうち、各国が領有権を争う南シナ海では、「九段線」と呼ぶ独自の境界線をもとに、ほぼ全域の管轄権を主張し、ことし4月には南沙諸島=英語名・スプラトリー諸島と西沙諸島=英語名・パラセル諸島などを、それぞれ管轄する新たな行政区を設置すると、一方的に発表しました。
また、南沙諸島では、岩礁を埋め立てて人工島を造成し、滑走路やレーダー設備など軍事関連の施設を整備するなど、実効支配を強めています。
こうした中、ベトナム政府によりますと、ことし4月から先月にかけてベトナムの漁船が中国海警局の船に沈没させられたり、中国の船に襲撃されたりする被害が相次いで起きているということです。
こうした動きを受けて、アメリカのポンペイオ国務長官は今月13日、声明を出し「中国の南シナ海のほぼ全域における海洋権益の主張は完全に違法だ」として、これまでの当事国どうしでの解決を促す立場から踏み込んで、中国への対抗姿勢を鮮明にしています。
また、これまで経済面での関係を重視して直接的な対立を避けてきたASEANの国々の間でも、中国への不信感から外交姿勢を転換する動きが顕著になっています。
このほか、中国とインドの国境地域にある係争地帯では、先月15日、双方の軍が衝突し、インド軍はインド側の20人が死亡したと発表しています。
中国はさらに、インドが影響力を持つブータンでも、東部にある野生生物保護区の領有権を主張していたことがわかり、周辺国の間で警戒感が強まっています。
台湾外交トップ「中国の現状変更に警戒」
台湾の呉※ショウ燮外交部長は22日、海外メディアを対象に記者会見を開きました。
台湾は、沖縄県の尖閣諸島について領有権を主張していますが、呉部長は、尖閣諸島周辺海域での中国公船の活動について「中国海警局の船が連続で100日間も入ったことは過去になく、もし日本の公船や漁業者が追い払われることになれば現状の変更となり、心配している」と警戒感を示しました。
また、呉部長は、中国軍機が先月、ほぼ連日にわたって台湾の空域に進入していたことを明らかにし、「中国は台湾周辺の現状も変えようとしている」として強い懸念を示しました。
そのうえで、尖閣諸島や台湾の周辺で活発化する中国の活動を念頭に「台湾と日本の運命は緊密に結び付いており、関係を促進しなければならない」と述べました。
※金へんに「りっとう」
中国外務省「島は中国固有の領土」
中国外務省の汪文斌報道官は22日の記者会見で「島は古くから中国固有の領土であり、中国海警局の船が周辺海域のパトロールを行うことは中国固有の権利だ」と述べ、従来の立場を改めて主張しました。
そのうえで、日本政府が繰り返し抗議していることについて「受け入れない」としたうえで、「両国は双方の共通認識にもとづいて、事態をエスカレートさせないようにすべきだ」と述べて、日本側に反論しました。
専門家「中国の最終目標は領有権を日本から奪うこと」
中国の安全保障に詳しい防衛省防衛研究所の飯田将史主任研究官は「中国としては、尖閣諸島周辺でのプレゼンスを着実に高めるのがねらいだ。最終的な目標は、尖閣諸島の領有権を日本から奪うことであり、そこに向けて着実に一歩一歩ステップを踏んできていて、今回の事態は起こるべくして起きた」と話しています。
そのうえで「中国はアメリカとの関係が悪化する中で、防衛上の観点から西太平洋に軍事力を展開する動きを強めているが、その通り道である東シナ海や南シナ海は戦略的に重要な地域だ。各国が新型コロナウイルスへの対応に追われる中、中国はアメリカ軍や自衛隊、海上保安庁の対応能力が低下しているのではないかと見ている向きもあり、尖閣諸島周辺での活動を通じて、日本やアメリカの出方を探ろうとしているのではないか」と指摘しています。
飯田氏は、中国は公船の大型化や武装化を進めながら、今後も尖閣諸島周辺での活動をエスカレートさせることが考えられると分析したうえで、「中国によるプレゼンスの高まりを止められていないのが現状だが、日本の対応次第では、中国がより強硬な姿勢に出る口実を与えることも懸念される。日本としては『この一線を越えることは許されない』という決意を中国にどのように示すかが問われている。政策面での周到な準備や対応能力の強化を図るとともに、場合によっては法整備なども含め、対応を抜本的に見直していくことが不可欠な状況になりつつある」と話しています。
14 notes
·
View notes
Text
コロナと日本人と餓死。
拡散してくれという気持ちは分かるが、政治家としてこれまで何をやってきたのかと、敢えて厳しく問いたい。これは山田氏だけではない。この国の政治家全員に対してだ。自給率が保たれていれば最悪なんとか国民は生きていけるが、今の日本の状態では輸入が途絶えると国民は間違いなく餓死する構造になっている。私がTPPに反対してきたのも、自国の自給率を破壊するのが見えていたからだ。危機的状況はいつ訪れるか分からない。もちろん安倍政権の責任は死ぬほど重いが、与野党含めた全政治家の責任も相当重い。そしてそんなバカ政治家に力を与えてきた有権者の責任は、安倍晋三の無知無能を超えると言っても過言ではない。さあどうする。ここでも安倍ヨイショを続けるのか。まだこの現実を無かったことにするのか。見なかったことにするのか。国は愚政では滅びない。愚政を許した愚民によって滅びるのだ。今はまだ庶民による買い占めで済んでいるが、もし今後輸入が滞れば、庶民が買い占める以前に、上級国民に買い占められて下には何も降りてこなくなるかもしれない。もし有権者が今後も大局に目を向けた判断を怠るとしたら、間違いなく悍しい日常を生きることになると私は考えている。現に私たちの親や祖父祖母たちは、その地獄を経験したからこそ、誰もが戦争のない平和と繁栄を願ったのだ。しかし喉元過ぎれば熱さ忘れて、安倍のようなキ印を平気で担ぐ愚かさには絶望感しかない。日本人の好きな日本一番は、このとっちゃん坊やによってものの見事に陳腐化され、白人に最も都合の良い民族へと成り果ててしまった。だから白人はみんな日本人が好き。何でも言うことを聞くからだ。しかし、彼らは最後は絶対に日本を助けない。日本の敵は白人、アメリカ、ハザールマフィアといってもTVと新聞しか見ない庶民には「何のこっちゃ?」かもしれないが、こんな売国政権を支持している限り、日本は永遠に危機的状況の中にあることだけは忘れないほうがいい。
追記:「日本は米は100%、野菜は79%自給しており、全ての食料が輸入に依存している訳ではありません」という尤もらしい声もあるが、危機管理に対して私は「too little、too late」だけは絶対にあってはならないと考えている。日本人の多くがなぜこんなに脳天気なのか理解に苦しむが、このコロナの風評だけでスーパーの棚が空っぽになるということは、実は国民は心の奥底にトラウマを抱えていることを表している。為政者の戯れ言に騙されるのはいい加減やめようではないか。日本を強くする為には軍備や兵器ではなく食糧自給率の充実だろう。

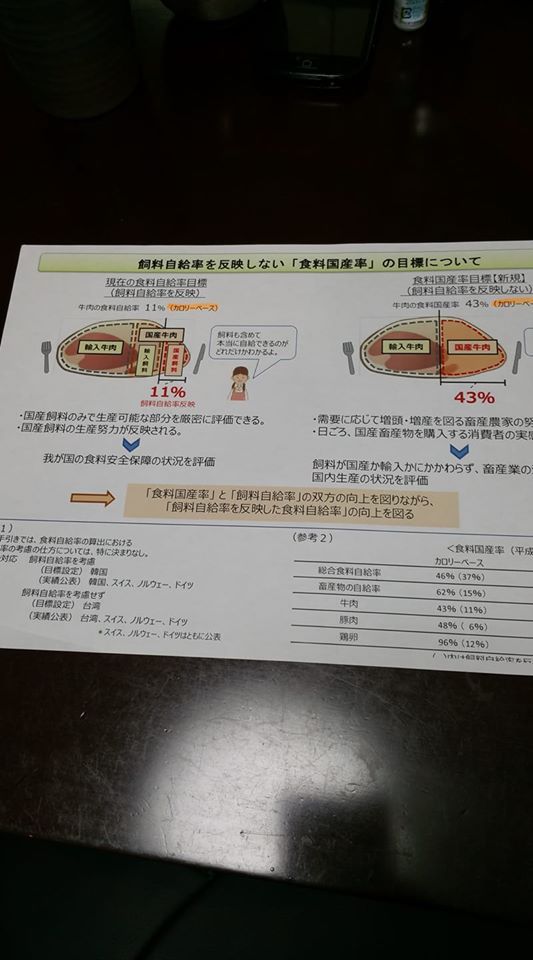
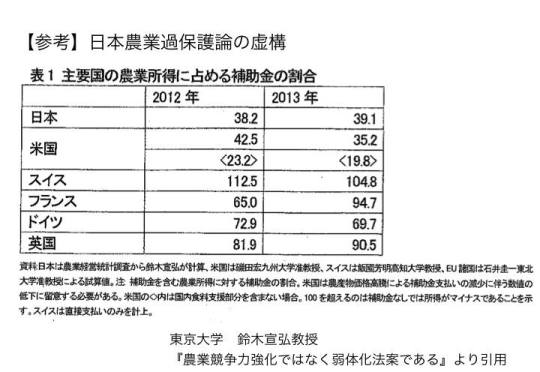
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
山田 正彦
11時間前
恐れていたことが始まりました。お願いです、是非シェア拡散していただけませんか。
新型コロナの感染爆発では、都市封鎖で流通が止まり、東京でも一時スーパーから食料品が消えたように、私達の食料危機が間近に迫っていると言えます。
日本農業新聞一面トップに「新型コロナ拡大で食料生産国」「自国優先し輸出制限」とあります。( 写真参照)
日本の食料自給率はカロリー計算で37%とされていますが、この1年間でTPP、日欧EPA、日米FTAと、食料品の関税を免除又は大幅に引き下げています。
私は農水大臣の時、TPPを締結した場合の日本の食料自給率の影響を試算をさせましたが、14%まで落ち込むという結果が出ました。
こともあろうに農水省、与党は、戦後長い間続けてきたカロリーベースの自給率を、食肉等では輸入飼料を計算から除外したのです。
例えば牛肉の場合、飼料自給率を反映させれば11%ですが、 それを反映させずにカロリーベースでの国産率として、43%に引き上げるというのです。(写真参照)
注目すべきはいずれもカロリーベースになっていることです。
江藤農水大臣も農業新聞では、私にとっては「不本意なことだ���と述べています。
絶対に許されません。
このような理不尽なことをしてまで政府は国民を騙そうとしていることです。
。
新型コロナ感染拡大の今こそ、私たちはグローバル化を見直し、日本国民を飢えさせない為にも真剣に食料安全保障を考えるべき時です。
EU諸国では食料安全保障、食の安全、環境保全の為に、農家収入の8割は直接支払の国からの税金による所得保障です。
米国でも、食料生産の原価と国際相場との価格差を即払い制度で補い、農家収入の4割は国の税金でまかなっています。
私は農水大臣の時に、農業土木予算を削減して農家への直接支払の戸別所得補償を実現しました。
農家への税金による所得補償は農家収入の29%になって、わずか1年で農家所得が17%上がりました。
私の田舎の五島列島でも若い人が 2 人参入を始めたのです。
残念ながら政権交代して戸別所得補償も廃止されてしまいました。
現在農林水産業を生業として希望している若者はたくさんいます。
政策次第では、食料自給率を日本でも60%まで引き上げることは可能です。
コロナ 感染拡大で食料危機を迎えようとしてる現在 日本にとって国家の安全保障同様 食料安全保障は 最も大切なことです。
1 note
·
View note
Photo

2019年を振り返る。前編。みたいな。
何だか人生の中で最も予定がギュウギュウな一年だった気がします。だって全然ブログ書けてないじゃないですか。お久しぶりです。おまたせ(?)しました。トップ画像は橋(だったと思う)から撮った綺麗な夕暮れの写真です。LEDも相まって幻想的な気がしないでもない。
今年は自分の個性才能が何であるのか神様に祈り尋ねつつ、興味のある分野を開拓する年だったように思います。私は神様に出会ってから一応電気系分野に行った身ですが、それまで医療従事者に囲まれていたこともあり、人体を神様の設計製作物として考えて日々を過ごすなどしました。


これは夏休みに実験したモンスターエナジー(近年若人が飲んでるのをよく見かける)で発電した(溶かしている)ときのお写真(インターネットで実験してる人を見かけたのでやってみようということになったため)。0.3Vレンジで0.05Vくらいまで針が振れた。
実験に使った歯は、歯親知らずとか、顎に収まりきらなくて仕方なく抜いたとかそういう、要らなくなった歯を使いました。抜かないと横の歯を圧迫してやばい場合もあるので、痛い人はちゃんと歯医者に行ったほうがいいと思う。あと歯医者は当たりはずれ多いから、事前にリサーチしたほうがいいです。というか、まずは祈りましょう。神様に相談しよう。
紙パックの100%オレンジジュースでやったときもまあまあ発電できたんだけど、水でバシャバシャしたらゆるやかに0Vへ近付いた(しかし完全に0Vまで下がったわけではない)。けれどモンスターエナジーは添加物のせいか水でなかなか落ちなくて歯を磨かないかぎりずっとこんな調子で歯が溶け続けてしまうっぽいことがわかった。やばくないですか。ちなみに一番発電できたのは白ワインでした。神様がお酒を飲むなって仰るのは脳を守る為ですが、歯にもよくないんですよね。
ネットで有名な重曹水洗口はどうなんすかね?ということで重曹水でバシャバシャしたら、一旦0.05Vまでガッと振れたあとに一気に0Vまでしっかり下がった…からまあ確かに、水でゆすぐより効果あるんだと思う。だってニュートラルになって発電が止まるわけだから。
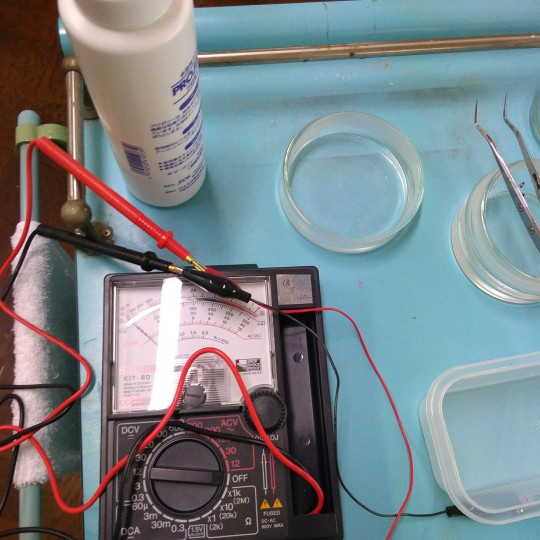
テスタは自分ではんだ付するキットのやつで、アナログなんだけど、電気系の学校行ってた人は授業で作った思い出あったりすると思う。ちなみに私はブザー付けなかった派です。最近は鉛フリーはんだが主流なんだけど、このキットについてくるはんだは鉛入りなのであった。

これも夏の写真なのですが、都内を散歩していたときに遭遇したカレー屋さんの天井で回っていたミラーボールの画像です。いつか行ってみたいなと思っていたカレー屋さんでもあったんだけど、まさか出くわすとは思っていなかったし、こんなにカオスな店内だとも思っていませんでした。ランチタイムで食べ放題だったのですが、オクラが一番美味しかった気がする。
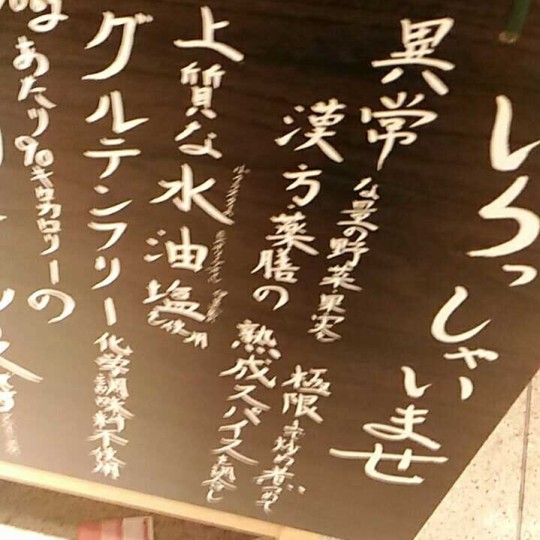
これが店の看板(?)だったんですが、確かに野菜の甘味が効いていておいしかった。お肉は底の方に肉ブロックが沈んでいるので行った人は頑張って発掘してください。

これはビックサイトで開催されたファッション産業機器展に行ったらめちゃめちゃいい天気で、こんなにいい天気なのに私はこれから室内で過ごそうというのか…とか思いながら撮った青空の画像です。
主にミシンとか刺繍機とか裁断機とか編み機とか、ステッピングモータでガガガガガッて感じの展示会です(あ、でもプリンタで有名なブラザーはDCモータ使って制御して費用を抑えてるとかいう噂を聞きました)。もちろん服飾用のCADもあります。ホールガーメントで有名な島精機あるじゃないですか?そこのCADの布の質感表現はものすごかったです。5GになったらYouTuberとかVTuberはもう服買わなくていいんじゃないかしら。好きな服をデザインして取っ替え引っ替えをバーチャルでできるようにすれば楽しそうだと思いました。
こういう規模の大きな会社が集まる会場ではこの先この国はどうなるんだろうねって話をすることが多い。私はもう普通に誰とでも神様の話をしたい気持ちでいっぱいなんだけれど、まあまずはRAPT理論に辿り着いてもらわないと世界について真剣に考えるなんて無理なので、とりあえず政治経済から宗教史までの話を振ったりします。
大体の大人たちが、「勉強になります」とか、「そんなふうにちゃんと未来のことを考えてる若い人たちがいるってわかって安心しました」とか言ってくるんですけど、いや、そこで終わらせないでほしい。自分でも突っ込んで調べてほしい。あと昨日神様が言及されていた老害問題はどこの会社も一緒でした。そして毎回お互い明るい未来のために頑張りましょうって解散する。

ずっと立って喋って過ごすとお腹がすきます。展示会ではみんな水分も摂らずに喋り続ける傾向があるので、私はちょいちょい相手に水分補給を促すんだけど、プロ意識なのか社畜根性なのか水分補給をすると怒り出す老害が身近にいるせいなのか、彼らいつも目の前では絶対に飲まない。脳が…脳が…神様…
あと酸素。酸素超大事だからみんな積極的に酸素を吸っていきましょうね。
ビックサイトからはどういうわけか東京駅に向かうバスが充実しているので東京駅経由で帰ることが多い気がする。東京駅は目的をもってサカサカ動いている人が多いので繁華街の人混みよりは虚無感薄くて気分が楽です。

これは私が東京駅で一番好きな食べ物で、にしんそばっていうんですけど、京都のメニューらしい。でも京都とか修学旅行で一度行ったきりだし、私はこの蕎麦を東京でしか食べたことがない。でも美味しいんですよ。ただ若干高いから2~3年に一度食べるか食べないかって感じです。おまけに瓦せんべい?(ニッキ味)がついてきます。東京駅に寄るまでこのお店の存在忘れてたけど好きな味です。自分で作るとコレジャナイ感する料理の一つといいますか。神様ありがとう。

今年やった普段やらない初めての作業で最も入魂できた作業は溶接だったと思います。熱を入れると金属は熱に引っ張られて曲がってしまうので冶具(じぐ)で固定して溶接する。冶具はだいたいオリジナルで、これは溶接の先生が考案したものなんですが、普通どんな冶具を使うかは公にはしないというか、企業秘密に入るらしい。ふーん。

今回は試作機の車体の溶接だったわけですが、なんだかRAPT理論を学びたての人たちが見たら「うわっ…」ってなりそうなデザインなんですけど、普通にトラス構造です。3が本来神様の数であることと、3つポイントがあるとバランスが取れるという現実には何か意味があると思う。イルミナティが三角を多用したり三位一体にこだわるのは単に神様のパクリなので、そこまでアレルギーになることはないです。
前にもどっかで言った気がしますが、例えばイルミナティが赤や青を使っているからといって(李家なら黄色)、その色を作ったのは神様なのだし、別にイルミナティが使っているからといって好きな色を嫌いにならなくてもいいんです。好きな色を着ればいいってRaptさんも以前仰っていました。イルミナティなど便利な技術を残して滅びゆく人たちなんですし。問題は彼らが滅んだ後どうするか?なのであって。
どうですか。白いボディカラーにすることで鋼材のずっしり感が軽減された気がしませんか…?
しませんか。そうですか。
今年の7月に神様が変化があるよって前もって仰ってくださった回があったのですが、そのひとつに(個人的なことではありますが)、成立した東京都受動喫煙防止条例により都の施設が全面禁煙になったというものがあります。都の関係施設に行ったとき、環境整備かなにかで喫煙所が使えないとかで、どういうわけかエントランスが阿片窟みたいになっていたことがあって、辛みだったんですが、それが無くなったんですよね。正直小躍りするくらい嬉しかったです。だって煙草産業の壊滅はしょっちゅう祈っていることでもあるんだもの。Twitterでも一瞬叫びましたが他のツイートの邪魔になる気がして一旦消しました。神様ありがとうございます!!!
2 notes
·
View notes
Text
茨戸編での尾形は何だったのか あるいは沈黙する破戒神父・鶴見中尉はなぜ死神を自称するのか
ガッツリ本誌176話まで。
1、序 鶴見と尾形の言説の不思議な酷似
父殺しってのは巣立ちの通過儀礼だぜ…お前みたいに根性のないやつが一番ムカつくんだ
ホラ 撃ちなさい 君が母君を撃つんだ 決めるんだ 江渡貝君の意思で… 巣立たなきゃいけない 巣が歪んでいるから君は歪んで大きくなった
こと江渡貝母への発砲については、私は鶴見の言い分をずっと好んできた。ここでの鶴見の江渡貝への殺害の示唆は正しく思える(母君は元々死んでいたから私にも倫理的禁忌感がない)。鶴見は時折とんでもない正しさで私を苦しめる。硬直した仲間の死体に向かって「許せ」と言う男。同じ4巻の回想には、マシュマロでゴールデンカムイには珍しい雲吹き出しで内面が記されていることも教えて貰った。
まるで死の行進曲のようなマキシム機関銃の発射音 この無駄な攻略を命令した連中に間近で聞かせてやりたい
私は鶴見中尉の内面描写が少ないという通説をとてもとても疑問視している。これはもはや読み手の願望に近く、検討するのであれば幅広い読解が必須であろう。ゴールデンカムイの人物は総じて内面描写が少ない。それところか、当初は梅ちゃんと寅次についてあれだけ饒舌だった杉元の内面は、「俺俺俺俺俺俺俺俺俺」という叫びとは裏腹に、「俺」も、その内面も、徐々に欠落を始めてしまったのだ。15巻にはアシㇼパの顔を思い出せていないのでは無いかと思わせるカットすらある。15巻で杉元の『妙案』が宙に浮いたままであるのは象徴的だ。私たちの心が取り残され、疑問は解決されず、1つの核心だけが深まるーー杉元佐一は自分を失っている、と。この話は杉元が梅ちゃんに認識されるような自分を取り戻す話出会った筈なのに(そしてそれを認知できない杉元は、梅ちゃんに自分を認識してもらえるように視力回復に躍起になる)、旅の過程で彼はますます自己を喪失していく。
これから延々と鶴見の話となる。
2、死神の自称
鶴見は意図的に自分を失わないために死神になることを選んだ男である、というのが私の基本的な考えである。それは「脳が欠けているから杉元佐一は自分を見失っている」という説を遠回しに否定する存在である。だいたいにして脳が欠けていなかったら杉元はスチェンカで相手を殴り続けなかったと言えるのだろうか。まぁ、杉元の話はさておくとして、それはおそらく尾形のこういった態度と対照づけることも出来る筈だ。
俺のような精密射撃を得意とする部隊を作っておけばあんなに死なずに済んだはずだ
今となってはどうでも良い話だが
鶴見は「今となってはどうでも良い」をやり過ごさなかった男である。一度は鶴見の腹心の部下であった筈の尾形は、戦後も心を戦場に置いてきたのではなく、戦場の側を自らに引き寄せようとする鶴見(や土方)にたいして冷笑的な視点を浴びせ続ける。
仲間だの戦友だの……くさい台詞で若者を乗せるのがお上手ですね、鶴見中尉殿
変人とジジイとチンピラ集めて 蝦夷共和国の夢をもう一度か?一発は不意打ちでブン殴れるかもしれんが政府相手に戦い続けられる見通しはあるのかい? 一矢報いるだけが目的じゃあアンタについていく人間が可哀想じゃないか?
ここでの尾形の「正しさ」は、鶴見の「正しさ」とは違い私の心の拠り所になっていた。尾形が「いい人になれるよう 神様みていてくださろう」に適合するような行動をすると私はいちいち救いを求めてしまい、彼の行動がいつも噛み合わず言説が否定されるのを見てこの男の救いのなさに頭を抱えていたのだ(まさに本誌の『176話 それぞれの神』で現れた関谷の神にすがる心情である)。そして鶴見は、月島をある意味救ったが、尾形を救うのには失敗した。むしろ鶴見は尾形を利用するだけ利用していたように思えた。
尾形と鶴見と親殺しは4度交錯する。江渡貝。花沢中将。月島。ウイルク。
外敵を作った第七師団はより結束が強くなる 第七師団は花沢中将の血を引く百之助を担ぎ上げる 失った軍神を貴様の中に見るはずだ よくやった尾形
たらし めが…
尾形にとって鶴見の取り巻きであることが幸せなのかどうかは分からないが、他の造反組や、あるいは役目を見つけて下りた谷垣とは異なり、尾形は鶴見を『切』った、数少ない人物である。尾形は、月島同様戦前から鶴見の計画に加担していたのにもかかわらず、鶴見中尉から月島と同じ様に扱われなかった人間でもあった。
江渡貝の母殺しに関しては鶴見にも見るところがあると考える私も、この鶴見の花沢中将殺しにおける尾形の扱いが原因で、長らく鶴見のことをよく思えずにいた。さらに15巻149話、150話で鶴見が月島を父親殺しから救った(?)事実や、本誌にて戦前から尾形が鶴見の命で勇作を篭絡および殺害しにかかっていた事が判明した事を鑑みて、鶴見の風見鶏的態度に辟易していた。加えて言うのなら、ゴールデンカムイの中に時折現れる聖書に基づく表象や、それに対するキリスト教に軸足を置いた読み解き方というのは私が最も苦手とするところであったが、一方で鶴見が71話の表紙にて不完全に引用された聖書の一節を通じて『にせ預言者』(マタイ7:15)であると示されていることを筆頭に、いくつかのキリスト教的モチーフを(ところどころで反語的に)取り込んだキャラクターであることも否めずにいた。
にせ預言者を警戒せよ。彼らは、羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その内側は強欲なおおかみである。(wikisorceの口語訳より)
そもそも鶴見もまた、その他大勢のキャラクターおよび我々と同様、多面的な人物として描かれている。偽預言者であり、彼の演説はヒトラーのパロディとして描かれるほど(作者によるとミスリードらしいが。Mislead? Misread?)だ。そして、外敵に対しては自らのことを死神と称しながらも、仲間に対してはむしろ告解をうける神父の役割に近いものを演じ、坂本慶一郎とお銀の息子の前では聖母マリアとなり、月島や杉元と共有する傷は、スティグマと見ることも出来るだろう。キャラクターデザインには、明らかに鶴の要素が取り入れられている。さらには編集者のつけた仮面を被る悪魔、という表象ですら許容される向きにあるのだから、鶴見も大変である(悪魔という呼称は江渡貝の母によっても齎されている)。私がこの鶴見という、出自も分からぬいろんな人形が載せられたクリスマスケーキを長らく食べる気になからなったのは、そこに土俗の信仰と西洋的信仰が混ざり合って、あまつさえ鶴や死神の細工菓子まで載っていたことを考えると不思議ではあるまい。
私はどこかで、にせ預言者としての鶴見、という表象の正当性についてすら、もしかして議論になるのではないかと辟易している。不信の徒である私の読み解ける事項など限られていることは重々承知だし、そもそも私はゴールデンカムイを読み解くときに、作中での記載を第一に考え、外的世界に存在するマキリで作品をチタタプしない様に細心の注意を払ってきた。最近ラジオが出現したことで、ようやく文言に尽くし難かったそのバックグラウンドをまとめる事ができたような気がするが、私は解釈を取り払った読み方が先にくることを好むし、そもそも『らしさ』への拘泥は私の目を曇らせるのではないのかと考えている。とりわけキリスト教を扱う時には、竹下通りで千円で買った十字架のアクセサリーを身につける女の子のようにならないためには、むしろ触れずにいるのが一番なのではないかと長く考えていたものだった。それが私の最低限の敬意の示し方であった。
とはいえ、キリスト教と日本の間での困難を感じていたのは何も私だけではなかった。多くの作家がそれに苦しみ、むしろその困難を以って、日本を描き出そうとする作家もいた。もちろん私の考えでは、作家の作るものに於ける宗教的解釈は、仮に異端であっても一つの芸術作品になり得る一方で、評論家の宗教的解釈の異端さは、単なる誤読として片付けられる可能性がより高く、慎重を期するものであるのだが…。しかし私はだんだんと、そういったキリスト教と日本の狭間で描かれた作品であれば、鶴見像を見出せるのではないかと思う様になっていった。もっと言えば、私がキリスト教的表象を前にして立ち竦む、その逡巡自体を語ることならできるのでは無いか、と思う様になったのだ。
「にせ預言者ー貪欲な狼」「ヒトラー(ミスリード)」「マリア」「告解を受けるもの」、そして「聖痕」…を持つ「悪魔」で「死神」…の「鶴」をモチーフとした「情報将校」。
「にせ預言者ー貪欲な狼」に対してのとても簡潔な読み解き方は、単に鶴見が偽の刺青人皮を作ろうとしている、というものである。もう少し解釈を広げれば、鶴見が北海道の資源を活用して住むものが飢えない軍事帝国を作ろうと嘯くことであろうか。
軍事政権を作り私が上だって導く者となる お前たちは無能な上層部ではなく私の親衛隊になってもらう
これはヒトラーとして描写されていること(繰り返しとなるが、作者によるとミスリード)でもあり、ヒトラーとはたとえばその土地の出身では無いという点などでも共通点が見られる。実際には北海道はロシアと違って天然資源には恵まれておらず、またその後の軍事政権というトレンドの推移、戦争特需にも限りがあることを考えれば、金塊を持ってしても独立国家としての存続がおよそ不可能であっただろうことは見て取れる。
3、マリア、そして告解を受ける破戒的神父としてのあべこべさ
面白い事に、聖母として描かれる鶴見はほとんどもって無力であり、子をアイヌ的世界に属するフチに預ける事しか出来ない。
一方で「告解を受けるもの」、すなわち神父としての鶴見は極めて破戒的である。鶴見への告解は子羊たちの救済を意味しない。鶴見は誰とも共有すべきではない告解を共有することで、結束を強める「見返り」を期待する者である。教会に於いては告解の先には主による赦しがあることが期待され、十字架に架けられたキリストの苦難がそれを象徴していた。一見してキリストの苦難は鶴見の告解室においては「戦友は今でも満州の荒れた冷たい石の下だ」で代替されている。しかし鶴見の厄介さはその様な単純な構造におさまらないところである。一方で満州を彼らのいる北海道と分けて見せるそぶりを見せながら、時として「満州が日本である限り お前たちの骨は日本人の土に眠っているのだ」と口にし、それどころか戦争の前から月島・尾形らと何かしらの謀略を図っていたことすらわかり、『我々の戦争はまだ終わっていない』という悲壮にも満ちた決意が段々と『戦争中毒』である鶴見のハッタリであったことに我々は気づかされる。
彼への告解は何もかもがあべこべであり、神父の皮を被りながら極めて破戒的である。洗礼後ではなく洗礼前――つまり第七師団入隊前――の罪を、谷垣に至ってはあまつさえ衆人の前で告白させ、傷を共有させる。告解が終わった後に司祭は「安心して行きなさい(ルカ7:50)」というものだが、鶴見は自分に付いてきてくれるように諭すのだった(「私にはお前が必要だ」)。
破戒というのはあまり神父に使う言葉ではない。それでも、島崎藤村の『破戒』は、聖書のモチーフを色濃く反映させながら、被差別階級とその告白を描いた作品だったのだから、やはり破戒、と言う言葉はここにふさわしい気がする。
『破戒』において島崎が真に目指したのは、「身分は卑しくてもあの人は立派だから別」という、個人の救済を批判することであった。そのような個人の救済は、いわば逆説的に被差別階級の差別を補強する、矛盾した論理であったのだ。
この論理は2018年にも広く流通した。杉田水脈氏がLGBTに生産性がないと発言したことに、一部の人が、アラン・チューリングやティム・クックといった生産性のあるLGBTの名前を挙げて反論を試みたのである。このような言説が流布した後、リベラル派は、自分たちの身内の一部に対して、「生産性のないLGBT」が仮にいたとしても、その人たちも等しく扱われなければならない、とお灸を据えなくてはならなかった。
これこそ私が鶴見の恣意的な月島の依怙贔屓を、そして尾形の利用を、いまだに批判すべきだと考える���由である。
外敵を作った第七師団はより結束が強くなる 第七師団は花沢中将の血を引く百之助を担ぎ上げる 失った軍神を貴様の中に見るはずだ よくやった尾形
誰よりも優秀な兵士で 同郷の信頼できる部下で そして私の戦友だから
私はこの差異に於いて鶴見を許す気は毛頭ない。それは、私が谷垣を愛しながらも、アシㇼパを人質に取った事を未だに許していないのと同等である。谷垣を受容するに至った経緯が、私に鶴見というキャラクターを拒絶する理由は最早ないことを教えてくれた。そしてよくよく読み解いてみると、この、一見すると月島への依怙贔屓ですらあべこべなような気すらしてくるのであった。
4、主格の問題 ー 「死神」という主語について
ここにおける問題は『主格』に於いても明らかだ。鶴見が月島に話す時の態度は、軍帽を脱ぎ、主語は「私」、時折「おれ」と自らを自称する親しみのあるものだ。その一方でしかし尾形へは軍帽またはヘッドプロテクター(仮面)を装着して主語をあろうことに「第七師団」に置いている。尾形の父殺しについては未だに謎が多く、発端が誰なのか(花沢中将自身・尾形・鶴見)、なぜ花沢中将が死装束を身につけられたのかを筆頭に、また鯉登少将への手紙をいつ誰が書いたのかも問題となろう。よって、尾形が鶴見への忠誠心を失いつつも自らの父殺しの願望を成就させるために鶴見の案に乗っただけなのかどうかは、よくわからない。とはいえ、自らが時に「どんなもんだい」と誇示さえする狙撃手としての腕を買わなかった第七師団への離反は、狙撃手と対称をなすような旗手としての勇作を評価し、勇作の殺害作戦を撤回した鶴見への、勇作の狙撃をもっての”謀反”を契機として、花沢中将死亡時に、すでに尾形の胸の内にあったと考えるのが自然であろう。加えて尾形も、どこかの段階で破戒的神父・鶴見への告解というステージを踏んでいたことも想像に難くない。
このように読み解いていくと、単に鶴見は月島にだけ心を許しているようにも読めるのだが、そうは問屋が卸さない。まずはいご草への呼称問題である。月島は自らのことを『悪童』ではなく『基ちゃん』と呼ばれる事に意義を見出しているのに、彼女の事を『いご草』と表現する(本当は鶴見との会話の上でも名前で呼んでいたのだろうが)。さらにそれを受けて鶴見は『えご草ちゃん』と彼女の非人格化を進め、さらには自らの方言も決して崩さないことで会話の主導権を握る。加えて、私は長らく、江渡貝と炭鉱での爆発に巻き込まれ、煤だらけで雨の中を帰ってきた月島への労いの少なさにも違和感を抱いていた。これも一つの「あべこべ」なのかもしれないし、あるいは月島への圧倒的信頼が根底にあり、彼なら心配に及ばないと考えていただけなのかもしれず、もしくは鶴見がヘッドプロテクターという仮面をつけた時の「死神」としての決意の表れかもしれない。
「死神」を自称すること。
そもそもにおいて、我々が日々感じている他人への判断、偏見、予断の集合体、例えば、あの人は秋田出身で大柄で毛が濃く少々ドジなマタギである、と言われたことによって”我々が想起する予断と偏見”と、漫画を切って話すことはできない。小説よりもさらに視覚的な漫画という分野においては、ステレオタイプと”キャラ”立ちするための記号化というのはほとんど隣り合わせにあり、分離することがむずかしい(この論だけで何百ページも割かなければ説明できないであろう)。それでも、だ。この作品のキャラクターほど、「あの人はこう言う人だから」と型に嵌める行為が適切ではない作品もないのではないか。
作品内で繰り返される「あなた どなた」という問い、あるいはその類型でのマタギの谷垣か兵隊さんの谷垣かどっちなのか、山猫の子は山猫なのか、という問い、そしてその問いに対するわかりやすすぎる「俺は不死身の杉元だ」という回答を、繰り返しながらもゆるやかに否定し続ける世界線の中で、「私はお前の死神だ」という言葉は鶴見の決意と選択を象徴しながらも、結局のところ杉元の「不死身」の様にアンビバレントな価値を持つ言葉の様にすら思える。
鶴見と杉元はスティグマを残す男である点も共通している。鶴見は月島が反射的に自らを守った際に微笑み、二人はその後スティグマータを共有する人物になった。
杉元と傷の関係については未だに謎が多い。彼自身が顔につけた傷についても多くが語られる事はない。時間軸として1巻以降で彼が顔に受けた傷跡はかならず治っていくのに、彼が周りに残していく傷は確実に相手に痕を残していく。なぜ尾形が撃った谷垣の額の傷跡は消えたのに、杉元が貫いた頬の傷はいつまでたっても谷垣の頬から消えず、尾形の顎には縫合痕が残り、二階堂は半身を失い続けているのか、分からないままだ。ずっと分からないままなのかも知れない。
そしてウイルクもまた、顔に傷を残す男性である。傷を残しても役目を終えない男たち。聖痕と烙印ーー両極な語義を内包するスティグマータを共有し合う男たち。それはかつての自己からの変容であり、拭い去れない過去の残滓でもある。そしてそれは、作中の男性キャラクターたちが「視覚」を中心として動き回ることと決して無関係ではないが、ここではその論に割く時間はない。
「あなた どなた」に対してあれほど口にされる「俺は不死身の杉元だ」を“言えない”こと。この言えない言葉について、私はどれだけの時間をラジオに、文章に、割いて来ただろうか。そのことを考えると矢張り、「あのキャラクターはこうだから」と言う解釈がいかに軽率にならないかに気を使ってしまう。たとえば鶴見においては、まさに本人が、「俺は不死身の杉元」よろしく「私はお前の死神だ」と言っているのだから、もうそれで良いではないかと言う気がする。「不死身の杉元」は杉元が不死身ではないからこそ面白みの増す言葉であるように、今まで見てきた通り鶴見も何も「死神」だけに限定するには勿体無いほどの表象を持っているが、その中で杉元が、ある種の悲痛な決意を持って、半ば反射的に「不死身の杉元」と口走る一方で、「死神」にはもっと計画的な、そして底が知れぬ意志の重みを感じるのは私だけだろうか。「不死身の杉元」にも感じないわけではないが、「死神」はより一層”選択”であった、という感じがする。偽の人皮を、扇動を、月島を、傷を、周りに振り回されることなく自ら道を切り開いて”選ぶ”という高らかな宣言が、「死神」である、という感じがする。
5、「運命」と「見返りを求める弱い者」
『役目』を他人に認めてもらうことが作品内でどれくらい重要なのかは難しいところだ。谷垣源次郎が役目を見出し、果たす事を体現するキャラクターとして描かれ、見出す事、果たす事の重要性は単行本の折り返しから我々に刷り込まれているとは思うが、その結果としての他者承認は必須なのだろうか。杉元や尾形が他者承認を執拗に追い求めている様に見える一方で、白石が、シスター宮沢、熊岸長庵、アシㇼパ、杉元と、認めないー認められないことをずっと体現し続けているのもまた面白い。
長年の谷垣源次郎研究の成果として、谷垣の弾けるボタンは、インカラマッが占いきれない予測不可能性と、それを元にした因果応報やら占いに基づく予測的行動の否定の象徴であると気付いて、私はだいぶスッキリした。網走にいるのがウイルクである可能性は彼女の占いに基づくと50/50であるが、これがウイルクではないと100/0で出ていたとしても、彼女は網走にそれを確かめに行かなくてはならなかっただろう。それは北海道の東で死ぬと知っていながら網走に行く選択をするのと同根であり、いずれボタンが弾けとぶと知っているからと言ってボタンを付けない理由にはならないこと、またはボタンが弾け飛ぶからといって、彼女が谷垣に餌付けするのをやめはしないことと共通する。そもそもにおいて自分の死期を悟っている、ある種の諦念を持つインカラマッの行動は、途中から愛に近しいものを手にいれるにつれ、淡い未来への希望と言語化されない献身を併せ持つものになりつつあった。未来への希望と言語化されない献身……そういったものの為に嘘をつくことすら厭わない女たちを総括して、二瓶は『女は恐ろしい』と称し、自分たちの行動原理では理解不能なものとして警戒していたのだった。二瓶の持つ『男の論理』は、明白な見返りを望むものだったからだ。谷垣もその例に洩れず、インカラマッは怪しい女だからといって救わずにいようとすらしたし、彼女と打ち解ける様になった後も、その『女の論理』の如何わしさを感じ取って、彼女と寝る際には、やましさから『男の論理』の権化である二瓶の銃を隠し、彼女と寝た後には、その求愛は彼女を守らせるための行動ーーすなわち明白な見返りを求めた打算ーーだと考えすらしたのだ。もちろん、彼女自身のかつての行いによって、それを谷垣に見えづらくして、当たりすぎる占いが谷垣の心を遠ざけているのも皮肉であるし、その当たりすぎる占いが全て占いではなかったことは皮肉であった。妹を亡くしていること、アシㇼパの近くに裏切り者がいること、東の方角が吉と出ていることは、すべてインカラマッが既に知っていたことであり(探しているのはお父さんだという占いも同等)、キロランケの馬が勝つかもしれない可能性や、三船千鶴子の場所を言い当てるだけの能力を持ちながら、占い師としての力を使わず内通者として動いたことで、彼女自身が彼女を『誑かす狐』に貶めてしまっていた。彼女が溺れる話の表題が『インカラマッ 見る女』なのは、そんな彼女の人間性の回復を示唆しており、それは彼女自身が占いから逃れて、弾け飛ぶボタンの行き先ような、予測不可能性に身を委ねることであった。
「最悪の場合、こうなるかもしれないからやらないでおこう」だとか、「相手がいずれ自分にそうしてくれるはずだから、今こうしよう」という報酬と見返りの予測に基づく行動とその否定は、ゴールデンカムイを読む上で極めて重要な要素だと考える。
予測に基づく行動の抑制を行わない登場人物たちの決定は、残念ながら愛のみではなく、殺しと暴力も含まれる。即断性という言葉で言い表すこともできるかもしれない。私はこれをよく『反射的』という言葉を用いて説明している。私に言わせれば、極めて幼稚な、原始的な論理であり、月島が鶴見を助けたのもこれに分類される。それで鶴見が満足をしたのは、それはそれで鶴見の孤独を浮き上がらせる。反射とは、結局のところ「そうするしかなかったんだ」という男たちの言い訳に使われるものでもであり、杉元が初めて尾形に会った時に川に突き落とした時の口ぶりと100話の口ぶりなどは、まさにその代表例である。杉元という人物の中では、そのような反射的な即断性と、殺したものの顔をずっと覚えているという保持性の二つの時間軸が交差しており、その内的葛藤が我々を強く惹きつけている。そしてそこから、杉元が持つ時間軸は「地獄だと?それなら俺は特等席だ」「一度裏切った奴は何度でも裏切る」という回帰性、または因果応報性にまで波及するのだが、その思考の独特さは「俺は根に持つ性格じゃねぇが今のは傷ついたよ」という尾形の直線性と対をなす。尾形は直線的に生きていかなければ耐えきれない程の業を背負っている。それでも過去は尾形を引き止めに来る、杉元が梅ちゃんの一言を忘れられないのと同等に。
即断性/反射的の反語はなにも計画的/意図的なことだけではない。極めて重要な態度として、保留があり、現在この態度はインターネットが普及して、即時的な判断とその表出のわかりやすさが求められるようになったことで、価値が急速に失われつつあるが、明治期においても軍隊の中では持つことが叶わなかった態度であっただろう。保留を持つキャラクターの代表格こそ、白石由竹であることは言うに及ばないであろう。
保留を持ち得なかったものたちが代わりに抱くのが反発か服従であり、造反組は勿論のこと、気に入らない上官を半殺しにした杉元と、諦念に身を任せて問いすら捨てた月島を当てはめることができるであろう。
その即時性や保留や反発や服従を生み出すのが、自らを死神に例える鶴見であり、鶴見はまさに意志の人、意図の人、計画の人である。そして仲間に対して「相手がいずれ自分にそうしてくれるはずだから、今こうしよう」という見返りを期待して関係を構築する人である。これも、私が彼を苦手としていた理由の一つであった。しかし繰り返しになるが、鶴見の”選択”は、「即時性や保留や反発や服従」を生み出す。そして本編では、どちらかというと出だしから鶴見からの離反者ばかりが描かれ、人たらしの求心力を持つ魅力的な人物であるということを読み解くまでに、私はじっくりと長い期間をかけなければならなかった。「先を知りたくなる気持ち」「ページをめくる喜び」を強く求められる男性向けの週刊連載において、保留の態度を試されていたのは、読者の方であったのだ。
それでもなお私は、裏切られる鶴見、離反される鶴見というものを立ち返って見るにつれ、この男の立場の脆さというのを改めて重要な要素として捉えるようになったのだ。
それは「死神」とは遠く、自らの周りを賞賛者で固めた男の、ともすれば惨めとすら言える姿であった。そして私は遂に「死神を目指す弱い男」、鶴見を見出したのであった。
そこで大事なのは、鶴見が「死神」になろうとしている、というただ一点であった。それはおそらく尾形が銃に固執するのと同等の、自己決定権のあくなき希求であった。
11巻で尾形は言った。「愛という言葉は神と同じくらい存在があやふやなものですが」。その11巻で鶴見は愛を見出していた。「あの夫婦は凶悪だったが…愛があった」。そして同じ巻で、鶴見はふたたび高らかに宣言したのだ、「私は貴様ら夫婦の死神だ」ーーと。
以上の文章は既に3週間以上前に書いたものだったのだが、本誌ではさらに「神からの見返りを求める弱い男」として関谷が登場した。この「弱い」という言葉は私の元ではなく、イワン・カラマーゾフが『カラマーゾフの兄弟』の一節『大審問官』にて述べた、大部分の信者を指す言葉である。さらに本誌では、私が谷垣とインカラマッの関係に見ていた「予測不可能性」を、ある意味逆手に取った様に、自分への逆説的幸運をもたらす人物として門倉が描かれ始めた。私は一読して彼は谷垣の類型であると感じ取ったが、それは即ち尾形の「かえし」である事も意味することを忘れてはならない。尾形はキロランケが神のおかげだと言った直後に、「俺のおかげだ」「全ての出来事には理由がある」と神の采配を否定するような男だからだ。
すべてのあやふやな存在に輪郭を持たせ、弾け飛ぶボタンを先にむしり取っておこうという「覚悟」。その覚悟の名前が「死神」。私にとっては、それが最もしっくりくる「死神」の捉え方であるような気がした。
覚悟については鶴見の口から15巻でこのように語られる。
覚悟を持った人間が私には必要だ 身の毛もよだつ汚れ仕事をやり遂げる覚悟だ 我々は阿鼻叫喚の地獄へ身を投じることになるであろう 信頼できるのはお前だけだ月島 私を疑っていたにも拘らず お前は命がけで守ってくれた
そう思うと尾形と月島の扱いの差にも、月島へのあの苦しい弁明も納得がいくような気がした。
6、月島への『言えなかった言葉』
話は最後まで聞け 月島おまえ… ロシア語だけで死刑が免れたとでも思ってるのか?
初読時にはこの物言いは癪に障った。そこまで自明のことだと思うのなら。そうやって父の悪名を利用して月島を助けたのなら。月島にそう言えばいいじゃないか、と思っていた。しかしそれは、結局の所「ゴールデンカムイ」の根底を為す、『言えなかった言葉』の一種であったのだ。9年間、鶴見は自分の工作を月島に明かすことが出来なかった。それは杉元が、いずれ梅子に再び見出してもらう未来を目指している期間(つまり本編)よりもっともっと長い時間であるような気がする。その事実だけがまずは大事で、それに対して色々な意味づけをする前に、私は鶴見が”言い淀んだ”事実に向き合わなければならなかった。私は鯉登でも宇佐美でもないのだから、鶴見を信望する必要などなかったのだった。裏切りたくなるほど痛烈に、その存在を意識すればいいだけであった。
そして、理由はどうであれ『言えなかった言葉』を9年間抱えていた鶴見には、やはり弱さという単語が似合った。もし、もし本当に、月島の父親の家の地下から掘り出されたのが白骨であったのなら、10日前に行方不明になったいご草ちゃんが月島が逮捕されてすぐに掘り出されたのだから、白骨化するのには時間がかかりすぎるので、ジョン・ハンターよろしく骨格標本を作るような細工でもしない限り、髪やら服やらで誰だかすぐに分かってしまう。だから、きっと鶴見の工作は説得力のある良く出来たものであったのだが、それですら、月島に言えなかった、という事実の確認。
月島をどうしても手元に置いておきたかったのだろう。「告解を受けるもの」であった鶴見が月島の前では弁明をする男に成り下がる。それでもそこで「スティグマ」が2人を繋ぎ止める。鶴見は言った。「美と力は一体なのです」。そして彼の言葉にある”美”の定義は彼の顔の傷をも厭わないものであった(二階堂が本当にヒグマを美しいと言ったかどうかは大きな疑義が残るが)。この点に関しては、私はずっと鶴見の考え方に感心させられていたものだった。自らを美しいと定義してしまえば、もはや何も恐れるものはない。
ますます男前になったと思いませんか?
これは鶴見が自らの容姿に(杉元のように)無頓着であると��、または本当にますます男前になったと考えている訳��はない、と考える。15巻で大幅に加筆された鶴見のヘッドプロテクター装着シーン。
どうだ 似合うか?
鶴。
杉元の言を借りよう。
和人の昔話にも「鶴女房」って話があってね 女に変身して人間に恩返しするんだけど 鶴の姿を見られたとたんに逃げていくんだ
鶴の頭部を模したヘッドプロテクターは、おそらく杉元が被り続ける軍帽と同種のものである。とはいえ杉元は軍帽をなぜか捨てられない男として描かれているのに対し、鶴見はむしろ「覚悟」の顕在化としてヘッドプロテクターを装着している。そしてその内部には、自ら御することすらできない暴力への衝動があり、その暴力を行使する時に、そのヘッドプロテクターからあたかも精液/涙のように変な汁が”漏れ出る”。編集の煽りによるとこれは「悪魔」の「仮面」である。たかだか煽りの一文を根拠に、悪魔かどうかを議論するのはかなり難しいが、それでもやっぱりヘッドプロテクターが「仮面」であるというのは、意を得た一文と言って良いのではないだろうか。それは不思議にも姿を隠す鶴の昔話に符合する。
正直に言おう!鶴見が悪魔だったらどれだけ解読が楽だった事か!原典が山ほどある。しかも悪魔は二面性を持つ。ファウスト 第一部「書斎」でメフィストフェレスはこのように話す。
Ein Teil von jener Kraft, 私はあの力の一部、すなわち
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. 常に悪を望み、常に善をなすもの。
Ich bin der Geist, der stets verneint! 私は常に否定し続ける精霊。
Und das mit Recht; denn alles was entsteht, それも一理ある、
Ist wert dass es zugrunde geht; すべてのものはいずれ滅びる。
Drum besser wär’s dass nichts entstünde. であれば最初から生まれでない方が良かったのに。
そしてイワンの夢の中で、スメルジャコフは「メフィストフェレスはファウストの前に現れたとき自分についてこう断じているんです。自分は悪を望んでいるのに、やっていることは善ばかりだって。」と、ファウストに言及するのであった(第四部第十一編九、悪魔。イワンの悪魔)。
このファウストの素敵な一節にはいずれ触れるとして、鶴見は悪魔を自称はしないことを念頭に先を急ごう。
この情報将校を語る上で、最も大事な事象は彼が自身を「死神」と定義することだと私は考えている。そんな中で、数々の日本的ーキリスト教的装飾に彩られ、たとえば「スティグマ」というキリスト教的文脈で鶴見に聖痕/烙印という聖別を与えることを���く厭わない私からも、「死神」がキリスト教的であるかどうかには首をひねってしまう。よしんばキリスト教のものを作者が意図していたとして、「死神」という訳語を当てるのは、デウスに大日という訳語を当てたザビエルの如き、弊害の多いものであるように思える。もしかしたら鶴見はpaleな馬に乗った男であり、隣に連れるハデスが月島か何かであり、第一~第三の騎士が鯉登、宇佐美、二階堂のいずれかの人物であるのかもしれないが…それにしても示唆する表現が少なすぎるのだった。このことは私を悩ませた。というのも鶴見をキリスト教的に読み解くという行為は、私にとって禁忌だからこそある程度の魅力を感じさせるものだったからである。ましてや鶴見を「弱い神」と位置付けるならなおのことであった。日本におけるキリスト教的神は、決して強者たりえない。強者だと感じていたらこの程度の信者数には収まっていない。そもそもゴールデンカムイには何となくキリスト教を思わせるような描写が散りばめられており、それでもいかにそれが合致していてもその文脈で語る必要はないのではないかと思われる事象も多々ありつつ(たとえばアシㇼパによる病者の塗油をサクラメントとして読み解く必要はないと感じるなど)、その禁じられた評論とやらを、試しにやってみるとこうなる。
そもそもにおいてまず、キリスト教に触れること自体に禁忌感がある、というのは既に記した通りだ。「スティグマ」「マリア」一つに取っても、私にとっては言及する前に、日本的キリスト教観について長大な考えを巡らせることがそもそも不可欠であった。キリスト教自体は現地の土俗宗教を取り込んで来たが、こと日本においてはそれすら叶わず、日本的キリスト教観というのは、おおざっぱに言えば日本の多神教感との習合ということが出来るかもしれないが、むしろ、日本の側がキリスト教の本質を捉えることなくキリスト教を取り込んでいく、という逆転現象の方が著しいほどだ。
評論家における教義の解釈のズレは、ともすれば不勉強や読み違えとたがわない為、私も慎重にならざるを得ない。しかし創作者における教義や解釈のズレは、等しく芸術となり得る力を持っているのであって、私はそれを読み解いて良いのかどうなのかずっと逡巡していたのだった。日本に於いてキリストを描くことの可能と不可能は、作家自身がキリスト者であった遠藤周作が身をもって体現していた。遠藤の描く神は一部で絶賛を受け、2016年にマーティン・スコセッシが映画化したことも記憶に新しいが、一方でカトリック協会の一部からは明白な拒絶を受けた。そして彼の描く神は、誰かを救う力を持つような強い神ではなく、弱い誰かに寄り添うような神であった。
鶴見は「愛という言葉は神と同じくらい存在があやふや」であるものに、覚悟を持って形を付けていった。それは日本人に許された特権であるかもしれない。ゴールデンカムイの作品世界の中で「神」「運命」「役目」が目に見えぬ大きな力としてキャラクターを飲み込む中(そしてそれが本誌に置いてリアルタイムでますます力を持とうとし、ともすれば谷垣のボタンすらそれに組み込まれてしまうのではないかという恐怖に怯えながら)、鶴見はひたすらに自律できる人生を求めている。運命を意のままに操ることへの飽くなき渇望。その裏返しとして彼は大嘘つきとなった。
そんな大嘘つきの鶴見ですら、嘘すらつけなかった事実が月島をあの手この手で自らの手元に置いておこうとした事実であった。9年間も彼はその努力をひた隠しにしようとした。それは大嘘つきの死神に存在した「俺は不死身の杉元だ」と同義の『言えなかった言葉』であった。奇しくも遠藤周作は、まさにこの国での神との対話の困難さについての一片の物語を、まさしくこのように著したのである――『沈黙』と。
対話の不可能さには逆説的な神性がある。
それはアイヌのカムイにおいても同じである。だからこそ送られるカムイに現世の様子を伝えてもらおうとし、それでもバッタに襲われた時にキラウシは天に拳を振りかざして怒ったのだ。しかしカムイとキリスト教的神の間には決定的な違いがある。キリスト教的神は全てを統べているのだ。そして「知って」いる筈なのだった。長年このことは日本の作家を悩ませていた。遠藤の『沈黙』においても、主人公は繰り返し、聖書におけるユダの記載、そして「あの人」がなぜユダをそのように取り扱ったのかを問うている。
だが、この言葉(引用者注:「去れ、行きて汝のなすことをなせ」)こそ昔から聖書を読むたびに彼の心に納得できぬのものとしてひっかかっていた。この言葉だけではなくあのひとの人生におけるユダの役割というものが、彼には本当にところよくわからなかった。なぜあの人は自分をやがては裏切る男を弟子のうちに加えられていたのだろう。ユダの本意を知り尽くしていて、どうして長い間知らぬ顔をされていたのか。それではユダはあの人の十字架のための操り人形のようなものではないか。
それに……それに、もしあの人が愛そのものならば、何故、ユダを最後は突き放されたのだろう。ユダが血の畠で首をくくり、永遠に闇に沈んでいくままに棄てて置かれたのか。(新潮文庫 遠藤周作『沈黙』p.256)
当時若干25歳の萩尾望都が抱いたのも全く同じ疑問であった。編集から1話目にて打切りを宣告されるも、作者自ら継続を懇願した結果、その後少女漫画の祈念碑的作品として今尚語り継がれる『トーマの心臓』において、萩尾は以下のようなシーンをクライマックスに持ってくる。
ーーぼくはずいぶん長いあいだいつも不思議に思っていたーー
何故あのとき キリストはユダのうらぎりを知っていたのに彼をいかせたのかーー
“いっておまえのおまえのすべきことをせよ”
自らを十字架に近づけるようなことを
なぜユダを行かせたのか それでもキリストがユダを愛していたのか
その後も「知ってしまうこと」は萩尾望都の作品の中で通底するテーマとして描かれ続け、時にそれはキリスト教的なものとして発露した。『トーマの心臓』の続編『訪問者』はもちろんのこと、『百億の昼と千億の夜』ではまさに遠藤が指摘した通りの役回りをキリストとユダが演じ、そして敢えてキリスト教的な赦しを地上に堕とした作品として、『残酷な神が支配する』を執筆することとなる。
私は日本に生まれた非キリスト者であるからこそ、むしろ不遜に、無遠慮に、宗教的な何かについて切り込んでいけるのではないかと常々感じていた(例えば私にとっては聖典とされる教義の中でも聖書に記載がないのではないかと思う箇所がままある)。そしてその鏡写しのように、概して宗教が封じ込めるものは懐疑と疑念と疑義と疑問ではないか、と考えてきたのだった。
神とは何か、愛とは何か。
そういった問いを挟まないために自らが神になることを決めた男。
それはおそらく弱さを自認した上での自らへの鼓舞であった。
はたして私のような不信の徒が、どのような表象にまで「神」を見て良いのか、いつも憚られると同時、そしてその弱い神をまさに、ドストエフスキーは『白痴(Идиот-Idiot)』として現代化を試みたのではなかったか、という思いがある。『白痴』という和訳は今からするとやや大袈裟なきらいもあるが、それでもやはり、罪なく美しい人間というのは、当時のロシア社会において『Идиот』としてしか発露し得ないというドストエフスキーの悲痛でやや滑稽な指摘は、裏を返せば知恵の実を食べた狡猾な『人間』であるためには、罪を犯し汚れる覚悟をしなくてはならないということであり、それをナスターシャ・フィリッポブナとロゴージンというキャラクターに体現させていた。このような本作を、黒澤明は、日本的なキリスト映画の『白痴』として図像化したのである。このように日本において不思議と繰り返される弱い一神教の神としてのキリストという存在は、ますます持って私の鶴見観を固めていく。
罪を犯し汚れる覚悟は、鶴見によっては以下のとおり示されているものかもしれない。
殺し合うシャチ… その死骸を喰う気色の悪い生き物でいたほうが こちらの痛手は少なくて済むのだが… 今夜は我々がシャチとなって狩りにいく
一方でキリストを『Идиот』と呼ぶことすら厭わないその姿勢は、私にとっては極めてロシア的なものである。信仰において美しく整っていることは最重要課題ではない。そのような本質性がロシアでは”イコン”に結実している。家族が毎日集まって祈る家の片隅のイコンコーナーの壁に掛けられた、決して高い装飾性や芸術性を誇るわけではなく、木片に描かれたサインすらない御姿の偶像。しかしそれこそが最も原始的な「信仰」のあり方なのではないか。ゴテゴテとした教会の装飾でも着飾った司教の権威でもなく、余分なものが根こそぎ取り払われて、日々の礼拝と口づけの対象となる木のキャンバス。真に信仰するものへの媒体としてではあるが、特別な存在感と重みを持つ象徴的なイコンという存在は、英語では「アイコン」と読み下されるものであり、文脈を発展させながらポップカルチャーにおいてもその役割を大きくしていったことは周知の通りだ。
7、親殺しの示唆と代行 ー 尾形の場合
翻って尾形の新平の親殺しはどうか。
父殺しってのは巣立ちの通過儀礼だぜ…お前みたいに根性のないやつが一番ムカつくんだ
鶴見も尾形も親殺しの事を「巣立」ち、という同じ形容を使うという事実。きっと何度も語られてきたことだろうけど、改めて15巻にて新たな父殺しが描かれてたことで、その関連性に驚く。父親の妾を寝取りながら、自らが手を汚す事もなく、両親が絶命した事で自由を得る新平のような人物は、私が『因果応報のない世界』として称するゴールデンカムイの特徴である。あるいは『役目』重視の世界とでも言おうか。そこで『役目』を果たしたのは意外にも尾形と彼の「ムカつき」であった。ただし尾形は、他人を結果的に助けてもその事を認識されない人物であるので、この『役目』もまた誰にも認識されることなく消えていく。
ホラ 撃ちなさい 君が母君を撃つんだ 決めるんだ 江渡貝君の意思で… 巣立たなきゃいけない 巣が歪んでいるから君は歪んで大きくなった
江渡貝の母は既に死亡していたが、江渡貝には支配的な母の声が聞こえ続けており、その声は鶴見に与することに反対し続けていた。母は江渡貝を去勢していたことすらわかっている。そんな母を殺せと示唆する鶴見。何より面白いのは「決めるんだ 江渡貝君の意志で…」という鶴見らしくない言い回しである。しかし結果として齎される“対象の操作””偽刺青人皮の入手”という点では功を奏しているので、単に相手によって取る手法を変えていて、それが本人にとってプラスに働くこともあれば、そうでないこともあるだけかもしれない。
ここで関谷のような問いを死神たる鶴見に投げかけるとこうなるーー鶴見は江渡貝から得る『見返り』がなくても江渡貝を助けただろうか?
これは関谷への以下の問いはこのように繋がるーー弱く清い娘を殺し、殺人鬼たる関谷を生かす神だったとして、関谷は神を信じ続けただろうか?
善き行いをした者に幸運しか降りかからないのであれば、なぜこの世に不遇は、不条理は、戦争はあるのであろうか。
これに対して「すべての出来事には理由がある」とする尾形が、自分の置かれた環境と新平の環境をダブらせた上で、親を殺す事が出来ず(巣立つ事が出来ず)大口を叩くのみの新平に対する「ムカつき」であることは明らかでありながらも、そこで結局新平が「救われた」事の偶発性、蓋然性、見返りのなさは見逃してはならないであろう。
同時に、墓泥棒を捕まえるのは自分の仕事ではない、と語る鶴見が、なぜ遺品の回収をしていたか(出来たか)、そして「傷が付いていた」という詳細、の��ぺらぼうがアイヌだということまで尾形に情報共有していたという二人の結びつきを考えるのも実に面白い。アイヌを殺したのは誰なのか? そこにいたと分かっているのはもはや鶴見だけなのである。
兎にも角にも、鶴見は、むしろその「不遇、不条理、戦争」の側に立つ事で、幸福を齎そうとする者なのである。
それは奇しくも、イワン・カラマーゾフが大審問官で言わせた「われわれはおまえ(キリスト)とではなく、あれ(傍点、悪魔)とともにいるのだ。これがわれわれの秘密だ!」のセリフと合致するのであった。
8、デウス・エクス・マキナの否定
と、ここまで書き上げた中で、本誌でキリスト教の神を試すキャラクター関谷が出てきた事で、私は論考を一旦止め、その後176話が『それぞれの神』というタイトルで柔らかく一信教を否定する日本的描写にひどく満足し、自らの「弱い神」「死神」の論考を少しだけ補強のために書き加え、大筋を変える事がなかったことに安堵した。
既に触れたファウストでの悪魔の発言、「すべてのものはいずれ滅びる であれば最初から生まれなければよかったのに」は、自らの死に対して諦念を、そしてウイルクとの再会に疑念を抱いていたインカラマッを連想させる。インカラマッ、そして関谷がこだわった『運命』は、やはり緩やかに谷垣によって、そして土方・門倉・チヨタロウによって否定される(このあたりはまさにドストエフスキー論的に言うポリフォニーというやつだ)。
関谷の持つ疑問は「ヨブ記」に置いて象徴されている。ヨブは悪魔によって子供を殺されるが、信仰を捨てず、最終的に富・子供をもう一度手にいれる。『ファウスト』では、やはり悪魔がファウストを試すが、最後に女性を通じて神がファウストを助ける。『カラマーゾフの兄弟』では、神を疑ったイワンは発狂・昏睡に陥る。つまりヨブ記を元にした作品群では、一神教の神は勝利している(『カラマーゾフの兄弟』のドミートリーのストーリーラインは除く)。これは演劇において「デウス・エクス・マキナ」と呼ばれる手法であり、最後に神が唐突に出てきて帳尻を合わせていく手法の事である。
関谷は自らの死にそれを見た。自らの悪行に等しい罰、裁きが下され、意志の強い土方が奇跡を起こしたと考えることで神の実在を感じたのであった。もっとも、我々読者にとっては、関谷への裁きは遅すぎるし、それが娘の死の何の説明にもならないため、関谷がどう捉えようと我々には神の存在が十分に確認できた「試練」ではなかった、と指摘しなければならないだろう。ただ、「デウス・エクス・マキナ」はむしろ因果応報を覆す超常的な描写であり、関谷が見た「意志の強い人間の運命」や「奇跡」、「裁き」という物差しすら飛び越えるものであったので、皮肉なことに、かえって関谷を包む状況とは一致を見せるとすら言えるのであるが……。おおよそにおいて良作とは、物語も人物も「あべこべ」で「矛盾」と「パラドックス」を抱えるものであるため、関谷とヨブ記についてまとめた記載をするには、稿を改めた方が良いと思われる。
それでも関谷についての序章を、本稿の終章に持ってきたかったのは、まさに、新平への運命を急に出てきて変えていく尾形が、あくまで人として、それも銃の���を除くととてつもなく弱く、惨めな人間として現れ、新平の親の殺人によって新平を救ったという、いわば「デウス・エクス・マキナ」の”変形という名の否定”ではないか、と指摘したかったからである。
時に死神でなくとも、人の子も人を救う。その一端が、尾形の「ムカつき」であったこと、そしてそれが本誌の白石や1牛山に引き継がれていくことを指摘して、この文の結論とする。
そこに「見返り」はない。尾形は新平を助けようとしたわけではないし、白石はアシㇼパを助けても依頼主の杉元が生きているかどうかすら知らないし、チヨタロウは牛山を失って自身に新たな力を得たわけではない。
だからこそ、「見返り」を問題にしてはならないーー外れてしまうとしても、ボタンを縫い付ける必要はあるのだから。
そしてインカラマッはきっと、情を持たず自分を守ってくれないとしても、谷垣に愛を伝えなくてはならなかったのではなかったのかと思うのだ。
読んでくださってありがとうございました。
過去の文をまとめたモーメント。
マシュマロ。なぜ書いているってマシュマロで読んでるよって次も書いてって言われるから書いているのであって、読まれてない文も望まれていない文も書かないですマシュマロくれ。と言って前回こなかったので人知れず本当に筆を絶ったのであった。そのことを誰にも指摘されなかったので、やっぱそんなもんなんだなって思ってる。
8 notes
·
View notes
Photo

ツアー5日目、盛岡から仙台へ。
おかげさまで22日(水)の岩手公演を無事、しっかりとした手応えで終了することができました。
ついに岩手日報で大谷翔平選手のオープン戦初登板を上回る、今日の紙面トップの写真入り扱いとなりました。
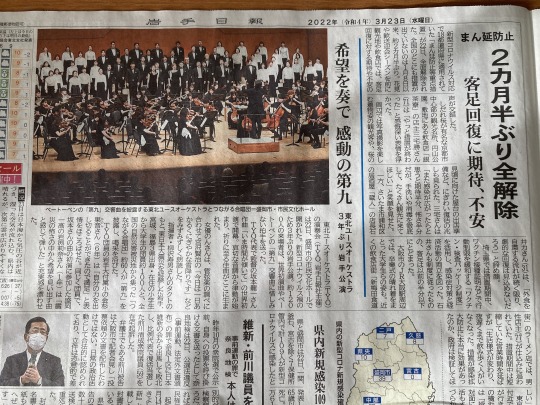
こちらデジタル版記事です。
ゲストとして観客のみならず演奏する団員を魅了する詩の朗読でご共演くださいました、女優・創作あーちすと、のんさんの公式ブログでもご紹介いただいています。
岩手公演当日のバックステージレポートは、またあらためて。
ともあれ、ご来場いただいたみなさま、どうもありがとうございました!
翌日23日(水)は朝からバスで仙台に移動です。わたくしが担当する3号車では・・・。

熟睡率は90%を超えておりました。
3日間の直前合宿で初日は予期せぬ大地震の影響で移動日になってしまい、二日漬けで前日の拍手喝采の名演を見事成し遂げたのですから、疲れてますよね。
胸張って寝よう。

途中の宮城県に入った長者ヶ原サービスエリアでは、福島出身の団員が不思議な名産品を見つけたようで、宮城出身の団員に尋ねているようです。

ふたたびバスに乗り込むと、隣のホルン菊野奏良くん(福島市出身の高校2年生)とトロンボーン海津洸太くん(白河市出身の高校3年生)がお菓子を食べながら小声で話をしていました。
奏良くんから
「田中さん、”がんづき”って知ってますか?」
さきほどのサービスエリアで話題になった宮城の名産品のようです。
「何、それ?」
「いやぁ、福島にもないんですよ」
「東北ってひとつにくくっても、それぞれ違いがあるよね」
「普通に話をしていても、突然わからない方言が出てくるんですよ。仙台の団員だと”いづい”とか、”むつける”とか。」
「そう、実はみんな言葉もいろいろだね」
「そういうの知れるところが東北ユースの良さなんだよなぁ」
さすが第1期に小学5年で入って休団無しの生え抜き団員!
というような話をしているうちに目的地に着きました。

今日の宮城公演が地震の影響で中止になってしまったため、急きょ日立システムズホール仙台をお借りして練習できることになりました。この先、今日を逃すと東京公演まで合奏練習をする機会がありません。

つながる合唱団のみなさんも合わせは無しの練習のため到着されました。

まずは練習会場となるコンサートホールに入る前に、

みんなだんだん慣れてきました、抗原検査の時間です。

検査結果を待つついでに今日の「主張の強い服を着ている人」を探していたら、声をかけてくれました。

郡山市の大学一年生、ヴァイオリンの阿部姫乃さんなのですが、一見すると主張の強さが感じられません。

しかし、靴が主張していました。
「かわいいでしょ!」
果物王国を謳う都道府県が多い中、福島県もその一つです。福島応援の意味も込めて、合わせ技一本で「主張の強い服を着ている人」認定です。

団員と隔離しての「つながる合唱団」サイドの抗体検査待ちの列の中に「主張の強い服を着ている人」候補者を見つけました。
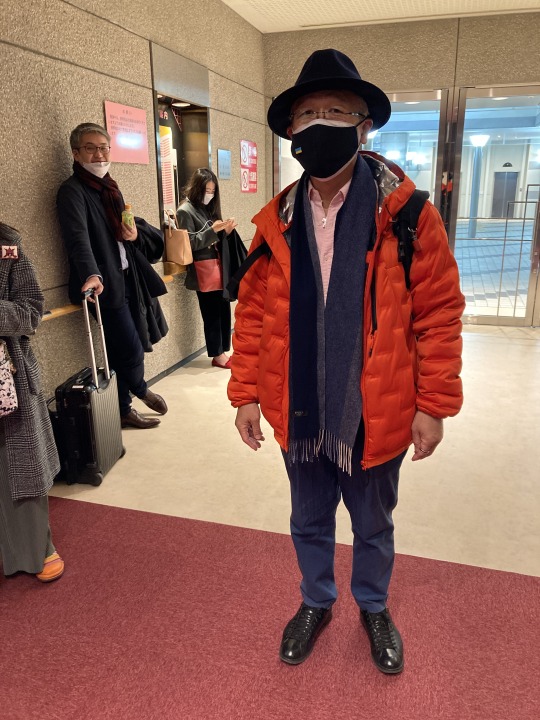
福岡県からご参加で、「ペ・ヨンジュンと顔が間違われるのではなく、名前が間違えられる」とおっしゃっていた在日韓国朝鮮人のぺェ・ヨンジョンさんです。
マスクが気になって近寄ってみると、
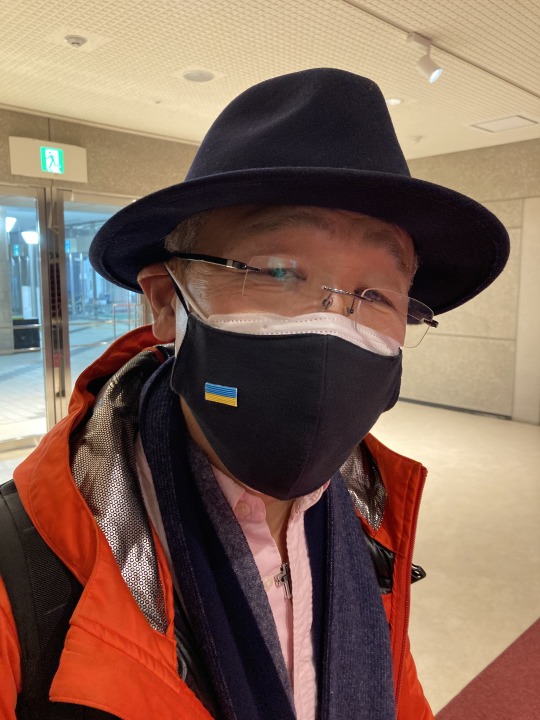
国旗でした!
さらに、

オリジナルでウクライナ・カラーで水引のバッジをつくられたのです。
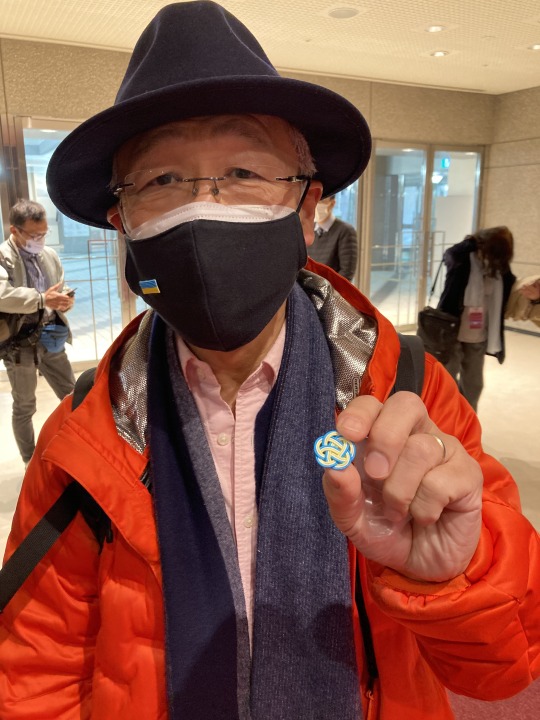
九州からご参加の9名全員がこのバッジをつけて第九を歌うのだそうです。あとで合唱担当の事務局平子英子さんに伺うと、ペェさんがつながる合唱団の団長とのこと。
もちろん「主張の強い服を着ている人」認定。
現在までのベスト「主張の強い服を着ている人」に間違いありません。
実はわたくしも最近買ったPCケースは、こんな色合いにして主張をしております。
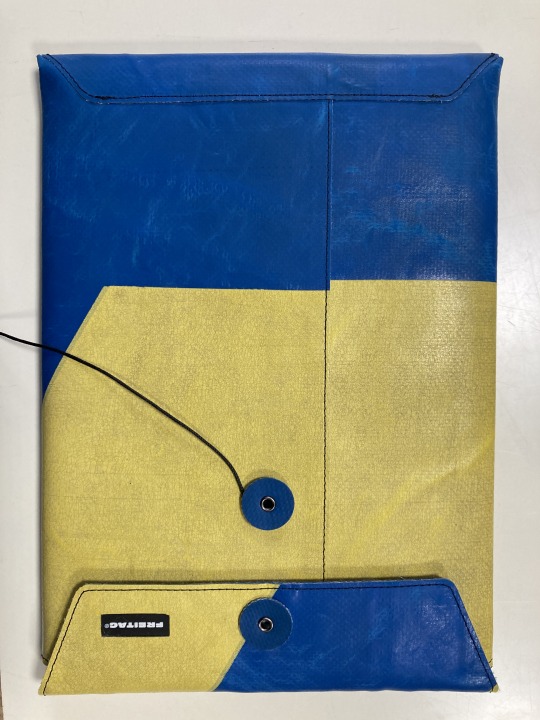
さて、抗原検査の待機組みに眼をやると、合唱団に岩手県宮古市から親子参加の第1期OGのオーボエ鳥居紗季さん、昌子さん親子の姿を発見しました。
やはり似ていらっしゃるものですから、思わず記念撮影をお願いしました。

す、すみません、眼をつむるところまで似ていらっしゃいました。
次のチャンスで再撮させてください。

この日のお昼です。

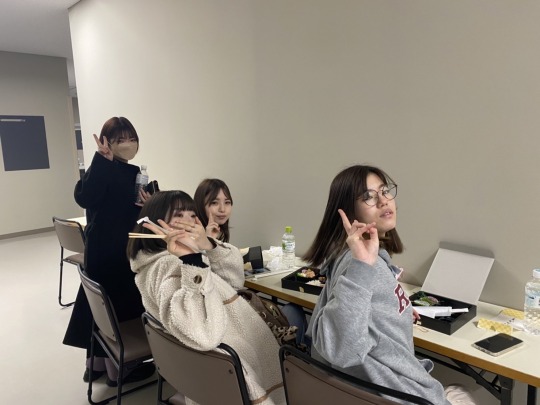
感染に配慮した横並びスタイルでのランチタイム。
ピーズサインは無言です。

���日の練習会場は仙台フィルのホームとして使用されている立派なホールです。
ここに地元仙台出身のサプライズゲストが来られました。
2019年に東北ユースオーケストラの初の委嘱作品『くぐいの空』を作曲なさった仁科彩さんです。なんと前日の岩手公演を鑑賞してくださっていました。

開演前のプレコンサートから団員の演奏の成長ぶりに感心され、開演で不肖わたくしが司会代役として話はじめた時から涙が溢れたとおっしゃってくださいました(舞台に登場し、話しはじめてスピーカーからのノイズとともに「マスク着けたまま出ちゃってた!」と気づき動揺のあまりマスクを外す際に眼鏡が外れそうになった事件で落ち込んでいたわたくしは救われました)。

みんなが音を一生懸命に聴きあって演奏する姿、素晴らしい演奏に感動しましたとの音楽のプロからの激賞を有り難く拝聴しました。さらには、150個の黒砂糖まんじゅうの差し入れまで、公演お祝いとして頂戴しました。
この春から仙台の某大学で音楽を教えられるために地元に引っ越しされたという仁科さん、今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

東北ユースオーケストラの合宿恒例の忘れ物紹介をしてくれたのは福島事務局の竹田学さん。先週の地震6を記録した国見町にお住まいです。自宅の瓦が飛んでしまい、雨漏りを役場で借りたブルーシートで覆う状態の中、今回のツアーに参加してくださっています。どうもありがとうございます。あらためてお見舞い申し上げます。
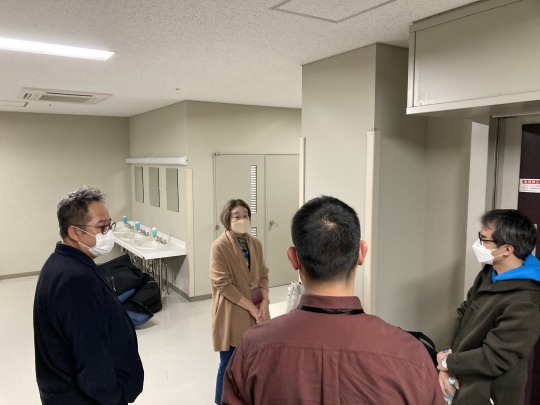
栁澤寿男さんによる昨晩の盛岡での公演の振り返り反省練習がはじまって、舞台裏で「こんな立派なホールで練習できるっていいわね。最初の年は高校の下駄箱が並ぶ入り口の吹き抜けで寒がりながら練習してたもんね」と述懐されるのは、福島事務局の大塚真理さん。FTVジュニアオーケストラに続く、ジュニアオケ、ユースオケの事務局のベテランです。今回も日々増える忘れ物をまとめて持ち歩くなどのサポートに深謝です。
そして、さっきからの写真で気になっていた方がいらっしゃるかもしれません。今日3人目の「主張の強い服を着ている人」。

東京事務局で会社の後輩、宮川裕さん(第九合唱参加経験有り)のパーカーが強い主張の色でした。恥ずかしがり屋なので背中でポーズの一枚です。
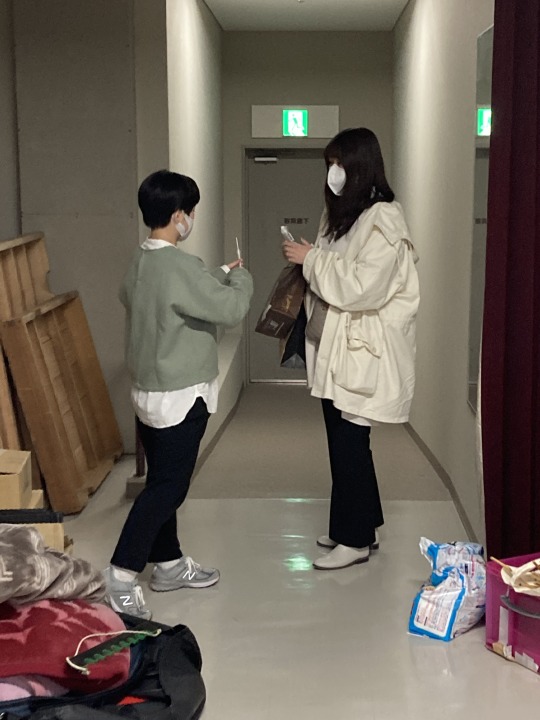
もう一人、ゲストが楽屋口に来て、抗体検査を受けていました。

第2期、第3期とキャプテンを務めてくれたOGのヴァイオリン畠山茜さんです。現在は東北ユースオーケストラ を長年応援してくださっているJA共済の宮城県本部に勤めています。今日行う予定だった仙台公演のために会社に休日申請をしていたので、そのまま仙台でのホールに来てくれました。手にチョコレートは、TYO同期同学年だった佐藤実夢さん(福島県出身で現在は千葉県で保育士)との共同差し入れでした。


休憩時間には見つけた団員に取り囲まれ、「会いたかったよ〜」と再会の喜びに溢れていました。コロナの時にはできなかったことが、そろそろ戻りはじめている気がします。

練習開始前に団員に挨拶をしてもらいました。1年前の地震による補償をようやく払い終わる作業が済んだのに、先週の地震で未消化率が100%になってしまったとのこと。大人の貫禄を感じました。
途中、栁澤さんは木場義則さんがご指導中の「つながる合唱団」の練習会場へ。

全国からつながって、まだ4日目というのに、妙な連帯感がありますね。
もうひとり、地元在住のゲストが来てくれました。
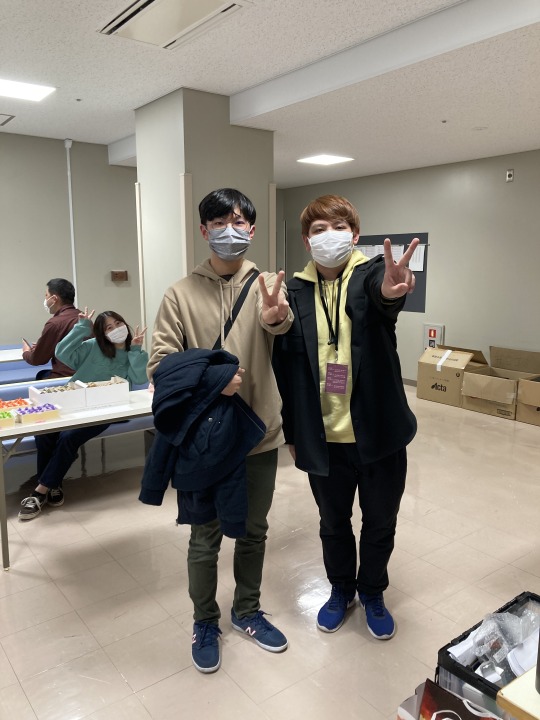
現在は大学受験のため休団している高校2年生のトロンボーン福澄茉音くんです。同じパートの一つ先輩の海津くんと仲良く再会を喜んでいました。
茉音くんが、「今日、一番ショック受けたわー」と言っていたのが、最初の年の夏の宮古島合宿で福島事務局の渡辺豊さんに同行していた颯太くん(当時5歳、現在は第6期のヴィオラ担当)との背比べでした。

落ち込む茉音くんの周りに高校2年生の同級生メンバーが集まってきたので、再会を祝う記念撮影です。

4月からは「高校三年生ズ」ですね。 茉音くん、志望の理学部物理学科に合格し、復団して東北ユースオーケストラのリーダーとして引っ張っていってくださいね。
この日は3時間ほどの調整練習で、バス3台に分かれて仙台のホテルに向かいます。
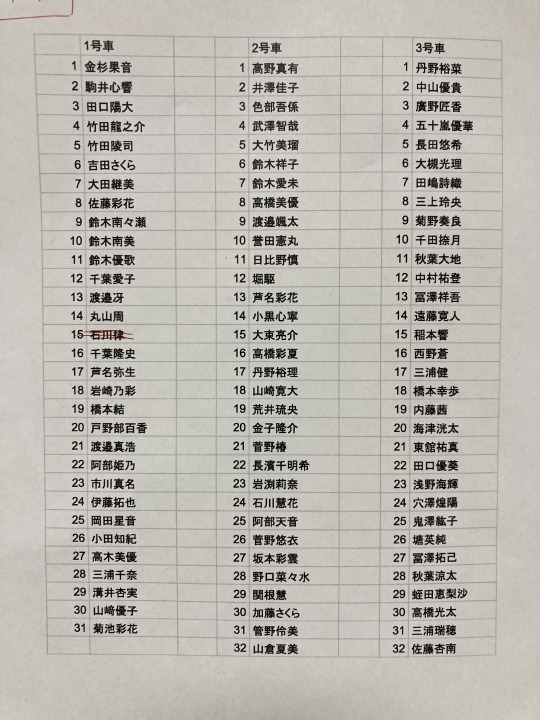
わたくしは、ひさびさの「バスの号車担当」として、3号車に乗り込みました。
市街地に入ると、白河市の海津くんが「やっぱり、仙台は人が多いなぁ」と感心しきり。近くに座っていたホルン奏良くんが「コロナ前の中学時代は、よく仙台に友達と遊びに行っていました」というのとは、同じ福島県でもだいぶん違いますね。

バスを降りて、3台分のスーツケースと楽器を運び出し、ホテルの1階から3階にエレベーターで上がって、全員に部屋の鍵を渡すだけで1時間以上かかりました・・・。
とにもかくにも全員元気にしております!
1 note
·
View note
Text
Collections of Hiroki Kikuta’s blog
1997年秋から1999年末まで携わった、
「クーデルカ」という仕事は、僕の人��の中で大きな意味を持つ。
嬉しかったこともあり、残念だったこともあり、しかし、制作に費やした二年間は、
無駄ではなかったと、今振り返って思う。
サクノス立ち上げに助力していただいた、元セガ副社長の故藤本敬三氏の思い出。
ロサンゼルスはウエストハリウッドでの夢のようなモーションキャプチャーセッション。
胸に浮かぶままに、語るべきことは尽きない。
ここでは、写真、設定資料、デザイン画を中心に、ゲーム制作のプロセスと、
その印象を綴っている。
クーデルカのための宣伝用イラストレーション/1998 岩原裕二 部分
このサイトは、1999年12月にプレイステーション向けホラーRPGとして発売されたゲーム「クーデルカ」のディレクター菊田裕樹が、制作資料の掲載や作品解説を目的として運営するものです。ゲームをプレイしてくれたユーザーが、より深くクーデルカの世界とその魅力に親しんでもらうために、僅かなりと助けになれれば幸いです。
---
「クーデルカ」のモーションキャプチャーは、1999年1月、ロサンゼルスはサンタモニカにあるスタジオで収録された。技術面を担当したのはフューチャーライト。普段は「ゴジラ」等のハリウッド映画のSFXを担当している映像制作会社である。遡る1998年9月、僕はイベント系を担当する人員の不足から、それを全てモーションキャプチャーで賄うという構想を建てた。全体で見れば一時間をこえるイベントシーンを、手打ちのアニメーションとスクリプトで実現しようとすれば、5人がかりの仕事となる。しかも、一向に従来のRPGの域を出ない、面白みの無い方法だ。ゲームのドラマ部分を表現するために、効果的で、目新しくて、しかも大きな省力化になる方法として、モーションキャプチャーは画期的な試みだった。無論、問題はあった。技術的に不可能だというのだ。物語の性質上、最大4人を同時にキャプチャーし、併せて音声も収録する必要があったからだ。僕はまず、日本国内のスタジオで実験をし、手応えを掴んだ。その結果、モーションキャプチャーは十分に魅力的な効果を生み出すという確信を得た。しかし同時に、僕の要求する仕様は日本国内では実現不可能であるということも分かった。だが、そこで諦めてはクリエイターが廃る。幸い、以前「双界儀」の録音でお世話になったデイブレイク社の大竹氏が、海外のコーディネイターに詳しいというので、畑違いながら探してもらったら、ロスにそれらしい技術を持った連中が居るという。早速連絡を取り、俳優のオーディション方々会いに行った。ところが実際に会ってみると、彼等も僕が考えるような仕様でキャプチャーをしたことがなかった。4人を同時に、音声もいっしょに、しかも数分に及ぶ芝居をいっぺんに収録する。そんなの聞いたことがない。しかし驚いたことに、面白そうだから是非やってみょうと、彼等は言ったのだ。新しいことにチャレンジするのが嬉しくてしょうがないスタッフ達。こうして、この前代未聞の試みは実現したのである。
クーデルカを演じてくれたヴィヴィアンとエドワードを演じてくれたマイケル。100人程のアクターをオーディションした中から選んだ人達だ。アメリカのアクターの層は厚い。皆、良い作品に出演することを夢見て、演技の勉強をし、技術を身に付け、レストランなどで働きながらハリウッド近辺で暮らしている。アメリカでは基本的に、どのような有名な役者でも、名前だけで出演が決まることはない。必ずオーディションをして、その役に本当に相応しいかどうかを確かめられる。彼等は、役の大小に限らず、それを勝ち取ることに真摯で、また仕事に臨んでも出来るだけ良い結果を残そうとする姿勢を崩さない。
セッションに参加してくれたスタッフ達。フューチャーライト側から、モーションキャプチャーの陣頭指揮にあたってくれたダン・マイケルソンをはじめ、プログラマーのランディ、エンジニアのジョン。彼等は4日に及ぶセッションの中で起った、様々な問題に素早く対処してくれた。日本側から、クーデルカのモーションを担当した竹原君。IPG側から、わざわざこのコーディネイトのためにニューヨークから駆け付けてくれたポール。そして、サウンドエンジニアのキース。
写真中央、このセッションのディレクションを全て担当してくれた、IPGから参加のデビッド・ウォルドマン。彼は日本でビデオクリップのADをしていた経歴があり、日本語が話せたため、今回の仕事に適任として選ばれた。映像制作の現場でのノウハウや、その進行に関して、彼に学ぶところは大きかった。その後、ロスでムービーキャメラマンの学校に入り、本格的に映画制作を志しているらしい。左は、デビッドの女房役のADであるクレイグ。右に居るのは、9才のシャルロッテ役を演じてくれた12才のサラ・パクストン嬢。その可愛らしさで、スタジオの人気者だった。しかし、プロとしての意識は本物で、長台詞を覚え、慣れないキャプチャーに戸惑うこともなく、見事に演じてみせた。下の写真は、キャプチャーセッションに先立つ、リハーサルの時のもの。近くのホテルで部屋を借り、本番の時と同じように、全ての芝居をチェックする。この時キャラクターはどんな気持ちなのか、何を考えながら演じればいいのかを、ひとつひとつ、押さえていく。このシーンは、クーデルカとエドワードが、オグデンとベッシーにスープを振舞われるところ。中央に、いかにも人の良いおばさんを演じてくれた人の良いおばさん、デニス・ホワイト。
スタジオというよりは工場といった有り様だが、実際すぐ横にプロップを組み立てる工房があったりした。一応サウンドステージとして作られてはいるのだが、防音がしっかりしていないため、上空を飛ぶ軽飛行機の音がうるさくて、撮影が中断したのには参った。真中に置いてあるのは、ジェームズら3人が大聖堂に入る扉が開かなくて悪態をつくシーンのための大道具。例えば、扉を叩く芝居が欲しい時に、何もないのにそういう振りだけしても、リアリティーは生まれない。扉を叩く時には、そこに扉があるべきだ。下の写真は、ゴミの山に埋もれてひっそりと稼動しているSGIのONYX。これに限らず、驚くような機材が、ごく当たり前に使われているのをあちこちで見た。聞けばそれらは全て、レンタルなのだという。こういう所にも、日本との状況の違いを感じた。右は、連日に及ぶ深夜の撮影で疲れ果てて眠りこける僕。
2000/11/25 菊田裕樹
---
ヴォイニッチ文書 部分
Emigre Document
紀元前5000年をさかのぼる昔、ブリタニアには高度な巨石文明を持った民族が栄えていた。今も島のあちこちに残るドルメンやストーンサークルは、現代科学を持ってしても不可能と思われるほどの彼らの技術力を、我々に示している。彼らはケルト人が到来するまで、全世界でも最も進んだ文化と文明を持つ民族であった。エジプトでピラミッドが建築される遙かに昔。中国、バビロニア、イスラエル、どの文化圏よりももっと以前に、ブリタニア全土に分布する巨石遺構は建てられたのである。
その力の秘密は、彼らの持つ宗教にあった。彼らは大地より湧きいでる生命の秘密に手をかける術を知っていたのである。生と死を操り、不死や、あまつさえ死者の再生をも我がものにし、労働力としての人間ならざる怪物を生み出し、高度な文明を築き上げた。それは自然の持つ輪廻の法則そのものを御する行いであり、神の為す神秘に等しい。いや、彼らこそが原初の「神」だったのかもしれない。彼らはその「神を遙かに遡る世界の成り立ちの秘密」を、文字にして書き記すことはなかったが、その祭儀や術としてのノウハウは、ケルト社会のドルイド僧に引き継がれた。ドルイド僧は古代人の残した祭儀法を基盤に、自分たちなりの技術的アレンジを加え、古代人には及ばないまでも、天地の秘密を力に変換することを自らのものとした。
だが、彼らもまた、自分たちの慣習や宗教に関して書き残すことをしない。ケルト民族の在りように関して最初に言及したのは、まさにそこを征服せんとして兵を進めたユリウス・カエサルである。しかし、彼が紀元前50年頃に「ガリア戦記を」書き記す以前に、前4世紀頃ケルト民族と親交のあったアレクサンダー大王が、アレクサンドリアの大図書館に收めるべく、ドルイドの秘儀をギリシア語で文書化させていたのである。彩飾図版を交えて作成されたこの文献は、その任に当たった人物の名を取って「エミグレ文書」と名付けられた。
この文書は閲覧を禁じられた秘密の書として王宮の図書館に保管された後、戦禍を逃れて持ち出され、数世紀の間、各所を転々とする。その間にはキリスト教の成立やローマカトリックの隆盛などがあるが、6世紀に入り、アイルランドに様々な修道院が建設され、写本事業が盛んになった結果、イタリアの片田舎に忘れられていた「エミグレ文書」は、リンデスファーン島にある写本で名高い修道院に持ち込まれた。だが、ギリシア語に堪能でない彼らは、内容の美しさや彩飾の艶やかさに目を見張りこそすれ、文書の持つ本当の力に気づくことはなかった。
9世紀に入って、度重なるヴァイキングの来襲により、蔵書の保存に危機を感じた修道院は、重要な文献を各地に避難させ始める。アイルランド生まれで敬虔な信者であるヨアヒム・スコトゥスとダニエル・スコトゥスの兄弟は、大修道院長より「エミグレ文書」を託され、その内容に驚愕した兄ヨアヒムは弟ダニエルをウェールズの辺境にあると記される聖地へ赴かせ、自らは写本を携え、フランス王の元に庇護を願い出た。弟ダニエルは聖地で修道院を建て、祈りを捧げて一生を終わる。兄ヨアヒムは碩学として歴史に名を残すが、その死後、ローマ法王庁に写本を接収されてしまう。
キリスト教を脅かす力を持ったこの文書は、ローマ法王を恐怖させ、禁断の書物として誰にも閲覧を許すことなく、書庫の奥底にしまい込まれたが、13世紀になってその損傷の激しさから、新たな写本を作る必要が生じ、当時最高の知識人として名高かったフランチェスコ会修道士ロジャー・ベーコンにその任が与えられた。彼は10年にも渡ってフランスに幽閉され「エミグレ文書」を精確に複製することを強いられたが、その過程で文書の知識は彼の物となった。秘密を守るため彼をそのまま監禁し、二度と世に出すまいという法王庁の意図とは裏腹に、彼は密かに外部と連絡を取り、自らが解読した文書の示す聖地へ赴き、生命の秘密を探る試みに取りかかるべく、着々と準備を進めていた。
彼は、先にダニエル・スコトゥスが建てた修道院を��修し、実験施設となるべきゴシックの大聖堂を建築させた。そこで彼がどのような秘術を試みたのかは、記録に残っていないが、法王庁の手を逃れフランスを脱出した彼は、二度と姿を現すことはなかった。彼は、姿を消す前に、新たな一冊の写本を残している。エミグレ文書の記述を元に、ウェールズ語の暗号で書かれたその写本は、聖地の修道院に残されていたが、16世紀になってエドワード・ケリーとジョン・ディーによって発見され、新たな写本として書き直され、さらにローマの修道院を経て、20世紀になって古物商ヴォイニッチによって再発見され、ヴォイニッチ文書と名付けられて、現在エール大学のベイニック図書館で閲覧できる。
また、ロジャー・ベーコンによって複製された「エミグレ文書」写本(原典は破棄された)は19世紀までヴァチカン宮殿の奥深くに秘蔵されていたが、1890年頃何者かに盗み出され、以後その行方を知る者はいない。ダニエル・スコトゥスが建てた修道院は1536年の修道院廃止例の後、政治犯や重要犯罪人を拘留し処刑するための施設へと転用され、聖なる場所で多くの人命が闇に葬られた。
(設定資料より)
2000/10/25 菊田裕樹
---
2000/10/25 Hiroki Kikuta
Koudelka Iasant
1879年生~没年不詳。イギリスはウェールズの田舎、アバージノルウィンの寒村生まれのジプシー。幼い頃から強すぎる霊能力を持ち、様々な怪異を起こすため、呪われた存在としてジプシーの世界から追放される。1888年9才頃ロンドンで霊能力者ブラヴァツキー婦人に拾われ、秘蔵っ子として厚遇されるが91年婦人が他界すると共に、再び放浪の旅へ。普段は霊媒として失せ物を探したりして、糊口をしのいでいる。
年は若いが、世の中の事情を一通りわきまえたところがあり、良く言えば大人、悪くいえばすれっからし。普段はあまり明るい顔をせず、大体において不機嫌そうで態度が悪いが、時折女らしいところを見せる。差別される者や愛されない者に肩入れする傾向がある。自分を表現することが下手。
(登場人物設定資料より)
Notes
クーデルカという名前は、著明な写真家であるジョゼフ・クーデルカから採ったものだ。口にした時の不思議な響きと、民族や国籍を感じさせないところが気に入って、名字ではなく名前として使わせてもらった。手元の資料を見ると、キャラクターデザインの岩原裕二氏にコンペ用のスケッチを発注したのは1998年の3月26日だが、遡る2月10日の段階で、僕はゲーム全体の進行手順と、シナリオの箱書きを完成させていたし、キャラクターの心理設計も完全なものとなっていた。クーデルカはジプシーの出身である。彼らはインドをもっとも古い故郷とし、放浪に生きる人々で、自分たちのことを誇りを込めてロムと呼ぶ。それは人間という意味で��る。一般社会の人間たちとは隔絶され、自分たちの血縁関係の中だけで生きている彼らにとって、追放はもっとも苦しい罰となる。クーデルカはその特異な能力ゆえに、子供の身でジプシーを追われることになった。僕は彼女を、どこにも安住することを許されない、最も孤独な存在として設定した。平和で豊かな暮らしの中に、彼女の居場所は無い。呪われた魔物や幽霊が跋扈する、廃虚の暗闇の中にだけ、かろうじて自分を置くべき空間を見出せる。クーデルカは、そういう悲しい存在なのである。
岩原氏はこのプロジェクトのために、100枚にも及ぶキャラクタースケッチを描いた。クーデルカだけでも数十枚になるが、そのほとんどはポリゴンによるモデル化のための制約から来る衣装デザインの試行錯誤であり、キャラクターの本質部分に関しては、最初から完成形に近いものを掴んでくれていたようだ。また、氏にはゲームの制作に先行して角川書店の雑誌で漫画連載を始めてもらい、ゲーム設定の1年後のストーリーという立体的な構成で、物語の厚みと魅力を増すことに貢献してもらった。
クーデルカのポリゴンモデルは、当時広島のコンパイル社の倒産で行き先を捜していた渡辺伸次氏に、経済的に援助するということで東京に移り住んで制作してもらった。彼は同社の仲間とCGスタジオであるD3Dを設立した。そのころの彼等には全く実績が無かったが、見せてもらったプロモーションムービーのキャラクターの動きに並ならぬ情熱を感じ、彼等と一緒に新しいチャレンジをする気になったのである。しかし実際、キャラクターのモデリングは難航した。ゲームスタッフ側の無理解も大きな原因だったが、D3D側もクーデルカほど高いレベルのモデルを作るのは初めてとあって、試行錯誤のために何ヶ月も時間が必要になった。リテイクに次ぐリテイクの嵐。最終的には、僕自身が彼等の後ろに付いて、鼻をもう少し縮めてだの、唇をもう少し上げてだのと細かく指示を出し、なんとか納得のいくものに仕上がるまでに半年近くかかっている。
モーションキャプチャーにおいて声と演技を担当してもらったヴィヴィアン・バッティカ嬢は、米サンタモニカ・スタジオで行ったオーディションの中で、クールで独特の色気があり、抑えた芝居の出来る人として選定した。ただ可愛いだけではなく、クーデルカの持つ陰の部分を表現するためである。彼女自身まだ若く経験も浅いとはいえ、その熱意と努力は相当なもので、10分にも及ぶ長丁場の芝居、何十行もある長台詞を、たった数日で完全に頭に入れて撮影に臨む辺り、なるほどプロというものはこういうものかと感心させられた。度重なる技術的不備にも嫌な顔をすることなく、エドワード役のマイケル・ブラッドベリーと現場の雰囲気を明るく盛り上げてくれたことには、感謝の言葉もない。
2000/10/25 菊田裕樹
llustrated by Yuji Iwahara
このページ内の全ての画像及び文章の著作権、版権、複製権、二次使用権は全てその正当な著作者、権利所持者に帰属します。よって、無断複製、無断転載を含め、著作権法に違反する形態でのあらゆる利用を禁止します。
All Rights Reserved 1997 1998 1999 2000.
クーデルカは(株)サクノス・SNKの登録商標です。
All Rights Reserved (C)SACNOTH/SNK 1999
---
Nemeton Monastery
イギリスはウェールズ地方。アバースワースにほど近い、海沿いの断崖に、人気もなく廃墟と見まごうようなネメトン修道院がある。ちょっとした公園ほどもあるその敷地の中には9世紀頃に建てられたと思われるロマネスク様式を色濃く残した修道僧の宿坊をはじめ、13世紀頃に建てられた飛び梁も美しいゴシックの大聖堂、会堂をかねた図書館、鐘つき堂、屠殺場を兼ねた炊事場、処刑台に使われた東屋、近代になって建てられた宿舎などが、全体を囲む壁と一体化して並んでいる。16世紀に修道会を禁ずる制令が発布されるのを待たずして寂れ、廃墟と化したこの場所は、17世紀に入って政治的な犯罪者や虜囚などを閉じこめたり処刑したりする目的に使用された。今でもどこかに地下牢が隠されているといわれている。近代になって、訪れる者も居なくなり、荒れるに任せていたのを、ある資産家が物好きにも買い取って移り住んだが、程なくして彼は姿を消し、後には様々な憶測と噂だけが残った。あるいは、財宝が隠されたまま埋もれているといい、あるいは、悪魔が彷徨っているといい。再び廃墟と化したこの修道院を訪れるのは、人目を避ける犯罪者や一攫千金目当ての食い詰め者だけだった。
(制作資料より抜粋)
ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三
1998年2月の段階で、ゲームの進行に伴う、マップ全体像の設計は、ほぼ出来上がっている。八棟の建物、地下道、墓地など、全部で100個見当の区画からなる構成で、イベントと連動して移動できる範囲が拡がっていく。実は、このような閉鎖された空間を舞台として設定したのは、単に演出的な意図によるものではなく、人的物理的制約による結果なのである。例えば、高度に訓練されたグラフィックスタッフが20人居るならば、一年間に500から600枚を超える背景画を制作することが可能だ。しかし、楽観的に考えても数人が限度と思われる人材確保の現状を前提にすると、およそ100マップ200~250画面が、用意できる背景数の上限と見なければならない。一般のRPGのように、ワールドマップがあって幾つもの街があって、などという仕様は、最初から無理。そこで、極めて限定された空間を設定し、それを有効に活用しつつ、様々な雰囲気のバリエーションを提供できるような仕掛けを考案した。それがホラーRPGという枠組みだったのである。
ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三
ネメトン修道院を構成する建物群は、そのひとつひとつが、建てられた年代も、目的も異なるものである。各々の建築様式の違いは、ドラマの進行と相まって、ユーザーを飽きさせないための装置として機能する。扉を開けて新しい建物に入る度に、物語が次なる展開を迎えたことを実感してもらうために。微にいり細にわたり、緻密に作り上げることが、あたかも実際にそこに居るかのような臨場感を生む。そのために最も必要だったことは、実際の建築物を参考にすることであった。
ネメトン修道院初期設計図/1998 松野泰三
物語上でアバースワースとしたのは、アイルランド側の海岸にその場所を置きたかったからだが、98年8月にスタッフを伴って訪れた実際の取材は、ウェールズの下側に位置する観光地ペンブロークシャーを中心に行った。その一帯は、草原から突然に切り立った断崖が現れ、地平線の彼方まで続く、不思議な景観の土地である。その周辺に夥しい数の修道院や城跡が存在する。あるものは往時を偲ばせて健在だが、ほとんど廃虚と化した遺構も多い。セント・デイビッド教会は、中世そのままの姿で我々の目を楽しませてくれると同時に、石造りの聖堂が持つ、独特な雰囲気を理解するのに役立った。また、垂れ込めた雲と雨が作るどんよりとした暗い空気は、実際にその場に立ってみないとイメージできないものである。近辺の修道院の壁や石組みを大量に撮影して、3Dモデル用のテクスチャーとして使ったのも、大きく意味がある試みであった。
さて、ネメトン修道院の大聖堂はゴシック建築として作られているため、本当ならば、その常として側廊が無ければならない。ゴシック建築は荷重を分散する構造にすることで壁を薄くし、ステンドグラスの設置を実現しているからである。しかし、ゲーム仕様上の制約としてプリレンダリングのマップを考えた時に、多数の柱を立体的レイヤーとして配置することが困難であるために、内部を単純な箱型にせざるをえなかった。外側から見ると、飛び梁様の補強柱が一定間隔で取り付けられているが、現実の物として考えれば、全体の重量を支えるために、壁自体もさらに厚くせざるをえないと思われる。なお、大聖堂頂部の鐘突き堂は、そのものが飛び梁によって構成されている特殊な形式だが、これは架空の物ではなく、実際に存在するスタイルであることを付け加えておきたい。
2000/10/25 菊田裕樹
---
Library : クーデルカという物語
By
菊田 裕樹
– 2000年 3月 28日Posted in: Library, Library : ARTICLE
クーデルカという物語
2000年3月 公開
このサイトを御覧の方には僕の制作した
RPG「クーデルカ」を未プレイの向きも多いと思う。
手短に説明すると、19世紀のイギリスはウェールズの
片田舎にある今は廃墟同然と化したある修道院を舞台に、
クーデルカという19才のジプシーが出会う様々な
怪異をテーマにした、いわゆるモダンホラーと
呼ばれるジャンルに属するゲームである。
僕はこの作品のコンセプトに始まり、キャラクター設計、
マップ構成、シナリオ、ムービーや
モーションキャプチャーイベント部分の
ディレクション等など、様々な種類の仕事をした。
基本的な部分の組み立てには約3ヶ月ほど要しただろうか。
全部で100冊以上の本に眼を通したが、
物語の発想の土台となったのは、
「幽霊狩人カーナッキ」という本であった。
短編集で、主人公である怪奇現象研究家カーナッキが、
様々な「怪異」と「怪異に見えるもの」に遭遇し、
あるものは解決し、あるものは良く分からないまま
終わる(笑)という、味わいのあるホラー小説集だ。
興味のある方は是非一読されたい。
さて、僕が物語を組み上げる段階でこだわるところは、
歴史上の事実を曲げないということである。
実際に起こったとして、記録に残っている様々な事件を、
相互に関連付け、その隙間を虚構で埋めていくという
やりかたが僕は大好きだ。
同じ嘘をつくのでも、まったく根拠も無く考えるのと、
事実に基づいてその基盤を組み上げていくのとでは、
細かい部分でのリアリティーが違ってくる。
だから、クーデルカという物語には、
プレーヤー諸氏が考えているよりも、
ずっと多くの史実が含まれている。
エドワードやロジャーが実在の人物である事など、
歴史に興味のある方は、調べてみられるのも一興かと思う。
1898年は科学と迷信がせめぎあう世紀末の、
まさに移り変わる一瞬を捉えて興味深い時代である。
明ければすぐに1900年、近代科学文明の浸透の
象徴ともいうべき、パリ万博が開催される。
そしてそれこそが、僕がクーデルカの続編と
目論んでいた物語の舞台なのである。
ウェールズを描くために、ロンドンやペンブロークに
足を運んだのと同じように、僕はパリやベルギーに
取材をするつもりだった。
(パリ万博に出展されていた建物が、当時の
ベルギー王の要望で買い取られ、
ブリュッセルに現存するのだそうだ)
会場から郊外を結んで建設された地下鉄と、
そこで起こる怪異。エースネクスト誌連載中の
漫画版のエピソードを終えたクーデルカが、
拠ん所ない事情でパリを訪れ、地下に巣喰う
亡霊どもの争いに巻き込まれていく。
実はクーデルカの続編は、僕の頭の中では4作目まで
出来ている。第一部イギリス、第二部フランス・・・
とくれば、第三部はアメリカである。
時代は大きく跳んで、1973年アメリカはシカゴ。
主人公は、シカゴ大学で教鞭を取る文化人類学者、
クーデルカ・ロードメル。
クーデルカの娘アメリアが後に渡米して産んだ子供で、
つまりは孫だ。ベトナム戦争末期とあって、
帰還兵が持ち帰ってしまった悪霊が、
様々な殺人事件を引き起こすのを、まだ生きている
ロジャーの助けを借りて解きあかしていく。
(ちなみにロジャーはスーツを着て出てくる)(笑)
そして第四部は1984年奈良。
関西大学で教える友人の宗教学者の元を訪れたクーデルカは
何者かに命を狙われ、陰陽師や式神と戦う羽目になる。
奈良の巨石墳墓や京都の町並みが、
雰囲気造りに一役買うだろう。
残念なことに、今のところ僕がそれらの
続編を作る予定はないが、
小説のようなものであれば、書いてもいいかなあと思う。
Story of Koudelka : Library
---
Haven: On Koudelka, you served as producer, writer, and composer. What were some of the goals you accomplished in taking on these various responsibilities? Were there ways in which the project could have been better realized?
Hiroki Kikuta: Let me begin by saying, whenever you divide up responsibilities among a group of people concerning the judgments that get made on a project, the end quality is bound to suffer as a result. To keep the quality high and the schedule organized on a project, it's better for as few people as possible to be making key decisions, and for them to be communicating within the group with as few conflicts as possible. The ideal situation would be for but one director to be delegated the responsibility of expressing his or her creative vision. That said, for Koudelka, I was pursuing that degree of creative control.
To prepare, in gaining an understanding of the game's setting, I read about one hundred books on English history, touching on periods from the Medieval era to around 1900. It proved useful in discovering relevant episodes which could be incorporated into the story. Having several events to ground the plot in a kind of historical reality, I then started building on that foundation with some fictional events. For example, the character of Edward is based on an actual Irish dramatist named Edward Plunkett, 18th Baron Dunsany, while the woman who writes a letter for Charlotte is based on Sophie Dorothea of Württemberg. Roger Bacon is, of course, a historically famous philosopher. Also, the incident on the Queen Alice really occurred and is recorded in the captain's log of the vessel. By filling out the gaps in those historical events with fictional incidents, such as the Emigre Document and reincarnation ritual, I aimed at providing a realistic basis to the imaginary aspects of the story.
Before production, some members of our staff went on a trip to Whales to gather information and capture the genuine atmosphere of the place with our own eyes. We demanded extreme accuracy in providing the background details, and we even used motion capture technology to provide culturally appropriate body language for the characters, techniques advanced enough to compete with the standards of the Hollywood industry at that time. Those challenges, which were provided by the passion motivating that project, were the real essence of Koudelka.
Koudelka, "Patience," music sample
I remember that I was reading the critical biography of James Cameron, who was making Titanic at that time, on the airplane to England. I was overwhelmed by his tremendous efforts to capture those startling images. At that time, I realized that it is necessary for creative work to have a degree of obsessive passion involved. I hope that some degree of that conviction had a positive result on the end product.
---
As soon as it is in the year 1900, the Paris World Expo is to be held as a symbol of the penetration of modern scientific civilization.
And that is the stage of the story that I was thinking as a sequel to Kuderuka. In the same way that I went to London and Pembroke to draw Wales, I planned to cover Paris and Belgium.
(It seems that the building which was exhibited in the Paris Expo is bought at the request of the King of Belgium at the time and exists in Brussels.) The subway built by connecting the suburbs from the venue and the monster occurring there. Kuderuka who finished the episode of the comic version in the series of Ace Next magazine visits Paris due to circumstances that are not based, and is caught up in the strife of ghosts who nest underground.
(The first line of the Paris Metro opened without ceremony on 19 July 1900,[4] during the World's Fair (Exposition Universelle - that is what is meant by subway)
Actually, the sequel to Kudelka is made up to the 4th in my head. Part 1 England, Part 2 France · · ·
If you do, the third part is the United States. The era greatly jumped, in 1973 America was Chicago.
The hero is a cultural anthropologist, Kurdelka Roadmel, who teaches at the University of Chicago.
Kuderuka's daughter Amelia is a child who gave birth to the United States later, that is, it is a grandchild. With the end of the Vietnam War, the evil spirits brought back by the returning soldiers will solve various murder cases with the help of living Roger yet.
(By the way, Roger comes out wearing a suit) (lol) And the fourth part was Nara in 1984.
Kurdelka who visited the origin of a religious scholar of a friend taught at Kansai University is targeted to someone, and it will be fought against the Yin Yang masters and the expression god.
The megalithic tomb of Nara and the townscape of Kyoto will contribute to the atmosphere building.
Unfortunately, for the moment I have no plans to make those sequels, but if it's like a novel, I wonder if I can write it.
---
RocketBaby: At what age did you become interested in music?
Hiroki Kikuta: When I was ten years old, I met up with the music of Emerson, Lake & Palmer. I had never heard such marvelous music before. It was quite an impact for me. A few months later I heard that Keith Emerson was using a particular instrument called MOOG synthesizer.
RB: At what age did you start writing music?
HK: When I was twelve years old, the Folk blues movement came over to Japan from America. I studied Acoustic Guitar and started to create an original song immediately. I wanted to be a singer/ songwriter... if I wasn't a terrible singer. Actually, Digital equipment opened up my potential as a music composer. Without a musical sequencer, I can't create any complicated tunes. When I first acquired a YAMAHA SY-77 synthesizer/sequencer, I felt as if I got a ticket to a different world.
RB: Why did you start Sacnoth?
HK: I had held many original ideas about video games and visual expression for a long time. The most important purpose is to create an entertainment. When I was searching for a way to achieve my dream, I met a dominant business advisor. He introduced me to the chairman of SNK. I told him about many pitfalls that every existing RPG had. I thought those were lacking a comprehensive insight and a integrative interpretation. It is a structural defect of game production. To resolve the problem, it is necessary to get the picture of each element of game creation at the same time. I have an ability to do that. I established a company SACNOTH and took up my position as CEO in order to produce a new horror RPG project, Koudelka. But unfortunately... Though I conceived a grand scheme to realize an innovative game system and visual expression, many old staffs from SQUARE were not able to accept real change without hesitation. I say that the person who will have no change is already dead. After termination of Koudelka project, I retired as CEO of SACNOTH. It was my choice.
RB: As a composer how should music effect the game? As a developer how should the music effect the game?
HK: A music composer wants to create a good tune with utter simplicity. But if you want to create a good game as a developer, it is not enough. Because good music does not necessarily fit a good game. The most important problem is adjustment of each of the elements. If the visual element exactly synchronizes with the musical element, a dramatic effect will be generated.. And I take it for granted that everybody wants to hear a good melody in the end.
RB: What were your influences for Koudelka?
HK: In the first instance, I designed all concepts and fundamental settings of the Koudelka's world. I gathered various graphic and text materials in London and Wales. I did character design, map design, event design, scenario writing, direction of computer graphics movie, direction of motion capture... I got involved with all of the integral parts of Koudelka except battle and game system. Especially, I had no influence in battle section. I still have a great regret. I wish I could have designed it. And a quick digression, I consulted many movies and books for Koudelka. A most impressive movie is The Name of the Rose (Jean Jacques Annaud 1986). I also read the original book which was written by Umberto Eco. It is a definitely masterpiece. If you want to know some origins of Koudelka's world, you may read Carnacki the Ghost Finder written by William Hope Hodgson and The Case of Charles Dexter Ward written by Howard Phillips Lovecraft. Many fantasy novels by Lord Dunsany (His his full name and title is Edward John Moreton Drax Plunkett 18th Lord Dunsany) are also important. If you want to know about visual origin of Koudelka, see photographs created by Bob Carlos Clarke and Jan Saudek and Holly Warburton. Those are extremely exciting works.
RB: How did you manage to write, direct and compose the music for Koudelka?
HK: Writing a scenario. Directing a CG movie. Composing a BGM. Each of those is no more than a single face of game creation. When I imagined the world of Koudelka, I figure graphic elements and story elements and sound elements all at once. Because, those are mingled with each other organically. So I think that It is rather easy to manage multiple affairs.
RB: What was the easiest aspect of working on Koudelka? What was the hardest?
HK: The easiest aspect is music composing. Because I can create a music by my lonesome. It makes me free and I feel comfort. Hardest aspect is behind-the-scenes maneuvering of power game in company organization. I am so tired to do that. Let's get something straight, I am not a buccaneer but rather a creator. All aspects about creation are really pleasant for me.
RB: Why do you make music? Why do you make games?
HK: Music composing is a natural behavior for me. Like breathing. I usually conceive a good melody and a harmony without suffering. So I have no reason to make music. I think that it is my vocation. Meanwhile, creating video game is not my vocation. It is my wish. I want to produce high quality entertainment in the future. When I write a story and a plot, I usually suffer by myself. Though it is very hard and thorny, I feel maximum accomplishment.
RB: What inspires your melodies?
HK: Many great works of famous composers and musicians inspire me. If I must respect only one person or group as a music composer(s), I will take Pink Floyd.
RB: What are your hobbies and why?
HK: Good question. Riding bicycles is my hobby. I also love my yellow Peugeot MTB made in France. I also have some fun playing with my cat. She is extremely pretty.
RB: When did you begin working at Square?
HK: I began work at Square in 1991. I was twenty seven years old. In those days, the production studio of Square was placed in Akasaka Tokyo. It was small and homey, different from now. I remember that Nobuo Uematsu and Kenji Ito interviewed me in their office. We talked about progressive rock music and famous guitar player Allan Holdsworth with each other. I created sound effects for Romancing Saga at the start of my career. A few of graphic staff worked with me to design a lot of novelty sounds. We worked hard in night and day.
RB: How much freedom did you have making music at Square?
HK: In a sense, I had perfect freedom. Because, the planning staff of Square put none of the assignments relevant to the menu of music work and schedule in my hand. Nobody explained to me about game detail which they were producing. I had to think and imagine what kind of music was needed for our game project. Changeover,changeover, and more changeover of specifications. It was difficult to foresee the final image of it. But I did.
RB: What is favorite game that you worked on at Square and why?
HK: May be Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana). I think that it was a pretty good game except for the big BUG. The multi player system was extremely fresh and delightful. In the aspect of music, I was fully challenged in regard to sound expression using 8 voice PCM system of SNES hardware. Please see and hear the opening sequence of Seiken Densetsu 2. It is so simple but so lyrical, isn't it? I am really proud of my visual direction and music composition.
RB: Did Nobuo Uematsu influence your work?
HK: I think there is no influence from Nobuo Uematsu. I have never taken any lessons about composing game music. The style and the melody of my music are totally conceived by myself. Just the same, every staff composer at Square were free from influence of somebody else. Originality and personality were cheerished in our studio. It was the policy of Nobuo Uematsu.
RB: What are the best and worst memories that you have of Square?
HK: Hmmm... Best memory... it seems a trip to MANA island of Fiji republic. After a production of the game Secret of Mana, I and my friend decided to visit an island placed in South Pacific Ocean. We played skin diving everyday and watched some corals. Those were extremely beautiful. It looks like a blue heaven. I will never forget the view of the sunset from Mana's beaches. It is one of my treasures. By the way... Worst memory is a dissolution of the game team in which I was supposed to participate. I wanted to propose an innovative game system using music and sound effects.
RB: Who is your favorite Square composer and why?
HK: I recommend Jin Sakimoto (Hitoshi Sakimoto). His works are extremely dense.
RB: One of our favorite soundtracks of yours is Soukaigi. The sound quality and styles are some the best for a game.
HK: Soukaigi has many characters of sound. I designed it with different complex styles. House music meets real performance, fusion meets folk choirÖÖ It was an adventure for me. To tell you the truth, the style of music does not a matter. I don't dwell upon it. Though I put a high value on counterpoint it does not bind me. It is only a method. In the case of Soukaigi, I was mainly influenced by East European pops like Varttina.
RB: Why did you leave Square?
HK: I wanted to direct not only musical expression but also visual expression. And of course, I wanted to write a fine scenario which is different from existing one. I had felt a big complaint against those juvenile works. But unfortunately, I couldn't get a chance to take a part in those kind of production works in Square. I suffered terribly for a long time. After all is said, I left Square and established new company Sacnoth to achieve my idea.
RB: Do you perform your music live?
HK: If I have a chance to do that, I wish to play my music as a live performance. I didn't make an attempt to do that in Japan yet. Do you want to hear my music in front of your eyes, ya?
RB: Who would you like to make music with?
HK: Jin (Hitoshi) Sakimoto. Because, I could not collaborate with him on composing game music when we were hired together by Square. I respect him. Except for game music composer, I want to collaborate with Allan Holdsworth, a fusion guitar player. His music is a miracle.
RB: How do you think game music compares to other genres of music?
HK: I think that is similar to movie soundtracks. It is important to synchronize the music with visual element. It has an expressive purpose. If you want to create a game music, don't forget to construct it as an emotional device.
RB: How will the next generation consoles allow you to express yourself as composer and game designer?
HK: I feel a strong attraction to X-box and Game Cube. A big visual capability makes me hot. I have many ideas to display fascinating characters using real time computer graphics. They will sing and dance and talk with real emotion. Don't you want to play the Musical RPG on Network? I want to play it.
RB: What would your advice be to people who:
A. People who want to create game music.
HK: Listen to as much music as you can. Don't confine yourself to your room. The genre of music is meaningless. If you want to find your treasure, you must challenge the common practice at any one time.
B. People who want to create games.
HK: Video games are not art. They are an entertainment. You must amuse your audience first instead of amusing yourself. I am always conscious of the feeling to accommodate someone with a fun service. Can you create a lot of gimmicks for the player? If you work so hard and push yourself enough, the day will come to collaborate in some way with me for sure. Let's think of a next game together.
RB: What is in the future for Hiroki Kikuta?
HK: I will be involved in some new game projects that are not directed by me. I will be a technical advisor. I will create computer graphics and sounds. But soon, I hope to form my studio and develop my own game project. So now I am looking for new investors around the globe.
RocketBaby would like to thank Mr. Kikuta for chatting with us.
#koudelka#shadow hearts#hiroki kikuta#if anybody finds this post I'll be thoroughly surprised#archive
3 notes
·
View notes
Text
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/58940
台湾のヘリ墜落は中国の斬首作戦か
台湾総統選の裏で発生した“事故”とソレイマニ将軍暗殺
2020.1.15(水)
用田 和仁
1 イランと台湾
イランの革命防衛隊コッズ部隊(対外工作部隊)司令官、ソレイマニ将軍への攻撃は米国の斬首攻撃だった。さぞや北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は肝を冷やしたことだろう。強烈な抑止力だ。
一方、その陰で1月2日に台湾軍の参謀総長が乗ったヘリコプターが、北東部・宜蘭県の部隊を訪問するため台北市の松山空軍基地(軍民両用)を離陸した直後、山中に墜落し、乗っていた参謀総長をはじめ8人が死亡した。
しかし、この「事故」があったことに、日本人は関心がないようだ。
この2つに何か類似性はないのか、疑問に思うことはないのだろうか。そして、誰がこの2つの出来事を喜んでいるのかを考えることはないのだろうか。
国際社会を揺るがす事件に直面しても軍事は他人事、国民皆評論家ではこの国の行く末は危ない。
2 中東の危機
米国とイランの本格的な対決は始まったばかり
言うまでもなく、現代の中東の危機はイスラエルに起因していると言っても過言ではない。
そして、米国の中東政策の大きな誤りは、イラクを2度の戦争で壊滅させ、力の空白を作ったことに起因している。
湾岸戦争まで、イラクは少数のスンニー派が支配し、過酷な統治であったものの、中東における米国の盟友であった。
過酷な統治が悪いというならば、アラブの国の統治はサウジアラビアなども例外でなく過酷であろう。
イラクが壊滅し、力のないシーア派の政権になって以来、イランが浸透する土壌ができ、さらに、スンニー派の残党を中心とするイスラム国を米国が中心となり壊滅させたが、結果的に、米国がイランのイラクに対する浸透を手助けしただけだった。
今イランは、核武装する可能性のある反イスラエルの最後の砦であり、米ドナルド・トランプ大統領がイスラエルに傾倒すればするほど、イラン壊滅に向かうだろう。
今回の休戦は一時的であって、イランの後押しを受けた民兵組織などが、もし、イスラエルを攻撃したならば、米国は即、イランに対して大規模な攻撃を仕かけるだろう。
中東の危機は日本の危機
米国が、イランに関与すればするほど喜んでいるのは中国・北朝鮮だ。
しかし、米国は中国打倒を諦めたわけではない。イランを叩き、中東が不安定化すれば、中国は原油を輸入することが困難になってこよう。
米国は、イラク、アフガニスタンの軍事作戦で圧倒的な破壊力を発揮したが、中東諸国の粘り強いゲリラ戦には手を焼いている。
そこで、今後は、①経済制裁を主とし、粘り強くイランを屈服させる②短期決戦でイランを攻撃し決着をつけるという2つのオプションを持ちながらイラン対処に臨むだろう。いずれにしても核の放棄は妥協しないだろう。
②のイランを攻撃する場合は、限定的な「A2/AD」能力を持つイランに対する攻撃の様相は、ミサイルや空軍、空母からの対地攻撃、すなわち、太平洋正面では放棄した「エアシーバトル」で一挙にイランの重要なインフラや地上目標を破壊することになるだろう。
当然、イランの核施設の完全破壊が主目的だ。
核のないイランはイスラエルにとって、もはや脅威ではない。その後米国は、経済制裁を強化することによってイランを3流国にまで貶めることは可能だ。
上手くいけば、もう一度イラン革命へ持っていけるかもしれない。
一方、米国は、中東の石油はもはや米国にとって必要ないと明言した。
今後、米国はゲリラ戦に巻き込まれる不毛な戦いには関与せず、中東から大きく距離を置く可能性が出てきたと見るべきだろう。
そうなると、中東石油依存率約88%の日本は、遂にそのような事態になったかと生存の危機を感じないだろうか。
米国にとっては、当面、イランと中国という2正面作戦で不利な態勢ではあるが、イラン問題が収束し中東に関与をしなくてよくなれば、その後は中国へ専念できる。従って米国にとっては
①万一、武力衝突に突入した場合、イランとの対決は海空主体の短期決戦に持ち込む。
米国の軍事産業にとっては、対地用の旧い弾を撃ち尽くすことで、対中国用の新型弾道ミサイル、対艦ミサイルなどの増産へ移行ができ、結果、新旧交代で(言葉はよくないが)儲けることができる。
②今後の中東は、NATO(北大西洋条約機構)や関係国に任せる(日本も含まれる)。
③中国の石油については、中東のみならず、長いシーレーンを活用して海上封鎖網を構築し抑止体制を強化する。このため英仏印豪などとの連携は必須だ。
日本は、これらの激変に指をくわえて見ているのか。即やるべきことはあるだろう。
①自らの国は自ら守り切る防衛力を至急構築、このため、防衛国債などを活用して防衛費を2~3倍に増加。
②イランやロシアが行う、サイバー攻撃や電磁波攻撃と連携した非正規軍(階級章はつけていなくても精強部隊)によるハイブリッド戦は、米国のみならず日本の「正規軍」では対処が難しい。
さらに日本では、グレーゾーン事態に対処する法規もないために、自衛隊ではほとんど対応できない。
1発も弾を撃たないで戦いが終わる可能性は極めて高い。結局、自衛隊が軍隊でなければならない理由はここにもある。
至急、グレーゾーン事態においてサイバー・電磁波攻撃と連携する、海上民兵に先導された大量の「精強部隊」に対処できるよう、法律の制定も含め体制を整備すべきだ。陸自を削っている場合ではない。
③石油に頼る日本の体質を改善するため、本気で原発の再稼働、新原発の開発・増設、そして、気まぐれ発電の太陽、風に頼らない水素を中心とした新電源開発への転換を図る。
さらに、食料の自給率の向上、閉鎖的な農業政策の抜本的改革の断行などやるべきことは沢山ある。
野党は桜を見る会がどうしたと些末なことを言っている場合か。そして、これらの改革と実行に、これからの日本の繁栄と防衛がかかっている。
3 台湾の危機
蔡英文総統は最高得票で再選され、民進党も議会の過半数を維持できたことは幸いだった。これで、少なくとも今後4年間は米国と共に、自由主義の盾となり続けるだろう。
日本も祝意は示したものの、米国のマイク・ポンペオ国務長官はもっと踏み込んで「台湾が民主主義を求める国々の手本となる事を望む」「容赦のない圧力にもかかわらず、台湾海峡の安定に対する蔡英文総統の取り組みを称賛する」と語った。
残念ながら、日本人は台湾が日本の運命共同体だということを理解していない。軍事的に見れば明白である。
すなわち、台湾が中国のものになれば、中国は米国を西太平洋から排除し、かつ、中国の3つの経済的核心的地域である、
北京・天津、上海、広州・珠海を守る外壁である第1列島線に出城を築くことができる。その破れた第1列島線から、中国の航空機、軍艦・潜水艦などが太平洋に自由に進出できる。
一方、前方展開戦略を基本とする米国は、その中核の足場を奪われて戦略的破綻をきたし、グアム以東への退却を余儀なくされ、東アジアにおける覇権や権益を中国に明け渡すことになる。
換言すれば、中国の「接近阻止・領域拒否(A2/AD)」戦略の完成を許し、米国は、中国の思惑通りハワイ以東に駆逐される。
そして、中国軍の軍事的影響力は日本の太平洋側へも直接及ぶことになり、もはや、米軍も近づけず、日本は中国の軍門に下ることになろう。その意味をしっかりと心に刻み込む必要がある。
一方で収まらないのが中国だ。
香港で躓き、台湾でも躓いたことになる。日本だけが、相変わらず危機感もなく、習近平国家主席を国賓で招待することを進めている。
中国は、日本は政治・経済的に籠絡することができると読んでいるのだろう。
一方、台湾は、総統選および立法委員(国会議員に相当)選において与党民進党が勝利したことで、中国は、武力統���を行わない限り、2020年の中国共産党創設100周年記念で台湾を中国のものとして、祝杯を挙げることができなくなってしまった。
参謀総長が乗ったヘリコプター墜落事故に戻ると、あくまで推測の域を出ないが、中国が、台湾総統選挙で敗色濃い情勢に一矢を報いたいと思っても不思議ではなかった。
墜落事故の原因は、今後の詳細な調査結果を待たねばならないが、下記のようなことが考えられる。
①ヘリコプターの整備不良、または、部品の損壊
②人為的な操縦ミス
③天候不良
④誰かが作為して墜落させた
事故の第1報では、天候は良く機械の故障でもないようだ。また、「UH-60」というヘリコプターは、エンジンが2つある優れたヘリコプターで、そう簡単には墜落しない。
一般的に言って、軍トップの参謀総長が乗るヘリコプターは、十分に整備されていると考えてもおかしくないだろう。
そうなれば、今のところ証拠はないが、誰かが作為してヘリコプターを墜落させたという推論は、架空の議論ではないだろう。
もっと言えば、台湾軍の80%は中国を支持する国民党員であることは台湾にとって懸念材料だ。
もし、中国が関与していたならば、その目的は
①台湾の軍トップでも蔡英文総統でも、中国は何時でも斬首攻撃ができるぞという脅し
②中国は台湾の統一はあきらめず、台湾の生殺与奪の権は中国が握っているというメッセージ
③習近平国家主席は、腰抜けではないというメッセージを中国共産党へ見せる
などが挙げられよう。しかし、中国関与の証拠は示されないであろう。
曖昧にしておく方が脅しは効くし、米国などの国際社会の非難を避けることができる。それでいて、得体のしれない恐怖を台湾に与えることができるからだ。
4 2020年は日本の鬼門
日本は、夏のオリンピック、パラリンピックの成功に向けて、世界中からたくさんの来訪者を歓迎し何とか盛り上げようとしている。
しかし、今春の習近平国家主席の訪日は別問題であり、外交関係者や経済界は、日本の生存という国益を顧みず、習近平国家主席を国賓で招くことに固執しているが、正月早々から、そんな状況ではないことが見えてきた。
日本は、もう一度、与党も野党も些事に囚われることなく、この国の真の繁栄と生存を考え、即、実行に移さなければならない歴史の曲がり角に来たことを自覚するべきだろう。
3 notes
·
View notes
Link
台湾総統選(投票日は1月11日)は、蔡英文現職候補が圧勝すると予想している。民意調査が出そろっているが、ほとんどの調査で蔡英文の支持率が3割ほど国民党・韓国瑜をリードしている。
昨年(2019年)12月に入って、蔡英文政権支持者で、ネット上の民進党の広報宣伝を請け負っていた著名ネット・ユーザーの楊蕙如らが、2018年9月の台風21号で関空が封鎖されたときの台湾旅行者への対応のまずさを台北駐大阪経済文化弁事処代表になすりつけるような世論誘導を行い、当時の大阪弁事処代表を自殺に追いやったとしてネット公務員侮辱罪などで起訴された。そうした国民党側による民進党側のスキャンダル暴露もあることにはあるが、「台湾の主権が中国に飲み込まれてよいか」という大争点をかき消して今の蔡英文優勢をひっくり返すほどの影響力はないだろう。
何より、中国側がちょっと諦めムードになっている。昨年(2019年)末に発表した習近平の新年挨拶で、台湾同胞に何のメッセージもなかったのが、その証拠ではないか。香港とマカオに言及しているのに、不自然なほど台湾の名を出していない。新しい国交樹立国が増えたことには言及しているのに、台湾の名を避けている。今はその名を口にしたくもない、という習近平の気分が見えるような新年挨拶であった。
さらに人民日報海外版(1月3日)に寄せられた論評「台湾問題は必ず民族復興で終結する」(王昇・全国台湾研究会副会長)を読めば、「台湾社会はストックホルム症候群(被害者が加害者に親近感を覚える)」という表現で、台湾人自身が祖国・中国よりも占領国であった日本や、台湾海峡を分断して第1列島線に台湾を組み込んで両岸の対立を生んだ米国のほうに親近感を覚えている現状を確認している。台湾問題の解決が遅々として遅れているのはそれが原因だという。そして、「将来30年のプロセス」のうちに両岸関係の発展を推進し続け、最後には必ず民族復興により中台統一という結果で終わる、としている。昨年、習近平は年明けに「台湾同胞に告げる書」40周年記念で、「習五条」と呼ばれる強硬な台湾政策を発表し、自分の政権中に中台統一を実現するといわんばかりの強気を見せていた。それが王昇のコラムでは、今すぐという話ではなく、将来30年のうちに最後には統一する、といった長期ビジョンの話になっている。
蔡英文、習五条への対応で息を吹き返す
昨年の今ごろ、蔡英文政権は前年秋の地方選の惨敗を受けて党首を引責辞任、政権支持率は20%代に低迷し、蔡英文を候補にしては総統選挙は戦えない、と誰もが思っていた。前行政院長で反中姿勢を際立たせていた頼清徳を候補にした方がまだ望みがあるのではないかという空気が、民進党支持者の中にもあった。古参支持者の中には、頼清徳を候補にして万が一負けることになれば、民進党自身が瓦解しかねない、という危機感を言う者もいた。頼清徳で負けたら、民進党内に、あとに続くタマはない。
蔡英文政権の人気の無さは、官僚気質の蔡英文の対中姿勢の曖昧さやゆらぎ、経済低迷、脱原発やLGBT婚といったリベラル政策が(若者には受けても)、保守層の多い中高年台湾有権者から反発を受けていたことなどが要因だった。また民進党自体が、運動家気質で未熟な政治家の寄せ集めという面もあり、党内の結束も甘かった。
高雄市などでは、ろくな政策運営ができないまま、ただ市民の国民党への反感から民進党が選ばれ続けている現状に胡坐をかき続け、その結果、キャラの際立った国民党・韓国瑜候補の「ワンフレーズ」選挙と、中国のネット世論誘導の前にあっさり敗れた。
この風向きを大きく変えることになった最初のきっかけは、2019年新年早々に習近平が打ち出した「習五条」と呼ばれる対台湾政策だろう。「一国二制度」による中台統一を「必須」「必然」と言い切り、「中国人は中国人を攻撃しない」(台湾人を名乗れば攻撃する、というニュアンス)、「武力行使の選択肢を放棄しない」「中華民族の偉大なる復興に台湾同胞の存在は欠くことができない」(先に統一して、今世紀中葉の中華民族の偉大なる復興を共にめざす、というニュアンス)とかなり恫喝めいたものだった。
習近平はこの時点で、自分が権力の座にいるうちに台湾統一を実現する自信があったと思う。そして台湾統一を実現することによって、揺らぐ共産党の正統性(レジティマシー)を固め、米国とのヘゲモニー争いの劣勢を挽回しようと考えたのではないか。習近平がそういう強気をみせられるほど、その時の蔡英文政権は窮地に立たされていたのだ。
だが、この習五条が打ち出されると、蔡英文は珍しくきっぱりと、「一国二制度」に対してノーの姿勢を打ち出した。一方、国民党主席の呉敦儀は2月の段階で政権を奪還した暁には「両岸和平協議」を推進することを言明しており、統一大中国を完成させることが国民党の変わらぬ願いであることを確認した。この時点で、2020年1月の総統選の争点は「一国二制度による統一か、抵抗か」という選択肢を有権者が選ぶというものになり、過去4年の与党政権の政策の評価はあまり関係なくなった。
一気に流れを変えた香港の「反送中デモ」
ただし、2019年4月の段階ではまだ、世論も揺れていた。
聯合報(4月9日付け)によると、台湾生まれの米デューク大学教授、牛銘実が行った台湾民意調査で、「台湾が独立を宣言すれば大陸(中国)の武力侵攻を引き起こすが、あなたはそれでも台湾独立に賛成するか?」という質問に対して賛成は18.1%、非常に賛成は11.7%と合わせても3割に満たなかった。牛銘実によれば、台湾人はコストの概念が強く現実主義で、基本的に独立はしたいものの、「独立か統一か」という二者択一を迫られた場合、戦争という高いコストがかかるようなら統一を選ぶ傾向がある、という。
揺らぐ世論を一気に、統一反対に動かしたのが、いうまでもなく香港の「反送中デモ」である。特に6月9日の100万人規模のデモと、その後の抗議活動に対する香港警察の容赦ない暴力、それに抵抗する勇武派デモとの応酬がエスカレートするにつれ、蔡英文の支持率がウナギのぼりに上がっていった。楽天的な台湾人も、中国のいう「一国二制度」の恐ろしさを香港の現状で悟ったわけだ。
中国は、フォックスコンのカリスマ経営者・郭台銘を国民党から出馬させることで、中国との経済緊密化による台湾経済の引き上げを餌に台湾世論を引き付けようとした。だが、あからさまな親中派である郭台銘の人気と信頼は、中国が予想するほど高くはなかった。結局、郭台銘は総統候補の予備選に敗れた。
さらに言えば、米国が民進党政権を推していることが決定的な追い風になった。伝統的に国民党を応援していた米国は、中国との対立が価値観・秩序をめぐるヘゲモニー争いとして先鋭化していく中で、中国共産党に対して明確に距離を置く民進党支持の姿勢にシフトした。
昨年12月に上院で可決された米国防権限法では、米台のサイバーセキュリティ―での連携、台湾総統選への中国の干渉への警戒が盛り込まれた。同月はじめ、オーストラリアでは「共産党のスパイ」を名乗る王立強が台湾や香港での工作をメディアに告白。台北101タワーにオフィスを構える香港・中国創新投資会社会長の向心夫妻が自分の上司にあたる上級スパイだ、と爆弾発言。台湾当局は向心夫妻に出国制限をかけて取調べを始めた。こうした状況を受ける形で、台湾立法院でも、年明けに中国の選挙干渉を防ぐための反浸透法を賛成票69票・反対0票で可決。この法により国外の「敵対勢力(中国)」による選挙運動やロビー活動、政治献金、社会秩序の破壊、選挙に関連した虚偽情報の拡散などの活動を禁止し、違反した者には5年以下の懲役および1000万ニュー台湾ドル(約3600万円)以下の罰金が課されることになった。
もう1つ言うと、韓国瑜は総統候補としては、あまりに無能すぎた。高雄市長選のときは、中国の世論誘導もあってブームにうまく乗ることができたが、メディアへの露出が増えるに従い失言が増え、無知や無能ぶりがばれていった。6月9日の香港100万人デモについて記者から質問されて「知らない」と答えたり、ドイツの脱原発政策の見直しが浮上していると発言してドイツ政府からクレームが入ったりしたことは、その一例だ。
蔡英文政権2期目突入の大きな意味
さて、今回の総統選でもし民進党・蔡英文政権が勝利し2期目に突入するとしたら、その意味は歴史的なものになるかもしれない。
1つには、習近平は香港への対応だけでなく、台湾への対応も失敗し、中台統一の機運をほぼ永久的に失うかもしれないからだ。この事態は、「習近平の失態」として党内で問題になるかもしれない。1年前までは蔡英文再選の目などなかったのだ。
人民を豊かにするという目標を掲げるも経済成長が急減速していくなかで、共産党一党独裁の正統性を維持するために台湾統一は必須であった。それが不可能になれば、共産党の執政党としての正統性は根底から揺らぐ。台湾総統選で蔡英文が勝利すれば、それは習近平の敗北である。
さらに、歴史的に国民党推しだった米国が初めて民進党推しに転じての選挙であり、米台の安全保障面での緊密化は加速していくだろう。中国の金銭外交によって国際社会での孤立化が急速に進んだ蔡英文政権だったが、米国との急接近は台湾の国際社会における地位を大きく押し上げることになる。
さらに言えば、蔡英文政権の後を頼清徳政権が引き継ぎ、通算16年の長期民進党政権時代が誕生する可能性も出てきた。それだけの時間があれば、台湾アイデンティティは、中華アイデンティティと異なる形で確立でき、また官僚や軍部に根強く残る国民党利権、しがらみも浄化できるかもしれない。東シナ海に、中国を名乗らず、脱中華を果たした成熟した民主主義の自由な華人国家が誕生することになれば、それは近い将来に予想される国際社会の再編を占う重要な鍵となるだろう。
かなり私的な期待のこもった見立てではあるが、今も続く香港の若者の命がけの対中抵抗運動と、米中対立先鋭化という国際社会の大きな動きの中で、台湾は国家としての承認を得られる二度目のチャンスに恵まれるかもしれない。
5 notes
·
View notes
Link
有料会員登録サインイン
日本語 (Japanese)
2021年1月31日
60年超え現役、米B52爆撃機が活躍する事情 将来の戦争に備え、冷戦時代の爆撃機に頼る 米戦略爆撃機B52 U.S. Air Force/Getty Images
2021 年 1 月 28 日 09:10 JST 更新
【東シナ海上空】「戻れ」。中国の航空管制官が警告を発した。「中国の領空に接近している。直ちに進路を変更せよ。さもなければ迎撃する」
中国の沖合160キロをゆっくりと進む米空軍爆撃機B52の乗員は、無線機から聞こえる警告を無視した。就役60年を経た機体はそのまま飛び続けた。
これは爆撃機のプレゼンスを示すための任務だ。こうした飛行の狙いは、米軍がカバーする範囲の広さを誇示し、領有権争いをする空域で国際通過通航権を擁護することにあった。
同時に、米国防総省の計画が垣間見える機会でもあった。すなわち将来の戦争への備えを、冷戦時代初期に作られた航空機に頼っているということだ。
この任務はグアム島のアンダーセン空軍基地で夜明けと共に始まった。乗員は酸素マスクと「プーピースーツ」を身につけた。万一海に不時着した場合、寒さをしのぐための膨らみのある全身スーツだ。
そして、操縦する乗員よりはるかに年季の入った爆撃機は、ごう音を立てて滑走路を走った。アナログ式ダイヤルと老朽化したレーダーを頼りに、太平洋上をジグザグ飛行し、米国は未承認だが中国が「防空識別圏」と主張する空域内で機動作戦を行うために。
中東やアフガニスタンで反政府勢力との戦争を20年近く続けた国防総省は、ここにきて「大国間競争」に軸足を移した。同省の支出や計画を対中・対ロに大転換するために頻繁に使われる決まり文句だ。
この装備の一新は、過激派武装グループとの戦いで疲弊し、より危険性の低い北東アジアや中東のならず者国家への対応に焦点を移している米軍にとって、コストのかかる軌道修正となる。この戦略はジョー・バイデン大統領の下で就任したロイド・オースティン国防長官もおおむね支持するが、同長官は今後、実現への道筋をつけなければならない。
海兵隊は戦車全廃を進め、代わりに西太平洋の島々を起点に中国艦隊を封じ込める軍事能力を備えようとしている。陸軍は最近、人工知能(AI)やセンサーネットワークを活用し、敵に攻撃を仕掛ける訓練を実施した。海軍は無人艇の開発を進めている。
だが、この戦略転換が特に大きなチャンスをもたらしたのは長距離爆撃機だ。国内に新型コロナウイルスの感染拡大問題を抱える中、米国は長距離爆撃機の力を借り、世界中で力を発揮できることを示している。
敵の高度な防空網をすり抜けるため、空軍は次世代ステルス爆撃機B21「レイダー」の開発を進めている。この爆撃機隊には1948年設計の戦略爆撃機B52「ストラトフォートレス」も加える予定だ。同機はコンピューター以前の航空計算尺を組み込んでいる。
「それは実際、作りがタフだった時代に作られた古いトラックのようなものだ」。空軍参謀総長で元太平洋軍司令官のチャールズ・Q・ブラウン大将はこう話す。「そうしたプラットフォームが現在抱える課題は、新しい技術と機能をいかに搭載するかだ」
古い家屋を全面改装するのと同じく、耐久性のある航空機の機体は保存し、燃料を大量消費するエンジンや、年代物の無線機、アナログ式計器類、胴体内部の爆弾倉は最新のシステムに入れ替えられる。
空軍の長期計画にB52は不可欠な存在で、少なくとも2050年まで76機を運用することになっている。その頃には最新のものでも機体年齢が90歳近くに達する。軍幹部の一部は100歳の「長寿」を祝う可能性もあると話す。1960年代にB52(ノーズコーン部分)の形状に似たビーハイブヘアが流行し、後にその髪型をしたバンドの名になったことは今も人々の記憶に残る。
空軍が今後数十年続くこうした異例の解決策に頼ることになったのは、国防総省が冷戦は終結したとみなし、中東で武装組織と戦うのにその後の年月を費やした判断の産物だといえる。
年代物の爆撃機への依存は、国防総省が大国間紛争の多発する世界にかじを切り直すまでの道のりの長さも映し出す。国防総省は財政赤字拡大に直面する中で、戦力を維持しつつ、最先端技術を導入するのに大いに苦戦している。
核の時代の幕開けと共に登場したB52はそもそもの役割が核戦争の抑止であり、必要ならば、戦闘にも出向くというものだった。フットボール競技場の長さの3分の2近い翼幅を持ち、8基のエンジンを搭載するB52は「BUFF」(Big Ugly Fat Fellow=巨大で醜く太ったやつ)という親しみを込めた愛称で呼ばれた。
1960年代には、核兵器を搭載した十数機のB52が24時間、空中待機の状態にあった。その胴体には核爆発の熱を表す光沢ある白い塗料が塗られていた。
「核兵器環境での戦闘のストレスや緊張に耐えるよう設計されていた」。元B52パイロットで現在はミッチェル航空宇宙研究所の所長を務めるマーク・ガンジンガー氏はこう話す。
紛争の非核化によってB52には戦闘の役割が与えられた。核爆弾2基を搭載できる設計だった同機はベトナム戦争では約27トンの通常爆弾搭載能力を持つよう改造された。
空中発射巡航ミサイルの開発によりB52は国防総省が「スタンドオフ」と呼ぶ、敵の射程圏外からミサイルを発射できる能力を備えた。B52は1991年の湾岸戦争を機にその役割を引き受けた。同機はアフガンやシリア、イラクの武装勢力に対し、衛星誘導爆弾を投下するプラットフォームとなり、過激派組織「イスラム国(IS)」からモスルを奪還する戦いでも活躍した。
B52が適応できた一方で、他の爆撃機は逆風にさらされた。B52の最初の代替機はB70になるはずだった。極めて高速かつ高高度の飛行に力点が置かれたが、ソ連がそうした脅威に照準を合わせる防空体制を整えたために意義を失った。
空軍が開発したB1B爆撃機「ランサー」は、可変後退翼の採用によって低高度飛行が可能になった。だがアフガンや中東での高高度任務のために翼を前に倒すと予期せぬストレスに直面した。
ステルス爆撃機B2「スピリット」は空軍が最先端技術を駆使して開発した。だがロシアとの緊張緩和や��算ひっ迫のため、当初の132機から21機に計画が大幅縮小され、1機当たりの費用は20億ドル(現在のレートで約2074億円)を超えた。
だが、同機は長距離ミサイルを発射できるほか、衛星誘導爆弾や地雷を搭載することが可能であり、現在運用されている空軍爆撃機の中で唯一、核弾頭装備の その一方、国防総省との意見対立で、次世代爆撃機(NGB)開発に遅れが生じた。空軍の提案がコスト急増を招きかねないと懸念したロバート・ゲイツ国防長官(当時)は2009年、この提案を白紙に戻し、立証済みの技術だけを用いるよう空軍に指示した。
2018年には、台頭する中国との摩擦拡大やロシアとの新たな緊張が、国防総省の考えに変化をもたらし、当時のジム・マティス国防長官は中ロ両国が今後数十年にわたる米国の主要な脅威だと認識するに至った。
この戦略シフトはさまざまな空中戦システムの開発に弾みをつけた。例えば操縦士が乗るジェット機とドローンが編隊を組むといったことだ。それはまた、長距離爆撃機の新たな黄金時代の始まりでもあった。
空軍の将官らは昨年、戦略核戦力の3本柱(長距離爆撃機・陸上発射型ミサイル・潜水艦発射型ミサイル)を維持する一方で、通常任務用の爆撃機を少なくとも220機保有するよう軍に要求した。この目標は現在の158機からの大幅増を意味する。
コックピットを背後からみた様子
Photo: Michael Gordon/The Wall Street Journal
だが、同機は長距離ミサイルを発射できるほか、衛星誘導爆弾や地雷を搭載することが可能であり、現在運用されている空軍爆撃機の中で唯一、核弾頭装備の 空軍は新型ステルス爆撃機B21の開発を進めている。2020年代の中盤から終盤には戦力に組み込まれる見通しで、少なくとも100機は配備する意向だ。空軍は爆撃機の体制を維持するため、B52の寿命を延ばすと同時に、機体が少ないB2や戦闘で消耗したB1Bを段階的に退役させ、資金を節約する方針だ。
「空軍がB52の近代化にこれほど依存する理由の1つは、他の後継機候補が途中で挫折したことにある」。米議会調査局(CRS)の軍事航空アナリスト、ジェレマイア・ガートラー氏はこう指摘する。「空軍は性能より搭載能力が必要だと判断した」
B52では強固な対空防衛能力をかいくぐることは見込めず、燃料を食う同機のエンジンはもう製造されていない。空軍は予備のエンジンや部品に頼るしかなく、備蓄は減る一方だ。
巡航ミサイルを搭載できる。これは同機に残された唯一の核兵器能力だ。
B52には別の利点もあった。同機が購入された当時、価格は1機当たり600万ドルをわずかに超える程度だった。
「近頃その値段ではリアジェット(小型ジェットのブランド名)1機も買えない」。B52の元レーダー航法士で、現在は米空軍地球規模攻撃軍団のB52担当副プログラム・マネジャーを務めるアラン・ウィリアムズ氏はこう述べた。
空軍はB52の爆弾倉を改造し、攻撃能力を高める方法を考え出した。そうすれば精密誘導兵器8基を胴体に格納した上で、さらに12基を翼に搭載できる。翼下にパイロンを取りつけ、空軍が開発中の射程約1600キロメートルの極超音速ミサイルを運べる可能性もある。
中国は自国沿岸に米軍を近づけないため、南シナ海で米軍艦の後を追いかけたり、中国が「防空識別圏」と呼ぶ沿岸から約320キロメートルの範囲の東シナ海上空に米軍機が侵入しないよう要求したりしている。この海域には日本の尖閣諸島があり、中国が領有権を主張している。
グアムはこの紛争における米国の重要な前哨基地だ。空軍はアンダーセン基地の第一弾薬庫地区に要塞(ようさい)化した掩蔽壕(えんぺいごう)を建設中で、同軍最大の爆弾・ミサイル保管施設の一つとなっている。米インド太平洋軍司令部は、2014年にグアムに配備された地上配備型ミサイル迎撃システム「THAAD(サード)」を補完するため、16億ドルの防空ネットワークをここに構築するよう提案している。
B52の順応性の高さはゲーツ元国防長官にとっても驚きだった。同氏は少年時代、カンザス州ウィチタの自宅上空に向けて近くのボーイングの工場からB52が飛び立つのをよく眺めていた。「60年後、こいつがまだ空を飛んでいると誰が想像できただろう?」
0 notes
Text
済州島と詩

2001年からずっと、秋になると韓国の釜山国際映画祭に行くということを続けてきたので、さわやかな秋の風や青く高い空を見ると、無性に釜山に行きたくなる。初めて行ったのが夏の終わりからだったせいか、秋の韓国がとても好きだ。
今年は、40年来の我が家の恒例行事である母・嵯峨美子のコンサートも中止となり、これまたなんだか調子がはずれた秋でもある。本来であれば来週が本番だったので、会場でのスタッフの動きの確認やお弁当の手配、リハーサルなどで落ち着かない日々を送っているはずだった。
そんな、少しのんびりした今年の秋、私にとってもっとも大きなイベントは昨年、参加した「2019日韓市民100人未来対話」で��一緒した方からお誘いを受けてスタッフに加わった「歩く文学、ソウルから東京・福岡まで〜〈文学〉と〈歩行〉を通じた新たなる日韓交流のかたち」という催しだった。
「日韓市民100人未来対話」は「日韓両国の各界の専門家、学者、NGO、一般市民たちが近年の東北アジアの環境変化や両国が直面している共通の懸案事項に対して、ともに解決案を模索することにより、未来志向的かつ語形的な日韓会計の基盤を構築する」ことを目的に、日本と韓国の会場を行き来しながら17年から行われている。主催/主管は韓国国際交流財団、ソウル大学校日本研究所、早稲田大学韓国学研究所で、参加者はテーマ別の分科会や全員での総合討論で言葉を交わす。私は千葉で行われた18年と韓国の一山(イルサン)で行われた昨年の2回参加した。

昨年の会議では、「会議の当日だけで交流が終わってしまっていた」過去2回の反省を踏まえ、「参加者が企画を出し、韓国交流財団が認めた」ものに助成する「小プロジェクト事業」を行うことが発表された。これを受けて神奈川県庁にお勤めの中川慶太さんを中心に立ち上げられたのが「歩く文学、ソウルから東京・福岡まで」だった。東京と福岡で活動されている団体の協力を得て行う「歩く」イベントと小説『ギター・ブギー・シャッフル』(新泉社)の著者であるイ・ジンさんと翻訳者の岡裕美さん、ホ・ヨンソンさんの詩集『海女たち 愛を抱かずしてどうして海に入られようか』(新泉社)の訳者のひとり(共訳は趙倫子さん)で作家の姜信子さん、そして、韓国語がご専門である九州大学の辻野裕紀さんが東京、福岡の2カ所で行う「トーク」イベントを合わせるというユニークなものだった。
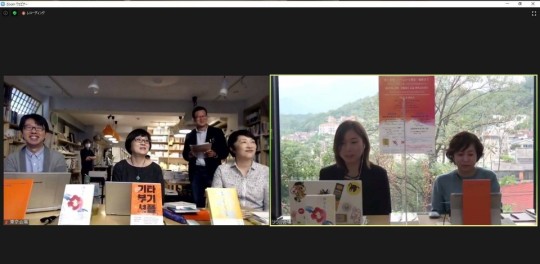
当初、私はスタッフとしてのみ、お手伝いする予定だったが、中川さんからのお声がけで、東京会場のトークにも参加することになった。テーマは「韓国文学の魅力」。主に『海女たち』について話しましょうということになったのだが、さて、私が何を話せるのかと、途方に暮れた。
ジャーナリストとしての経験も豊富な済州島生まれのホ・ヨンソンさんが、海女たちとの対話を元に生み出した『海女たち』。原書は「冊子」と言ってよいほど薄くて小さな本だが、表紙に描かれた赤い椿の挿画が目に飛び込んでくる日本語版は、「日本語で読む人たちにどうしたら伝わるか」が考え抜かれた作りとなっている。一人一人の名前が冠された海女たちについての詩が並ぶ第一部「海女伝 生きた、愛した、闘った」と、「他の誰かから与えられた言葉では到底語り尽くせない地点にたどり着いた」(姜信子さんの解説より)ホ・ヨンソンさんが「みずからの声で」歌った詩を集めた第二部「声なき声の祈りの歌」に分かれている。
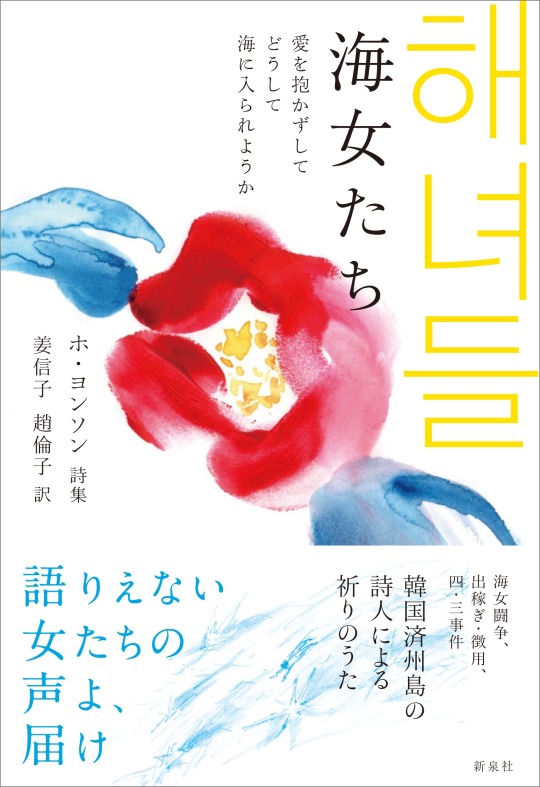
日本では(長く韓国でも)、もっぱら観光地として知られている済州島は、とても厳しい歴史を経験してきた場所でもある。その歴史を、“海女”という、過酷で命がけの仕事をしながら生きてきた女性たちの言葉で書いたのが、この詩集だ。映画を見るという仕事をしながら、「悲劇的な出来事は、どのようにフィクション化すれば見る人の心に響き、残るのか」ということを、いつも考えてきたが、この詩集を読んで、とてつもなく傷ついた人たちの心を慰めたり、いなくなってしまった人を偲んだり、悼み悲しんだりすることは、文学(あるいは詩)にしかできないのかもしれないと強く感じた。
姜信子さんは、別の著書である『生きとし生ける空白の物語』(港の人)の中で「記憶とは、どんなに聞いていっても、最後にはきっと「空白」にたどりつく。そこには言葉にならぬ思いが渦巻く。それは、もっとも悲しく、もっとも痛い、同時にもっとも強く、そしておそろく、もっともかけがえのない思いの渦」と書いているが、余白をたっぷりと含む詩という文学のジャンルは、この「空白」をとらえるのにとても適しているのだということに、改めて気づく。済州島で1948年に起きた四・三事件を映画化した『チスル』が、モノクロという表現を選んだのも、「空白」を残すための工夫だっただろう。
こんな風に済州島と海女のことを考えながらイベントまでの時間を過ごしていると、ちょっと不思議な偶然があった。私は、ひとりでテレビを見る時は、ケーブルテレビのチャンネルで放送されている韓国の番組を見ていることが多いのだが、ふと流れたバラエティ番組の中で、ある女優が済州島を訪ね、海女たちと一緒に海に潜っていた。彼女にお手本を見せた海女のひとりが水の上に顔を出した時に、口笛のような独特な音を出す。『海女たち』の中に何度も登場する「スムビソリ(磯笛)」だ。詩集を読みながら、どんな音だろうを気になってYouTubeで調べてしまった音が、当たり前のようにテレビから流れてきた。その後、女優は海女たちの昼食に合流する。お客を迎えて作られるご馳走の数々は、ところてん、サザエ、トコブシのような小さな貝のスープなどで、「なんだか伊豆で食べているものと似ているな」と思っていたら、西伊豆に住んでいる知り合いからサザエが届いた。
また、イベントが終わった後のことだが、アイドルグループ出身で、現在はソロとして活動する歌手イ・ヒョリが済州島の自宅に一般の客を受け入れるバラエティ番組『ヒョリの民泊2』を見ていると、イ・ヒョリが「この詩が好きなんだ」と言って詩を朗読する場面があった。彼女が紹介したのが、金子みすゞの『硝子』という詩だったのが意外だった。もちろん、『海女たち』とはまるで関係ないことではあるが(『ヒョリの民泊』の中で日本による植民地の時代や四・三事件のについて語られることはない)、「済州島と詩」について、もう少し頭に残しておきなさいという、誰かからの伝言だったかもしれない。
数えてみたら、留学時代を含め、済州島には5回訪れていたが、私自身も四・三事件にまつわる場所や資料館にはまだ行ったことがない。まだまだ、知らなければならないことは多い。
最後に『海女たち』から、読んでいてとても励まされた「わたしたちが歩く海の道は」という詩の後半を紹介したい。
わたしたちが歩く海の道は
さあ おまえはおまえの道をゆけ
おまえはおまえらしく波をかきわけ生きてゆけ
そう語りかける道なんだね
わたしよりも先に旅立って 挫折を知った翼が舞い降りて
ともに歩いてくれる道なんだね
死んだと信じこんでいた希望が 歩けばあとからついてくる
今日は今日の道がある
固く閉じられた心を開いてくれる道
泣いたきのうを
笑う明日へと歩ませる道なんだね
(2020.10.10)
0 notes
Text
プロパガンダ映画『主戦場』の偽善 山岡鉄秀
2019.07.08
月刊『Hanada』2019年7月号に掲載され大反響!
山岡鉄秀「プロパガンダ映画『主戦場』の偽善」を特別公開!
※今月号(2019年8月号)に掲載されている藤岡信勝「慰安婦ドキュメント『主戦場』デザキ監督の詐欺的手口」と併せてお読みください。
■上智大学の思想環境
私の元に興味深い報告が届いた。4月上旬、北海道のある小さな映画館に、ひとりの女性が映画の宣伝に訪れた。
「東京でたいへん話題になっていて人気だから、こちらの映画館でも上映していただけませんか?」 と言いながら示した映画が、『主戦場』だった。
その女性の名は石純姫(ソク・スニ)。苫小牧駒澤大学助教授だった。石氏は、2017年に『朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながり』という著書を出版している。「強制連行されて日本国籍を持たない在日朝鮮人には平等な機会、権利は保障されておらず、生存が脅かされている」と主張する方だ。
4月13日には映画『主戦場』のデザキ監督のロングインタビューが、朝日ファミリーデジタルに掲載された。
「僕はもともとユーチューバーで『日本における人種差別』という動画を自分のチャンネルにアップしたところ、日本の“ネトウヨ”と呼ばれる人たち(ネット上で活動する右翼)に見つかり、オンラインでものすごく叩かれた。 その後、元朝日新聞記者の植村隆さんが慰安婦について書いた記事で同じように叩かれているのを知り、慰安婦問題に興味を持った」
「植村さんと僕のケースは『ある人が語ろうとしてい��問題を語らせまいとしている』という点で共通していると感じた。 アメリカ人としての自分は、誰かが語ろうとする言葉が遮られようとしたら『それはいけない!』と反応する。なぜなら告発や発言の背景には、苦しんでいるマイノリティー当事者が必ずいるからだ。彼らはただでさえ差別を受けているのに、告発の声を遮られることで二重に苦しむことになる」
インタビュー映像が撮影された上智大学には『主戦場』のポスターが誇らしげに貼ってある場所があった。「上智大学グローバル・コンサーン研究所」だ。映画に登場する中野晃一氏がかつて所長を務め、現在も所属している。
当該研究所のホームページに行けば、思想的傾向が明確にわかる。たとえば、雑誌、新聞、メディア関係のリンクをクリックすると、各種刊行物のリンクがリストされている。岩波書店『世界』、『週刊金曜日』、人民新聞(天皇制廃止を主張)等々である。
デザキ氏がどのような思想環境に身を置いてきたか、どのような人々と繋がっているかを見れば、『主戦場』があのように偏向した映画になることもうなずける。最初からそういうスタンスだったのだ。 映画のナレーションで、デザキ氏は言う。
「驚いたことに、私に付けられた反日的なイメージにもかかわらず、多くの保守系論者が取材要求を受け入れてくれた」
朝日ファミリーニュースのインタビュー記事のなかでデザキ氏は、「自分が日系アメリカ人であることがポジティブに影響した」と考え���旨の発言をしている。
またもや完全な勘違いである。彼が日系アメリカ人であることは100%無関係だ。インタビューに応じた保守系論客たちは全員、「慰安婦の証言も矛盾しているんですよねえ」などと言うデザキ氏が「慰安婦性奴隷説に疑問を抱き、公正中立なドキュメンタリーを作ろうとしているまじめな大学院生」だ、と単純に信じ込んでいたのである。
ケント・ギルバート氏は、試写会に行って驚愕したという。それほどまでに皆、人が良いのだ。
彼らがなぜデザキ氏を信用したのか? それは彼の国籍などではなく、彼が上智大学の大学院生だったからだ。「学生なら協力してあげなくてはいけない」という道徳観に従って動いたのだ。それにまんまと付け込まれてしまった。
■取材せずに虚偽を流布
それにしても、特に災難だったのは櫻井よしこ氏だろう。ギルバート氏の紹介だったので、うっかり取材依頼を受けてしまったが、ひどい扱いを受けた。
突如、映画に登場し、慰安婦性奴隷否定派から肯定派に転向したと紹介されるケネディ日砂恵(ひさえ)氏は「深く考えずに米国人ジャーナリストに6万ドル支払ったことを後悔している」と語るが、この部分で登場回数が少ない櫻井よしこ氏にインタビューが飛ぶ。
「あなたもそのジャーナリストと関係があったと聞いたのですが?」と訊かれ、櫻井氏は表情を曇らせて「その件には触れたくありません。複雑なので」と短く答える。
デザキ氏は、この櫻井氏の反応を、いかにも都合が悪くて言葉を詰まらせているかのように映画の宣伝バージョンに使用している。
しかし櫻井氏が言葉を濁したのは、自身に後ろめたいことがあるからではなく、ケネディ氏のプライベートな問題(人間関係・金銭関係など)に触れたくなかったからである。ケネディ氏が様々なトラブルの果てに姿を消したのは、彼女を支援した人々にとっては苦い思い出だ。
そして櫻井氏こそ、ケネディ氏に相談を受けてサポートしようとした人だ。コメントを避けるのは当たり前なのである。 櫻井氏の発言は少ないのだが、映画の後半ではさらに「明治憲法復活を目指す日本会議という恐ろしい軍国主義集団」の宣伝塔だとしてレッテルを貼られてしまう。
日本会議はすでに「映画は事実無根の妄想だ」という抗議の声明を発表している。取材もせずにこのような虚偽を流布するに至って、『主戦場』はもはやドキュメンタリーではなく、プロパガンダ映画の正体を晒す。
それにしても奇妙なのは、ケネディ日砂恵氏の名前が映画のパンフレットのどこにも書かれていないことだ。出演者一覧のなかにも含まれていない。左派に転向したケネディ氏こそ、デザキ氏の最終兵器だったのだろうか? ちなみに、彼女が接触し、現金を渡したとする米国人ジャーナリストは「彼女に騙された」と激怒している。
オウム真理教ウォッチャーで有名なジャーナリストの江川紹子さんが、『主戦場』を見て次のようにツイートしている。
〈《主戦場》見てきた。最初は面白いなと思ったし、よくまあこれだけの否定論者を引っ張り出したなあと感心しながら見ていたが、作りのあまりのアンフェアさにうんざり。一人一人が考える機会をくれる作品かと期待していたけど、むしろ分断と対立を煽る作りに、かなり落胆した〉(6:20 - 2019年5月7日)
慰安婦問題に関する知識の多寡や立場に関係なく、冷静な人が客観的に見れば、極めてアンフェアなプロパガンダ映画なのが明白なのである。
■慰安婦の涙を政治利用
後半、荒唐無稽になってしまう『主戦場』だが、最後の最後にデザキ氏が登場させるのが、生前の金学順さんだ。幼い頃、初めて客を取らされた時の驚きと恐怖と苦痛を思い出して涙する金さんの姿を見て、「日本人は反省しろ」というわけだ。
私は、このような手法は苦難の人生を生きた女性への冒瀆であり、偽善の極みだと思っている。
金学順さんは基本的に正直な方だと思う。だから、これまでにも最初から包み隠さず、自分が幼くして親にキーセンに売られたことも、キーセンのオーナーに中国へ連れて行かれたことも率直に話している。長いこと日本でも、貧困から娘を遊郭に売る悲劇があったし、さらに貧しかった朝鮮半島ではなおさらだった。
幼くして親から離された少女たちはどんなに不安だっただろうか。また、芸人として生きていくと思って修行していたら売春をさせられてしまった彼女たちは、どれほど傷ついただろうか。金学順さんの悲しみを他人が推し量ることは難しい。しかし、彼女の涙は本当の心の叫びだと思う。
だからこそ許せないのが、金さんのような人を利用しようとする人々だ。朝日新聞の植村隆記者は金学順さんについて初めて報道したが、彼女がキーセンに売られた事実を書かなかった。植村氏の韓国人義母が会長だった太平洋戦争犠牲者遺族会は「日本政府を訴えれば賠償金を取れますよ!」と嘯いてお金を集め、本人を含めて詐欺罪で逮捕者を出し、有罪判決を受けた者もいる。
当時、慰安婦問題が国際問題にまで発展したのは、単純に慰安婦が存在したからではなく、日本軍が組織的に人間狩りのように女性を駆り集めて慰安婦にしたとか、勤労奉仕の女子挺身隊として集められたのに慰安婦にされたとか、朝日新聞が流布した虚報を日韓の国民が信じて衝撃を受けたからだ。
西岡力氏は、金学順さんがキーセンに売られた女性で、軍隊に拉致されたわけではないことを『文藝春秋』誌上で指摘した。 これを受けて、吉田清治の慰安婦奴隷狩り証言の検証をすべく済州島に向かう準備をしていた秦郁彦氏が、金学順さんの弁護士である高木健一氏に電話をして「金さんは親にキーセンとして売られた人ではないのか?」と訊いた。
高木弁護士は「あれは玉が悪かった」と言い、「いま、次のいいのを準備している」と答えたという。彼らにとって元慰安婦は、反日活動と金もうけのツールでしかないのだ。
西岡氏はソウルで金学順さんに会おうとするが果たせず、代わりに日本語通訳を務めていた韓国人女性に会って話を聞く。 彼女によれば、彼女が「おばあちゃん、なんで出てきたの?」と訊いたら、金学順さんはこう言ったという。
「寂しかったんや。親戚も誰も訪ねてこない。食堂でテレビを見ていたら、徴用された人が裁判を起こしたと報じられていたから、私も入るのかなと思った」
■壮絶な人生を歩んだ女性
日本人として初の従軍慰安婦被害者として祭り上げられたのが、城田すず子さん(仮名)だ。城田さんは下町でパン屋を営む裕福な家庭で育つが、切り盛りしていた母親が急死すると家は急速に困窮化し、神楽坂の芸者置屋に奉公に出される。最初は雑用をしていたが、やがて座敷に上げられるようになる。
彼女はあとで、父親が置屋から多額の借金をしていたことを知る。近所の学生との初恋もつかの間、遊び人の男に水揚げされて、いきなり淋病をうつされる。その後は台湾、サイパン、トラック島、パラオと転々とするが、南洋諸島には自分の意思で行き、内地とはうって変わった伸び伸びとした生活を送る。
米軍の攻撃が迫ると内地に返されるが、恋人に会いたくて無理やり舞い戻り、激しい空襲を体験する。 日本軍人との恋、米軍兵士との恋と彼の帰任に伴う自殺未遂、学徒動員から帰国した男性との駆け落ちと流浪の果ての心中。自分だけ蘇生して知る恋人の死。
途中、何度も彼女を救い出そうとする人も現れるが、恋は成就せず、覚醒剤、賭博、たばこ、飲酒に溺れて立ち直ることができない。最後の最後に、奇跡的に知り合った赤の他人に助けられてキリスト教団体が運営する支援施設に転がり込み、やっと更生するが、作業中に腰骨を折って寝たきりとなった末に他界する。
私は、彼女の自伝である『マリヤの讃歌』(日本基督教団出版局、1971年初版)を読んで何度も目頭が熱くなった。裕福な家庭に育ったおきゃんな少女が、母親の死を境になんと壮絶な人生を生きなくてはならなかったことか。彼女は自分の境遇を嘆きながらも、「貧乏が悪い」と人を責めず、苦労する兄妹のために借金を繰り返す。
しかしひとこと、「父親はなんと無慈悲な人だろう」と本音を漏らすシーンが胸を打つ。もし、彼女の父親に命がけで娘を守る気概があったら、きっと彼女はここまで悲惨な人生を生きなくても済んだだろうに、と思わずにはいられない。
■碑文にある虚偽の一文
だが、自伝を読んではっきり言えることは、彼女は人生のかなりの部分を売春婦として生きたとはいえ、従軍慰安婦ではなかったということだ。軍隊によって強制連行されたわけでもない。日本軍人も米軍兵士も相手にしたし、恋愛関係に陥ったりもした。
せっかく借金を返してまとまったお金を得ても、贅沢三昧で散財したりもした。親切にしてくれる人もいたが、守ってくれる親や親戚がいなかったばかりに、社会の底辺をひとりで彷徨わなければならなかったのだ。
まだ貧しかった日本が大戦争を経て焼け野原に帰した時代、彼女のような人生を歩まざるをえなかった人も少なくなかった。心から哀悼の意を捧げたい。
彼女の写真が、北米で初めて慰安婦像が建てられたカリフォルニア州グレンデール市の図書館に掲げられた。2013年、韓国人反日活動家たちが開催した慰安婦関連パネル展に、唯一の日本人女性として登場したのが城田さんだったのだ。
彼女の写真の下には「I was their slave. 私は彼らの奴隷だった」と書かれ、英文の説明が続く。
〈1938年、城田すず子さんは17歳の時、父親の借金返済のため日本軍に身売りされた。戦争が終わるまで城田さんは台湾やサイパンの慰安所で働き、日本軍の性奴隷となった〉
完全な虚偽である。 そして、慰安婦像の脇にはめ込まれている碑文には次のように書いてある。
〈1932年から1945年まで、日本帝国軍によって、朝鮮、中国、台湾、日本、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、東ティモール、インドネシアで家から連れ出され、性奴隷にされた20万人以上のアジア人とオランダ人女性に捧げる〉
これもまた虚偽である。前述の弁護士といい、韓国人活動家といい、女性の人権を云々しながら、女性たちを政治的ツールに利用しようとする人々を私は心から軽蔑する。
このような碑文とともに像が建ち、故人を虚偽の経歴で利用されたら、当然コミュニティに悪影響を及ぼし、侮辱されたり嫌がらせをされる日系人も出てくる。日本のブランド力低下にもがる。
韓国人の反日メンタリティは中国共産党の「超限戦」にとことん利用される。豪州ストラスフィールド市のケースでも、突然、中華系の「日本の戦争犯罪を糾弾する会」が結成されて、韓国人会に慰安婦像設置をけしかけたのだ。日本政府が謝罪したり補償したりすればするほど、「弱さ」と捉えられて激しく攻撃される。
■問題が解決されない構図
そのような事態になってしまったから、���者ではない者まで反論せざるを得ない状況に追い込まれてしまったのが現状なのだ。だから、『主戦場』に登場した保守派の人々は総じて、前述した反日団体のプロパガンダに反対意見を述べているのだ。
たとえ左派でもまともな学者なら、反日団体の主張は学術的にも虚偽が多いことはわかるはずだ。デザキ氏でもある程度は気付くだろう。しかし、「反日団体の主張は学術的に正しくないし、強引に無関係な土地に慰安婦像を建てる行為は非生産的だからやめるべきだ。慰安婦をめぐる議論は自分たち学者に任せるべきだ」と主張する左派の学者を私は見たことがない。
それどころか、「性奴隷」や「強制連行」の定義を拡大して、反日団体や活動家を後押ししているようにさえ見える。それは偽善的で、問題の解決を遠ざけるだけの行為だ。だから、いつまでたっても議論がみ合わないのだ。
ちなみに、『主戦場』の慰安婦性奴隷派のメイン話者の吉見義明氏は著書にこう書いている。
〈「官憲による奴隷狩りのような連行」が朝鮮・台湾であったことは、確認されていない。また、女子挺身勤労令による慰安婦の動員はなかったと思われる。(中略)しかし、「官憲による奴隷狩りのような連行」が占領地である中国や東南アジア・太平洋地域の占領地であったことは、はっきりしている〉(『「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実』大月書店)
つまり、法律が存在し、統制が取れていた朝鮮半島や台湾では権力による強制連行は行われなかったが、それ以外の前線では統制が崩れて犯罪行為も散見され、記録にも残っている、というわけだ。
しかし、前述の碑文を予備知識のない人が読めば、当然、「武装した日本軍が組織的に民家に押し入って、一般女性を拉致して性的目的で奴隷のように酷使した」と理解するだろう。これは吉見氏らの学説とも明らかに異なる。明らかな虚偽なのだから、反論せざるを得ない。
すると、デザキ氏のような活動家が現れて「歴史修正主義者」 「否定論者」と侮蔑的な表現でレッテル貼りを行う。それを吉見氏や林博史氏らが後押しするという構図になっている。
吉見氏も林氏も、慰安婦制度とは日本軍が単独で創り上げていたわけではなく、女性の人権を完全に無視する朝鮮半島の儒教的な封建制と徹底的な男尊女卑文化が背景にあったことを指摘している。
今日的価値観からすれば、日本軍や日本政府にも道義的責任があると主張するのは自由だが、現実には娘を売る朝鮮人の親がいて、女衒がいて、客としての朝鮮人もいたわけで、それが当時の朝鮮社会における現実の一部(fact of life)だったから、ただの一件も暴動が起きなかったし、日本軍に所属していた朝鮮人兵士も反乱を起こさなかった。
また、反日の李承晩政権でさえ、日本の責任を追及して賠償を求められるものとは考えなかったのである。それもまた現実なのだ。
にもかかわらず、ことさらに慰安婦制度は「日本軍性奴隷制度だった」と強調し、政治的目的を持って明らかに事実に反するプロパガンダを展開する反日団体を容認する姿勢は独善的で、学者としての誠意(integrity)を疑わざるを得ない。
吉見氏や林氏がその時代に生まれ、目の前に金さんや城田さんのような女性がいたとしたら救うことができたとでも言うのだろうか? 金さんや城田さんの境遇に胸を痛めるのであれば、困窮した元慰安婦がいたら労り、政治活動に巻き込むようなことをしてはいけない。
それどころか、現在も存在している女性の人権侵害問題に取り組むべきである。韓国で売春が違法とされたあと、大勢の韓国人女性が世界中に進出して売春をしている。悪質な業者に拘束されている女性も多い。
シドニー空港の税関で止められた若い韓国人女性はテレビカメラの前で、「私は韓国にいたら気が狂う」(Korea drives me crazy)と泣きながら訴えた。北朝鮮から命からがら中国へ脱出した朝鮮人女性は、文字どおりの性奴隷にされていると報告されている。
それらの、いまそこにある問題に取り組む��ともせず、慰安婦像を建てたり、偏向した映画を作ってあたかも女性の人権を擁護する善人のように振る舞う人々とそれを応援する人々は、極めて独善的で偽善的だと言わざるを得ない。
■今度は植村隆記者の映画
驚くべき情報が飛び込んできたので、最後に報告しておく。なんと、元RKB毎日放送社員で映画監督の西嶋真司氏が起案者となって、植村隆元朝日新聞記者を支援する映画の製作が企画されているというのだ。タイトルは『標的』。植村氏が不当な言論弾圧の標的にされているという主張を展開する映画だそうだ。
チェックしてみると、A-Port という朝日新聞社のクラウドファンディングサイトで資金集めをしていることが確認できた。反日急先鋒のテッサ・モーリス=スズキ(オーストラリア国立大学教授)も絡んでいることがわかる。
資金調達達成率は、残り約100日を残して56%とのことだが、すでに完成している部分があり、プロモーション動画の冒頭には「日本の正義が問われている」と書かれている。うんざりだが、裁判では飽き足らず、情報戦まで仕掛けてくる執念は見習うべきか。
貧しい時代の不条理を生き抜いた、同情すべき女性たちを政治ツールに利用する反日勢力からの攻撃は止むことがない。彼らは慰安婦問題を円満に解決したいとは考えていない。どんな手口を使ってでも日本を世界史上に例を見ない犯罪国に貶め、永遠に日本人と日本政府を糾弾し続けたいのだと見做されても仕方がない。デザキ氏と『主戦場』が、そのことを改めて教えてくれた。
彼らが「標的」にしているのは日本の名誉だ。
(初出・月刊『Hanada』2019年7月号)
0 notes
Text
2月11日(月) 次代舎「イノベーション史から学ぶ事業承継」(講師/出口治明氏)
2月11日(月)、次代舎最終回は、立命館アジア太平洋大学(APU)学長の出口治明氏による「イノベーション史」の講義と、参加者による事業企画のプレゼンテーションが行われました。

冒頭、吉川晃史先生から「今日は次代舎の10回目ということで、最終回になります。先週までの学びを経て、自分たちの新事業を考えるということで、苦労をされたと思います。今日は出口先生のご講演の後で5分ずつ発表をしていただきます。緊張されると思いますが、いつも通りリラックスしてやっていただきたい」と挨拶。
「本日は立命館アジア太平洋大学学長の出口治明先生にお越し頂きました。『イノベーション史から学ぶ事業承継』というところで、先生のご専門である歴史らかイノベーションの概念を学びつつ、事業承継についても教えていただきます。また本日はProject180の受講生も来られています。我々次代舎は座学によるインプットが中心でしたが、Project180のほうはそれを具体化していくということでやっています。Project180の受講生の方々にも学びの場としていただければと思います」

続いて出口氏の登壇です。
「今日は『イノベーション史から学ぶ事業承継』という難しいテーマで話をさせていただきます。まず自己紹介から始めます」とし、大学のプロモーションDVDを約3分間紹介。
続いて、この大学のプロモーションDVDをタイのAPU学生が自主的に作ったこと、大変良く出来ているのでほぼ無料でプロモーションビデオとして使っていること、その学生が去年の3月にAPUを卒業して仲間と別府で起業したことなどを話しました。「みなさん興味があれば、ご紹介しますのでメールをください」。

日本の人口問題と男女差別との関係
APUと九州が置かれている問題について出口氏は、「学生6000人のうち3000人が世界90の国や地域から来ている。設立時に大分県別府市から200億円頂いたが、1年の経済効果が200億円なので1年で元が取れる。日本人の学生は3分の1が九州、3分の2が東京や大阪から来ている。これは全国でも珍しいこと。今九州では福岡の一人勝ちで、若者を含め他の県はすべて人口を取られていると言われているがこれは間違い。過去3年間で増えた人口を分析したら、福岡は他の九州の県から全部若者を集めているが、東京や大阪は吸引力がもっと強いので、それ以上に福岡も取られている。過去3年間の人口の増加を牽引しているのが外国人。日本人だけ見たら福岡も純減している」
「東京の一極集中はけしからんという話になるが、人口が減ればどんな地域も国もコンパクトシティにならざるを得ないというのが世界の常識。アメリカもそう。そういうに考えたら、ごく当たり前。人口の問題もわかりやすくなる」としました。
「歴史を見れば、人口が減って栄えた国や地域は皆無。人口1億人をキープしたい、出生率1.8を確保したいという政府の中長期的な目標は間違っていないと思う。先進国特にG7の中で出生率が一番低いのは、男女差別が激しいのが全ての原因だと考えられる。育児や介護や家事がすべて女性の方にかかっていることが当たり前であるという風潮そのものが、この国の出生率を下げている根本的な原因だと思う。先進国と言いながら、女性の地位は149カ国中110位。これは男性も女性も、おかしいと怒るべき問題」とし、ヨーロッパのすべての国で取り入れているクオータ制の導入により男女の壁をなくすことが多文化共生社会の第一歩、ひいては日本の少子化を解決するスタートになると指摘しました。
30年間に新しい産業を生み出せなかった日本
ここで世界における日本の経済状況について、
「平成の30年間を振り返って見たら、数字から明らかなようにGDPの世界シェアは半減している。競争力は1番から25番に落ちている。もう一つ数字を言えば、平成元年の世界トップ企業20社の中に、トップのNTTを含む日本企業が14社入っていた。ジャパンアズナンバーワンの時代。現在はゼロ。トップのトヨタでさえ35位という。GDPのシェア、競争力、トップ企業。どのデータを見てもこの30年間、日本は停滞していると言わざるを得ない」と言及しました。
その原因について、
「GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)とその予備軍であるユニコーン(優秀なスタートアップ企業)です。日本では未だにものづくりこそ日本の価値があるという人がいる。僕自身、製造業は日本の宝だと思っているし、ものづくりに日本人が向いていることも事実。しかしGDPに占める製造業のウェイトはとっくの昔に1割を割り込んでいる。こういう状態で製造業が、500兆円を超える日本経済を牽引できると考える方がおかしい」
と産業構造の転換ができていないことを指摘しました。

「タテ・ヨコ・算数」で物事を見る
「GAFAは、ものすごく若い産業。Googleはわずか20年、Facebookはわずか14 年でトヨタの2倍のバリューを勝ち得ている。GAFAの予備軍であるユニコーンは、シリコーンバレーに150匹以上いると言われている。日経新聞によれば、中国に70匹、インドが17匹。ファイナンシャルタイムズによれば、EUには31匹。日本にはゼロです。1匹いるという人がいるが話にならない。こういうファクトをみれば、日本がこの30年間に新しい産業を生み出せなかったということに結論が出るのは容易な事」
「新しい産業を生み出している例として、大学をドロップアウトしたスティーブ・ジョブス。個性が際立った人。Googleの創設者はロシア人とアメリカ人のロッカー。日本がこれまで得意としてきた製造業で必要とされる人材は、素直で我慢強くて偏差値がそこそこ高くて、協調性があって先生や上司の言うことをよく聞く人。こういう人がいなければ社会が回らない。でも、素直で我慢強くて偏差値がそこそこ高くて協調性があって上司の言うことを聞く人が、新しいアイデアを産み出せるか?」とし、バーナード・ショーの言葉を例に、日本の教育が生み出した弊害を指摘しました。
「GAFAやユニコーンを産んでいるのは、「多国籍」「個性が際立ってとがっている」そして「超高学歴」。つまり変態。素直で我慢強く、偏差値が高くて、協調性があって、先生の言うことを聞く人を育ててきた日本の教育こそがこの国の低迷に結びついている」と明言。
「製造業の工業モデルで社会を引っ張ってきたキャッチアップの時はそれで良かったが、今はそうではない。考えなければならない」とし、
「高校は国立理科系、国立文科系、私立理科系、私立文科系の区別は辞めて、7割は偏差値クラスを作り、あとの3割は変態クラス=個性派クラスにしてはどうか。ゲームが好きな人は徹底的にゲームをすればいい、絵を描くのが好きな人は絵を描いていればいい。好きなことを極める学生を育てる。僕はAPUの学長になってから言い続けていることが一つある。偏差値が高い人は東大、変態や個性派はAPUが引き受ける。ミニ東大を作っても日本のためにならない。大学も富士山ばかりでなく、多様な峯を作っていかなければ日本の将来はないと思っている」
「この30年間の日本の低迷は、とがった個性を大事にしなかったこと、ワクワクするような場所を作れなかったことがすべて。悪循環している。世界中からおたくや変態が集まる国は成長している。自分の能力に自信があり、やりたいことがある人は、成長している国に集まる。これがアメリカの強さ。人間は顔が全部違うのと同じように、意見や考え方が違うのは当たり前。みんなで決めたことを守ろうっていう教育をやっていったら絶対ダメ。違って当たり前という教育を社会挙げてやっていかなければいけない。個性のとがった人を徹底的に大事する教育をして、ダイナミズムがなければ、日本は成長できない」
「世界中からダイバーシティあふれるとがった個性のある高度プロフェッショナルを集めて、ワクワクドキドキするような場を作っていかなければならない。そして新しいユニコーンを生み出して、成長していかなければこの国の成長はない。フランスのマクロンが言っているように、教育投資は徹底的に大事」とし、日本の租税負担率、保険料の負担率の低さに反する給付の高さを指摘。
「国の政策としては負担を上げて、プライマリーバランスを戻して、投資に振り向かなければ将来はない」。これが日本の置かれている状況だとしました。
「今日のテーマはイノベーションの歴史ですが、大切なのは、物事を色眼鏡で見るのではなく、『タテ(歴史)・ヨコ(世界の人がどう考えるか)・算数』の視点で見ること。日本はもともと夫婦別姓の国だが、OECD加盟国で夫婦別姓反対を強要している国は皆無。この30年間、日本の正社員の労働時間は2000時間以上で全く減少していないのに成長率は1%。イングランドは労働時間が1500時間を切っているが、2%以上成長している。日本のコンビニエンスストアのサービスは素晴らしいなどというエピソードで見れば日本人は優れているかもしれないが、エビデンスをどう説明するのか。過剰なサービスをやっているのに生産性の向上に結びつけることが出来ないから、みんなが一生懸命働ければ働くほどくたびれて、成果が見られない。エピソードで議論してはいけない」とエビデンスで議論して世界を見ること、「タテ・ヨコ・算数」が基本であるとしました。

人類の歴史とイノベーション
話題はいよいよ本題へ。
イノベーションの歴史について。
人類最初のイノベーションについて出口氏は、「人間の歴史は、約20万年。ホモサピエンスの最初のイノベーションはまず、言語の発明。脳が発達して、思考のツールとして言葉が発明されたという説の可能性が高い。7万年から10万年前。この言語の力によって同じ人類であるネアンデルタール人を全部滅ぼしてしまった」としました。
さらに第2のイノベーションについて
「1万2000年前に起こった定住。みんなが狭い所に集まっているとインフルエンザにかかってよく死んでしまう。だからキレイな所を順番に、移動している方が遙かに楽。ホモサピエンスが定住を始めた理由はよく分からないが、多分、脳が世界を追いかけていく生活ではなく、自分は動かず周囲を支配しようと考えた。植物の支配が農耕、動物の支配が牧畜、金属の支配が冶金、自然界の原理を支配しようと考えて神という概念を考えたと言われている」
「第3のイノベーションは、紀元前1200年。地球が寒くなり、海の民が大移動を始めてヒッタイトが滅びた。ヒッタイトは鉄を作る技術者を抱えていたが、滅んだので全世界に鉄器が拡散していった。日本では、北九州で最初に文明が起こるが、これは南朝鮮で鉄が産出したから。鉄を使えば、農耕もしやすくなる」
「何をバーターに鉄器をもらっていたのか。人間は生態系を超えて外来種を持ってくることで、文明を起こす。実は人間のキーは交易。交易を理解するキーワードは、決済です。良い物はただではくれない。日本の場合は人間で、傭兵や奴卑。卑弥呼が皇帝に若い男女10人を連れていって、なんにもさしあげるものはありませんが、この10人は元気で優秀ですから使ってくださいと差し出した記録が残っている。貿易の理解はもう一つは世界商品という概念。中国のお茶や絹。世界中の人が欲しがるモノが、世界商品。日本が平和だったのは、世界商品がなかったから。安土桃山時代に世界から来たのは、石見銀山があったから。当時の世界通貨の銀の3分の1は日本産。こういうふうに考えれば、世界の歴史の流れは分かりやすい」
「第4のイノベーションは、産業革命。産業革命によって人間の社会は大きく変わった。産業革命の3要素は、近代文明の3要素と言われている化石燃料と鉄鉱石とゴム。資源は偏在しているので、自由貿易が大事。この3資源がない国は、自由貿易をしない限り近代生活はできない。この大原則が分かっていれば、3資源のあるアメリカはアメリカファーストできるが、3資源のない日本は日本ファーストができないことが分かる。だから、近代文明の基本は産業革命にある」としました。
さらに、
「産業革命はもう一つ、教育の姿を大きく変えた。それまでの教育は、教育イコール人生、生活することだった。分かりやすく言えば、ギルド。料理人は親方について料理を教えてもらう。生活が教育であり、それが人生、いわゆるギルドの世界。しかし産業革命は大量に均質な工場労働者を必要とする。スクールの語源は、ギリシャ語で「暇、余暇」。生活から切り離して若者を一カ所に集めて、ある程度のことを教えなければ工場で使えない。だから学校という制度を産業革命は生み出した」
「もう一つのイノベーションは、フランス革命で生まれてナポレオンによって完成されたネーションステート(国民国家)。1848年、ネーションステート(国民国家)は完成しました。これが今の世界の枠組みを作っているイノベーションの根本です」
としました。
イノベーションとは何かについて、 「イノベーションの父と言われているシュンペーターによると、イノベーションのほとんどは知識、既存知を組み合わせることによって起こる」とし、
イノベーションの原則について、イノベーションを起こしたラーメンを例に挙げ「大切なのは、イノベーションの間の距離が近いものはたいしたものはできないということ。既存知の間の距離が遠いものを組み合わせれば、面白いイノベーションが生まれる。ごく少数の天才が考えるモノを除いては、イノベーションはどこにでもある知識の組み合わせ。遠ければ遠いほど新しいイノベーションが生まれてくる」としました。
「メシ・風呂・寝る」から「人・本・旅」の生活へ
ここで新しいアイデアを生み出すコツについて、
「政府は働き方の改革を言っています。長時間労働、「メシ・風呂・寝る」では、脳みそが疲れてしまってアイデアが出ないということが政府も分かったから。だからこの4月から、残業規制が始まる。しかし新しいアイデアを生み出すためには、インプットしなければいけない。早く帰って勉強するしかない。僕は分かりやすく、「メシ・風呂・寝る」から「人・本・旅」の生活に切り替えるようにと言っている。早く帰っていろんな人に会う、いろんな本を読む、いろんな面白い所に出かける。そうしなければ、アイデアは生まれない。新しいものを見れば、「なんや、これは!」ってビックリする。僕の脳が刺激を受けている。いろんな面白い場所に行くのが旅」
「政府が副業や兼業にも前向きなのは、新しいことを始めるためには勉強をしなければならないから。日本では未だに仕事の事を24時間考えている経営者がいる。部下にもせめて12〜3時間は仕事を考えてほしいと言っている。こういう経営者は、部下が6時に帰ってピアノを弾きたいって言ったら、きっと激怒するだろう。こういう経営者がいる限り、日本は浮上しない」とし、ゴールドマンサックスの新しい社長は、プロのDJをしているから、入社して以来一切残業をしていないということを紹介。
「頭を使う仕事は、24時間仕事のことを考えると煮詰まってしまってアイデアなんか出ない。大脳の研究者によると、1回の集中力は2時間が限界。人間の脳は疲れやすい。体重の2%未満なのに、20%以上のエネルギーを使う。1日、2時間を4コマくらいが限界。頭を使う仕事は長時間労働ができない。これからのイノベーションを考える時に、管理者やマネージメントが考えないといけないのは、脳の仕組みや人間の真実を良く勉強することに尽きる」。
Amazonなどのグローバル企業のオフィスが楽しげなのは、
「面白いオフィスにしたほうが、人間の脳みそは騙されて勝手にワクワクドキドキして一生懸命アイデアを出そうとする。だから、オフィスから考えていくことは極めて理にかなっている」としました。

事業承継に求められるもの
続いてテーマは事業承継の話へ。
「日本は、創業100年以上の企業が世界で一番多く、次がドイツ。このことは世界商品がなかったので誰も来なかったのがいちばんの原因」としました。
「長ければ良いのかっていうものではない。アメリカで100年間続いている企業はゼロ。何百年という企業が何百とあるけれど低成長の国か、あるいは100年企業はないけれど成長し続ける国か。どちらがいいかは、エビデンスで考えなければならない」
「一番優れた事業は、新しい国を作ること。これ以上のベンチャーはない。日本の天皇制が長く続いているのは、天皇が政治をやらなかったから。実際権力を持っている人が、実力のある人間を抜擢して事業を承継させる」と話し、外国人が社長となり国宝の修理をしている会社の例を紹介しました。
「能力のある人がやったほうが、どんな事業でもうまくいく。極端に言えば、公募でもなんでもいいから、能力をある人を探してきて事業承継をやる方がひとつ。もう一つは、組織をちゃんと作ること。組織は理念。この企業は何をやっているという理念や夢があると、人が集まってきて、その事業はうまくいき、継承される。事業を長続きさせようと思ったら、能力のある人を上手に作っていくシステムを作っていくことがいちばん。その後は、その組織の理念やビジョンを上手に社会に合わせていくこと。社会の変化に合わせて、会社の仕組みを変えていくこと」とし、チベットのダライラマを例に、事業の承継において優秀な人材を見つけることの重要性を強調しました。
ここで講義は終了。
「あとの30分は質疑応答で、議論を深めていきたい。何でも聞いてください」と出口氏。
「もともと貴族社会で男女平等の文化を持っていなかったヨーロッパがどうやって男女の平等性を培って来たのか? 日本との違いも含めて教えてほしい」という質問に対し出口氏は、
「どの国も製造業からサービス業に変わっていきますが、製造業のユーザーは男性。僕は70年にサラリーマンになったが、先輩から、頑張って働いて、車がなかったらデートをしてくれない、カラーテレビとクーラーがなかったら遊びにきてくれないと言われました。それで一生懸命に働いて、車とカラーテレビとクーラーを買った。3Cの時代。ここまではユーザーが男だったが、サービス産業になると全世界どんな統計をとっても、ユーザーは女性。消費を牽引している女性の欲しいモノが、日本経済を牽引していると自負しているおじさんに理解できるか? サービス産業になれば、供給サイドに女性がいない限り経済は発達しない。だからヨーロッパは、女性もがんばってもらう以外にないということで始めました。日本人は資質が無いわけではありませんが、勉強できる雰囲気になっていない。大学進学率が低く、ピークで52%。OECDの平均は6割以上。日本は大学に行かない、大学で勉強しない。これは学生が悪いのではなく、採用基準に成績を入れない企業のせいだと考えます。大学院生で勉強した人は使いにくいと言って採用しない。社会に出たら2000時間労働して『メシ・風呂・寝る』で勉強する時間がない。日本の社会は、構造的に低学歴になっていて不勉強ということがヨーロッパとの違い。知識は力。ヨーロッパが必死にクオータ制をやって女性の地位の引き上げをやっているのは、早く少子高齢化が起こって低成長になったからです」
「現状に対する数字のロジックに対する明確な認識がなければ、腹落ちしなければ、社会は変わらない。大企業から率先してクオータ制を大企業から入れるべき」と答えました。
「中小企業で取り入れる際のポイントは」という質問については、
「Googleは、先入観が入ると、人事部のデータから本籍、性別、年齢、顔写真も外しています。キャリアと夢さえ分かればそれで十分。大企業、中小企業というくくりは関係ありません」としました。
「ユニコーンで働く人はめちゃめちゃ働いている気がする」という問いに対しては
「めちゃくちゃ仕事をしている人もいるが、1年を通じて見ると労働時間は少ない。頭をフルに使ったら、それ以上働かないんです」。
「事業承継について、教育すれば立派な経営者になるという帝王学の考え方もある」という質問には
「人は教育をしたら育つという考え方が根本から間違い。人には適・不適があります。世界のマーケットは広い。リーダーにふさわしい人を探してきて、教育する考えがふさわしいのではないでしょうか」。
「リベラルアーツに関する見解を教えてもらいたい」という質問に対しては、
「タテ・ヨコ・算数で勉強することに尽きます。大事なことは、自分の頭で考えること。おいしい教養豊かな人生と、貧しい教養のない生活と、どちらを送りたいか。いろいろな材料を集めるのが知識。「メシ・風呂・寝る」では知識が得られない。今まではみんなと同じことをやっていれば良かった。考える子どもたちを作るには、大人たちが、子どもがどんな屁理屈を言っても説明で��なければいけない。知識×考える力が教養」だとしました。
イノベーションは、既存値の距離が遠いほど、新しいアイデアが生まれます。好きなことを徹底してやることがイノベーション。「人・本・旅」でおたく変態になることからイノベーションが生まれる」これがダイバーシティの基本だとしました。
「離れすぎたものをつなげるコツは?」「まだ常識の枠にとらわれる人が変態になるには?」という問いに対しては、
「ひたすら好きなことをやることです。何かのためにする勉強はためにならない。好きなことを徹底的にやることが、ある日、イノベーションにつながります。好きなものを見つけるまでもがくこと」とし、拍手で質疑応答を終了しました。

最終事業発表プレゼンテーション
出口氏の講義後、休憩を挟んで、最終事業発表プレゼンテーションタイム。
「会社の内容と今の会社課題、それに対するアイデアについて発表してもらいます」と吉川先生。各受講生が、自身で温めてきたアイデアを具体化した計画を発表しました。

すべてのプレゼンが終えたところで出口氏は、エレベーターピッチという考え方について紹介。
「①会社ではエレベーターに乗っている短い間に、上司に応援してもらえるような魅力的なプレゼンをすること ②自分の会社を紹介する場合、グローバルでは数字で ③ビジネスモデルキャンバスも数字で。新しい会社の課題をトップライン、ボトムラインの動きの変遷を数字で見ること。それに対し、自分のアイデアがどれくらいのポーションで貢献できるかを考えることが大切」とアドバイスし、数字で提示することの大切さを強調しました。
全課程を修了したところで、
蒲島知事に代わって、熊本県商工観光労働部産業支援課坂口審議員から修了書の授与。
代表して前原さんが、受け取りました。

記念写真の撮影

続いて行われた懇親会で参加されたみなさんによる
主なコメントは次の通りです。
「発表は緊張したが、次代舎の10回の講義で、これからの会社への貢献へのスタートラインに立つことができた」
「ここに来なければ考えなかった思考法を得ることができた。新しいもののひらめきのためにはインプットが大事だと知った」
「最初は、やったことのないプログラムに躊躇したが、やっていくと面白くて、ムダがない進め方だと思った。シリーズならではの良さがあった」
「参加する度に考えさせられる内容で、プレゼン含め勉強になった。これから会社で活かしていきたい」
「楽しかった。新しいことを考える部署にいて、いろいろな視点や切り口、検証の仕方など面白かった。イノベーショノートと資料を見返しながら、今後に活かしたい」
「イノベーションというと新しいことを思いつくことかなと思っていたが、そうではなくて、ビジネスと一体になって考えることがイノベーションということが分かった。今後はもっと数字にこだわっていきたい」
熊本イノベーションスクール「次代舎」全10回、半年間の全カリキュラムが修了。
参加者の表情には、やっと終わったという安堵感と、ここからがスタートという新たな緊張感のようなものが感じられました。
そう遠くない将来、この中から熊本に新しいイノベーションが誕生するかもしれません!!
みなさん、お疲れ様でした。
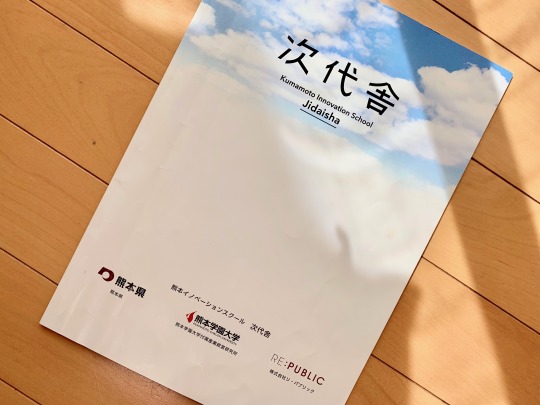
0 notes
Photo

台湾「蔡英文」が最も恐れる男 「国民党の反日的言動は支持しない!」–野嶋剛 台湾で昨2018年11月に行われた統一地方選は、蔡英文総統率いる与党「民進党」の惨敗で終わった。 その激変を演出したのは、圧倒的不利と見られた台湾南部最大の都市・高雄市の市長選で「韓流」と呼ばれるほどの現象を巻き起こして勝利した国民党の韓国瑜氏(61)だ(2018年11月25日「速報! 台湾統一地方選:与党『民進党』打ち砕いた『韓流』ポピュリズムの破壊力」参照)。 2020年の総統選にも影響を及ぼすとも見られる人気者だけに、12月25日の着任後もその一挙手一投足が注目を集めている。このほど、ジャーナリストの野嶋剛氏と「フォーサイト」に対して、日本のメディアで初めてとなる単独インタビューに応じた。 「韓流」は合理的な現象 野嶋剛 韓市長は元立法委員ではありますが、国民党や政府で重要ポストを経験したわけでもなく、全国的な知名度も低く、高雄とも縁が薄かった。立候補したとき、当選できると思っていましたか? 韓国瑜 五分五分ですね。投票の日まで、五分五分という思いでした。 野嶋 高雄では伝統的に国民党は弱い。誰も候補者のなり手がいないなか、最初は当選不可能な泡沫候補扱いでしたね。 韓 犠牲バントみたいなね(笑)。でも私はそう思わなかった。高雄を歩きながら私の考えを伝えていくと、人々の受け止め方が次第に変わっていったのです。常に選挙費用は不足し、大変な選挙戦でしたが、私に恐れるものは何もなかった。 野嶋 高雄市民が熱狂的にあなたを支持する様子はあなたの名字を取って「韓流」と呼ばれ、台湾全体の選挙情勢すら変えました。なぜ「韓流」を起こせたのですか。 韓 日本に小泉純一郎という首相がいましたね、真っ白い髪の毛をした人。彼も、人々を大きく感動させ、動かしました。政治学でカリスマ、という存在です。私がこの選挙でカリスマ化したとすれば、私の力ではなく、台湾の人々が現状に「もう勘弁してくれ」と感じていたのです。台湾は何十年も(統一か独立かの)イデオロギー対立に巻き込まれ、経済は低迷する一方だったからです。 野嶋 だから韓市長は選挙で「政治はゼロ、経済が100」と主張したのですね。 韓 私は選挙のスローガンに生活の改善を掲げました。一方、私の対立候補である陳其邁氏はイデオロギーの路線を選び、「民進党は台湾民主の聖地・高雄で負けられない」と昔ながらの主張を繰り返しました。陳氏は台湾の民衆の思いを理解できていなかったのです。 野嶋 先ほどのカリスマという指摘ですが、あなたの当選はポピュリズム政治の出現という要素もあったのではないかと感じます。 韓 私は「高雄はどんどん老いて貧しくなっている」と主張しました。市民は最初は怒り、拒絶し、反論しました。メンツがあるからです。ですが、いつしかこの点をめぐって論議が始まり、私の主張が広がり、みんな沈黙して思考し、「なるほど、そうかもしれない」と考えてくれたのです。それが投票結果につながりました。 野嶋 あなたの当選は、ポピュリズムではなく、奇跡でもなく、合理的なものだったと? 韓 そうです。合理的な理由があったのです。 野嶋 もし当選していなかったら、今頃、何をしていましたか。 韓 北海道でのんびり旅行していたかも(笑)。そのあとは帰国して、農家をやっていたでしょう。私はなんといっても「賣菜郎(八百屋のおやじ)」ですから(筆者注:韓市長は出馬前は台北で農産物販売輸送関係団体のトップを務めており、選挙中は自らを賣菜郎と呼んで庶民性をアピールしていた)。 台湾が大切にすべき「日米中」3つの文化 野嶋 日本に行ったことはあるのですか。 韓 実は私は1985年に中華民国政府が日本に派遣した大学生10人の1人なのです。数千人の大学生の希望者から選抜されました。当時は1ドルが260円でした。(同年のプラザ合意で)1年後には150円台の円高になって日本は大騒ぎになった頃ですね。 野嶋 お父さんは日本と戦争を戦った軍人で、あなたも眷村(大陸から渡ってきた外省人の軍人らの居住区)で育った人間です。日本を憎む気持ちはないのですか? 韓 子供時代はありましたね。しかし大人になって日本文化と日本人に触れて、そうした伝統的な対日観と、実際の日本の姿は一致していなかった。1985年の訪日では日本での飛行機の離着陸で日本アジア航空(後に日本航空に吸収)の職員が滑走路で深々とお辞儀をしてくれました。農村に行くとみんな挨拶して頭を下げてくれる。衝撃でしたね。お菓子も羊羹もきちんと綺麗に包装されている。都市も農村もどのトイレも清潔でゴミ1つ道路に落ちていない。子供の頃に受けた教育と全く違いました。たった14日の日本旅行でしたが、それから徐々に日本の人々と接触するようになり、考えも変わりました。私の妻は小学校を経営していますが(筆者注:雲林県の私立ヴィクトリアアカデミー)、台湾で唯一、日本語を教える小学校なのですよ! 台湾の日本関係の人材には断絶があります。私は、次世代には中国語と英語に加えて、日本語の能力を身につけることを期待しています。 野嶋 あなた個人は別かもしれませんが、(慰安婦像の設置や福島県などの食品の輸入規制問題などで)国民党の最近の動きは反日的だと日本人が受け止めても仕方がない面があり、日本では国民党の復活を心配する声があります。 韓 (コップを持って)これが台湾です。中には3つの文化が入っています。米国文化、中華文化、日本文化です。この3つの文化がすべてこの島にあり、台湾はこの3つの文化と経済力を吸収して健康に強く育った「子供」なのです。米中日の世界3大経済体が台湾内部で衝突すれば台湾は衰え、弱体化します。台湾の指導者、政治家はこの点を理解すべきです。 野嶋 他文化に対する包容力が必要ということですか。 韓 まさにその通りです、野嶋さん。包容力、融合、受容、そして喜び。その方向に向かわないと、台湾はパワーを失ってしまう。あってはならないことです。いまの台湾では衝突が起きてしまっている。これは聡明なやり方ではありません。 野嶋 では、党内の反日的な言動は支持しませんか? 韓 党内の反日は受け入れません。日本の皆さんの、高雄への投資や観光を大歓迎します。高雄には壁はなく、世界と友人になります。反米、反華(中国)も受け入れません。台湾は美しい女性で、3人の男性(米中日)に追いかけられるようでなければならない。我々は3人の男性と一緒に映画をみてコーヒーを飲み、しかし「結婚」はしてはいけない。結婚するとあとが大変だからです(笑)。 野嶋 高雄はずっと台湾ナンバー2の都市でした。しかし、最近は台南や台中に関心が集まり、日本人観光客からも敬遠され、高雄の重要性や魅力が低落しているように見えます。 韓 日本人だけではなく、若者も高雄から離れています。仕事がない。お金が稼げない。生活がよくならない。空気汚染がひどい。都市全体が没落しています。高雄人が暮らしたくないのにどうして外部の人が来てくれますか? 野嶋 高雄の没落が観光客にも影響している、ということですね。 韓 日本、韓国、香港、中国大陸、誰も来てくれない。だから医療ツーリズムやキャンプ、高齢者滞在、映画産業などを発展させたい。人々が台南に行くのは正常です。古都で楽しく食事も美味しい。台中、桃園に行くのも当然で、そして高雄に来ないのも当然なのです。高雄には特色がないのです。例えば、高雄には(日本統治時代に日本軍が掘った)洞窟がたくさんあり、観光地として整備してくれと指示しました。旧日本軍の山下奉文という人もいますね。マレーの虎と言われた人です。彼の財宝がどこかに隠されているという噂があります。もしかすると高雄の洞窟から出てくるかもしれません(笑)。高雄に観光資源がないわけではないのです。うまく活用するために頭脳を使っていないだけです。 総統の椅子に興味はない 野嶋 日本の安倍晋三首相への評価はいかがですか。 韓 米国のドナルド・トランプ大統領も、大陸の習近平総書記も強烈なナショナリストです。安倍首相も同様です。この3人のナショナリズム意識はとても強いと感じます。ですから、いま台湾は非常に注意深く行動しないといけません。このタイミングでもし台湾がナショナリズムを高めたら大変なことになります。安倍首相の故郷である山口県の出身者からは、ナショリストが多く輩出しています。安倍首相には「日本・ファースト」の気持ちがあり、それはトランプ大統領の「アメリカ・ファースト」にも通じます。ただ、安倍首相は米国と中国との関係についてはとても慎重に対処していますね。 野嶋 韓市長は、同じ人気者である台北の柯文哲市長(無所属)と関係が良好だと聞いています。彼のことをどう見ていますか。 韓 彼は5歳から50歳まで優等生クラスでしたが、私は5歳から50歳まで劣等クラス生でした(笑)。だから個性は全然違います。当然、友人ではあります。(農業関係を通して)台北で一緒に仕事をしていましたから。 野嶋 将来、彼と組んで総統選挙を戦う可能性はありますか。 韓 彼と一緒に日本に遊びに行くことはあっても、総統選挙には一緒に出ませんよ。 野嶋 では、あなた自身は総統の椅子に興味がありますか。 韓 ありません。いまは高雄の経済と教育を急いで改善する。これが最重要です。 野嶋 くどいようですが、2020年の総統選に出るという選択肢はない? 韓 興味はありません。高雄のことに専念するのは最重要です。 野嶋 国民党の総統候補では、高雄市長選であなたを大いに助けた王金平元立法院長はいかがでしょう? ほかにも、朱立倫・元国民党主席、呉敦義・現国民党主席、馬英九元総統などが野心を示しています。 韓 いま国民党はこの4人で麻雀をしています。誰が上がるのか私はわからない。タッチしません。誰が上がるか決まったら、彼(総統候補)と協力するだけです。 野嶋 あなたがそう思っても、韓流人気に頼りたい人たちが放っておきませんよ。 韓 妻でさえ私を頼りにしていないのに、彼らが私を頼りにする?(笑) 麻雀は4人で打つものです。彼らが麻雀を打っている間、私は高雄経済の発展に専念します。 野嶋 いまの国民党に欠けているものはなんでしょうか。 韓 民意に近づくことです。庶民の声に耳を傾ける。この4人は政治の世界に数十年ずっといます。人民から遠く離れていないでしょうか。私の心配はそこです。蔡英文総統も同じで、民衆と離れてしまい、たった2年間で有権者を失望させました。私は高雄市長選まで政治から17年間離れていました。だからわかるのです。もしずっと政治家であったら、傲慢で冷淡な人間になって民衆から離れてしまっていたでしょう。政治家はセブンイレブンに買い物に行かず、ショッピングモールにも市場にも行かない。秘書が全部やってくれるからです。国民党の総統候補には、ぜひ民衆の声にしっかりと耳を傾けてほしいと思います。 野嶋 2016年の総統・立法委員選挙で国民党が大敗を喫したのも、馬英九総統(当時)がそうだったからですか。 韓 それだけではなく、(馬氏は)政治において気迫不足で、実行力もなかった。台湾をより強く、より豊かにすることができなかった。 野嶋 国民党が長い間、あなたを評価せず、重用しなかったという思いは? 韓 私も相当悪ガキでした。毎日怒り散らし、毎日うろつきまわって、怒りっぽく、上層部を困らせまくった。(民間にいた)17年間で多少はいい子になりました。 野嶋 あなたには少々ヤクザっぽいところがある。認めますか? 韓 ははは、少しだけ、少しだけです。私の気質は庶民的で、誰とでも仲良くなれます。あなたが来る前にこの部屋にいた人たちは仏教徒です。昨日は米国人が5人訪れました。ヤクザも素人もどんな人も歓迎し、心を開いています。 最良、唯一の選択肢は 野嶋 最後に、センシティブな中国問題です。「92年コンセンサス」は「一中各表(1つの中国、解釈は中台それぞれ異なる)」だとあなたは思いますか。中国は「一中」は言いますが、「各表」は言いませんね。 韓 対岸がどうであれ、我々は(台湾側の考える「92年コンセンサス」を)堅持すればいいのです。 野嶋 では、中国も、台湾側のそうした姿勢(「各表」)をある程度、受け入れると? 韓 対岸も否定、反対はしないと思います。対岸にとって重要なのは「1つの中国」。そのあとの部分はまた別の話です。同時に、大多数の台湾人も「92年コンセンサス」には反対しません。つまり台湾人と対岸はともに「92年コンセンサス」を受け入れられる。台湾は、この仕組みのなかで、現在のライフスタイルを維持していくことができます。 野嶋 「92年コンセンサス」は、台湾が中華民国であるという前提です。台湾が「中華民国」体制を維持すれば中国ともうまくいく、という考え方ですね。 韓 大多数の台湾の民衆は、中華民国を受け入れています。蔡英文総統は、中華民国は好きではない、「92年コンセンサス」も受け入れないと言う。ならば独立しかない。でも独立はしない。では一体、台湾人民をどこに導いていくのでしょうね。台湾は五輪には中華台北(チャイニーズ・タイペイ)名義で参加する。中華台北は国名ですか? 違います。でもそれを受け入れている。一種の方便だから��す。「92年コンセンサス」もそのようなものです。 野嶋 では最近の習近平氏の演説で強調された「一国二制度」はどうでしょうか。 韓 「一国二制度」は、台湾の絶対的多数が受け入れません。香港、マカオを見ればわかるでしょう? 「92年コンセンサス」のもとで中台関係を発展させる、それが現時点での最良であり、唯一の選択肢です。 野嶋 中国を訪問する予定はありますか? 韓 現時点では決まっていません。決まっているのは、2月と3月にシンガポールとマレーシアを訪問して、高雄のフルーツをセールスしてくることです。基本は「南南協力」です。1つは東南アジア、1つは中国南部。中国北部には行きません。北部は政治的に敏感ですが、南部は経済の要素が大きいからです。 野嶋剛 1968年生れ。ジャーナリスト。上智大学新聞学科卒。大学在学中に香港中文大学に留学。92年朝日新聞社入社後、佐賀支局、中国・アモイ大学留学、西部社会部を経て、シンガポール支局長や台北支局長として中国や台湾、アジア関連の報道に携わる。2016年4月からフリーに。著書に「イラク戦争従軍記」(朝日新聞社)、「ふたつの故宮博物院」(新潮選書)、「謎の名画・清明上河図」(勉誠出版)、「銀輪の巨人ジャイアント」(東洋経済新報社)、「ラスト・バタリオン 蒋介石と日本軍人たち」(講談社)、「認識・TAIWAN・電影 映画で知る台湾」(明石書店)、「台湾とは何か」(ちくま新書)。訳書に「チャイニーズ・ライフ」(明石書店)。最新刊は「タイワニーズ 故郷喪失者の物語」(小学館)。公式HPは 関連記事 中国人の「行動原理」と「思考法」を掘り起こす 歌舞伎町伝説の「元中国人」密着選挙映画が見せる日本人の「排外性」 速報! 台湾統一地方選:与党「民進党」打ち砕いた「韓流」ポピュリズムの破壊力 「蔡英文総統」崖っぷちの「台湾統一地方選」直前情勢 台湾「脱線事故」根源にある「人的要素」と「構造的問題」 (2019年1月15日フォーサイトより転載) Source: ハフィントンポスト
0 notes