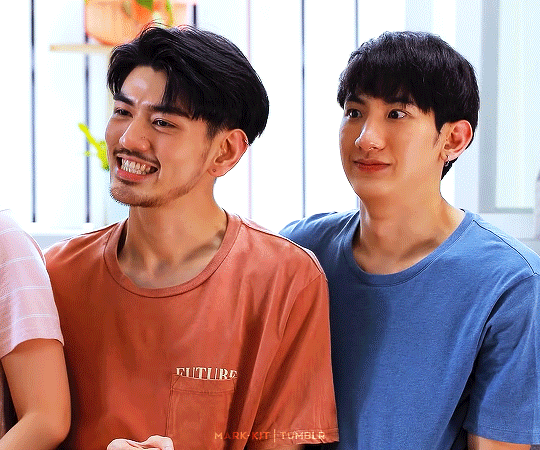Text
Hello dazzling world
cr:toptap_jirakit ig, mmikesiri ig





#2gether#they two are the best couple ever#i wanna do hug everyone loves this couple#mantype#mike chinnarat#toptap jirakit#man×type#miketoptap#aini#ainhai#tonhon chonlatee
97 notes
·
View notes
Text
Hi guys!
I wanna ask you something about MikeToptap.
Why they do not any communication in their SNS anymore like before?
There are often something complicated, especially at show business.
But I can’t stop thinking THIS SITUATION IS TOO WEIRD. And Why.
I just want to know what do you think about that. Pls tell me.
cr: toptap_jirakit ig

#toptap jirakit#mike chinnarat#😭😭😭😭😭😭#i just wanna see they do cute teasing each other again#mantype#miketoptap#2gether the series#2gether#thonhon chonlathee#ainhai#aini#mama gogo
19 notes
·
View notes
Video
chrisevans: When I opened my eyes this morning, he was wide awake just staring at me. If a person did this it would be unsettling. When a dog does it, it’s hilarious.
4K notes
·
View notes
Text
I understand many people want to recognize couple of boys as husband/wife and it’s a kinda natural thing for “BL series”. But I want to see TWO PEOPLE just love each other. In this series, MikeToptap a.k.a. ต้นหอมผักชี shows us that by the switching positions. It deserves to praise.
Thank you Mike and Toptap. And thank you GMMTV for using this guys as such a precious role. It’s new and valuable. It also has the worth enough to challenge. I’ll support them and MikeToptap much more even if some people criticize them.
Thank you for challenging and respecting about love.

#mike chinnarat#toptap jirakit#miketoptap#i’m so proud of you#gmmtv#gmmtv actors#thonhon chonlathee#ainhai#i want to see their own series as main roll sincerely#ต้นหอมผักชี#ต้นหนชลธี#2getheredit#2gether the series#mantype
51 notes
·
View notes
Photo
I have no words to explain how much I love this couple...😭😭😭😭😭❤️❤️
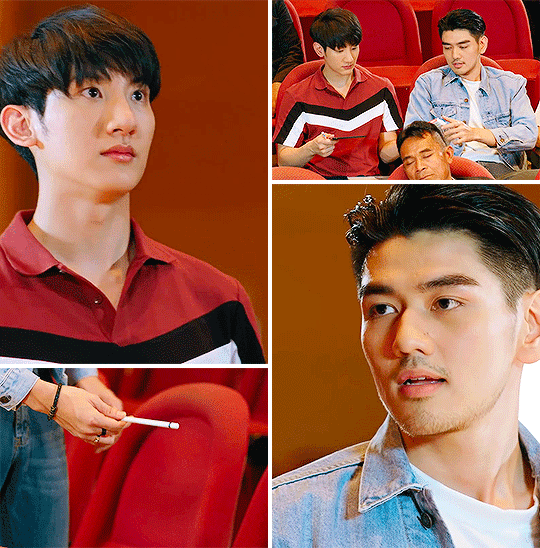
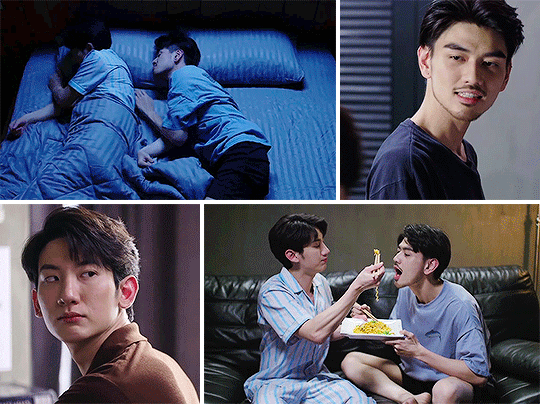
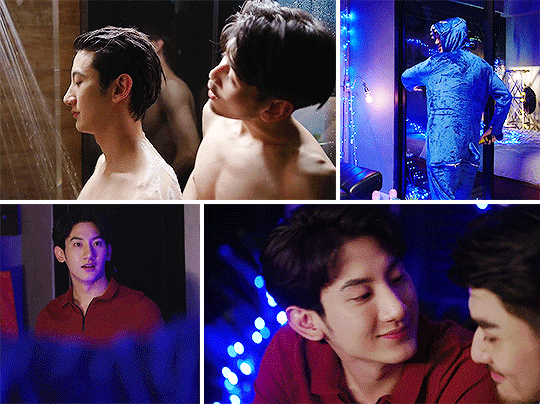
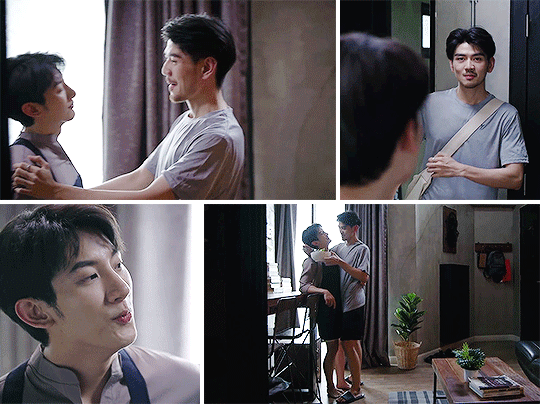


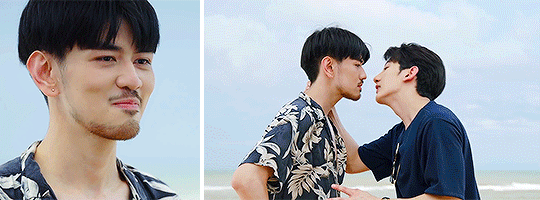
Long distance relationship is tough.
It requires trust. It requires patience.
And I want you to be patient.
I will be too.
3K notes
·
View notes
Text
Good night, my love

The moonlight is shining through the open curtains. As the calm night is approaching midnight, a couple of lovers are huddled together on the bed in the bedroom, facing each other.
Their bodies are breathing slowly, like waves that come and go. Their warm skin is touching each other under the thin quilt. Type quietly traces down Man's shins by the soles of his feet. Man slightly is bending his knees. Type is not as tall as Man would be, so he can only follow it to Man’s ankles. Somewhat frustrated, Type casually scratched the point of destination with his claws. Then a ticklish laugh came from the man in front of him. In a pleasant voice, like a dog with a full stomach, Man muttered.
“...... You still look full of energy today.”
“Yeah?”
“Wasn't that enough?”
Type can't help but let go of the toes that he has been flirting with because Man mutters such things with his eyes closed.
“Not so ...... you only have 0 or 100.”
“As for you, I have only 100.”
His voice is quite lispy, and his gibberish response is probably because sleep is already on its way. The rounded voice of the lover propagates his sleepiness to Type. The love affair which was carried out slowly and compassionately filled the heart of Type. He doesn’t think it wasn’t enough at all. It’s just that he is in that mood today, somehow.
Type moved closer his face to Man who is breathing deeply now and whispered.
“Hey, where do you want to go out tomorrow?”
The only response to that was now an indistinct grunt.
“Shopping and stuff."
Regardless of Man like that, Type continues.
“Movie, something.”
While smiling with his bright lips that Man always compliments.
"...... I'll go anywhere you like.”
Their lips were already close to the point of touching. And then Type finally shake his lips.
“Because I love you.”
The words are so delicate that quickly unravel and disappear in the air. Type held his breath for a moment and stared at his lover's face. He came near his face as close as he can no longer even focus on Man, and counted the streaks on his lips. Sure enough, the only response from Man was a gentle sleep breath. After savoring the warmth of his breath for a moment, Type slowly left to his face again. Type doesn’t know why he is so full today. Then, it was at that time.
“If with you, P’Type…… I can go to ...... anywhere.”
Man's mouth, which should have been asleep, mumbled. Type startled and looked at his face with wide eyes.
“Man?”
Maybe he was pretending to be asleep? The thought crosses his mind for a moment, but there is no answer as Type called out to him. Instead, all he heard was the sound of deep breathing, the same as before.
Type let out a laugh this time as he looked at the lover’s face.
“...... You're an idiot.”
You can't even hear me, and you talk about me in your sleep.
Man moved his mouth like a fretful child. Type gazed at his face finally and quickly jumped into his chest. It was the warm skin of a sleeping man.
May his face be the first thing in my eyes when I’ll wake up tomorrow. Type hoped so, was breathing his that in time with his slowly rising and falling chest.
“…… Goodnight, Man.”
If be with you, tomorrow, and the day after that, it's going to be a good day.
Type quietly closing his eyes. The curtain of the night gently envelops them both.
#2gether#2gether the series#ManType#Man×Type#toptap jirakit#mike chinnarat#slice of life#night bedroom#wish theirs happiness would last forever#my fanfic
1 note
·
View note
Text
Why don't GMM TV plans MikeToptap's own series as main roll? They must be one of the cutest side couple I guess...
17 notes
·
View notes
Text
ManType fan fiction
Title: Your Voice
If someone asked the old me what do you like about him, I would say his looks are all I care about firstly. When I knew nothing about him and I looked everywhere for him. I wasn't able to stop thinking of his sharp face even when I slept and awoke to come to mind how he laughs like.
Well, How about now? What would I say if someone asks me that once more now?
His personality is twisted, obstinate, and not be honest with his feeling. But he also can’t hide his thoughtful. Additionally, he is a surprisingly graceful person! Of course, I still love his cute face.
And then,
(――voice)
Yes, I know, this is it.
“Would you like to call my name, P’Type?”
“…Huh?”
At 10 pm. After taking the shower, We were sitting side by side on the bed, spending each time for yourself.
“What’s the matter with you?”
“Nothing, go on please.”
Type was checking his schedule by the cellphone raised his head and looked Man quizzically. Despite his cold face, Man keeps staring with his smile. But the more he smiled, the more Type raised his eyebrow gradually.
It seems like Type guess that Man’s smile has something not good for him even though they both are lovers now. It can’t be helped more or less because Man has been gone to everywhere he appears with this smile. Man repeated his request again without worrying about that.
“Would you please call my name?”
Using this way, My lover gives in to push than he thought, often accepts his boyfriend’s favor. Man knew so well it that he kept it going again and again. After a while, he took a deep sigh as if he gave up on suspecting just as Man expects.
“……Man”
…Damn, Close.
The voice Type said passed through almost touching the floor as if some small animals run through between the grass. It ran through in front of Man with swoosh noise and he went after it with his eyes unconcernedly.
Umm… That's not bad. Actually, Man was able to see Type’s adorable canine tooth from between thinly opened mouth. But it wasn’t one satisfy Man’s desire correctly.
“Umm, It’s not bad, but you know…”
“YOU made me say it, aren’t you?”
“That’s definitely correct but…I just mean…Uh, anyway, could you say that again?”
“What?”
“Please! I beg you!”
”What the heck. I never say that again until you tell me why.”
His face tells me how uncomfortable he feels directly. Man knew he couldn’t do it until he explains why he wants Type to say that. It’s nothing to hide about. Having thought about that, Man told his boyfriend what he has thought, gazing at his eyes.
”I just… I was thinking about what I like about you.”
Type’s facial expression suddenly changed when he heard it. His eyebrow still raised, but Man understood. It’s not the face when he is uncomfortable but is embarrassed. His boyfriend who couldn’t hide his upset looked so cute that Man couldn’t help without got too carried away.
“ I can tell you everything, of course, I’m more honor to tell you than――”
”Enough! You must not do it anymore .”
Do you see it? He doesn’t let me finish when I’m just pulling his leg. How sweetie he is. Man tried not to break into a smile and carried on.
“There are more many points that I like you than stars in the sky. But the most is your voice.”
“…Voice?”
“Yes. Especially that one when you call my name.”
He blushed his snow-cheek now, puckering up his beautiful mouth.
“That’s why I want you to call my name.”
Man said that, and he placed his hand on Type’s one which fingers intertwined. Type looked down their hands on his thigh and said bluntly.
”…You don’t know embarrassing.”
”I know, but…P’Type?”
Without saying, Man tells his boyfriend what he wants him to do.
“…Man.”
This slower voice sounded like smooth silk. It has touched Man’s heart and lighted a little candle in his heart.
“One more?”
“…Man?”
“Wow, can I say one more please?”
“Man…Man, Man, Man, Man….”
“Come on! You are such a joker!”
He would have been seriously embarrassed, he frowned his brow and started murmuring his boyfriend’s name deeply like a magic spell. What the hell is he doing. Man burst out laughing. Who’s going to say P’Type who doing such a silly thing to cover up his embarrassment isn’t cute?
This magic spell is also his voice that he call me. Many candles in Man’s heart are lighted.
I love his voice. I love my name, “Man” he says.
When we meet firstly, this "Man" was hard so much as a block of concrete. He also says “Man” with various kinds of voice. Sometimes it was tired, sometimes it was said to reprove, sometimes it was said to hold me up trying to go out from the classroom, and sometimes it was said like a special secret in the bed.
Every “Man” are must be precious to Man. And the unbelievable thing is this “Man” has more various kinds of tone than every instrumental around the world and more various kinds of color than any famous pictures.
Man laughed again. His hearts were warmed by the amount candle in his heart.
After a while, finally, Type stopped murmuring his boyfriend’s name when his mouth couldn’t keep it going anymore. And then he also started laughing at Man who is looking at Type with happiness.
Man also loves his boyfriend's smile.
“…Hey Man”
At last, Type said. It was similar to one when Man heard at the cafe used to go together. And Man responded to him, staring his beautiful eye.
“Khrap, P’Type.”
And then they started laughing again.
#2gether#ManType#Man×Type#toptap jirakit#mike chinnarat#S1EP13#my fan fiction#slice of life#2gether the series
3 notes
·
View notes
Text
パターソンについての考察ーFriday
頬に何かが擦れる感覚がする。羽のような、でも温かくて、もっとと頬を寄せてしまうような。心地よい感触に目を開くことができず、ふわふわと眠りの淵をさまよう。そうしているうちに、今度はまばらに生えたバッキーの髭をなぞり始めた。無精髭の上をさりさりと掠めていく何か。微睡から引き上げられたバッキーは僅かに眉間にシワを寄せて呻く。流石にそれは、
「……くすぐったい……」
もごもごと呻いて目を開けると、暗がりの中で自分を見つめるスティーブの顔があった。
「……ごめん、起こした」
「いい……もう、行く?」
まだ起き切らない頭で問いかける。確か、任務への出発は早朝だったはずだ。今が何時だか知らないが、部屋の中にまだ朝の気配はない。
「いや、まだ大丈夫。何か食べてから行こうと思って。バッキーはもう少し寝るか?」
「や、起きる……。お前、準備とかあるだろ、朝メシ、作るよ……」
なんとかそう返すと、頭に血を回すために寝転がったまま大きく伸びをした。口からんーという声が漏れて、身体中に酸素が行き渡る。起こされたのは確かだが、寝過ごすくらいなら早起きすぎるほうがマシだ。スティーブは眠気を追い払おうと格闘するバッキーを眺めて微笑んでいた。そういえば、寝起きのバッキーは言葉が幼くて可愛いと言われたことがある。そんなのお互い様、というか誰だってそんなもんだろうと思うけど。
バッキーはもう一度伸びをして身体を起こした。1人だけふにゃふにゃしているのが許せない時もあるのだ。今度はしっかりと目を開けたバッキーを見て、スティーブは小さく頷いた。
「……ありがとう、じゃあシャワーを浴びてくる」
そう言ってするりとベッドから抜け出す。ボクサーパンツだけを履いた後ろ姿には綺麗な背筋が見て取れる。その辺に散らばったTシャツを集めて寝室から出ていく時のしなやかな筋肉の動きをバッキーは眺めた。どうしてかスティーブのそれは誰よりも美しいと思う。もちろん自分の引き攣れた皮膚なんかとはそもそも比べるべくもないのだが。
(そういえばあいつ、ゆっくりしたいって言ってたか……)
夕べの言葉を思い出し、そして先ほどのバッキーが起きるまでのスティーブの行動を思い出し、その結果バッキーは朝から胸の内がむずつくような恥ずかしさに口元を押さえることになったのだった。なんて取るにたらない、ささやかな「ゆっくり」なんだろうと。
「やっぱアイツ……たまに恥ずかしいよな……」
もう少ししたらベッドから降りて顔を洗わないと。任務に発つスティーブの為にも、彼の望む朝――というにはまだ暗すぎるが――に答えてやらなくちゃいけない。
ミルクをたっぷりと使ったオムレツとトーストを食べ、結局バッキーもスティーブと連れ立って家を出ることにした。外はようやく木々の向こうが白み始めた程度で、町も人もほとんどが眠りについている。ただその中でも、ぽつぽつと窓から明かりの漏れる家たちがある。夜を迎える時と朝を迎える時、どちらにも同じ景色があるのに、夕方のそれが温かみを持つなら、早朝の空気の中に点在するそれらは清澄だ。
住民たちを起こさないような控えめなエンジン音が街を抜けていく。アベンジャーズ基地には既に調整の終わったクインジェットが待機しており、スティーブは小さなブリーフィングを終えるとナターシャと共に空へと飛び立っていった。
「……アンタも来たのか。アイツらが到着するまでは暇だぜ?」
小さくなっていく機体をラウンジの窓越しに眺めていると、後ろからサムの声がした。
「起きちまったんだよ……それを言うならお前だってそうだろ」
「オレは今から朝飯とか食う」
その言葉にふうんと返してサムの方を見ると、既に彼は振り向いてキッチンへと向かおうとしていた。朝の挨拶にしては随分だが、そういうところが彼らしい。サムもバッキーもスティーブたちが任務に当たっている間は基地で待機することになっている。基地内の居住スペースに滞在しているサムこそ、もう少しゆっくり起きてきても問題ないだろうに。
バッキーは軽く息を吐き、自身もコーヒーを淹れようとキッチンスペースに足を向ける。するとちょうど良くサムが顔を上げ、あまりにぶっきらぼうな顔でコーヒー飲むかと聞いてくるのだった。
「そういえばさ」
サムの朝食を見守り、管制室のモニターを眺めたりラウンジで過ごしたりしているうちに時刻はランチの時間になっていた。スティーブたちの作戦は進行中だが、かといって自分たちがモニターにひっついてできることなどそう多くはない。新たな暗号やデータが発見されればバッキーの出番であり、彼らに何かあった場合はサムがすぐサポートに向かうが、つまり今回の任務における待機なんてものはそんなレベルだ。大人しく昼食を取ることにした2人はソファにかけてサンドイッチを頬張っていた。
バッキーが斜め前のサムに声をかけると、彼はベーコンを噛みちぎっていた顔を上げる。咀嚼を急ぐ様子もない相手に、バッキーもまた気にせずに会話を続けた。
「この前スティーブと映画の話をしたんだろ」
「……あー、ああ、オレが勧めたやつか」
「それ」
それがさ、と続けようとしてバッキーはつと口を閉じた。そのまま窓の向こうへと視線を投げる。何となくサムに会ったら話そうとしていた気がするのに、話し出してみるとそうでもなかったことに気づいたような。口に出した途端、見切り発車のような浮遊感がバッキーを襲った。
「……それが?」
瞬きを繰り返すバッキーに向け、サムが続きを促した。
「ああ、うん……。スティーブは何て言ってた?」
「は? 面白かったって言ってたぞ。古き良きアメリカだなとか。……なんだよ、一緒に見たんじゃないのか」
サムが眉を潜める。
「いや、一緒に見たよ。面白かった、教えてくれてありがとうな」
そうは言うものの、バッキーの表情は今ひとつ煮え切らない。
「……あんまり面白かったって顔じゃないけどな」
「うるさい、顔は元からこんなだ……いや、面白かったよマジで」
言い淀んでいるのは、決して言いにくいことがあるからじゃない。なんとなく正しく言える気がしないだけだ。バッキーは両手に収めたマグをことんことんと傾けては中のコーヒーを揺らした。
「スティーブがさ、素直には信じきれないって言ってて」
「……スティーブが?」
「その、この映画が大事にされてるのは良いことだとも言ってた。けど……多分、あいつが言ってるのは、良い奴は報われるっていう、そういうとこなんだと思う」
「……へえ」
「もちろんファンタジーだってわかってるけど……。でさ、スティーブはそう言ってて。でもオレは、あの終わりを見ててさ……スティーブもこうなるべきだなって思ったんだ」
その言葉に、サムが首を傾げる。バッキーは続けて補う。
「自分の人生とか、幸せとか犠牲にして人助けしてさ、いろいろあったけど結局は報われるんだ。オレはすごく嬉しかったし、スティーブみたいだって思った。こいつがこんなに幸せになるなら、スティーブにだってきっとこれくらいの幸せが似合うって」
「……今のスティーブは幸せに見えないって?」
「そういう言い方はずるい」
バッキーが眉間に皺を寄せると、相手もそれをわかっていたのか意地悪げに釣り上げた眉をすっと下ろした。
今のスティーブが幸せじゃないなんて、自分は決して言えない。ワカンダにいた頃から、そしてアメリカに戻ってきてからも、バッキーが平穏に暮らせるように内に外にと奔走し、一軒家まで見つけてきた男のことを。2人で初めてソファに腰かけた時に、心の底から漏れ出たような安堵の息を。それだけの想いをかけて作り上げた今の生活のなかで、スティーブがどんな風に笑うのかを。それらを間近で見てきたバッキーは、たとえ胸の内がどうあろうとスティーブが幸せじゃないなんて言えるはずがないのだ。それでもそんなことを思うのは、おそらくバッキーがスティーブの幸せの形を知ってしまっているから。かつてスティーブが望んだであろう、ハッピーエンドに似合う光景を想像できてしまうから。だからなんとなく、彼にはゴールがあると、そう感じてしまうのだ。
しかしそれを上手く言葉にできるはずもなく、バッキーはマグカップを手の中で遊ばせてから呟いた。
「……まあ、そこそこ楽しくやってる。今のは映画を見て、なんとなくそう思ったってだけだよ」
そう言ってコーヒーを啜る。冷め始めたそれは少し酸味が強い。
サムはしばらくバッキーの顔を眺めてからふうんと呟いた。
「まあ、誰だってキャップには幸せになって欲しいって思うよ」
「ああ」
「オレには、今でも十分幸せそうに見えるけどな」
「……うん」
そう言ったきり、サムはサンドイッチの残りに意識を戻したようだった。
変な方向に話を振った挙句、言葉を呑み込んだ自分に合わせてくれる。バッキーの浮遊感は消えてはいないが、言葉にしただけでほんの少し気持ちが軽くなったような気がした。こいつも大概なお人好しだ。
情報は入手したが気になることがあるから別拠点によっていく。帰投は日曜になるだろうとスティーブから連絡があったのはその日の夕方のことだった。
家に戻り、夕食のチキンを焼き始める。1人だから適当にパスタでいいかと思った矢先、昨日も同じものを食べたことを思い出したのだ。同じメニューで構わないという妥協と、なんとなく気が乗らない自分とを天秤にかけた結果、冷蔵庫を覗いたバッキーはワカンダで覚えた一番簡単な料理を作ることにした。
フライパンで両面を焼き、残った油にニンニクとアンチョビをいれ、乾燥バジルの瓶を大きく一振り。塊で落ちてきたバジルが細かく泡立つ油の上に絨毯のように広がった。誰かをもてなしたり、考え事をしたりするときのものではなく、ただ単に胃を満たすだけの料理。10分で完成した食事を終えても、時刻はまだ20時にすらなっていなかった。
(……シャワーして、本読んで、22時か……寝るか)
バッキーはその通りに行動し、22時にはペーパーバックを置いて灯りを消した。明日はもうちょっと手間をかけたものをつくろう。そして習慣で横たわってしまったスティーブの部屋のベッドについても。キングサイズのベッドに1人なんて、2日もやるもんじゃない。明日は自分の部屋で眠ろう。
目を覆うようにカバーを引き上げバッキーは目を閉じた。彼の金曜日は雪の夜のようにひっそりと幕を下ろした。
0 notes
Text
パターソンについての考察ーThursday
伸ばした手に触れたのはシーツにできた皺の凹凸だった。
「……?」
バッキーははた、と瞼をあげる。違和感による覚醒は普段より性急で、脳が隣にいるべき男の不在を認識する。手のひらを数度往復させてシーツをなぞり、頭の中にもう一度クエスチョンマークを浮かべた。
(寝過ごしたか……?)
部屋の中は普段起きたときよりも僅かに明るい。そうはいっても遮光カーテンから漏れる光による明るさなんてたかが知れており、焦るほどの日の高さではないことを瞬時に判断する。バッキーは伸ばした右手でサイドボードに置いてあるモバイルを探った。画面に表示された時間は朝の7時。今日がオフであること、そして昨夜のことを考えるとスティーブもまだ眠っていてもおかしくない時間なのだが。
先に目が覚めてしまったのだろうか。いつもならこんな日はもう1人が起きるまでベッドの中でゴロゴロしたり寝顔を見つめたり、もしくはからかって起こしたりするのが習慣になっているはずなのに。
バッキーはとりあえず欠伸をしながら起き上がり、ベッドの下に脱ぎ捨てられていた部屋着に手を伸ばす。おそらく朝食の準備でもしているのだろう。いつもとは違うペースで覚醒した頭は、なんとなくまだ身体と繋がっていない感じがする。起きているようで霞がかった頭を動かし、髪をかき上げながら寝室のドアを開ける。そしてその先にあった光景に、バッキーの脳はもう1段階急速な覚醒を強いられることになった。
「ハァイ。お目覚めね、バーンズ」
ぴったりとしたインナーにカジュアルなジャケット。組まれた足を覆うタイトなジーンズ。朝とは思えないほど完璧に仕上がったいつも通りのナターシャがソファに座っていた。
「……は?」
バッキーはドアノブに手をかけたまま固まった。一瞬の後に、脳が凄まじいスピードで現状に追いつこうと動き出す。なんでこんな朝早くに、家にナターシャがいる?というか、なんで気がつかなかったのか。自分はスティーブの起床どころか、他人の来訪にも気づかず寝こけていたのか。それはさすがに不味くないだろうか。いつから。いや、そもそもなんで。それは把握というより主に疑問の連続ではあったが、どちらにせよふわふわと残っていた眠気が吹き飛んだことに違いはない。バッキーが混乱した頭でなんとか最初の一言を口から捻り出そうとした時、意識の外からもう一つの声が聞こえた。
「おはようバッキー」
声の方向に視線を向けると、リビングの奥、ダイニングスペースに立ったスティーブがこちらに微笑んでいる。窓からの朝日を受け、普段通りの爽やかで清潔な雰囲気を纏ったスティーブだ。そんな日常の風景に、イレギュラーによる急回転を強いられていた脳が少しだけ落ち着くのを感じる。戸惑いながらもバッキーはとりあえずといった風に右手を上げてその声に応えた。
「――ああ、おはよう」
スティーブが僅かに眉尻をさげる。お前の混乱も無理はないとでも言いたげな顔だ。2人の間に位置するナターシャがその様子を見て再度口を開いた。
「あら、私よりさきにそっち?」
その声にバッキーの視線も戻る。
「ええと、悪い。――その、何かあったのか?」
ナターシャがこんな時間にスティーブの元を訪れるなんて、なにか緊急を要することが起こったのだろうか。でもそれならスティーブは自分を起こすだろう。ならばただ単に寄っただけなのか?
「いいえ、まだそんな緊急じゃないわ。でも今日のオフは残念ながらお預け。それを伝えに来たの」
ナターシャは事も無げに言い放った。それは何かあったという事ではないだろうかと、バッキーは訝しげにナターシャを伺う。しかしその視線の問いには返答することなく、代わりに告げられたのは気の抜けるような言葉だった。
「ねえ、せっかく来たのに朝食も無し? しっかり食べる派だと思ってたんだけど」
そう言って彼女は左右に顔を向ける。その言葉をきっかけに、やっとバッキーも動きを再開することにした。
「……とりあえず、着替えてくる」
そう言うと向かいにある自室へと入っていく。その姿をナターシャが意味ありげな目で追っていたことなど気づきもしなかった。
◇◇◇◇
「――わざわざ来る必要はなかったんじゃないのか」
キッチンへ引き返す前に、スティーブはソファで寛ぐ彼女に戸惑いの声をかけた。実際、自分も状況を全て理解できているわけではない。スティーブだけに聞こえた着信で、彼女は今日のスケジュールに変更がある為、5分後に来訪することだけを告げた。覚醒直後でまだコントロールできていない身体から思わず発せられたは?という声にバッキーが起きなかったのは偶然でしかない。要件だけを告げて終了された通話画面を数秒見つめ、スティーブ眠り続けるバッキーをそのままにベッドを抜け出し、最低限の身支度を整え彼女を迎え入れることにしたのだった。
「気づかなかったら面倒でしょ。電話も取れなかったかもしれないし」
スティーブが何かを言い返す前に、続けてナターシャはこう言う。
「まあ、でも電話も取れない状況なんて、直接来たところで朝からお邪魔になるだけだったわね」
平然と言ってのけるナターシャに、やっと彼女が言わんとしていることが伝わる。伝わったが故に、スティーブはその眉間に深く皺を寄せることになった。朝からなんてことを言い出すんだ。
「ナターシャ、」
「あら、いいことじゃない。それにあながち間違ってなかったみたいだし……相変わらず仲良しね」
「は?」
「……だって、ベッドはそっち――」
そう言ってナターシャはバッキーが出てきた部屋を指差す。そしてその指はふいと向かいの部屋に向けられた。そこは今しがたバッキーが入っていった部屋で。
「――で、着替えはそっち……、そこがバーンズの部屋なんでしょ? ねえ、毎日一緒に寝てるの? それともタイミングが良かっただけかしら」
そこまで言うと背後のスティーブを見る。眉間に一層力が入るのがわかる。今の自分は大層面白い顔をしていることだろう。
「……からかいに来たのか……」
「まさか。心配で見にきたのよ」
心配のしの字も窺えない格好で、ナターシャは満足した猫のような笑顔をしていた。
◇◇◇◇
結局3人で仲良く朝食を取った後、スティーブとバッキーは揃って基地に顔を出した。どうやらバッキーが解読していた情報について、明日にでも動きがあるだろうと判断されたらしい。全員で押しかける必要はないが、もしそこで新たな情報が手に入るのなら行かない手はない。対象の状況から、向かうのはかさばる(この表現が頻出するのは少し笑える)手合いより静かに行動できる人間の方がいいなどのやりとりが交わされる。結局今回はスティーブとナターシャが出動することになり、出発は明日の早朝、そのほか細やかな段取りを決めた後にミーティングは解散となった。
バッキーは解散後もモニターを覗き込んでナターシャと意見をやり取りするスティーブを少し離れたところから眺めていた。明日のミッションは特に勢力の頭を叩くという大きなものではない。むしろそこから得られた情報を次につなげるために、またバッキーの能力を使った解読作業が必要になってくるだろう。バッキーも明日は現場にいる彼らと迅速に情報を共有するために基地に詰めることになっていた。
真剣に話し込むスティーブの後頭部をぼんやりと見つめる。今朝バッキーが部屋から戻ると彼は紅潮のなごりを残したしかめっ面で卵のボウルを抱えており、ナターシャのからかいにあったことは明白だった。その反応が面白がられてるんだと、ナターシャの気持ちも多分にわかるバッキーだったが、一応幼なじみのメンツのために隣に並んで軽くフォローをしておいた。なんとなく、内容に予想がついていたからというのもある。
そんな今朝の様子は微塵も残さず真面目な顔をしているのが頼もしくもあり、同時に少しくすぐったくもある。バッキーは無意識のうちに上がりそうになる口角を押しとどめた。中庭のようなスペースには気持ちの良い初秋の日差しが差し込んでいて、実際に陽に当たっているわけではないのに指先が温まるような心地がする。バッキーは窓の外に目をやり、しばらくその光を眺めていた。
「――バッキー?」
ふと、後ろからスティーブに呼びかけられる。ふわふわしていた意識を室内に戻すと、どうやら話し合いは終了したようで、こちらを伺うスティーブと目が合う。
「終わったか?」
「ああ、大丈夫だ。バックは準備とか、大丈夫か?」
「ん、俺は特に」
「そうか。じゃあ帰ろうか」
「あ、え? 帰るのか?」
てっきりスティーブは基地に泊まるのだと思っていた。盾は車に積んであるから問題はないし、明日の出発は早い。バッキーはそのまま疑問を口にした。
「お前、今日は泊まると思ってた」
「いや……帰るよ」
「そうか」
スティーブがそう言うなら別に問題はない。2人は諸々の確認を済ませ、昼過ぎには基地を後にした。
夕方前に2人は遅めのランニングに出かけることにした。ナターシャの来訪によって消化できなかった毎朝の日課分だ。少しずつ日の落ちるのが早くなったアップステートニューヨークをハドソン川に向かって走る。川沿いは雑木林のため見通しが良いとは言えないが、それでもたまに木々の隙間からキラキラと光る川面が覗くのが見える。道幅も狭いのにどこか清々しい気分になるのは秋の気配を感じさせる高い空のおかげだろう。2人は車が来ないのを確認しつつ、最低限に舗装された道路をのんびりと併走した。
「夕飯、何にするかな」
「この前トマト缶を買いすぎたから使わないと」
「あーそうだな……じゃあパスタにでもするか。お前明日早いんだから、簡単なやつにしよう」
夕飯を食べて、今日は早めに寝てしまった方がいい。数日間寝なくても平気な身体を持っているとはいえ、できる限り万全の体勢で臨むのは当然のことだ。簡潔かつ完璧なスケジュールを脳内で組み立てたバッキーだったが、予想に反してスティーブからの返答は曖昧だった。
「……どうした。食いたいもんがあるならそれにするけど」
「え、ああ、いや、夜はパスタでいいよ。簡単なものがいい」
「……スティーブ?」
一定のリズムで吐き出されていたスティーブの呼吸が不自然に乱れる。ペースを保ったままスティーブの顔を覗き込むと、彼は慌てたように視線を外にずらした。
「おい、どうしたんだスティーブ」
こちらも訳が分からなくて眉根を寄せたまま見つめていると、スティーブは観念したように逸らしていた視線を戻す。そのゆっくりとした動きに合わせるように、彼の耳がじんわりと色づいた。運動によるそれじゃない。バッキーがそのことに気付いておい、と声をかけるより早く、スティーブはもごもごと呟いた。
「……早めに食事して、はやめに……いや、その、」
そこできゅっと唇を引き結ぶと、スティーブは意を決したようにその先に続く言葉を発した。
「今日も、お前と一緒にできたらって」
これは余談だが日中のスティーブは直接的にその手の言葉を発することを避ける節がある。一度雰囲気を作り上げればこちらが戸惑うほどの直裁的な男気を発揮するが、特に日中に至ってはそれこそ別人のように潔癖なのだ。そんなときに使われる言葉は決まって時代錯誤なほど遠回しで、まあ自分たちにとっての時代の定義こそ曖昧なのだが、ともかくこの分野におけるバッキーの読解能力は幸か不幸かすさまじいほど向上していた。それはもう、今の発言を造作もなく完璧に理解できるほどに。そして理解できたばかりに、バッキーにこのままランニングを続けることなどできるはずもなかった。
「――ふ、ははっ、お前、それ今言うのかよ!」
「っ、煩いな、だから迷ったんだろう!」
「だって今、ランニング……ははっ」
足を止めて腹を抱えるバッキーにつられてスティーブも立ち止まる。急停止と笑いによる痙攣に、バッキーは久しぶりに腹が引き攣る痛みを経験した。
「ああ腹痛え……何、ずっと考えてたのか」
身を屈めたまま、むすっとした表情に変わった相手を見上げる。スティーブは答えない。その顔を見ていると別のことにも思い当たった。気にするほどでもなかった、ほんの些細な違和感。
「もしかしてお前、今日基地に泊まらなかったのもそのせい……?」
今度こそ図星をつかれたように視線をうろつかせたスティーブは、観念したように口を開いた。
「……だって今朝、ナターシャがいたからゆっくりできなかっただろ……」
「ゆっくりって、」
「別に朝に何かしたいわけじゃない。でもその、朝からずっと不完全というか、なんか、引きずってるような気がして……。僕は明日からいないし」
だから今日もしたい。そう言うスティーブに、バッキーは違う意味での笑みを抑えきれなかった。別に今までのもそう悪い意味じゃないが、これはもっと――そう、言うなれば胸の内から溢れ出すものだった。バッキーは目を細めて相手を伺う。全く、思わず困ってしまう程に。スティーブが、この男が愛しくて堪らない。
「でも明日も早いだろ」
実際には微塵も気にしないのに、バッキーはあえてそう答えた。なんとなく返って言葉がわかっていたからだ。
「だから早く帰って、夕飯にしよう」
どこか開き直ったように構えるスティーブに思わず笑いを溢す。
なんとなくのルーティーン。惰性ではないが、別に意向を確認してやるほどのことでもないそれら。そういったものを、スティーブは思ったよりも大事にしていたようだ。そして彼の言葉に染み入るような嬉しさを覚えた自分も、おそらく。
バッキーは大きく息を吐き出して屈んでいた腰を精一杯伸ばした。うーんと気持ちよく伸ばして、ついでに空を見上げると、西の空がほんのりとピンク色に変わっていた。残る白に近い青空には、さらに白く引き延ばしたような雲が伸びている。秋がやってくるのだ。
「帰ろう。スティーブ」
「え、……ああ」
直接的な返事をしないまま、バッキーはスティーブを追い抜かして再び走り始めた。しばらくして慌てたように追いかけてきては隣に並んだスティーブの左腕に、軽く自分の右腕をぶつける。よろめくことこそしなかったが、ぶつかられたスティーブは不思議そうにバッキーの横顔を伺ってきた。バッキーは前を見据えたまま、口角だけをあげてやった。
「夕飯、にんにく抜きかな」
「……別に、気にしない」
スティーブがぽつりと呟く。バッキーは息だけの笑いをこぼした。
スケジュールを守って、日付が変わる頃には2人とも満たされた眠りの中にいる。
「……にしてもお前、ランニング中に言うか普通」
「うるさい」
「そんなんだから揶揄われるんだ」
「……ほっといてくれ」
2 notes
·
View notes
Text
パターソンについての考察ー Wednesday
うっすらと目を開けると正面にスティーブの顔があった。バッキーは何度か瞬きをして目の前で眠る男に焦点を合わせる。唇をわずかに開き、穏やかな息の音を吐き出している。起きているときは何かと力を込めがちなその眉間も、今は皺の影もなく存分にリラックスできているようだった。
バッキーはシーツを静かに浮かせて、少しだけスティーブに身を寄せた。向き合った顔と顔の間からシーツの中の空気が漏れ、バッキーの顔を温かくこもった空気が撫でていく。ぼんやりとした頭に、その温度が心地よい。眠っている人間の体温は高く、バッキーの顔を撫でてから霧散したそれからは、焼き立てのパンのような匂いがした。
よくスティーブは起き抜けのバッキーに顔を寄せては「寝起きの匂いがする」なんて言って笑ってくる。恥ずかしいからやめろと言っても一向に聞く気配がない。寝起きの体臭なんて好んで嗅ぐようなものじゃないだろうに、いつの間にそんな癖をつけたのだろう。詳しいことも言わずに、ただ毎回首筋に顔を埋めては少しだけ愉快そうに言うのだ。もう最近は怒る気もしなくなって、好きなようにさせている。
バッキーは霧散した匂いにそんなことを思い出しながら、そっとスティーブに身を寄せる。足を動かしてスウェット生地を辿り、相手の足の甲に親指を触れさせた。案の定スティーブのそれはしっかりと温かく、バッキーを十分に満足させる感触だった。足先、土踏まず、次に踵とぺたぺたと自分の足を押し付けては、柔らかくしかしその中にある骨の感触を肌で確かめる。最後に足裏全体で撫でてやれば、とうとうスティーブの瞼がふるりと震えた。
「……バック」
「うん、おはよう」
バッキーはスティーブに名前を呼ばれることが好きだった。特に、起き抜けでまだ舌ったらずなスティーブが紡ぐそれが。たった一言なのに、どんな言葉より自分を安心させてくれて、吹き出しそうになる程甘い。自然と吊り上がる口元を自覚しながら、額に垂れた前髪を梳いてやる。スティーブはまだ覚醒の途中なのか、むにゃむにゃと口を動かしている。そして目を閉じたまま、ぼやけた声でこう呟いた。
「……夢を見た」
「ん?」
「僕とお前で……ずっとどこかを旅してるんだ。ルート66みたいな、開けた場所を走ってて、でも僕らの乗り物は安っぽい自転車で」
「……へえ」
随分と可愛らしく、夢らしい夢だ。バッキーは愉快さを含んだ声で応えた。
「何にもない一本道なのに、気付いたら周りが昔のブルックリンになってて……人混みがあるからってお前は僕に先に行けって言うんだ……僕はそれに真面目に頷いて、しばらく縦列走行して、でも次の瞬間にはまた荒野を並んで走ってる……」
依然として目を開けないのはまだその風景を瞼の裏に見ているからだろうか。夢なんてシュールであってなんぼだが、きれいに縦列になった自分たちを想像すると少し笑える。空気が揺れたのに気付いたのか、スティーブは今度こそ瞼をあげ、自身も可笑しそうに目を細めた。薄暗い室内で目の青色が濃く見える。
「なあバッキー、」
「どうした?」
「……来年の春になったらバイクを買おう。2人でツーリングするんだ」
スティーブはとっておきの計画を話すかのような声で囁く。起き抜けの無邪気さがバッキーの顔を更に綻ばせた。
「いいぜ、楽しみだな」
バッキーも声を潜めて答える。スティーブが運転するバイクの後部座席も好きだが、風を切って走るこいつを横から見られるならそれも良い。バッキーの返答を聞き、スティーブは笑った。
実際のところ、スーパーソルジャーが揃って数日間も休みを取れることなんて奇跡に等しい。だからきっとルート66を走れる日はずっと先までこないだろう。それでも2人は満足げに笑い合った。今ここで秘密の計画を共有できる楽しさを味わい、そしてそれを存分に満喫してから、日帰りで楽しめるルートを描くのだ。
昼前に基地に出向いた2人はそのままロッカールームへと直行した。昨日までバッキーが取り組んでいた暗号解析は既に情報精査の段階に入っている。それにはバッキーよりも余程適した人材がいるため、バッキーは一度ここでお役御免になるのだ。よって本日は久しぶりにスティーブと手合わせをすることになっていた。
昨日のサムとの演習とは違い、2人がいるのは屋内にあるトレーニングルームである。マシンの一つも置いていない殺風景な場所だが、派手な武器を使わない2人にとってはシンプルな方がありがたい。
「基地を壊すなって、トニーからの伝言だ」
「わかってるよ、サム。手加減はする」
そういうサムは監督役らしく、だだっ広い部屋の隅で腕を組んでいる。
「……へえ、手加減するって、負けた時の言い訳か?」
耳に入った言葉にバッキーは素早く反応した。挑発じみた言葉はからかいの意図が大きいが、気分が高揚しているのは確かだ。それはおそらくスティーブも同じだろう。なんたって純粋な身体能力でいえば、お互いの相手が務まるのは自分たちだけなのだ。全力までとはいかなくとも、マシンや他の相手と手合わせする時とは雲泥の差がある。だからスケジュールに組み込まれたこの日を楽しみにしていたのは、きっと自分だけじゃない。
「お前こそ」
サムに言わせてみれば「いたずらを企んでるガキ」にしか見えない笑みを浮かべつつ、2人の手合わせは始まった。決着がつけば小休止、着かなければ30分で区切って小休止。盾もメタルアームも使用しないステゴロ仕様。お互いが遠慮せずにスピードを出せるのは、いっそ爽快に思えるほどだった。
1時間が過ぎ、2時間が過ぎ、気づけば監督役でもなんでもないギャラリーが増えても、一向にお互いを負かすことができない。何度目かの休憩でバッキーは少し息を荒げながら告げた。
「なあ、ついでに今日の夕飯を賭けよう」
「いいぞ。どうせお前が負ける」
軽口に乗ってくるあたり、スティーブもだいぶ熱が入っているらしい。バッキーは鼻で笑うと、色が変わった相手のウェアを指差して続けた。
「んなこと言って、お前の方が必死に見えるぞ。……じゃあ恥ずかしい秘密を一個。これも付け加えで」
「乗った。ただお前が負けても女の子に振られた話は無しだ。もう聞き飽きてるし見飽きてる」
「お前もデートの前に風邪ひいてぶっ倒れた話は無しだ。そんなの全部知ってる」
サムに言わせてみれば「常人なら死ぬレベルで殴り合ってるのに口喧嘩はガキ」でしかない応酬を繰り広げながら、2人の手合わせはその後も続いた。
正直に言って、楽しくないわけがないのだ。大戦中から数えても、スティーブとバッキーが同等の力で純粋に手合わせができたのは、この現状に落ち着いて初めてできたことの一つだった。敵意のないそれは一種のコミュニケーションでもある。次にどうくるのか、どう動くのかを考えることなんて無意識にだってできる。だからトリッキーに仕掛けた時に相手がうまく対応すると、悔しさより面白さの方が優ってしまう。そして頭も心もより一層高揚するのだ。こんなこと、楽しくないわけがなかった。ナターシャに言わせれば「本気の遣り合いにかこつけたデート」だったらしい2人の手合わせは、大勢のギャラリーを魅了しながらも空が赤く染まるまで終わらなかった。
◇◇◇◇
「恥ずかしい秘密なあ……」
コーヒーの入ったマグカップを抱え、バッキーはいつものソファでリラックスした姿勢をとっていた。スティーブもその隣に腰掛ける。
結局あの後も純粋な勝負では決着がつかず、業を煮やした外野からのたくさんの条件付けによって夕飯はスティーブに、そして秘密の暴露はバッキーに課せられることになった。バッキーは悔しがっていたが、2人の、しかも相当なな運動量をこなした後の超人2人の食事量となると金額的にも馬鹿にならない。そんな予想に違わず、2人は大量のデリとバーガーをテイクアウトし、無言で平らげた。ちゃっかり食後のコーヒーまで準備させて、ようやくバッキーの番というわけだ。
とはいっても、スティーブからしてみれば、この幼なじみの恥ずかしい失敗なんて今更聞いたところで目新しいものがあるとは思えないのだが。
バッキーはしばらくマグカップの中を覗き込んだ後、思い当たることがあったのか小さく笑い声をこぼした。
「……昔さ、お前に小説を借りたことがあったろ」
「本?」
「そう、面白かったからって言って勧めてくれた。主人公の絵がどんどん変わっていくやつ……覚えてるか?」
「ああ、あれか。『ドリアン・グレイの肖像』だろ」
その小説のことは覚えていた。課題図書として読み始めたところ夢中になるほど面白く、その後バッキーにも貸したのだ。
「あれさ、あの後怖くてしばらく眠れなかったんだ」
「え……?」
スティーブは予想外のところから飛んできたバッキーの告白に面食らう。あの頃、怖いものなんて知らないとばかりに堂々としていたバッキーが。女の子に振られてもまたやっちまったよなんて飄々としていたバッキーが。まさか自分が貸した小説を読んで眠れなくなってたなんて。そんな思いが顔に出ていたのか、バッキーはばつが悪そうに身動ぎする。
「俺昔からああいうの苦手なんだよ。ホラーっていうか、ぞわぞわする感じが」
「そうだったのか……」
たしかにホラー小説の括りではなかったが、薄気味の悪さの漂う話ではあった。主人公が恋人を捨て、初めて自分の肖像画が醜く変化していることに気づいたときの衝撃は、描写も相まってスティーブも思わず背筋を震わせた。
「しかもお前、よく俺の絵を描いてただろ。夜になるとそういうのも思い出して」
「うん」
「お前に内緒で、スケッチブック全部盗み見たこともある」
「えっ」
「絵が変わってないか、怖かったんだよ」
そこまで言うとバッキーは非難の色を含んだ目でスティーブを見た。
「それなのにお前は平気で面白かっただろって聞いてくるし。こいつは怖くないんだって思ったらなんかムカついた」
思い出した、恥ずかしいっていうかムカつく話だった、とバッキーはぶつくさと呟く。視線はマグカップに戻り、スティーブからは彼の唇が僅かに突き出されているのが分かった。確か、ハイスクールに入る前の出来事だ。その頃のことを思い出して、当時のような幼い表情をして見せるバッキーに、スティーブは反対に面白さを隠せない。
「あ、笑ったな、クソ野郎」
「だってあの頃のお前の兄貴面を思い出したら。馬鹿だなあって」
「うるさい」
スティーブはとうとう耐えきれなくなって笑い声をあげた。振動で手にしていたコーヒーの水面に波が立つ。しかめっ面をしていたバッキーも、次第にその表情を緩ませると、ついには呆れたように破顔する。大の大人がソファに並んで肩を震わせている。スティーブの頭の中に、恐る恐るスケッチブックをめくるバッキーと、何食わぬ顔で自分に説教をしていたバッキーが交互に浮かんでは消えた。
しばらくそうして笑っていると、息を整えたバッキーが再び口を開いた。
「まあ、でも俺たちも言ってみりゃ、100歳越えでこの身体だもんな」
「どこかに僕らの絵があるのかも」
「やめろよ、ぞっとしねえ」
そう言ってまた小さく笑う。たしかに生まれた年と肉体的な年齢には大きな差があり、加え��血清で強化された身体は彼らの老化を通常よりも緩やかなものにしていた。
しかし、だからと言って完全に時間が止まっているわけではない。スティーブはそっと手を伸ばし、くつくつと笑うバッキーの目元を撫でた。その指の腹に伝わる感触に目を細める。
「大丈夫、僕らはちゃんと老いてる」
バッキーが笑う度、目尻に皺がよるようになったのはいつからだろう。きっとワカンダで過ごしているあたりだろうが、気づいた時には元からそうだったと言わんばかりに、それが彼の笑顔の一部になっていた。ただ一つ確実に言えるのは、それからスティーブは彼の笑顔を更に好きになったということだ。ひなたのように温かくて優しい目。今も、スティーブの言わんとしていることに気付いてその皺を深くしている。
「お前も髭が生えるようになった」
バッキーは穏やかに言い、同じように顎の骨をなぞった。じんわりと体温が伝わってくる。
「あれはもうしばらくいい」
「似合ってたのに」
バッキーの手が動く。彼の頬を覆っていたスティーブの手に重ねられる。
「手も柔らかくなった」
「……普通は逆じゃないのか」
「そうだな、でも昔のお前は骨張ってて冷たかった。今は温かくて柔らかい。肉付きもいい」
「バッキーも早起きできるようになった」
「しかも湖を見るために」
バッキーのこぼした息が掌をかすめる。
「俺ら、もうとっくに年寄りだな」
そう言って笑うバッキーの目元をスティーブはもう一度撫でた。
胸に迫るたくさんの思いがある。辛かったり、優しかったりするそれらは、もうほどくことができないほど深く絡み合い、スティーブの胸を押しつぶす。それは、時折苦しくて息ができないほどに。ただこうしてソファに身を預け、バッキーと笑い合うことができるうちは、スティーブは自分の心に少しだけ優しくなろうと決めていた。なぜならスティーブは、その苦しさの意味を知っていたから。
「……誰かといて満たされてると思ったり」
バッキーは一瞬瞠目し、すぐに目を伏せた。
「……ベッドのテクが上達したり?」
「こら」
「はは、悪い。老いっていうより成長だな、スティーヴィ」
照れ隠しをしてくれるなら、それは彼に正しく伝わった証拠でもある。だからスティーブはそれ以上言葉を重ねることをやめ、バッキーの左手から冷たくなったマグカップをそっと取り除いた。
時計の針は9時を回ったところだった。今すぐに寝ようとでもすれば、また一つ高齢者と言われる理由を作る羽目になる。スティーブは伺いの意味を込めてバッキーと目線を合わせた。バッキーはくすぐったそうに口元を動かすと、やがて囁くようにこう言った。
「……今は? 満たされきってる?」
「……足りない、かも」
2人は顔を見合わせた後、やはり耐えきれなくなって小さく笑った。
おそらく夜はまだ続き、知らない間に日付は変わっているだろう。
0 notes
Text
パターソンについての考察ーTuesday
なんとなくの息苦さにバッキーはうっすらと目を開けた。視界に映るのは、カーテンの隙間から僅かに青白い光。んん、とむずがるように身動ぐと、自分を起こした息苦しさの正体に気づく。自分の背後で、バッキーをしっかり抱き込んだままのスティーブが眠っている。その左腕がバッキーの脇腹の上に我物顔で居座っていた。ゆっくりと手を伸ばしてモバイルを見る。そしていつもとそう変わらない時間であることを確認してから、バッキーは自分の後ろに向かって囁いた。
「……スティーブ?」
静かな寝室の空気を僅かに揺らしただけの声でも、彼には十分な大きさだったらしい。弛緩しきった筋肉が僅かに震え、そして頸のあたりから掠れた声が聞こえる。
「……バック」
「うん……、おはよう、スティーブ」
そう言って自分の腹に回っていたスティーブの腕をあやすように叩く。スティーブは呻きながらも身体にぐっと力をいれて、バッキーを抱きしめた。筋を伸ばして身体を目覚めさせているのだ。大型の動物に懐かれているようで微笑ましいが、逞しい胸や腕に圧迫されて苦しいものは苦しい。バッキーはこら、と笑ってもう一度腕を叩いた。今度はタップの意味を込めて。
自室で着替えてから、ランニング用に軽くパンを齧る。カーテンを開けてもまだ外は薄暗い。だが雲は少なく、気持ちの良い晴れを予感させる空だ。朝晩は冷え込むようになってきたから、長袖にしたほうが良かっただろうか。バッキーがそんなことを考えていると、同じように支度を終えたスティーブがダイニングにやってくる。バッキーは振り向き、その右手が掴んでいたものに目を止めた。スティーブもそれに気づいたのだろう。笑顔を浮かべながら右手のそれ、朝のランニング用にしては大きめのナップサックを掲げた。
「なあ、今日は『荷物』をもっていかないか」
バッキーも心得たように笑い返す。本日の天気だとか、相手も窓の外を見て同じことを思ったのなら嬉しい。
「いいな、賛成だ」
スティーブとバッキーの日課であるランニングにはいくつかのコースが存在する。ハドソン川方面に向かい、雑木林の横を走ることもあったし、町を周回することもあった。後者の場合は朝食用のパンを買って帰ることも多い。空港の始発便に向かう車ぐらいしか見あたらない起き抜けの町を走るのは、緑を見ながらのランニングとはまた違う良さがあるのだ。
そしてもう一つは湖に向かって走るコースである。天気が良くていつもより少しだけ早起きした日、まさに今日のような朝には家から7マイルも離れた湖を目指すことがあった。もちろん片道7マイルといっても、彼らにとっては「近場だな」で終わらせられる程度のものなのだが。そしてそんな日にはスティーブの言う荷物、つまり小さなガスコンロとコーヒーのセットを持って、穏やかな湖を眺めながら朝日を浴びるのである。それはたとえトニーたちから爺さんじみた生活だと揶揄われようとも、2人にとって言いようもなく贅沢な時間だった。都市部からキャンプに訪れた家族が気合を入れて前日から待ち望むような時間を、彼らは気軽に日々の選択の一つとして享受できるのだった。
白み始めた空を見上げながら2人は走り始めた。森や生き物達が起き出す気配。鼻から息を吸えば澄んだ朝の空気が脳を冷やしてくれる。
目的地についた時、木々達の先から頭を出した太陽が、丁度水面を照らし始めようとしていた。視界のすべてが白い光の膜に包まれ、ナップサックを開いた時の僅かな埃さえキラキラと踊っていた。
顔を上げるとスティーブがこちらを向いていた。その姿を目に映して、バッキーは思わず息を飲んだ。朝日に照らされ白に近づいたブロンド。湖の水をそのまま移したような澄んだ瞳。睫毛にまで陽が当たっている。あまりにも神々しいスティーブに、視線の外し方を忘れてしまう。バッキーがそのまま言葉をなくしていると、ふいにスティーブが目を細めた。そうしてバッキーの目を覗き込み、深く穏やかな声でこう言った。
「……バッキーの目、光が当たると模様がよく見える……吸い込まれそうだ」
きっと昔の自分であればこの思いをすぐに口にできていただろう。お前の方こそ、だとかうまい例えを持ち出して。だが日頃から必要以上に言葉を発しなくなったツケなのか、素直に感情を伝えたい自分と捻くれた自分のバランスが入り乱れ、口を僅かに開閉させるだけで一向に言葉が出てこない。
バッキーにできたことは、捕まったままの視線をそらさずにスティーブの美しい目を見つめ返すことだけだった。ありったけの愛おしさをのせて、穏やかに目を細める。彼らはお互いの瞳を覗き込んでは、その美しさに感嘆の息をこぼした。
人は朝に生まれるのだと、バッキーは唐突にそう思った。
その後和やかに朝食を食べ、家に戻ってきた2人は施設に向かう準備をして昨日と同じように車に乗り込んだ。そしてバッキーについては昨日同じ画面との睨めっこが開始される。読めたと思った文章はまた違う暗号を示していて、その重複具合はまるでマトリョーシカを開けているような気分になる。だがそれだけ厳重にプロテクトされているとなれば、その内容の価値も相当なものだろう。
そのうちの一つの人形を開けたところで、深く息を吐き出す。案の定、新しいマトリョーシカが出てきただけだった。おそらく次に出てきた文章はだいぶ古い形式を用いて書かれているのだろう。なんとなく見覚えはあったがすぐに思い出せそうにはなかった。
バッキーは情報処理のスタッフに声をかけ、データベースを確認してもらうよう頼むことにした。おそらくこの時期に使われていたものだと思う、とあたりをつけて特徴を伝える。一度解読したものはすべてデータとして保存してある。そこから探し出すのは、自分より彼らの方がよっぽど速いのだ。スティーブよりは現代テクノロジーに対応できていると思うが、それでも他のスタッフからしてみればどんぐりの背比べでしかない。それくらいは両者ともきちんと分かっていた。
バッキーは凝り固まった眉間を揉み解しながらラウンジへと向かった。気づけば作業を始めてから随分な時間が経っている。ランチを食べたかどうかも曖昧だった。コーヒーを淹れるためにキッチンに入ると、ふと窓の外の景色が目に入る。マグカップを持って近づくと、それは屋外演習場で訓練をしているスティーブとサムの姿だった。サムのスーツの特性上、彼らの訓練は屋外で行われることが多いのだ。盾を持ったスティーブが、空を飛び回るサムからのペイント弾を避け続けている。バッキーはコーヒーを啜りつつしばらくその様子を眺めていた。心の中で小さくスティーブを応援しながら。
(……ファルコンなんかに負けんなよ)
スティーブは盾や障害物に隠れながら、向かってくる弾を躱し続けている。バッキーは彼が負けないことを知っていた。スーツをも凌ぐ身体能力をこの目で何度も見てきたのだ。
だがそれでもスティーブを応援してしまう。それは2人の関係の長さのせいでもあるし、もはや自分にとっては習慣みたいなものなのだろう。スティーブが戦っているのを見て、幼い時は心配もしたし怒りもした。血清を受けてからの無茶苦茶な戦い方を諌めたこともある。しかし同時に、どこか眩しいものを感じていたのも確かだ。ちょうど���、まさにその眩しさが胸を温めているように。それは彼がブルックリン時代から一度も、本当の意味で負けたことがなかったと知っているからかも知れなかった。
「――ミスタ・バーンズ、」
訓練の行方を見守っていると、ふいに後ろから呼び掛けられた。振り返ると先ほど解析を頼んだスタッフが立っている。
「解析が終わったので報告を」
「悪い。今戻るよ」
するとゆっくりで構いませんよ、少しオーバーワーク気味ですと返される。バッキーはそれに苦笑を返しながら、それでもそのまま入り口の方へと向かった。バッキーの後ろでは、サムが丁度窓際に飛来するところだった。
夕食に昨日の残りのポトフとチキンのローストを食べ、それぞれの時間を過ごす。そろそろ寝ようかと声を発したのはスティーブの方だった。
「今日サムに映画の話をしたよ、この前の日曜日に観たやつ」
横になったスティーブが言う。バッキーは彼の方に身体を向けて、ああと応じた。
「あいつが勧めてくれたやつか」
「ああ、面白かったと礼を言ったんだ。そしたらサムが、これであんたらも現代アメリカ人の仲間入りだな、って」
「……なんだそりゃ」
とんでもない物言いにバッキーはくしゃりと笑う。こちとらブランクはあれど100年前からアメリカ人をやっているというのに。
「毎年クリスマスに、テレビであの映画をやるんだって。誰でも一回は家族と一緒に見たことがあって、子供はあれを見て良心を学ぶんだと言っていた」「キャプテンアメリカの映画からじゃなくて?」
「違う」
「まあ今の子供にとっちゃ、キャップは教育ビデオのお兄さんだもんな」
にやついた顔で続けるとシーツの中から伸びてきた手に鼻を摘まれた。この前ネットから探し出し、その後しばらくスティーブの顔を見るだけで思い出し笑いをしていたのをまだ根に持っているらしい。別に批判したり馬鹿にしたりはしていない。だからこれは主にスティーブの羞恥からくるものだ。
スティーブはため息をついて話を続ける。
「あの話、1919年から始まっただろう。僕の生まれた翌年だって言ったら変な顔をしてた」
「……まあ、子供の頃から古い映画だって思いながら見てたのに、その時代に生きてたって言われるとな。いろいろリアルになったんだろ」
「そうかもしれない。でも実際懐かしかったし、優しい映画だった。クリスマスっていうのも良かった」
「ああ」
「……僕は正直、あの映画を信じ切ることはできないし、すべてが報われると無邪気に考えることもできない。でも、僕らと同じ時代にああいう映画が生まれて……皆がこの時代までそれを大事にしていることの意味は、信じたいと思うんだ」
そう言ってスティーブは少し照れたように眉をさげた。バッキーは彼の右手を握ってやる。義手ではない、ちゃんと温度を伝えるための手で。そうして握ったままのスティーブの手の甲に軽くキスをする。今日はなんだか、朝からずっとこいつのことが眩しい日だった。
「……世界は、お前の味方だぜ、スティーブ」
そう言うとバッキーは身体を寄せて、相手の額にも柔らかなキスを落とした。唇の離れる甘い音、そこにもこの思いが含まれていればいいと思いながら。顔を離してスティーブの目を見つめると、今度は向こうが唇にキスをしてくる。バッキーがしたのと変わらない軽いキスだ。なんだか儀式みたいで可笑しくなってくる。最後に一つ微笑んで、バッキーはサイドテーブルのライトを消した。
目が慣れる前の暗闇に向かっておやすみと囁き合う。火曜日はこうして眠りについた。
1 note
·
View note