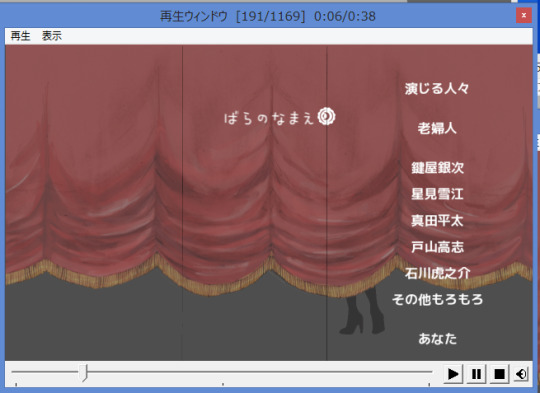Text
蛋白石 三話
少年探偵の変化にみな瞠目すること
おぼろげな黒い影が康子に呼びかけていた。
「誰? 誰なの?」
影は次第に収束し、青年の姿に納まる。
「ああ、正。やはり死んではいなかったのね。私は信じなかった」
健やかさの権化のように青年は、白い歯列を覗かせて微笑んだ。
「だって、遺体は見つからなかったんだもの。正、正」
病いで骨ばった指、割れた爪を空に伸ばす。しかし、稲光とともに青年の姿は二つに裂け、散り散りに飛び去った。悲痛の叫びが康子の口から洩れる。
「お母さま」
開いた目に飛びこんできたのは、亡き子息の姿ではなかった。三津枝が寝台の傍の椅子に座し、横たわる母、康子をうかがっている。康子は落胆のため息を吐いた。
「三津枝。私は決めました。予定通りお父さまの血縁から養子を迎えます」
「……それは」
思わず言葉を漏らした三津枝を康子は目顔で制する。
「弁えなさい。おまえは、女。家督を継ぐことは許されません」
「でも、お母さま。それでは、私はどうなりますの?」
「安心なさい。おまえには、嫁ぎ先を見つけてあげます。だいぶ格式は落ちるでしょうけれど、再婚ですからね。しかたありません」
三津枝は、膝の上で重ねた指を強ばらせいた。しかし、顔は笑んでいる。
「ありがとうございます。心から安堵いたしましたわ」
隅に控える看護婦に目配せし、三津枝は部屋を後にした。
雪江は、ベッドに座している少女の前で袱紗を開く。中には、少女の懐から零れた宝石が輝いていた。
「あなたが持ってらしたものですわ。どうぞ納めてください」
促されても少女は手を伸ばそうとしない。美しい宝石を目にしながら顔色は優れなかった。
「私、いらない。助けてくれた御礼にあげます」
驚いて雪江と平太は顔を見合わせる。
「簡単に決めちゃ駄目だよ。これって、すごく高価なものだと思う。ねえ、雪江さん」
「ええ。宝石ですもの」
困惑している二人に少女は口を開いた。
「いらないなら捨てて」
取り付く島もない。
「……そう。では、しばらくお預かりします。入り用になったら、いつでもおっしゃってくださいね」
少女は答えなかった。
「そうだ。記憶が戻るまで名前がないと不便でしょう? それで考えたんだけど『珠子』さんって呼ぶことにしたら、どうかな?」
「珠子?」
訝しそうに少女は平太を眺める。
「うん。だって綺麗な珠を持っていたから」
「まあ素敵! どうかしら? もちろん記憶が戻られるまでの仮の名前ですけれど」
少女は頷いた。
「……別にいいけど」
「気に入ってくれて良かった!」
小さなテーブルに白湯と急須、干菓子を並べ、雪江は席を立つ。
「まだお体が本当でないのですもの。そろそろお暇しましょう? 疲れさせてしまってはいけませんわ」
「うん。珠子さん、早く良くなってね」
雪江と平太は廊下へ下がり、扉を閉じた。
「……珠子だって。馬鹿みたい」
白湯には、塩漬けの桜の花が浮かんでいる。珠子は華やかな香りとともに湯を啜った。
「おかえりなさい!」
星見家の離れへ戻った虎之介は、元気のいい挨拶に迎えられた。真田平太である。彼はある事件を切欠に虎之介と関わり、今ではすっかり探偵助手気どりだ。室内の清掃、整理整頓、喫茶の用意まで引き受け、非常にかいがいしい。
「やけに冷えるな」
自室へ入った途端、虎之介は文句を並べはじめた。
「窓は閉めておけって言っただろ? 寒くてかなわないぜ」
「空気を入れ替えなけりゃいけないもの。虎之介さんだって煙たいでしょ?」
負けずに平太は抗議する。
「余計なことをするな。いいから閉めろ、閉めろ!」
自分は早々に椅子へ腰かけ、虎之介は平太が忙しなく働くに任せていた。懐から煙草を取り出し、ライターを探る。ふと机の上に置かれた紙片が目に入った。
「これは?」
「喜代さんに頼まれたんです。さっき電話があったからって」
ふりむいた平太は顔をしかめる。平太の心遣いは無造作に吐き出される煙草の煙でだいなしだ。
「……俺は出かける。もう帰れ」
虎之介は平太のふくれ面にかまわず、紙片を眺めている。送り手は三津枝だった。安田邸において今夜、元宵節の祝賀を行う。ついては、昼間の詫びがてら足を運んでもらえないだろうかとある。
「嫌だよ! 事件の依頼でしょう? ぼくも一緒に行く!」
「どうしておまえを連れて行くんだよ?」
「だって、ぼくは虎之介さんの助手だもの。お手伝いしてもいいって言ったでしょ? だから、掃除に来てるんじゃない」
虎之介は洋箪笥を探り、かまわず支度をはじめた。一張羅の燕尾服を抜き、引き出しからカフスとボウタイを取りだす。平太は目を丸くした。依頼人はかなり裕福な人物に違いない。
「良かった! これで借金を返せるね」
「うるせえな。まだいたのか? 帰れって言ってるだろ」
邪険にされても平太は慣れたものだ。
「靴はこれでいい? 磨きをかけようか? 車はどうするの? 歩いて行ったら足元を見られるよ」
子供のくせにわかったような口ぶりである。
「……女房をもらった覚えはないぞ」
虎之介は思わず、ごちた。
「虎さん。これは、なかなか難しいよ」
どうにも追い払えないと悟った虎之介は、平太を貸衣裳屋の戸口へ押し込んだ。これから銀行家の晩餐会へ出かけようというのである。ところが平太を眺めてみれば、洗いざらしの綿の袷一枚だ。
「この子は細っこいし、そうかと思えば手足が長いんだ。身幅と裄が合いやしない」
虎之介は帳場の新聞を広げ、店主に生返事している。
「女の子だったら五分袖、七分袖に直すんだが、腕を上げる下ろすで袖の位置が決まってる男の服じゃなあ。いっそ紋付きのほうがいいかもしれない」
幽霊騒ぎの記事に色鉛筆で赤丸がつけられていた。夜半、品川沖の砲台へ通りかかった酔漢が女の泣き声と灯火のない船影を目撃したというのである。記者は、この噂を眉唾としながらも砲台付近が怪異の絶えない場所であるとも仄めかしていた。『松前信太郎』と堂々署名された記名記事である。真偽は怪しいが、醜聞、怪事を書かせれば、彼の右に出る者はいなかった。
「この話。ちょっと面白いよね?」
店主が虎之介の手元を覗きこむ。
「商店会の酒席に使えないかと思ってさ。印をつけておいたんだ。みんな怪談が好きだから、幽霊船と聞いただけでも大喜びする。さながらフライング・ダッチマン号だ」
客寄せの扇情的な記事だが、虎之介の頭に蕎麦屋で邂逅した女衒の姿が浮かんだ。幽霊船と合わせて楽しい符号ではない。
「……黒いマストに真紅の帆か」
虎之介はつぶやいた。
「親爺。女の服でいい」
店主と平太へ言い放つ。
「ええ! 嫌だよ!」
「それなら帰れ。時間がない」
平太は、虎之介を睨んで唸っていた。
「虎さん。そいつは、あんまり酷だよ」
仲裁に入り、店主は平太を心配そうに見やる。虎之介は新聞を畳み、土間に杖をついた。
「待って! わかったよ。おじさん、服を持ってきて」
「坊ちゃん、いいのかい?」
頷く平太を見て店主は奥へ引っ込む。虎之介は店先の板張りから腰を上げた。
燕尾服姿の虎之介と非常に愛らしい少女が人波を泳いでいる。少女は、レースやリボンをあしらった水色のワンピースに短い上着を羽織っていた。
「平太。顔を上げてろ。みっともない。俺が女衒みたいじゃねえか」
うつむき、虎之介の背中へに隠れるように歩いている少女は、扮装した真田平太である。きらびやかな衣装に身を包み、よんどころない顔であった。
「いいか。通りの女を、よく見ろ。おまえみたいにドタ足で歩いてる女がいるか?」
平太は顔を上げ、通りへ目を向ける。老若、大勢の女が道を急いでいた。みな裾が乱れないよう気を配っている。時折、服を掌で払っては押さえ、髪を撫でつけていた。
「おまえは探偵、探偵と言うが、探偵の第一は観察だぞ」
「……こうかな?」
スカートを蹴飛ばさないように歩幅を狭めながら、平太は女たちの所作に目を凝らす。
「どうだ? 女ってのは、おまえの倍も気遣いしてるだろ?」
「うん。だから、女の人は、みんな身綺麗なんだね」
虎之介は手を掲げ、タクシーを停めた。
「平太。向こうへ着いたら俺はやることがある。おまえは観察の練習だ。わかったな?」
「はい! うんと気をつけるね!」
息巻いている平太が先に乗りこむ。虎之介は心中で舌を出していた。
「元宵節? 大陸の祭事ですね」
高志の言葉に雪江は頷いた。
「はい。康子夫人は、新婚の頃、旦那さまと世界中を旅行なさったんですって。その思い出に毎年、元宵節を祝ってらっしゃるの」
雪江はうっとり宙を見つめている。
「亡くなった旦那さまに今も思いを寄せていらっしゃるのね」
安田邸で開かれる祝賀に招かれたのは星見雪江の父親、星見辰一郎だった。しかし、彼は今夜も星の虜囚、天文学の研鑽に余念がない。そこで父親の代理に娘の雪江と婚約者の戸山高志が参上する次第となった。
この催しには、仮装を楽しむ様相もある。そのため二人は中華風の唐装に身を包んでいた。まるで竜宮から現れた姫と古代の王が連れ立って歩いているようである。
赤い提灯の明かりが石畳を照らす中、頭を垂れる運転手を後に雪江と高志は安田邸の門を抜けた。
INDEX PREV NEXT
3 notes
·
View notes
Text
ネコマタ 2
左目には涙
勝手口へ回り、放ってあった欠け茶碗に外付けの蛇口から水を満たす。
「何をしてらっしゃるの?」
声をかけてきたのは、義姉だった。
「ああ、いや。何ってこともないんですが」
猫に飲ませてやろうと考えていたのだが、急に馬鹿馬鹿しくなる。私は水場に茶碗を置いた。
「おかしな人ね」
私と兄は、姉を二人挟んでの兄弟になる。義姉とは干支の一回りほども年が離れていた。
彼女は、知り合ったときから兄の妻であり、義理の仲である。それでも私は彼女に特別な感情を抱いていた。慕うという意味ではない。欲望以外のなにものでもなく、到底、綺麗事ではなかった。
「すみません。……お悔やみを」
「朝から何度、口上を聞かされたとされたと思う? もうたくさん」
手を振り、眉墨の薄れた顔で渋面をつくっている。不機嫌な場合でも義姉の口角は決まって上向いていた。その行儀のよさが快い。
「そうですね。しかし、義姉さんが、しっかりしているので安心しました」
「あら、どんなことでも上手いふうにおっしゃるのね?」
喪服の義姉は常になく、刺々しかった。
「……ごめんなさい。憎まれ口なんか。すっかりくたびれてしまって」
「いえ」
「一本くださる?」
煙草を渡し、ライターに火を点す。義姉は煙草に火が移っても、私の手にそえた掌を、そのままにしていた。
「夫が死んだんですもの。私だって太平楽ってわけじゃないわ」
誰かに見られたら大事である。だが、義姉と手を重ね、私は黙って向かい合っていた。義姉は顔を少し傾けて細く煙を吐きだしている。
「我の強い人だったから苦労させられた」
義姉の掌は荒れて、ひどく冷たかった。加齢と水仕事のためだろう。それが私に、ある女を思い起こさせる。
若い時分、私は女の世話になっていた。はっきりした年を聞かなかったが、干支は虎だと言うから、今の私と義姉ほど離れていたのだろう。彼女には幼い娘がいた。私は、この娘の宿題を手伝ったり、占いを習ったりで日を無駄にする。
「あのね。女は生きてるときはつらいけど、死ぬときは苦しまないんだって」
トランプの札を繰りながら、娘は眉を寄せていた。
「そうなの?」
うつむいた娘の頬に艶々した髪が垂れている。
「そう。でも、男の人は違う。うんと苦しいよ」
「本当? 恐ろしいね」
「うん。お兄さんも、きっと苦しい。かわいそうね」
あの娘は、もう立派な大人に違いなかった。今頃、男に我儘申しているのかもしれない。
「兄は、苦しんだんでしょうか?」
義姉の爪が私の手をひっかきながら離れる。私は痛みに声も出ず、自分の手を押さえた。
「ごめんなさい。でも、驚かせるから」
「……いえ」
「本人でないもの。苦しんだかどうかなんて、わかりません。見たところは穏やかでしたけれど」
水を張った茶碗に義姉が煙草を落とす。火種が音をたてて、かき消えた。
九月の末、妻と若い女が座敷で話しこんでいる。滝の婚約者の君江嬢だ。彼女は、金釦のついた千鳥格子のワンピースに身を包んでいる。長い黒髪に結んだリボンが可愛らしかった。
「それはかまわないが、俺で大丈夫か? 君江さんのほうの仲人とつり合いがとれないとまずいぞ」
受ける前から衣装の相談を始めた二人を尻目に滝の顔をうかがう。
「叔父さんも大袈裟だな。結納なんか、かたちだけですよ。心配いりません」
滝はきわめて泰然自若とかまえていた。これでは、どちらが叔父かわからない。
「君江。叔父さんが引き受けてくれたよ」
滝と君江嬢は、近く結婚の予定だ。仲人を頼みに私のところへ訪ねてきたのである。
「うれしい! ありがとうございます、叔父さま!」
若い娘の笑顔に、ついこちらも頬がゆるんでしまった。それを見て妻は眉を寄せる。私は慌てて顔を引き締めた。
電話の音に妻が立ち上がりかける。
「俺が出る。いいから座ってなさい」
私は障子戸に手をかけた。
電話の相手は信久である。碌な話もせず、出向いてこいの一点張りだ。
「おい、信久!」
用件は済んだとばかり電話が切れる。腹は立つが、めずらしく慌てた声音だった。
「どうしました?」
不機嫌が表に出ていたらしく、座敷に戻った私に滝が声をかけてくる。
「信久だ。猫がどうとか言ってたが、はっきりしない。少し様子を見てくるよ」
「いやだ。今から出かけるの?」
妻もいい顔はしなかった。
「そうなんだ。君江さん、すまないね。気にしないで、ゆっくりしていてください。寿司をとってあるから、それでも食べて」
「わあ! お寿司は大好きです!」
手を叩いて喜んでいる君江嬢に安堵しつつ、座敷を後にする。
「叔父さん。ぼくも行きますよ」
滝が廊下へ出てきた。
「君江さんは? 大丈夫か?」
「洋子さんが相手してくれてます。結婚なんて女が主役でしょう? ぼくの出る幕はないですよ」
こんな薄情な男と君江嬢は暮らしていくつもりだろうか。私は内心、同情を禁じえない。着替えをすると断り、先に出ているよう滝を促した。
廊下を急ぎ、自室の衣紋かけから上着を抜きとる。袖に腕を通しながら鏡の中の自分を見るともなしに眺めた。可もなく不可もなく、何の取り柄もない中年の男が映っている。
信久の家へ赴く際にいつも粧しこんでいたのは、義姉のためだったと今になってようやく気がついた。
「智子」
滝と娘の智子が玄関先で猫を撫でていた。猫は体を長くして寝転がっている。
「もうすぐお寿司が来る。お母さんのところに行って相伴なさい」
「お出かけ?」
智子は、私と滝を順繰りに眺めた。
「智子ちゃん。しばらくお父さんを借りるよ」
滝に頷き、智子は猫を抱えて玄関に入る。
「可愛いですね」
「それだけじゃない。あれで立派な番兵なんだ。信久は猫が嫌いだから」
咳をする仕草で口もとを押さえ、滝は笑いを漏らしていた。
「猫じゃありません。智子ちゃんです。叔父さんに似てますね」
「……そこが問題だ」
私は街灯の点る路地に立ち、ため息を吐いた。
池に猫の死骸が浮かんでいる。私は信久の家の庭に佇み、額を押さえた。
「これは、いったい何なんだ?」
庭に面した座敷の障子が細く開いている。奥から顔をのぞかせているのは、信久だ。
「知りませんよ。勝手に死んでたんだ。早くなんとかしてください」
信久は言うが早いか障子を閉じる。
「信久!」
「叔父さん、無駄です。さっさと済ませて帰りましょう」
縁の下から滝が竹ぼうきを取りだす。通いの家政婦が放っているのだろう。
「信久。古新聞があるだろ? 持ってこい」
「嫌だ」
命じる滝に信久は否定を返した。
「どうして?」
「そっちへ行ったら、猫が見えるじゃないか」
「……このままにして帰るぞ。いいのか?」
障子が開き、信久が縁側へ出てくる。顔の前に手をかざし、障子のほうへ首をひねった不自然な体勢だ。こちらを見ずに新聞の束を投げてよこした。
竹ぼうきで猫を引き寄せ、重ねた新聞紙に安置する。あばらが浮き、濡れた毛並はみすぼらしかった。開いた口から舌が垂れ、雷に打たれたかのように手足を突っぱって硬直している。
「参ったな」
困惑する私に滝は当然という顔で答えた。
「庭の隅にでも埋めてやりましょう」
「庭に埋める? ぼくの家の庭に? 冗談じゃない!」
信久は大声になる。手を下ろした拍子に猫を目にして顔色を失くしていた。
「じゃあ、どうする気だ? 他に手はないぞ」
再び顔を掌で覆いながら、器用にこちらを睨んでいる。
「……ちょっと待っててください」
座敷へひっこみ、四角い冊子を手に姿を現した。冊子には『商店会』と記載がある。その間も信久は、掌を顔の横に立て頑なに猫と己を隔ていた。縁側を玄関のほうへ渡っていく。
「そういえば、本家の庭に猫を埋めたことがありました」
横たわっている猫に目をやり、滝が口を開いた。
「ずいぶん昔です。縁の下で子猫を見つけたんですが、かなり弱ってた。皿に水をためて戻ってきたら、もう死んでました」
猫の下で水を吸った新聞紙はたわみ、インクのにじみが広がっていた。
「それで思いついたんです。意趣返ししてやろうって。信久が縁側を通るたびに、おかしくて仕方なかった」
「葬式の時、智子が猫を見たと言ってたな」
「そうですか。亡霊かもしれませんね」
よく見れば、虎縞の猫である。なぜ溺れたのか。ふと池の水を飲みたかったのではないかと考えた。
「溺れ死ぬのは苦しいだろうな」
渇いて死ぬのと、どちらが苦しいだろうか。触れた猫の体は、固い部分と柔らかい部分が混在している。
「ひどいひっかき傷ですね」
信久が私の手の甲を見ていた。葬儀の日に義姉の不興を買った名残である。
「ああ。いや、これは」
かすかに猫の鳴き声が響いてきた。縁の下から子猫が顔を出している。滝は脇に積んであった新聞を猫の死骸にかけて隠した。
「……母親だったのか」
子猫は、母親と同じ虎縞である。「女は苦しまない」という言葉を思いだし、私は少し気が楽になった。そこへ乱暴な足音が響いてくる。
「話をつけました!」
意気揚々と信久が戻ってくきた。滝は子猫の襟首を掴んで、背広の隠しに押しこんでいる。
「三味線屋が引き取ってくれます。これで万事解決ですよ。それ、勝手口の外に運んでおいてください」
信久は相変わらず、顔を座敷のほうへ向けたまま庭のあらぬほうを指さしていた。足早に敷居をまたぎ、障子を閉める。
「三味線屋?」
しかめ面の私の横で滝が肩をすくめた。仕方なく猫の死骸を包み直し、腕に抱える。
「帰るぞ!」
私は座敷へ向かって怒鳴った。
勝手口の脇に死骸を置き、信久の家を後にする。
「どうする?」
滝は隠しから子猫を掴み、掌にのせていた。
「せっかくです。飼おうかと思います。信久を除けられるんでしょう?」
頭を撫でられ、子猫は目を細めている。母親の死を知ってか知らずか、安穏としていた。
「それは請け合うよ」
「しかし、こう呼びだされたんじゃ、かなわないですね」
「結婚すれば、少しは落ち着くだろう」
ヘッドライトを前方に認め、脇へ寄る。通り過ぎざま、業務用自転車の荷箱に三味線屋の屋号が見えた。
「忘れるといけないから渡しておきます」
懐からハガキをとりだし、私にさしだす。滝に宛てられたもので差出人の記入はなかった。
「珠からです。叔父さん宛てなんだと思います」
紙面を半分だけ使い、文字が書かれている。
『お兄さんへ 私はよく空を見ます ときどきお兄さんのことも考えます タマ』
空に月はなく、ただ星明りばかりだ。(了)
INDEX PREV NEXT
1 note
·
View note
Text
ネコマタ 1
右目には笑み
水をかえてやり、猫の皿へ餌を加減して出す。もっと欲しがっていたが、満腹ではネズミ採りの用をなさないと妻から厳命されていた。
座敷へ戻り、煙草の箱を叩く。出てきた一本をくわえてマッチを探した。
「マッチ! 洋子!」
呼びかけてから、妻と娘が外出していることに思い至る。鳴りだした電話の音に舌打ちしながら玄関へ向かった。
「叔父さん。お久しぶりです」
電話の相手はハガキの差出人、甥の信久である。
「早速ですが、ぼくのところへ遊びに来ませんか?」
「急だな。何かあるのか?」
信久は気の抜けたような笑いを漏らした。
「何ということもないんですが、来ませんか? 駄目ですか?」
「いや、行かないということもないよ」
「では、いらっしゃい。そうだ、今日は休みでしょう? ちょうどいい。今から訪ねていらっしゃい」
手前勝手にちょうどいいとは呆れる。しかし、信久の家まで、たいした距離ではなかった。
「じゃあ、お邪魔しようか」
言うが早いか電話は切れる。私は電話の脇にブックマッチを見つけ、煙草へ火を点けた。
手ぶらというわけにもいかない。露店で買い求めた鬼灯を手に桜木の並ぶ谷中の墓地を抜けた。桜は満開の花こそ素晴らしいが、青葉になってしまえば、みすぼらしい眺めの木である。凪いだ中、私は麻の背広を選んだ己を恨んでいた。別に信久の顔を見るだけなのだから普段着で十分である。生成りの仕立ては見た目ほど涼しくはないのだ。
墓地を抜けると三味線の音が響いてくる。同じ節回しが二、三度繰り返され、最初の奏者は明らかに上手だ。店の二階で三味線の教室を開いているらしい。下階のガラス戸へ墨で記した張り紙があった。
『猫ヲ 買イ取リマス 生死ヲ 問ワズ』
西部劇の賞金首を思わせる物騒な文句である。日のささない店内は暗く沈み、様子はうかがいしれなかった。
「早かったですね」
来いというから、わざわざ足を運んだのである。それなのに玄関先へ出てきた信久は驚いた顔だ。
「不都合なら帰る」
「どうして怒るんですか? おかしな人だなあ」
信久は兄の長男である。兄は信久に家を持たせ、生活費まで負担していた。本人は大学を出てから職にもつかず、絵描きになるとか物書きになるとか浮ついた考えでいる。
「どうぞ上がってください」
「では、遠慮なく」
鬼灯の鉢を信久に示して上がり框へ尻を据えた。
「綺麗!」
靴を脱いでいる背中へ女の声がかかる。バタバタと足音がして女が鬼灯の鉢を覗きこんでいた。足の付け根までしかないジーンズのスカートにノースリーブのブラウスを身につけた若い娘である。目のやり場に困って女の日に焼けた顔を眺めた。
「叔父さんのお土産だよ」
言われて女は私に笑顔を向ける。
「お兄さん、ありがとう!」
年は二十五、六といったところか。
「叔父さん。この子は、珠と言います。お珠、挨拶しなさい」
「珠です。早く上がって!」
面喰っている私の腕を女は掴んでひっぱった。
「ぼくは鉢へ水をやってくる。お珠は、叔父さんが不自由ないように世話してくれ」
「おい、信久」
呼びとめる私にかまわず、信久は鉢を持ち上げ、玄関を出ていく。
「お兄さん、どこから来たの?」
私は、女に腕を拘束されたまま廊下を渡った。
信久の家は典型的な妾宅の間取りであった。手前が座敷で、台所などの水回りは目立たぬよう奥に引っ込んでいる。手水鉢ほどの池を擁する小さな庭を左に臨んで座敷へ通された。
決まり事でもあるのか女は膝を崩し、私の隣へ侍る。黒目がちで首が細く、全体にすらっとしていた。美人というほどではないが、並に整っている。悪くない女だった。
「珠さんと言ったかな? きみ、住まいは近いのかい?」
「いいえ。ここでお世話になってます」
「……ああ、そう」
見知らぬ女と二人きりでは間が持たない。私は懐から煙草を取りだした。くわえるが早いか女がマッチの火をさしだす。
「ありがとう」
礼を述べ、マッチの炎に身を寄せた。女は細い指を振って火を払う。灰皿へ放り込む仕草は少々乱暴だ。
「お兄さんみたいな男の人って好きだなあ」
驚いたことに女は私の顔へ手を伸ばしてくる。頬骨のあたりを撫でていた。ここに至って、私の鈍い頭も事情を悟る。腹立ちまぎれに灰皿へ煙草を押しつけ、立ち上がった。女はきょとんとして私を見上げている。
「信久! どこだ!」
障子を開き、庭に向かって怒鳴った。
出てきた信久は悪びれるふうもない。
「何ですか、叔父さん? 大声は困りますよ。ご近所に迷惑だ」
鬼灯の鉢を手に現れた信久は、今にも吹き出しそうな顔だ。
「金の無心なら、そう言え!」
沓脱ぎへ鉢を置き、縁側に上がってくる信久の前に封筒を投げつける。
「あれ? わかってたんですか?」
信久は封筒を拾い、中身を確かめていた。
「今度は何だ?」
玄関へ向かう私を信久が追ってくる。その後ろへ女がついてくるさまは、まるでチンドン屋の道中だ。
「それが酷いんですよ。ぼくは裏切られた。密告です」
「密告?」
信久のほうへ見返る。
「滝を覚えてるでしょう? あいつは憎いヤツですよ」
歩をゆるめた私の横で信久は御託を並べだした。
「ぼくとは血の繋がった従兄弟だっていうのに、お珠のことを親父に言いつけるんだからひどい」
滝は姉の長男であるが、幼馴染というような生易しい間柄ではない。
「親父は親父で、金をよこさないと言ってくるんです。ぼくが困るのはわかってるのに。思いやりの欠片もない」
いうなれば、二人はハムレットとホレイショだった。だが、これは滝に限った話ではない。親族の男は、兄にとって彼の碌を食む家来だったからだ。時代を遅れも甚だしい封建制度の復古である。
「その点、叔父さんは頼りになる」
もちろん私も例外ではなかった。私の役回りは『山羊のおじさん』といったところか。しかし、私に立派な顎髭はない。兄の権威を簒奪する気概も、王妃を略奪する勇気もなかった。男として二階級は劣る。
「本当に帰るんですか? 寿司でもとろうかと思ったのに」
「どうせ俺の金だろう。馬鹿馬鹿しい」
私と信久のやりとりに女は吹きだしていた。
「まあ、そうですけど」
信久は頭を掻いている。
「だいたいな。金を借りるほうが出向いてこい」
「嫌ですよ。叔父さんの家には猫がいるでしょう? ニャーと鳴いてクネクネしている。考えただけでゾッとします。とても行かれやしない」
子供の時分に手ひどくひっかかれたとかで信久は猫が鬼門だった。
「おまえと比べたら百倍、いや、一千倍は可愛いぞ。猫にだったら、喜んで金を都合してやる」
「傷つくなあ。苦手なのは、しようがないじゃないですか。……そうだ、せっかくです。そこまで、お珠に送らせましょう」
「なにがせっかくだ。必要ない」
断る私を尻目に信久は女を促す。
「お珠。叔父さんを送ってさしあげなさい」
「はい!」
後ろから飛びだしてきた女は、早速サンダルを突っかけていた。
「信久。俺の話が聞こえないのか?」
「まあまあ。お珠は、すごく面白い女ですよ。なにしろ金魚を食べるんだから」
信久は、突拍子もない話を耳元でささやいてくる。
「尻尾のほうを、こう持って丸呑みです。ぼくも驚いたのなんの」
親指と中指、人差し指の三本で挟む真似をして見せた。
「……馬鹿なことを言うな」
「本当ですって。信じないなら、直接聞いてみたらいい」
私は女に目をやる。滑らかな褐色の肌とスタイルは素晴らしいが、何ら変哲のない若い娘だ。
「お兄さん、早く!」
笑った拍子に女の口元から、少し斜めにはえた犬歯が覗く。
通りは暮れはじめていた。しかし、宵の明るみは残っている。
「今日は、お月様がいないね」
女は残念そうに空を眺めていた。
「朔かな?」
街灯がまばらに道を照らしている。築地壁の間を抜け、歩を進めた。
「朔? 月が出てないこと?」
「そうだね」
頷きながら、私は女を眺める。彼女は、頑��して肉体的だ。溌剌として明朗、陰影は皆無である。私は煙草に火を点けた。煙を吐いて信久の言葉を追い払う。
「煙草、くれない?」
「吸うのかい?」
私は煙草の箱を振って、さしだした。女が指に煙草を挟む。
「うん、時々」
ライターを探る私に女は頭を振った。
「大丈夫」
手を掴んできたかと思えば、私の煙草から火を移している。女は後頭部が丸く、ショートカットの髪が頬へ垂れていた。炎で橙に染まった顔は、座敷で見るよりも美しい。
女の吐く煙の向こうに星が幾つか瞬いていた。
「ねえ、お墓のほうへ行く?」
覗きこんできた女は小首を傾げている。
「ああ。墓地を通るからね。嫌だったら帰りなさい。俺は一人でかまわないよ」
「ううん、違う。お墓が怖いんじゃなくて、手前にあるお店のほう」
張り紙の店が私の頭に浮かんだ。
「あそこは、三味線を売ってるんだって」
女は自分を抱いて、鳥肌の浮いた腕を擦っていた。
「三味線って猫の皮で作るんでしょ? 信久が言ってた」
「そうらしいね」
「お腹の皮がいいって。薄くてよく伸びるから」
己の腹を撫でている。
「……痛いよね?」
真面目に思い詰めているのが気の毒になり、私は口を開いた。
「信久は、思いつきを話すヤツなんだ。話を面白くするためなら何でも言う。聞き流していいよ」
「本当?」
「本当」
重ねて言うと女は表情をゆるめる。だが、前方を見て口を結んだ。通りに件の店から灯りが落ちている。白熱灯の光がガラス戸の張り紙を黒く濁らせていた。
「じゃあ。おやすみなさい!」
手を振った女は小走りになる。いま来た道を戻って行った。
それから、しばらくして兄が卒中で頓死した。襖をとり外した広間に膳が並べられ、精進落としの料理を思い思いに口にする。座しているのは男ばかりで、女たちは喪主の義姉を除き、慌ただしく立ち働いていた。
「そうですか。それじゃ、ずいぶん恨まれているでしょうね?」
滝は酒が入ったコップを手に笑っている。大学卒業の祝儀袋を渡して以来だ。喪服の甥は大人びて見える。
「どうだろう。もう忘れているんじゃないか?」
「それはないですね。信久は執念深い。忘れるってことがないんだ」
苦笑いしていた。
「ともかくぼくもこれで、お役御免です。肩の荷が下りました」
私も、つられて吹きだす。
「信久は喪が明けたら、すぐに婚儀だそうだ。忙しないな」
「まったくです。……叔父さんには話しておいたほうがいいでしょう。珠は、ぼくと信久を天秤にかけていたんですよ」
飲んでいたビールを吐きだしそうになり、私は咳き込んだ。
「大丈夫ですか?」
滝が傍にきて背中を擦ってくれる。子供の頃から面倒見の良い、気の利いた男だった。兄が信久にあてがったのも道理で��る。
「あちらからこちらへ週替わりで勤行ですよ。馬鹿にしたものでしょう? 初めは何とも考えてなかったんですが、だんだん情が湧いてきた」
私は、ハンカチで口もとを拭った。「水を」と立ち上がりかける滝へ手を振って断る。
「一緒になるから信久と別れてくれと頼んでみたんですが、はっきりしない。それで無粋な忠言したというわけです。しかし、結局のところ、逃げられました」
「……あの子。珠さんは、今どこに?」
「さあ。ぼくは、叔父さんがご存じなんじゃないかと思ってましたが?」
私は腹立たしい思いで滝を睨んだ。
「どうして俺が?」
「珠は、叔父さんのことを知りたがっていたんです」
知らぬ間に色恋沙汰へ巻き込まれていたとは、眩暈がしてくる。
「あなた。ちょっと智子を探してくださらない? 庭にいると思うんですけど、どこにも見えなくて」
妻の声に心臓が跳ねた。覚えのない浮気の嫌疑で、このざまである。廊下から座敷を臨んでいる妻に頷き、席を立った。
「ごめんなさい」
妻は、和服に合わせて結った髪のおくれ毛を撫でつけている。
「いいよ。どうせ帰ろうと思ってた」
囁きかけると妻の顔が安堵にゆるんだ。
「平気かしら?」
「次男なんて冷や飯食いだ。長居すると、かえって体裁が悪い」
廊下では退屈した子供たちが走り回って騒がしい。声をかけ、どうにか間を抜けて玄関から庭へ出た。
INDEX PREV NEXT
1 note
·
View note
Text
蛋白石 二話
虎之介、老婦人の舌禍に辟易すること
「申し訳ありません。驚かれましたでしょう?」
三津枝は虎之介の顔を伺った。
「いえ。しかし、夫人はご病気を患っていらっしゃる?」
「はい。母は、あの恐ろしい瘧ですわ」
瘧とは、高熱、悪寒、痙攣などの苦痛が周期的に表われる病である。ほとんどがマラリア主体であった。
「お医者様は、手の施しようがないとおっしゃいます。モルヒネで症状を和らげることができるのですが、苦しみは神が与えたものだから遠ざけるのは罪だと母は申します」
使用人たちが康子夫人へ示していた敬意は、これに由来しているのだろう。
「手立てがあるのに敢えて苦痛を選ぶだなんて。私には、そんな意気地はありません。到底、真似ができませんわ」
「誰でもそうでしょう。夫人は、特別に果敢な方のようですね」
「……母を許してくださいますの?」
虎之介は微笑んだ。
「驚きはしましたが、元から腹を立ててはいません。私は、康子夫人に雇われた。契約が履行されている間は、彼女が私の主人です」
俯き加減の三津枝の眼差しが虎之介の顔へ向けられる。柔肌に薄く化粧している三津枝は非常に美しい女だ。
「男の方が羨ましい。私は働いたことがありませんの。両の足で立ったことのない赤子のようなものですわ。いつも誰かに行く先を決められてしまう」
青みがかった瞼を伏せる。
「それが、どんなに情けない惨めな境遇かおわかりになるかしら?」
「……三津枝さん」
「私ったら、嫌ね。くだらない話ばかり。どうぞ忘れてください」
三津枝は気を取り直し、虎之介の斜め前に立ち、廊下を先導した。
「石川さま。金庫は、地下にございます。不自由なさらないでしょうか?」
杖を突いている虎之介を見返る。
「地下へはどのように参りますか? 梯子でしたら少々、難儀ですな」
虎之介は青年の頃、大陸へ渡った折に左足を負傷していた。杖の助けなしには立ち行かない。
「階段です」
「そうですか。それなら何とか凌げるでしょう」
備え付けの懐中電灯を外し、扉を開いた。
「地下は、電気が通じておりません。だいぶ急ですから、どうぞお気をつけあそばして」
虎之介も三津枝に続き、扉を潜る。仄かに懐中電灯の明かりが辺りを照らす中、虎之介は三津枝の後ろ姿を鑑賞しつつ、美女との道行を楽しんだ。
地下室は独特の臭気と湿気に満ちている。どこからか空調の響きがあり、窒息の心配はなさそうだ。
「……これは、これは」
虎之介は感嘆の声を上げる。部屋の中央に鎮座する巨大な鋼鉄製の金庫を仰いだ。
「三百貫弱あるそうですわ。父が生前、申しておりました」
懐中電灯で金庫を照らし、三津枝は感慨深げに、そう告げる。頼りない灯りに三津枝の滑らかな肌が金属光沢を放って白く浮かび上がっていた。黒目が青みを帯びて虎之介を見詰めている。
「ダイヤル式ですね? 開錠の番号をご存じなのは奥様の康子夫人でしょうか?」
その探るような視線に戸惑いながら、虎之介は口を開いた。
「いいえ。母と私の二人です」
車椅子の康子は地下へ立ち入れない。実質的に開錠可能なのは三津枝のみということになる。
「兄が亡くなってから、ずっとここへ仕舞っておりました。あの宝石は兄が出征前に母へ贈ったものですから、かれこれ二十年近くになりますわね」
三津枝の兄、正は観戦武官であった。観戦武官とは、文字通り戦争を見物する目的で派遣される軍人である。戦場において公式に軍事情報を収集することを許されており、駐在武官として外交特権を有していた。
「兄は、父の生業を『金儲け』と考えて嫌っておりました。男子たるもの国のために尽くすべきだと」
虎之介は如才なく頷いて見せる。
「立派な志でいらっしゃる。しかし、父上の経済行動も国を富ませるもののように思えますが?」
「兄は、妹の私の目から見ても世間知らずな人でした。そのために異国で亡くなった。自ら命を捨てたようなものです」
「……三津枝さんは、こちらへいつもお一人で?」
頭を振り、三津枝は身震いするように片手で自分を抱いた。
「いいえ、まさか。薄気味悪くて、とても私だけでは立ち入れません。ここへ電気を敷かなかった父を何度、恨んだことか。ご覧になって」
三津枝は懐中電灯の明かりを天井へ向ける。継ぎ目のない石材がむき出しになっていた。
「工事をして岩盤に穴が開くのを嫌っておりました。空調は通していますから、ただの縁起ですけれど」
壁と床も同じ石材で塞がれている。コンクリート、煉瓦の類は使用されていないようだ。十畳ほどの広さはあるが、圧迫感で息が詰まる。
「では、どなたとこちらへ?」
「別に決めておりません。手の空いている使用人の誰かですわ」
三津枝は事もなげに答えた。驚きを隠せず、虎之介は三津枝の顔を伺う。
「金庫には、盗難した兄上の形見の他に何が入っているのですか?」
「証券類や不動産の証書、当座の現金もありますわ。ご覧いただいたほうが早いわね。どうぞしばらく壁のほうへ向いていらして」
虎之介は三津枝に背を向けた。それを見計らい、三津枝は金庫のダイヤルを回す。錠の仕かけが働く機械音が小さく響いた。
「どうぞご覧あそばせ」
金庫の中は、三津枝の言葉通り金銀財宝の山である。なぜ犯人は『蛋白石』だけを持ち去ったのであろうか。紙幣の匂いを嗅ぎながら、虎之介は浮かない顔であった。
「三津枝さま!」
地下室から出てきた虎之介と三津枝の前に使用人がかけ寄る。
「ナツの姿が見えないんでございます。身の回りの荷物もなくなっております」
「まあ、いつから?」
使用人の女は首を傾げていた。
「どうでしょうか? 滞りなく内々が進んでおりましたから、昼頃までは家内にいたはずですが」
「ナツさんというのは?」
虎之介が割って入る。
「ええと」
三津枝の顔を女は、伺っていた。
「石川さまには、何でも話しなさい。我が家の災難を治めてくださる方なのですから」
「はい、三津枝さま」
女は虎之介のほうへ頭を下げる。
「失礼いたしました。ナツと申しますのは、当家の下女でございます」
二日ばかり前から安田家では、ナツという娘を雇い、厨房まわりや清掃などを任せていた。
「年は、たしか十四と申しておりました」
「まず、女中部屋を拝見したいですね」
虎之介は、三津枝に目をやる。
「ええ、もちろん。案内してちょうだい」
使用人が先導し、三津枝と虎之介は屋敷の奥へと歩んだ。
「その女中は、どなたかの紹介でお雇いになったのでしょうか?」
「いいえ。先日、銀座へ参りました時、はじめて行き合いました。話を聞いたら、勤め先を解雇されて住むところにも困っているとか。若い娘の身です。気の毒に思ったものですから」
三津枝は、あたり前といったふうに言葉を重ねる。
「三津枝さん。それは随分と、ご奇特な為さりようですね?」
「そうかしら? 私はこの間、教会の集まりで神父さまのお話を聞きました。富める者は、貧しい者へ施すのが道理だとか。そう伺いましたけれども?」
首を傾げ、三津枝は思案していた。
「そういえば、最後に供を頼んだ女中はナツでしたわ。おまえも覚えているわよね?」
三津枝が女中へ声をかける。
「そうだ、そうです! ええ! 二日前の晩でした。翌日、小切手帳の収支を銀行の方が調べにいらして。……それじゃ、まさか」
「どうして忘れていたのかしら? うっかりしていたこと」
三津枝の言いように虎之介は、返す言葉がなかった。
帝都の花といえば、カフェーなる遊興施設である。しかし、まだ夕刻にさしかかったばかりだ。虎之介は蕎麦屋の一角で杯を重ねている。向かいに座しているのは大柄な中年の男だ。背中を丸める姿勢の悪さが、男の風采を下げている。
彼の名は守宮要と言った。こう見えても天下の帝国ホテルのお抱え探偵である。
「そいつは大変な女傑だな」
守宮は吹き出していた。
「笑い事じゃないぜ。俺は大いに辟易したよ」
「人間だと考えるから腹が立つ。札束の山だと思って堪えるがいいぜ」
襖が開く気配に虎之介と守宮は顔を上げる。奥座敷のほうから着物姿の少女と男が出て来た。風呂敷を抱えた少女の年は十四、五だろうか。先を歩く男に置いていかれまいと必死だ。
男は洋装に咥え煙草、上着を肩へ担いでいる。金のかかった服装ではないが、物馴れたふうで堂々としていた。それが男の容姿を一段、優れたものに見せている。
「誰だ、あいつ? 見ない顔だが」
男の背中を見送って虎之介が口を開いた。
「へえ。虎が知らないとはね。この辺りは、ご無沙汰か? 随分、稼ぎが立て込んでたんだな」
守宮は銚子を盃へ傾ける。
「あいつは女衒らしいぜ」
「らしい?」
掏摸、物乞い、女衒には、それぞれ『元締め』というものがあった。彼らが職域を司っており、手前勝手に商売はできない。
「ああ。だが、女に商売させてるところを誰も見たことがねえんだ」
「それじゃあ、どうやって稼いでる?」
「そこが謎だ。置き屋出入りの連中はもちろんだが、街娼だって表通り、裏通り逐一、縄張りが決まってる。断りなしに女を立たせたら、血の雨が降るだろうに」
元締めへ稼ぎの一部を納めなければならないのだから死活問題だ。
「どこかへ楼でも構えてるのか?」
「それにしたって、客を案内しなけりゃ話にならない。しかし、あの野郎。客引きもしないんだとよ」
では、声をかけた少女たちに何をさせているのか。
「名前は?」
「花井健二って言ったかな。大方、親から授かった名前じゃなかろうぜ」
守宮の言葉に虎之介は頷いた。
「記憶喪失?」
角帽に袴姿の青年が首を捻る。
「お気の毒でなりませんわ。きっとひどく叩かれたせいに決まってます。あんなに悪い男の方がこの世にいるなんて!」
雪江は憤慨頻りだ。ここは雪江の父親、星見辰一郎の邸宅である。大理石の床に二人の影が寄り添い、揺らいでいた。
「……それで、星見教授は、何とおっしゃっていたんですか?」
青年は幼い婚約者の顔を伺う。彼の名は戸山高志、帝大へ通う医学生だ。天文学者である星見辰一郎の屋敷に詰める書生でもある。西洋人に引けを取らない大きな体に知恵を備えた丈夫であった。
「父が不在の間は、女主人として恥ずかしくない振舞いをするよう言いつかりましたわ。それから、あの方を客人として家に迎えても構わないと許可をくれました」
得意満面な様子で雪江は言葉を続ける。
「それだけですか?」
「後は、その。……これは、本当にもしもの場合ですけれど」
雪江はバツが悪そうに高志を見上げた。
「喜代が『どうしても』と言うことがあったら、どんなことでも絶対に従いなさいって」
「それで安心しました。では、そのお嬢さんに挨拶できるでしょうか?」
「それが、あの方。お医者様が苦手で。私、うっかり高志さんのことを医学生だと話してしまったものですから」
高志が顔をしかめる。
「まさかとは思いますが、きちんと医者に診せていないのですか?」
「……はい。でも、すごく怯えていらっしゃるんですもの。かえって病状が悪くなってしまう気がして。それに怪我のほうは心配ないと思いましたし」
思案している高志に雪江は言い募った。
「二、三日、様子を見ましょう。但し、その方が落ち着かれたら必ず診察を受けていただきます」
「はい! 心配なさらないで。私も同じ心積もりでしたもの」
廊下を歩む雪江の足取りは軽い。高志は、不安な面持ちで彼女を見守っていた。
INDEX PREV NEXT
2 notes
·
View notes
Text
魔女の子 4
校門を出たマークは肩で息を吐いていた。校舎のほうから銃声が聞こえてくる。
「どうしよう?」
マークの言葉に三人は顔を見合わせた。
「……コンウォールさんだったよね? 銃を持ってたけど、でも」
ジェイコブが記憶を手繰る。逡巡していた三人は襟首を掴まれた。
「こんな夜中に何やってる?」
保安官助手のポールの後ろで星形の金バッジを胸につけた男が顔をしかめている。スモールビルの保安官、ロン・スピーグルだ。上半身の隆起した小山のような体躯が大地を踏みしめている。
「ねえ保安官。俺の言った通りでしょ? 銃声なわけないですよ。おおかたバックファイヤかなんかに決まってますって」
納得がいかないのかロンは、口を一文字に閉じていた。
「違うよ! コンウォールさんが!」
「大変なんだ!」
「二人とも殺されちゃう!」
マークたちは一斉に話し出す。再び銃声が、その場にいる全員の耳を叩いた。校舎の入り口から人影が飛び出してくる。女を抱えるようにして走っているアーサーとショットガンを構えたロナルド・コンウォールである。
「コンウォール? 何をやってるんだ、あの爺さん」
ロンは追われている二人と男へ目を凝らした。
「そんなわけないって思いますけど、アーサーと黒人の女の子をコンウォールさんが撃とうとしてるみたいですよね?」
のんびりしたポールの口調に我慢できず、マークは声を上げる。
「だから、そうなんだってば! 何とかして。殺されちゃうよ!」
「……ポール。俺のライフルを持ってこい。早く!」
ポールは、慌ててパトカ��の前部座席からライフルを掴み���した。受け取ったロンは照星を合わせ、引き金をひく。続いて二発の弾丸を足元へ撃ち込まれ、面喰ったロナルドは立ち止った。
「コンウォールさん。保安官のスピーグルです。そのまま動かないでください。俺がそっちへ行きますから。いいですね?」
安心したのだろう。女とアーサーは地面に倒れ込み、息も絶え絶えである。ロナルドだけは突っ立ったまま、近づいてくるロンを睨んでいた。
ショットガンを取り上げられ、ロナルドは地面へ唾を吐く。
「ロン・スピーグル。おまえが寝小便を垂れてた頃から知ってるぞ。バッジをつけたからって偉くなったつもりか?」
ロンはポールにショットガンを渡し、ロナルドへ顔を向けた。
「コンウォールさん。違います。俺がバッジをつけてるのは、俺が保安官だからで、そのことを他の人にも知ってもらう必要があるからです。さっきみたいな時のためにね。別に偉く思われたいからじゃありません」
「口では何とでも言える」
掌を天に向け、ロンはロナルドを眺めている。
「それより、夜中に学校で何をしていたのか教えてもらえますか?」
ロナルドは顔を背け、黙っていた。自分の帽子の縁を下げ、口を曲げている。
「アーサー。おまえはどうだ?」
「……銃の暴発です」
息子の言葉にロナルドの表情は明るくなった。アーサーの傍らで俯いていた女も顔を上げる。
「暴発? コンウォールさんは、おまえに銃を向けて、追いかけまわしていたように見えたがな?」
「父は、事故で気が動転していたんだと思います。それだけです」
アーサーは、ロンを真直ぐに見返していた。
「『事故』ねえ。コンウォールさん。そうなんですか?」
「そうだ。息子の言う通りで間違いない」
マークの抗議が上機嫌で話していたロナルドの言葉を遮る。
「違うよ! あの女の人を撃とうとしてたじゃないか!」
指さされた女は顔を伏せた。
「見たよな?」
振り返ったマークに答えず、ロイドとジェイコブは俯いている。
「なんで黙ってるんだよ?」
「誰かと思ったら、アップルトンの倅じゃないか?」
ロナルドはジェイコブの顔をまじまじと眺めた。
「どうした? 親父の雇い主に挨拶しないのか?」
「……こんばんは」
ジェイコブが裾をズボンに押し込みつつ、小さな声で答える。
「そっちの眼鏡も見た覚えがあるぞ? 雑貨屋の御用聞きだろ?」
「……あの。ええと、はい」
言葉少ななロイドからロナルドは、マークに視線を移した。
「おまえは見かけない顔だが、なんて名だ?」
「……マーク・ビアスだけど」
ロナルドは、首を捻っている。
「ビアス?」
腹立たしさでマークは我慢ならなかった。
「父さん。止めてくれ。まだ子供じゃないか」
マークが言い募るより早く、アーサーが割って入る。
「この子の言うことは本当かい? コンウォールさんは、あんたを撃とうとしたって話だが?」
ロンに尋ねられ、女は戸惑っていた。
「……わかりません。暗かったし、ビックリしてしまって。でも、私。アーサーさんと旦那さんのお話が正しいんだと思います」
胸の前で手を握り、アーサーの顔を伺っている。
「おまえたちは、どうなんだ? マークと同じ意見なのか?」
ロイドとジェイコブに向けてロナルドが目をすがめた。
「……暗くて、よく見えなかった」
「うん。ちょっと見ただけだから」
二人は顔を見合わせている。
「当事者が事故だって言うなら、俺がすることはない。引き上げてもらいましょうか」
言い渡すロンをロナルドは睨み返した。
「俺の銃は?」
「暴発なんでしょう? 調査のために預からせてもらいます。整備不良かもしれないし、その場合は罰則があるかもしれません。はっきりするまで、銃に触るのは遠慮してください」
アーサーは悪態を吐いている父親を促す。
「父さん。帰ろう」
息子の背中に隠れるように立っている女にロナルドは言い放った。
「マリア。おまえはクビだ」
うなだれている女だけが、その場に取り残される。
「送ってやる。みんな車に乗れ」
マークたち三人は、パトカーの後部座席に乗り込んだ。
「あんたも乗ってくれ」
ロンはマリアに声をかける。
「……いいえ、そんな。坊ちゃんたちと一緒だなんて。いけません。私は歩きます」
落ち着いた柔らかい声が夜闇を流れた。マークは月明かりの中に佇んでいるマリアを眺める。
「そうか。気をつけて帰れよ」
「はい、ありがとうございます」
運転席にポールが座り、ロンは助手席に尻を載せた。
「すごく綺麗な娘だったなあ! まるで黒いビーナスだ。ねえ保安官」
ロンは頷きながら、閉じた口の端を下げている。
走りだす車をマリアは見送っていた。マークは何の気なしに小さく手を振る。それに気付いたマリアは最初、驚いた顔になり、次の瞬間には微笑んでいた。
「保安官。ぼくの話は本当なんだ。本当にあの小父さんは、女の人を撃とうとしてたんだ。信じてよ!」
ロンは後部座席のマークへバックミラー越しに目をやる。
「でも、他の二人は見てないんだよね? コンウォールさんもアーサーも銃の暴発だって言ってたし。見間違えじゃないかな?」
運転席からポールが口を出した。
「……それは」
マークの目が隣に座るロイドとジェイコブへ向けられる。二人は居心地悪そうに身動ぎしていた。
「もういいよ! わかってる。ぼくが子供だから信じないんだろ?」
ロンは後部座席を振り返る。
「それだけじゃない。同じ時間に、同じ場所で、同じものを見たはずの三人の話が食い違ってる。信用しろと言われても無理だ」
黙り込んだマークを夜が静かに包んでいた
INDEX PREV NEXT
0 notes
Text
魔女の子 3
裏庭は小さな農園になっている。用務員のジョンソン老人が手入れをしている畑だ。今年の収穫はほぼ終了し、盛り返された畝は黒々としている。
「何が木の幽霊だ。よく見ろ!」
かつては大木だったのだろう。マークは、切り株状に焼け残り、炭化した樫を指さした。
「おかしいなあ。そんなはずないんだけど」
さすがに弱気になったジェイコブに畳みかけようとマークは口を開く。しかし、その時、灯りが点った。裏庭に面した校舎の窓から光が漏れている。
「……誰かいるのかな?」
ロイドの呟きに三人は顔を見合わせた。
「間違いない! 魔女の子だ。だって、火を操れるんだから」
「火を操る?」
ジェイコブもロイドも真剣な顔で頷いている。
「……わかったよ。行こう」
三人は、窓から校舎を覗き込んだ。廊下に細い影が立っている。三人へ背を向ける格好で手にはランプを持っていた。白いドレスをまとった女である。
女は、廊下の向こうの闇を伺っていた。体の向きを変え、ランプを高く掲げた女の顔が露わになる。その美しさにマークは呆気にとられた。
縮れた黒髪に包まれた柔らかな頬の線、褐色の肌は内側から輝きを放っているようである。だが、明るい茶色の目は不安そうに伏せられていた。長い睫毛が目元に影を落とす。
彼女は、有色人種の若い女であった。褐色の美女に圧倒され、三人は息をのむ。
「マリア!」
沈黙を破って、低く男の声が響いた。乗馬ズボンをはいた若い男がランプの光に照らし出される。男を目にした女は笑顔になった。
「待たせてごめん。母さんがうるさくて。一人にしてくれないんだ」
女は頭を振り、男に抱きつく。男の腕が女の背中へ回り、彼女を強く抱きしめた。二人はキスを交わしている。
「……あれ。コンウォールさんのところのアーサーだよね?」
二人へ目を向けたままロイドは呟いた。コンウォール家は、広大なトウモロコシ畑を有する地主である。出自の富裕だけではなく、神はアーサー・コンウォールに白い肌を与えていた。彼はマークたちと同じ『白人』だったのである。
「なんで黒人女と?」
ジェイコブの言葉がマークの頭に天啓のように閃いた。『魔女』の身の上に起こった因縁が解き明かされる。彼女がなぜ子供の父親の名を口にしなかったのか。しかし、ゆっくりと思索している時間はなかった。銃声がマークの戸惑いを吹き飛ばす。
「息子から離れろ! このアバズレめ!」
初老の男がアーサーと女に向かい、ショットガンを構えていた。
INDEX PREV NEXT
0 notes
Text
魔女の子 1
三幕構成でプロットを組み、冒頭の第一幕(原稿用紙約30枚)を具体化したものです。世界観と主な登場人物の説明をしています。第二、三幕の具体化については未定(全体で120枚程度になると思います)。
======
INDEX PREV NEXT
0 notes
Text
幕間雑感「ウィズネイルと僕」
2014年に見た映画について書く。
ネタバレがあると思うので未視聴の映画の場合は、勘案いただき、ご賢察を仰ぐものとする。
売れない役者である主人公は、夢が破れかけている事実から目を背けていた。酒と薬に溺れる自堕落と困窮の日々である。
現状に嫌気がさし、同居人ウィズネイルの裕福な叔父から別荘を借りて週末の旅行を目論むが。
三十を前にした主人公と同居人のモラトリアムの終焉。
特に何も描かれていない映画。主人公の成長もないし、事件が起こるわけでもない。しかし、面白い。
汚らしい部屋の風景がとても懐かしい。子供の頃の秘密基地にあったような独特の雰囲気だ。まだ異性の存在が希薄で��ばかりという空間である。とはいえ、彼らは既に二十代後半なのだが。
この映画は監督の自伝的な作品だが、時系列や人間関係は事実に沿っていない。おそらく監督の記憶により近い形で再現したものなのだろう。事実と記憶は異なっているものだ。
ラストに一人残されるウィズネイルの佇まいが素晴らしい。
実際は、主人公の側である監督が取り残された。考えれば当然だが、実家が富裕なウィズネイルはモラトリアムを過ぎれば、自分の階級に戻っていくだけである。何の憂いもないわけだ。
途中、主人公がウィズネイルの叔父、モンティに肉体関係を迫られるシーンがある。これは監督が助監督時代に遭ったエピソードを持ってきたものらしい。事実だけあって、ちょっと思いつかないような切り抜け方をしている。
評判の作品で気になっていたのだが、なかなか機会を得ないでいた。映画を見てきて良かったなと思わされる作品である。
0 notes
Text
蛋白石 一話
『but of such purity and radiance that it twinkled like an electric point in the dark hollow of his hand.』
コナン・ドイル著 シャーロック・ホームズの冒険「青い紅玉」より
少年少女たちが謎の男に遭遇すること
大正十二年、帝都を見舞った大地震という災いは、麗しい都を瓦礫の山へと変貌させていた。数カ月の後も復興は表層に留まり、貧富の差はますます顕著である。
二束三文で売春を行う街娼で通りは溢れ、物乞い、盗みを働く震災孤児の群れが富貴の目を煩わせる。そこから顔を背けるように日本という国は薄暗い道程を歩もうとしていたのであった。
承知した石川虎之介に星見辰一郎教授は安堵の息を吐く。しかし、すぐにすまなそうに、こう言い足した。
「虎之介君。留意してもらいたいんだが、老いと病が彼女を非常に辛辣な人物にしている。出来得る限りで構わない。なるべく寛容に願いたいんだ」
四十を迎えた辰一郎の顔に憂いが浮かぶ。
ここは天文学者、星見辰一郎の私邸だ。洋館の聳える庭の一角に離れがあり、虎之介は、そこを事務所兼住居として貸与されている。
「ご心配なく。寛容なら売るほど持ち合わせがあります」
答える虎之介は三十半ば、辰一郎にとっては年若い友人であり、私立探偵でもあった。
「引き受けてくれて感謝する。本来は、私も出向くべきなんだ。しかし、今は観測所のほうが立て込んでいてね。どうしても外せない」
辰一郎は、夜空の星の虜囚である。彼の生活のすべては天文学の躍進のために捧げられていた。
「失せもの探しは大の得意です。どうぞお任せください」
虎之介の言葉にようやく笑顔を見せ、辰一郎は離れを後にする。
「本当に入るの?」
真田平太は友人である金田一男の顔を伺った。
「あたり前だろ。それでわざわざ来たんじゃないか?」
中学校の制服を着た少年二人の前に半壊した洋風建築が聳えている。震災の衝撃で崩落し、そのまま打ち捨てられていた。
「怖いの? 平太は弱虫だなあ」
一男に揶揄され、平太は気色ばむ。
「違うよ! 勝手に入ったら、良くないから。ここって私有地だよね?」
「誰もいないんだぜ。良いも悪いもないよ。それに見張りだっていないし、咎める人なんかいないだろ?」
崩れた壁の隙間から一男は敷地内へ体を滑り込ませた。その背中に平太も続く。近付けば、屋敷の惨状は明らかだ。しかし、かつては美しい建築物だったに違いない。
「……どうして直さないのかな?」
西洋の鬼瓦とでも言うべき大理石の獅子が土の上に身を横たえていた。屋敷は火災に見舞われたのだろう。周囲に雑草の姿はない。
「壊して建て直すより、新しく建てたほうが安いからだって父さんが言ってた」
一男の父親は、一代で富豪にのし上がった立身出世の人物だ。
「そうなんだ」
損得勘定は非情である。寂しい心持ちになり、平太は一男と並んで庭を歩いた。
「たしかこっちだよ。風見鶏のある屋根の下の部屋だってさ」
瓦解しかけた屋根の切っ先に傾いた銅製の雄鶏が屹立している。
最近、平太の通う中学校では、この屋敷の話題で持ち切りだ。何でも白いワンピースを着た女の幽霊が現れるという噂である。
「幽霊なんているわけない。あいつら臆病だからカーテンでも見違えてるんだ」
一男は端から幽魂狐狸の類を信じていなかった。
「……うん」
「何だよ。平太まで幽霊が出るって言うのかよ。科学的じゃないなあ」
「そうじゃないよ!」
この世には人間の想像を超える恐ろしい何かがいる。数カ月前、平太は、それを知ってしまった。だからこそ、こんな幽霊話さえ一笑には伏せないのである。
「……そうじゃないんだけど」
二人は件の部屋を窓から覗いた。火事に見舞われたらしき室内は壁紙が焼け落ち、扉は打ち壊されている。無残ではあるが、何ら変哲はなかった。
「何もないぜ。ここから見てても埒があかないよ。向こうへ回って中へ入ろう?」
つま先立ちになっていた平太と一男の肩が叩かれる。悲鳴を上げる二人の背後で柔らかい笑い声が起こった。
「何て声出すのよ、もう!」
耳を塞いでいるいち子の横で星見雪江が微笑んでいる。金田いち子は、一男の二つ違いの姉だ。一方、雪江は星見辰一郎の一人娘である。平太にとっては苦楽を分かち、ともに脅威と立ち向かった友人でもあった。
話してみると雪江といち子も幽霊見物に訪れたという。屋敷の噂は女学校にまで届いていたのだった。
「本当に出るのかしら? わくわくしちゃう。ねえ雪江」
「……ええ」
女学校の制服に身を包んだ雪江は言い淀んでいる。
「バカだなあ。幽霊なんかいやしないよ」
雪江は一男の言葉へ簡単に頷けなかった。彼女もまた、平太と同様にこの世ならざるものを目にしていたからである。
「バカとは何よ! それが目上に向かって言う言葉なの!」
即座、いち子に頭を叩かれ、一男は唸っていた。
「すぐ暴力を振うの止めろよな!」
吹き出す平太と雪江の耳に足音が響く。部屋の右手にある破砕された扉から少女が入ってきた。紺色の綿の着物に赤い帯を締めている。大家の使用人という風情だ。あちらこちらへ視線を遊ばせながら大事そうに襟元へ手を添えている。
思い詰めた顔で暖炉の前に佇んでいた。
「ただの女の人だ。幽霊じゃないぜ」
呟いた一男は三人に睨まれ、沈黙を促される。仕方なく一男も口を閉ざした。四人は再び、窓から室内を覗き込む。
続いて入室してきたのは中年の男だ。笑顔になった少女の様子から何れ逢引きかとも考えられたが、彼女は何事か呟く男に顔を曇らせ、俯いている。男の右手が上がり、少女の頬を平手で叩いた。少女の体は床へと倒れる。
「止めて!」
思わず、雪江が声を上げた。少女のほうへ屈み込んでいた男が雪江に顔を向ける。
「友達が巡査を呼びに行ったんだ! すぐにやってくるからな!」
平太は機転を利かし、男へ向かって叫んだ。男は真偽がわからず、迷っているようである。
「お巡りさん! こっちだよ! 早く、早く!」
「女の人が乱暴されてます!」
すぐ近くに巡査がいるように一男といち子は背後を振り返った。男は舌打ちしつつ、その場から逃げ去った。
「あー。恐ろしかった」
いち子は肩で息を吐く。平太、一男も額の汗を拭っていた。
「あの方。大丈夫かしら?」
雪江に促され、四人は入口へ急ぐ。部屋に踏み入った四人の前で少女は依然、倒れ伏していた。
「起きられますか?」
雪江は声をかけるが、返事はない。いち子も手伝い、少女の体を仰向けさせた。そのしな、少女の着物の襟元から丸いものが転げ落ちる。
「何かしら?」
いち子は首を傾げた。それはウズラの卵ほどの大きさの乳白色の石である。桃色を帯びた掌に蹲り、内側から虹色の輝きを放っていた。
「卵? この人が生んだのかな?」
一男の言葉を聞いたいち子は柳眉を逆立てる。
「バカね! 人間が卵を産むわけないでしょ!」
にべもなく一男を叱りつけた。二人のやり取りに雪江と平太は吹き出す。しかし、雪江はすぐ真面目な顔になった。
「余程、ひどく叩かれたのね。可愛そうに。でも、大丈夫。気を失っていらっしゃるだけですわ」
少女の容態をつぶさに眺め、雪江が宣言する。彼女には帝大生の婚約者譲りの医学知識があった。
「良かった。さっきの男が引き返してくるかもしれない。雪江さん。この人をどこかへ避難させようよ」
平太は、雪江へ顔を向ける。
「そうね。では、手を貸してください。私の家まで運びましょう!」
雪江の号令に三人は頷いた。
INDEX PREV NEXT
1 note
·
View note
Text
カエル堂の活動写真ご案内
http://matome.naver.jp/odai/2138090241404656101
イケメン寄りのミステリー・サスペンス映画のご紹介。
0 notes
Text
折本を作ってみた
【ニコニコ動画】【新刊ご案内】貸本屋カエル堂【折本】
◆USBのデータをコンビニで印刷することも可能です。 http://goo.gl/rpLta
0 notes
Text
あにきといっしょ
これが上手くできたら「ひとりでできるもん」もノベルゲームのインターフェイスでやりたい。
そうすれば途中でセーブしてもらえるし、いろいろ楽なはず。
シナリオの穴は見えやすくなるだろうけど。
0 notes
Text
使用ツールとかとか
ティラノスクリプト http://tyrano.jp/
Aviutl http://spring-fragrance.mints.ne.jp/aviutl/
クラシック名曲サウンドライブラリー http://classical-sound.seesaa.net/
SOUND JAY http://www.soundjay.com/
0 notes
Text
ががが概要
原案はあるので内容はぼんやり決まっている。
雪江と平太が前面に出る感じで虎之介や高志はサポート役。
いつもと同じである。
ゲームを遊ぶ方には銀次の貸本屋で働いてもらおうと思う。
0 notes