Text
リンダ・レ『キャリバンのコンプレックス』――翻訳で読めないフランス小説4.
*
読書家は誰だって、想像上の書物について思いを馳せたことがあるはずだ。子供の頃、まだ読んだこともないし、読むこともできない本の背表紙を前にして、未知の物語が込められた魔法の壺が並んでいるかのように考えていた。そうした思いは、後年、外国語を学習する際に再び現れる。読めない文字列を前にして、神秘的なものを前にしたかのようなめまいに襲われる。そう、書物にも外国語にも、理解の有無を越えたフェティシズムが存在する。
こんな誰もが一度は考えたことがあるであろう考えに寄り添ってつづられた1冊の書評集が存在する。その作者の名前はリンダ・レ。惜しくも2022年に亡くなった、ベトナム生まれのフランス語作家の女性だ。
1963年にダラットに生まれた彼女は、驚くほどの読書家だった。その事実は、この『キャリバンのコンプレックス』の頁を繰ればすぐにわかる。そんな彼女の書物へのフェティシズムは、子供時代に既に始まっていた。「印刷物」と題された魅力的な一篇では、小遣い稼ぎのため、魚屋に古新聞の束を売っていた頃のことが語られるが、そこには既に書物を神聖視していることがうかがわれる記述がある。
《魚を包むのに使おうとしていたケチ野郎たちに古新聞を売りつけた時、一時的でちっぽけなもうけのために聖なるものを売ったシモン・マグスのように、私は罪悪感を感じたのだ。なぜなら、言葉はたとえそれが使い古されたものであれ、聖なるものにみえたからだ。》
リンダ・レは、子供時代からずっと書物と文字を聖なるものと考えていた。そして、多くの読書家たちと同じように、彼女にとって読書は現実逃避の一手段でもあり、自らの創造の出発点だった。次々と世界の書物を読破して、理想の書物を待ち焦がれていた彼女が、自ら書物をつくるようになるのは必然的なことだったのだろう。
《読者家なら誰だって、自分の書棚に理想の書物、行間を読む書物を持っている。読書は、自由が最も保たれる想像の空間であるにちがいない。なぜなら、作家たちは読者にある種の共同の創造を要請する一方で、たとえペンを取らないとしても、ページの間に入り込み、書かれた書物の背後に、自分が書きたいと思う書物を読みとる可能性も残しているからだ。》
まるで〈バベルの図書館〉への滞在体験のように語られる読書体験。彼女の読書観には単なる誤読を越えた、来たるべき創作への意志、創造的な行為への肯定に溢れている。子供時代の読書は「空想の口実だ」とまで書く彼女の書評には非常に私的な体験のパッセージが多く散らばっている。書評を読んでいるはずなのに、私小説を読んでいるかのような気分にさせられるのも、彼女の書評の魅力のひとつである。
*
しかし、彼女がこれほどまでに読書に渇望し、書物にフェティシズムを感じるのは、単に美化されたノスタルジックな想いゆえではない。彼女がフランス語で書くことになったのは、ベトナム戦争の惨禍から逃げるために、思春期にフランスへ移住したからだ。
あるエッセイでは、悲惨な子供時代の思い出が語られている。サイゴン陥落後、外国文化を禁じるお達しが出ると、妹は『Oui-Oui』(フランスの有名な絵本)を捨てることになる。詩を愛し、自らも詩を書いていた姉は『金雲翹』を手放し、リンダ・レ自身は『レ・ミゼラブル』を手放した。母はエヴィルスやビリー・ホリデイのレコードを捨てて、父は聖書以外の書籍を持たなくなったという。共産主義により、書物と外国文化を家族で手放した体験があるからこそ、彼女には書物への神聖視があり、「ここにはない書物」への愛があるのだろう。
*
彼女は常に根無し草の感覚を抱いていた。フランスにもベトナムにも故郷を見出せず、自らを『テンペスト』のキャリバンにたとえている。自分はフランス語作家なのか、ベトナム出身のフランス語作家なのか、フランス語を用いるベトナムの作家なのか。こうした問いは、彼女から終生離れることがなかったようだ。
《育ったのとは別の言語で書くことを選んだ作家は、キャリバンがプロスペローに服従したように、この別の言語との関係を経験する。師匠の道具に誘惑され、プロスペローが到達した芸術の頂点に達したキャリバンみたいになりたいと願っている。しかし、この後天的な言語と文化への自らの憧憬は、政治的な意図を帯びている。フランス語で書くことを選んだ亡命作家は、キャリバンのコンプレックスに苦しんでいる。自らの言語への献身は、異端さと混ざり合っているのだ。》
フランス現代思想の隆盛以来、移動(ノマド)や多言語使用は肯定的なものとして捉えられてきた。だが、そうした行為の背後には、常に政治的・社会的な背景が潜んでいる。だから、リンダ・レの文章には、ノマド/多言語使用への単純な讃美は存在しない。そして、彼女が好む作家たちは、どこか憂鬱さを抱えている――マリオ・デ・サ=カルネイロ、ウィルキー・コリンズ、ベンヤミン、カフカ、レオニ・ド・アンドレーエフ、シオラン。
もしかすると、そんな作家たちに彼女は自らを重ねていたのかもしれないと思う。とりわけ、これらの作家たちに亡命を経験した作家が多い場合には……。しかし、それでも、リンダ・レが2022年まで生きてくれたことを嬉しく思う。まだほとんど知られていないこの女性作家が残してくれた文庫たちは、〈図書館〉で私たちが未来の読者となることを待ちわびているのだから。
【今回の書籍】:Linda Lê, Le complexe de Caliban, Christian Bourgois, 2005.
【注】:今回の書籍は書評集なので小説ではないのだが、作者の私的な思い出が多く語られているため取り上げた。
0 notes
Text
エドゥアール・ルイ『ある女の闘いと変身』――翻訳で読めないフランス小説3.
子どもの��、母親が学校での面談に参加しないように手を回していた。他人に自分の母親を知られるのがいやだった――そんな感情の想起から始まる小説だ。前回取り上げた同作者の『誰が僕の父を殺したか』は作家の父親について語ったものだったが、今度は母親について語った作品だ。
語り手の母親モニックは、長らく彼にとって敵だった。作者のセクシャリティに無理解を示し、父親の暴力に反抗もせず屈しつづけていたからだ。だが、ある日、彼は一枚の写真を発見する。一人の若い女性の顔写真。スマホもない時代にカメラを裏返しにして撮ったせいで、少し近づきすぎな感じもする。この写真は30年近く前の彼の母、モニックの写真であり、彼はこの写真を通じて彼女の半生と向き合いはじめる。
*
家族のために働くばかりで、スーパーと家を往復するだけの日々を送っているように見える彼女にも、かつては夢があった。彼女は調理師になることを望んでいたのだが、不覚にも妊娠し退学。そして出産を経験する。このパートナーが暴力的であり、その状況から抜け出すために別の男と暮らしはじめるが、また妊娠と出産を繰り返すことになり、さらにはこの男も暴力的だった。彼女の前半生は諦念ばかりが蔓延していた。
《彼女は自らの人生から事件を奪われていたから、僕の父によってしか事件は起こりえなかった。彼女は物語をもはやもっていなかった。彼女の物語は、必然的に、僕の父の物語でしかなかったのだ。》
そうして子供と男性の世話に支配された日常を送ることになるモニックという一人の女性が、アンジェリックという女性と出会い友情を結び、自立と自由を見出していくまでの物語だ。男や子供に従属しているだけだと作者が思い込んでいたモニックは、最終的に旦那を捨ててパリに出て、新たな自分の生活を始めることになる。それは彼にとって、信じがたいほどの変化を彼女にもたらすことになる。マニキュアをして、美容室に行き、高級ホテルのバーで大人になった語り手と杯を交わす。そんな姿は、かつては想像もつかないものだった。
《僕は母が家庭で不幸なことに見慣れ過ぎていたから、母の幸せそうな表情が、一刻も早く暴かなきゃいけないスキャンダルみたいに、詐欺みたいに、嘘みたいに思えた。》
だが、月日が経つことにより「変身」するのはモニックだけではない。語り手の感情も「変身」していく。たとえば、親元を離れて都会の高校に通うことになった語り手は、ある時、高校で知った難しい言葉を母親に対して使う。それにフランス語の活用の過ちを正そうとする。しかし、そうした振舞いは彼女を苛立たせるだけだ。そんな過去の振舞いを振り返り、「ごめんなさい」と謝罪の言葉を物語の中に作者は書き込んでいる。
*
こうした物語は、既にこれまでの作品でも部分的に語られてきたことである。読者はまたこの話か……と思うかもしれない。しかし、作者にとって重要なのは、何度も語りなおすことで可能なかぎり真実に近づこうとすることだ。だから、エドゥアール・ルイはオートフィクションしか書かない。同じ主題を描きつづける画家のように、同じストーリーを語り直しつづける。作中にもこんな一節がある。
《文学は繰り返してはならないと言われたが、僕は同じ物語しか書きたくない、何度も何度も、真実の断片が見えるまで書きつづけ、背後に隠されたものが現われはじめるまで、その物語に穴を穿つことを望んでいる。》
*
ところで、この小説のもっとも興味深い点は、その文体の駆使にある。エドゥアール・ルイという作家は文体について、インタビューで次のように述べたことがある。
《今日でも多くの作家が、ゾラやバルザックのものであった〈美〉や〈文学〉のイメージを保持していますし、対話、比喩、文体の偉大さ、章、登場人物といった形式の中でできる限りのことをしようとしています。これが受け入れられ確立されている文学の定義であり、作家の仕事は、この定義された枠組みの中で可能な限り秀でることなのです。》
上で挙げられているような伝統的な文学の規範に則ることを、もちろんルイは良しと思っていない。そんな規範はブルジョワ的な文学のものでしかない。この対談で、彼は簡潔で直截的な文体の使い手である��ニー・エルノーを褒めたたえている。
だがそれならば、エドゥアール・ルイの文体とはいかなるものなのか。いかにして、伝統的な規範と異なるのだろうか。そして、このことは、「アニー・エルノー以後には、彼女と同じように書くことはできない」と宣言しているだけに気になることでもある。作家による規範からの逸脱がよくわかる一節を『ある女の…』から引用しよう。
主人公の母親が、アンジェリックと疎遠になったことを示すシーン[「あなた」は、母親を指している]。
《しばらくして、パン屋からの帰り道で、あなたは彼女とすれ違ったが、彼女は挨拶をしてこなかった。あなたはため息をつき、目を伏せて、凝り固まった表情だった。彼女はわたしに挨拶すらしてこなかったのよ。理由が分からないわ、わたしたちって友達だったよね?》(強調引用者)
本書では、「私(Je)」は基本的に語り手を指しているものの、時おり憑依するように、別の人物を指し示すことがある。その一例が太字で強調した部分だ。つまり、テクストの中に鍵括弧のついていない直接話法が改行もなく混ざることにより、読者はより直接的に各登場人物の発言・心内語にアクセスすることができるようになっているのだ。
こうした効果をもたらす表現技法は、フランス語にはもちろん既に存在して、自由間接話法と呼ばれている。しかし、自由間接話法は一見すると地の文と似ているために、気づかずに素通りしてしまうことも多い。逆に言えば、地の文のように紛れ込んだ自由間接話法は、見た目としても違和感がなく美しい。しかし、誰もが自由間接話法に気づけるわけではない。
だが、エドゥアール・ルイは、大文字と「わたし(Je)」を文中に突如挿入して、歪な文体になろうとも、文中の直接話法という文体を用いている。それは、あらゆる読者に登場人物の声を聴きとらせる企てとなり、伝統的な〈文学〉の〈美〉を破壊する。
そうして、真のブルジョワ的ではない文学を、文体のレベルにおいても実現させようと試みているように思えてくるのだ。
【今回の小説】:Édouard Louis, Combats et métamorphoses d'une femme, Seuil, 2021.
0 notes
Text
エドゥアール・ルイ『誰が僕の父を殺したか』――翻訳で読めないフランス小説2.
*
文学界のグザヴィエ・ドランとでも言える新星がフランスに登場した。男性同性愛者を取り巻く社会状況を、スタイリッシュな文体で記す91年生まれのその作家の名は、エドゥアール・ルイという。
21歳で『エディーに別れを告げて』という衝撃的な内容のオートフィクションでデビューした彼には、献辞をグザヴィエ・ドランへに捧げ、タイトルも『マイ・マザー J'ai tué ma mère』のオマージュのような短い小説がある。今回はその小説、『誰が僕の父を殺したか Qui a tué mon père』を紹介したい。
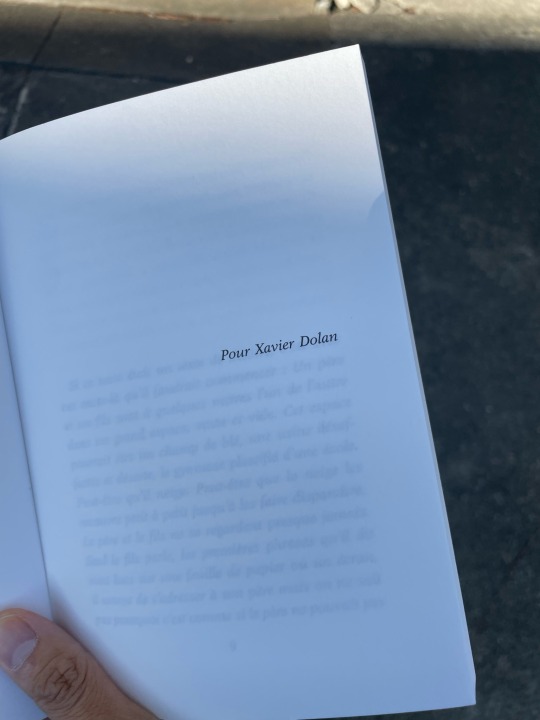
*
物語は非時間的で、思い出すままに語り手の父親への想いが呈示される。現在、50歳の父親は妻に捨てられて、フランスの田舎で暮らしている。まだ中年と言って���いはずの彼は、酸素吸入器なしでは生きることもできず、歩行もままならない。彼がそんな風になってしまったのは、長らく働いた工場で、重機落下の事故に巻き込まれたせいだ。
若き日の父親は家族に頻繁に暴力を振るい、彼のセクシャリティ――語り手はゲイである――を全否定してきた。この父親にとって何より大事なことは、タフに、男らしく生きることだ。子供時代の語り手がクリスマスに『タイタニック』のVHSを欲しがれば、「あんなのは女のものだ」と否定する。ホームパーティで女の仮装をした息子を恥ずかしく思って無視する。
語り手はこの父親に対して、複雑な感情を抱いている。それは、父親が彼一人のせいで傍若無人な振舞いをするようになったからではないことを分かっているからでもあるし、この父親にも男らしさで括ることのできない一面があることを知っているからかもしれない。
ある時、彼は母親に、どうして父を好きになったのかを尋ねる。そこで母親は、父親が香水をつけていたからだという。当時の男性たちが香水をつけることはなかったが、彼の父親はちがったのだと、母親は言うのだ。そうした女性的な仕草も身につけながらも、息子の同性愛や女っぽさを、彼は「ホモ(pédé)」と全否定する。まるで、自分は得られなかった自由を息子がもっていることを、憎しむかのように。
あるいは、子供時代の語り手の早熟な同情……。クリスマスの日、自宅に停めてあった父親の車はトラックに追突されて、跡形もなく大破してしまう。その車のトランクには、わが子へのクリスマス・プレゼントが隠されているのだ。逃げ去るトラックを必死になって追いかけ、叫ぶ父親を見て、7歳の語り手は泣く。だが、7歳の語り手が泣いたのは、プレゼントが跡形もなくなってしまったからではない。なけなしの給料からプレゼント代を工面した父親の絶望した表情を前にして、通勤に必須の車が消えたことを理解して、彼は泣いたのだ。
*
「誰が僕の父を殺したのか」――その答えは社会であり、そして社会を支配するエリートたちである。物語の末尾では、シラク、サルコジ、オランド、マクロン……といった政治家たちの名前が、書物の題ともなった問いへの答えとして書き込まれている。背中に障害を負い、もはや歩行も困難になった父親も、生きるためにはまだ働くことを要請される。そんな社会保障が不十分な社会をつくったのは、エリートたちだ。
16歳で勉学を諦めて、田舎の工場で重労働をするしかなかった一人の男を殺したのは、政治とそれを牛耳る支配階級なのだ。そして、父になった男は酒に溺れ、息子たちや妻へ暴力を振るうしかなすすべがない。実は彼の父親もまた、暴力を振るう親に育てられたのだった――《暴力は暴力の原因であると僕は長らく繰り返してきたが、間違っていた。暴力が僕らを暴力から救うのだ。》
こうした物語内容は、エドゥアール・ルイの実体験が元になっている。ルイは父を憎んでおり、かつては復讐を試みたことが分かる描写もある。しかし、今では冷静に自らの父親が陥った状況を分析し、原因を告発しようとしている。地方に生まれ、ブルーカラーの労働者となった人間が、社会の底部から這い上がることはあまりに困難だ。
《あなたはお金がなかった。あなたは勉学を修められなかった。旅に出ることができなかった。夢をかなえることができなかった。あなたの人生を表わすには、ほとんど否定的な言葉しかないのだ。》
*
いわば、この小説はある種の「親ガチャ小説」なのかもしれない。「親ガチャ」問題がもたらす困難は、与えられた環境から抜け出したあとにも残存する。社会の下層に位置する社会階級から上方の別の階級への移動は、貧困・搾取から抜け出す一つの手段であるが、それは自らの元々属していた環境を捨てることにもなるだろう。
自らが大卒者になることで親との軋轢が生まれることがあるし、階級の移動は過去の自身を否定することにもなるために、単純に喜ばしいことではない。この階級を捨てるという主題をめぐっては、労働者の父親と文学教師の娘の関係を記したアニー・エルノーが先駆者に当たるだろう(『場所』)。さらには近年、哲学者シャンタル・ジャケはこの現象を「階級の移動(transfuge de classe/transclasses)」と名付け、分析もしている。
エドゥアール・ルイは経歴だけ見れば超エリートに見えかねない。現役大学生の頃にブルデューとフーコーについての論集を大学出版で編纂し、自作小説の出版にこぎつけている。しかも、処女作はベストセラーだ。だが、彼が暴力と差別の蔓延した北フランスの町で育ったことも事実だ。つまり、彼こそが、「階級の移動」を経験した張本人なのだ。
*
語り手は先述の通り、父親に対して単なる憎しみとは言えない感情を抱いている。同性愛者で女っぽい自分をあれほど否定し続けてきた父を、語り手は単純に否定することができないでいる。そんな父と息子の関係を切り抜いた本作の後半には、次のような一節が存在する。
《数年後、町から逃げ出してパリに住むようになった時、夜のバーで会った人たちに、家族と僕の関係を尋ねられる。妙な質問だが、彼らはそれを聞いてくる。僕はいつも、父のことは大嫌いだと答えるのだ。でも、それは本当ではなかった。あなたのことが好きなことを自分で分かっている。それでも、あなたを大嫌いだと他人に言う必要を感じてた。だが、どうしてなのだろう?》
故郷と家族を捨て、高みを目指したひとりの青年の抱く苦悩を赤裸々に、本作は描ききっている。
【今回の小説】:Édouard Louis, Qui a tué mon père, Seuil, 2018.
0 notes
Text
映画上映日誌3. : ユペールとサロートの対談
今回、『レースを編む女』と『ヴィオレット・ノジエール』の上映にあたり、イザベル・ユペールの様々なインタビューを集めた。インタビューを集めるほど、ユペールという人物の聡明さにやられてしまう。どのインタビューも映画と同じくらい素晴らしいから、特にお気に入りのいくつかを紹介したい。
*
個人的に一番お気に入りのインタビューは、1978年5月19日にテレビ放送されたインタビューだ。このインタビューで冒頭から、映画祭は好きではないとはっきり表明するユペールには圧倒されるものがある。インタビュアーはぴったりな言葉を探すようにして、ユペールの演じる人物たちを「不可解なところがある、説明できないような人物」と評し、レースを編む女とヴィオレット・ノジエールというふたりの女性に共通点があることを指摘する。この点について、ユペールは迷いなく自らの考えを以下のように話してゆく。
《しっかりと現実に入り込めていない、思春期と成人の境界にいるような、すごく内向的で、自分のことでいっぱいで、想像のなかに生きているような人物が好きなんです。私はそういうタイプの人にかなり惹かれますし、レースを編む女とヴィオレット・ノジエールのあいだに共通項があるというのは、そうですね。外の世界と関係をしっかり持てずに、物事を夢や幻想の内に見ている人物たちですので……》
ここまではっきりと演者に指摘されてしまえば、言うべきことはなにもない。外の世界と関係を結べない人物とは、その後のイザベル・ユペールが演じてきた多くの人物の特徴でもあり、25歳の時点で既にここまで自覚的に演じているキャラクターを分析・理解していることに驚くほかない。
*
あるいは、ヴィオレット・ノジエールという人物については、別の放送でも、次のようにユペールは話している(パンツスーツで頬杖をつきながら、シャブロルの横で自信ありげに話す姿がかっこいい!)
《ヴィオレットは、ものすごく苦しんでいる痛ましい人物だと思います。彼女の行為の恐ろしさに匹敵するのは、彼女の苦しみだけです。彼女の攻撃的な行動はどれも根本的な愛の欠如と、その絶対的な探求という狂気の代償に過ぎません。》
実は、シャブロルはインタビューで、ヴィオレットの主張する父親による近親相姦を否定している。ユペールは近親相姦の有無には直接的には触れていないものの、ヴィオレットの苦痛を理解しているように思える。
あんな小さな部屋で親の性行為を毎夜見せられているのであれば、それは近親相姦に匹敵する性的な虐待だ。だから、問題はヴィオレットの証言の真偽というよりも、彼女の苦しみを映画の中で表現することだろう。このインタビューを見ると、ヴィオレットの抱える苦痛の重要性を、ユペールはシャブロル以上に理解しているように思える。
*
もう上映が終わったからネタバレをしてしまえば、『レース』と『ヴィオレット』の2作品の選定は、もちろん共通するラストショットに由来している。ミコノスのポスターが貼られた室内で、茫然と私たちのほうを見つめているポム。同室の囚人に「今ならできる」と希望を語って顔を上げ、私たちを見つめてくるヴィオレット。ユペールが演じる二人の女性には、力強いまなざしが共通している。
この二つのショットにおいて見つめてくる彼女たちが、どのような感情をもっているかについては、鑑賞者によって感じるものが違うだろう。それでも、まなざしの力強さだけは、誰にも否定しがたいものだ。こうした「見つめること」をめぐり、ユペール自身はしっかりと自己解説を行っている。
《様々な感情に対して、てこのように作用するのがまなざしの力です。[……]あなたをひきつけるまなざしの力は、あなたに何かするよう駆り立てます。また、私は自らのまなざしをカメラのレンズに近づけることが好きです。決して越えられない境界があるとしてもです。観客が私に、私の内面にできるだけ近づいてくるんだという強い意識をもちながら近づけるんです。》
ユペー���はやっぱりあらゆる演出に意識的な人物だ。ユペールにとって、カメラの前で露わになる顔のクローズアップは、登場人物の内面を私たちに伝えようとする試みに等しい。人間の内面は複雑で、簡単に理解することはできないだろう。それでも、というよりも、だからこそ、我々を見つめるショットは魅力的だ。
*
最後に紹介したいのは、小説家のナタリー・サロートとの対談だ。サロートがいつも通りの「内面の描写」について講釈を垂れるこの対談は、ヌーヴォーロマンの研究をしている者からすれば飽き飽きする。それでも、ユペールとサロートが言い争いをする部分があり、そこは面白く、更にユペールの立場・意志表明とも捉えられるので、長くなるが訳しておく。
《ユペール:女性文学の特性というものがあると思いますか?
サロート:それよりひどいものはないですよ。
ユペール:けれども、あなたの小説を読んでいると、非常に具体的な物を通じた強迫観念が示されているように感じるのです。事物への執着はとても女性的だと思いますが……。インゲボルク・バッハマンを、『マリーナ』の中で描かれた脅威的な物への執着を彷彿とさせます。
サロート:(熱弁して)それが女性的かは人が決めることですし、私の作品には物への執着はありませんが……。
ユペール:わかりませんね、『プラネタリウム』の革製のソファーは……。
サロート:ああ……。バルザックを再読しなさい。
ユペール:はい。でも、古典的な作家においては描写ですが、あなたの作品では……。
サロート:事物は触媒です。私の文学の新しさは、事物そのものが消失し、触媒としてしか価値がないということです。女性的かどうかということではありません……。みんなすぐに「これは女性的だ。繊細で、細部にこだわっている」と言いますよね。ヘンリー・ジェームズを読んでごらんなさい。
ユペール:はい。でも私としては、軽蔑的なニュアンスではなくて……。
サロート:そうじゃない、そうじゃないの。私にとっては軽蔑だわ。》
対談を読むと、サロートというのはなんて頭が硬いのだろうかと思うのだが、ユペールとサロートの立場の違いが明白になっていると思う。ユペールは「女性的である」ということに、積極的な意味をもたらそうとするのに対し、サロートは断固として男女で判断することを拒絶する。というか、とにかくサロートは対談全編を通じて、「心内の動きの描写」以外のあらゆる話題で否定を続けている。
しかし、別にユペールは本質主義に陥っ��いるわけではないし、「女性的なもの」に積極的な価値を見出す彼女の立場こそ、現代における一つの試金石となりうるのではないか? さらには、『黄金の果実』にジャック・タチっぽさを見出したりしてしまうユペールのほうが、よっぽどサロートよりも思考に柔軟性をもっていて、興味深いのだが……。
0 notes
Text
映画上映日誌2. : 字幕をめぐる冒険
Twitterを見ていたら、ウディ・アレンの最新作がボロクソに言われていた。どうやら全編フランス語でスクリプトを書かれたのだが、そのフランス語がめちゃくちゃだったらしい。そんなめちゃくちゃなフランス語を演者たちが意味の通じるものに直したせいで、台詞がどれも凡庸になってしまっただとか……。
ウディ・アレンに同情するわけではないが、本当に外国語は難しい。今回、字幕翻訳をしてみて、あまりの難しさに頭を抱えてしまった。やっぱりプロの翻訳者たちは凄いのだ。
字幕翻訳は1秒4文字だとか、1行24文字×2行だとか色々な制約がある。だから、台詞の全てを訳すことはできない時に、台詞の一部を省略して翻訳する。もちろん、ある台詞が後半の別の台詞と呼応していることだってある。そんな時は、訳語も統一しなくてはならない。2時間程度の映画なら、台詞は1000個以上に及ぶことになる。それだけの量を適切に訳すのは至難の業だ。
*
まず、大変だったのは字幕にする部分の取捨選択だ。この点は、とりわけ『ヴィオレット・ノジエール』が難しかった。この映画は、国家・カルチェラタン・家庭という3つの空間での出来事の錯綜によって物語が出来ている。戦争へ向かうフランスという国家における政治談議の台詞、ヴィオレットがさまようカルチェラタン界隈での半グレたちとのやり取り、そして家庭という閉鎖空間でのやり取り。カルチェラタンのホテルで寝ている時に、ナチの勢力を示すラジオが流れていたり、家庭内での会話に当時の大統領の話題が出る。どれもが意味をもって、絡み合っているために、なにがなんでも全てを訳したかった。
そういうわけで、『ヴィオレット』は通常の字幕のルールを破り、多少表示時間が短くなろうとも、全ての台詞を訳すという方針を取った。戦争・隣国のファシズムに国民たちが怯えていた頃に、小さな家庭での殺人事件が国民を熱狂させたことは重要だからだ。どうしてヴィオレット・ノジエールがこれほどまでに、文学の、歴史のミューズになったのか。それは戦争という大文字の歴史との関係がある。
*
他方で、とにかく説明をしない字幕を心掛けた。これも『ヴィオレット』についての問題だ。自分はシャブロルのインタビューを数多く読み、聞いているために、この映画の意図や近親相姦の有無について監督はどう捉えているかを知っている。だが、シャブロルは、映画の中に(近親相姦の有無、エミールとヴィオレットの関係など)多くの曖昧さを残している。だから、インタビューで言っていたからと、勝手に説明をするような訳文はつくらないように心掛けた。
*
また、前述と同じ字数超過のルール破りとして、『レースを編む女』におけるフランソワと友人たちの談議のシーンがある。マルクス主義、弁証法、箱の時代が云々……というシーンだが、インテリ大学生たちの難解な談議を全て訳すとルールに合致しない。しかし、ポムはこの談議についていけず疎外感を感じていることを示すのが重要だと思った。だから、その感覚を示すために、表示時間が短くなろうとも、ここは全ての台詞を訳すことにした。
*
一人で数多くの字幕を訳していると、誤訳がどうしても避けられない。基本的なうっかりミスは、フランス語の分かる友人に見てもらうことで直せる。しかし、そうは言っても、数千の字幕を訳すとなると、必ず誤訳が発生する(今まで映画館で見ている時は、誤訳を見つけるたびに「ああ、ミスってるな」と思っていたが、自分でやってみるとそんなことはもう思えません……)。
*
結局、プロに最終確認してもらったところ、「テイスト」なのだと言われた。もちろん単純な誤訳は問題だが、字幕翻訳は単なる誤訳か否かを問うのが難しい分野だとも思う。数多くの制約の中で、台詞のエッセンスを抽出して別の言語に変えてしまうこと。そこには訳者のテイストが必ず含まれる。だから、本当に作品を理解しようと思ったら、原語で聞き取って見るしかないし、名訳者とは彼の出すテイストと作品のもつテイストを常にぴったり合わせられる者のことなのだろう。
0 notes
Text
映画上映日誌1.:「フランス映画と女たち」の意図
「フランス映画と女たち」を企画して、フランスの配給との交渉、字幕翻訳、運営などのほとんどの作業をひとりでやってみた。もちろん、この企画には意図があって、���場者はそれを汲み取ってくれると思っていた。けれども、友人にちゃんと説明するように勧められた。友人曰く、「単にシネフィル的趣味で、日本未公開作を流しただけ」と思われてる可能性があるという。そう言われてしまうと不安だし、愚直に企画の意図を紹介しようと思う。
*
ここ数年、女性映画監督の特集上映が増していることは誰もが否定できない事実だ。シャンタル・アケルマン、アニエス・ヴァルダ、メーサーロシュ・マールタをはじめとして、多くの女性監督の特集上映が近年組まれている。シネフィリーたちがこれまで女性監督たちを無視してきたことを清算するかのようなこうした特集には、もちろん多くの意義がある。
けれども、女性監督を特集するだけでは(大抵男性中心の)シネフィルたちの意識を変えられるとは思えなかった。カメラの前で演じる女優たちへのまなざしを変えなくては。イリス・ブレー『女性のまなざし スクリーンでの革命』を読んで確信した。自分も全然、人に説教できるわけじゃないからこそ、そんなことを考えてた。
ドロシー・アズナー監督の『恋に踊る』(1940)には、舞踏団の女性二人が壇上にて、自らが男性客たちにまなざされることで性的に搾取されていることを感情的に訴えるシーンがある。この作品を2022年に見た時に、多くの年配の客は該当シーンで大きな声をあげて笑い出した。私は、映画ファンたちの見ることをめぐる自意識の低さに直面し、なにかこの状況を変転させる上映会ができないかと企みはじめた。その結果が、「フランス映画と女たち」だ。
*
今回の特集上映で選んだ映画には、発狂したり、黙り込んでしまったり、人を殺したり、誘拐を企てたり、「狂人」「犯罪者」「怪物」と形容されるだろう女性たちが出てくる。しかし、本当に彼女たちは狂人なのか、彼女たちの常軌を逸した行動は面白おかしいものなのか。彼女たちが過ちを犯すのは、本人の気質なのか、本人のせいなのか。そんなことを考える機会にしたかった。
うまくいったのかは分からない。各字幕の訳語もそういう意図で選んだのだけれど、どうだろうか。『レースを編む女』で起こった笑いは残念だし、若い人たちと一緒に考えて議論をしたかったのに、学生券はほとんど売れなかった。けれども、諦めるつもりはない。FilmarksやTwitterの感想を読んで、あるいはネットには書き込まれていない鑑賞者たちの気持ちを思い、決心した。これからも上映は続けるつもりだ。
竹内航汰(東京外国語大学博士後期課程)
1 note
·
View note
Text
「『ル・モンド』使用法」――翻訳で読めないフランス小説1.
『ルビー・スパークス』という映画がすこし昔にあった。その映画は、スランプの作家がタイプライターで描写した女性が実際に目の前に現れてしまうという話なのだが、このタイピングすると現実になってしまうという設定は、ちょっと難しく思想的な言葉を使うのなら、「パフォーマティブ・行為遂行的」の一種とでも言えるだろう。書くこと=現実化⇒パフォーマティブ。雑かつ矮小化しすぎていて専門家には怒られるかもしれないけど、とりあえずそうしておこう。ちなみに、この映画のヒロインを演じたゾーイ・カザンがあまりに文学オタク男子の妄想を刺激するようなハマり役だったのだが、それはまあ脱線……。
今回読んだエマニュエル・カレールの「『ル・モンド』使用法」は、まさにこのパフォーマティブなテクストで出来ている。しかも下ネタだらけ。いわば、下ネタ満載版のビュトール『心変わり』である。
***
この短編小説は、フランスの新聞『ル・モンド』2002年7月21日号に載った。そして、小説はまさにその同日発刊の『ル・モンド』を携えて、パリからラ・ロシェル行きの列車に乗るはずの「きみ」に向けて書かれているラブレターを呈している。つまり、列車である人物に読まれることを前提とした二人称(書簡体風)小説が『ル・モンド』に載っているのだ。しかも舞台はまさにテクストが世に出る日! だから、冒頭の一文はこんな感じだ。
《駅のキオスクで、列車に乗る前、きみは『ル・モンド』を買った。ぼくの小説が発表されるのは今日だ。ぼくは今朝、電話できみにそのことを伝え、絶好の旅の読書になるだろうと言い添えた。》
テクストは「きみ」が電車に乗るところから、ほとんど同時間的に進められていく。語り手は「きみ」に対し、ひとつのゲームを提案する。文字で書かれている・指示されていることを、その通りに「きみ」にしてもらうというゲームだ。たとえば、十分間読むのをやめると書いてあれば、「きみ」は読むのをやめなければいけない。
おそらく書き手とセフレ関係にある「きみ」に向けて書かれるのは、セクハラめいた下品な記述ばかりである。衣服の下の肌がどうだとか胸を愛撫する語り手の指だとかの描写をしたり、濡れるだとかなんだとかそんなことばかり……。
そんな風に扇情的な文章で煽ってくる語り手には一つの信念があるらしい。それは次の一節で明らかになる。
《文学には効力があるものであってほしいと、ぼくは思う。言語学者がパフォーマティブな言表を定義した意味で、文学はパフォーマティブであってほしいと理想的には思っている。[……]おそらく、あらゆる文学ジャンルの中で、ポルノはこの理想に最も近いと言えるだろう。「きみは濡れている」という言葉を読むことは、濡れさせる。これは単なる例で、「きみは濡れている」とは、ぼくは言ってない。だから、まだきみは濡れてない。もし濡れているのなら、きみは注意を払えていない。》
まったく、そんな信念でもってこの先もエロティックな描写ばかり続けるのだから馬鹿みたいだ。でも、5月23日木曜日にロシアで語り手はこの文章を書いていて、読み手の「きみ」は7月20日土曜日にフランスにいることを考えると面白い。「ぼく」は未来の列車の中の様子など知っているはずもないというのに、「きみ」の隣客について記そうとする。
語りの時間と出来事の時間の転倒は、この小説の面白さのひとつだ。つまり、超一般的な小説は【過去に起こったこと】を振り返りながら、【今書いている】。でも、この小説は、【今起こっていること】を【過去に既に書いている】。単なるエロ小説かと思ったけど、そういう書くことをめぐる時制の転倒が、パフォーマティブなテクストだとできるってわけか!
***
そして、この小説が真に面白くなるのは、書き手によってあることが示されてしまったときだ。あることとはなにか。それは「きみ」になりうる人物が、読者には確定できないということを語り手が気づかせてくる瞬間である。ブロンドで首が長く、スリムなウエストに豊満なヒップをもった「きみ」は、名指されていないのだから、読者の女性のなかに当てはまりうる人物は無数にいる。そうだとすれば、語り手がエロティックな指示を出していた相手である「きみ」とは、いったい誰になってしまうのだろうか。
《主人公はきみで、でもそれを知っているのはきみだけで、他の女たちはきみであるようなふりをしている。二時間前から、主人公はきちがいみたいに濡れていて、他の女たちもきちがいみたいに濡れ始めている。》
《ぼくはこの状況が大好きだ。『ル・モンド』のおかげで、彼女が本当に存在するなんて最高だけど、彼女をどうやってコントロールすればいいか、もはやわからない。人は多すぎるし、パラメータも多すぎる。だから、もうコントロールはしない。やめるんだ。もちろん、いろいろなことを想像しつづけている。動き回る視線、控えめな笑み[……]》
この瞬間から、ラブレターを読まされているだけで、語り手ときみの紙面での恋愛遊戯に付き合わされている部外者だと思っていた読者たちも、やっぱり自分こそが「きみ」なのではないかとドキッとさせられるかもしれないし、いやはやそれでもやっぱり私は断じて「きみ」ではないと思うだけなのかもしれない。いずれにせよ、「きみ」とかいう代名詞のせいで、このパフォーマティブな物語文章はより複雑な効果を生みだしてしまうのであり、語り手は終結部で、パフォーマティブなだけでなくインタラクティブ〔相互作用的〕になりうる読者それぞれのバージョンを語り手のヤフーメールに送ってくるよう勧めてくる。
パフォーマティブからインタラクティブへ。なかなか技に富んだ短編である。
【今回の小説】:Emmanuel Carrère, L'usage du Monde, dans Le Monde, 21 juillet 2002.
【注】今回の短編のタイトルは、もっと単純に「『ル・モンド』の利用」とか訳してもいいんだけれど、ジョルジュ・ペレック『人生使用法』の訳題がカッコよかったからパクってみた。もちろん、ペレックのほうの原題は《La Vie mode d'emploi》でちょっと使ってる単語がちがうんだけれど、そこはご愛嬌ということで……。
【注】この短編はのちに同作者の『ロシア小説』(2007年、未邦訳)という長編に組み込まれたそうです。
0 notes
Text
Quand on adapte un livre en film, on porte souvent une critique sévère à son égard. Certains disent alors que ce film n’est pas à la hauteur de l’œuvre originale. Mais, la fidélité à l’histoire de l’œuvre originale n’a pas d’importance. Ce qui importe lorsque l’on réalise un film à partir d’un livre, c’est seulement d’en extraire son essence.
Beaucoup de gens qui regardent le film de Neil Jordan, Marlowe pourraient trouver son intrigue faible. Nombreux sont ceux qui se plaignent de la difficulté à suivre l’histoire du film. Mais, cette difficulté fait partie intégrante des œuvres de Chandler. En apparence, ce film raconte comme d’habitude une enquête du détective privé, Philippe Marlowe. Deux femmes blondes lui demandent respectivement d’enquêter sur un homme que l’on pense mort. Bien entendu, cet homme n’est pas mort et ces deux femmes sont mère et fille. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, les relations entre les personnages se compliquent et Marlowe est battu par des gangsters sans raison. En outre, les « principes » du comportement de Marlowe n’ont pas du tout de logique. Les agissements de Marlowe semblent irrationnels pour le spectateur bien qu’il soit détective.
Depuis la Poétique d’Aristote, on pense que les événements de la fiction n’arrivent pas au hasard et qu’ils sont la conséquence nécessaire ou vraisemblable d’un enchaînement de causes et d’effets. Mais, les actes de Marlowe ne comportent rien de logique.
On veut considérer l’absence de cette logique comme une sorte d’anachronisme. Certes, on peut dire qu’il y a quelque chose d’« anachronique » dans ce film, qui se déroule dans l’Amérique des années 1930 mais qui est filmé dans des couleurs vives. Cependant, on peut penser aussi à un autre aspect « anachronique » dans ce film. Cet anachronisme concerne l’essentiel de l’Histoire du cinéma. Beaucoup de films contemporains perdent l’enchaînement causal dans leur narration pour se laisser aller à une réflexion philosophique. Par ailleurs, c’est une des caractéristiques du film noir classique. Et alors, quand le film noir contemporain perd cet enchaînement causal, comment évaluer ce film ? L’absence de causalité du film n’est pas peut-être due à des considérations philosophiques, mais à son imitation du film noir classique. Mais, nous devrions applaudir cet anachronisme du film et ce n’est pas seulement parce que l’on a une prédilection pour ce film et ce réalisateur. C’est aussi que nous pouvons ressentir une libération du temps linéaire et de la causalité, lorsque nous, habitués au cinéma moderne, regardons ce film. Avec ce film, nous nous rendons compte que le film noir et la Série noire ont clandestinement détruit la logique causale bien avant que la littérature moderne et le cinéma moderne.
0 notes
Text
Le dernier film d’Indiana Jones cristallise les pensées de deux grands réalisateurs, celles de Spielberg et de Lucas. L’intrigue raconte la dernière épopée archéologique d’Indiana Jones. Il s’efforce d’empêcher des nazis survivants de mettre la main sur une machine à voyager dans le temps. Dans ce film, si on utilise cette machine créée par Archimède, on peut remonter le temps. Les nazis survivants veulent donc changer l’Histoire en l’utilisant. Comme le montrent ces intrigues, la leçon des deux maîtres réalisateurs est le rejet du nazisme et du révisionnisme.
En fait, Indiana Jones est un personnage ambigu. Il lutte contre le complotisme ou le révisionnisme. Mais à la fin du film, quand il voyage dans l’Antiquité, il déclare son souhait d’y rester et il ne veut pas rentrer à son époque. Certes, tout chercheur historique souhaiterait se rendre à l’époque qu’il étudie. Mais, la collaboratrice de son aventure le persuade et, au bout du compte, il rentre à l’époque d’où il vient. Ces leçons sont très importantes et pédagogiques pour un film qui, à partir d’une histoire fictive, traite d’OOPArt. Surtout dans le monde actuel dans lequel se répand le complotisme. Bien entendu, ce film en apparence pédagogiques comporte une lacune. L’objectif de l’aventure est de collecter des trésors du monde entier pour ensuite les exposer dans un musée d’un pays dominant. N’est-ce pas une idée impérialiste que de les collectionner et de les exhiber dans un musée comme des trophées ? Cependant, l’élément le plus important du film est tout autre que toutes ces leçons.
Ce qui m’impressionne le plus dans ce film, ce sont l’attitude et la gestuelle d’Harrison Ford. Cet acteur âgé de quatre-vingts ans ne peut plus bouger comme auparavant. Quand même, cette fragilité m’a frappé. C’est parce que l’on peut se rendre compte de la durée de l’histoire cinématographique à travers le vieillissement de son corps. L’acteur, qui était déjà d’âge moyen lorsque j’étais petit mais encore assez athlétique, a maintenant du mal à se mouvoir. En fait, le critique Serge Daney a dit : « le cinéma ne peut pas être une simple succession de styles ou d’écoles et les phénomènes de filiation s’effectuent à travers les images nostalgiques, vieilles des mêmes corps. Le corps de l’acteur traverse le cinéma, il en est l’histoire véritable. » (La rampe)
Quand j’ai regardé son torse nu décrépit ou une des scènes où il lui faut beaucoup de temps pour grimper sur une falaise, j’ai été très ému. C’est à ce moment précis que nous nous rendons compte que ce film nous transmet une vraie « Histoire du cinéma ».
0 notes
Text
Ce qui m’étonne le plus en relisant l’œuvre de Jules Verne maintenant, c’est que ses romans contiennent trop de mots inconnus, scientifiques et techniques. Ces mots concernant les parties de bateau, le climat et la géographie, que je ne comprends toujours pas en tant qu’adulte, n’auraient évidement pas pu être compris lorsque j’étais plus jeune. Néanmoins, j’étais un lecteur avide de ses romans, peut-être parce que lire ces mots difficiles à comprendre était une aventure, c’est-à-dire lire Verne en pensant qu’il y avait une signification secrète derrière ces mots. Les livres de Verne m’ont donné ainsi l’impression de pénétrer dans le monde adulte et dans lesquels on pouvait lire des mots employés par ces derniers et dont le sens m’échappait quelque peu.
Être mûr signifie que chaque fois que l’on rencontre un mot inconnu, on vérifie son sens avec un dictionnaire. Mais lire sans dictionnaire, c’est tenter une sorte d’aventure. La lecture en imaginant le sens des mots inconnus à partir des mots environnants et du contexte nous conduit inévitablement à une lecture plus lente. C’est une « véritable aventure » que nous avons vécu dans l’enfance, lorsque nous avons lu maladroitement l’abécédaire à haute voix, en essayant de ne pas rater un seul mot.
0 notes
Text
Les films que je préfère partagent tous un point commun : ils narrent l'histoire d'un couple en fuite. À l'instar de Bonnie et Clyde, ces personnages doivent échapper à la société, de vivre en marge de la loi, car ils ont commis un crime. J'apprécie véritablement ce genre de films, car la convergence de trois éléments -- le crime, l'amour et la fuite -- est captivant. Par ailleurs, une autre raison nourrit mon attrait pour les « road movies de cavale ».
Cet attrait réside dans le fait que l'histoire de la fuite est l'une des structures les plus fondamentales de la littérature et du cinéma. La traque d'un personnage par un autre, telle une chasse au trésor, se conclut généralement de manière prévisible : la personne en fuite est rattrapée par celle qui la poursuit. L'originalité du contenu de l'histoire est donc ainsi relativement absente. Malgré cette prévisibilité inhérente au genre, sa structure offre à chaque cinéaste une façon de manifester leur propre style narratif, les contraint d'inviter leur propre syntaxe cinématographique.
En réalité, j'ai découvert tous les réalisateurs que j'admire lorsqu'ils ont mis en scène un drame impliquant un couple en fuite. Parmi ceux qui m'ont particulièrement marqué, on peut citer Douglas Sirk (Shockproof), Kelly Reichardt (River of Grass) et Azuma Morizaki (Onna Sakasemasu).
1 note
·
View note
Text
Les jeunes ont récemment commencé à s’intéresser aux vieux cafés et aux vieilles chansons au Japon. Ils semblent éprouver de la nostalgie pour ces choses anciennes. Mais c’est étrange, car ils ne sont pas nés à cette époque. Il est aussi curieux qu’ils en éprouvent pour une époque à laquelle ils n’appartenaient pas.
Il existe un autre phénomène lié à ce sentiment. De nombreux jeunes japonais se souviennent de leurs vacances d’été fantasmées avec nostalgie. En outre, beaucoup d’entre eux rêvent d’expériences estivales passées avec une jeune fille vêtue d’une robe blanche et d’un chapeau de paille. Il s’agit également de la même nostalgie d’un événement qu’ils n’auraient pas dû vivre. Cette fausse nostalgie est probablement influencée par de nombreuses scènes des fictions au Japon : par des films, des bandes-dessinées, des dessins-animés ou bien encore des chansons.
De nombreuses personnes consomment ces fictions et sont délibérément déçues lorsqu’elles rêvent d’un passé possible qui aurait pu advenir. Les œuvres procurant ces effets appartiennent au genre appelé « masochisme sentimental » (kanshou mazo).
Ce qui m’intéresse le plus, c’est la temporalité de ces expériences nostalgiques. Puisque l’expérience n’existe pas réellement, elle ne devrait appartenir à aucun temps. Mais alors, quel est le phénomène de cette nostalgie ? Est-elle « hors du temps », comme le dit Proust ?
0 notes
Text
Le paradoxe de discours
L’autre jour, en parlant avec un ami, il m’a dit : « tu ne dis pas du tout oui ». Il est vrai que je ne dis « oui » que lorsque je consens vraiment à l’opinion de la personne avec qui je discute. D’après mon ami, la plupart des gens n’utilisent pas « oui » comme un signe pour montrer leur accord avec l’opinion de l’interlocuteur, mais pour montrer qu’ils écoutent l’énoncé de ce dernier. En outre, si des interlocuteurs ne disent pas assez « oui », les gens ont l’impression d’être négligés.
Pour ma part, la communication verbale est un processus de confirmation des opinions de chacun. Je pense donc que chacun reconnaît dans la conversation les différences entre son propre discours et celui d’autrui, et clarifie sa position respective en confirmant ou en acceptant la diversité des opinions. Bien entendu, ce processus n’a pas pour but de nier l’autrui.
Il semble étrange pour la société à laquelle les gens appartiennent que certaines personnes prêtent trop attention à l’utilisation de certains mots, certaines expressions et à certaines nuances de langage. Il s’agit d’un aspect qui est ancré dans les sciences humaines en tant que discipline, mais qui est souvent critiqué dans la société. Cette attitude des sciences humaines à l’égard de la langue est socialement anormale pour la plupart de gens. Nous entendons souvent la critique selon laquelle les professionnels des sciences humaines ne saisissent qu’au vol une erreur, un barbarisme dits par l’autre. Il est étonnant de constater que plus on est spécialisé dans le domaine de la langue, plus il est difficile de communiquer verbalement avec les gens ordinaires.
0 notes
Text
Le mystère de photo
Quand nous regardons des photos, nous ressentons un sentiment un peu étrange. Je n’ai jamais visité les endroits photographiés et je n’étais pas encore né à l’époque où les photos ont été prises. Mais, j’ai l’impression de bien connaître la scène photographiée, comme si je l’avais déjà vécue.

Ce sentiment, je l’ai eu l’autre jour quand j’ai visité l’exposition photographique de Masahisa Fukase. Il a continué à photographier sa femme et ses séries d’œuvres sont connues sous le nom de « Shi-shashin », qui est emprunté au nom d’un genre littéraire japonais « Shishōsetsu »(autofiction). Bien entendu, je n’ai jamais rencontré sa femme et n’ai aucune connaissance des lieux où ont été prises ses photos. Cependant, je ressens de la nostalgie devant ses photos. C’est un sentiment très étrange.
Puisqu’il s’agit de « Shi-shashin », ses photos dévoilent des moments intimes, et pourtant il me semble curieux que le spectateur ait l’impression qu’une partie de sa propre expérience y soit représentée . L’expérience de Fukase renvoie aux propres expériences du spectateur. Le basculement du privé et du public dans la photographie est très étrange et intéressant. Ce phénomène peut être dû à la nature des photos, qui capturent la réalité dont on ne sait pas si elle y reste encore.
0 notes
Text
Nouveau instrument métaphysique d’Albert Serra
Albert Serra, cinéaste habitué à traiter de la fin dans ses œuvres, poursuit sa réflexion sur la condition humaine avec son dernier film, centré sur la fin du monde. Le point de vue adopté est celui d'un bureaucrate évoluant dans une station balnéaire en proie à une crise environnementale.
Le film se distingue notamment par sa représentation de l'île, considérée comme un "instrument métaphysique" permettant, selon Deleuze, de mieux saisir la condition humaine. Si de nombreux récits ont utilisé une île déserte pour évoquer cette thématique, Serra choisit cette fois-ci une île déjà peuplée pour explorer ce motif.
Loin des aventures distrayantes d'un Robinson Crusoé, les habitants de l'île sont des bourgeois profitant des installations déjà présentes. Le personnage principal, De Roller, n'a quant à lui qu'un objectif : gravir les échelons politiques. Si son comportement rappelle celui d'un personnage de Godzilla Resurgence, le film de Serra se distingue par sa lenteur, caractéristique récurrente dans l'œuvre du cinéaste.
En abordant de manière singulière le motif de "île", le film de Serra permet de mieux appréhender une réalité contemporaine : celle d'un monde qui s'éteint lentement, sans spectacle. Cette lenteur mortelle, omniprésente dans l'œuvre du cinéaste, traduit une angoisse profonde face à un futur incertain, comme l'exprimait déjà Baudelaire : « un monde qui va finir lentement sans spectacle. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c’est qu’il existe. Que cette raison est faible comparée à celle qui annoncent le contraire. »
0 notes
Text
De Proust à Tinder
À mon avis, être amoureux, c’est être victime d’une illusion. On dit que les gens ne peuvent pas regarder l’être aimé quand ils sont fous d’amour. Tout d’abord, il est difficile de trouver les défauts de la personne que l’on aime. L’amour est comme l’alcool : il limite souvent la vue du monde et fausse notre jugement.
Certes, plus l’amour est grand, plus la distance physique entre nous se rétrécit. Mais, toucher le corps de l’amoureux ne signifie pas nécessairement la disparition de l’illusion. Comme l’a montré Proust, l’illusion amoureuse disparaît lorsque le partenaire est absent. Dans l’amour, c’est par cette absence que l’on découvre son vrai visage. En effet après une rupture on énumère souvent ses défauts.
Cependant, cet aspect de l’amour pourrait changer avec l’apparition et l’utilisation des applications de rencontres en ligne.
0 notes
Text
Le moment de la maturité et de l’indépendance dépend de chaque personne. Dans mon cas, c’est le moment où j’ai eu 18 ans. Après la sortie du lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire. J’ai donc décidé de partir en voyage avec seulement une carte, un recueil de poésie et un peu d’argent. C’était la première fois que je quittais ma maison complètement, seul et libre. J’allais découvrir ce que je voulais faire pendant mon voyage.
J’ai délibérément choisi de ne pas prendre de smartphone, de sorte qu’il était difficile de trouver un logement. Je me suis pris pour Rimbaud. Pour tout faire, je devais communiquer avec les gens que je ne connaissais pas. Je pense que c'était une bonne expérience dans ma vie.
Cependant, après ce voyage, je me suis rendu compte que je n’avais visité que des endroits ou fait des choses dont j’avais déjà entendu parler dans des livres pendant ce voyage. Certes, l’importance de gagner en liberté loin de mes parents a été apprise au cours de ce voyage. Mais, la leçon la plus importante que j’ai retenu de ce voyage, c’est que voyager pour gagner en liberté et en autonomie est une idée ridicule, et les livres sont ceux dont on tire le plus d’enseignements.
0 notes