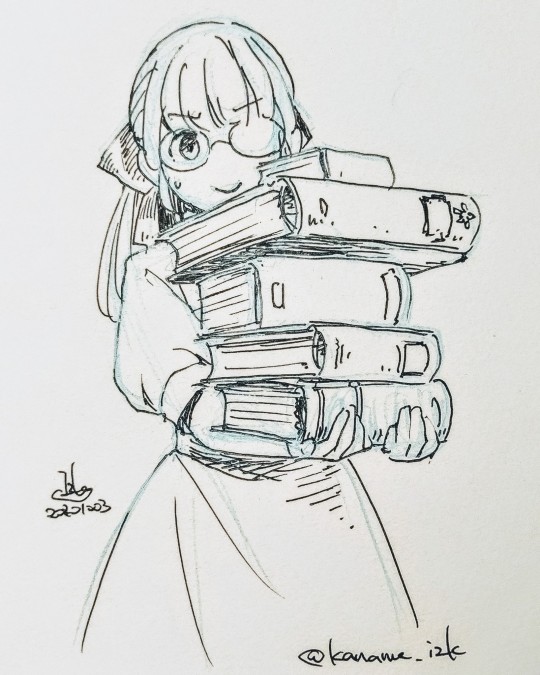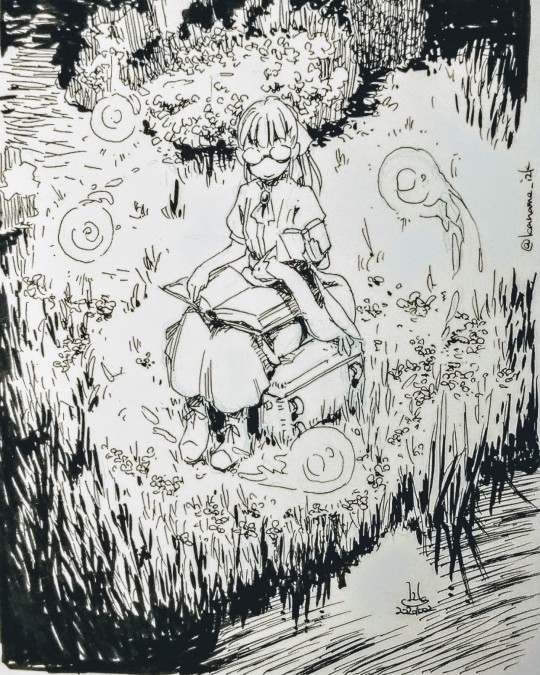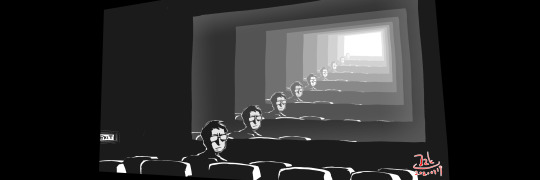Text
シン・ウルトラマン(2022 樋口真嗣)
さあ「シン・ウルトラマン」について書くぞ。
長くなっちゃったので久しぶりにこの見捨てられた地に置くことにする。
個人的な話なので、他の人がどうかとかは一切関係ないしどうでもいい。映画に合わせてわざわざ初代「ウルトラマン」を全部見直すようなダメオタクの言ってることだから、うっかり見てもスルーするくらいがいいと思う。
まあ、禍威獣が元気があってよかった。冒頭の禍特対前史は「そうくるかー!」と思ったし、各禍威獣のアップデート(そして流用)アイデアは面白かった。デザインワークスを買えていないのが悔しいが、一般流通に乗ったら買おうと思っている。
怪獣(もういいよね)デザインは「着ぐるみの制約を外したい」というだけあって多彩で刺激的だった。
特にガボラは予告編が卑怯にもミスリードを誘っていたので、全貌をスクリーンで見て「そうくるかー!」と思い、ウルトラマンを圧倒するパワーの格闘シーンを楽しんだ。直前の予告ですごいドリル回ってたから「えっグビラも出すの?」と一瞬思ったんだよなぁ。
ザラブもよかった。元デザインからそう変わらないかと思ったら、見えているのはポリゴンの表側だけみたいな、実体があるかどうか不明なぺらっぺらな立体の生物なんて、CGIじゃなかったらやろうと思わないよな。
メフィラスももちろんよかった。元のデザインを踏まえて鋭角に抽象化を大胆に進めたあたり、「初代」の造形デザインに携わったアーティストたちの個別の作品群を思うと「制約なしのエスキース段階っぽい!」という気持ちになった。
予告を観たとき一番危惧したのは「解像度だけ上げてシーン再現みたいなことになったら最低だ」ってとこなんだけど、それは完璧に杞憂に終わった。まあ個人的にはもっと炎を上げてもらって、低い視点から熱の揺らめきの向こうに怪獣を見たかったんだけど、ちょっと乾いた感じにしたいのだったら、それもまあなしではない。変化のあるアングルは楽しかったしね。
ただ、個人的に大事な話としては、これ多分ソフトを買わない。持っていたいと思える作品にはならなかった。
それは主に、僕が好きな「初代」の作品的な雰囲気はほぼ拾われていなかったためで、要するに解釈違いというやつだ。「シン」が最大公約数の「みんなが求めるウルトラマン」だろうと、僕は別にそうじゃなくてもいい。
「初代」は前企画「ウルトラQ」を引き継いでスタートしているので、ウルトラマンという全話通じた主人公的存在はいても、そのヒーロー性だけを前面に押し出して展開された物語群ではない。宇宙人であり、異星の文明においてある種の役割を持っており、同族も存在していることは描かれこそすれ、基本的には「未知」であり「神秘」の領域にいるものだ。それこそ「怪獣というカオスと対置されるコスモス」というコンセプトそのものの存在が「ウルトラマン」だ。
そういうカオスとコスモスが、何に介入してくる物語かといえば、言うまでもなく「普通の日常」である。日常に入り込んだカオスをコスモスという力で元通りに、あるいはちょっと変わった新たな日常に戻していくのが物語のスタイルだと言っていい。それゆえ非日常的なコスモスは、最後に地球を去るのである。
だが、そういった日常を侵食される怪奇な雰囲気が、この映画には微塵もない。さらに言うなら「浸食される平穏な日常」自体がない。描いてないけど日常なんですよ、なんてそんな馬鹿な。ほぼCGIで作った映画に「意図して描写しないで」どうやって日常が描かれるというのか。
だから、ほとんどが戦闘行動に終始する物語になっている。まあ、怪獣災害に悩まされる日々が日常なんだ察しろ、というのであればそれでいいんだけど、それはもう「初代」とは別の精神性の物語にならざるを得ないし、そもそも、そこまでの非常事態下にある日常として描かれてもいない。
怪獣対策がかっこいい、のか?まあそういう向きはある。けどもそのプロセスそのものは決定的に物語の尺が足りず、コンパクトに説明するべく煮詰めた故にルーティンとなってしまうし、怪獣の駆除に成功した事例は過去の事実としてしか描かれていないので、軽口たたいてるけど禍特対はそこまで優秀なチームなの?という風にも見えてしまう。
物語の尺というのは、かなりの部分で物語が表現できるものの範囲を決定する。本来が39話あったものの一部をピックアップしてきたとはいっても、そのほかの話数で培われた表現や了解を切り捨てられるわけではない。
そういった部分を大事にしないで「事件だけで構成した」から起きている問題はこの映画の中に多くあるけども、特にキャラクターにそれを負わせざるを得ないせいで、イデほどの苦悩の深さとストレスを滝に感じられなくなっている。打ちのめされるほどのことお前この映画の中でしてないじゃん、何言ってんだよ、と言いたくなる薄っぺらさが終盤になって現れるのはどうなのか。いいのか。いいことにしようか。僕はごめんだけど。
浅見というキャラクターの扱いもひどい。尺が足りないせいでなんでそんなに神永に好意を持つのかが不明だ。もう物語の都合上そうしました、という感じにしか見えない。「初代」で同じ位置にいたフジは集団の中にあって常に自由な立ち位置にいる(時代性のある描写を強いられることはあれども)キャリアウーマンだった。だが浅見ときたらどうだ。能力集団の中で不在の神永を印象付ける役回りでしかないし、しかもそこにプロフェッショナルとは思えない感情まで入り込んでいる。この21世紀にもなって。
しかも。
巨大化させられ意思を奪われた挙句、スカートの中を衆目にさらし、それを野次馬に撮影され世界中に拡散され何度も閲覧される。もうこの描写自体が醜悪極まりないのだけど、映像拡散に関して気にしているのは顔が割れたことだけだという。動画がメフィラスの力で全削除されたらOKだという。正気か?そのキャラクター造形は大丈夫なのか誰も問わなかったのか。
異空間に隠されたβボックスを追跡するために浅見の「匂い」を手掛かりにしよう、というアイデアが出る。その前に自分の体臭を気にする描写がありつつ、禍特対の面々の前で神永に全身の体臭を嗅ぎまわられる。状況が状況なので仕方がない、という面白シーンのつもりなんだろうけども、誰もそれを少しも止めないのが、良識ある人間の社会という描写ということでいいのか。本当に誰もこれをおかしいと思わなかったのか。
この下品さが、僕には耐えがたかった。
なので、ウルトラマンはこれを守りたいと思うのかなぁ、という気持ちを抱いたまま残りを観ることになった。
僕は最初のほうで怪獣のデザインアイデアに関してはすごく感心して面白がったと書いたけども、画面の中での描写に関しては全く納得がいっていなかった。
何しろ、圧倒的に質感表現が足りない。そういう巨大なものが、光を受けて存在しているとは思えない平板さ。「こんにちは、僕CGIです!」そうか、可哀想にな。ぎゅんぎゅん動いているときは多少ごまかされるけども、動きが静まると途端に造形のエッジばかりが立って、心許ない胡乱な表現の面が露見してしまう。宇宙人はギリギリOKだが怪獣はダメだ。もしもこれWETAがやってたらいったいどんな怪獣がスクリーンで咆哮していたんだろう。
ゼットン、でっかいなぁ。火力すっげえ。僕が最終決戦で思っていたのはせいぜいその程度だ。だから僕はこの映画のソフトを多分(ということはかなりの確率で「絶対に」)買わない。
まあ解釈違いだけなら買ってたかもしれないけど、僕、それが偶然であっても許されずに人のスカートの中を見て喜ぶ趣味ないんだよ。劇場で目を背けていたんだぞ。わかるかこの苦痛。わかんないんだろうな。それを笑って見過ごすのが最大公約数だというならば、本当に願い下げだよ。
まあ、それはそれとして。
ウルトラマンをめぐる国際社会の動き関係はちょっと面白かった。国際関係や各国決定権者の未成熟に宇宙人が付け込んで謀略を巡らせるあたり、どこに落としどころを持ってくるんだ!って思いながら観ていた。
あと、「ヒーロー」ウルトラマンをある首尾一貫した存在として描く、というのはこの映画の独自性としてありなんじゃないか、と思った。ウルトラマンという「神」を僕はこう理解しました。そういう論文みたいなもの。僕は宗派が違うのでその主張を首肯するかは別だけども、愛のあり方としては理解する。
ただ「初代」では「ヒーローの有り様」はエピソードの中に内包しつつも、その存在もまた怪奇や神秘のうちにあったことを踏まえると、すべてを合理の中に収めるのは「現代的ではあるけども理屈が勝ちすぎる」のではないかな、と思う。
僕もウルトラマンと怪獣に対して愛を捧げてきた時間がとても長いので、わかる部分があり、絶対に認められない部分があるのだ。
手放しで楽しめて、手放しで褒め讃えられる人に幸あれ。僕は無理でした。
樋口真嗣が特技監督より上の権限で参加している映画は、劇場にもう観に行かないと思う。元凶が庵野の脚本に仮にあるとしても、それ���コントロールできない人間がどうして監督を名乗れるのか、僕には理解できない。
1 note
·
View note
Text
シン・ウルトラマン(2022 樋口真嗣)
さあ「シン・ウルトラマン」について書くぞ。
書いてたら長くなっちゃったので、仕方なくここに放置することにした。
個人的な話なので、他の人がどうかとかは一切関係ないしどうでもいい。映画に合わせてわざわざ初代「ウルトラマン」を全部見直すようなダメオタクの言ってることだから、うっかり見てもスルーするくらいがいいと思う。
まあ、禍威獣が元気があってよかった。冒頭の禍特対前史は「そうくるかー!」と思ったし、各禍威獣のアップデート(そして流用)アイデアは面白かった。デザインワークスを買えていないのが悔しいが、一般流通に乗ったら買おうと思っている。
怪獣(もういいよね)デザインは「着ぐるみの制約を外したい」というだけあって多彩で刺激的だった。
特にガボラは予告編が卑怯にもミスリードを誘っていたので、全貌をスクリーンで見て「そうくるかー!」と思い、ウルトラマンを圧倒するパワーの格闘シーンを楽しんだ。直前の予告ですごいドリル回ってたから「えっグビラも出すの?」と一瞬思ったんだよなぁ。
ザラブもよかった 元デザインからそう変わらないかと思ったら、見えているのはポリゴンの表側だけみたいな、実体があるかどうか不明なぺらっぺらな立体の生物なんて、CGTじゃなかったらやろうと思わないよな。
メフィラスももちろんよかった。元のデザインを踏まえて鋭角に抽象化を大胆に進めたあたり、「初代」の造形デザインに携わったアーティストたちの個別の作品群を思うと「制約なしのエスキース段階っぽい!」という気持ちになった。
予告を観たとき一番危惧したのは「解像度だけ上げてシーン再現みたいなことになったら最低だ」ってとこなんだけど、それは完璧に杞憂に終わった。まあ個人的にはもっと炎を上げてもらって、低い視点から熱の揺らめきの向こうに怪獣を見たかったんだけど、ちょっと乾いた感じにしたいのだったら、それもまあなしではない。変化のあるアングルは楽しかったしね。
ただ、個人的に大事な話としては、これ多分ソフトを買わない。持っていたいと思える作品にはならなかった。
それは主に、僕が好きな「初代」の作品的な雰囲気はほぼ拾われていなかったためで、要するに解釈違いというやつだ。「シン」が最大公約数の「みんなが求めるウルトラマン」だろうと、僕は別にそうじゃなくてもいい。
「初代」は前企画「ウルトラQ」を引き継いでスタートしているので、ウルトラマンという全話通じた主人公的存在はいても、そのヒーロー性だけを前面に押し出して展開された物語群ではない。宇宙人であり、異星の文明においてある種の役割を持っており、同族も存在していることは描かれこそすれ、基本的には「未知」であり「神秘」の領域にいるものだ。それこそ「怪獣というカオスと対置されるコスモス」というコンセプトそのものの存在が「ウルトラマン」だ。
そんなカオスとコスモスが、何に介入してくる物語かといえば、言うまでもなく「普通の日常」である。日常に入り込んだカオスをコスモスという力で元通りに、あるいはちょっと変わった新たな日常に戻していくのが物語のスタイルだと言っていい。それゆえ非日常的なコスモスは、最後に地球を去るのである。
そういう、日常を侵食される怪奇の雰囲気が、この映画には微塵もない。さらに言うなら浸食される平穏な日常自体がない。描いてないけど日常なんですよ、なんてそんな馬鹿な。ほぼCGIで作った映画に「意図して描写しないで」どうやって日常が描かれるというのか。
だから、ほとんどが戦闘行動に終始する物語になっている。まあ、怪獣災害に悩まされる日々が日常なんだ察しろ、というのであればそれでいいんだけど、それはもう「初代」とは別の精神性の物語にならざるを得ないし、そもそも、そこまでの非常事態下にある日常として描かれてもいない。
怪獣対策がかっこいい、のか?まあそういう向きはある。けどもそのプロセスそのものは決定的に物語の尺が足りず、コンパクトに説明するべく煮詰めた故にルーティンとなってしまうし、怪獣の駆除に成功した事例は過去の事実としてしか描かれていないので、軽口たたいてるけど禍特対はそこまで優秀なチームなの?という風にも見えてしまう。
物語の尺というのは、かなりの部分で物語が表現できるものの範囲を決定する。本来が39話あったものの一部をピックアップしてきたとはいっても、そのほかの話数で培われた表現や了解を切り捨てられるわけではない。
そういった部分を大事にしないで、事件だけで構成したから起きている問題はこの映画の中に多くあるけども、特にキャラクターにそれを負わせざるを得ないせいで、イデほどの苦悩の深さとストレスを滝に感じられなくなっている。打ちのめされるほどのことお前この映画の中でしてないじゃん、何言ってんだよ、と言いたくなる薄っぺらさが終盤になって現れるのはどうなのか。いいのか。いいことにしようか。僕はごめんだけど。
浅見というキャラクターの扱いもひどい。尺が足りないせいでなんでそんなに神永に好意を持つのかが不明だ。もう物語の都合上そうしました、という感じにしか見えない。「初代」で同じ位置にいたフジは集団の中にあって常に自由な立ち位置にいる(時代性のある描写を強いられることはあれども)キャリアウーマンだった。だが浅見ときたらどうだ。能力集団の中で不在の神永を印象付ける役回りでしかないし、しかもそこにプロフェッショナルとは思えない感情まで入り込んでいる。この21世紀にもなって。
しかも。
巨大化させられ意思を奪われた挙句、スカートの中を衆目にさらし、それを野次馬に撮影され世界中に拡散され何度も閲覧される。もうこの描写自体が醜悪極まりないのだけど、映像拡散に関して気にしているのは顔が割れたことだけだという。動画がメフィラスの力で全削除されたらOKだという。正気か?そのキャラクター造形は大丈夫なのか誰も問わなかったのか。
異空間に隠されたβボックスを追跡するために浅見の「匂い」を手掛かりにしよう、というアイデアが出る。その前に自分の体臭を気にする描写がありつつ、禍特対の面々の前で神永に全身の体臭を嗅ぎまわられる。状況が状況なので仕方がない、という面白シーンのつもりなんだろうけども、誰もそれを少しも止めないのが、良識ある人間の社会という描写ということでいいのか。本当に誰もこれをおかしいと思わなかったのか。
この下品さが、僕には耐えがたかった。
なので、ウルトラマンはこれを守りたいと思うのかなぁ、という気持ちを抱いたまま残りを観ることになった。
僕は最初のほうで怪獣のデザインアイデアに関してはすごく感心して面白がったと書いたけども、画面の中での描写に関しては全く納得がいっていなかった。
何しろ、圧倒的に質感表現が足りない。そういう巨大なものが、光を受けて存在しているとは思えない平板さ。「こんにちは、僕CGIです!」そうか、可哀想にな。ぎゅんぎゅん動いているときは多少ごまかされるけども、動きが静まると途端に造形のエッジばかりが立って、心許ない胡乱な表現の面が露見してしまう。宇宙人はギリギリOKだが怪獣はダメだ。もしもこれWETAがやってたらいったいどんな怪獣がスクリーンで咆哮していたんだろう。
ゼットン、でっかいなぁ。火力すっげえ。僕が最終決戦で思っていたのはせいぜいその程度だ。だから僕はこの映画のソフトを多分(ということはかなりの確率で「絶対に」)買わない。
まあ解釈違いだけなら買ってたかもしれないけど、僕、それが偶然であっても許されずに人のスカートの中を見て喜ぶ趣味ないんだよ。劇場で目を背けていたんだぞ。わかるかこの苦痛。わかんないんだろうな。それが最大公約数だというならば、本当に願い下げだよ。
まあ、それはそれとして。
ウルトラマンをめぐる国際社会の動きは、ちょっと面白かった。宇宙人が人間の国家関係の、また個々の決定権者の未熟さに付け込んで謀略で絡め取っていく流れは、これどこで手打ちにするんだろう、とわくわくしていた。一方で「所詮日本はアメリカの属国だから」みたいに自嘲的に言ってみせるお決まりの現状認識があらわれてくると「またか、またその僻みか」という気になってしまう。新しいリアリティある関係性を提示したって罰は当たんないだろと思うが、どうなんだろうか。
「ヒーロー」ウルトラマンをある首尾一貫した存在として描く、というのはこの映画の独自性としてありなんじゃないか、と思った。ウルトラマンという「神」を僕はこう理解しました。そういう論文みたいなもの。僕は宗派が違うのでその主張を首肯するかは別だけども、愛のあり方としては理解する。
ただ「初代」において「ヒーローの有り様」はエピソードの中に内包しつつも、その存在もまた怪奇や神秘のうちにあったことを踏まえると、すべてを合理の中に収めるのは「現代的ではあるけども理屈が勝ちすぎる」のではないかと思うのだ。
僕もウルトラマンと怪獣に対して愛を捧げてきた時間がとても長いので、わかる部分があり、同時に絶対に認められない部分があるのだ。
手放しで楽しめて、手放しで褒め讃えられる人に幸あれ。僕は無理でした。
樋口真嗣が特技監督以上の権限で参加している映画は、劇場にもう観に行かないと思う。庵野の脚本が元凶だとしても、それをどうにかできない監督がなんで監督を名乗れるのか、僕には理解ができない。
1 note
·
View note
Text
ロボコップ(1987 ポール・ヴァーホーヴェン/2014 ジョゼ・パジーリャ)
2014年に書きかけたままの記事を6年後に書き足して仕上げるというひどいもんですが、まあそういうこともあります。とりあえず本編。
二つの「ロボコップ」があります。
ひとつは1987年の偉大なヴァーホーヴェン版をその基点とするシリーズおよび派生シリーズ。
もう一つは、先ごろ(2014当時)公開されたリブート版。
ここではその両方について話そうかと思います。ええ、もちろん僕はどっちも大好きです。
ヴァーホーヴェン版「ロボコップ」は、これを彼の最高傑作と見る向きも決して少なくないほどの伝説的な映画です。 恐らくまったく知らない映画ファンの人を探す方が難しいんじゃないかと思いますし、何度でも観返すヘヴィなファンも少なからずいるでしょう。
かく言う僕も年に一度以上は観返しています。
この映画の何が素晴らしい、はまあ挙げると切りなく出てくるわけですが、その後の文脈を形成した部分ということに限って言えば、やはり「機械化された人間はそもそも人間か?」であり、また「機械化された人間の立つべき位置とは」というとこなのではないかと思います。
ヴァーホーヴェン自体はSF的な観点というよりは「死して後、墓から再生する聖者」そして「聖者の孤独」というキリスト教説話的構図を強く意識していたようですが、それがガジェットや独特の「映像内映像」描写によって揺ぎ無いSF感を獲得するに至ったのは、この映画の類まれな幸運といっていいでしょう。
実際マーフィーの主観視点カットの寄る辺なさはいま観ても圧巻で、彼が売りに出された元自宅を訪れ、実景に記憶がフラッシュバックするあたりのどうにもならなさは、何度観ても涙を誘います。このあたりの「主観の実景に別の情報がインサートされている」イメージの先駆性はこの映画を特徴付けているだけでなく、このあと現れる主観映像を扱った映画の多くに影響を与えていくことになります。
とはいうものの、さすがにもう30年近く前の映画であることは否めない部分も多々あって、たとえばそれは「失われた身体機能を機械でサポートする」ということへの意識的距離感に大きく表れています。
ヴァーホーヴェン版のマーフィーの絶望は「もうこれは人間の体ではない」ということにも根ざしていますが、しかしそれは「高度に制御されたサイバネティクスの身体」が遠い夢物語であった時代の意識でした。聖人でありつつ、彼はフランケンシュタインの怪物でもあったわけです。
しかし今現在、失われた機能をどう代行するかの技術開発はさまざまなレヴェルで進んでおり、まだ現実に下りてきてはいないものの、そういった高度な技術でサポートされた人体を異形の化け物とは、もはや思わなくなりつつあります。少なくとも生体として回復を図る再生医療よりはよほどリアリティのある選択と言えるでしょう。
「攻殻機動隊」が「義体」という言葉を定義してから、全身サイボーグのイメージはそれまでとドラスティックに変わりました。義手や義足といった「部分」から、ほぼ「全身」へ。その延長にある「今」のイメージの上にリブート版「ロボコップ」は立っています。
オムニ社という企業が立ち上げたプロジェクトの産物であるロボコップは、ヴァーホーヴェン版では、そのままジャパンフォビアの気分を持っています。
「ジャパンフォビア」と言ってももうそれがどんなものかピンとこない人が多いような気がしますが、工程の多くをロボットによって自動化し生産効率をすさまじく上げた日本の自動車をはじめとする産業が、驚異的な貿易黒字をもたらした時代がありました。80年代前半のことです。
勤勉で会社のためにどんな労苦もいとわないロボットのごとき日本人の働きぶりも相まって、アメリカの自動車は低価格で高品質な日本車に圧倒され産業ごと駆逐されるのではないかという恐怖がアメリカの人々の間に渦巻きました。―現実的にどの程度圧倒されたのかはさておき、旧態依然とした工場は閉鎖が相次ぎ失業者があふれ―といったイメージが喧伝され、日本はミステリアスなだけでなく理解不能で恐ろしいという印象が共有されました。ロン・ハワードの「ガン・ホー」はまさしくそういう時代を描いた映画ですね。
マーフィーが戻ってきて目覚ましい働きをすると、生身の警官たちが「あんな風に働けない俺たちはいつかお払い箱にされる」とふて腐れて集団的反抗をする、というのは まさしくそういう気分を引き写したものです。今でも自動化されることで働く場所が失われる、という不安はどこにでもあるものですが、今は「いつの間にか失われる」で、この頃は「鋼の腕で追い出される」という感じなのです。
リブート版においてはそういう実力行使的な雰囲気はすさまじく希薄です。なぜならば、言及したように人の居場所は「いつの間にか失われる」からで、その理由を語ることからこの映画は始まっています。そうです、「ED209とロボット歩兵、航空ドローンによる相互連携が実現するシステマティックで人的被害の出ない都市制圧」の風景です。その高度な判断、対応速度、制圧力の前に人間の入る余地はありません。むしろ都市戦においては「人間を主戦力とするがゆえに、最終的にはロボットを端末とするシステムに勝てないのではないか」と提示されます。
現実に、前線で兵士を戦わせるリスクに対し、とてもデリケートになっているのが現代の先進国の軍事です。今や無人機は様々な種類が戦闘の現場に投入され、自国(まあ主にアメリカですが)の兵士を死なせることなく、自国の兵士の肉体的鍛錬を無に帰することなく作戦を遂行します。そんな今だからこそ、ネットワークで接続されたロボット群の作戦遂行能力には一定以上の説得力があり、この���画の中でも「治安維持のような危険な仕事に人間は従事するべきではない」という論調が幅を利かせている、と描写されます。冒頭のニュースショウのホストはまさにそういう論調の急先鋒でした。
しかし、その一方で「『判断』は人間がすべきである」という考え方も根強く、米国内での大規模なロボット治安維持システムの導入はある法律によって阻まれていました。今回のロボコップはこの法律「ドレイファス法」をクリアするために半ば人間、半ば機械のキメラとして第二の生を受けます。
人間の機能としては、判断をするべき脳がありさえすればいい。
人間とは脳と、人間であることを主張し規定する程度のパーツのことだ。
マーフィーが、自分の体がどうされてしまったのかを知る場面の絶望感は、そのブラックコメディ的な絵面も相まってすさまじいものがあります。それは、彼にはアイデンティティと自由意志が(仕方なく)残されており、不幸にも「自分」を確認できてしまったからです。そして、彼は彼の意志で生存しようとしたわけではない、ということも彼の絶望に拍車をかけます。
死に瀕した家族の生還を願うのは家族としては至極真っ当で、もしそれを可能にする手段があるのなら、どんな形ででも回復してほしいと願うのも至極真っ当です。「この方法でしか助かりません」と言われれば、たぶん多くの家族がその方法を選ぶでしょう。救われるべき本人の意思確認ができないのであれば、意思決定は家族に委ねられます。かくて彼は生還を果たしました。
ですがそうして救われたいのちがその意思でこう口にするのです。
「殺してくれ」
と。
自力で死ぬことはできないいのちが懇願する死。
しかし、高度なテクノロジーと多大な投資により維持される彼の体にとって自由意志の居場所はほぼありません。もちろん死ぬことなど許されはしないし、選択的に行動することもできません。「意思決定の事後承諾」という矛盾すらコントロールの下にあり、そしてそれは彼に知覚されません。
しかし彼がロボコップとして甦ったから、そうなのでしょうか。
違います。
「社会」という巨大な投資により運営されるシステムに依存して生きる我々のすがたは、彼と大差ありません。 我々が自分の意志で決定できることは実は社会が用意した選択肢の範囲で自由なだけであり、生も死もそのはじまりから終わりまで、決して好き勝手にできることではないのです。
恐るべきさまざまな手続きを経て社会に参加し、退場するときもまた手続きを必要とする。それが社会に生きる我々であり、その姿を端的に戯画的に悪趣味に絵にしたのがリブート版ロボコップだといって過言ではありません(個人的にこういう悪趣味さは大好きです)。
リブート版はロボコップの身体に関して「ガジェット」としての描写を大幅にアップデートしています。ネットワークに接続するものが多くなった今、むしろ自然にそうなってないとおかしい、というレヴェルで外部からコントローラブルな道具として描かれます。
現実問題モニタできない精密機械なんて、運用面でも保守面でも危険極まりない。当たり前のことです。機能が高ければこそ「コントロールの自主性による危険」をガジェットは常に内包しており、危険が他者に及ぶ可能性があれば、システムとしてそれを回避することを考えるし、技術としてそんな外部コントロールや、フェイルセーフシステムの強制介入で自主性を剥奪することもわりと普通なのが今現在。「自由意志の選択」を巡る部分に関してもはっきりと劇中こう言っています。
「彼は主役は自分だと思っているが、それは自由意志という名の幻想だ」
言葉にするって大事なことです。
「人間の意識とか感情って、割と簡単に薬物でコントロールできるものなんだって知った」
という友人の言葉を僕は思い出しましたが、「そうである」ことを宣言することで生じる意味というものがあります。��れもその類いで、戯画として描かれてはいますが「現実的」です。
昨今を考えても、人間一人一人の行動をどこまでモニタできるのか、が社会的に重要なトピックになっています。システムとしては個人の上部構造としての社会として振舞うことが合理的である以上、「社会を成り立たせるコントローラブルなガジェットとしての個人」でいてくれないと困る、というのはまあ偽らざる本音でしょう。そんな「普通」の気分がこの映画には蔓延しています。
ヴァーホーヴェン版とリブート版が大きく違うのはここです。
およそ30年のあいだにあった技術革新やそれが可能にした社会の変化、それに伴って「個人」の自己認識も当然のように変わります。なにが悲劇か、なにが救いか、も「社会」との関わりの中で描けば変わってしかるべきです。
「暗黒メガコーポvs.ロボコップ」
は
「社会の合意形成vs.ロボコップ」
と構図を変えました。リブート版はそれゆえに、より「個人」マーフィーの側面を強く押し出し、ラストシューティングの意味合いもがらっと変わりました。
僕個人的には「そういう奇跡みたいな部分をある種の『望み』として見せるのって『もうかなりマシンになった彼』の描写としてどうなのかな」という気持ちがないではないんですけど、「警官」ではなくまず「個人」として続いていく彼の行く末を考えれば、システムを意思がねじ伏せた瞬間と、そこから神の視点に移る流れはまぎれもない祝福の場面でありました。彼は聖人ではない。ヒーローは正義を体現しこそすれ必ずしも聖人ではない、というのは、これも30年の大きな変化ですね。
リブート版はそうなるに至る手続きと、その後をニュースショウで語る構成になっていましたが、現実にはこの映画のあとトランプが大統領になってマスコミとすったもんだやるのだなぁ…と考えると、なかなか感慨深くもありますね。
人体をパーツの集合体として、交換可能で維持コストのかかるものってことで徹底した映画だと「レポゼッション・メン」という壮絶な映画がありますが、リブート版は絵面にそれに近いドライさを感じました。これも30年の医療の進歩が変えた認識の違いで、要するに両方観直して比較してみようぜ、というとこに落ち着くわけです。僕のお薦めはもちろんヴァーホーヴェン版→パジーリャ版ですが、思い入れの強い方から観るのももちろん良いです。
アメコミ勢にはフランク・ミラーが脚本をやってる「ロボコップ2」もお薦めです。こちらはなにげに「人間の脳が人間に本来ない機能を持つ機械の体に適合してコントロールする」ところがしれっと描かれていて、ストップモーションの味わいも深い逸品です。まだ観てない方はよければ是非。観てても是非。
0 notes
Text
リンカーン(2013 スティーヴン・スピルバーグ)・リンカーン/秘密の書(2012 ティムール・ベクマンベトフ)
お話は見ればわかるから割愛…したいのだけど、アメリカの歴史なんて社会人だってそうは知らんだろうどうせ異国のことだしな、と言わんばかりに冒頭スピ本人が出てきて「日本の皆さん、この映画はこんな時代、こんな情勢下でのお話ですよ」と背景の概略を説明したのに驚いたので、ざっくり書きます。
1865年。
未曾有の内戦「南北戦争」の開戦から4年を経て、疲弊しきった北部アメリカおよび南部アメリカの両陣営が内戦の落とし所を模索しているその時期、国会上院で審議されるある法案を巡り政治家たちが動いていた。
「米国憲法修正第13条」。
恒久的な奴隷制度の廃止を目的としたそれは、実に取り扱いの厄介なものだと取られていた。実際問題政権政党である共和党の中においてすら、急進的な奴隷解放派と保守派の間には深い溝があった。国内の危機的状況を収拾したいと思いこそすれ、長らく続いた差別的観念を一から改めるのは別の問題だと多くの人々が思っていたし、解放された後新たに「市民」となる黒人たちにいずれは参政権も与えねばならないのではないか、あまつさえ女性にまで参政権を与えることになったとしたら―という危惧も根強かった。まして野党民主党においてをや、である。
アメリカは疲弊しきっていた。何か理由をつけてでもこの戦争を終らせねばならないという雰囲気が蔓延していた。しかしリンカーンをはじめとする解放論者は、この雰囲気を強く恐れていた。修正条項はすでに下院は可決で通過していたものの、上院での審議で可決されなければ、これは通らないかも知れない。この厭戦気分の中で、単なる政治取引の方便として「奴隷解放」が宣言されてしまうかも知れないからだ。それは口約束の域を出ず、仮に一時解放されたとしても法の拘束がなければ早晩元の木阿弥となるだろう。それだけは断固避けねばならない。何としてでも、南部からそれが提案され、北部の指導層が待ってましたと食いつくより前に国会で可決し、しかる後に批准を求める手続きにしなければならない。
アメリカの未来を拓くことはおろか、南北戦争を継続してきたことの意味さえ失わせる最悪の事態を、政治の領分で間違いなく解決せねばならない。
審議まであと半月あまり―。
とまあ、こんな状況の中で、いかにして賛成議員の数を確保していくのかを描いた凄まじく地味な映画なわけですが、ギャグシーンは(スピだから)多少あるものの緊張感が漲っており、ダレる部分は一切ありません。群像劇として、あるいは家族の物語として実に高密度であり、何よりも「政治の射程と速度」に関してこうまで正面から向かった映画はそうはないのではないでしょうか。
アメリカにおいてこの映画が評価された背景には、偉人の物語であるというより以上に、昨今の国会審議の状況がこの歴史的状況に近しいからだ、という話があるのだけれども、実際に観てみれば容易に思い当たるでしょう。公開当時の日本の状況もそう変わりはなかったし、政治に対する反応一般とすればより悪かったかもしれません。
射程に関して見識の低い批判が繰り返され、速度に関して無頓着な非難や罵倒が繰り返される。固定観念と脊髄反射と自分を棚上げした醜い差別意識を丸出しにして政治を語ったつもりになれる程度の、あらゆる世代に蔓延るお目出度い人々が大声でがなり立てる。
そうじゃないんだ、それじゃだめなんだ、ということを現実の時間感覚の中で認識するのは大変です。政治の時間は長い。ある方向性に定めたまま時間をかけないと出ない結果がある。それを確認できないかもしれないという不安が、ちょっとした失策をあげつらう罵声となり、どうせ意味なんかないよという根拠のない冷笑になる。
政治を恐れ、不安に駆られる、そんな僕らのためにこの物語は、この映画はあります。過去のアメリカの話だけど、どうしようもなくアクチュアルな話題です。政治を舵取る人々が僕らと同じように人である、そんな息吹を感じることができます。
「政治を信じられない」と切って捨てられるほど、政治について、政治を行う人々について興味を持ち見識を備えているでしょうか。「政治家はさぁ」と誰も彼も安易にひとくくりにして考えることを放棄してはいないでしょうか。望むと望まざるに関わらず国の根本である「憲法」の重みと、積み上げた歴史のことを軽んじてはいないでしょうか。
今これが作られたのは、きっとそれなりの理由があるのです。
まあそんな感じの映画なので、ダニエル・デイ・ルイス演じる長身痩躯のハンサムなリンカーンもまた、疲弊しきってストレス全開のような姿で常に画面に現れます。常に斜めに傾いだ感じに立っていて、痛々しいことこの上ありません。
南北戦争を扱っていながら戦闘シーンはほぼなく、しかし戦争の空気が充満しているのが実に特徴的で、粒状感を効かせた撮影もそれを強力に後押ししています。
エンドロールにずらりと並ぶ資料協力をした個人・団体の数を見れば納得の「時代の風景感」も圧倒的です。この映画の地味さは、そういったものに裏打ちされた凄みに満ちています。
「やっぱり感覚的に政治ってよくわかんないよ」「憲法を変えるってどういうこと?」という人にこそ観て欲しい映画です。というかそういう不安が少しでもあるのなら、こっそりでも観ておいて損はないと思います。
こんな今だからこそ。
さて、この「リンカーン」の話をした以上、もう一つの「リンカーン」についても話をしておかなければなりません。
スピの方は「リンカーン(斧なし)」、こっちは「リンカーン(斧あり)」。
その名も「ヴァンパイアハンター・リンカーン」。邦題は相変わらずセンスないのでガン無視したいのですが、エントリのタイトルには仕方なく入れました。
あの「高慢と偏見とゾンビ」のセス・グレアム・スミスの長編小説第二作を原作とし、かつ原作者本人による脚本で「ナイト/デイ・ウォッチ」「ウォンテッド」のティムール・ベクマンベトフが監督した伝奇アクション映画です。
お話は割愛したいがざっくりと言っておかねばならないでしょう。
要するに「リンカーンは実はヴァンパイアハンターだったんですよ」という話です。奴隷制のバックには新大陸に根付いた吸血鬼社会の収奪構造があった。母の死からその秘密に触れてしまった若きリンカーンは、吸血鬼社会の伸長を危ぶむ吸血鬼ヘンリーから闘う技を教え込まれ、子供の頃から使い慣れた手斧を武器に恐るべき支配者へ戦いを挑む。やがて表面化していく対立が南北戦争となってアメリカ全土を巻き込み…というようなおはなし。
原作は「リンカーンの手記」というその存在が眉唾物の古い紙の束を渡された小説家志望の青年がそれを読み進めていくうちにアメリカ史の裏に潜む闇と、闇との果てしない暗闘を知ることになるというもので、よく知られているリンカーンの伝記におけるこの行動の裏には実はこういう事情があり…というかたちで史実と虚構が緻密に組まれた怪作でしたが、映画脚本の方はより外連味を増し、バトルヒーローとしてのリンカーンを前面に押し出したアクション大作となっていました。
監督のベクマンベトフと言えば「明らかに何か間違ってるんだけど映像の力で『そうなんだなぁ』って思わされてしまう」的なイリュージョニストで、一方で効率よく映像を積んで行って簡潔に表現することも巧みという才人です。その手管の見事さは映画開巻、「モール」と呼ばれる国会議事堂前の長大な広場を、ワシントンモニュメントでワイプしながら急速に時代を遡らせ、槌音の響く空き地へと変貌させるというカットですでに見て取れます。もともとが3D上映だったので奥行きを効かせた構図が特に多いけども、元来それは彼の得意とするレイアウトなので恐るべき安心感です。
ダイナミックなアクションと過不足ない状況説明、そして程よく制御された情報により、原作小説の雰囲気を残しつつ、より頭の悪い、いい感じに下世話な映画となりました。原作との差異を比較して楽しむ、というおまけまでついて。
まあ何しろ斧ですよ。リンカーンといえば斧。貧しい開拓農民の家に生まれて父を手伝い斧を振るって土地を切り開き、やがて長じて弁護士となり…という立志伝中の人物なわけですが、そのシンボルといえば昔から斧と決まっています。幼年向け伝記だって大抵は斧の話を外しません。
そこから一歩進んで、「リンカーンといえば斧であり、斧こそがリンカーンなのだ」というとこまで致命的に踏み込んでしまったのがとりわけこの映画版。原作からの最大の改変ポイントもそこで、政治ではもはや解決できない。奴らに実力で対抗せねば!と再び愛用の手斧を持って吸血鬼と立ち回るリンカーンの生き生きとした姿といったらありません。スピの真っ当な表現とは真逆です。彼の人生とはまさに斧に集約されているのだと言わんばかりです。
手斧映画は数々あれど、その中でも歴史上最強クラスの斧使いだと言って過言ではありません。ぶっちゃけそれだけを期待して観たっていいくらいの映画です、冗談抜きに。あまりの見事さに僕は劇場で大喜びしていました(僕が喜んでいる、というのは別に何の価値も付与しないわけですが)。
リンカーンの扱いが原作とそう変わるので、お話の細部も収まり方も方々異なっています。だがそれは原作の精神をどこかに置き忘れたわけでは別にありません。
終盤の大逆転を導く仕掛けの一つに、実在した黒人奴隷を秘密裏に逃がす逃走経路およびそのシステムが用いられるのですが、これは原作では触れられていない要素で、翻って原作はそれが史実に忠実であるがゆえにこのネタを入れる余地がなかったということなのかも知れません。しかし、アメリカ史をそれなりに押さえていればああ、と膝を打てるというのは、まさしく原作が持っていたテイストで、映画は原作のifとして成り立っていると言えるのです。
だから、熱心なファンなら両方等しく楽しむのが嗜みなのだ、と言っても多分間違いではないでしょう。
そして、たぶん原作から大幅にお話のつくりを変えたのは「リンカーン(斧なし)」が控えていたからなのだろうとも思われます。スピがド正面から真っ当な映画を作るであろうことを考えたら、不真面目な方は不真面目を徹底すればいい、と思うのは当たり前です。
僕らは真面目も不真面目も運良く並べて楽しめる。これはとても幸せなことといっていいでしょう。
というわけで、映画「リンカーン」は斧の有無に関わらず実に面白いのでどちらも、できれば両方どうぞ。
0 notes
Text
The DEAD/ゾンビ大陸アフリカン(2012 フォードブラザーズ)
以前ある飲みの席でゾンビ語りになり、そのときに薦められたのです。
予告編は見たことがあったもののとうに劇場公開は終わっていて、知らぬ間にソフト化もされていて、飲み会のときのことを突如思い出して観たくなってレンタルしてみたら、あまりの素晴らしさ、聞きしに勝る傑作ぶりにソフトを購入してしまいました。まあそんなことはどうでもいいんですが。
日光に照らされとめどなく広がる不毛の大地。
黒いマントを着てAKを携えたその男は、行き会った「それ」―片足を酷く損傷し、普通に歩くのもままならない―をやり過ごし、歩を進めた。
程なくして軍服を着た「それ」と遭遇すると、迷うことなく頭部を撃ち抜いた。倒れた「それ」の衣服を注意深く物色する。拳銃、使える。紙幣、役に立たん。数発の実包とマガジン、これは願ってもない。ポケットをまさぐるその間も周囲への警戒を怠らない。手に入れるべきものを全て手に入れ、再び移動を開始しようとしたとき、さっきやり過ごした「それ」が視界に入った。「それ」はずっと不自由な歩みで、しかし諦めることなく追ってきていたのだ。畜生め。
彼はほんの数日前、機上の人だった。非常事態に際し撤退する米軍とともに、このアフリカを後にして母国へ帰るはずだった。はずだったのだ―。
というわけで、理由は不明だけれどもアフリカでゾンビ大発生。折りしも部族間闘争の只中にあった西アフリカ某国から駐留米軍は脱出を図るも、算を乱して飛び立った機はガス欠により墜落。軍属エンジニアの主人公はかろうじて一命をとりとめた。浜に、野に、林に、農地にうごめくゾンビにめげそうになりながらも、長距離移動の足を求めて崩壊した集落へたどり着く。そこで出会った黒人兵士。彼はその集落の出身者で、哨戒任務の途中妻子の消息を確かめに来たのだった。二人は利害の一致を見、残存兵力が集結しているという基地へ協力して向かうことになる…というおはなし。
仕立て方としてはロードムービーです。ロードムービーの要件は、通過していく風景にほぼ負っているわけですが、この映画はすごい。何がすごいってゾンビが完全に風景の一部と化しています。ゾンビ映画の多くは都市部でのゾンビ発生と、彼らとの闘争を扱っています。言わば人類が最適化した環境の中に異物として発生したゾンビを扱っているわけです。
ですが、この映画において人類に最適化された環境などほとんど登場しません。夜を照らす街灯も、舗装された道もなく、あるのはただひたすらに過酷な自然。そして恐ろしいことにゾンビは自然の側に立っています。沈む夕日の中に佇むゾンビのシルエットは、まるで野生動物の面持ちです。
彼らに文化はありません。ただ、人類を捕食するという行動だけ。彼らは人類のように文化に制御されません。いついかなるタイミングからでも、捕食のチャンスを窺っています。さらに過酷に牙をむく自然に対して、人類のできることはあまりに少ない。この野性の摂理の中にあって人類を人類たらしめるものとは何か―。
人の形をしていながら人ならざる動く死体への恐怖は、姿に反して意思疎通が不可能であるという(たとえば異民族や異教徒のような)「理解できない相手」への恐怖と同根であり、そういったものが集団となって襲い掛かってきたなら、成すすべもなく蹂躙されてしまうのではないか、という恐怖でもあったわけです��、そういった「古典ゾンビ」的構図は近年だいぶ表からは姿を消しました。
その一方でほぼ主流になっているのは「ゾンビのいる環境」を自明のものとした物語です。新たな環境要素としてゾンビが加えられ、従来の環境が一変する。ライフラインが断たれ、物資の供給がストップし、情報も流れてはこない。その中でいかにしてサヴァイヴするか「文化を成し遂げるか」が、骨子となっています。問われるのは個々の人間性であり、そんな人間同士が文化を成り立たせるためのギリギリの信頼関係であり、そして「生と死の界面」です。
傑作「ゾンビーノ」における問いかけ「ゾンビって生きてるの?死んでるの?」に対し、明瞭な答えを出しえる者は恐らくいません。語弊はあるが、これはもはや哲学的ですらあります。そういう領分にゾンビ映画は突入しています。
この「ゾンビ大陸アフリカン」はその中でも極北に位置する一本だと言っていいでしょう。なぜならば、人類から文化を剥ぎ取ったものがいかに「野生」であるかを映像で雄弁に歌い上げているからです。ゾンビという野生に立ち向かう人類という野生。生存のための戦い。
そして、そうでありながらも「人類が自然から人類として立つために必要なもの」とは、ということを語りつくしています。
いや、正直「ゾンビ大陸」で「アフリカン」でしょ。ヤコペッティかよ、暗黒大陸って言っちゃったよこの期に及んで!とかそういう際物的な何かだと思っていたのです。原題はシンプルに「The DEAD」だし。でも、観終わってみるとこの邦題は実にツボを心得ているというか、巧みであるな、と納得してしまいました。
うん、観ない人は観なくていいんだよ。観もしないで価値がないなんて言う奴は観る必要ないんだよ。どうせ何にもわかりゃしないんだから。そういう篩落しが、タイトルの段階ですでにされています。それを乗り越えた人間だけが観ることができる奇跡のように美しい地獄。凄惨な詩情。
道に転がる砂利のように、野に繁茂する草のように彼らはそこに佇んでいます。そもそもここは人間に約束された領域などではなくて、ほんの借り物に過ぎないのだ、という圧倒的な風景と、ゾンビ。
僕はきっと、その風景を見るために何度もディスクをドライブにセットすることになるのです。
だって、もうすでに7回観てるんだもの。
あ、アフリカのゾンビは純粋に夜見えないので恐いです。近くに寄った時ようやく白目剥いてるのが見えるのもすっごいやな感じ。そういう向きでも普通に面白いですよ。
0 notes
Text
はじめに(移植版)
どうも、初めての方は初めまして、そうでない方はお久しぶり。斎かなめです。
ここは、僕が観た映画について、適当にだらだらと愛を語るだけの、どうということのないtumblrです(前に書いたやつからの引越しなので適当ですがw)。
ですので、見かけのカスタマイズとか多分そんなにしないと思います。すんごい適当でやる気がないように見えるでしょうけども、まあそんなことはわりとどうでもいいのです。ここはだらっと語り倒したいだけの場所なのですから。
というわけで「SOMEWHERE OVER THE SCREEN」。
スクリーンの彼方に。
なにがあるんでしょうね。
なにがあるのかはわからないけども、少なくとも胸躍る景色がいつもそこにあることだけは確かです。
だから僕は映画を観に行き、また、自宅でも映画を観ます。 新作旧作問わず適当にいろいろな作品を何度も繰り返し観ます。
取り上げる作品のジャンルは比較的でたらめなので(まあ偏りはありますが)、ジャンルファンにはもしかしたらあまり面白くもないかも知れませんね。
まあでも、映画は観てなんぼです。
「映画は数観ることが必要である」といったようなことを、僕の私淑するある映画監督は言いました。 「映画は二度観る必要がある」とも。
それが映画でありさえすれば、少なくとも僕には観るに値する理由となります。観て良ければ何度でも観るし、釈然としなければふと思い出したころに観なおすこともあります。
そしてまた、「映画は語られることに意味がある」とも言いました。
その映画がどのように面白いか、愛すべきところがあるのか、 そういう話をするのが僕は好きです。尊敬すべき僕の友人もそういう人間でした。まあ彼のようにはいきませんけど、僕もそろそろあたりかまわずそういう語りをしようかと思います。
それでもし、「そんなに言うならじゃあひとつ観てやろうか」という気になってくれたのであれば、それに勝る喜びはありません。
様々な映画があって、それは様々な世界に開かれた窓のようでもあります。人は居ながらにして、スクリーンという窓から、彼方の景色を観ることができるのです。
であれば気軽にちょっと変わったものを観たって罰は当たらないでしょう。さほどのコストがかかるわけでもありませんしね。
更新はまあ、ぼちぼちですけども、その辺はご容赦ください。
さて、 最初の映画は――。
1 note
·
View note