#待っているときに自然と生じる感情はふだん私たちが何を気にしているかということの表れだ無視せず認識し向き合ってみると発見がある
Text
「彼が会いに来ない理由」
「彼が会いに来ない理由」
Why he doesn't come to see me.

ーChapter1
時刻は午前7時。
暗い部屋の中。一際青い光を放つPC画面の前、無精髭を生やした男が疲労感を露わに椅子にもたれかかっている。ホブ・ガドリングは窓の隙間から差し込んでくる冬の朝日に目を細めていた。重い体を引きずりキッチンに向かったホブは棚からマグカップを取り出しコーヒーを淹れるための湯を沸かす。大学で使用する資料の作成や担当する生徒たちの課題の採点、その他雑務を全て終わらせた彼は霞んだ目を擦りながらポットの湯をマグカップに注いだ。
(結局こんな時間になるまで作業してしまうとはな…)
苦味の強いコーヒーを胃に流し込みながらホブは心の中で呆れたようにそう呟く。今は、ゆっくり眠る気になれなかった。というよりベッドに横になり眠るまでの、あの時間が訪れるのが嫌だったのだ。ここ最近、その時間になるといつも同じことばかり考えて心が沈んでしまう。ホブを悩ませている原因は、彼のとある“友人”だった。
彼とは知り合ってから600年以上が経つ。不死身になってから数え切れないほどの人と出会い別れてきた、そして自分が存在し続ける限りこれからも同じことを繰り返すのだろう。だが彼だけは、100年という月日が経つたびいつも変わらぬ様子で目の前に現れてくれた。最初は、その存在の奇妙さに戸惑いを隠せなかったが、そんな彼がいつしか自分にとって安心できる居場所となっていた。彼だけはこのホブ・ガドリングという人間を知ってくれているのだと、この自由で孤独な不死身の男がありのままで過ごせる相手なのだと、そんなことを心のどこかで感じていたのだ。だが、そんな彼との交流は1889年を最後に一度パタリと途切れてしまっていた。原因は実のところ自分にはとんと関係のない事柄だったことがつい最近判明した。しかしここ1世紀ほど自分のせいだと思っていた。それはひょんな一言、側から見れば喧嘩に発展するとは思えない一言だ。だが彼の性格を考えればそれは怒らせるのに十分なものだったと会えないショックを抱えたホブはずっと反省していた。そんな思いを抱えながら、いつ現れるのかわからない、もしかするともう現れないかもしれない彼を来る日も来る日も待ち続けていたのだ。
そして数ヶ月前、まだ夏の暑さが身に張り付く8月の頃。微かな希望を胸に日々を過ごしていたホブの前に彼はついに現れてくれた。やはり変わらぬ様子で、しかし以前よりどこか温かみのある表情と、そして彼の口から出る“友人”という言葉がホブの心を温かく包み込んでくれた。自分がどれほど幸せな気分だったか、この先忘れることはないだろう。
ビールを1杯注文して乾杯をしたあと、彼は落ち着いた声で600年来の友人に向けて初めての自己紹介をした。
彼の名前はモルフェウス。エンドレスのドリームという存在で、夢の王国「ドリーミング」の支配者。そこは眠りの先にあるもう1つの世界で、人間の心の奥底が具現化された夢の世界だそう。彼はドリーミングの王として、人々の夢やそれに関連する全てのものに関して支配力を持っている。目覚めると忘れてしまうが自分達人間は夢の中で彼に会っている者もおり、彼が初対面のホブの名を知っていたのはそういうことだった。そして100年ほど前に起きていた嗜眠性脳炎の騒動、あれは人間が彼を捕縛・監禁したことで彼が王としての責務を果たせなかった結果引き起こされていた。彼がホブとの約束に来られなかったのもこれが原因だったのだ。目の前の友人が概念の擬人化だという事実にはかなり驚いた。しかしそれ以上に、その友人が100年以上もの間、自由と尊厳を奪われ孤独な日々を送っていたというショックにホブはしばらくの間言葉が出なかった。
淡々と自分の素性について話した後、黙り込んでしまったホブを前にモルフェウスは不思議そうにその様子を伺っていた。それに気づいたホブは何か言わなくては、と回らぬ頭を必死に動かした。彼にかけたい言葉はたくさんあれど、今何を伝えたいか…わずか数秒の間、脳内でぴったりな言葉を探し回った結果ホブの口から出たのは
「…ハグしていいか?」
お前は本当に600年以上生きてきたのか?時々そう自分を疑いたくなる。これだけ生きているのだからもっとマシな言葉の引き出しがなかったのか、と呆れるが時すでに遅し。口から出てしまった言葉はもうどうしようもない。前にも同じような失敗をして痛い目にあったのにまたもや俺は…と嘆きたくなる気持ちを今は抑え、恐る恐る向かい側に視線を向けるとそこには意外な光景があった。困惑の表情を浮かべたモルフェウスが、少し戸惑いながらもこう言ったのだ。
「あぁ…別に、構わないが」
無言でスルーされるか、奇怪な視線を向けられると思っていたから、受け入れられたのは驚きだった。
少し安堵の表情を浮かべたホブは、ゆっくりと席を立って向かいに座るモルフェウスの側に向かった。
「待て、今ここでするのか?」
「えっ、あっ…ダメか?」
まだ俺の頭は回っていないらしい。ハグしていいと言われたからと言って、この内気で物静かな、目立つことが好きだとは到底思えない彼が昼間の酒場でハグなどハードルの高い話だろう。彼にそんなフランクさがないことはこれまでの経験からも明らかだった。ハグを受け入れられたことに心が弾んでつい思考より行動が先をいってしまった。
「そ、そうだよな。すまなかった、君にハグしていいって言われると思ってなかったから嬉しくてつい。じゃあまた別の機会にでも…」
「別にダメとは言ってない。少しその、確認しただけだ…」
「えっ?」
そそくさと席に戻ろうとしていたホブは驚いて振り返った。そう言ってそっぽを向く彼はいつもと同じ静かで冷たい雰囲気を纏っているが、その耳が少し赤みを帯びていることをホブは見逃さなかった。
「そんなところで突っ立っていては目立つぞ」
至って冷静なモルフェウスの声にハッとする。以前と変わらぬ、ミステリアスで孤高な雰囲気を纏う彼。だが、どこか…少し丸くなって戻ってきた彼にホブはすっかりペースを乱されていた。
「そう、だな。じゃあ…」
ホブは改めてモルフェウスと向かい合い、席に座る彼に合わせて少し身を屈めた後そっと腕を回した。雪のように白い肌から温かみを感じる。
捕らえられていた間、彼はどれほど苦しい思いをしたのだろうか。100年以上もの間監禁される苦痛は想像を絶するものだろう。自身も魔女と疑われ捕らえられた経験のあるホブにとってはなおさらそう感じられた。自由と尊厳を失い、自分の居場所にも戻れず、大切な存在を奪われ、悲しみと憎しみを抱えた続けた彼を思うだけで胸が張り裂けそうだった。無意識に抱きしめる力が強くなる。
「本当に、戻ってきてくれてよかった」
ふと口から出た言葉。きっとこれが自分が本当に伝えたい言葉なのだろう。
「本当に無事でよかった」
「身体は、大丈夫か?」
「今は、辛い思いをしてないか?」
「自分の国にはその後戻れた?」
「ちゃんと眠れてる?」
「ご飯も食べてるか?」
彼を抱きしめて、温もりを感じて、ホブの中からゆっくりと言葉が溢れ出てきた。
そんなホブの様子に、最初は緊張していたモルフェウスの表情も緩んでいた。1つ1つの問いかけにただ「あぁ」と頷く。どこか安心した表情で、柔らかな声色で。ただ最後の問いかけに関しては例外だが。
「食べれてないのかッ?」
突然身を起こし心配した顔でそう言うホブにモルフェウスはくすくすと笑った。
「私は人間のように食事をせずとも大丈夫だ。それに元々、そんな食事を好むタイプではないしな。全く食べない訳ではないが。」
「まぁ確かに、君と会い始めて以来1度たりとも食事をしているのを見た試しはないが…。でも、今日ぐらい好きなもんを好きなだけ食べよう、俺が全部奢る!あれだ、17世紀に君に奢ってもらっただろう、そのお返しに!」
「だがそう言われてもな、好きなものか…。ホブの好きなメニューは何だ?」
「えっ、俺の好きなメニューか?あるけど、自分のじゃなくていいのか…?」
「私は特に好きな食べ物というものが思いつかないし、それにこの店のメニューもよく知らない。君はここでずっと私のことを待ってくれていた、ならどんなメニューがあるか詳しいんじゃないのか?」
「そうだな、メニュー表を見なくてもなにがあるか分かるぞ。なんたってかなりの常連だからな。」
「なら決まりだ、君のおすすめのメニューを頼もう。久しぶりの食事だ、せっかくだし君の好きなものを私も食べてみたい。」
笑顔を浮かべながら話すモルフェウスにほっとしたホブは、席に戻るなりメニュー表を開いて「この店はこれが美味い」「この料理はこの酒と合う」「あれは昔に比べて少し味が変わった」と楽しげに話し続けた。ときどき、穏やかな顔でこちらを見つめるモルフェウスにドキッとしながら。
―――
午後7時、窓の外には夕焼け空が広がっている。テーブルの上は綺麗に平らげられた料理の皿と空になった何杯かのグラスで埋まっていた。100年以上の空白を埋めるように2人はいろんなことを語り合った。今までと変わらずホブが喋っていることが多いが、モルフェウスが自分のことについて教えてくれるようになり自ずと彼からも多くの話が聞けたことは嬉しい変化だった。
でもまだまだ話し足りない、もっと一緒に酒を飲みながら他愛もない話を続けていたい。彼との楽しい時間はあっという間で、ホブはこの時間に終わりが来ることを考えたくなかった。今日が終わればまた100年後。その100年はなんだか今までよりも長く、途方もない時間に思えた。
「そろそろ出よう。」
モルフェウスの一言で我に帰ったホブは少し重たくなった心を隠すように明るく返事をし、会計を済ませて店を出た。
夕焼け空は一層色を濃くし、遠くの方には星がちらちらと見え隠れしている。ホブは名残惜しさを隠すように笑顔を作り、隣を歩く彼に話しかけた。
「今日はありがとう、君が会いに来てくれて本当に嬉しかった。もしかしたらもう会えないかもなんて少し思ってたから。」
「私こそ…本当に感謝している。君が私を待ってくれていたからこそ、こうして会うことができたのだから。」
「これで酒を飲み続ける日々もおしまいだ。まぁそれはそれで寂しいけど。」
「あれだけ飲んだのにまだ飲み足りないというのか、ホブ・ガドリング。」
そう微笑んでこちらを向くモルフェウスに、なんだかとても寂しい気持ちになった。たらふく飲んだ酒も全部抜けてシラフに戻りそうだ。あぁ、まだ飲み足りないよ。本当は酒を片手にもっと君の話を聞いていたい。そんなことを考えながら「そうかもな」と軽く返事をするホブは、隣にいたはずの友人が後ろで立ち止まっていることに気づいた。
「どうした?モルフェウス」
彼は黙って歩道の片隅に視線を落としている。酒で少し赤くなった顔が沈みかけの夕日に照らされる。握り拳を撫でるようにモゾモゾと親指を動かし、何か言いたげな様子だった。ホブが歩み寄ろうとした時、彼はこちらを向いてゆっくりと口を開いた。
「また、会えないか?その…100年後ではなくもっと近い日に」
一瞬2人の間に時間が止まったかのようにも思える静寂が訪れた。ホブは踏み出した片足をそのまま、大きな目をぱちくりさせて今起きたことに驚きを隠せない様子だった。彼からの突然の提案、これはつまりホブが彼にもっと会いたいと思うように、彼もホブに対してそう思ってくれているというなによりの証拠だった。今日の彼には驚かされてばかりである。だが、こんな嬉しい驚きならいくらでも大歓迎だった。
居た堪れなくなったモルフェウスが目を逸らす前にホブは彼の側まで駆け寄って、彼の手を優しく掴んだ。
「あぁ、会おう!俺ももっと君に会いたい、まだまだ話したいことや一緒に飲みたい酒がたくさんあるんだ。次はいつにしようか…!」
ホブは満面の笑みでそう答えた。さっきまで沈み込んでいた心は、��つしかふわふわと宙を舞っているように軽く感じた。
「そうか…」
夕日に照らされたホブの笑顔を見てモルフェウスはほっとしたように呟く。
「私はいつでも大丈夫だ、君が来れる時でいい。」
「んん〜ならどうしようか…平日の夜は空いてるけど、大学の仕事が長引いたりする日もあるからなぁ。やっぱり休日の方がゆっくり会えるかな。」
「ではそうしよう。」
「どのぐらい先にしようか、そこ大事だよな…」
「さっき酒場で今月一杯は仕事が忙しいと話していただろう。それならば来月はどうだ?」
「んん、そうだな…!そうしよう!じゃあ来月初めの日曜日に。」
「わかった。では、またその日に。」
そう言うと彼の真っ黒のコートが風になびき、本来の形が崩れて周囲に散っていく。彼にどんな能力があるのか詳しくは知らないが、きっと“ドリーミング”に帰ろうとしているのだろう。別れの寂しさは、ひと月後の約束の喜びにかき消されていた。
「今日は楽しかった、おやすみモルフェウス。」
砂のように舞う黒に彼がかき消される前、ホブは柔らかな声でそう呟いた。その声が彼に届いていたのかはっきりとは分からない。だが、消える直前に見えた少し照れくさそうな顔はきっと見間違えではないだろう。
「100年に1度が、ひと月に1度か…」
―あとがき
「彼が会いに来ない理由」Chapter1を読んで下さりありがとうございました!
Chapter1〜5で構成されているこのお話、今回は2人が1月後に会う約束をしたところまでになっています。ドラマ第6話ではTHE NEW INNで出会った場面で2人の話は一旦終了しましたが、その後を妄想して自由に書いてみました。今までは100年ごとの飲み会でしたが、本編でもこれを機にもっとたくさん会って欲しいですね。
初の文章での二次創作、初めてのことで色々と試行錯誤しながらのチャレンジでした。もし楽しんでいただけていたら、とても嬉しいです☺️🙏
さて、次回はどんな飲み会になるのでしょう、そしてその後2人にはどのような展開が待っているのでしょうか。お楽しみ!
Chapter2はこちら↓
20 notes
·
View notes
Text
統合 〜 分離された魂のプロセス
【第二部:統合のプロセス】
アンティエ・リンデンブラット

オリジナル動画:https://youtu.be/ikfg2YCk7H0
公開日:2023年2月9日
【和訳:ALAE PHOENICIS】
最新情報は Telegram:https://t.me/alaephoenicis
➡第一部🔗
ーーーーーーーーーーーー
第二部のテーマは、分離された魂の統合プロセスです。
最初に、過去生について触れるのは、多くの場合、トラウマは過去生に起こっているからで、「トラウマを癒やすために、過去生で何があったか思い出さなければならないのですか?」という質問がよく寄せられるからです。
いいえ、過去生を思い出すことは必然ではありません。
もし、思い出すことが役に立つ場合は、魂はそれに関する情報を与えてきます。それは、大抵は「パズルのピース」や「側面的な一部」という形です。
なぜかというと、過去生のトラウマを癒やすために、今生でも同じトラウマとなる出来事を体験しているからで、過去生で起こったことを思い出さなくても、今生の体験をベースに癒やしのプロセスを経ることが出来ます。時には、過去生で背負ったトラウマまで思い出すのは害になることもあります。なぜかというと、過去の物語に理解が偏って、感情移入しすぎてしまうことで、「癒やしのプロセス」難しくなることがあるからです。
この統合プロセスは魂によって制御・監視されています。そうやって魂は、その時に処理できる程度の記憶や感情が放出されるように調整しています。統合プロセスではまさに、元々トラウマになったものを処理できることが課題だからですが、例えば幼い頃に虐待に遭うと、それがインナーチャイルドの魂の一部となっているので、その視角からは癒やしをもたらすことが出来ません。ですから、ある程度の精神的な成熟度・意識のグレードに達している必要があります。
分離された魂が日常にどのような影響として現れてくるのかというと、それは身体的なブロックであったり、もしくは生活状況、特定の生活領域にも現れることがあります。なかなかうまく行かないこと、努力が実らず、それが辛い感情と結び付いているのは、どの分野でしょうか。
まず、これらは「引き寄せ」の法則として現れてきます。トラウマを内に抱えていると、そのエネルギーは「似通ったもの」を引き寄せます。しかしそれは、無意識下に追いやられ、気づけなかったトラウマが何なのか、を知らせてくれるものでもあります。
その他、「被害者意識」「無力感」といった信念構造に、影響が現れて来る場合もあります。トラウマを体験することで、いったんは「被害者」の立場になるわけなので、この経験によって生じる信念構造というのがあります。
身体的に現れるものとしては、病気、もしくは特に敏感な身体の部分や臓器があります。例えば胃、呼吸器官、その部位特有の病気など。エネルギー的にはその起源はトラウマで、それと関連した身体部分に弊害が出てきます。エネルギー的な刻印は、もともとの状況からきているのです。
例えば、ナイフで刺されたとします。するとその部分にはエネルギー的な刻印が残されたりします。ナイフによって傷つけられたという事実と、傷口にもそれが残るのです。
このトラウマにより、神経系に緊張感が現れたりします。トラウマを背負うと、神経系が警戒態勢に入ります。そして、このトラウマと関連していて、解消されていない全てが神経系に警戒態勢を布きます。つまり、その人はストレス状態にとても敏感となる、もしくはすぐにストレス状態に陥り易くなります。例えば、大したことのない情報によって簡単に生命が脅かされるほどの負担を感じます。それは神経系が、そのような警戒態勢にあるからです。
不眠症となることもあります。そうなるとリラックスできなくなり、悪夢を見る傾向があると尚更です。
不合理な行動にでることもあり、その人が特定の状況になぜ過剰反応するのか、外からはそれが説明できませんが、この場合トラウマが背景にあったりします。
ありがちなのは、この世に留まりたくない、生きていなくない、という感情です。その理由は、トラウマによって基本的な信頼や安心感が酷く損なわれているからで、魂はこの体に留まりたくないと感じていますが、特に下部のチャクラがトラウマの影響を受け、支障をきたすので、魂はそのエネルギーを下部のチャクラまで通せないのです。このような影響は、比較的よくあるケースとなります。
よくある傾向として次に述べられるのは、麻痺感覚、ある種の感情的な麻痺で、これはうつ病へ向かっていくことがあります。
第一部でお話したように、トラウマを受けた流れが主流から切り離されてしまった状態です。主流に流れている本来の感覚から切り離されると、こうした麻痺感が現れます。
あまりの痛みで、切り離されていた支流の水はしかし、主流へと少しずつ流れ込んできます。しかし、それを扱うにはまだ未熟だと感じている魂は潜在意識下へその水を押しやってしまいます。そうやって「一部の感情」に蓋をするようにしていると、その他の感情も蓋されてしまうので、全体が麻痺して感じられなくなってしまうのです。まさに多くの感情を抑圧し続けることで、「うつ病」に発展していくのです。
トラウマによる魂の分離の結果、日常に現れる更なる傾向は、自信の欠如です。これがどのように統合されていくのかというと、最初の兆候は、再度トラウマとなる出来事が繰り返されることで起こる圧迫感である反面、魂自体が「川の水」のように流れているため、トラウマで閉塞されると自然の流れではなくなっているところに圧力が生じます。こうして、魂の一部が作り出した感情や信念構造といったものを徐々に無視できなくなってくるのです。魂はこうやって、統合プロセスに協力するよう、意識に呼びかけてきます。
トラウマを思い出させる類似状況が繰り返されることで「もう沢山だ!」となり、その人は意識して「どうすれば良いのか、一体どういう仕組みになっているのか」など、考えるようになります。これは、実はそうした統合プロセスに取り組むよう、魂に促されているのです。「癒やされたい、克服したい、状況を変えたい」という願いが強くなり、統合プロセスに対して心を開くようになります。
この統合プロセスに意識的に取り組めるよう、魂は元のトラウマに似せたあらゆるトリガーを使います。人間関係だったり、似たような状況、場所だったり、または生活の中のあるシーンで何かに導かれるように特定の行動を取ろうとしても、あまりの閉塞感、不安や疑念が出てきて出来なかったりします。
その時、真っ先に反応するのは「身体」です。体には全ての記憶が振動周波数として保存されているので、トリガーがもたらす振動に反応します。
光の周波数を上昇させることによって、この統合プロセスを促進させます。
高い振動数の光が体に流れて込んであふれることで周波数は高まりますが、体の何処かに痛みが走ったりするのは、切り離されていた魂の部位に光が当たったときです。これによって統合プロセスがブーストされ、浄化が始まります。
これは、真っ暗闇で懐中電灯を点けたときと似ていて、突然光が差し込むことで何かが見えてくることがあります。急に認識したり、記憶が蘇ったり、身体に痛みが走ったりします。閉塞されていた場所でエネルギーが詰まったような感じになるわけです。
こうして分離されていた魂の部位の癒やしとは、様々なレベルで起こります。感情面、精神面、身体面、そしてエネルギー面です。
つまり、辛かった感情や展開された信念などがチャクラを詰まらせ、エネルギーや情報が身体を健全に流れなくなるので、全体に統合されるには上述の其々のレベルで癒やしを必要とします。
感情面:
「感情」は癒やしへとガイドしてくれる最も重要な鍵となります。つまり、統合のプロセスではどのような感情であろうと、全て「ひと通り感じる」必要があります。「感じる」ということを通して、手放すことが可能になるからです。この「感じる」ということが解毒になり、主流に戻ることが出来るからです。しかし「感じる」だけでは不十分です。「何故そう感じているのか」を理解することが必要です。
傾向として、私たちはそこにある感情をジャッジしてしまい、否定し、拒否してしまいがちです。そのように条件反射するよう、学習させられています。特に「その感情は自分に何を語りかけているのか」を理解することが大切です。ここで、感情が癒やしへのガイド役をするのです。
また、感情とは常に、私たちの欲求を表現してくれている、ということも大切な点です。
例えば、恐怖とパニックという感情は、安全への欲求が満たされていないことを示しているわけです。
ここで、「では安全��はないと思わせるのはどのような状況なのか」と問いかけ、その状況を避けてもいいですし、もしくはどうやって安心感をもたらして欠けている欲求を満たせば良いのかを考えることも出来ます。
精神面:
これは、経験によって構築してきた信念・信条と強く関わってきます。これを変容させるためにはまず、よく認識・自覚せねばなりません。思考が変わらなければ同じ信条を掲げ続けることになり、従って同じ感情を引き起こすので、破れない悪循環の中に閉じ込められることとなります。
あなたの信念・信条が結局、変化を阻止します。
例えば、「自分は罪深いのだ」「自分には価値がない」などと思っていれば、そこから身動きが取れません。だから、同じことばかり繰り返し体験してしまうのです。精神はあなたの内側を外側に向かって投影するので、あなたが被害者意識からそのように信じていれば、その通りのことをあなたは体験するのです。その意味で、精神面の癒やしも非常に重要な部分です。
被害者意識の仕組みは、自分に集中して自分を中心軸に持っていかず、「あなたのせい」と考えることです。これも癒やしのプロセスを妨げます。つまり、感情・思考というのは、自分が自分で展開したものなので、それらに対して自分で責任を担う、というのが非常に大事なポイントです。
身体・エネルギー面:
結局のところ、全てが「エネルギー」として総括できるので、この2つは纏めました。意識のエネルギー領域は質的に微細ですが、身体というのもエネルギーで、ただ質的にはより粗雑です。
このに種類のエネルギーは互いに依存しあっています。
また、感情と思考もエネルギーですが、これらは身体に「記録保存」されていて、魂の部位とつながり合っています。
トラウマに関する思い出と情報は、身体、エネルギーシステムの両方に記録されています。
身体とエネルギー体の動きは一致しているため、両者は依存しあっています。すると、エネルギーの不調和は、エネルギーシステム全体において、感情的にも思考的にも調和の取れた流れを阻止し、同時に身体のエネルギーシステムをも害します。
これは大抵、チャクラと経絡に障害をもたらし、エネルギーが上手く流れず、行き渡らない身体部分は痛みや強張り、もしくは病気で反応します。そうやって可視化することで、魂は「ここを見て!様子が可怪しいよ!」と語っています。
ヒーラーとしての私の経験では、トラウマを経験すると、大抵下部3つまでのチャクラに関わって来ます。これらのチャクラは、私たちの地上での存在の仕方に大きく関わってくるからです。これ対し、上部のチャクラは高次の存在、自分のハイヤーセルフ(魂)と繋がっています。
トラウマというのはある種の「ショック(衝撃)」であり、急激なものと長期に渡って刻まれるものがありますが、これらは下部のチャクラに淀むため、身体的にはその位置に症状が出ます。これは閉塞部分の鏡であり、エネルギー的・身体的に解毒し、健全な流れを取り戻すことで統合され、癒やされます。
分離された魂の統合プロセスは、下記の二つの領域に分けることが出来ます。
片方の領域では、魂が統合プロセスを制御し、監視するとともに、上述したように意図的にトリガーとなる状況を創り出して分離された魂を���合させようとします。
もう一方の領域は、私たちが内側へ働きかける部分です。つまり、統合プロセスは勝手に進むわけではなく…「私の魂が勝手にやっておいてくれる」というわけではありません。私たちは自覚をもって、いわゆる「シャドー・ワーク」をしなければなりません。この時、魂が担うのは繰り返し渡されるダウンロードを受け取ることです。魂によって、トリガーや、そこから気付きももたらされたりしますが、周波数が魂から肉体へと流し込まれ、それが支流へと分離されていた魂の部位へと染み渡っていきます。
これは、トラウマに関連するエネルギーを意識上に持ってくるためと、更に、思い出を徐々に解明して不調和の全てを浄化するためです。
私たちが取り組むべきシャドー・ワークは、これまで無意識下にあったこと、そしてそこにある「傷」に気づくことで、心を開いてその部分を直視します。自分の影の部分を認めるのです。これはなかなかの挑戦です。なぜならこれは感情的な痛みを伴うからで、思い出すのが辛いからです。
また、トラウマを思い出すと、「被害者意識」も自動的に戻って来てしまいます。
本人は自らをジャッジし、自らの感情や特定の行動の仕方を否定する傾向を、もうなんども繰り返し学習してきてしまっていて、こうしたジャッジや否認をし続けている間は、癒やされません。
ここで「中庸の精神」が大事になってきます。中庸をもって、自らの影を直視し、ジャッジしたりせずに、自分に問いかけるべきことは、「何故、こんな目にあったのか?どんな意味を成すのか?これは、私に何を見せようとしているのか?」などです。
ここで、「感情面」が鍵となってきます。感情の部分こそが、その裏にどのような思考があるのかも示しており、それが行動の選択にも繋がります。
これらを一つ一つ観察することが、あなたの内面での取り組みとなります。
とても大事なのは、あなたの「被害者としての姿勢」を自己認識することです。これはトラウマによって自動的に生じてしまったもの。
自分自身が被害者的な姿勢になっていることを認めるのは、かなりしんどいことです。繰り返し自分が「被害者」であるという感覚になったり、「攻撃された」とか「悪意を持って迫られた」と感じて続けているのです。
ここで重要なのは、「どこまでが現実で、どこからが自分の内的投影なのか」を区別することです。そして、そこでまた、自分をジャッジしないこと。だって、トラウマを体験したということは、誰かがあなたに何かをしたわけで、その時あなたは「被害者」だったのですから。
しかし、あなたがそこで癒やされること無くずっと引っかかっていると、分離された魂は統合されないのです。
あなたが被害者意識を手放して行けば、あなたは徐々に自分のパワー領域に戻ることが出来ます。
そもそも、トラウマを得るとともに、強烈な無力感が生じます。その時のあなたには、状況を操るパワーが無くなっていた、もしくはそれが起こるのを避けられなかった、どうにか出来るような手段も持っていなかったわけですから。これも「私には、起こってしまったことを受け止めるだけの力がない(自分は無力である)」という感情なのです。少なくともそれが起こった時点では。ですから、これを消化していく必要があるのです。
そして、心にできた「傷」がそこにあります。これを癒やすには、あなたが自分自身に対して大きな愛情、信頼、共感を持つことが大事です。
わかりやすい例えだと、足を骨折し、骨が見えるほどで手術をしなけばならないとします。この手術が統合プロセスに値します。手術をして、全てを正しい位置へ戻し、つなげあわせるのです。しかし、治癒はまだ完全ではなく、術後にすぐにマラソンを走れるわけではありません。統合プロセスを経た後も、全快するまで暫くは、癒やしの期間が必要なのです。そして最後にもう痛みはなくなっても傷跡は残っています。その傷は、「ここを怪我して痛かったのだ」ということを思い出させるのです。
この統合プロセスは、玉ねぎを一枚ずつ剥がしていくような作業です。なぜかというと、上述した感情面、精神面、身体面、エネルギーといった4つの層の全てを、いっぺんに癒やすことは出来ないからです。
統合プロセスに取り組むときは、余裕がなくなりがちなので、全てを一挙にやるのは不可能です。特に統合プロセスの初期段階は最も過酷なときです。その時点では「これからどうなっていくのか」という感覚がまだ持てず、不安になります。
真ん中の核心に触れられるまで、時間を掛けます。その間、多くの感情を通り抜け、徐々に理解していきます。これまでの信念構造も解除されていき、全体の関連性を認識していきます。
もともと、トラウマは一瞬にして魂の分離を引き起こすことがありますが、「意識化と癒やしのプロセス」というのはこうして、段階を踏んで徐々に行われるのです。
共感することと忍耐をもつこと、にも言及しました。そして、このプロセスを信頼することも大事です。
統合プロセスの途中で、「もうこんなにも全て見つめ直したし、感情も繰り返したし」、そして「もう全部やったのに」と苛立っていると、次の層が見えてきて、改めてまた同じ感情を通り抜けることになるので、段々と焦りが出てきて、これまで頑張ってきたことが無意味に感じたりします。しかし、どんな小さなことでも、意識化していくことに意義があります。その努力が無駄になることはありません。ただ、多層になっているので、忍耐をもって徐々に進んでいくことで、どんどんと深いところにある分離された魂へと進む事が出来ます。
だから、「まだこれもあった、あれもあった、ここにもまだあった」となるのです。
トラウマを抱えて分離した魂の部位とは、非常に子供っぽい状態なのだと想像するといいでしょう。意識の成熟と、という点で幼いのです。幼い子供は、大人の大きな愛情と忍耐を必要としています。
ですから、この分離した魂の部位が感情をむき出しにしたときには、あなたの成熟した部分で「大人」として手を差し伸べて上げるつもりで、自分自身に優しく言い聞かせます。「うん、これとこれが起こったから、今癒やしましょうね」というように。これは分離された魂の部位にとって大きなサポートとなり、癒やしに貢献します。
癒やしがもたらされることを信頼し、統合プロセスに身を委ねようとするほど、癒やしは早く、楽にやってきます。
統合プロセスの最終目的は、「完全体に戻ること」です。
内なる統一、内なる調和を取り戻すこと。
自分の肉体の内に、エネルギー的に完全に戻ること。
そして自分の人生の中で、エネルギー的に完全に戻ること。
なぜなら、魂に分離された部位があって、身体の中で統合できていない間は、自分の願望も顕現させることが出来ないからです。
人生を自らの願望どおりに創造・顕現しようとする側面において、魂全体が癒やされて統合されていることは大変重要なことです。さもないと、あなたの創造性は阻止されてしまいます。
ですから、魂のエネルギーを身体全体に定着させることが、統合の目的なのです。
これは、創造主である「神」から、分離した私たちが、「ひとつ」に戻ろうとする、普遍の大きいプロセスと同じです。ここには身体は関わってきませんが、精神面の部分です。
また、この人生であなたに与えられた可能性を。フルで発揮するという目的もあります。分離された魂は「影」なだけではなく、光の部分もあるんです。ですから、統合がなされると、分離していた間にはみられなかった才能や性質が戻ってきて開花することもあります。そうした素質が「ある」ということは認識していたかもですが、実際にはロックされていたり、不安を感じるなどが理由で「活かす」ことが出来ていなかったはずです。
また、この統合されることになった「光」には賢智も含まれています。
なぜかというと、トラウマは「偶然」に起こるのではなく、その領域で特定の賢智を得るために、あなたの魂は契約としてその体験を「選んだ」からです。
こうして、統合プロセスのが進むと、また途中の段階でも、どれほどの悟りがそこにあり、宝が隠されていたのか、どれほど深いことがわかる自分になれたのか、ということに気付いていきます。
それは個人的な収穫かも知れませんが、もしかすると誰かに伝えていくことになるかも知れません。
だから、「このトラウマで、私は何を学んだのか」を自分に問い直して下さい。あなたは「人間の性」をより深く知ることになったり、もしくは「自分が何者なのか」「私たち(人類)とは何なのか」を悟ったことでしょう。
統合プロセスは、癒やしであり、完全に戻ることであり、魂と調和し直して、秘められた可能性を開くこと。魂の可能性には限界がないのです。つまり、統合プロセスが完成した時には、全ての扉は開いているのです。
5 notes
·
View notes
Text
ネオファウナ

白と黒。それがこの台地に登って抱いた最初の印象だった。起伏に富んだ白い氷原のあちこちから、黒い崖が顔を覗かせる。雪がちらついているせいか、それとも大地の白を映し出しているせいか、空もまた、灰色のはずが白んで見える。初めて訪れる北極圏は、太古の昔から日の沈むことのない、かといって日が高く昇り、大地の氷河を溶かすこともまたない、薄明の世界だった。
雪原専用の8脚車両で、傾斜の緩い台地の東側から登って早半日、狭い空間で疲れは溜まっていたが、私の体重が他の乗組員より重い分、贅沢は言えなかった。大丈夫、あと数時間もすれば、発掘のためのキャンプ基地に到着する。この辺りは雪の粘度が低く、おまけに雪の下の固まった氷河をうっかり踏んでしまうと、車両ごと転倒する危険がある。車体の脚部分に付いた音響センサーで、なるべく雪の厚い場所を探りつつ、進むしかないらしい。
私の隣では、ダンと名乗った白いクマの男性が車両に接続して操縦している。一見すると椅子にもたれかかっているようにしか見えないが、後頭部には電磁コントローラが付いている。彼自身によればちょっと前の型番だが、車両を動かすには使い慣れたものが一番しっくり来るらしい。後頭部樹状核増設手術を受けているらしく、扱いには手慣れているという。もう10年になるそうだ。他の2名が小柄で、荷物もかなり多い以上、体重の大きいゾウである私と、ダンの2名はそれぞれコクピットとサブピットに座ることになった。
「僕は地元の村の出なんですが」
思いのほか、荒々しげな見た目とは裏腹に、丁寧な口調でダンは喋り出した。運転中とはいえ、重苦しい静寂に耐えられなくなったらしい。
「どうもそっちでも、起きてるみたいなんですよ、失踪事件」
「本当なんですか」
それまで黙りっきりだったネズミの男、ジェイが、淡々と訊いた。別段驚くでもなく、寒い車内の温度に合わせたような冷やかさだった。仕事をし始めて半年間、ここに来て躓くまで彼と世界を巡ったが、未だに彼の感情の起伏は捉えられていない。
「えーと、報告では、確かに4件の失踪事件が、マクファーレンさんのご出身の村で確認されてますね、種はいずれもバラバラですが」
そそっかしいラエンの女性、ライラと名乗ったか、が手元の携帯モニタを叩いて読み上げた。ダン・マクファーレンと同じく、ここに着いた際に中央都市の空駅で出会ったばかりで、なおかつ、私とジェイの終盤を迎えた調査が躓くことになった原因だった。
いや、原因というのはよそう。別に彼女が引き起こした事態ではないのだから。
私たちはこの地に到着した瞬間に、すでに躓いていたのだ。
私とジェイ・マウゼリンクスが実地調査を始めたのは半年前、そのきっかけになった、彼の調査に同行したのが1年程前だったか。赤道地帯の高地で発見された膨大な壁画、そしてそれを覆い隠していた巨大な洞窟は、数万年前に明らかな、我々知的生物による文明が存在した最古の証拠となり得るものだった。当時一介の動物文化学者だった私に、その研究の最前線に入って欲しいと言うオファーが来たのは、ジェイの横やりあってこそだと聞く。途中から研究に無理やり入り込んだジェイを疎む者はいたものの、全知的動物の大系統を、分子を用いて提示し、世界的に注目されている彼には、表立って反意を示すことができなかったようだ。無理やり私を暑い洞窟へ連れ出した彼は、これまでの古代文化とも違う、独特な意匠の壁画と、その物語る意味を教えてくれた。
それはカタログ、と言ってもいいものだった。中央に描かれた、楕円形の物体の中から、様々な種の、知的生物が出てきて、一様に並ぶ光景。そこには何万もの「立った絵」があったが、1色で描かれていながら、それぞれの絵はディテールが異なり、明確に別種と認識できた。赤道付近と言っても、安定陸塊上、そう、オセアニア大陸に位置する以上、ゾウやウマといった旧大陸を出自とする種は、ここには載っていないはずだった。だけれど、私の種だけではない。たぶん、あらゆる現生の知的生物が、この「カタログ」に載せられているのだろう。
分子生物学者のジェイは、恐らく人類のルーツを明確にしようとしているに違いなかった。そこで私に、手伝ってくれるように要請した。
誰もが気づかないふりをする。
感情の起伏に乏しいジェイが、この話をする時は苦々しい顔を必ず浮かべる。我々知的生物、つまり動物は、単一の系統である微生物として誕生し、無脊椎動物、魚類を経て、爬虫類となり、そこからそれぞれ鳥類と哺乳類が分かれた。これが、どんなにプロセスに疑問を抱こうと、この地球の教育機関で、幼獣ですら習っている仮説だ。
しかしこの仮説には矛盾が生じている。我々は進化の過程で、知能が発達したが、知能が発達するのが先だったのか、それとも様々な種に分化するのが先だったのか、という問題だ。知能が発達するのが先なら、例えば知能を退化させた種や、相応の歴史を示す物が残っていてもおかしくないが、実際はそんな種や事物は残っていないし、現在昆虫や魚類で示されているような、進化に至る原理、突然変異や、特に自然選択が、知能を持つと生じにくくなるのではないか、という仮説もある。一方で、様々な種に分化するのが先で、その後知能が発達したという仮説なら、上記の問題はクリアするが、いくら収斂進化という、似た生態的地位の生物に似た形質が出るという仮説があるとはいえ、そのような斉一的な知的生物化が起こり得るだろうか、という疑問が浮かぶ。そもそも、様々な種に分化しているのなら、我々には様々な、枝の途中となり得る、祖先種が数多見つかるはずだ。しかし、現状そんなものは一切見つかっていない。化石記録は魚類まで、それも現生の無脊椎動物や魚類とはかけ離れた姿で、我々の現在の姿を支持しない。
このジェイの主張に私は魅せられたのだろう。彼に伴って様々な古い遺跡をフィールドワークした。そうして、場所を絞り込んでいくうちに、文明誕生の起源となる候補が、この、新大陸の北極圏内にある、大きな台地で見つかった遺跡だと突き止めた。
残すは実地調査、既にキャンプ地が作られ、行われるはずだった大規模な調査に参加させて貰えることになり、北極へ向かう途上は、一睡もできないほどだった。しかし、いつまで経っても迎えの車両が来ない。どうもおかしいと思って、上空から気象観測用の無人機で見て貰ったところ、キャンプ地に誰の気配もない、ということが判明した。地元の警官隊に待機を命じられた私たちは、警官隊所属でこの地域を管轄していると名乗るライラと、この辺の地理に詳しく、仕事柄車両の扱いにも慣れているらしいダンと共に、キャンプへ向かうことになったのだった。
洞窟の中は、明るかった。発電機が稼働したままになっていたせいか、洞窟の壁に設置されたライトが空間を照らし出し、携帯ライトを持たずとも奥深くまでの道は見えていた。ずっと昔読んだ恐怖小説と違って、静寂こそあれど、何十人ものスタッフが失踪したような、不気味な雰囲気は感じさせなかった。
先を行くジェイを呼んで、私より二回りは小さな彼の様子を聞く。
「キュクロプスさん、この先は若干狭いがあなたでも入れないわけではなさそうだ。ただ灯りがもう設置されていない。誰かライトを貸して欲しい」
そんな声が狭い道の前、ダンやライラの前から聞こえてくる。私は持っていた携帯ライト、ジェイには若干大きいかもしれないが、をダン、ライラに渡し、ジェイに渡すように促した。
「この奥は広い空間だ」
「慎重に進んでくださいね」
ライラが呼びかける。裂け目が出来て落ちていたりしたら大変だろう。
ライラに続いてダンが、そして私が狭い穴をくぐる。真っ暗であまり見えないが。空間が広いのは声の響き具合でわかる。
「これは、特に岩の裂け目とかはないみたいだ」
慎重に前進して、ジェイから渡された携帯ライトで周囲を見渡したダンが、何かに気づいた。
「なんだ、あれ」
真正面の、ライトで灯された場所を見る。明らかに場違いな物が、岩に貼りついていた。
「扉、ですね」
ライラが立ちすくんだまま不安げに言う。
鎮座している金属製の、明らかに現代的な円い扉は、私でも余裕で通れるぐらいには大きい。左側には、取手のような金属製の棒も繋がっている。
狼狽しているのか、先にこの空間に入ったジェイは、扉を見て何か考え込んでいるように見えた。そんな彼の横を通って、ダンがおもむろに取手に手をかける。
少しだけ、空気の吸い込まれる音がして、扉が開いた。
考え込むのをやめたらしいジェイが、吸い込まれるように扉の奥に入っていく。
「マウゼリンクスさん!」
ライラは止めに入ろうとしたのか、後を追った。私もそれに続く。
後ろから足音が聞こえる。ダンも来ているようだ。
扉の奥は、少し上向きの傾斜のある、通路だった。4名分の足音、金属音が響く。それ以外は、ジェイの今持っている携帯ライトが頼りだった。
こんなところに近代的な人工物があったなんて、何かの軍事基地とかだと、非常に私たちはまずいことをしているわけだが、なんでこんな洞窟の奥深くにあるのか、見当もつかない。
好奇心はとうに消え失せ、徐々に後悔と不安と恐怖が胸の奥を占めつつあった。そんな時、ジェイが立ち止まった。
「行き止まり?」
最後尾のダンが聞いた。ジェイは短く、いや、とだけ答え、目の前の壁、いや、長方形の扉だろうか、に設置された黒いパネルに、手をかざした。
扉が開くのと、視界が明るくなるのは同時だった。しばらく薄明りや闇の中で過ごしてきたせいか、目が痛い。なんとか視界を取り戻すと、通路と思しき、私たちが辿ってきた空間が明るく、ライトのようなもので照らされているのが見えた。扉の向こうは、少し落ち着いた明るさのようだ。ライラやジェイに続いて扉をくぐる。
そこは、一面緑色の森だった。
唖然としていた私たちに、ジェイが呼びかけた。
「立体映像だ、本物の森じゃない」
各々が、凄まじい密度で生えている草木を触ろうとするが、すり抜けてしまう。どうやら本当に、偽物らしい。
「こんな植物見たことない。地球上でこんなの発見されてたっけ、それに日差しも」
「青い空だな」
上を見上げてジェイが言った。空と言えば、エアロプランクトンが漂っているため、地上からは緑色に見える、日差しもこんなに明るくはないはずだった。
「これが故郷の景色か」
そうジェイが呟く。
「その通りです、ここが本来の地球の景色です」
今までの穏やかな口調のまま、ダンが言い出した。
「マクファーレンさん?」
何を言い出すのか、��思い、私は振り向く。ライラも遅れて振り向いた。怯えているのか、その顔は強張っている。
「ようこそ、汎用生態系生産プラント、ネオファウナへ、私はこちらのオペレーションを行っているメインシステム、チャーリーと呼ばれています」
ダンは全員の方を向くと、恭しく礼をした。
「皆さんがご覧になっている映像は、本来の地球、東南アジアのカリマンタン島付近の熱帯雨林を再現したものです。本来の地球で最も多様性が保たれていた個所と言われています」
淡々と話すダンにはどこまでも表情が無かった。まるで愛想笑いを無理やり貼り付けたかのように、いや、人形や標本の魚のように、虚ろな笑みを浮かべたまま語り続けている。
「マクファーレンさん、どうしちゃったの?」
「私が現在操作しております個体は、身体の一部に改造を受け、なおかつ日ごろから電磁ネットワークに接続状態にありました。そこで、アバターを実体化させるよりも低電力で済むとみなし、デバイスとして使用するに至った次第です」
「俺をここに呼び寄せた理由はなんだ」
ジェイが、これまで聞いたことのない、敵意の籠った声で言った。赤い目が射止めるように、ダンを見つめている。しかしダンは答えなかった。
「ジェイをここに呼んだ理由は?」
今まで黙っていたライラが今度は言った。さっきまで怯えていたとは思えない、鋭い声だった。
「私は当該個体、あなたがジェイと呼ぶ個体を通して、ユーザーの設定した開始コードの発現タイミングを計算していました」
もはや私には何がなんだかわからなかった。洞窟の中の見知らぬ施設、見覚えのない緑、そして態度の一変した同好者たち。立っているのがやっとだった。
「一から説明してくれ、彼らがここに呼ばれた理由を」
ライラが続けた。ダンは薄笑いを浮かべ、苦虫を嚙み潰したような顔でジェイがそれをにらんでいる。
「始生暦時代に入って、人類の文明は大きく進歩し、大規模な星間文明を築くに当たりました。その過程で、本来の地球は大きく生態系を衰退させ、私が稼働を始めた段階では、乱開発防止のために所在不明とされていました。その代わり、多くの惑星が植民化され、人類は星間文明を自らの故郷とするに至りました。しかし、本来の故郷である地球への憧憬が無くなったわけではありません。数多の星々をテラフォーミングする過程で、人類はそのノウハウを蓄積させ、より高効率に、より速やかに他の惑星を地球化することを実現したのです」
「そして、故郷への憧憬は、私が制作されたネオファウナ計画に繋がりました。星間文明で用いられていた、地球由来の生物の遺伝情報を基に新たな労働力、知的生物を作り出す技術と、先に述べたテラフォーミング技術が結びつき、新たな地球を生み出すという計画へシフトしたのです」
「手順はまず、簡易な条件での地球化から始まります。条件に見合った惑星に、こちらのプラントで遺伝情報を改変し作製した大気性プランクトンなどを放ち、大気構成を地球により近いものとします。その後、水生プランクトンやごく微小な生物、水生生物、陸生植物、小型陸生動物といった順に作製し、放流します。生態系がそれぞれ安定してきた段階で次フェーズに移行し、最終的に大型動物を除いた不完全な生態系ができます」
「その後、大型動物をヒト型知的生物として作製し、惑星上に解き放ちます。初期はある程度の調整が必要ですが、徐々に文明化が進むと、自然と個体数も増えていくことでしょう。
ユーザーであるホモサピエンスに形態的に近いグループが作製されたのは、文化基準をかつてのユーザーの文明に合わせ、個体数増加を促すためです」
「ラエンのことだよ」
静かにライラが呟いた。
「私が開始コードを発現しようとしているのは、更にその次のフェーズです。当該個体を作製した私は、接続可能な別個体を使って、当該個体を外に出し、その脳を通して現在の惑星の状態を観察していました。もちろん、当該個体には脳神経の加速化措置と、私に情報を送るためのリソースも設置済みです。24年6か月を観察したことで、私は開始コードの発現を行うのに十分な時間が経過したと認識しました」
「それが、俺が作られた理由か」
相変わらずダン、否、チャーリーを睨んだまま、ジェイが吐き捨てた。
「開始コードの発現後はどうなる、先住種族と同じように、彼らを消去するのか」
「いいえ、開始コードの発現後は、現在作製している神経加速化の遮断、脳内の感覚抑制の解放、ボトルネック防止に用いられていた多系統繁殖用遺伝領域の切除、そして次代における原種形態への移行、これらを促すウィルス群を散布します。現在、その準備段階として、複数個体にこれらの措置が可能かどうかを試験しています」
「どういうこと?何が起きるの?」
何を言っているのか、門外漢の私にはわからない。だけれど何か恐ろしいことを言っている気がして、口走る。
「俺たち知的生物は知能を失い、動物に戻る。感覚も戻り、少子化対策に用いられかけてた遺伝領域はもぎとられ、子孫は四つ足の獣に、ってことだ。失踪事件は、その準備として、試験的にウィルスをばらまいたってことだ」
ダンは何も言わなかったが、ジェイが代わりに答えた。
「私に記録されている地球生命の情報は膨大ですが、基礎さえ完成すればあとは難しくありません。残りは生態系が安定するに従って、徐々に作製し定着させていく予定です。早ければ数十年で、この星は第2の地球となります。私やユーザーの願った地球の復活が遂に為されるのです」
ダンは両手を広げてまるで演説でもするかのように宣言した。私にはこれが夢の中の出来事のようでならなかった。
「当該個体と、そうですね、こちらの個体は私の本体にフィードバックすることにしましょう。現状のサンプルでは効率的なウィルスの散布が行えないので」
そう言うとダンの体は何も映っていない瞳で私の方を見た。ここが北極であることを思い出したかのような寒気が走る。先んじて捕まえられたジェイがもがいている。私も腕を強い力で引っ張られて、森の奥まで連れていかれそうになる。
「AIの癖によく喋るなお前は。中に誰かいるだろ、飛びっきりのイカれた奴が」
突然、腕が離れた。同時にジェイの咳き込む声がする。
見ると、大柄なクマを取り押さえているラエンの女性の姿があった。非現実的な光景に何が起こったのかわからなくなる。
「チャーリーだったか、以前遺跡を回って、似たような壊れた施設を見た時にあんたの名前を確認したよ。設置予定の生体プラント兼液体コンピュータの素体になるって時点でやばいと思ったが、こちとら先住種族を駆逐されんのも、せっかく根付いた知性を踏み台に懐古主義に走られるのもごめんでね、悪いが稼働停止してもらう」
出会った時の態度はどこへ行ったのか、荒々しい口調で告げると、周囲に火花が散った。
途端に、立体映像の森が消え失せ、通路と同じ無機質な灰色の部屋に変わる。
「案の定、システムはニューロン式を使ってたか。悪いけれど私はラエンじゃないし、体はあんたの言うホモサピエンスでも、宿っている意識は年季の入った量子の寄生虫なんだ。量子脳に関してはこっちの方が上手なんだよ。3億年かけて辿り着いた、被食者と捕食者が共にいられる楽園、そう簡単に潰されてたまるか」
「私の活動が停止すれば、今後エアロプランクトンが作製されることもなくなりますよ」
苦しげでもない、さっきと同じ淡々とした口調でダンの体が言う。
「エアロプランクトンも継代を重ねて、あんたの供給なしに殖えるようになってるんだよ。この世界は変わっていくさ。でもそれは地球と違う、大型動物相の代わりに知的生物が優占し、交雑を重ね、多様化と均質化を入り混じらせる世界としてだ。本来の地球生命が今も変化を続け、この星だって変化の最中にあるのに、時を戻して止めようとした時点で、あんたは詰んでたのさ。わかったらとっとと凍りな、あんたの望んだ永遠の停滞だ」
轟音が響き渡った。床が震える。部屋のライトが点滅して、消える。真っ暗になった部屋が振動を続ける。盛大に転倒した私は、解放され糸が切れたように崩れ落ちたダンと、同じく転げまわるジェイをなんとか抱きしめる。
「私はこいつのやらかした後始末に行ってくるから、またどこかでね」
覚えているのは、そこまでだった。
台地で起こったことは、巨大な雪崩によってキャンプ地と、内部の空洞が崩壊した、というニュースで片付けられた。私は他の2人と共に病室に缶詰になり、あれこれと話し合った。ダンは荒っぽいが人懐こい性格で、私のことは全く知らないが、幼い頃に父親が連れてきて兄弟のように育ったらしいジェイのことはよく覚えていた。ジェイは遺跡巡りと、ダンがジェイを覚えていないことで気づいていたらしい。
キャンプ地で失踪したスタッフと、近隣の村から失踪した住民が保護されたのは、私たちが洞窟の入り口で倒れていたところを発見された翌日だった。ちょうど反対側の海岸で見つかったらしいが、不思議なことに皆が一様に「吹雪が酷くなったのでビバークした」という記憶しか覚えていなかった。1本だけ、空の注射器が置いてあったそうだ。
ライラの行方は分からない。そもそも、地元の警官隊にはそんなメンバーどころかラエン自体がいなかったのだ。
「これからどうするんですか」
ダンは寝ている。病室の窓から空を見ているジェイが、どうしても気になった。
生きる目的を失ったのではないかと、思ったからだ。
「枷が外れた気分だ、清々しましたよ」
いつもと同じ、だけれど少し晴れやかな声色で彼が返した。
「なに、資料は集まってますから、最後の仕上げだけできなかったってことで」
彼らしくない、楽観的な言葉だった。彼も、吹っ切れたのかもしれない。
「あの場にいた誰もが、あの場所に関係している者だった、あなたを除いて」
「そうですね、傍観者として、大事たと思われたのかもしれません」
「チャーリーが言ってましたね、星間文明がどうとか」
「言ってましたね、多種族からなる星間文明とか、地球由来の遺伝情報で人類の伴侶を作り出すとか、あれ」
「そんなこと、言ってましたっけ」
記憶と知識の食い違いに、戸惑う。すらすらと出てきた言葉は、私の理解を大幅に超えていたはずだった。
「磁気映像で撮影した、あなたの脳のカルテを見せてもらいました。先天的な改変の痕跡が見つかったようです」
「私には、そんな自覚は」
「無いんでしょうね。誰かが、どこか遠くからあなたの脳を介して、この星を見ている」
私と同じですね、と彼は言った。彼が言っている間に、まるで目の奥の濁りが取れるみたいに、目の前は鮮やかになっていった。
目の前に広がるのは、白い空。
でもその向こうに広がるのは、プランクトンに覆われた碧色の空。
脳裏に浮かぶのは、あの時見た青い空。
「モッティさん」
白い空をバックに、白い毛並みの彼が振り向く。その顔には、見たことのない表情が浮かんでいる。
「この世界って、綺麗ですね
5 notes
·
View notes
Text
テラヒューマニティ・星海殉葬
0.
「なんて、エキゾチックなの」と母は言った。
異国風という言葉選びは、果たして正鵠を射たものなのか。判断しかねた俺は、沈黙を保つ。
部屋には、三人がいる。自分、母、そして一人の少女だ。
少女は、その外見に人類にはない色彩を持っていた。それは、彼女が異星種……つまり宇宙人の血を引いているということを示していた。
地球以外の星に知的生命は存在するか、という宇宙に関する問いは、新天地よりも、ゴールド以上の価値がある物質よりも、強く人を惹きつける命題の一つだった。その一方で、決して実在が確認されることもなく、専ら、フィクションの中だけの存在だと目されてきた過去がある。未解決問題、だったのだ。
今、その結論が目の前にあるという事実に、母は目を輝かせていた。
ひょっとすると、人は無意識レベルで宇宙人と出会うことを渇望していたのかもしれない。何せ、そうすることでしか、宇宙の知的生命のスタンダードを知ることなどできないのだ。
人は古来より、異人との接触によって、自身の性質や、自身の所属する集団の特徴を俯瞰してきた。他所の人と話をしている時、ふと「これは、うちだけのローカル・ルールらしい」と気づくみたいに、だ。これが何を意味しているかと言えば、人は宇宙人を見ることで、地球人らしさというものを、初めて自覚するだろうということだ。
いずれにせよ、宇宙開拓時代を迎えてから百年以上の月日が経った太陽系圏でも、地球人らしさというものは未だ存在しているらしい。
母の言葉は、その実在を証明するものだと言えた。
彼女を見て「自分とは異なる存在だ」と、確かにそう評したのだから。
1.
小さなモニタを光点が滑る。世間では空間投影だの、網膜投影だのとモニタの流行は移り変わっているが、目の前にあるのは溜息が出るほど古いタイプの板だ。コクピットのシート右側からアームで支えられた、それは、機体が向きを微調整する度に慣性で軋んで揺れていた。
左舷スラスタの反応もやや鈍い。きっちり整備しているはずだが、これはもう、こいつが年寄りだからとしか言えないだろう。
両手のコントロール・スロットルを微細に動かして、今後こそ、光点をモニタの中心に。三次元レーダーで、飛来する目標物を正面に捉えた。
「FL1からFL2、及びFR1からFR2マニピュレータ展開」
呟きながら、指差し、ワンテンポ置いてからトグルスイッチを上げる。搭載された四対八本のマニピュレータのうち前面側四本で、捕棺網を展開した。ここまで異常無し。長めに息を漏らし、中ほどまで注意力を落とす。
手元のモニタから目を離し、前を見る。そう広くないコクピットの前面を、星空を映すメインモニタが占めている。
漆黒の宙に、星々が瞬いていた。目標物は、まだ視認可能範囲外にあるが、三次元レーダーで正面に捉えている限り、待っていれば、向こうからやって来るだろう。
俺は、棺を待っていた。チタニウムの棺だ。何の比喩でもない。
宇宙を漂う棺を、中型の作業ロボット……汎用船外作業用重機コバンザメに乗って、待っている。
平らな面を上とした正三角錐に、楕円柱状の胴がくっついたようなロボットだ。コバンザメという俗称に反して、マニピュレータ四本で網を張る様子は、深海に漂うクラゲのように見えるかもしれない。
こうして指定ポイントで網を展開し、彼方から飛んでくる棺をキャッチする。
それが、俺の仕事だった。人類が地球から宇宙に進出したばかりの頃、このような仕事が生まれることを、誰が想像しただろう。
「ダズン、聞こえていますか?」
無線から、名を呼ぶ声がした。少女の声だ。
母船シーラカンスで留守番をしている同居人の声だった。
「どうした、シャル」と名前を呼ぶ。発音としてはシヤロに近い。
「どうしたということはありませんけど」
通信の向こうで、逡巡するような間が空く。別に騒がしくしている覚えもないが、静かな艦に残されて、やはり落ち着かなさを感じているのだろう。脳裏に、少女が、話題を選んでいる様が思い浮かんだ。輝くような金髪が目を引くハイティーンである。
「これってやっぱり、地球方向に飛んでいるんでしょうか」
数瞬して、いつもの話題に行き着いた。これというのが、レーダーに映る光点……チタニウムの棺を指すことは明らかだ。
「多分な」
第一に肉眼で地球が判別できる距離ではないし、シーラカンスにしろ、コバンザメにしろ、ヘリオスフィア規模の分解能を持つ絶対座標系の航路計なんて高級品は積まれていないので、確かめようもない。
だが、星海葬という性質上、恐らくそうなのだろうと思う。
星海葬。それは、人は地球に属し、地球に還るべきだという思想から生まれた、人が地球へ還るための儀式だ。
彼女はこれに、少しばかり疑問を持っているのだろう。
「何故、人は星海葬の魅力に囚われるのでしょう」
「……地球をルーツとする知的生命だからだろう」俺は答えた。
宇宙で死期を迎えた人間は、その魂が地球へ帰還することを望むという。
人類がまだ地球を主な生活圏としていた頃、地球上で死んだ人間が地球の生命に転生するという考え方は普通だった。実際、物質的に見ても、人が死んだ時、人体を構成する元素は別の地球上の物体へと姿を変えていくのだから、魂の循環という考え方は感覚的にイメージしやすかったはずだ。
しかし、地球を遠く離れた場所で人体が処分されれば、地球に還ることはない。その事実は、魂もまた、還れなくなるという自然な連想を生んだ。人類が地球を離れて活動するようになった時、転生という宗教概念は破綻したのだ。
実際、宇宙開拓初期における、地球の神々の凋落はシリアスな問題だったらしい。地球が宇宙に浮かぶ光点の一つに過ぎないと分かった時、たかだか半径六千三百キロの岩石塊の表面で謳われていた神々に何ができようか……と思うのも、無理からぬ話ではある。宇宙開発黎明期、ソ連の宇宙飛行士チトフもこう言ったという。「私はまわりを見渡したが、神は見当たらなかった」と。
あるいは、いやだからこそというべきか──そう認めるからこそ、神の恩寵の届く星に還りたいという欲求は強まるばかりだったのだろう。
「そうまでして地球に還りたいのでしょうか」
「宇宙で死んだ人間の灰を、地球に持ち帰ることが禁止される程度には」
それが一般的だった頃、いずれ地球は灰まみれになるのではと揶揄されていた。
地球行の宇宙貨物艦の荷に占める灰の割合は加速的な増加傾向にあった。宇宙規模で繁殖し始めた人類が、帰属意識と伝統と宗教心のままに灰を地球に送るようでは、当然そうなる。そして、今後も増えていくことを危惧した連邦により禁止された。当時は反発もあったというが、長期的に見て公益性は高く、今では妥当視されている。
星海葬なるものが市民権を得たのは、その頃からと聞いていた。
物質的な帰還が叶わぬ以上、魂だけは帰還できるように。人々はそう願いを込めて、地球へ向けて棺を打ち出すようになった。
「そうしたら、今度は金属資源の散逸だ、なんだという話になった」
広大な宇宙空間に棺という形で無作為に金属資源が散らばる傾向は、嬉しい事象ではない。単に資源の有無だけで言うなら、適当な地球型惑星から採掘し続ければいいわけだが、それを無駄にしていいかは別だ。
保安上の都合から見ても、意図的にデブリを増やす行為が推奨されるわけはなく、星海葬もまた、連邦によって禁じられる瀬戸際にあった。
「しかし、それは今でも行われています」
「そうだな」誰が見ているというわけでもないが、俺は頷いていた。「スペース・セクストンと呼ばれる団体が生まれ、星海葬をシステム化した」
スペース・セクストンは、宇宙教なる宗教機関として星海葬を斡旋し、宇宙に流された棺を適切に回収する役目を公然と担うこととなった。
今では、星海葬は宇宙で最もポピュラーな葬��だ。純粋な地球生まれの地球人がほとんどいなくなった現在でも、セクストンはしっかりと存続しており、多くのエージェントが所属している。
俺もその一人だ。改装した古い小型貨物艦船で、棺を回収している。
連絡艦、旅客艦、貨物艦、遺棄船漁りのスカベンジャー、宇宙海賊、軍艦。宙を往く船にもいろいろあるが、セクストン認可艦の辛気臭さは最高峰だろう。他人を乗せることもなく、華やかな客室もなく、積荷は棺で、一攫千金の夢もなく、争いもなく、地位も名誉もない。
「私がいるではないですか」
どこからか、口に出していたらしい。
不意に、そう言われた。何故だか慰めるような言葉を投げ込まれ、俺は笑う。
2.
コバンザメの狭いコクピットから這い上がり、シーラカンス艦内に戻ってきた。艦内の人工重力に気怠さを感じながら、ヘルメットを外し、後部右舷通路を歩く。流れで首元に手をやりかけて、直ぐに下ろした。
「やれやれ」と口の中で呟き、そのまま、棺を運び入れた格納庫へ向かう。
棺の回収が終わったら仕事が終わるかと言われれば、そうでもない。
回収した棺自体は最終的にはセクストンの溶鉱炉で生まれ変わるわけだが、受け渡す前には、中身のチェックをする必要がある。
セクストンの仕事は総じて気乗りしないが、個人的に一番気乗りしない作業だ。人によっては、一番ワクワクするらしい。死者が生前愛した何某を棺に入れる……という風習は根強くあり、炉に入れると不純物になるからというような大義名分の下、懐に入れることが認められているからだ。
以前、少しばかり同業の集まりに参加する機会があったが、それで美味しい思いをしただとか、そういう話は聞く。俺はその説について賛同できないが、昨今の情勢は安定しているので、腐乱しているだの、欠損しているだの、そういう死体を目にすることは、あまりない。それだけが唯一の救いだ。
梯子を下りると、格納庫の前には黒いボディスーツに身を包む少女が待っていた。
彼女……シャルは、しなやかなボディスタイルを露わにする、いつも通りのスーツ姿である。宇宙での活動は今なお、決して安全ではないが、古典映画で見るようなモコモコとした着ぐるみは廃止されて久しい。今の主流は、生命維持デバイスと防護外骨格の展開機構が備わった汎用スペーススーツである。俺や、彼女が着ているそれだ。
彼女は手にしていた情報端末からこちらに視線を動かすと、壁から背中を離した。
「お帰りなさい、ダズン」
「ああ。どうも、異物反応があるらしいな」俺が言うと、彼女は頷いた。
棺をシーラカンスの搬入口に運び入れた時にアラートが鳴ったかと思うと、すぐにシャルから通信が来たのだ。棺の中に、何かがいる、と。
気が重くなる。
異物反応センサーは棺内をスキャンした結果、動体と熱源が確認された場合にアラートを出す。そういう意味では、しょうもない悪戯(例えば、熱を出して動くおもちゃが入っていたとか)の場合もある。
しかし、棺の中に、もしも生きている人間が入っていたら? 放っておけば、そのまま焼却されることになる。寝覚めは最悪だ。
「じゃあ、始めましょうか」
彼女は首元にあるパネルをトンと叩いた。そこには防護外骨格を着脱するためのパネルがあって、青く点灯する。シャクシャクと小気味のよい金属質の擦過音が響き、彼女の体表を、背中から包むようにアーマーが広がっていた。
防護外骨格は、背骨に沿って等間隔に配された六つの小さな突起パーツ内に圧縮格納されているため、展開する際には背面から広がるようなプロセスを踏む。
俺は、自身のアーマーを確認しながら、シャルの展開を待つと、格納庫のシャッターにアクセスした。
ブザーの音。大仰な開閉音。一瞬遅れて、照明が点灯する。
「また家族が増えるかもしれないですね」シャルはそう言いながら、格納庫に入った。
「それは、ゴメンだな」
そう返すと、彼女は苦笑した。
俺たちは、いくらか積まれている棺たちを見ながら、最後に格納した棺の方……つまり、搬入口に近い方へと足を向けた。
棺は、基本的に幅二メートル、縦三メートルのサイズだ。その大きさの大部分は装甲/気密機構/保冷材/副葬品というように、遺体以外の要素に由来する。遺体を入れるスペースは必要以上に広くする理由もなく、人が最後の旅に出る船としては、適度なサイズとも言えるだろう。
見栄っ張りな富豪が、とてつもない大きさの棺で星海を往くこともあるが、そういう手合いはVIPなので、俺みたいな末端のエージェントが担当することはない。
これらの棺は、この後、金属製の外装部と内部の有機物フレームに分別される。外装は溶鉱炉へ、内容物は焼却炉へ投入されることになる。しかし、回収してすぐに炉に行くというような感傷的なスケジューリングは基本的に認められないため、回収された棺はこうして庫内で並べられて、その時を待っているのだ。
「これですね」「ああ」
棺を挟んで、立ち止まる。
俺は腰の自衛用のハンド・レーザーウェポンを抜いた。マニュアルによれば、棺の中に異物反応がある時、それはセクストン・エージェントの脅威となる可能性もある。本人が死んでない場合。遺体が別のものにすり替わっている場合。遺体もあるが、別の生物が紛れ込んでいる場合。それぞれ事情は異なるが、どの場合でもレーザーウェポンによる対象の殺傷がベストプラクティスとなるケースは多い。結局のところ、棺の中にいるのは死んでいるはずの存在なのだから。死人に口なしだ。
向かい側に立ったシャルに目を向けた。
金色の髪に、金色の瞳。色白の肌。整った美貌は作り物めいている。彼女は、俺の視線に気づいて、こくりと頷いて見せた。
「……では開けよう」
棺にアクセスし、アンロックコードを送信する。セクストンの関係者だけが取得できるコードだ。このロックの施錠もセクストンが司っているため、セクストンが開けられる棺は、セクストンが斡旋した正規の棺である、という証明ともなる。
ピッという簡素な認証音。
何かの手続きを無視した葬儀ではないようだった。少なくとも今回は。
スライド式のドアが開き始めて、冷気が漏れる。
「顔を近づけすぎないように」
腐敗を防ぐためにドライアイスが入っているのが通例だ。濃い二酸化炭素は一瞬で好気性生物の意識を刈る。別れを告げる遺族が棺に溜まった二酸化炭素を吸引して意識不明となり、そのまま死亡するケースは多い。
「……異物反応があるんですよね?」
「一応だ」確かに、棺内の空気成分自体に問題はない可能性は高い。紛れ込んでいる異物が生きているということは、逆説的に空気に問題ないとも取れる。
いよいよ、ドアは完全に開いた。
初老の男性だ。体格はいい。髪は白髪交じり。確かに、生命反応が無いとしても、今にも動き出しそうではある。新鮮な死体だ。
「今のところ、異変は無い」
「そうですね」
と言った舌の根も乾かないうちの話だった。視界の隅で、黒い何かが蠢く。
瞬間的に、レーザーウェポンを向けて、スイッチする。青いエネルギー弾が瞬き、遺体の腕を焼いた。黒い何かは、素早く這い回っている。大きさは三、四十センチに達する。大型の齧歯類ないし、比較的小型の猫科。そう思い、いや、と否定する。
黒毛のずんぐりとした胴。手足には毛がなく、灰色で、不気味なほどに細長い。脳内の何にも該当しない生物だ。
そいつがガサゴソと棺の中を這う音は、耳障りで、嫌悪感を抱かせた。
「閉じろ!」俺は怒鳴っていた。
シャルが頷くと、ガコンと力任せにドアが閉じた。だが、棺が閉じきる前に、そいつはもう、飛び出していた。
「ちっ……!」
目の端に映った影に、エネルギー弾を叩きこむ。
棺が積まれた庫内に火花が散った。だが、それだけだ。
当たろうはずがなかった。この倉庫には、棺があり、死角が多すぎる。
俺は、そのクリーチャーを捕捉できていなかった。
事実、そいつの鳴き声は背後から聞こえた。
「ダズン!」
その声に振り向いた時、目の前にそいつが迫っていた。
黒い毛の中に、醜悪なまでに開いた口が見えた。口蓋が見えるほどだ。汚れのこびりついた不清潔な牙が、ずらりと二重に並んでいる。明瞭に見えた。それは紛れもなく、死の前にある体感時間の伸長体験のように思えた。
だが、幸い死ぬことはなかった。怪我をすることも。
透明な何かに弾かれたように、そのクリーチャーが吹き飛び、強かに、床に叩きつけられたからだ。
「捕えます」少女の声。そして、手のひらを、下から上に。握る仕草をする。
不可視の尾の如き力場が、クリーチャーを巻き上げた。
黒い毛が不自然に押さえられ、手足があらぬ方向に曲がっている。その様が、よく見えた。目の高さに浮かんでいる状態だからだ。その様はまるで、見えない蛇に巻き付かれて、全ての動きを封じられた哀れな被捕食者だった。いや、全てではない。活路を探しギョロつく眼球、手足の指はもがき、そしてその心臓は動いている。
そいつは、潰されまいと懸命に爪を立てるが、抵抗は無駄だった。
彼女の力場には、痛覚も実体もない。それは彼女の尾骶骨の延長上から伸び、自由自在に動く第三のカイナだった。出し入れ自在かつ、最長で十メートルに及ぶ、純粋なる力の尾である。
「ふー」
それが、彼女の……血統(ジーン・)加速者(アクセラレイテッド)、シャル・ラストテイルの異能だった。
彼女は、地球人と異星種との交配種だった。
異星種のサイキック遺伝子を継承し、研究施設で生まれた実験体である。それだけでも驚いたが、彼女はただの交配実験体ではない。血統加速……時空歪曲を利用した人為的な世代交代の加速による特定能力の選択的先鋭化実験……によって現代に生まれた、約五千年後の世代と推定される超能力者だった。
本来ならば、交配種に連なる者たちが五千年の月日の中で獲得する超強度サイコキネシスを、現代に持ち込む技術。それは、彼女に超越的な力と、絶対的な孤独を与えている。
「ありがとう。助かったよ、シャル」
少女は前に出していた手を下ろした。クリーチャーは宙に捕えたままだ。力の尾は、彼女の手の動きに同期するものではないので、手を動かすのは、近くにいる俺に注意を促す意味が強い。
「これ、どうしますか?」彼女は言った。
「始末しよう」
特に、他の選択肢はない。明確な対人凶暴性を発揮した危険生物だ。特に、生きたまま保護して提出するような義務もない。
俺がレーザーウェポンを構える前に、彼女はこくりと頷いた。
「グギィ……ッ」
なんとも耳に残る断末魔だった。尾が締まり、クリーチャーが弾けた。付近の棺に、床に、赤い血肉が飛び散る。
「……ああ、うん。ありがとう」
「ううん」彼女は顔色一つ変えず、軽く頭を振るう。
既に尾は消えていた。それ自体は間違いなく不可視だが、斥力の集合体なので、周囲の空気を押しのける。発生や消滅は空気の流れで何となく分かる。避けられるかと言われれば、俺には不可能だが、有無の変化くらいは分かるものだ。
「シャルは先に戻っていいぞ」
「ダズンは?」
「掃除だ。シャルも、興味あるか?」
彼女が微妙な顔をするので、俺は笑った。
彼女を見送り、改めて惨状を確認する。どんな寄生虫を持っているかも分からないクリーチャーだ。消毒も必要だろう。肉塊にくっついたままの眼球が、こちらを恨めしそうに見ていた。無論それは主観的な感想に過ぎず、それは既に絶命している。
3.
片付けを終えて通路に出ると、そこは既に暗くになっていた。足元にはぼんやりと光る非常灯が、点々と続いている。夜になったらしい。
宇宙において昼夜という概念は希薄だが、人間の営みには、昼夜という概念が必要である。それは宇宙開発が進み、宇宙が一時的にいる場所ではなく、生活圏へと次第に変わっていくなかで、明確にルール化する必要が出た事柄だった。人は一時的に昼夜のない場所で過ごすことはできるが、それがずっととなれば話は異なる。
地球人は、地球上の環境に適応した地球生物種の一つであり、地球で生きていたからこそ、今の形になった。となれば、地球環境の一要素である昼夜が消滅した時、人はその異常にストレスを感じるし、その環境で世代を重ねるごとに、地球人ではない別の何かへと変貌していくことになるだろう。
人が人として種の形を保つための法。それは連邦により規定された照明制御規則として、宇宙船やコロニーで運用されている。ライフライン設備、防災上の事情により特別に規定された区画を除き、約十三時間の連続した活動タームにつき、十一時間の休息タームを設け、当該施設内共用部分の照明を規定光量まで落とさなくてはならない。
このルールは制定以来、その制定理由の尤もさから重要視されており、少なくとも、民間モデルの宇宙船にはデフォルトで採用されている。当艦……シーラカンスも、もちろんそうだ。
目が慣れて来たので、俺は非常灯の明かりを頼りに歩きだす。
別に、手動で点灯させることはできるが、最近は、そういうことはしない。同居人がいるからだろうか。自問しながら歩く。
しかし、そういう気遣いは、とりあえず今回は無駄だったらしい。
居住区画に入ると、明るい光が俺を出迎えた。
「お帰りなさい。シャワーにしますか? サンドにしますか? それとも練・り・餌?」
目の前にシャルが立っていた。逆光のためか、不思議な圧がある。
その右手には、トレーに乗ったサンドイッチが。左手には、銀の包装に包まれた手のひら大のパックが乗っていた。
「……なんの真似だ、それは」
俺がトレーを受け取りながら横を抜けると、彼女は「同棲する地球人の男女は、古来より、このようなやりとりをしていたそうですよ」等と言った。
「そうか」と流した。俺も別に、地球生まれではない。だから、絶対に嘘とも言いきれないが、無論、本当とも思えない。あと、同棲ではなく同居が正しい。
「練り餌は違うんじゃないか」
その名の通り、ペースト状であることが特徴の宇宙糧食だ。銀色の密閉されたパッケージに入っており、保存性に富む。もちろん、それは俗称であり、非常に長く厳とした公式名称も、公式略称もある。だが、その風情なさとネットリとした食感から、専ら溜息混じりに練り餌と呼ばれるのが常だ。
談話スペースにある背の高いスツールに腰かけると、向かいにシャルが座る。
「確かに、これでは食の選択肢が被っていますしね」
そう言いながら、彼女はその話題には大した興味も無いようだった。
「というより……起きてたんだな」
「先に消灯するのも申し訳ないなと思いまして」そう言いながら、手伝おうという方向にはいかないのが、彼女の意外と強かなところか。
サンドイッチを口に入れる。
パサパサした合成パン。風味のない合成バター。ひたすら特徴のない辛味を放つ合成マスタード。コクがなく、平面的な合成マヨネーズ。脂っこいだけのベーコン。しんなりした食感の合成レタス。青臭さがオミットされ、味が単純化した合成トマト。フードプリンターが有機フィラメントから生み出す食材は、全てがオリジナルに劣る胡乱な複製物だが、それでも練り餌よりかはマシだった。
「美味しいですか?」彼女は言った。
「ああ」と俺は返す。
それは、彼女を料理係として雇った時から、繰り返しているやり取りだった。
「……客観的に見て、美味しそうに食べているようには見えませんけど」
確かに不味い。それは、シャルの料理の腕とは別の部分にある問題だ。すなわち、食材の限界である。
だが、スペースを取り、保存コストも嵩む天然食材の貯蔵には限度がある。仕入れても、一、二週間もすれば、また合成食材の生活になるだろう。中途半端に積むより、オフや寄港の楽しみにしておく方がメリハリになろうというものだ。
それに、彼女には、複雑な味わいの食材を上手く扱うことはできないだろう。
「手料理なのが重要らしいぞ」
目の前に料理があるなら、いつもの二倍幸せだ。それが手料理なら、さらに二倍。自分以外の手によるものなら、そのさらに二倍。つまり八倍の幸せだ。それは、父親の言葉だった。とても古い記憶の一つだ。父が、まだ明朗だった頃の。
尤も、その言葉の続きには「だが不味ければ零倍」というオチもあったが、言わぬが花という言葉の意味は知っているつもりだ。
「私も、少し、喉が渇きました」
彼女は言った。どうでもよさそうな声色だ。
そのくせ、金の瞳は輝いていた。
「そうか」
予想外ではなかった。力の尾は、彼女の体力を消耗させるからだ。
折よくサンドイッチを食べ終えた。
俺が立ち上がると、シャルも椅子を降りた。
特に言葉は必要ない。それはすでにルーティーンとなっていたのだから。
「じゃあ、シャルも食事にするか」
彼女は頷いた。シーラカンスには、それぞれに個室を用意してあるが、今日は二人で俺の部屋に入ることになった。
そこはこぢんまりとした部屋であり、備え付けのベッド、棚、情報端末だけが置かれており、古の単位で言えば、六畳ほどだ。これは、シャルの部屋でも同様だった。宇宙船の設計というものは、有限のスペースを活動空間/装置/リソースで取り合う陣取りゲームである。精神健康上の観点から、登録乗員に対する最小の居住区画容積と、人数分の個室の設計が遵守されているが、削減されやすいのは個室のサイズだった。
そんな狭い室内で、俺は汎用スペーススーツを脱ぎ始めた。といっても、大袈裟な話でもない。肩を抜いて、上半身を開けるだけだ。
隣で、シャルもスーツに手をかける。
彼女の、白い肢体が露わになった。
金の髪、金の瞳、いっそ不自然なまでに整った美貌。華奢な���元には鎖骨がくぼみを作っており、乳房がふっくらと佇んでいた。薄い胴はしなやかに伸びており、まるで無意識下にある理想を彫像にしたようだ。
その途中、鳩尾辺りから、肌がすっと透け始めている。幾重もの白い半透明の表皮が覆うようになっており、その下にある、青い筋肉が見えていた。彼女の下半分は、シルエットこそ人間のようだが、異星種の特性を確実に受け継いでいる。
背中側はお尻のすぐ上までは人肌で、前後で変貌の境界は異なっていた。ただ、頭から肋骨の辺りまでが人間で、腹から下が異星種であるという意味では、一定のルールの下で明瞭に分かれている。
白いショーツだけになった彼女が、じっと、俺を見ていた。
ベッドサイドのパネルを操作して、光量を落とす。仰向けに寝転ぶと、シャルがゆっくりと俺の上に覆い被さって来た。まるで恋人同士がそうするみたいだったが、彼女の瞳に宿るのは愛だの肉欲だのではないようだった。
ゆっくりと俺に体重を預けてくる。青い筋肉が透ける下半身も、見た目の印象からは想像もできないほど熱い。彼女はそのまま、俺の首元へと唇を寄せてきた。俄かに、甘い香りが鼻腔を擽った。
そう思うのも束の間、じくりとした痛みが首に広がった。我慢できないほどではないが、気にせず無視しようというのも難しい、痛痒にも近い、鋭い感覚。しかしその感覚も、熱で曖昧なものへと変わっていく。牙で穴が開いているのか、血に濡れているのかも、はっきりとは分からなかった。
ただ、こくんと、嚥下する音が響いた。その音は小さかったが、血が飲まれていることを自覚するのには十分だった。音は静かな部屋の中にあって、強く耳に残る。
彼女は血を飲んでいた。
彼女が引き継ぐ異星種の遺伝子がそうさせた。シャル・ラストテイルは、地球人と同じ方法で栄養補給をすることができない。内臓の作りが異なるからだ。彼女にとって食糧とは哺乳類の血であり、そのことが判明した時から、俺はこうして、彼女に血を飲ませていた。
俺は上半身を開けて。彼女は下着姿になって。
しかしそれは、儀式めいた行為だった。
やがて彼女が口を離すと、身体を起こした。
ぽたりぽたりと、赤い雫が落ちた。彼女の口元から滑り落ちた血がしずくになって俺の胸元に落ちた。
首元に手を伸ばすが、そこに傷はない。傷が塞がった後みたいな滑らかな膨らみの感触が、指先に小さく残るだけだ。
不思議なものだ。これは彼女が引き継ぐ吸血種の性質なのだろう。彼女たちは、ある種の麻酔成分と、血液の凝固を防ぐ成分を送り込む。多くの吸血生物と同様に、だ。それと同時に、牙を引き抜く時には傷跡の再生を促す。
尤も、彼女も最初からそれができていたわけではなかった。
彼女には、それを伝える親がいなかったからだ。
食事には、痛みと、今くらいでは済まない多くの出血を伴った。
彼女が自分の性質に気づき、慣れるまでは。
4.
ぼたぼたと血が滴った。シーツに赤い染みが広がっていく。
先ほどまで彼女が噛みついていた場所から、急速に痛みが広がっていた。
俺は用意していたタオルで押さえて、開けていたスーツを着込んだ。その手首にあるコンソールで、ナノマシン統制プロトコルを小外傷整形モードにする。普段は待機状態で循環/代謝されている医療用ナノマシンが、傷を察知して人体の働きを補助することで、通常の何十倍もの自然治癒力を発揮できる。
「……ごめんなさい」と彼女は言った。
その少女はシャル・ラストテイルと名乗った。美しい少女だ。正直なところ、彼女の口から謝罪の言葉が出ることにすら、俺は驚きを感じていた。
彼女は殉葬者だった。
かつては別の意味もあったが、我々の業界では、捨て子という意味になる。
彼女は、俺が回収したチタニウムの棺の中で、深い眠りについていた。
セクストンのライブラリによれば、そういった事案は稀にあるという。政治的な事情から、食糧事情……いわゆる口減らしまで。
宇宙開拓時代にもなって、望まれない境遇に生まれるケースというものは変わらずあるらしい。いずれにせよ、殉葬者らにとって、それは死んで元々の旅ではあるが、立ち会ったセクストンの匙加減次第では、生きる道が開かれることもある。
彼女は、棺で、俺の船にやってきた。
そして、その前は「ヒト殺しだった」という。
シーラカンスで目覚めた彼女の一言目は、それだった。
『二人の部屋は、ガラス張りの部屋。そこは白くて清潔で、狭くて、周囲にはいつも誰かがこちらを見ていた。食べる姿、寝る姿、彼らは何にでも興味があるようだった。時には血を奪われた。痛めつけられた。尾の力を見たがった。妹は、籠から出るには籠を壊すしかないと言った。だから、私はみんな殺して自由になった』
それは、彼女の観測する現実の話で、事実とは異なるかもしれない。
しかし、実際に超越的な力は彼女に宿っている。
それ故、彼女の事情も、また真なるものだと明らかだった。
俺は、その境遇から考えて、他人の痛みに対する常識レベルの配慮が欠けている可能性は決して低くないだろうと思っていたのだ。
「いや」と俺は少女に返していた。
何が「いや」なのだろう。俺は誤魔化すように続けた。
「だいぶん、体重は戻ったか?」
「……そうですね」と、シャルはスーツに包まれた自分の身体を、緩く抱く。
そんな彼女の肢体は、俺の目にも、最初に見た時より幾分か健康そうに見えていた。
シーラカンスで目覚めたばかりの彼女は、酷く痩せていた。生きていたのは、その身体に流れる異星種の血がもたらした強靭性の賜物だろう。
俺はシャルを引き取ってから、違法な情報屋を少しばかり頼った。
彼女は研究施設で生まれた実験体であり、地球人と異星種の交配実験体で、血統加速実験の被験者だった。試験管から生まれ、妹とされる存在とペアで生きてきた。そして妹と共に研究所を破壊し、外の世界へと飛び出した。一方は当局により身柄を確保されたが、もう一方は現在も行方不明である……。
それは推測だらけで、不確かで、そして馬鹿げたレポートだった。
だが、疑う必要があるだろうか。
彼女を棺から出して、ベッドに寝かせる前に、俺は外傷の有無を確認するために、その肢体を診る必要があった。その時から、彼女に人並み外れた事情があるだろうことは、明白だった。
上半身は地球人で、下半身は異星種。
彼女の身体には、それがハッキリと形として表れていたのだから。
シャル・ラストテイルは人ではない。
不意に目の前に現れた異形様の少女に、驚きがなかったわけではなかった。
彼女が持つ力に恐れがなかったわけでもない。
宇宙開拓時代でも、人殺しは罪である。それでも、殺すことでしか救いが得られないこともある。実験のために生み出された彼女が、実験のない日々へと至る道を、殺し以外で掴む方法があったかは分からなかった。
そうして外の世界に出ても、彼女たちには行く当てというものが無かった。
だから、棺の中にいたのかもしれない。
星海を漂い、殉葬者としてセクストンを頼る。その切符は一枚しかなかった。死者を納める棺に、内側の取っ手は不要なのだから。
彼女は多くを殺め、最後には、妹の献身によって、ここに至った。
それが、彼女の生だった。
人には人の生があり、実験体には実験体の生があるとも言えるだろう。そして、それを逸脱するには、罪を犯し、死に、そして生まれ変わる必要があったのだとも、解釈できた。彼女と人の差は何かと問えば、生まれとしか言いようがないのだから。
それは上手くいくだろう。
このまま地球人らしく振る舞うことを覚えれば、彼女は人の隣人になれる。
彼女は明らかに異星種の特徴を有しているが、人前で服を脱がなければ露見することはない特徴だ。人としての振る舞いを覚えれば、秘密は秘密のまま、人の輪に溶け込める可能性が残されている。
ただ、彼女の方は、そう思ってはいないようだった。
彼女の瞳には絶望があり、声は暗く、その立ち姿は、人間らしさからいっそ遠く空虚だった。
俺一人では、彼女をどうこうするのは難しいのかもしれなかった。
そう思ったのを、覚えている。
……。
「ありがとう、ダズン」
「ん、ああ……」
少しばかり、ぼうっとしていたらしい。
すでに彼女はベッドを降り、床に落ちたスペーススーツに手を伸ばしていた。
スーツと一体型となったショートブーツを揃えて、足を入れた。さらりと流れた金髪を少し押さえてから、彼女は足元でひと塊になっていたスーツに取り掛かる。脱ぎっぱなしにしていたそれを整えて、袖の位置を確かめると、ゆっくりと引き上げていく。丸まった背中に肩甲骨が浮かびあがり、揃えた脚を、ぴったりとした黒い布地が徐々に、包んでいった。
青い筋繊維が透ける白いヒップは、見た目の印象とは裏腹に、確かな女体の柔らかさを持っていた。スーツへと収まっていきながら、少し窮屈そうに形を変える。その肉感は、色彩を無視できうるほど艶めかしいものとして、目に映っていた。
実際、そこまでスーツを着ると、彼女は普通の……というには語弊のある美貌ではあるが……地球人の女性に見えた。
だが、そのスーツの下の秘密は、無かったことにはならない。
その事実を忘れさせないために、彼女はその美しい裸身を晒し、俺の血を飲むのかもしれない。
5.
汎用スペーススーツの上に羽織ったジャケットが、歩くのに合わせて揺れる。俺は腰までの黒い上着で、シャルはクロップド丈の白い上着。
セクストンのオフィスに、俺たちは連れ立って入った。
ホールには、数人のエージェントの姿がある。目は合うが、顔見知りはいない。そこで、シャルが視線を集めていることに気付く。
「あまり離れるなよ」耳打ちすると、彼女は心得たように頷いた。
同じエージェントとは思いたくない素行の人間は多い。
スペース・セクストンは、宗教団体と考える人もいるし、極めて物理的な、死体処理機関であるとも言える。いずれにせよ、地球人の勢力圏であるヘリオスフィア全域で星海葬を管理しており、単一の組織が影響する範囲としては、連邦に次ぐ。人類の宇宙開拓の総指揮を執り、渉外にあっては人類の意思決定機関として働く連邦という機関に次ぐと聞けば、高尚な感はあるが、実際に所属する人間はぴんからきりまでだ。
セクストンの人事は来るもの拒まず。それは、いい面もあり、悪い面もある。悪い面の一つが、末端ほど、何某崩れしかいないという点。良い面は、社会信用度ゼロの人間でも、エージェントとして生きていける点。つまりは、セーフネットとしての面。俺もその面には少しばかりの恩恵を得た身だった。
シーラカンスは、荼毘炉に寄港していた。
ここしばらくの回収にひと段落がつき、一度、荷を下ろす必要があったからだ。
荼毘炉は、セクストンが経営する小さなコロニーの総称だ。ヘリオスフィア全域に点在しており、どこでも同じ機能を備えている。宇宙港、簡単な整備ドッグ、精錬プラント、遺体焼却炉、一時滞在用のホテル、エージェントを管理するオフィス、オフィスワーカーたちの居住区、マーケット、食糧生産プラント、小規模な歓楽街等があり、収容人数は場所によって異なるが、最小では数万ほど。
オフィスの窓口に近づくと、カウンターの向こうにいる男性は肘をついてこちらを見た。妙に若く、気怠そうな表情だが、小規模な荼毘炉オフィスの窓口係としては、やはり珍しくない。隣のシャルは何か言いたげにして、黙った。
「……納入ですかね?」
「ああ。艦名は、シーラカンス」
情報端末を差し出す前に、食い気味にピピッという認証音がした。本当に確認しているのか怪しい速度だが、手続きは済んだ。
しばらく待っていれば、セクストンの分柩課が勝手にシーラカンスの体内に貯め込んだ棺を運び出し、代わりに連邦クレジットが口座に入る。
分柩課は、文字通り棺を分別する役目を担っている連中だ。金属として溶かして再利用する部分と、遺体を焼くための部分を分別し、炉に投じる準備をする。
「他に何か?」
「報告があるんだが」
俺が言うと、彼は「はあ」と気の乗らない声。
「棺から、このくらいの獣が現れて、襲われたんだ」
言いながら、両手でサイズを示していると、その係員はやっと俺の顔を見た。彼の瞳が初めて俺を映す。面倒くさそうに、鼻を鳴らした。
「防疫課は向こうだよ」
「怪我はしてない。そうじゃなくて、例えば、似たような報告は? ああいうのを棺に仕込むのは流行りだったりするのか? 何か情報は?」
「さあね」
シャルがほとんど溜息のような、長い息をついた。
やれやれ。
オフィスを出て、メインストリート・ブロックに入る。通常のコロニーは、いくつかのモジュールの集合体である。いわゆる隔室型宇宙都市だ。屋内/屋外という概念は無いため、隔室型宇宙都市の全ては屋内だが、どの施設でもない接続用モジュールも存在しており、それらはストリート・ブロックと呼ばれている。
「やる気がなさすぎると思いませんか?」
「セクストンとは、結局、そういうものだ」
「それにしてもです」
「まあな……」と俺は空を見上げた。
空と言っても、天井の映し出された空だ。閉塞感を緩和しようとしているもので、その努力を考慮しないとすれば、モジュール単体のサイズは、さほどでもない。上方向だけで言うなら、三階建て以上のビルは入らない程度だ。
二人でメインストリート・ブロックを歩く。
宇宙都市内には当然のように空気があり、疑似重力によって、地球人にとって都合のいい環境が整えられている。宇宙都市というのは何型であれ、どこもそうだ。空気がなかったり、無重力だったりする環境は、人間種の正常な生育にとって都合が悪いのでコロニーとして認められない。
通りは晴天状態で、通行人はぼちぼちと行き交っていた。荼毘炉にはセクストンやその関係者しか近づかないが、閑散としているわけではない。エージェントにはそれなりの人数がおり、そしてそれぞれに家族がおり、空腹になれば、食欲を満たす必要があるからだ。昼時になって、人々の動きは活発だった。
「……仮想レストランですね」と彼女が言う。
「だな」
軒先から見える限り、どの店もそれなりに盛況なようだ。客がスツールに座り、虚空に向かって見えないフォークを繰っている様子が見えた。一見すると、少し滑稽なようにも見えるが、彼らには美味しそうな料理が視えていることだろう。
ミクスト・リアリティによる食事提供は、現代では一般化した光景だ。彼らは、網膜に投影されたホログラムを現実に重ね、レストランのネットワークとナノマシン統制プロトコルを連携することで、任意の味覚/食感データを脳内に再生している。
「入ります?」
「いや」
「私の作る料理より、あっちの方が美味しいのでは」
「そうかもな」
味覚/食感はデータで楽しみ、栄養補給は練り餌で済ませるというのは、コストパフォーマンスに優れた食の形式だ。データは買えばコピーペーストできるし、練り餌も完全栄養食として流通している。本来論で言えば、こうして店先にいる必要性もないのだが、友人と食事している、とか、外食している、といった事象自体にバリューがあるのだろう。会計時に渡される練り餌をそっちのけで、味覚の摂取と世間話に集中しているようだった。そして、店側としても、調理によってハイクラスな味と栄養を両立できる形に加工するのは、よりコストが必要となってしまう。
総じて、料理というものに、こだわりがある人というのは少ない。
俺がそこに拘泥しているのは、親の教育の成果だろう。
ふと、シャルを見ると、彼女は少しばかり面白くなさそうな顔をしていた。
「どうした」
「美味しくないけど、作れと言っています?」
「まあ、そうだ」
「あまりに悪びれもなく言いますね」
「不味いとは言ってない。プロの域には達してないというだけだ」
自分からそう言うよう誘導したくせに、とは口にはしない。
そもそも彼女は料理に関してはハンディキャップがある。
彼女は地球人とは栄養補給方法が根本的に異なり、従って、人と同じ体系の味覚器官も持っていない。それでも、食べられるラインのものを作ることができるのは、分量の計算で味の着地地点をコントロールできうるからだ。
とはいっても、言うは易く行うは難しというもので、実際にそれをハズレなく遂行できるのは彼女自身の努力の結果であり、師が良かったという面も多分にあるだろう。
それから、有機フィラメント食材の味が単純化されているという面も。辛いものは辛く、甘いものは甘く、酸っぱいものは酸っぱく、各食材の個体差や複雑な要素は、詳細には再現されていない。よって、甘いものと甘いものを合わせれば、もっと甘い……くらいの解像度でも、想定と大きくずれる味になりにくいらしい。
「でも、言うなれば、私もプロですよ」
「……」と黙る。彼女の良い分も尤もだった。
俺と彼女の間にあるのは、まさにそのサービスを供給する契約だ。
シャル・ラストテイルは料理係として雇った。
「別にいいだろう。雇い主がいいと言っているのだから」
そういうと、彼女は「まあ……」と煮えきらない返答。
噛みついてはみたものの、料理を今以上の仕上がりにすることが困難であることは分かっているだろう。そして、それが原因でクビにされても困るということも。
そもそも、何か仕事を……と言い出したのはシャルの方からだった。シーラカンスに乗っていたい。そして、乗るからにはクルーとしての仕事を熟さなければならないのだと、そう思ったのだろう。
別に、捨てられて生きていけないということもないだろうに。彼女の容姿と能力を以てすれば、それなりの待遇を得られる可能性は高い。単に荷運びとして考えても、彼女の力は非常に有用だ。服の下がどうなっていようと運送に支障などない。
確かに血を飲むが、別に輸血パックでもいいとも言っていたし、実際、施設にいた頃はそうだったと本人も言っていた。
「あの……ダズン?」
どこかに行こうとしていた思考が、その声で帰って来た。
シャルは路地の方を指さしていた。そこにはフードを被った男がいて、こちらを見ていた。人通りの中から、自分たちを見ているのだと、何故か理解できる。彼は、そのまま、お辞儀をするような仕草をして、���を返した。
「追おう」
「う、うん」
路地に入る。どこの路地裏もそうであるように、表に入りきらずに溢れた猥雑さが溜まっている。勝手口に、室外機に、ゴミ箱に、非常階段。少し歩くと、フードの男が俺たちを待っていた。彼はフードを被っているばかりか、サングラスと、マスクを着けていた。これでは黒い肌を持つことしか分からない。この手の、身元グレーなメッセンジャーの正体を暴くことに何の意味もないが。
「誰かが、お前たちを狙っている」と男は告げた。
その誰かとは、恐らく、シャルの行方を捜す者たちだ。
しかも、多分、思っていたのとは違うタイプの。
脳裏に二つの声が響く。これまでバレなかったのに、という声と、それから、ずっとバレなければよかったのにという声だった。
6.
「どこに向かっているのか、教えてくれてもいいんじゃないですか?」
艦橋に響くシャルの声は、少し非難の色を帯びていた。シーラカンスくらい小型の宇宙船でも艦橋というものはあり、コクピットとは異なるものとして定義される。立派ではないが、そこには艦長の席があり、オペレーターの席がある。前方には、シアターのようなサイズのスクリーンがあって、最低限ながら、宇宙船の艦橋というものの体を成していた。
そして、スクリーンには航路図が表示されているが、今は、コンソールの向こうに立ったシャルが視界を塞いでいた。
「そうだな。別に、教えたくないということもなかった」
「なら、もっと早く言ってくれて、よかったじゃないですか」
そう言われてから、どうにも気が急いていたのだなと、ついに初歩的な自己分析に達する。しかし、それを正直に言うのも憚られた。憚る理由の方は分からない。自己分析が足りないのかもしれないが、もはや手遅れだろう。思考を放棄する。
荼毘炉を去って��ら、すでに三日経っていた。そのことから、彼女の忍耐力は非常に高いといって差し支えないと言えた。
「ワイズマンズ・シーサイドスクエアだ」
「月ですか」
「正確には月の裏側だが」
「……それ、どこから見た時の話ですか?」
「地球だ」
シャルが「ふーん」と俺を見た。言いたいことは分かる。別に地球生まれというわけでもないくせに、というような顔だ。
「生まれがどうとかではない」
「じゃあ、なんです?」
「連邦の定義だ」
この連邦の定義というのが、重要なのだ。何しろ、ヒトが人類史の中で学習したものは、その大半が地球環境を前提に語られる。代表的なのは、暦や時間だ。地球から遠く離れた場所でも、太陽暦や地球時間は基準として大きな意味を持っている。宇宙開拓による混乱を避けるため、連邦が基準として定めたためだ。
そう言いながら、航路計をチェックする。ヘリオスフィア連邦相対航路計だ。
艦の進路と、進行中の航路との誤差を割り出し、必要があれば軌道修正する。航路線と呼ばれる、宇宙空間に便宜的に引かれた線との退屈な比較/修正作業だ。
それをしなければ、シーラカンスが宇宙を飛びまわることはできない。連邦の定義する航路線が一定範囲に無い場所では、航行できないとも言う。
これは特にシーラカンスが旧式だからというわけでもなく、ほとんどの宇宙船は同じだ。相対座標系の航路計しか積んでいない。ヘリオスフィア内の艦は、どのみち、星々を最短経路で結んだ航路網に基づいて運航するものだ。航路線に関わらず自身の座標を知ることができるという絶対座標系の優位性を、航路網が充実しているヘリオスフィア内で感じることはない。道具は、それを役立てる機会のある船にこそ意味がある。例えば、ヘリオスフィア外を往く、連邦開拓局の艦とか。
「里帰りですか」と彼女は言った。
「そうだ」
ワイズマンズ・シーサイドスクエアは、月の裏に作られた都市だった。
そして、俺の両親が住んでいる。
「半年ぶりくらいですね」
言われてから、そうなるかと、表情には出さないままに自問した。
シャルと出会って、すぐ後に、一緒に訪れたことがあった。助言をもらいに、あるいは、そのまま実家に置いて行こうかと考えて。
その頃の俺は、シャルの扱いに迷っていた。どうにも、年頃の女の扱いが分からなかったというのもある。幼少から、周囲には女ばっかりだったはずなのに。長いセクストン生活が祟ったとでも言うのだろうか。
もちろん今も、分かってはいないが、仕事仲間だと思えば、何とかはなった。
俺がそう扱えば、こいつもそう応えてくれた。
「真顔で、えっと、日数でもカウントしているんですか?」
もちろん違う。
「……月に行く理由は、あれが父からのメッセージだと思うからだ」
心裡にある感慨のようなものについて、あえて彼女に告げる必要はなく、俺は話の流れを元に戻した。少女は思案顔。
「そうだとして、どうして、その……怪しいメッセンジャーを?」
丁寧にオブラートに包んだ表現だ。コロニー内という安定環境下で目深にフードをしており、さらにサングラスとマスクで人相を隠している様を、不審ではなく、怪しいという範疇に留めておくのは理性的である以上に、少し面白くはあった。俺は一目で違法メッセンジャーの可能性を考えたが、彼女の目に、オブラートに包むことに足る何かが映っている可能性も皆無ではない。
「まず、普通に艦載通信システムが疎通できる距離ではないからだろう」
あの荼毘炉と月は距離が離れていた。航路線上で、七単位以上だ。航路線単位は、航路上の中継となりうる惑星間の距離である……という規定であるから、実際の距離としては、かなりタイミングによる揺らぎが大きい。普通の艦載通信であれば、航路線上で一・五単位も疎通できればいい方だった。
「では、連邦公共通信を使うとか」
「それが普通だな」と俺も思う。時空歪曲を利用した超長距離通信だ。
地球人が実効支配できる宇宙規模は一日以内に通信が届く距離に依存し、宇宙開拓の速さは通信技術の発展速度と相関するだろう……という宇宙進出前の未来予測は尤もなものだった。そして、それを乗り越えたからこそ、人類に宇宙開拓時代が訪れたとも言う。現代では、お金さえ払えば、民間でも利用できる類のサービスだ。
それならば、七単位も一瞬ではある。
含みのある俺の返答に、彼女は議論を諦めたようだった。
「それは、会えば分かるという判断ですか?」
「そうだ」
本当は、シャルの身柄を追う者には心当たりがある。父以外のイリーガルな存在が俺たちに警告を行った可能性もゼロではないが、あえてその可能性ではなく、父がグレーなメッセンジャーを用いた可能性を追求することについて、十分な説明ができる。
だが、それを口にするには時期尚早のようにも思えた。推測に過ぎず、何ら確信もない。父を訪ねようと決めたのは、確信を得るためとも言える。
「跳躍潜航に入る」
会話を断ち切るように俺が告げると、彼女も黙って定位置に着いた。
7.
到着には、それからさらに数日を要した。
ともあれ、延べ七単位分の超長距離移動が数日レベルの旅行で済むのは、跳躍潜航の恩恵と言えるだろう。これも、時空歪曲技術の進歩が地球人に齎したものだ。
そうして俺たちは、月の裏側最大の都市に降り立った。
直径百キロ余りもある冷えた溶岩による湖。その岸に、巨大ドームに覆われた月面都市がある。月の都、ワイズマンズ・シーサイドスクエアだ。宇宙開拓が始まって間もない頃、そこは新しいもの好きが集まる最先端の宇宙都市だった。地球から最も近く、遠い都市として人気となり、栄華を極めていたらしい。今となっては、偏屈の巣窟だ。
「相変わらず、継ぎ接ぎだらけですね」
「旧い宇宙都市の特徴だからな」
都市内部には、どこもかしこも、その施行年の新旧が年輪のように表れている。それが、時代遅れの天蓋型宇宙都市の特徴だった。
宇宙都市の寿命は決して長くない。外に空気が無いからだ。大気がない環境というのは、温度にも課題が生じる。月面では、昼夜で摂氏三百度近い温度差がある。そのような酷環境では、人工の殻の綻びが、そのまま人の死を意味する。安全基準は厳しく、経年劣化で問題が起こる前に改修することになる。ワイズマンズ・シーサイドスクエアだけでない。現存する天蓋型都市というものは、常に改修を続けている。全体のドームとしての機能を維持しながら、内装も外装も、だ。
港からキャリヤーを乗り継ぎ、俺たちは、一際寂れた区画に降り立った。
すん、と隣を歩く少女が小さく鼻を鳴らす。
「慣れないか」
「ええ、まあ」
人の生活の匂い以上に、都市工事用の重機による排気や、建材の加工時に生まれる粉塵、真新しい金属部品が放つ独特な臭いが、この都市の空気というものを構成している。俺にとっては慣れたものだが、彼女にとっては違うのだろう。
「この町は、やはり人の気配というものがありませんね」
「それなりに多く住んでいるはずだが」
「荼毘炉などよりも、むしろ陰気なほどです」
エアクリーナーも働いているが、健康への影響を軽微なレベルに抑える以上の効果を期待するのは難しい。この都市の空気で病にはならないが、別に快くもない。
だから、この都市には往来の人間というものがない。
人々はフィルターを通した無味無臭な空気を堪能するため、室内に籠っている。家同士を直接繋ぐ回廊文化ができるほどだ。高い天蓋に建ち並ぶビル群。その間を繋ぐチューブのシルエット。改修工事ですぐに書き換わる交通標識。道を往くのは、無人重機たちばかりだった。ビルは人々の生活の明かりを漏らすこともなく、暗いモノリスのように沈黙している。
かつて、このいかにも先鋭的な天蓋型宇宙都市を設計した天才たちも、ワイズマンズ・シーサイドスクエアの人々がドームの強みを捨て、このようなゴースト・タウンを作り上げるとは考えていなかっただろう。
「俺の故郷なんだ。手加減してくれ」
そう言うと、彼女はフームと頷いた。
ともあれ、ワイズマンズ・シーサイドスクエアが初期の宇宙開拓の失敗であったという点は明らかだった。この反省を活かして、以降の宇宙都市開発では、モジュール毎に安全な付け外しが可能な隔室型へと立ち戻っている。ここのように、ドームを維持するためにドームの改修を続けるような、財的にも住環境的にも高い負荷の生じる都市の在り方は、早々に否定されていた。
この都市の最大の悲劇は、宇宙開拓ペースが、多くの地球人の想定を遥かに上回っていた点にあるのだろう。ワイズマンズ・シーサイドスクエアが出来上がった後、連邦はその版図を爆発的に拡大し、すぐに多数の宇宙都市が出来上がった。かつてワイズマンズ・シーサイドスクエアに集まっていた人も、財も、果てなき宇宙に拡散したのだ。
流行に見放され、商業的な意義を失った田舎は、顧みられることなく廃れゆくはずだった。それでも未だワイズマンズ・シーサイドスクエアが存続しているのは、この都市を維持せんとする、血よりも濃い連帯があるからだ。
「皆は、元気にしているでしょうか」
「恐らくな」
角を曲がると、下品なネオンに彩られた店が姿を見せた。
店の外観など、回廊が整備されたワイズマンズ・シーサイドスクエアにあっては、どうでもいいだろうに。いや、どうでもいいからこそ趣味に走れるのだと、父は言っていた気もする。看板には、裏月酒店の文字。
ホテル・リーユェンと呼んでもいい。食と性を満たすための店。それが、俺の実家とも言える場所だった。
裏手に回って、勝手口のドアを開くと、ちょうど一人の女性と目が合った。彼女の手から、空の小型コンテナが落ちるのを、力の尾が掴んで、床に軟着陸させる。
「ダズン」とその女性は俺を呼んだ。恰幅のいい立ち姿。白髪交じりの、ざっくばらんなショートカット。目尻に小皺を作り、笑んだ。母だ。
「……父は?」
「上よ」
彼女は頷いて、俺に近づいてきた。
「前より健康そうに見える」そう言って、両側から腕をパンパンと叩く。
「……だとしたら、シャルのお陰だ」
「ふうん」と母は薄く笑んだ。「それは、師である私のお陰とも言えるね」
そうかもしれないなと、俺は苦笑した。彼女が、シャルの料理の師だった。それと同時に、シャルをヒトとして教育したのも母だった。ヒト殺しであり、殉葬者であり、地球人ではなかったシャルを、今の彼女にしたのは母の功績だと言える。
俺は、シャルを母に押し付けて、一人でエレベーターに乗った。
8.
父の私室は、ビルの上階にある。月面都市の街並みを眺望するのにうってつけの場所だが、肝心の景色がよいというわけでもない。それだけが残念だった。ドームが気密性を失ってしまった時に備えて、ワイズマンズ・シーサイドスクエアの建物には隔壁を閉じる機能が備わっている。裏月酒店のそれは開いているが、ここから見える建物のほとんどは完全に閉じていた。開いているとしても、中に火は灯っていない。この数年で多くの仲間を失ったと、父は言っていた。最後にこの景色を見た時のことだ。その時も、こうして向かい合って、俺はシャルをここに残して、去ろうとしていた。
俺が部屋に入ると、父は応接用のソファに座って、俺を迎えた。
「来ると思っていた」
父の声は、深い溜息混じりだった。まだ背筋はしゃんと伸びており、耄碌しているという雰囲気ではない。そのことに俺は、少しばかりの安堵を感じている。
テーブルを挟んで向かいのソファに座り、父と相対する。
「訊きたいことも分かっているつもりだ。メッセージのことだろう」
全くその通りだ、と頷く。
「私が送った」
「俺たちを狙う誰か、とは?」
俺が聞くと、父は眉を顰めて逡巡するように顔を俯かせた。それから、一度は床まで落とした視線を、じっくりと俺の顔に戻す。
「あの娘の言っていたことは、嘘偽りではない」
「最初から、そこを疑ってなどいない」俺はそう断って左膝に肘をつく。「何を濁す必要がある?」
「分かるだろう。うちを継がず、家の力も借りずに、独力で生きる道を選んだお前になら。お前は、結局、聡明で正しい」
「……」
「確かに、この月の裏に未来はない」
かつて俺がこの家を飛び出した時には、ついぞ認めなかった言葉だった。
俺がセクストンとして生きることになった切欠となる口論、その結論だ。家業を継げと言う父と、このワイズマンズ・シーサイドスクエアに未来はないと言う俺。あの頃は一致しなかった意見が、ついに合意に至ったらしい。
十余年という月日は、父の考えが変わるのに十分な歳月だというのだろうか。
それとも、父が納得するまでに十年以上もかかったというべきか。
「だが、今は、あのままお前と縁を切っておけばよかったのにと思う。そのくらい、あの娘は危険だ」父は吐き捨てるように言った。
シャルと一緒にいることを選ぶのなら、裏月酒店に迷惑をかけないよう、縁を切れと言っているようにも聞こえた。
「危険? あの尾が?」
「馬鹿なことを言うな。あの娘には、理性がある」
その言葉に俺は頷いた。否定の余地もなかった。危険な力を持つだけで制御の利かない少女であるなら、俺はすでに死んでいてもおかしくはないだろう。
「だが、やはり、関わるべきではなかった」
「母は、そうは思ってないみたいだが」
「あいつもあいつだ」父は自身の胸元を指先で小突いた。「情が深すぎる」
ワイズマンズ・シーサイドスクエアは、その維持を連邦から第三セクターの管理下に移譲されて久しい。現在その維持を担っているのは、まさにここに住む市民たちだ。この天蓋型宇宙都市の莫大な維持費を賄うため、市民は掟を作り、団結する必要があったはずだ。外貨を稼ぎ、都市に富を齎す。その一点で、都市はまとまっていた。幼い頃、父もその情とやらを大事にしていた。それは今や、呪いと化して、目の前の壮年の男を苛んでいるのだろうか。
「誰がお前たちを狙っているか、答えは明白だろう」
「……」
「お前が、今、考えていることを言ってみろ。ダズン」
「それは」と逡巡する。それに何の意味がある?
推論がお互いに一致していようと、それが事実であろうと、なかろうと、もう話は決裂しているように思えた。
しかし、その推論を披露する前に、扉は開いていた。
お盆にドリンクを載せ、女性が入って来た。彼女は、その女体のほとんどを見せつけるような、シースルーの挑発的なドレス姿だった。裏月酒店の女だろう。
「レイシィ」父が咎めるような声音で、その名前を呼んだ。レイシィと呼ばれた女性は肩を竦める。「奥様に頼まれたんです」
彼女はドリンクを二つ、ゆったりとした動きで差し出す。
一つは父の前に、一つは俺の前に。
それから、俺に妖艶な笑みを向けて、囁く。
「お姫様をお連れしましたよ」
彼女は再び扉が開いた。
そこにはシャルが立っていた。薄藍のドレスを着こなしている。いわゆる、チャイナ・ドレスだ。薄い布地の下に、美しい曲線が浮かび上がっており、スリットから覗く脚は、白いタイツに覆われている。彼女の特徴的な下半身の彩りさえ、それを薄っすらと透けさせたタイツによって、艶めかしく活かされていた。
幸い、シャルが俺に感想を求めるような言葉を告げることはなく、ただ彼女の視線がゆらゆらと俺の右耳と左耳の辺りを掠めるだけだった。
二人はそのまま俺の両隣を挟むように座った。
今、俺たちは重要な話をしている。とは、言えなかった。邪魔をするな、とも。レイシィは兎も角としても、拳四つほど離れて控えめに座るシャルに対して無関係だから離席するよう告げるには無理があった。他ならぬ彼女の話だからだ。
母は、俺と父の話し合いが険悪なものになることを予見して、二人を送り込んだのだろうか。そうだとしたら、その効果は覿面だと言える。
父が立ち上がった。
「話は終わりだな」
「待ってくれ」
腰を浮かせて、後を追おうとする。父が扉に手をかける前に。
何かを告げようとして、その前に変化が起きた。
そこで再び、扉が開いたのだ。
男が、父を押し退けて部屋に入って来た。
その大男ぶりと言ったら、そう低くもない扉を、上半身を傾げて通るほどだ。縦に大きいだけでなく、横幅もあり、筋骨隆々という言葉で評するのに相応しい。彼が入って来ただけで、部屋は狭くなり、その厳めしい顔を見るだけで、息が詰まるような錯覚を覚えた。
それからもう一人、その後について、女性が入って来る。先に入った男の後では小柄にも見えるが、その実、しっかりと身体を鍛えているようだった。ヒールを履いているが、その足運びには安定感があり、タイトスカートの稼働範囲をいっぱいに使った大きな歩幅で、ほとんど部屋の中ほどまで進入する。
二人は汎用スペーススーツの上から、黒いスーツを着ていた。
そして、腕には連邦捜査局の腕章を着けていた。
「貴様らは……」
父の誰何に、その女性は小首を傾げた。結い上げた金髪が、肩を撫でて滑った。
「私は連邦捜査官、エスリ・シアンサス。彼は、部下のア・スモゥ」
連邦捜査官。
そうだ。
「連邦宇宙開拓秩序に基づいて、シャル・ラストテイルの身柄を拘束する」
彼女たちこそが、シャル・ラストテイルを追っていた。
それは、全く意外ではない。
言うまでもなく、時間と空間は、世界の最重要ファクターである。時空歪曲は、宇宙開発においてブレイクスルーを引き起こす技術であり、超長距離通信や、跳躍潜航が生まれる端緒であった。そして、それにまつわる全ての研究は、連邦が主管している。全ては宇宙開拓秩序の為だ。
そして、宇宙開拓の先に、地球人と異星種の交流という大きなマイルストーンが想定されていたことは想像に難くない。地球上での開拓史ですら、開拓者と原住民の出会いというものは、あったのだから。
同時に、地球人と異星種が交わることが可能なのかという命題も存在している。
血統加速という技術には、それを測る意図があったのだろう。少なくとも、研究が始まって、間もない頃は。それがいつから能力開発の側面を持つようになったのか、あるいは、最初からそれを期待した交配実験だったのか……その委細にそれほどの興味はないが……いずれにせよ、その成果物であるシャルを追うのは、連邦だったのだ。
「よろしいですね?」
エスリ・シアンサスが、無造作にハンド・レーザーウェポンを抜いた。
9.
「お二人とも、逃げてください!」
鋭い、レイシィの声。彼女の手には、どこからか取り出したハンド・レーザーウェポンが握られていた。
「あああ、馬鹿者が」頭をガシガシと掻き乱し、父も懐から銃を抜いていた。
無論、俺も。
逃げる? それはいかにも考えられない選択肢だった。
「ナノマシン統制プロトコル、戦術モード!」
俺と父の声が響く。汎用スペーススーツを着ていないシャルとレイシィを、背に隠した。ナノマシンがアドレナリンを合成して、身体を戦闘モードへと切り替えていく。そのまま銃を構えながら、肩で首元のコンソールを圧迫した。
防護外骨格が、全身をアーマーのように包んでいく。その装甲展開の隙間を縫うかのような眼光の鋭さで、エスリ・シアンサスはトリガーを引いていた。
そして、それに応じる形で、室内に多数のレーザーバレットが飛び交う。
エスリは、ア・スモゥの巨躯を盾にしていた。
光弾を生身で受けたように見えた大男だが、恐るべきことに、些かも痛みを感じたようになかったし、その活動に支障が生じたようにも見えなかった。
「かぁああああああああ!」
それどころか、エスリを守るために広げた腕をそのまま振り回し、こちらに飛びかかって来た。大男の体重の乗った振り下ろしを受けても、外骨格を破壊せしめることはないだろう。だが、そのまま拘束される愚は犯したくない。
逃げるしかない。だが、後ろにはシャルもいる。
迷いで、身体が硬直する。それは命取りになるような隙だった。
「……ダズン!」
少女の声。
ア・スモゥの巨躯が、何かにぶつかった。まるで室内でトラック同士が正面衝突を起こしたように、爆ぜるような空気の振動が巻き起こった。
力の尾だ。
不可視の尾の如き力場が、巨漢を受け止めた。
彼女の力場は、疾く奔り、破壊される心配もない。それは彼女の心のままに動く、自由自在の第三のカイナだった。
自分が把握する限り、その上限を感じさせないほど力強いものだ。
「う、ん!?」
だが、シャルは疑問と、そして苦しそうな声を漏らした。
「ん・ん・ん!!!」
拮抗し、しかしそれでも、尾を振りぬく。
ア・スモゥは弾き飛ばされて、壁に背中から激突した。
この一瞬、形勢は逆転した。
エスリはそれを理解していた。タタタンと素早く部屋を走り、父とレイシィに狙われながら、レーザーバレットをやり過ごす。これで、位置関係が逆転した。今、俺たちの方が出入口に近くなっている。尤も、それは相手も承知している。
「ア・スモゥ、起きなさい!」
エスリの声で、大男が起き上がった。まるで効いていないとでも言うのか。
そう思うが、彼は頭から流血していた。血が滴り、床を汚す。それでも、その歩みは止まらなかった。傷つかないわけではない。だが、歩みを止めるには至っていない。
「……もう一度……」シャルが言った。
俺は彼女の肩を掴んだ。
「ダズン、邪魔しないで!」いつになく悲痛な声に聞こえた。
いや、と俺は逡巡していた。レーザーウェポンが効かない相手に対して、結局、戦力として期待できるのは彼女の超常の力だ。だが、彼女に「ア・スモゥをぶちのめしてくれ」と願うのが本当に正しいことなのだろうか。
「このデカブツめが!」
父がレーザーウェポンを乱射した。
その言葉に反し、エスリの方に向かって、だ。それは有効な目論見だった。大男はエスリを守るために歩みを止めざるを得なかった。
「お二人とも、逃げて!」
レイシィが叫んだ。彼女の妖艶なドレスは何かに引っ掛けてボロ布のようになっており、父もすっかり埃で汚れている。ソファは破れ、テーブルは盾の如く立てられたままだ。ひび割れた床のタイル。へこんだ壁。部屋は、何もかもが滅茶苦茶だった。
それらは全て、連邦捜査官の来訪により引き起こされた。
「いや……」
俺がシャルを保護しようと考えたことが、この状況を招いたのだ。
そうであるのだとしたら。ヒトならざる存在であるシャルの扱いに困り、この都市に連れて帰ったことが間違いだったのだろうか。
あるいは、棺の中で深く眠っていたシャル・ラストテイルを、そのまま殺していればよかったというのだろうか。
俺はシャルの腕を取って、走り出していた���
表は、さすがに見張られているだろう。裏口から出た。ワイズマンズ・シーサイドスクエアの暗い路地裏が、今は有難い。
「とはいえ、どうする」
「逃げましょう」シャルが言った。「宇宙に」
「……まあ、そうなるか」
だが、ここから港までは遠い。
シャルが不意に俺の手を振り払った。
「どうした」
「では、急ぎましょうか」
「あ、ああ? そうだな」
何だ、このやり取りは、と首を傾げた瞬間、俺はシャルに足払いされていた。
視界がほぼ半回転する。
「は?」
そして気付くと、俺は、横抱きに抱え上げられていた。シャルに。
力の尾を使っているのだろう。不思議と、落とされそうだという不安感は無い。
「舌を噛まないでくださいね」
「何をするつもりだ、お前は」
少女の金の瞳が、俺を見下ろしていた。その後ろに、星海を背景に黒いビルが浮かび上がっている。その壁面からガシャンと音がして、何かが弾けた。
「……来たぞ、シャル!」
その言葉で、すっと滑るように横に避ける。
先ほどまで俺たちがいた場所に、黒い塊が落ちて来た。タイルが砕ける。
ア・スモゥだ。そしてその肩には、エスリが座っていた。
俺たちは、そのまま見合っていた。
「……滑稽ですね」ぼそりと、エスリは呟いた。明らかに俺を見ていた。
「何だと、お前」
「貴方も、我々と同じですよ」
彼女の目には、犯罪者を捕まえよう、みたいな色は無かった。
哀れだとか、そういう心情がありありと浮かんでいるようだった。
その手にあるハンド・レーザーウェポンが、ゆっくりとこちらを向いた。
「跳びます!」
シャルが叫んだ。その瞬間、俺は、俺たちはワイズマンズ・シーサイドスクエアの空に投げ出されていた。飛んでいると言ってもいい。いや、跳躍と言うべきか。
ともかく、大気がうるさいくらいに耳元で荒んでいた。
「……追っては、来ないみたいですね」
「真似できるものなのか」
俺たちは、ゴースト・タウンを俯瞰する身にあった。
これを生身の人間に?
「分からないですけど」と彼女が呟いた。「彼も、血統加速者かもしれません。彼の拳は明らかに重かったですし」
確かに、そのような節はあった。謎の頑強さは、レーザーバレットを受け止めることから、裏月酒店の最上階からの着地まで、ハッキリと示されていた。それを血統加速者の何らかの特質によるものだと仮定した場合、俺たちを追って跳躍できる可能性は何パーセントあったのだろう。
「……」
「全く的外れなのかもしれませんけど」
俺は流れていく景色を見ながら、そうなんだろう、と思った。彼女が思うなら。
次に、そうだとして、と考えた。血統加速者の連邦捜査官がいる。
それは、血統加速者の力を連邦が利用しているということだ。
そんな話は聞いたことがない。
脳裏の誰かが警告する。一介のセクストンに過ぎない俺が、連邦の何を知っているのだと。俺は描きかけた邪推を掻き消して、あとはされるがままになった。
一度の跳躍で港までは辿り着けないので、俺たちはもう既に何度か弾んでいた。
全く苦に感じないのは、シャルが慎重に力場を操っているからだろう。
途端に手持ち無沙汰となり、その顔を眺めてみた。
以前に聞いたことがあるが、力の尾という念動は、野放図的にパワーを引き出すことよりも、精密に制御する方が大変なのだと言っていた。星海の下の彼女の顔は、眉を顰めて凛々しく歪んでいる。
彼女はもう、棺で目覚めた頃のままではないのかもしれない。
「……あの、そう見られると、集中力が乱れます」
「すまん」
10.
都市の出入口たる宇宙港は、ワイズマンズ・シーサイドスクエアの中で最も活発な施設だった。ゴースト・タウンじみた都市の様子とは裏腹に、多数の宇宙船が普段からそこを利用している形跡がある。それは、この天蓋型宇宙都市の維持資金を稼ぐための選択肢に出稼ぎというものがあるからだろう。あるいは、資材の搬入である。
シャルを連れて、運送業者側の通用口から港に入る。シーラカンスは輸送船の一種と言えるので、正当な入り方と言えるだろう。まあ、俺が運ぶのは棺だが。
いずれにせよ宇宙港の宇宙港の構造と、俺たちの進路は単純だ。このままターミナルビルを抜けて発着場に進入し、そこにあるシーラカンスに乗り込む必要がある。
だが、シーラカンスの前には、連邦捜査官たちが詰めていた。
それはそうだ。
「……見張ってますね」
「そうだな」
「艦まで着いたとして……かもしれませんけど」
彼女がそう言った理由は、よく分かった。物陰に隠れながらでも、はっきりとその理由は見えた。連邦の艦が、その巨体で離着陸用ゲートをブロックしている。これでは、宙に逃げることはできないだろう。
俺はハンド・レーザーウェポンを抜いて、残弾を見た。
「……それでも行きますか?」
「それでも、だ」
連邦捜査官は三人いた。ア・スモゥのように無茶をしてくることはなさそうだ。油断ならない雰囲気もない。有り体に言えば弛緩しており、エスリ・シアンサスのような真剣さがなかった。少なくとも彼女の部下には見えない。一人を撃って無効化する。もう一人は、力の尾が吹き飛ばしていた。
異変に気付いた三人目が武器を構える。ライフル型だ。
銃口がこちらに向く。シャルの方じゃなくて幸いというべきか。
力の尾でレーザーバレットが防げるかというと、そうもいかない。
力の尾は力場であって、物質的な特性はない。実弾ならば防げるが、レーザーバレットは防げないのだ。できるとしたら、マイクロブラックホールレベルの力場を生成し、空間ごと光弾の軌道を歪曲する方法だけだ。
だが、血統加速者であっても、できる事とできないことがある。つまるところ、彼女の出力では、レーザーウェポンを防ぐことはできない。
身を盾にする。不運にも、光弾は装甲の間を抜けて、左肘を僅かに焼く。
だが、二発目は来なかった。
シャルが打ち倒したからだ。
「大丈夫ですか?」
「…………俺のセリフだが」
「私は後ろにいただけですから」
「違う。力を使いすぎじゃないのかってことだ」
彼女は言われてから、ニコリと笑んだ。
「それこそ大丈夫です。普段から余分に飲んでいますし」
「お前……、……まあいい」
とりあえず、平気ならいい。だが、溜息はついた。
「とはいえ、さすがに宇宙船サイズのものは」
「だろうな」俺は頷いた。「コバンザメを使おう」
今もシーラカンスの船底にくっついているソレに、シャルはなるほどと頷いた。
コバンザメの逆正三角錐の頭には、船底のポートに接続するためのジョイントと乗降用のハッチが備わっている。これにより、艦の外部に連結した状態で運搬・必要に応じて稼働できる仕組みだ。船内に格納スペースを設けなくても配備可能な汎用船外作業用重機だとして、小型輸送艦の類では定番なのである。
コバンザメのサイズは全高五メートルほど。シーラカンス自体のサイズとは比べるべくもない。ブロックを抜けることができるだろう。
シーラカンスに乗り込み、コバンザメの搭乗ポートに向かう。
その途中で、防護外骨格を格納した。
「ヘルメット、どうします?」
「要らん」コバンザメの気密性は十分安全とは言えないが、二人で乗り込もうという時には、邪魔にしかならないだろうからだ。
「言っておくが、狭いからな」
「まあ……そう……ですよね」
床のハッチを開く。
コバンザメは船底にくっつくようになっているので、梯子を降りる格好だ。
今はワイズマンズ・シーサイドスクエアの重力下だから関係はないが、艦の装甲内には、艦載重力機関による疑似重力域の境界がある。宇宙空間では、そこを行き来する際に重力を感じることができた。例えて言えば、プールで水面に出たり入ったりするような感覚だ。だから梯子を降りる……つまりコバンザメに乗る……のは楽だが、梯子を上がる……つまりコバンザメを降りる……のは、しんどくなる。
「……よし、いいぞ」
まず俺が座り、そこへシャルが降りて来る。脚の間に座らせる形で考えていたが、すぐにその計画は修正することになった。膝の上に座ってもらうしかない。二人乗りが想定されていない、狭いコクピットの中だ。スペースはギリギリだった。
「どこかに掴まってくれ」
「どこかって、どこにですか?」
「とりあえず、変なところを押したり引いたりはしないでくれ」
「それは、難しい注文ですね」シャルはそう言いながら、狭い機内で器用に身体を反転させた。そうしてそのまま、ぎゅっと俺に抱きついてきた。柔らかい肢体が、先ほどまでよりも克明に感じられる。
「……、……何をしているんだ……お前は」
「論理的に考えて、これが一番安全ではないですか?」
そう、かもしれない。
コバンザメの内部には様々なコンソールが並んでいて、どこを触れても何かを操作してしまいそうだった。論理的に考えて、触れる場所の選択肢はそう多くない。
「……このまま出発するからな?」
どうぞ、と彼女は言った。
「システム起動」
コンソールを小突く。
機体コンディションチェック、エネルギー残量チェック、ハッチ閉鎖、気密確認、分離準備。一つ一つ確認していると、不思議と落ち着いてきた。
いつもと何ら変わらない。
腕の中のシャルも、口を挟まず、邪魔をすることもなかった。
狭いコクピットの前面は、メインモニタになっている。
船底は床面より下に位置するから、ここからは港の下部構造が見えた。
「メインモニタよし」
それから、両手をコントロール・スロットルに置いてみた。
操縦には問題なさそうだ。
問題は、三次元レーダーモニタが使えないことだ。さすがにシャルを抱える形になっている現状では、アームを動かして見える位置に固定しておくというのも難しい。目視で何とかするしかないだろう。
「分離するぞ」
呟きながら、指差し、ワンテンポ置いてからトグルスイッチを上げる。
ガクンと、重力に引かれてコバンザメが落ち始めた。耳元で、シャルが息を吸う音が聞こえた。
スラスタを噴かす。
重力と推力が均衡する。
「さっさと出よう」
目論見通り、コバンザメの小さい機体ならば、連邦艦の進路妨害は何の障害にもならなかった。だが、何かしようとしていることはバレたらしい。
メインモニタの左隅で、同系の汎用船外作業用重機のシルエットが動き出した。
連邦捜査局のそれだから、対重機用戦闘機と言うべきかもしれない。その腕には大口径のレーザー・キャノンが装着されている。
もっと言えば、その腕の大口径のレーザー・カノンはこちらに向いており、その銃口は既に瞬いていた。
「う、おお!?」
メインモニタが青く輝く。即座に輝度補正が掛かるが、何も見えない。それから、強烈な横Gが掛かっている。���うやら、左に大きく移動しているらしい。被弾したわけではない。その証拠に、俺はまだ生きているし、シャルの熱も感じている。
一瞬して、揺さぶられるような衝撃が全身を貫いた。衝撃アラート。機体コンディションの左半分が赤い。何が起こった?
考える前に、脳裏に閃きが起こった。左舷スラスタだ。
どうも調子が悪いと思っていたところだった。このタイミングで、ダメになったらしい。それで、バランスが崩れて左に滑ったのだ。いや、ダメになったお陰で、銃撃には当たらなかったと捉えるべきかもしれない。悪運だ。
だが、左舷スラスタが使えない状態で、キャノンを装備した戦闘機から逃げおおせることができるかと聞かれると、それは疑問だった。
「……大丈夫ですか?」
「どうも、駄目そうだ」
メインモニタが復活した。目の前に、戦闘機が近づいていた。
「貴方には、私がいるではないですか」
お前は、勝利の女神か何かなのか?
俺が問うと、彼女は笑った。
「私は、シーラカンスのクルーです」
力の尾が、取りつこうと近づいてきた戦闘機を薙ぎ払う。
そいつは、反射的にスラスタの出力を上げるが、それはわずかな抵抗だった。
彼女の力場には、物理的な隔たりも意味をなさない。それは彼女の尾骶骨の延長上から伸び、自由自在に動く第三のカイナだった。出し入れ自在かつ、最長で十メートルに及ぶ、純粋なる力の尾である。
それが、シャル・ラストテイルの異能だった。大型の宇宙船をどうこうはできなくとも、コバンザメと同程度のサイズならば、排除できうる。
「クルーとして迎えて、良かったでしょう」
「そう……らしいな」
俺は苦笑して、コントロール・スロットルを握り直した。
「このまま港を出よう。手伝ってくれるか」
「ええ、もちろん」
11.
港を脱出した勢いで、月面を行く当てもなく、進む。
だが、それに限界があることは明らかだった。汎用船外作業用重機であるコバンザメには、宇宙空間を長距離航行できる能力はない。空気も燃料も数日は持つが、それだけだ。
「これから……どうするかな」
「もし行けるなら、月の表に行ってみたいです」
彼女は言った。
幸い、追手はない。今の時点では、と悲観的な補足をしておくべきだろうか。
「分かった」
左舷スラスタは沈��したままだ。
だが、急がないなら、それを補って進むことはできる。
シャルの尾を借りる必要もない。
「行くか」
「はい」
逃亡の終わりは、すぐそこに迫っているはずだった。
その終着が、地球を臨む丘なら、それもいいのかもしれない。
月の裏で生まれた俺には、地球への帰属意識なんて無いし、シャルにだって、そんなものはないのだろうけど。それでも。
やがて、白い大地と黒い星海だけの世界に、青い星が現れた。
「……」
随分と久しぶりに、しっかりと地球を見た気がした。
「なんで、こちら側に都市を作らなかったんでしょう」
もし、そうしていたら、いつでもこの美しい星を眺めることができる都市になったのに、と彼女は言った。
そうかもしれない。もし月の都が、地球側にあったら。
ワイズマンズ・シーサイドスクエアの空には、青い星が浮かんでいただろう。
「地球人の月への興味は、美的なものに留まっていたんだろう」
「美的、ですか」
「夜空に浮かぶ月が綺麗なままであることは、地球人にとって一番重要だったんだ」
「地球人っていうのは、ロマンチシストなんですか?」
「俺は、現実的だったんだろうと思っている。綺麗な景色に意味を見出すというのは、一見、ロマンに見えるかもしれない。だが、綺麗な海を守ろう、綺麗な川を守ろう、綺麗な町にしましょう……宇宙開拓前時代の地球では、そういったスローガンの下、環境問題に取り組んでいたという。これは、ロマンだと思うか?」
「……いえ」
「対象への美意識を意識させるというのは、最も基本的な環境保護施策だ」
だから、ワイズマンズ・シーサイドスクエアは月の裏にある。
月の表では大規模開発をしない。それが、宇宙開拓時代に入るに先立って連邦が決めたルールだった。地球の総意だったのだ。
実際には、月は巨大だ。仮にワイズマンズ・シーサイドスクエアが表にあったとしても、地球から見れば、ひとかけらの黒い点にも見えないことだろう。しかし、一を許せば、それはいずれ千になり、億にもなるかもしれない。地球人には、地球でそれを証明してきた歴史があった。空き缶一つで直ちには環境が破壊されないからこそ、そこを意識することには意味がある。
「……詳しいですね」
シャルが俺を見ていた。その表情には見覚えがある。別に、地球生まれというわけでもないくせに、という顔だ。
「生まれがどうとかではない」
「じゃあ、なんです?」
「父の影響だ」
父のする、地球の話が好きだった。
もっと言えば、海の話だ。地球の生命は海から生まれ、やがて生命は陸上を支配し、宙を目指し、ついには月に根差した。そんな、壮大な生命と人類の物語を聞くのが好きだった。
「そういう、気の利いたお話しをするタイプの方だったんですね」とシャルは言った。
「はは」
彼女にとって、父は気難しい人間に見えたかもしれない。そもそも父は、あまり彼女と顔を合わせないようにしていたみたいだった。
シャルを可愛がっていたのは、母の方だった。
まるで娘が出来たみたいだと喜んでいたのを覚えている。そうして短い期間で、人形のようだったシャルを随分と表情豊かなヒトにしてみせたのだから感心する。そして、そんな母の様子を見ながら、父は深すぎる情を案じていたのだろうか。
父が、彼女は危険な存在だと言い、縁を切れと言ったことを思い出した。そうしないのなら、俺との縁を切るとすら言ってみせた。
それでも、仲が悪かったというわけではない。良かったはずだ。
「……ただ、意見が合わないだけだ」俺は言った。「昔からそうだ。俺がセクストンになる前、ワイズマンズ・シーサイドスクエアの将来について二人で話していた時もそうだった。でも議論での対立は、決して仲の良し悪しとは関係ないだろう?」
「……それは、希望ですか?」
「そうかもしれない」
だが的外れとも思わなかった。土壇場で銃を抜いたからだ。
父は、俺を連邦に突き出すことも、静観することもしなかった。そうすることもできたはずだ。事実、そうすると思っていた。
でも、抵抗を選んだのだ。
議論の上では、俺たちは対立していた。父はシャルのことを危険視していた。俺と同じように、違法な情報収集手段を活用したかもしれない。父からすれば、自分や母を守るのに支障がない限りで、俺を守り、俺を守るのに支障がない範疇ならば、他人に手を貸してもいいとするのは当然の順位付けだ。
意固地になっているのは俺の方なのだろうか、と、ふと思った。
じゃあ、シャルを見捨てれば良かったのか?
それも甚だ馬鹿らしい話だ。
最初から確固とした理由があって彼女を助けたわけではない。敢えて言うなら、放り出すことを選ぶのには不快感があったからだ。そこには意外と同情も憐憫もなく、俺の考えの芯には、いつも俺自身がどう思うかが根差している。
それは、そんなにダメなことなのだろうか。大したワケもなく人助けしてはならないという理由で、見捨てることを選ぶべきだと言うのなら。
これからがあれば、の話だが……俺は、これからも偽善だと言われるような行為をするだろう。コバンザメの狭い筒状のコクピットの中で、そう思った。
「暑くないか?」俺は言った。
「そ……うですね。空調、強くできないんですか?」
「やろうと思えばできるが、それだけバッテリーを食う」
端的に返すと、沈黙があってから、彼女は小さく言った。
「それは、よくないですね」
シャルも、終わりを理解しているのだろう。それが近づいていることも、それを早めることをしても、しんどいだけだとも。
空気も燃料も有限だし、コバンザメは故障しており、ワイズマンズ・シーサイドスクエアに残していった父や母や、裏月酒店の皆だって連邦に拘束されただろうし、俺たちが月の表に来ていることも、もう明らかになっているだろう。
だから、俺たちの時間は、あと僅かしかないだろうと思う。
「次は、どうする?」と俺は聞いていた。
「次……ですか?」
「やりたいことはないのか?」
しばし、沈黙に包まれた。それから、遠慮がちに声がした。
「最後に……貴方の、ダズンの血が飲みたいです」
「そんなことか」
思えば、彼女はここまで何度も力の尾を行使していた。
スーツの首元を開けてやる。
シャルも、いつも通り、するりとスーツを脱ぐ。狭い機内の中、メインモニタいっぱいに広がる青い星を背景にして、彼女は白い肌を晒していた。
窮屈そうに腰の辺りまでスーツを下ろして、綺麗な裸体を晒す。
「ダズン」
唇が近づいてくる。首元にしっとりとした感触が触れた。
そのまま抱き合うようにして、俺たちは密着していた。隔てるものはなく、肢体の柔らかさがダイレクトに伝わってくる。
じくりとした痛みが首に広がった。牙が首元を小さく穿つ感触だ。
それから、こくんと、嚥下する音がコクピットに響いた気がした。
「いっそ、全部飲んだっていいんだ」
彼女が弾かれたように顔を離した。
唇の端からつうと血が垂れて、酷く苦しそうな顔で、俺を睨んでいた。
「そんなこと、私は望んでいません」
「……そうだな」
「本当に分かってますか?」彼女が詰め寄ってきた。「私が何を望んでいるか」
「多分、分かっていないんだろう」
俺が白状すると、彼女はそれほど気を悪くした様子もなく、しかし、あっさりと頷いた。気を悪くした様子もないというのは、希望的観測かもしれないが。
「私が、なんで、こうして脱ぐのかも?」
「分かっていない」
分かっていないのだ。
以前からずっと、俺はただシャルの裸身を眺めていたわけではない。
予想してきた。そして、自分で、その予想が嘘くさいとも気づいていた。
普段から一緒にいたら半人半異星種であることを忘れられそうだから、肌を見せているのだなんて、酷い、こじつけだ。
それと伝える為だけなら、もっと相応しい手段があり、脱ぐ必要はない。
そもそも俺は、常から彼女がそうだと感じているのだ。外見や、力の尾は、その認識に直接的に関係ない。そもそも食べるものが違う。それに付随する、生活様式が異なる。彼女の振る舞いは、やはり純粋な地球人とは異なる。
然るに、その問題をクリアできずして、彼女は人の輪の中に混ざることができない。
俺は常にそう思っていて──彼女も理解しているだろう。だから、わざわざ肌を見せる必要などなく、お互いが違うことは、お互いが一番分かっている。
「私は別に、ヒトの輪の中で隣人として生きたいなんて、思ってないんです」彼女は自分に言い聞かせるようだった。それから、俺に伝えるよう、声を大きくした。「ただ、貴方と一緒が良いん��す」
彼女はそう言った。
言われながら、俺は今、彼女にとても人間を感じている。
そのことに気付いた。
「……そうか」と、動揺から声が揺れないように努める。
「俺のことが好きだって言いたいのか?」
「そう……なのかもしれませんね」
そのような煮えきらない返事にさえ、生々しさがあり、つまり、血統加速者だとか、半分は宇宙人なのだとか、問題はそういうことではないのだった。
そういう思想に傾倒して、彼女の感情から逃げていたのは俺自身だ。
目の前にいる女性が、ずっと俺の情欲を引き出そうとしていたのだと気付いた。
今になって。
「ダズンは、どう思ってますか? 私のこと」
どうだろう。
俺は、ついに戸惑いを隠そうとも思えず、逡巡していた。
口を半端に開いて言葉を見失った俺を、シャルは真っ直ぐに見つめてくる。彼女は意外にも微笑を浮かべており、その身は青い地球を背負っていた。
指先に、何かが触れる。彼女の手だ。指先が絡み合い、その美しすぎる貌は間近に迫って来た。
「……どう、なんですか?」
彼女の掠れるような声が脳に染み、痺れるような錯覚を覚えた。
そうだな。
結局のところ、俺は彼女に情を持っていると思う。だが、それが友情なのか、愛情なのか、あるいは色情なのかというところを断ずるには、至れなかった。
単純な話ではなく、それは、渦巻いている。
混ざり合った青なのだ。
だが、あえて遠くからそれを眺めるとするならば。
絡み合った指先に力を入れると、彼女はそっと瞼を閉じていた。
テラヒューマニティ・星海殉葬(了)
2024.1.16 - 3.31 first draft(35k)
2024.4.8 update
0 notes
Text
第6話「悪(はじまり)夢」

アンナ・グドリャナは夢をみる。
彼女の憎悪の根源、彼女の立ち上がるための燃料であるそれ。多くの人々と出会い、別れ、そしていなくなった人々のために前をむき続け、後ろを振り向かない全ての元凶をみる。
「――ッ」
アンナは声を出そうとして、出せなかった。上に瓦礫が乗った足が燃えるように熱い。煙が視界を曇らせる。
炎が周囲を進行していく。瓦礫と化した列車の金属部分は燃えず、けれどぼろぼろになった座席には火が付いている。
焦げ臭さと同時に鼻へ届く、肉が燃えていく匂い。先程まで助けを求めていた少女の声が聞こえなくなった。身近なところはなくなったが、悲鳴は遠くで響き続ける。
奇怪な形――獅子の体に羽が生えながらも頭部は人間のそれだったり、あるいは極めて太い足で二足歩行しながらも痩せこけた腕がついた巨人だったり――をしたペティノスたちが、爆発音とともに先程まで列車に乗っていた少年少女を殺していく。
逃げ惑う彼ら、彼女ら。倒れていく彼ら、彼女ら。悲鳴と懇願と恨言の合唱。それを動けないアンナは見続けていた。
「おい、大丈夫か⁉︎」
未だ成長途中だと思わせる少年が、金色に輝く猫目をアンナに向ける。頬は煤けていて、爪は割れて血が滲んでいた。アンナと同じような制服に身を包み、同じピンバッジを胸元に留めていた彼は、必死に彼女へ声を掛ける。
「クソッ、足が動かせないのか。……でも、これさえ退ければ動けるよな?」
必死にアンナの足の上にのし掛かる瓦礫をどかそうとする少年。彼は意識を保て、こっちを見ろ、死ぬんじゃない、と何度も言葉をかけ続ける。
ただ待つことしかできない彼女は、足元に広がる灼熱が痛みとなり、そのおかげで何とか意識を保てていた。
「もう少しで」
息切れしつつも、少年が最後の力を込めて瓦礫をどける。アンナの足からは、痛みが続くが重みはなくなった。
「肩を貸す、逃げるぞ」
彼は震える腕を隠すこともできず、それでもアンナの腕をつかみ抱き起こす。その時、炎で鈍く輝く異形が彼らの前に舞い降りた。
それは翼を持つものだった。
それは翼に無数の目があった。
それは少なくともアンナが知っているどのような動物にも似ても似つかぬ、ただの羽の塊であった。その塊の中央に、なんの感情も浮かべていない美しい人間の顔がある。銀色に輝く顔だけがあった。
翼にある複数の目がギョロギョロと蠢き、そのうちの幾つかが少年とアンナに固定される。ヒッとアンナは息を飲んだ。ギリッと少年は歯を食い締めた。
少なくとも少年だけは逃げられる状態であったが、それを彼は選ばずにアンナを強く抱きしめる。そして、彼は「ふざけるな」と小さな声で囁き、ペティノスを睨みつけた。
彼の怒気にもアンナの恐怖にも何も感じないかのようにペティノスは翼を広げ二人へと近づこうとした。その時、上空を黄昏色に染まる機体が飛んだ。
ペティノスは二人から視線を外し、機体――後にそれがイカロスと呼ばれるものだったと彼女らは知る――へと飛びかかる。それまで淡々と人々を殺害し続けた奇妙な造形をしたペティノスたちが、親の仇と言わんばかりに殺意を迸らせ、機体を追い続ける。
十いや百にも達するほどの数のペティノスが、黄昏色のイカロスへ攻撃を仕掛けるが、空を飛ぶ機体はそれらを避けて、避けて、そうして多くの敵を薙ぎ払う。
「助かった……のか?」
呆然としながら、少年とアンナは空を見上げた。
黄昏色に染まった機体が、実は地上で燃え盛る炎の色に染まったのだと知ったのは、それよりも少し後の話だ。
それでもアンナや少年にとって、現見空音とユエン・リエンツォの操縦する銀色のイカロスは、後に幻想の中で出会う最強の存在――大英雄に匹敵するほどの救世主だったのは言うまでもない。
「――」
「目が覚めたか」
瞼を二、三回閉じて、開けてを繰り返すアンナは、ぼやけた天上の中央に少年の面影を残したアレクの姿を認める。
上半身が裸の彼は心配そうにアンナの頬を撫でて「うなされていた」と言った。その際に彼が覗き込んだことでアンナの視界はアレクだけになる。柔らかいベッドの中で下着だけを身につけたアンナは、パートナーの手を両手で取り、大丈夫と口を動かす。彼女の声は悪夢の日から出ない。
「……あの日の夢か」
まるでアンナのことなら全てを見通せると言わんばかりに、アレクが彼女を抱きしめながら耳元で囁いた。それに抱き返すことで答えを告げる。
「今回は、久々の犠牲が出そうだったしな。……毎年毎年、律儀に思い出させてくれる」
アレクの言葉に、アンナは彼を癒したいと願いながらも、優しく頭を撫でて、次に口付けた。あの悪夢から十年以上経っても、消えない傷が常に隣にあることを二人とも痛感している。
ベッドの中で抱きしめ合いながら、互いの存在を確かめるアレクとアンナ。その中で、彼らのサポートAIであるローゲの声が届けられた。
「お二人とも、そろそろ時間です。準備をお願いします」
声だけで全てを済ませるAIの気遣いに、仕方がないなとアレクは笑ってベッドから降りた。アンナも微笑みながらベッドから出ていく。
「行くか」
アレクは手を出し、アンナはその手を取った���
ファロス機関の待機所はそれなりに広い。広いが、無機質な印象を抱かれる。カラフルなベンチも、煌々と光る自販機や、昼夜問わず何かしらの番組が流れるテレビだってある。それでも、無機質なものだと誰もが口を揃えていた。
待機所の中ではいくつものグループが何かを喋っている。互いにパイロットとオペレーターの制服を着て、時にジュースを飲んだり、カードゲームに興じていたりしていた。その誰もが顔色が悪いので、より一層待機所が無機質な印象になっていく。
そこにたどり着いた制服に身を包んだアレクとアンナは、多くの室内にいた人々と挨拶をしながらも中央で待機していたナンバーズ四番のナーフ・レジオとユエン・リエンツォの元へ向かう。
「ご苦労だったな」
アレクがナーフへ声を掛ける。それに無表情のままナーフが頷き、一枚の電子端末を彼に渡した。
「報告はこちらに。今回発生したペティノスは、これまで観測された形状と一致した。ただ攻撃範囲が広いタイプが増えている」
「損害は」
「一機撃墜されたが、パイロットは無事に保護されている。今は処置も終わり療養施設に運ばれたところだ。完治したところで、今後はカウンセリングを受けるだろう」
「そうか」
それは何よりだ、と零したアレクの言葉に同調するかのように待機所にいる面々がホッと息を吐いた。その様子を見ていたユエンは呆れたように言う。
「ははぁ、今晩は二番の同期たちばかり……と思ったらそういうことですかぁ。毎年毎年、君ら律儀だねぇ。おいらはそんな気分になったことないよ」
十年も眠れない夜が続くだなんてかわいそう、とユエン・リエンツォが口にするが、そこには似たような境遇であるはずの彼らへの多大な揶揄が含まれていた。
「そういうあんたも、この時期は多めに任務に入るじゃねぇか」
言い返すつもりでアレクがユエンの任務の数について告げる。
「小生、そろそろ後進に引き継ぎたいところでありますが、現見が許してくれないんだわ。せっかく新しい二番が生まれたってのに、未だに信用できないんかね」
「ユエン、そんなことは」
小馬鹿にするかのような言い回しの彼女に、ナーフは顔をしかめて制止する。だが、それを無視してさらにユエンは話を続けた。
「毎年毎年、この時期になると不安定なやつらが増えるからねぇ。早く悪夢世代のなんて無くした方がいいんじゃない? あの問題児たちも虎視眈々と上を狙ってるようだし。君ら夜勤多いから、下の子たち割と快眠タイプ多いじゃないか。噛み付く元気満々なんだから、そろそろ下克上くらいしでかすんじゃない?」
「余計なお世話だ」
アレクがユエンにきつい口調で告げた。
「少しは羽目を外しなさいよ。同世代のスバル・シクソンの社交性を見習うべきじゃないか」
「あいつは、俺たちの中でも腑抜けたやつだ」
今度はアレクをナーフが制止しようとしたが、それをユエンは止めた。
「ハッ! 笑わせるねぇ。あのスバル・シクソンの死後も、君らが彼の言葉を無視できてないの、我輩が知らないとでも?」
「……ユエンさんよぉ、今夜はやけに突っか��るな」
「なぁに、気が付いたんですわ。あの五番の坊やが、自力で立ちあがったのを見てね。悪夢世代の多くは救って欲しいわけじゃない。ともに地獄にいて欲しいだけ」
その言葉にそれまで黙って聴いていたアンナは、ユエンを叩こうとする。が、呆気なく彼女はその手を避ける。そして、けらけらと何がおかしいのか侮辱を込めて「平々凡々、やることなすこと繰り返しで、飽きたよ」と彼女は言う。
「あんたがそれを言うのか。同期の誰一人助からず、現見さんが戻るまで誰も助けられずにいたあんたが、それを言うのか」
アレクは怒りを滲ませて返す。
「あんたは地獄を見なかったのか。あの怒りも、嫌悪も感じなかったのか。俺たちが救われたいと本気で思わなかったとでも」
「その共感を求める言葉は、呪い以外の何者でもないだろうよ。少なくとも、スバル・シクソンは悪夢世代という共同体から旅立った」
その結果が五番という地位だろう、と告げたユエン。彼女は、そこで口調を変えた。
「あいつの素晴らしく、そして恐ろしいところは、あの視野の広さだ。オペレーターとしての実力だけでなく、よく人間を見て、観察して、そして洞察力で持って最適解を出せるほどの頭の良さがあった。もしも倒れなかったら、間違いなく私たち四番を超えていっただろうし、二番の君たちも脅威を覚えたはずだ」
滅多に人を褒めないユエンの賛辞に、隣にいたナーフが呆然とした表情を浮かべた。
「あの双子たちは、パイロットとしては私たちを超えているよ。恐怖でも、憎悪でもなく、君たちのような大義も掲げず、ただ互いへの競争心と闘争心だけでペティノスを撃破し続けている彼らの存在は、新しい時代が来たとファロス機関に知らしめた。スバル・シクソンはそれを敏感に感じ取り、そして彼らを導いている」
その言葉にアレクは皮肉を込めて「違うだろ、過去形だ」と言い返す。だが、ユエンは首を横に振った。
「いいや、現在進行形だ。現に、あの坊やは次のオペレーターを見つけてきた。あの大英雄のプログラムを損傷できるほどの能力を持った新人を」
「まぐれだ」
「それが成り立たない存在なのは、お前たちだってよく知っているだろう」
冷徹な指摘にあの勝負を見た誰もが口を紡ぐ。
先日の裁定勝負のことを知らなかった幾人かが、話を知っている面々から小声で詳細を聞き、その顔を驚愕に染めた。嘘だろう、とこぼれ落ちた本音が全てを物語っていた。
それらの反応を見たユエンは、最後の言葉を紡ぐ。
「時代は変わっていくんだ。否応にも、人間という種は未来を求める。その先が地獄でも構わない言わんばかりに、彼らは前へ行く。いつまでもその場に突っ立ってるだけじゃ、何も成せない」
「……説教か」
「吾輩ごときが、らしくないことを言ってるのは百も承知だ。が、毎年の恒例行事に嫌気が差したのも事実だよ。お前たち悪夢世代は、少しは外を見るべきだ」
そこまで言って、ユエンは部屋から出ていく。ナーフがアレクたちを気にしながらも彼女の後を追って行った。
沈黙が室内を満たした。誰も彼もが思い当たる節がある。誰だって今のままでいいとは思っていなかった。それでも悪夢世代と呼ばれる彼らは立ち上がり、アレクとアンナの元に集まる。
彼らは顔色が悪く、常時寝不足のために隈がくっきりとしていることが多い。
誰かがアレクの名前を呼んだ。
誰かがアンナの名前を呼んだ。
それに呼応するかのように、アレクとアンナは手を繋ぎ、同期たちを見る。
「みなさん、そんなに不安に思わないでください」
唐突に落とされた言葉。ハッとしたアレクが、自分の腕につけていた端末を掲げれば、現れたのは彼ら二番のナビゲートAIであるローゲのホログラム。微笑みを浮かべ、頼りない印象を持たれそうなほど細いというのに、その口調だけは自信に満ちていた。
「あの臆病者の言葉を真に受けないでください。彼女が何を言ったところで、あなたたちが救われないのは事実でしょう」
ローゲの指摘にアレクは視線を逸らせ、アンナは鋭く睨む。だが、かのAIはそれらを気にせず更に言葉を重ねる。
「悪夢をみない日はどれほどありましたか? 笑うたびに、願うたびに、望むたびに罪悪感に苛まれたのは幾日ありましたか? 空に恐怖を抱き、出撃するたびに死を思い、震える手を押さえつけ、太陽の下にいる違和感を抱えて生きていたあなたたちの心境を、あの人は本当に理解していると思いますか?」
彼女の言葉は何の意味も持たない戯言ですよ、とローゲは告げる。
静かに「そうだ」「ああ」「そうだったな」「あいつらは分からない」「そうよ」「あの悪夢をみたことがないから」「そうだわ」と同意する言葉が投げられた。
アレクがそれらをまとめ上げる。
「そうだな。今夜もペティノスが現れるまで、話そう。どうやってやつらを殲滅するか。なに、夜は長い」
誰もが救われなかった過去を糧に、怨敵を屠る夢想を口にした。敵を貪りたいという言葉ばかりが先行し、それよりも先の未来を願う言葉が出てこない歪さを誰一人自覚していなかった。
***
ゆらめく炎を前にして、ゆらぎとイナ、そしてルナの三人は困惑していた。
ここは都市ファロスの外れにある墓地であり、そして多くの戦争従事者たちの意識が眠る場所。つまり肉体の死を受け入れ、新しい精神の目覚め――擬似人格の起動を行う施設でもあるため、人々が『送り火の塔』と呼ぶ場所であった。
擬似人格とは常に記録された行動記録から思考をコピーした存在だ。永遠の命の代わりに、永遠の知識と記憶の保管が行われるようになったのは、ペティノス襲来当時からだと言われる。地球全体を統括しているマザーコンピューターはその当時の人々の擬似人格から成り立っているのは、クーニャで教わる内容だ。
しかし擬似人格は思考のコピーであって、本人そのものではないために、起動直後はたいてい死んだことを受け入れきれずにいる。
擬似人格が擬似人格として、自分の存在と死を受け入れる期間がしばらく存在するのだが――特に都市ファロスはペティノスとの最前線に位置するため、その死者たちは多大な苦痛を伴って亡くなっている場合が多い――その際のフォローを行うのがこの施設の役割であった。
また、擬似人格が安定した後に自分が電子の存在であり、データの取扱い方を覚えていった先に生まれるのがAIでもある。これは都市ファロスに来てからゆらぎたちも知ったことなのだが、エイト・エイトを筆頭に人間味のあふれるナビゲートAIたちは、その多くが対ペティノスで亡くなった歴代のイカロス搭乗者たちだった。そして、あれでも戦闘に影響がでないよう、感情にストッパーが課せられているらしい。
そのAIへの進化や感情への制御機能がつけられるのも、『送り火の塔』があるからであった。
そして『送り火の塔』の入り口、玄関ホールの中央に聳え立つのは、天井まで届く透明の筒の中に閉じ込められた巨大な青い炎だった。
地下都市クーニャでは街の安全のために炎がない。火という存在をホログラムでしか知らない彼ら三人は、教科書に載っている触れてはいけない危ないものというだけの情報しか持っておらず、ただただ初めて見るそれに魅了されていた。
「おや、そのご様子ですと、初めて火を見たようですね」
三人とは違う声が掛けられる。
ふわふわとした淡い白金の髪を結いだ青年が、建物の奥から歩いてきた。彼の姿は白に統一されており、腰元に飾られた赤い紐飾りだけがアクセントになっている。彼はゆらぎたちの前にやってくると、同じように炎を見つめた。
「この火は、送り火の塔の象徴的存在でもあります。肉体の終焉をもたらすもの、あるいは精神の形の仮初の姿、人間が築いた文明の象徴であり、夜闇を照らす存在として、ここで燃え続けています」
男の説明にイナが尋ねる。
「しかし、クーニャでは火は存在しなかった。人々を危険に晒すためのものとして……なのに何故ここでは」
「地下世界の安全のためでもあります。火は恐ろしいものですので、できる限り排除されたと聴いています。ですが……ここ都市ファロスでは、火は身近なものです。対ペティノス戦において、火を見ないことはないでしょう。燃やされるものも様々です」
あなた方も、いずれ見ることになりますよ、と三人を見て男は微笑む。
「初めまして、新しく都市ファロスに来た人たちですね。私は自動人形『杏花』シリーズの一体、福来真宵といいます。ここの送り火の塔の管理人として稼働しておりますが、今日はどのようなご用件でしょうか」
ゆるりと笑う線の細い青年は、どこをどうみても人間にし���みえないと言うのに、己を自動人形と告げた。
「自動人形? こんなにも人間みたいなのに?」
その存在に、ゆらぎは戸惑いを覚える。感情的なAI、執念を込めて人間に似せられたプログラム、そして人間そっくりな機械と、ここまで人間以外の存在を立て続けに見てきたからこそ、いよいよこの都市は人間がこんなにも少ないのかと驚いていたのかもしれない。
「もしかして、ゆらっち自動人形見たことないんじゃない?」
その戸惑いを感じ取ったルナが指摘する。それに対しイナも「そうか」と何かに気づいたようだった。
「獅子夜は始めからナンバーズ用宿舎にいたからな。僕ら学生寮の統括は自動人形だ。ナビゲートAIが与えられるのは正規操縦者になってからだし、それまでの日常生活のサポートは自動人形たちが行っているんだ」
ここ都市ファロスでは珍しい存在ではない、と続くイナの説明にゆらぎはほっと詰めていた息を吐く。
「……そうなんだ」
「そうなんよ」
ゆらっちは特殊だもんねぇ、と笑って慰めるルナの言葉に、イナもまた頷く。
「私のことを納得していただけましたか?」
苦笑混じりに真宵が声を掛けてくる。ゆらぎは小さな声で「すみませんでした」と謝罪した。
「いえ、お話を聞く限り随分と珍しい立場のようです。都市ファロスに来たばかりでありながら、すでにナンバーズとは……まるで」
「まるで?」
ルナの相槌に真宵はハッとしたように首を横に振る。その動きは滑らかで、やはり機械とは思えないほどに人間味があった。
「……いえ、何でもありません。それで、どのような用件でしょうか」
「あ、そやった。あんな、うちら大英雄について調べに来たんよ」
ルナが告げた大英雄の言葉に、真宵の顔がこわばったのが、イナとゆらぎにも分かった。
「なぜ、来て間もないあなたたちが大英雄のことを」
疑問と不審の感情が乗せられた視線を三人は向けられる。やはり、ここが正解なのだと全員が確信した。
大英雄と呼ばれる存在について、三人が調べた限りわかったのは、あの銀色のイカロスに乗っていたパイロットとオペレーターであること。そして、空中楼閣攻略を人類史上初めて成し遂げ、三十年前の大敗のときに命を落とした存在であること。そこまでは、学園内の資料や右近、左近たちから聞き出せた。
だが、とここで不可思議なことに気づく。彼ら大英雄の名前も、写真も、どのような人物であったか、どのような交友関係があったのか分からなかったのだ。
ナンバーズ権限を使っても同様、セキュリティに引っ掛かり情報の開示ができないことが殆ど。他のナンバーズからの話――主にあの双子のパイロットからだが――では、三番のパイロット現見が嫌っているらしい、ユタカ長官が彼らの後輩であった、くらいの情報しかなかった。
これは故意に情報が隠されていると感じ取った三人は、他に何とか情報を得られないかと手を尽くしたのだ。
結果、ここ『送り火の塔』という存在を知ることになる。あの謎のAIが告げた、正攻法では情報に辿り着けないの言葉通り、ここの擬似人格に大英雄に関連した人がいるのではないかと三人は考えたのだ。
丁度、右近と左近、彼の相棒のオペレーター、そして先日裁定勝負を仕掛けてきた兎成姉妹たちは、あの銀のイカロスについての調査があるということでファロス機関本部への呼び出しがあった。その隙を狙ってゆらぎたちは送り火の塔へとやってきたのだ。
「先日、彼――獅子夜ゆらぎが受けた裁定勝負のときに、仮想現実で銀のイカロスが現れました。なぜ現れたのかは謎ですが、それでも」
「大英雄と呼ばれる彼らをおれたちは……知りたいんです。あの電脳のコックピットにいた二人が、一体どんな人たちだったのか。執念染みたあのプログラムが」
先日の銀のイカロス戦について説明するイナ。それを引き継ぎ、ゆらぎもまた、正直に気持ちを吐露する。その二人の説明に真宵は目を見開いた。
「……そんな、君たちはあれを――彼らを見たのですか? まさか、そんな日が来るなんて」
驚きと戸惑いを隠しもせずに、視線を左右にゆらす真宵。
「見たのは獅子夜だけです。でも、あの銀のイカロスの中にいる人が正直どんな人だったのか、僕だって気になります」
「とっても優しそうな人やった、てゆらっちは言っとった。擬似人格は残らなかったってことやから、たぶん一から作り上げたんやろ? そんなにも遺したかったお人たちなんやろうな、てうちは感じる」
「お願いします、福来さん。おれたちに、大英雄のことを教えてもらえませんか? もしくは、大英雄を知っている擬似人格を」
「知ってどうするのですか?」
それまでの揺らぎが嘘のように、真宵の声は冷たかった。いや、意識的に冷たくしているのだろう。
「大英雄を知ってどうするのですか。彼らは既に過去の人です。この戦局を変えるような存在ではありませんよ」
その真宵の言葉に反論したのはイナだ。
「なぜ、そんなにも大英雄と呼ばれる人々が隠されるのですか。名前すら見つからず、功績だけが噂されるだけの存在にされて」
「彼らは罪を犯したのです」
痛ましい罪です、と真宵は続ける。その言葉に、今度はゆらぎたちが戸惑う。
「大英雄が死んだことで、多くの人々が擬似人格を残さずに自殺しました。戦いへの絶望、未来への絶望、自分が立つべき場所を失った人々は、その命を手放しました。それは罪です。私は……あの光景を記録として知っています。あの地獄の底のような怨嗟を知っているのです」
ですから、と彼は話を続ける。
「大英雄は隠されたのです。これ以上、彼らがいない現実を受け止められない人々を増やさないように」
その説明に納得できなかったのはルナだ。
「おかしいやん。確かに人類が負けたことに絶望した人がいたかもしれへん。でも、それが大英雄のせいなん? 違うやろ、全部受け入れられなかった側の問題やねん。そんなんで、その人らが隠される理由にならへんわ」
それに、と彼女は小さな声で尋ねる。
「名前まで隠して……おらん人のことを思い出すのも、罪なん?」
ルナの言葉に真宵は複雑な表情を浮かべる。彼もまた必死に何かに耐えるようにして言葉を紡ごうとしていた。
「彼らは……海下涼と高城綾春は」
大英雄の名前が出された時、第三者が現れた。
「珍しいな、自動人形のお前がそこまで口を滑らすなんて」
低い大人の男の声だった。その声でハッとしたような表情をうかべる真宵は、何かを断ち切るかのように「なんでもないです」と言ったきり無言となった。
一体誰が、と思ったゆらぎたちは、振り向いて固まる。そこにいたのは、随分とガタイのいい男と、無表情の美しい女性であったからだ。
「……アレク、それからアンナ。ああ、そんな時期でしたね。二人ともいつものですか?」
男女の名前を真宵が呼ぶ。そして、簡略化した問い掛けを彼がすれば、やってきたばかりの二人は頷いた。その仕草に真宵は了承の意味で頷き返し「少し準備をしてきます」と告げてその場を離れる。
置いていかれた三人に向かって、やってきた二人組が近づいた。
男は筋肉質で、身長は百八十を超えていた。身体つきだけならばエイト・エイトと似たようなタイプだが、刈り上げた黒髪と金色の鋭い猫目が相まって、威圧感がある。
対し女はゆらぎよりも少し大きい、ややまるみのある身体つきだった。もしかしたら全身を覆う服装なのでそう見えるだけかもしれない。ゆるく結われた白髪が腰を超えており、右目を隠すかのような髪型。出された紫色の目は丸く、無表情でありながらも美人だというのはよく分かった。
「……獅子夜ゆらぎだな」
男がゆらぎを見て、その名前を当てる。ゆらぎもまた、この男女に見覚えがあった。
「そうです。ええと、あなたたちは」
「ああ、自己紹介がまだだったな。俺はアレク・リーベルト。ナンバーズの二番パイロットだ。こっちが、パートナーのアンナ・グドリャナだ」
そこでアンナは両手を動かして何かを伝えようとした。
「よろしく、だとさ。……悪いが、アンナはこの都市ファロスに来るときの事故で、声が出せねぇんだ。耳は聞こえるから、挨拶は声で問題ない」
「そうですか。改めまして、五番のオペレーターになりました獅子夜ゆらぎです。こっちの二人はおれの友達の」
「イナ・イタライだ。オペレーター候補で、相棒予定がこちらの」
「早瀬ルナです。イナっちと組む予定のパイロット候補です」
それぞれが挨拶すれば、アンナがおもしろそうに笑って何か手を動かした。
「あの?」
「ああ、お前たちが随分と礼儀正しいからあの馬鹿どもには苦労させられそうだな、とさ。俺も同意見だ」
問題児どもに迷惑掛けられたら、さっさと他のナンバーズに言えよ、と続くアレクの言葉に、ゆらぎたちは曖昧な表情を浮かべる。その問題児たち以外に現状出会ってないのだ、彼らは。
困った現実を知ってか知らぬか、いや興味もないのか、話が元に戻される。
「……真宵に大英雄のことを聞きにきたのか」
唐突なアレクからの問いかけに、頷く三人。
「あいつがあそこまで大英雄の話をしないのは、仕方がないんだ。大敗の記録はあっても、記憶はない」
「え」
「自動人形は稼働年月に明確に決まっている。それで同一素体――あいつのは場合は杏花シリーズだな――に記録を書き込んで目覚めるんだが、真宵は不完全な起動だった。三十年前の大敗の記録はあるが、先代の感情は一切受け継がれず、目覚めたばかりの身で理不尽な現実と向き合うことになった」
淡々と告げられる説明に当時を思い出したアンナはそっと目を逸ららす。彼女の肩をアレクが抱き寄せた。
「大英雄を失った地獄で目覚めたんだ。そこからずっと大英雄という存在を恨んでいる。俺たちもこの都市に来る洗礼で取り乱したが、それ以上だったよ、真宵は」
その優しい目とともに吐き出される残酷な言葉に、ゆらぎはなんて言えばいいのか分からなかった。
「長いお付き合いなんね���
代わりにルナが返せば、アンナが何か告げようとした。それをアレクが訳す。
「長いさ。あいつの起動と俺たちがファロスに来たのは一緒だった。同じ地獄を見たんだ。俺たちのことなんかさっさと割り切ればいいのに、あいつは律儀だ。だから、未だに大英雄のことを口にするのを躊躇う」
そこまで説明されてしま��ば、ゆらぎたちはこれ以上の追求を諦めるしかない。しかし、大英雄である二人の名前は分かったのだから、少しは収穫があったと言えるだろう。
「そう言えば、先程いつもの時期と」
イナの疑問にアレクは「墓参りだよ」と返す。それにアンナも頷いた。
「誰のだ?」
「お前たちが尊い犠牲にならないように頑張った連中」
その瞬間、ゆらぎたち三人は顔を硬らせた。
自分たちが無事に都市ファロスへ到着していたから忘れかかっていたが、あの時列車の中で見た画像には、ペティノスの猛攻を受けたイカロスたちが確かにいたのだ。
「忘れるなよ……犠牲は常に出る」
アレクの言葉に続くように、アンナもまた頷く。彼らはそれだけの犠牲を見続けたのか、とゆらぎが思った矢先に「かと言って、悪夢世代の俺たちのようにはなるなよ」と苦笑混じりに告げられる。
聞き覚えのない単語に、ゆらぎだけでなくイナやルナも首を傾げた。その様子に、アンナが呆れた表情を浮かべ、何か伝えようとしている。
「呆れた、何も言ってないのかあいつらは、だと」
ほぼそう言う意味だろうな、という予感が三人���もあったが、やはりそうだったらしい。
「あー、悪夢世代ってのは」
「十五年近く前の、ナンバーズ復活から犠牲を出しながらも生き残ったパイロットとオペレーターたちの世代のことですよ」
唐突にアレクとアンナの前に小さなホログラムが現れた。病的に痩せた男で、顔は整っているが整いすぎている印象を抱く。真っ白な髪と真っ白な肌、そして全身を隠すかのような衣服。垂れ目でありながらも、その緑の目だけが爛々と生命を主張していた。
「ローゲ」
アレクがホログラムの正体を告げる。
「初めまして、新しくやってきた地下世界の人類さん。俺はローゲ。この二人――二番のナビゲートAIです。以後お見知りおきを」
にっこりと笑い、丁寧に会釈をしたローゲというAIはそのまま悪夢世代について大仰に説明する。
「まずは簡単な歴史です。三十年前の大敗の後、ファロス機関は一度壊滅しました。ですが、その際生き残った現司令官、ユタカ・マーティンとその仲間たちは大敗で重傷となった現見空音をサイボーグ化してパイロットへ復活させ、ファロス機関を蘇らせました」
ゆらぎの脳裏に初めて会ったときのユタカの表情が思い出される。絶望的であった光景をあの人は直接見ていたのだ。
「この現見復活が大敗からおおよそ十年ほど経過しているのですが、その時の都市ファロスへやってくる新人の生存率はほぼゼロだったようです。現在四番のオペレーター、ユエン・リエンツォ以外の生存者はいません」
ヒュッと息を呑んだのはルナだった。イナは表情も変えずに、ローゲの説明を聴き続ける。
「現見復活と何とか生き残れたオペレーターであるユエンの二人が初めて新人を助けられたのが、ここにいるアレクとアンナだったのです。……とはいえ、たった一体のイカロスでどうにかなるほど戦場は甘くないのですから、彼らの同期の半分以上は犠牲になりましたがね」
苦々しい表情を隠しもせず、アレクがローゲの説明を引き継ぐ。
「……戦力が整い、完全に無傷で新人を輸送できたのは、お前の相棒の神楽右近たちの代からだ。それまでは、必ず犠牲が出ていた。その世代のことを」
「悪夢世代、と呼ぶのですよ」
さらに被せるようにローゲが結論をつける。にっこりと先ほどと何ら変わらぬ笑みを浮かべて、彼はゆらぎたちを見つめていた。
「神楽右近さん、神楽左近さんの両者ともに、悪夢世代については知っていたはずですよ。なにせ、右近さんの前のオペレーターは悪夢世代の一人でしたから」
前の人のことくらい教えてもいいでしょうに、と続くローゲの言葉に、ゆらぎは背筋が震える。
彼が暮らす部屋は、かつての主の日用品が残されていた。いや、正確には適当な箱に詰め込まれて部屋の片隅に置かれていたのだが、それが誰だったのかを教えてもらったことはない。右近に尋ねてもはぐらかされるし、左近に尋ねたところで邪魔なら引き取るとだけ返された。それだけで彼らの持ち物ではないのは明白だ。だが、処分するには躊躇う何かがあったようだ。
「あの」
ローゲに向かってゆらぎが質問しようとしたとき、真宵が「お待たせしました」と彼らの間に割って入る。
「準備ができましたよ」
「ああ、そうか。ローゲ、端末に戻れ」
アレクの呼びかけに、すんなりとローゲはその場から消える。そして彼らは真宵がやってきた方向に歩き出そうとした。が、そこで何か思い出したのか、アレクがゆらぎに声を掛ける。
「そうだ、獅子夜。神楽右近に伝えておいてくれ。前を向いたんなら、いい加減に元相棒の墓参りくらいしろってな」
それだけを告げて、アレクもアンナもあっさりと去っていった。
呆然としたまま、ゆらぎはその場に立ち尽くす。
「少し話が途切れてしまいましたが、私は大英雄については」
戻ってきた真宵は先程の話の続きをしようとしたが、それはイナもルナも首を横に振って止めた。いない間にアレクたちが何か言ったのを察したのか、真宵は「そうですか」と安堵の表情を浮かべる。
話はそれで終わりになるはずだった。だが、
「あの……ナンバーズで五番のオペレーターだった方をご存知ですか?」
ゆらぎが真宵に全く違う話を振った。
「亡くなった五番のオペレーター、ですか」
「おれの前に、神楽右近と組んでいた人です」
その言葉で、ゆらぎのポジションが分かったのだろう。真宵は「ああ、あなたが新しい五番のオペレーターだったのですね」と納得の表情を浮かべる。
「確かに、五番の前オペレーターであるスバル・シクソンとは交流がありました。それに彼は自分の死後の擬似人格の起動に関して、遺言がありましたから」
自殺や死ぬ直前に擬似人格を残さない意思表示がされた場合は、このデータが残らないのもゆらぎたちは知っていた。が、まさか起動にまで条件をつけられるとは思っていなかった。
だが、それよりも先に彼が気になったのは。
「名前……スバル・シクソンと言うんですね」
「そこから、ですか」
「何度か聴いたかもしれませんが、直接教えられたことはおれにはありません」
「……スバル・シクソンはとても優れた人でした。それ以上は私からは告げられませんが、彼の擬似人格の起動には特別な条件が付けられています。未だこの条件は達成できていないため、私からあなたにスバル・シクソンの擬似人格へ対面させることはできません。申し訳ないのですが、故人の権利としてこれを破ることは、ここの管理を任されている自動人形の私には不可能です」
もしも、擬似人格が起動したら是非お話してください、と真宵はゆらぎを慰める。
「新しいオペレーターのあなたと話せば、彼もより早くナビゲートAIになれると思いますが、まずは……神楽右近に来ていただかないと話が進まないですね」
そう残念そうに告げる真宵に対し、ゆらぎは弱々しい声で「伝えておきます」と返した。
そして彼は真宵から離れ、送り火の塔から出ていく。通り過ぎる際の弱々しさと、浮かべる複雑そうな表情に、イナとルナは不安を抱いた。
「獅子夜」
「ゆらっち」
後を追った二人がゆらぎの名前を呼ぶ。そして、両者ともにとっさに手を伸ばした。友人たちの様子に気づいたゆらぎは伸ばされた手を握り、微笑む。
「大丈夫」
優しい友人たちを安心させるように、ゆらぎはしかたがないんだと口にする。
「たぶん右近さんたちは、まだ前を向いただけなんだ。歩けるほど割り切ってはないし、未練がましく後ろが気になってしょうがないんだよ。きっと、それくらいに、スバル・シクソンという人が大きな存在だったんだ」
そこまで言って、ゆらぎは深呼吸した。そして、今度は力強く宣言する。
「そんな人におれも会いたいよ。会って、話して、ついでに右近さんと左近さんの弱みを握れたら握りたい。できれば恥ずかしい話で」
その真っ直ぐなゆらぎの思いに嘘偽りはなかった。
途端にイナは吹き出し、ルナは声をあげて笑う。
「ええな、それ。ゆらっち、散々振り回されてるわけやし、うちもあのお二人の話気になるわぁ」
「それだったら僕も協力しよう」
三人が三人ともあはははと笑い、握っていた手を話したと思えば肩を組んだ。
「獅子夜、無理はするな。お前は何も悪くない」
「そうそう、ゆらっちは正真正銘ナンバーズのオペレーターなんよ。どんだけ前のオペレーターがすごいお人でも、ゆらっちだってすごいんだからね」
その優しい思いやりに、ゆらぎは二人を力強く抱きしめる。
「……うん、ありがとう……二人がいてくれて、本当によかったよ。おれは未熟だけど、確かにナンバーズの五番のオペレーターで、神楽右近の相棒なんだ。慢心もしないし、怯みもしない」
――おれは、イカロスであの人と一緒に飛ぶんだ
0 notes
Text
下書き
未送信ポスト
予約済み
ちょっとしたトラブルでも完全に心が破壊されそうな気配がするよ〜怖いよ〜
結局謎のヤミカネで広告マネーが動いてたの!?何?もう!
球技のルールや戦略がわかる人間は偉いな…(スポーツ漫画全然知らんマンの感想)(アイカツの文法はだいたいスポ根よりなのにね)
ツイッター、本当にこれなのか?(流石にそんなわけなくない…?)
不透明なマネーの支払いがあるのかと思ったら薄ぼんやり系のぼんやりした自己裁量だったの、本当にどうなるのかわからんね
ワンピースの数字で格を出すやつで魚人空手の段位に文句言ってる人も居て、良かった
国境に部隊を展開しているのにただの脅しだろ〜って空気のほうが強かったことそれはそれで納得行ってないのかしら(朝鮮半島が海に打ち合っていることにコメントする露)
絵、とりあえず中身それぞれの細微性よりモチーフを全体にどういうバランスで配分するかという点から考えてしまうところがあり、それぞれがコピペでも写真でも対して気にしないのかもしれない
アラヤシキシステム、なんか『その時代』の好きじゃない方向のセンスみたいな直感があるけど多分個人的でどうでもいい俺の好き嫌いとか偏見だろうなって…(わざわざ書く必要あまりにもなさすぎる)
キリエライト氏が嫌いなの、直截に言えば初期のアレさは甘ったれていた頃の中高の自分を思い出す上にそういうところが見た目の良さと実務の有能性で許される上に人間らしさや長所として変換の上でまとめて肯定されることへの嫉妬なんだよな
おはキャーーーーット!!!
(うるセーーーーックス!!)
インターネットな場でも差別・政治・合法性みたいな真剣な話題をには場の雰囲気・ローカルルールではなく裁判所の判例などを参照して議論を行うことが普通だと期待していたけど、ローカルルールの方が重要だと��じる野蛮人が酷く騒ぎ立てて俺を侮辱し、管理者が俺を嗜める必要が発生したことがあった
好きな人と恋愛結婚して首都圏で就労・生活しているような人間でもきっと何者にもなれない云々の実存的なやつに悩むんだ、というのは意外だった(言われてみればそりゃ当然かと思い直す程度の鷹揚さはあるように努めたいけど)
老若男女全部出てくるコンテンツの詰んだ中年男性だけど荼毘兄が面白すぎるせいで手が回ってない男、エンデヴァーがヒロアカに対するスタンスそのままって感じがこう…
八方美人やらキョロ充やらになんとかコメントすることがさあみたいなうわ言
さそり座の女じゃんと思ったらフルタイトルが好戦的すぎて泣いてしまうボカロ曲
他者を倫理判断して自分の倫理を点検するためにこそ人間は気に入らない/お気に入りの他者をSNSで監視したり物語を暇を惜しんで消化したりするんだろ
大げさな嘘をついている人を嘘松wとか言って影からクスクス笑いするのも倫理判断、切断と外部化、目配せと毛づくろいと報復の予告だろ
いい話
何を言っているの?って感じだけどなんかマジでおもろい名前だった、ガンジー・ホセマリアみたいな西洋系の…(何?)(ガンジーは西洋じゃなくない?例えだよ例え)
烏賊ビトかと思ったらヒョウ柄のツインテールの人
ド優秀な人間、遠くから見ると俺はド優秀じゃなくてよかった〜となる
戦闘行為における楽器というか号令の重要性を茶化して軽んじるようなキリエライト氏のボケがそれでめちゃくちゃ嫌いだったんだよな…(既に何しても嫌いになるゾーンだったんじゃないのか?)(吹けもしない法螺貝を声真似するの、父親にもやられて嫌だったんだよな…)
触りたくもない他人の胸部に触り、胸骨の位置を確認することが業務の一部に含まれる仕事
もう全部わからんつって赦されたい…という気持ちが永久に強くあったが、全員そういうわけではなく、そういうわけではないのだが人生は続く…ということがついに覚醒してきた
好きって伝えたときはよくわからないキレ方をしながら有耶無耶にされたけど、それには触れずにワハハって話してるとワハハって言ってくれるしもうこの距離感でいいや…な状況を突き刺そうとしてくる隣姉から感じるリアリズムっていうか
貧困を重視しすぎている自殺論、その時点で大体ド素人のやつだと思って切り捨てていい 自殺雑語り雑語りという新ジャンル
ゴッホの絵の価値は作られた仮想的なもので、環境だの動物だのの命は社会活動がどうであれ存在する独立的なものという理屈はまあ…
むしろ経済的貧困にフォーカスが強すぎると「ド素人が自殺論やってんじゃねえよカスが…」って思うまであるだろ
仕事で他人の尿を毎日扱っているからな…と思ったこと
当事者性を持ち出してどうこう言ってくるの、仮に本人がセクシャルマイノリティだったらどうするんだよ(それでレスバ逆転できるような空気を導入するの、アウティング行為)
作家性って意味不明なものを弄っている現ア、という認識を一通り勉強もやって実作もやっている人間が持っているの、何も知らん人間としては安心する
他人に生きてほしい→△
他人に生きて苦しんでほしい→○
生きて苦しんで俺を憎んでほしい→◎
左派的価値観の信望者のほうがよくわからないし、今から何を取り繕うこともなく直球の差別をします!と宣言して演説を始めても怒って串刺しにしてくるじゃん(反動がどういう理路なのかわかってなくない?という疑いがある)
口に指を挿れていると…うれしい!の気持ちにカナリなるようになってきたわ(何の話)
忘れないでくださいをああいうふうにハンネに入れることで私があの人に執着していることへの気づきを示唆したのは卑怯ではないでしょうか、あの人はああいう人だったので私が感情を寄せてもきっと返してくれることはなくて、だからそんなに入れ込もうとしないようにしたのにそういう期待が残っていて
道徳は文化内の節度という範囲でしか役に立たず、文化間対立のために起こる闘争に対して道徳によるジャッジを行うことはできない…みたいな説もあったようななかったような気がするけどつい今朝メタ倫理…もっと読みたい!となったばっかりの気がするのであまり偉そうな話をやりたくない
詩情にかけてサイゼリアメニュー表の番号を批判し続けるポモの人、どこからそれほどのモチベーションが…!?みたいな感動はある
雲の上に国があると思うのと月の上に国があると思うの、そんなに違わなくない…?ていう直感
相手をナチス呼ばわりすればオンライン上の政治議論で論破が成立すると信じている人、語彙と喧嘩の経験が少ないんだと思う
斜め書き文字にエーアイに広告!!!でめちゃくちゃ嬉しくなってしまったやつ
俺が経済的貧困にそんなに悩んだことないので何言っていいのかわかんないのもあるし…
現代のやれるはずもない宇宙開発と当たってるはずのない星占いのおまじないみたいなのじゃなくてぇ…中世に星の動きを記録して正確な暦を作るのは農産品の生産性と密接に関わっていたし、暇潰しにきっちりしたカレンダーでも作ろーみたいなモチベーションじゃあなかったと思うんですけど…的な
だいたい中性の天文学って(数百年あれしてたらそこそこ正確程度の暦も月単位で誤差が出てきて…みたいなところにれきしのうまみがあるのであってぇ…
チ。霊魂と医術とかでも科学の似たような話できるだろう…みたいな苛立
実際明確に根源になる出来事はあるから一応言及してしまうかと思ってしまう瞬間もあるけど、破滅願望どの見分けもろくにつかないけど、寝てから考えるとまあええわになりがちだから全予約投稿を始めてから勝手に落ち着きがちになってしまった
【「倫理的に低い」を直截に言明する】と【侮辱的な発言を威圧的に連投して憚らず、注意されても一言の反省もなく言い訳じみた『世相』『独裁者』批判をやってのける】というのは道徳程度においては等しく低いけど、武士道においては後者のほうがなんか言い訳の余地を残した潔くない行為だと思う
小説書き、まずは友達とか感想をいってくれる人を作るのが大事だと思うし学校でどうとかからが嫌ならpixiv大人気二次創作から始めるのも割と王道っぽい気はする
民主主義では論理的な整合性より詭弁(だろうと)で聴衆なり大衆なりその場にいる人々を扇動する事のほうが権力の行使のために必要、
というのが設定で、ここから
①扇動の技術を磨くこと
②民主主義を打倒すること
のどちらかが道徳的に正しい行為になるのだけれど、②の選択肢を取る場合でも
ジョセーは初対面求婚カマしてもなんとかなるから狡いよなーと思っているところまぁまぁある(そんな例外は2例くらいしか知らないだろ)
政治主張を実現可能性は無視して理想を叫ぶことだと思っている人、庭に油田が湧けばいいのにとか金のなる木があればいいのにとかのただ都合の良い妄想とどう区別をつけた上で必要を為しているつもりなんだ
左翼が理論的には正しいというのならさっさと清教徒革命でもしてみせろよ
キリエライトさんだけは本当にポジティブなのかまぁまぁ怪しいけど
とりあえずキリスト教徒である自覚は持てないし教会に通ったり献金をしたり洗礼を受けたりはしないけどキリスト教徒的でありたいと願うことにはしたので、差し当たって同性婚に反対する政治的立場を表し、一度はその理屈についても文字で公開することする(具体内容はnoteに置く)(予定と宣言)1/4
あえてツイッター上で現実の政治に触れる発言は(深夜への予約投稿であっても)控えるべきかもと思いつつあるのですが、最後に一つだけ言うと、私はずっと昔からハリポタの作者であるJ・K・ローリングを深く尊敬していましたし、彼女がトランスフォビアに立つ変人として扱われることに耐え難い苦痛2/4
を抱きながらも仕方ないかもなとも常識的に思い表立った反論をできなかったことを多少は歯がゆく感じていましたし、今では後悔しているかもしれません。(結局高度な道徳?政治?判断については、権威である裁判所の結論を待つ以外のことは全くする気も起こさなかったので)3/4
所詮私が何に政治的態度を示そうが現実に対してそれほどの活動力を持つわけではなく持とうともせず、賭け事の亜種でテレビ見てるだけなのを少しは恥ずかしく思っています。恥ずかしく思うだけです。特にそれ以上何かをしようとは思えません。4/4【以上】【消すかもしれないし、消さないかもしれない】
ツイッターやめたいっっったらツイッターはやめるなって言われて、その命令だけがくれたものだったから拘っているけど何を言えばいいのかわからないから混濁した戯言を垂れ流すしかないんやぞ、わかっているのか
色々な人
シャカ・ズールー、戦闘は名ばかりの儀礼や儀式に近い牧歌的行為で縄張り問題を解決していたアフリカ人をバチバチ暴力でまとめ始めたんだけど、その頃ヨーロッパ人はライフルを軍備している戦力格差
処女地だの処女航海だのの話をめたくそねっとり書く人(あの辺の語が訳されたのがあのへんの時代だからだいたい一致してんじゃないの)
物に性別がどうこうみたいなやつ、ポモとはフランス現代思想なのでだいたい野蛮な話しかしてなくて終わり
ゲーフリをけなすターンと褒めるターンを一人で交互に回している人、心配になる
螺子巻き仕掛けのナッツ・クラッカー
ネジの外れたナッツ・クラッカー
大丈夫。ナッツ・クラッカー
愛・ナッツ・クラッカー
殺人鬼
洗礼名簿
シンドラーのリスト
穢翼のユースティティア
文系大学生詩人志望の驚いたの使い方、特に政治的意見に対してがムカつくの回
漫画で意味不明な前提だから、とロビン過去編にマジレス芸をする予定
実際というか実理的には自分は(も)性的マイノリティーであるという(マイノリティは善くなくて恥ずべきものだという右派信念のために)認め難い仮説を呑み込んだら決着することなんだけど
働く車が出てくる4コマが好きだった
あんな殺され方をしたあとでも「チンポを見せろ安倍晋三」をバカウケジョークと捉える人が結構いるんだ、というのはそれなりに呆れた
死者を悼むとか敬うみたいな感覚が薄めの自分は「これであのクソくだらないジョークを言う人が減るんならいいな」とテロられたときに思ったんだけど
開発チームと調整チームってそんなに別なの?
オタク除霊師で公式に左右聞くのもやめろ…で人々が大変そうになっていたやつ
ゲームの賞が発表されたとき、フォロワーにダイパリメイクに強い感情を持っている人とニディガに強い感情を持っている人がいたりしたので、迫力があってよかった
政治領域の中で誰も排斥なり冷遇なりをしないことなんて無理だろ
道徳を基準にして気に入らないやつを締め出したい、別に道徳的行為でもなんでもないしそもそもこの世に道徳的行為なんて言うものは存在すると思ってないですよ、それは権力の闘争に用いられる単なる手段の一つです
道徳を基準にして自分の気に入らない相手を締め出したいという場合にはバカ騒ぎして権力者におもねり世間の空気に迎合しているようなことを言えばよい、まるでそんなことも知らなかったのかと言われているようで本当に恥ずかしくなってきますね
『元日本赤軍が作るテロリスト賞賛映画を国葬に合わせるという危険なプロパガンダ』、まあそれはそうでは…
人種…白…自由…は白ハゲ漫画より白人至上主義の気配が…
快楽を伴わない精液
無償の愛
かけがえのない絆
神事としての去勢
性格に説明を与えることをすべてバーナム効果で済ませようとする人、覚えた言葉を使いたがる中学生か?と思わないでもないけど…
新選組に思い入れがなく、沖田総司が男という認識をfgoが完全に破壊しつつある
『創造力もないのにこれだけ謀略を巡らせて選択と決断をし続けているのすごいよ』という胎サタナキア評、すごすぎる
一人の話なので話半分に聞くにしてもすごい話
短歌/川柳の二項対立に言語化せざるこだわりと自信を無駄に持っているが、振り回すと実質川柳の悪口でしかないことのバランスをどう取ればいいのかまぁまぁ悩んでいる(勝手にしろシリーズ)(n回目)
アルゴリズムの道徳律しか駆動させられない人間、人間が持っているはずの誠実さというものを裏切っているのでは?という不信感がある
マイノリティより家畜の方が共感できるし、一次産業に従事するのがどういうことかっていう想像力を都会の人間は失ってそうなのでムカつく話
松井優征の好きなキャラ、芸術のために最愛の人を殺す歌手
おどけて見せることで無理に集団に溶け込もうとしているのだと見られたら一番嫌だ、と反射的に思ったけど禁止されたものこそ欲望であるの論理と逆張りの相性悪すぎるだろ
・論理ではなく気分の問題
・衆人環境で罵倒されることが自分の望みだった
・一度そうストーリーの糸が繋がってしまったので以降そのように補強される
・向こうがマスターベーションて語彙を使ったのが…
・昔ツイキャス配信で「死ね」と罵倒されて気持ちよかったことをずっと引きずっていた
考えの違う人間を浅い程度でばかにするのが健康なネットでのストレス解消法、まあそういう態度もあり
ノース二号、すべての要素が好きだし短編なので読め!くらいしか言わなくたってもいいけど歌に思い入れのあるロボットなので初音ミクなんだよなが強いよ それで機械はダメ系の音楽家の爺さんとペアはそんなん最強やろだよ
一番楽しかった酒飲み、弟と東京旅行してホテルの床で転んで寝てたとき(多分弟はまだ未成年だった)(普通に一人で行く気だったのに東京行きたいから着いて行かせろつってくるのだいぶかわいいな)(いきなり気色の悪い自慢話を始めるなよ)
こういう宗教観の民族がキリスト教神学の結婚は神と教会の介在による男女の神聖なる合一を指すという概念を理解できないのは仕方ないのかもなみたいなキレになってきた、まあ新ジェンダータイプの結婚観はまず西洋の結婚様式から制圧してきてるのは事実だし…
ぐだぐだイベント、毎回「日本史にも好きな人はいるんだなぁ…」みたいな他人事目線が発生しがち 武将も新選組もなんか別に…
藤丸くん、政争で他マスターに呼び出された静謐のハサンに殺されてくれ…の要望がある(静謐さん、原作の方でも親愛の一回性と交換性に厳しい思いをしていたらしい)(型月ウィキ読み齧りの知識〜)
ルッバッ統合失調症イメージ、ポリコレ理由から人の形をした悪(傷つけても構わないもの)としてゾンビもの、鬼、巨人的な描き方の需要が増える、という話があったけど少なくとも進撃の巨人は見た目が醜悪とか意思疎通ができないとか歴史対立があるとかを切断処理の言い分に使うなって話だったろうが
ファン心理問題で推し燃ゆはよく聞くな〜金閣寺だからか?ってなったけどまあ金閣寺に比べたら推しなんて所詮人間だしなとはなっちまうわね(適当こくな)(真面目に適当こくなを末尾に記載すれば適当こいてもいいと思ってたらそのうち痛い目合いそう)
親殺しの罪が重くなるやつ、俺も殺したくなる方のガキだったし…
それでも俺はヘンリー・ダーガーの生き方に賭けるよ
オナ禁すると起床時に寝ぼけながら情事妄想を加速させているのでそれをメモっといて後から編集することでエロ文創作ができるかも、という仮説がある(ストイックさなのか本能ドリブンなの��わからないんだけど)(知らんて)
老害なんて単語がそもそも若造どもの思い上がりでしかなくて
天皇制には中立だけど元号制度にはクソがよ…と思っているせいで、元号ナンタラの式のときに虹が出ているのにワイワイ騒いでいた奴らにカスがよ…と思っていたことを思い出した(政治的意見は、持たないほうがいい)
『人々が自らを手放したんだ』と空目した
月〜金(19時55分)までの予約投稿数、103
たーくん一生練り回してる部分をすっと乗り越えられたのでもう俺のための物語としての隣姉は終わってしまったのかもしれないという恐怖があるね
俺はストーリーよりもキャラ萌えなのか…?って一番なったのが層アなんだよな(なんか創アの悪口みたくなってないか?)
死ぬほど当たり前のことを突き詰めていたら何故か難しくなっている瞬間、というものがあるらしい(自分は数学は全然やらないし知らんけど、メタ倫理とかでの経験ならある)
別種生物のある活動スタイルを人類が模倣すべきなんて馬鹿げたことを言うの、自分の気に食わない分野だったらどうするつもり?(一夫一婦制の動物がいる時点でお話にならなくなるのに)
左派はふざけて真面目に問題にすべきではないような風潮を作ろうとしてくるが、一切ふざけないか一周回して完全にふざけきるかという戦略が考えられるが、大概やる気がなくなって終わる(井戸端会議だから)
左派はふざけて真面目に問題にすべきではないような風潮を作ろうとしてくるが、一切ふざけないか一周回して完全にふざけきるかという戦略が考えられるが、大概やる気がなくなって終わる(井戸端会議だから)
いいだろうが歌詞ツイートをしてもよ(強気)
ラジカルな左派を自認(笑)している人が倫理に疑問を呈されると相手の人格に問題をブチ込んで悪魔狩りかよみたいな罵倒してくるやつ、まあ素直な人間だったので藁人形論法による愚かな政治対立者イメージなんじゃないかという期待をしていたところがね、あったのかもしれないですわね
私は完全に本質主義者なので石の裏でギャーギャー汚い言葉を使っている人たちは軽蔑しますが…
先進国が金銀銅ではしゃぎまわるクソ汚いスポーツ大会は不穏なナショナリズムを煽るという理由で嫌いだったし、ゲーム音楽で絆されてインターネットが歓迎ムードになるのをすごく苦々しく思っていた
レイくんはトロフィーの花嫁とセックスしてましたか?みたいなやつが母親ヅラ概念だと思うこと
リスナーが母親ヅラしてコラボ相手に挨拶とかしてるのがクソ恥ずかしい、大人のやることか…?
インテリ寄りの母親の妹、そのバリバリ感で子供を両方東京の大学にやり東京の大学に行った子供のサポートをやりをやったけど、子供が大学出てしまうと置いてきた夫との違和が違和になって軽い家族崩壊になっている感、すごく、
ボカロの鑑賞シーンが教養バトルみたいになってるの、いい話だ
恥を晒さないならTwitterじゃないぜインターネットじゃないぜ、そういう覚悟を掛けて踏ん張っていく
バかが思い付きで誰も幸福にしないような放言を吹聴しているのも倫理的に低い行為ではありますが、その低さをいちいち取り締まる必要があるかは程度によるでしょう(悪質なヘイトスピーチにおいては、禁止が妥当である可能性は高いでしょう)
当然人類が滅びるべきか滅びないべきかという話をしているし、なんかウケるという理由だけで極論と極論で断絶を呼び込もうとするのは治安に悪い
宗教画描いてたら異性愛至上主義者から性愛とか全部キモいにお気持ちが傾いてきた、社会全部よくわからん怖い不適合
https://jp.quora.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7-%E4%B8%80%E7%95%AA%E7%8B%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B
水着・ふーやーちゃん、ついにできた地元以外のエレシュキガルの友達なのでガッチャガチャに挑んで討ち死にしたりしていた
インターネットがあってよかったもの、3章までのサイバーカラテ(4章からは完全に加速してサイバーカラテの治安がインターネットそのものになり、終わり)
ジョジョ5部を読んで運命について書くフォロワー、めちゃくちゃいい話(Twitter良いこと5選くらいには余裕で入るよ)(果てしなく何の話?)
絵のかき方、まずめちゃくちゃに線を挽きます、次に直線ツールだけでいい線だけを拾います、バケツで色を付けます、いい感じになるように消しゴムと筆を当てます、
運命論…ピンドラの運命ポエム…
胸を削った三臨ちゃんが書きたいよ…という欲はかなりある 本当に乳房去勢するのもいいけどそういう絵のほうが間違いなくとてつもなく難しいだろ(乳房去勢、ちらっと見てもグロくて怖いので書けるように観察するの普通につらいだろ)
釘にいまいち迫力が出ないな〜と思ってネジでビス留めしたらかっちりハマったの、クリエイティブ〜って気持ちになってめちゃくちゃ気持ちいい
とにかくセックスしたことがないので人間未満という自意識がバリバリしていき、早く死ぬしかない
ホモフォビアinインターネットに烈火の如く怒る人、現実に相対した気に食わない全員にいちいち烈火の如く怒ってるのか?(まともに社会生活できる?)(インターネットの治安と社会のあり方に対する捉え方が独特なのだろうと思い、気にしないようにしようと思う)
https://healthy-person-emulator.memo.wiki/d/%cb%ab%a4%e1%b8%c0%cd%d5%a4%cb%a5%b0%a5%ed%a5%c6%a5%b9%a5%af%a4%ca%c9%bd%b8%bd%a4%f2%cd%d1%a4%a4%a4%ca%a4%a4%a4%db%a4%a6%a4%ac%ce%c9%a4%a4
何もわからない。リョナとか自慢とかの話なのか?
アへ顔Tシャツ大阪で2回くらい見た、都会は怖いところやで
忙しすぎる、死ぬ(あと半時間…)
サタナキアおじさん、楽しそう(胎)
天眼の民がアマゾネスみたいな女戦士部族だったこととかキニスの親の近親が判明していく回
どうしても小型船舶免許が取りたかった人間からすれば嫌嫌大学卒業させられたアピールと同じのダルいことを言ってる(居るのか?どうしても小型船舶免許が取りたかったけど取れなくかった上ツイートを見る人)
ざっくりしんどいよ〜(だるいけど眠みが半端で寝られないわ!)
家に到着すると同時に呼び出し似合うという感動の体験が君を待っている
カーティスのCVの希望、石田彰さん
自分が当事者性を発動して性的少数者でーすつったら逆転できるのかよの問題、そこに持っていくような話題の動かし方をしてるのがアウティングっていう差別行為なんだよな、しょうもない論破をやるために意地張ってたの?、綺麗な話をやってっていうくだらない政治がさあ
自分の行為の幼さや生理的欲求に根ざした欲望について指摘されてもじもじしながらも恥ずかしがって気持ちよくなっている人物、盛り上がりの空気を全く場と共有できなくて自分の世界に入れ込んでいるのがキモいんだろうな(いちいち言葉に落とし込む必要あるか?レベルの話)
根源的には他者に自分の性欲を指摘されるシチュエーションへのなんかそのそういうアレのそれがこう
性すぎる(読み方が最悪)
最近押しつぶされながら幸福を感じていた気がするんだけど(何?)、弟とは長らくあってないはずだし、なんか犬に押しつぶされるようにしたが、夢で見たことを忘れているのかどちらかの公算が高い
アニオリに登場したメンヘラが全員振り回して自爆する、もしかして軟派な消費豚が男の世界にズカズカ意見したせいで案件か?(やめろやめろ!)
歌う頼みをためベタ全身歌人間
めちゃ嬉しそうに「敗戦記念日じゃん!」と言ってしまった(政治思想〜)
インターネットで自分の生活分野にムキになっている人を見るとかなり(笑)の気持ちが盛り上がってくるけどクリエイト業の人間とか比にならないほど感じてるだろうし特に言及することができない
子どもが小便器に向かってズボンを完全にずり下げケツを丸出しにしながら用を足していた
管理人様を通して本音が聞けたことが本当に嬉しいけど管理人様、他の同席された方々には本当に無意味な徒労を負わせてしまったし、そうこうするうちに本人様にも大変無礼なことをしたと思うし、論理ではなく気分の問題
本当に恥ずかしくてしかも火種になるから向こうには書けないこと、こちらで書けばいい
インターネットで喧嘩をしてしまいした。絶対にインターネットで喧嘩はしないほうがいい。(本当に申し訳ない)
昼間では議論が深まっ太郎くらいのことを言おうかという気持ちがなくもなかったので時間おいてよかったんじゃないすか
あんたがBAN権利持ってるようなサーバーならもっと媚び売ったりしてるし、そもそもそんなところ居たくないし、なんでいきなり突飛な仮定に入るんだ
よくわからん人によくわからんことをブツブツ言う男、駈込み訴え(俺はこんなにBLが好きなのにフィクションロマンスの題材として優れてはいても同性愛は悪徳とされるべきと発言してボコボコに貶されるの、本当にかわいそう)
普通に言葉とか左右の問題でしかないものについて言葉とか左右の問題ではないという飛躍を繰り出してしまうの、メタ思考についての訓練が足りてないんじゃない?とかね
すきだぜ、pixiv大百科
率直に言えば反LGBT者に対して議論を打ち切るときの典型的な態度と勝利通告だな、という程度のことでした。もっと予想外で激烈な態度を取ってくれる人がいつかいればいいのにとも思わなくもない
他人のいいね欄覗くやつで自分のアカウントミュートが反映されるようになってる!やったぜ(他人のいいね欄を覗くな)
えっちな残業…?
↓
Hardな残業でした…
AIの絵、普通にとりんさまAIのほうが多く流れてくる
自分の左右の定義は
左:人は平等で自由であること
右:人に序列と運命があること
を指します
あっしのような底辺コメディカルじゃあ未来のお医者さまにはかないせんや、へへへ…
本当にBLが好きだが本当に同性愛を憎んでいる人のために存在してそうなカプを推しカプにし、各方面にご迷惑をかけそうなので言わんほうがいい
中二 平気で全裸
中三 精通
高以降 下級生の二の腕をへし折りたいという欲求を二次に突っ込むことで無視する
ラブデスター読み返してるけどやっぱりこの漫画変だし面白いわね(変…)
Wikipedia、権威
強大な姉妹がよくわからなすぎるスケールの熾烈な内部争いを繰り返しているっぽい超常組織、星見の塔
アマゼロトはぼうの化身なので仕方ない(どういうこと)
①別にいうだけなら勝手にさせれば良くない?
②「こういう風な主張や表現であれば連帯してやっても良かったのに」みたいな言い種がムカつくし、自分が権力者であることに無自覚的にみえるのもムカつく
好きだった人を嫌いになって、嫌いだったことに慣れていって、何もかも覚えてられなくなって
トライデントの『口舌』、お前はどこで戦っている…
ミャクミャクに対して好意的に捉えるとか何かしらの反応をするとかいうことも政治じゃないですか、ゆるきゃらとかああいうのが政治的に曖昧に利用されるのって危機感があって、あるんですね
カエル・犬・政治
裸の自分、服を着た誰か
神霊と境界記録帯はなんか違うんじゃないのこう…マスター差による人格の影響とかそういう系が(本当にわかっていっているのか)
エレシュキガルの恋愛要素は良くてぐだアナのそれはなんか…!って言ってるの、よくわからない衛生琴線の話っぽくて嫌そう
粘着獣、一部が汚い〇〇で最高〜と思ってるけどネタバレかつ両方知っている人にしか伝わらないので感想としてはかなり低俗かつ下品
腹パン枠なのでついつい歌姫Spearちゃんへのあたりが強くなってしまう そんな枠はない
『チョコレートリリーのスイーツ事件簿Season2 Case.14 アズチョコに挑め!』も普通に好き
Season2 Case.14←堂々たる嘘
下から順に読んでください
許すとか許さないとかじゃなくて現実で起きたことはただの事実に過ぎないし、ある一つの現実だけが政治行動に特別の意味を乗せたりするわけではないだろ ある事件に乗せて模範市民としての意識を煽る言説を喜ぶやつ本当に自我とかある?
なんかコロナ陽性者が出たときにウワーって騒げるのが社会性なんだよなみたいな落ち込みがあった
すべての人間の価値観は左翼か右翼かで分類されうるし、これに同意しないのは馬鹿あるいは怠惰だと思うけど、男と女は自分が男だから右翼に入れられるけどそうでなかったら例外事項として設定したかったかもしれないライン
魔法を信じていた(い)
初音ミクが左翼価値のあれを司っているアレが
0 notes
Text
傭リについての思考①
区切り毎に独立している文言。
短い文言の詰め合わせ。
設定や世界観、衣装ごちゃ混ぜ。
----------
主人格の事を愛している(恋愛���いうよりかは親愛に近い、もっと幅の広い愛)リッパーと、リッパーを好きな傭兵の傭リも大好き。
リッパーは、別に主人格に愛されていなくていいと思っている。主人格はリッパーの被害者であるように、リッパーも主人格の被害者である。お互いがお互いに虐待をしている様なもの。
リッパーは主人格の深層心理に近いものの具現化なので、それを主人格に受け入れて貰えないのは居場所が無いのに等しい。
主人格は殺人なんて望んでは居ないのは本当だが、嘘でもある。
リッパーが人を殺した後に主人格が描いた絵は、いつもの絵以上の値を付けられる。それを憎く思うと同時に、求めてる自分もいる。
----------
画家リ(良い子×悪い子)&傭リの三つ巴
画家はリッパーの事を一生愛さないと思っているけれど、その根本にあるのが自己愛なので結局リッパーの事を愛してはいる。でも愛の在り方は一生変わらない。そこに傭兵が加わり更にどろどろになる。
画家は傭兵がリッパーを愛する事は絶対に許さない。
独占欲では無くて、「それを愛する者が存在してはいけない」という考えから来ている。
でも本当は、リッパーこそが自分の愛されたかった部分だった。
リッパーは、画家が居ればそれで良かったし、別に誰にも愛されなくても問題は無かった。産まれた時から愛を知らなかったので、知らないものは無くても困らなかった。
だから、自分が愛される事も、画家以外の誰かを愛する事も想定していなかったリッパー。
----------
×芸術学助教
女学院なんてまぁなんて生殺しな職場に割り振られたんでしょうね?酷くありません??あんなに美しい女性達が常に間近に居るのですよ?まぁ、彼女達はあまりに無垢なので、私を満たすには少々味気ないのですが。と、女学院を出た後に薄暗い路地裏で女を殺しながら傭兵にぐちぐちと言う芸術学助教のリッパー。
でも、傭兵がその服似合ってるぞ。と言ったら、ふふ、良いでしょう。まぁ私は何を着ても様になりますからね。と機嫌を直して服を見せびらかすリッパー。
女の死体の傍らでいちゃつく傭リは良い。
----------
傭兵→→→→→悪い子→→→→→良い子の傭リ&良悪
自分に告白してきた傭兵に、
「貴方の髪色と目の色、私が唯一愛してる人と同じなんですよね。」
とリッパーが伝える所から始まる。
だから付き合ってあげても良いですよ。と言うリッパーに、縋り付くきっかけが欲しいのでそれでも良いと承諾する傭兵。
でも、リッパーは傭兵の髪と瞳だけを愛でてその奥に他の男を見ていて、傭兵を見る事は無い。
(目の色が同じかは分からないので完全に私のご都合設定、髪色は近そう)
周りのハンター達からも流石によへが可哀想では?と窘められるのだけれど、でもリッパーは「自分が誰かに愛される事も、主人格以外を愛する事も有り得ない」と思っているので頑なに押し通している。
自虐とかではなくて、そう在るべきと想ってる。
傭兵は傭兵で、それで良いのか。と周りから言われていて、良い訳無いけれど、でも、そうしている間だけあいつは笑顔を向けてくれるんだ…って酒飲みながら項垂れる。
リッパーは正直、傭兵の事を別にウォルターと似てるとも思ってないし重ねて見ていないけれど、早く諦めて欲しいと想ってる。
リッパーが愛してる男に似せた身なりをさせられて、茶を飲みながらその男との思い出話を聞かされる傭兵は本当に可哀想。
自分が、どう頑張っても塗り替えられない思い出話を、愛おしそうに聞かされるの。その思い出話の中でリッパーは主人格に愛されていないので、更に傭兵は叫び出したくなるのを抑えてる。
---------
私、名前って嫌いなんです。
誰でも平等に分け与えられているみたいな顔して歩いているでしょう?それが嫌なんです。
皆、名前を貰う事が出来ない存在なんて、居ないと思ってるんですよ。
だからと言って、欲しいとも思いませんが。私を縛るものなんて必要無いので。
というリッパーから始まる傭リ。
---------
目を覚ましたリッパーが、朦朧とした意識の中で自分の姿を見て化け物の身体な事に動揺するのだけれど、その歪な手に指を絡めたまま眠る男の姿を見付けて、その瞬間霧が晴れるかの様に安堵してしまって自嘲するリッパーの傭リ。
霧がある方が自分も他の人間も等しく姿が紛れて安心するのに、その男が居るなら霧がなくても悪くは無いなと思ってしまう。
---------
まだお互いを理解しあっていなくて、仲も良くない
貴方、傭兵でしたっけ?良いですよね。人を殺しただけ褒めて貰えて、お金を貰えて、認められて。私と同じ人殺しなのにねぇ!何が違うのでしょう?
と、地べたに転がした傭兵に対して踏みにじながら嘲笑を落とすリッパー。
事の発端は、この気狂いめ。とチェイス中に傭兵が吐いた言葉。
同じ人殺しなんですから仲良くしましょうよぉと傷口を執拗に踏み躙るリッパーに、お前は殺しても誰も認めてくれなかったんだなぁ、可哀想に。と脂汗を滲ませながら挑発めいた笑いを浮かべる。すると、画面越しでも分かる程リッパーの出す空気が冷える。
そうですね。
私も、殺す事で認めて貰えたら良かったのに。
と、何処か遠くを見ながら小さく呟くリッパー。
その言葉は、自身にだけ向けられた物だったが、傭兵の耳はそれを拾ってしまう。それから、傭兵がリッパーの事を気になり始めて片思いが始まる。恋なのかもしれないけれど、傭兵は恋を知らない。
---------
うちの傭リは、基本的に肉体関係全然持たないのに、キスするし、一緒に寝るし、たまに一緒にシャワー浴びるし、一緒に食事するし、一緒に殺しに行くしって感じ。
肉体関係持つタイプの傭リも考えたい。
---------
愛されたいと思っているけれど無自覚・無意識なリッパーと、他の人間に愛されないか気が気ではない傭兵の傭リも可愛い。
傭兵も不器用なので、リッパーの気を引こうとするけれど全然気付いて貰えない。でも、フードの下から熱が籠ってどろどろとした視線をずっと送り続けているから、リッパー以外は気付いてる。
リッパーが、多人数に愛されたいのならそれは致し方ないとは思いつつ、本当は自分にだけ愛されて愛して欲しいと思ってしまう傭兵は可愛い。
本人もそういう感情は初めてなので困惑してる。
リッパーは自分が愛してるのは主人格だけで、愛してくれるのも主人格だけだと思ってる。今は愛されてないけれど、いつか…と。
---------
傭リ、常に死の匂いを纏ってて欲しい。
うちの傭リは2人揃って碌な死に方しないのだけれど、碌な死に方って何よって感じよね。
家族に見守られながら死ぬのが碌な死に方だとしたら、2人共端からそんな死に方出来ない人間だしな。
追い詰められた時に2人揃って潔く死ぬ結末も良い。
---------
傭兵とリッパーの「人の殺し方の知識」は別物なので、その辺の情報交換というか話し合う傭リ可愛い(※共犯者関係)
顎砕いておいた方が、身元特定されづらくなりますよ~とか。
---------
えっちな傭リについて考えていたのだけれど、リッパーが性行為で全く感じない不感症なので、自分の性欲だけぶつけて終わってしまった事に傭兵が罪悪感をめちゃくちゃ持ち、肌重ねたのはその1回だけで終わる展開しか思い浮かばなくて困る。
リッパーが寝たの見届けてから、独りで鼻すすりながら酒飲む傭兵。
リッパーは、それでも別に良くありません?って思ってるけれど、傭兵がダメなんだよな…。
---------
暗殺者×美術学助教
何使って殺してみたいのかを聞くと、やはり刃物ですかね。と助教が答えるので、俺も刃物の方が好きだ。お揃いだな。と嬉しそうに笑う暗殺者。
暗殺者、銃だとノーコンなので肩狙おうとして脳天ぶち抜く。
助教「私の居る方向に向けて、絶対に撃たないで下さいよ」
---------
愛は「贅沢品」だと思ってる傭兵とリッパーの傭リ。
だから、2人揃って荘園に来るまで無縁な物だと思ってる。愛するのも、愛されるのも、そういう感情が育った人間だけが得られるもの。
2人とも、愛の為の感情が欠落してる。
---------
傭兵もリッパーも、荘園を来る前は愛とか知らなくて、傭兵に関しては生きる事への執着が無い状態だった所から、2人の間に歪な愛が生まれてしまって傭兵に生きる事への執着が生まれる傭リが描きたいなぁとぼんやり練ってる。
執着が無い=死にたがりではない。
「自分は、いつ死んでもおかしくは無い人間」と考えている感じ。他人への自己犠牲は、自分への興味の薄さに等しい。
---------
恋人の様な、それにしては互いの事をそこまで知ってる様で知らない関係性の傭リが好き。
今、お互いが関係を持って知ってる事が全てで、過去についても相手が話さない事は知らない感じ。別段聞き出しもしない。今目の前に居る相手が、自分にとっての全てなので。
---------
関係を持つ様になった傭リで、自分がする事でたまに傭兵が嫌悪感を少し表情に出すのが好きでわざとやってケラケラ笑うリッパー。
嫌なら言えば良いのに、と思うと同時にそれが傭兵の愛なのを知っていて、愛情の心地良さも感じている。
貴方のその顔可愛くて好きですよ、と背中に腕を回して、そのままベッドへと2人でなだれ込んでほし。
---------
傭リは、教会で人を殺しまくって、どうする?もう俺等、神様に嫌われたんじゃない?と、死体と血に塗れた聖堂で煙草吸ってほし。
最初から好かれた事なんてありませんよ。というリッパーに、それもそうだなとキスして笑う。
(これはリッパーの為に殺しを行う方の傭兵)
---------
荘園の外に出た傭兵とリッパーが何かの縁の巡り合わせで邂逅するが、互いに記憶が無い上に印象最悪で、避けても腐れ縁なのか何度も顔を合わせてしまい、最終的にリッパーが傭兵の腹にナイフ刺した所でやっと互いに思い出す転生傭リ。
印象最悪なのは、無意識に自分の中の愛する相手と噛み合わなかった影響。
---------
0 notes
Text
☆プロトタイプ版☆ ひとみに映る影シーズン3 第七話「決戦、ワヤン不動」
☆おしらせ☆
今回でひとみS3の無料掲載分は終了となります。物語のエピローグと恒例の追加イラスト、そして次回作情報は電子書籍版の発売をお楽しみに!
☆プロトタイプ版☆
こちらは無料公開のプロトタイプ版となります。
段落とか誤字とか色々とグッチャグチャなのでご了承下さい。
→→→☆書籍版発売までは既刊二巻を要チェック!☆←←←
(シーズン3あらすじ)
謎の悪霊に襲われて身体を乗っ取られた私は、
観世音菩薩様の試練を受けて記憶を取り戻した。
私はファッションモデルの紅一美、
そして数々の悪霊と戦ってきた憤怒の戦士ワヤン不動だ!
ついに宿敵、金剛有明団の本拠地を見つけた私達。
だけどそこで見たものは、悲しくて無情な物語……
全ての笑顔を守るため、いま憤怒の炎が天を衝く!!
pixiv版 (※内容は一緒です。)
དང་པོ་
現実世界に戻ると、空はうっすらと明るくなっていた。光君が霊的タブレットを覗く。
「ふぅ。体感では億年単位の時間旅行も、実際はたった一晩きりの出来事で……ん?」
光君が訝しむ。うん、私もおかしいと思った。だってイナちゃんが空を見て呆然としているから。
「イナちゃん?」
「……ん? あ、二人とも無事ね!? よかた! ワヤン輝影尊(フォドー)と如来が真っ白になって消えちゃたのビックリしたヨ!」
私達の究極フォームがなんか略されちゃってるのは置いといて。やっぱり、さほど如来戦から時間は経っていないみたいだ。塔を登り始めた時から経過した時間を考えると恐らく、今は大晦日の夜。ちょうど年越しの少し前くらいだと思う。今夜は白夜というわけでもない。となると、これは……
「金剛の有明ですよ」
「!」
一同が一斉に空の一点を仰ぐ。そこには歪に大きなダイヤモンドがあしらわれた箒に乗る、一匹の巨猫。
「オモナっ……うそ、その声……」
現れた諸悪の根源を目の当たりにして、イナちゃんは目を見開いた。そうなんだ。人類史を遡った私と光君は既に知っているけど、この猫と……いや。この『人』と私達は、とっくの昔から知り合いだったんだ。
「お久しぶりです。『タナカさん』」
「ええ。ごめんね紅さん……また騙しちゃった」
テレビ湘南のディレクター、タナカ。彼は私の職場関係者として、ずっと行動を共にしてきた男だ。
གཉིས་པ་
佳奈さんと私が旅をする番組、『ドッキリ旅バラエティ したたび』は二〇一一年に始まった。当時は別のディレクターが撮影に同行していたけど、一昨年あたりからタナカさんが二代目ディレクターに就任した。あれは丁度、アンダスキンを倒した直後……そして、初めて光君と出会い大散減と戦う少し前のことだ。
タナカさんはイナちゃんや光君とも面識のある、朗らかな男性だった。でも局の入館証を紛失していて、いつも警備員さんに顔パスしてもらったり、後輩ADさんにゲートに入れてもらっていた。そして局内の誰も彼の下の名前はおろか、『タナカ』の漢字すら覚えていない。彼の人柄故に誰も怪しんでいなかったけど、今考えればかなりミステリアスな人物だった。
「た、タナカD……タナカDだよね!? 本当にタナカD!?」
「にゃはは! 今回はオルチャンガールのパクさんも騙しちゃいましたね。そうです、タナカは仮の姿……僕の本当の名前はロフター。金剛有明団団長、大魔神ロフターユールです」
ロフターは箒から降り、高度三千メートルに浮くこの庭園に立った。彼は山猫のように耳がぴんと上向きの巨猫。改めて同じ目線の高さで見ると、背丈は確かにタナカさんと一緒くらいだ。
「どうです? 皆さん、金剛の有明は絶景でしょう。ああ、下を御覧下さい。もうこの地球上の全人類が同じ光景を見ています」
「え!?」
本当だ。全知全脳の力で下界を見下ろすと、大変な事になっていた。なんと地球上の全人類が失っていた霊感を取り戻している!
「こいつはコトだ! もう計画を!?」
「わはははは! 光君もよぉく耳をすませてみて下さいよぉ。ほら、聞こえるだろ。パニックに陥るバカどもの叫びがね」
―きゃあぁーーっ、お化け! お化けが!! パパぁーママぁー!―
―刑事さん聞いてくれ、あんたの推理は間違ってる! 私を殺したのは息子じゃなくて妻だ!!―
―やっぱり総書記は替え玉だったんじゃねーか! ブチ殺せ!―
地上は空が明るくなった現象などまるで眼中にないほど混乱を極めていた。幾つかの地域では暴動や事故が勃発し、各地の霊能者に力を持った神、精霊、妖怪らが騒動を鎮めようと奔走する。それゆえ多神教の地域ほど治安の悪化は少なく、一神教の地域で特に深刻な事件事故が多発している。
「おいおい、ここまで僕の思い描いていた通りになるとはなぁ。でもご心配なく、地上の皆さん。間もなくあんた方の信じる唯一神が光臨しますからね」
ロフターの持つ魔導書が玉虫色に輝きだす。まさか、全人類……いや、地球上の全生物にアレを見せる気か!?
「待って下さいタナ……ロフター! そんなことしたらどうなるかわかってるんですか!?」
唯一神、すなわち創造主とはこの世の全ての礎。それを少しでも認知した人間は人格がゲシュタルト崩壊して廃人になる。ていうか神をばっちり直視なんかしたら、ヒトどころか殆どの動物の肉体が元素レベルで分解霧散して死ぬ! 地球の自然そのものがハチャメチャに崩壊してしまうんだ!!
「にゃはは、わかってるも何も。金剛の楽園を造るためには必要な事ですから」
「文明や自然を壊してまで目指す楽園って、一体何なんですか!?」
「世界平和ですよッ!」
ロフターの瞳孔がキッと細まり、尻尾と全身の毛が逆立った。
「誰も創造主を崇めない。かといって、誰も創造主を目指さない。資源(リソース)が限られたこの宇宙の中だけで、全てが完結する世界。余計な争いをせずみんなで身の丈に合った共同生活を送りながら、静かに終わりの日を待つ。生き物として……これ以上幸せな暮らしはないでしょう?」
ロフターの握りしめる箒がギリギリと軋んだ。これが、彼の答え。代々この宇宙のために尽力してきたカオスコロルの三代目が、最後に出した答えなのか。
「そ、そんなの……そんなの平和じゃなくて、絶望ていうんだヨ!!」
イナちゃんが目に涙を湛えて叫んだ。
「絶望ですか。上等だよ。バカどもが抱く希望なんて、余計な争いや格差を生む無用の産物なんだから」
魔導書の輝きが増し、下界が段々と静まっていく。みんな空を見ている。金剛の魔術によって、私達のこの会話が世界中に見え始めているんだ。
「どうして拒むんですかい? あんた方は唯一神様が大好きなんでしょう。神のために死ぬのは幸せなことで、神を敬わない人間はいくら殺してもいいんでしょう。おうそれなら見せてやるって言ってるんだよ!!!」
「やめて!!」
輝きが頂点に達し、イナちゃんが飛び出した! 私は……
「!」
「ヒトミ……ちゃん……?」
私は気がつくと、イナちゃんを止めていた。
「どうして!?」
「うわはははは!! まさかワヤン不動が、僕の金剛の思想を理解してくれたんですか!?」
どうして。……どうしてだろう。ただ……
「そのまさか、なんですよね」
「……え?」
意表を突かれたロフターの、魔導書の輝きが一瞬弱まった。
「ロフターの言ってる事、そこまで間違ってないと思うんです。もしかしたら将来、人類がこの宇宙の垣根を越えられる時も来るかもしれないけど。少なくとも今の文明レベルでは、外とは関わらないでみんなで手を取り合って生きるのが最善……じゃないですかね?」
「……ほ、ほほぉ。意外ですなぁ、脳筋で小心者の紅さんが、冷静に僕の話を聞いてくれていたなんて」
「一言余計だ三角眉毛」
うん。ちゃんと考えて���実際、彼は思想的にはおかしな事は言っていない。だって現に最近の人類は、資源を守るために環境保護を始めたり、多様性を認めようとかなんとか言い出しているわけだし。どんな物かもわからない神様に祈るより、ずっと現実的に生き始めている。ロフターはそんな人類の最後の甘えである『創造主』という幻想を、この世界から取り払ってしまいたいだけなんだ。
「にゃはははは! なぁんだ、じゃあ僕達も不要な争いをせずに済むわけですなあ! では改めて……ぐッ!?」
ヴァンッ! 再び魔導書に力を込めようとしたロフターの左手に、高熱のエネルギー塊が爆ぜた。高圧の力を帯びていた魔導書は瞬く間に炎上!
「そんなわけないだろ外道が。お前は予定通り滅ぼすし、この世界に創造主は顕現させない」
「なんだと!?」
当たり前だ。それとこれとは話が違う。私は光君と目配せし、合体(ヤブユム)の構えを取る。
「あんたは野望のために魂を奪いすぎた。それが平和のためだったなど関係ねぇ、罪は罪できちんと償わなせにゃ!」
「喜べ。お前を完膚なきまでにブチのめした後で、この星に生きる全ての衆生と共に金剛の有明を迎えてやろう」
「くっ……」
ロフターは煌々と燃える魔導書を抱きしめ、表紙に埋め込まれたダイヤモンドをむしり取った。それを胸の中にグッと押し込むと、彼の体はたちまち巨大化していく。
「不動明王らしい、いえ、実に紅さん方らしい答えですな。こりゃいくら腹割って話したところで無駄ってわけだ」
私はその隙にテレパシーでカスプリアさんを呼び、イナちゃんと共に空を元に戻すよう依頼した。そして四本に伸ばした腕に武器を構える。
「カハァハハハハ!! 私がおめおめ見逃すとでも思ったか、ド外道が! これ以上は誰一人殺させない。神影繰り(ワヤン・クリ)の時間だ!」
ワヤン不動輝影尊(フォトンシャドウフォーム)対大魔神ロフターユール! 地球全土の存亡を賭けた合戦の火蓋は切って落とされた!
གསུམ་པ་
巨大化した大魔神はローブを広げ、さながら空に浮かぶサーカステントの様相。その帳にルーン紋様が浮かび上がると、強烈な突風が噴出! 周囲の雨雲と雹を取り込み大嵐の如く私に迫る。瞬間、私の中で仲間との絆がフラッシュバック!
―私が初めて人のために影法師の力を使うきっかけになった親友、リナ。金剛を裏切り私に修行をつけてくれた和尚様や、地元の神々。人生で初めて悪霊に立ち向かった時の、勇気の記憶―
私は赤外光を纏った灼熱のキョンジャクを高速回転させ天高く飛翔、そのまま遠心力で嵐を捕えた。
「ァアブダクショォン!」
それを大魔神へ腕力任せにブン投げ返す! ズドオオォン!! さながらジェットエンジンを直に受けたような衝撃音を立てて大魔神の帳が翻り、ロフターの顔が苦痛に歪んだ。しかし間髪入れず次のルーンが浮き上がる。
オォ……オォォォ……玉虫色の霧が立ち込め、木枯らしか亡霊の呻き声のような風音がそこかしこから上がる。するとどこからともなく宙に浮かぶ亡布録の大群が出現した! 瞬間、私の中で仲間との絆がフラッシュバック!
―抗う事を決意したイナちゃん。そしてNICや平良鴨証券の人々。力を貸してくれるみんなと共に闘った、友情の記憶―
「影影無窮!」
襲い来る大群に負けない、大量の影法師。その全員が燃え盛る龍王剣を掲げて悪を薙ぎ払う! そして全軍で大魔神に突撃ィィィ!!!
「カハァーーーッハハハハァーーー!!!!」
ダカダカダカダズダダダァァァン!! 大魔神の六割が灰燼と化した!
「ぎゃはあははははは! うにゃはははははは!」
絶叫とも高笑いとも取れる声を上げ、大魔神は目や口から黒いタールのような血涙を噴き出しながら更なるルーンを滲出! すると今度は大気圧がグヮンと急変し、周囲一帯が吐き気がするような生温い空気に包まれた。
……マアァァァウァァ……マバアァァァ……
無数に響く、飢えた怪物の声。そして中空から蠢き出る数多の菌脚。瞬間、私の中で仲間との絆がフラッシュバック!
―見知らぬ土地、見知らぬライバル。連綿と業を受け継ぐ祟り神。人生を奪われ続けて化け物になってしまった少女。でも最後は皆で手を取り合い呪いを破った、団結の記憶―
「救済せにゃ!」
��天高くティグクを掲げると共に、私は灼熱に輝く太陽となる! 全ての穢れは瞬く間に干上がり、色の飛んだ世界で唯一つくっきりと存在する明王の影が斧を振り下ろした!
「ニャアアアアアアアァァァ!!!」
ダガアァァァン!! 大魔神の帳が崩壊し、巨猫のシルエットが真っ二つに割れた! そして世界に色が戻ると……
「!?」
中空に一瞬ルーンが浮かんだ次の瞬間、そこは突如カイラス山の岩窟になっていた。私は両腕を鎖で大岩に縛られ、足元を炎で炙られている。なんだ、今更悪夢攻撃なんて……
「ヒッ」
違う!この炎は、かつて私が経験したどんな憎しみや悲しみとも違う。まるで地球史が始まって以来、世界中で起きた死という結果のみを集めて燻したような、恐ろしく冷たい炎。その圧倒的な絶望に晒された私の心臓はすくみあがり、だんだん体が動かなくなる……
༼ ヌンッ! ༽
「ドマル!?」
すると突然、私から強引に分離したドマルが自らの心臓に腕を突っ込んだ!
༼ こっ、これは、拙僧が抱えていたトラウマだ……今ここで拙僧が消えれば、術も解ける ༽
「だ、ダメだ! この心臓を失ったら、ドマルは……」
༼ ふ。もともと拙僧は、あなたの中に僅かに残った残滓に過ぎぬ。今更自我を保とうなどとは、思わない……よッ! ༽
ドマルは私との接点だった悪魔の心臓から自分をメリメリと剥がし、このまま逝去するつもりだ! 確かに彼は既に引退を宣言した仏。だけど、何もこんなところでお別れになるなんて!
༼ よいか? 悪夢の術が消えたら、あなたの足元で燃える苦の本質を見ろ。そしてあの猫の声に耳を傾けるんだ…… ༽
「ちょっと待ってよ! あなただって一緒に戦ってきた仲間じゃない! ドマル……」
༼ 一美 ༽
「!」
彼は最後に振り返ると、卑怯なほど穏やかな微笑みで私を見つめて言った。
༼ 行くのです ༽
心臓に貼りついていた何かの線維が千切れる。抜苦与楽、体がふわっと軽くなったような感覚の後……私の前世は、邪尊ドマル・イダムは、悪夢と共に涅槃(ムナル)へと消え去った。
བཞི་པ་
闇があった。広さのわからない闇。まるで棺桶に入れられたような、あるいはだだっ広い宇宙に放り出されたような掴みどころのない空間。そこに一人の人影が佇んでいた。
「あなたは……」
その人は、とげとげロン毛……いや、ただのウェーブがかったロングヘアーの男性だ。かの有名な、茨の冠を被った神の子によく似た雰囲気の人。私は彼に近付くと、再び心臓が凍てつくような絶望の感覚を覚えた。
「あ……悪魔」
たった今逝去した前世の記憶を引き継いだ私は勘付いた。この人は私の心臓のドナー。砂漠で行き倒れになっていた、例の悪魔だ。
人間を堕落させる存在として忌み嫌われ、死ぬ事も消える事もできない……彼が仏典にそう書かれた理由がようやく理解できた。彼が本当に望んでいたのは、『安らかな滅び』。苦痛も暴力もない、穏やかな終わりだったんだ。
―いけェーーっ! ワヤン不動ーーー!―
―負けるなーー、立ち上がれーー、ワヤン不動ーーー!!―
どこかから声が聞こえる。何十人、何百人、何億人……最初は共に戦った仲間達の声。私を応援してくれる友達や邪尊教信者達の声。それどころか、一度も出会った事がない人達の声も、仏教とはまるで違う信仰を持つ人々の声も。この地球の命を守るため、身近な大切な人を守るため、あらゆる垣根を越えた大勢の衆生が私を呼んでいる! そして、
―……たすけて……―
「!」
もう一つ。私の目の前で、か細く泣く猫の声。
―……僕はただ、グリーダと静かに暮らせる楽園を作りたかっただけなんです……―
―……そのためにたくさんの命を奪いました。こうするしかなかった。だけど、グリーダはもういない……僕は償う事も、死ぬ事もできない……―
本来なら自分の感情すら自由自在に制御できる究極の神の子が、自己矛盾と絶望に苦しみ喘ぐ声。……大丈夫、ちゃんとわかります。だって私の中にも、悪魔の心臓(カオスコロル)があるのだから。
―……助けて……ワヤン不動……―
薄暗い世界に、希望が満ちていく。光は影を強く形取り、救いを求める声に伸びていく。
―ワヤン不動ーーーー!!!―
……さあ。滅ぼしてくれる。
ལྔ་པ་
「ミィ……ミィ……」
極彩色の宇宙に輝く満点の星。地平線を照らす金剛の有明。そこに浮かび上がった一匹の小さな子猫は、三角帽子の魔女と共に箒で空へ消えていった。
「大丈夫です。お空に創造主はもう見えないヨ」
「地上の混乱も順次収めていきますの。弊社の財力と国際社会とのパイプを利用すれば、お正月中に済むでしょう」
イナちゃんとカスプリアさんのおかげで地球の危機は去り、ここには奇跡のような明るい空だけが残っている。
「……あ」
ふと、全知全脳の力が感知した。たった今、グリニッジ標準時は丁度〇時となった。
「この地球が新年を迎えました。全ての命ある皆さん、あけましておめでとうございます」
1 note
·
View note
Text

------------------------------------------------------
『癒し系彼女の束縛レシピ』
------------------------------------------------------
「みさきちゃん……」
近づくふたりの距離。
触れ合う唇。
熱い吐息。
舌を伸ばせば、素直に応えて絡めてくる。
ごく普通の大学生の、ごく普通のカップルの、ごく普通の夜の甘やかなひととき。
――ガチャン。
手首に違和感。
サラサラと鎖の音。
「みさきちゃん、コレ……今日も?」
「もちろんだよ」
目の前の彼女は、ふんわりと和やかな天使の微笑みを浮かべて言った。
「私、大事なものはちゃんと繋ぎ止めておきたいタイプなの」
(タイプというか、性癖じゃないかな……?)
内心で突っ込みつつも、みさきちゃんに嫌われたくない俺は、両手首にかけられたおもちゃの手錠を受け入れた。
講義が終わって昼休み。
恋人と待ち合わせて、大学構内のカフェで昼食を摂る。
「千歳くん、ご飯粒付いてるよ」
「え、どこ?」
「ふふっ、ほっぺたに。取ってあげるね」
みさきちゃんは自然な仕草で俺に近づき、取ったご飯粒を自分の口元へと持って行く。
「……えへへ、もらっちゃった」
にっこり微笑む顔が可愛い。
みさきちゃんと付き合い始めて3か月。
優しくて可愛くて、完璧な女の子。
日増しに彼女を好きになるばかりだ。
(だからこそ……)
彼女の性癖だけが引っかかる。
初めてみさきちゃんとセックスをしたのは、付き合って2週間目のデートの日だった。
大学がある駅から数駅離れた町の、駅から徒歩10分の場所にあるアパートの205号室。そこがみさきちゃんの部屋だ。
男子校出身の俺にとって、みさきちゃんは人生で初めてできた恋人。
そんな彼女の部屋に招かれ、手料理をごちそうになって、順番に風呂に入って……。
まるで漫画か何かのように完璧な流れ。
何度もシミュレーションしてきた初体験の段取り。
清潔な身体で、ベッドに並んで座って、それから――。
「千歳くん……手、貸して?」
無防備なパジャマ姿で、みさきちゃんが言った。
全身から石けんの良い匂いがする。
鼓動がうるさくて耳が痛い。
興奮と緊張で頭が上手く回らない。
みさきちゃんの言う通りに手を差し出すと、「両手だよ?」と可愛らしく言われる。
両手を差し出すと、みさきちゃんの小さくて可愛らしい手が握って��る。
「ふふっ、手、熱いね」
ふにゃりと微笑むみさきちゃんが可愛い。
みさきちゃんが可愛いということしか、もう考えられない。
「千歳くん、目、つむって?」
「う、うん……」
声が掠れたのが恥ずかしくて、大げさなくらいぎゅっと目を瞑る。
視界が真っ暗になると、鼓動の大きさが余計気になる。
ドクドクと全身が心臓になったかのように鳴っている。
ドクドク、ドクドク、ドクドク、ドクドク――ガチャッ――ドクドク、ドクドク、ドクドク
(……ん?)
何か変な音が混ざった気がする。
興奮しすぎて心臓が壊れたのかもしれない。
薄目を開けようとした瞬間、不意に押されて背中側へと倒れた。
「えっ!?」
思わず目を開けたその時、また『ガチャッ』と音が聞こえた。
「ふふっ、まだ目、開けていいって言ってないのに。わるいこ」
みさきちゃんは、目を閉じる前と同じように可愛らしく笑っていた。
「ご……ごめん?」
よく分からないまま謝った。
「いいよ。次からは、私との約束ちゃんと守ってね」
みさきちゃんがにっこり笑う。
可愛い。
可愛いんだけど……さっきまでとはちょっと違う、ような……。
「あのさ、みさきちゃん」
「なあに?」
「なんで俺の手に手錠がかかってるの?」
目を開けてみれば『ガチャッ』の原因は一目瞭然だった。
俺の手に手錠がかけられていた。しかも鎖はベッドのヘッドボード側のパイプに通されている。
簡単に言えば、バンザイするように両腕を上にあげた状態で寝かされ、手錠はベッドにくくられている――拘束状態にされている。
誰に?
他の可能性は一切考えられないにも関わらず、信じられなかった。
「私、こうしておかないと安心できないの」
みさきちゃんは、どこか切なそうな、儚げな表情でそう言った。
「お……俺、優しくするよ。初めてだけど、みさきちゃんを傷つけるようなことはしないから、安心して」
「うん、それは大丈夫。千歳くんは優しい人だって、知ってるから」
「それなら……」
「うーん、どう言ったらいいのかな」
みさきちゃんは、小さな手を顎に当てて小首を傾げた。
仕草がいちいち可愛い。可愛いからこそ、拘束状態の異常さが際立つ。
「あっ、そうだ」
可愛らしい悩み顔が、可愛らしい笑顔へと変わる。
くるくる変わる表情もみさきちゃんの魅力のひとつだ。
そんな愛らしいみさきちゃんは、愛らしい声でこう言った。
「あなたが大切だから、ちゃんと閉じ込めておきたいの」
それが自然の理だとでもいうように言い切った。
「今夜は帰さないから……楽しい夜にしようね、千歳くん」
そしてそのままされるがまま、騎乗位で童貞を卒業した。
みさきちゃんもたぶん処女だったと思う。少し痛がっていたし、血も出ていた。
両手を拘束されたままだったから、抱きしめて慰めることすらできなかったけど……。
「千歳くん? ぼんやりして、どうしたの?」
気付けば、みさきちゃんが不安そうな顔でこちらを見ていた。
「最近ぼんやりしてることが多いけど……もしかして、悩み事?」
「ごめん、違うよ……みさきちゃんは可愛いなって思って見惚れてた」
「ふぇ……っ!?」
色白の顔が真っ赤に染まる。困りつつもまんざらでもない感じの表情で、みさきちゃんが身もだえる。
「もうっ、すぐそうやってからかうんだから」
「からかってないよ、本気だって」
みさきちゃんは可愛い。
大事にしたい。
初めての彼女だし。
初めての彼女だから、俺の認識が間違っているのかもしれないし。
拘束プレイなんて、みんな普通にやってる当たり前の行為なのかもしれないし。
「千歳くん、またぼーっとしてる」
「ああ、ごめん。バイト忙しいからかな」
「そうなの……?」
みさきちゃんが距離を詰めてくる。俺の腕をぎゅっと抱いて、うるうるした瞳で見上げてくる。
「なんでも相談してね。だって私、あなたの彼女なんだから」
周囲からの羨望の眼差しを感じる。
誰が見たってみさきちゃんは可愛い。そのうえ健気だ。彼氏冥利に尽きる。
「ありがとう、みさきちゃん」
だからこそ、俺も彼女にふさわしい彼氏にならないと。
……とはいえ、俺が抱えている悩みをみさきちゃんに打ち明けるわけにはいかないのが現状だ。
夜、自室でパソコンの画面を食い入るように見つめつつ、心の中でみさきちゃんに謝った。
ぼんやりしている原因は寝不足だし、寝不足の原因は調べものをしているからだし、調べものの内容はみさきちゃんにまつわることだからだ。
つまり俺は近ごろ熱心に『SMプレイ』について勉強しているのである。
みさきちゃんは拘束プレイが好き。ということは、おそらくSMプレイが好きだということだ。しかもみさきちゃんがS側。女王様側。女性上位プレイ派。
しょっぱなから手錠拘束で来たのだから、本当はきっと相当濃いプレイをお望みなんだろう。調べれば調べるほど自信がなくなってくる。
(ロウソク……は本当は熱くないらしいし、テープ拘束も静電気で接着するテープだから見た目よりエグくないらしい……でもスパンキングは普通に痛そうだ。磔とかも怖いし……ボディピアスとか字面だけで震える……)
殴り合いのケンカとは無縁に生きて来たし、今までで一番痛かったのは親知らずを抜いた時の痛みくらいなものだ。ネットで少し検索しただけであれよあれよと出てくるSMプレイの上澄みにすら恐怖を覚えてしまうほど、俺には痛みの耐性が無い。
今後、拘束からさらにプレイが発展していった時、俺はみさきちゃんについていけるだろうか?
平凡なプレイを望む俺を見限り、別れを告げられたらどうしよう。
「せめて、求められた時にただ恐怖に震えるだけじゃなくて……代替案を提案できるくらいには知識を付けておかないとな」
それが俺にできる精一杯だ。それ以上のことはいざ求められてみないことには分からない。
決意を新たにネットサーフィンを続けていると、インターフォンが鳴った。
「なんか通販頼んでたっけ?」
首を傾げる。
最近SMプレイ用の本やグッズをいくつか取り寄せてはいるが、今日配達予定の荷物は無いはずだ。すると勧誘か何かだろうか。こんな夜に? 時計を見ると21時を少し過ぎたところだった。
無視を決め込もうと思っていると、続けざまにインターフォンが鳴らされた。
「なんだ……?」
首を傾げつつ玄関へ向かう。のぞき窓から外を見ると、みさきちゃんが立っていた。
「みさきちゃん、こんな時間にどうしたの!?」
驚きのあまり扉を開けると同時に尋ねていた。
「ごめんね、突然……あがってもいいかな?」
「あ、ああ……うん」
何気なさを装って返事をしつつ、室内をザッと見渡した。近ごろ通販で買い集めていたSMプレイの資料はクローゼットの中だ。洗ったまま畳んでいない服はちらほらあるが、汚れ物は散らかしていない。あとは――SMプレイについて検索したままのパソコンが点いたままだった!
「あれ、千歳くん何か作業してたの?」
みさきちゃんがパソコンに近づく。
「いや、大したことじゃないから!」
大急ぎでパソコンのコンセントを引き抜いた。
「……そういう電源の切り方して大丈夫?」
「普通はだめだけど大丈夫……」
心配そうなみさきちゃんに対して、ただ怪しいだけの返答をしてしまう。
しょっぱなから大失敗だ。
「と……とりあえず、何か飲む? たしか冷蔵庫にペットボトルが何本か入ってたはず……」
なんとか気持ちを切り替えようと、一旦キッチンへ避難する。水のペットボトルしかない。仕方なく、それを持って部屋に戻った。
「ごめん、何も無いから近くのコンビニでなんか買ってくるよ。お腹は空いて……」
言いかけて固まった。
みさきちゃんは、SM資料の数々を前にして肩を震わせていた。
「ちょっ!? なんでそれを!? 隠しておいたのに……!」
「ごめんね、勝手に見て……でも、ベッドの近くに怪しい伝票の段ボールがあったから、気になっちゃって……」
「怪しい伝票?」
みさきちゃんの傍らにある段ボール箱へと目を向ける。送り主は「大人の」……。たしかに、こんな伝票をみたら怪しむのも無理はない。
「やっぱり……千歳くん、他に気になる子ができたんだ」
「え!?」
「最近、私と一緒にいてもぼんやりしてることが多かったでしょう? だから、他に好きな子ができたんじゃないかなって、うすうす思ってたんだ……」
みさきちゃんは、大きな瞳いっぱいに涙を溜めていた。
「千歳くんは、その……こういうエッチをさせてくれる女の子がいいんだね」
うつむいた視線の先に、SM系の雑誌があった。ボンテージ姿の女性が表紙を飾り、過激な煽り文が躍っている。
「誤解だよ! 寝不足なのは、たしかにこういうのを見てたからだけど……みさきちゃんの他に気になる子なんていないから! 俺、本当にみさきちゃんが好きなんだ!」
うつむいたみさきちゃんの肩を掴み、なんとか目を合わせた。
「千歳くん……」
みさきちゃんは目を瞬かせて、表情を少し明るくした。浮気なんてしていないのは分かってくれたようだった。けれど、すぐにまた表情が曇る。
「で、でも、少なくとも私とのエッチに満足してないんだよね……? だって、こういうおもちゃとか本とか買ってるわけだし……」
「違うちがう、逆だよ」
「え……?」
「みさきちゃんが、俺とのエッチに満足できなくなる日が来るんじゃないかって不安で……SMプレイについて予習してたんだ」
「えぇ……!?」
みるみるうちに、みさきちゃんの顔が赤くなっていく。
「ど、どういうこと? 私、そんなに……あの、エッチな子に見えてた……!?」
「いや、エッチというか……その、性癖が」
「せ、性癖!?」
これ以上ないくらい真っ赤になっている。ここまでいっぱいいっぱいになっているみさきちゃんを見るのは初めてだった。こんな場合にどうかと思うけれど、みさきちゃんは混乱している最中でもめちゃくちゃ可愛い。
とはいえ見惚れっぱなしでいるわけにもいかないので、俺はこれまでの経緯を説明した。
「つ……つまり、私が手錠で千歳くんを拘束してからエッチしてたから、SMプレイ好きだと思って……私の趣味に合わせようとしてくれたってことなんだね」
「理解が早くて助かるよ」
みさきちゃんは、少し赤みの引いた顔をぱたぱたと手で扇いでいる。
先ほどまでよりは、だいぶ落ち着いてきたようだった。
「えっと……千歳くんが事情を話してくれたから、私もちゃんと説明しないとだめだよね」
決意するようにひとりごちて、みさきちゃんは俺に向き直った。つられて俺も居住まいを正す。
「心配させちゃってごめんね、千歳くん。でも大丈夫だよ」
向い合せの俺の手を、みさきちゃんがギュッと握りしめて来る。
「私はただ、拘束したいだけだから」
「……うん?」
「その……サドとかマゾとか、プレイとか、関係無いんだ。私はただ、千歳くんを縛りたいだけなの」
一点の曇りもない瞳でそう言い切るみさきちゃん。
対する俺は曇りまくりの顔をしていることだろう。彼女の言っていることがよく理解できていない。
「えっと……つまりみさきちゃんは、緊縛は芸術派の��ってこと……?」
「あはは、違うよぉ! そういう高尚な話でもなくって」
緊縛趣味が高尚かどうかは分からないけれど、みさきちゃんは謙遜するような照れ笑いを浮かべた。
「私、昔犬を飼ってたの。柴犬でね、ポチっていう名前をつけて、すごくすごく可愛がってたんだ」
みさきちゃんが柴犬を可愛がっている姿を想像した。ほのぼのとした幸せな光景は容易に想像することができた。心優しいみさきちゃんのことだ、きっと言葉で言い表せないほど可愛がっていたに違いない。
「でもね、ある日脱走しちゃったの。お散歩中に首輪が外れて、パニックになって……色々手を尽くしたけど見つからなかったんだ」
その時の悲しみを思い出したのか、みさきちゃんは涙声になっていた。
「私……ポチの事があってから、大切なものは自分の側に縛り付けておかないと安心できなくなっちゃったの」
悲しい思いでの延長線に、唐突に性癖の話が現れて度肝を抜かれた。
「な、なるほど?」
��んとか相槌を絞り出す。
「手錠とか、首輪とか……とにかく私のそばに縛り付けて、拘束しておかないと安心できなくて……安心って信頼と同じでしょ? 安心して信頼できないと、本当の意味で好きにはなれないよね?」
「そうだね。たしかに」
恋人になるということは、より深い信頼関係を築いていくということ。
そういう話なら、俺にも理解できる。
嫉妬したり、浮気を禁じたり、そういうのも拘束の一種と考えれば一般的な感覚とそう変わらない気もしてくる――が、物理的に縛り付けるという発想に結び付けるのはさすがに厳しい気もする。
「今まで、告白してくれた人もいたんだけど……付き合うなら縛らせてほしい、とか、手錠を付けたいって言うと怖がられちゃって……」
「そう、だったんだ」
自分が告白した時のことを思い返した。そんな話はされなかったはずだ。されていたら、初エッチの時にあそこまで衝撃を受けなかったはずだし。
俺が疑問を抱いているのに気付いて、みさきちゃんはもじもじと視線をさまよわせた。
「千歳くんはポチに似てるから、絶対に絶対に手放したくなくて……黙ってお付き合いを始めちゃったの。だまし討ちみたいな形でエッチまでして、ごめんね」
「いや、それは全然いいんだけど」
「えっ、いいの……?」
なぜかみさきちゃんの方が驚いている様子だった。
「さっきも言ったけど、俺はみさきちゃんが好きだし、みさきちゃん以外の恋人なんて考えられない。だから付き合えて嬉しいし……手錠の理由も分かったから、十分だよ。みさきちゃんが誤る必要なんてない」
「千歳くん……ありがとう」
みさきちゃんが抱きついてくる。
ふわりと甘い香りがする。
華奢な身体だ。こちらから抱きしめ返したら折れてしまいそうなほど。
あどけなくて庇護欲を誘うみさきちゃんが、まさか縛り付けたい側の人間だとは思ってもみなかったけれど……俺の中のイメージなんて、現実のみさきちゃんの可憐さに比べれば些末なことだった。
「みさきちゃんは、ポチのことがトラウマになっていて、忘れられないんだよね」
「うん……」
「分かった。それなら俺……ポチの代わりになるよ!」
恋人であると同時に、ペットになってもいい。それくらいの覚悟はできていた。
「あ、そういうのは大丈夫」
「そ、そっかぁ……」
俺の覚悟はあっさりと流された。
「ポチはポチ、千歳くんは千歳くんだもん。それはちゃんと分かってるよ」
みさきちゃんは、俺の胸板に頭を擦り付けた。サラサラの髪が、細い肩からこぼれる。
「あなたは私の大切な彼氏さんだもん。誰の代わりでもないんだよ」
「みさきちゃん……」
今度は俺の方が感激する番だった。
気持ちが通じ合っている。
好きな人が自分のことを好きでいてくれる奇跡。
幸せだ。
多幸感に浸っている俺の顔を、みさきちゃんの可愛らしい笑顔が覗き込んでくる。
「ただね、私は大切なものを二度と失いたくないの。だから……」
――カシャン。
首元で金属音。
冷たい革の感触。
次いで圧迫感。
「え、これ……」
「首輪だよ。あ、もちろん人間用のね? いつか千歳くんに付けたいと思って、持ち歩いてたの」
「そ、そうなんだ……」
みさきちゃんの可愛らしいカバンにそんな重たい秘密が隠されていたなんて全然知らなかった。
新事実に戸惑う俺の頭を、みさきちゃんが優しく撫でた。
「私だけの彼氏くんっていう証、受け取ってくれるかな?」
俺にとってみさきちゃんは初めての彼女だ。
普通なんて分からない。
他の愛の形なんて知らない。
だから、迷う余地も無かった。
首輪以外の服を脱ぎ、みさきちゃんの裸身と向き合う。
首輪をしたということは、今日はとうとう手錠をせずにエッチできるかもしれない。少しワクワクしてしまう。
「せっかく千歳くんが色々買いそろえてくれてるし、一緒に使ってみる?」
いざ抱きしめ合おうという瞬間、みさきちゃんがにっこり笑って言った。
「別に、活用しようとしなくてもいいんだよ。みさきちゃん、SMには興味なかったんだって分かったし」
「でも、せっかく買ってくれたものだから……」
そう言って、迷わず『緊縛入門第1巻』と赤い縄を手にした。
「この本に緊縛のやり方載ってるみたいだし、今日はこれを試してみよう?」
みさきちゃんはちょっとうきうきしている。いや、わりとあからさまに興奮している。明らかに興味津々の様子だ。
「緊縛って高尚そうで私にはできないって思ってたけど……千歳くんが協力してくれるなら、頑張れそう」
緊縛か高尚かどうかはおいておいて、彼女がこんなにキラキラした目をしていたら反対なんてできるわけがなかった。
「千歳くん、ベッドの上に座って?」
首輪に指を差し込んで、軽く引っ張られる。
意思とは関係なく、まず息苦しさで反射的に身体が動いてしまう。
「…………」
俺を見るみさきちゃんの目は、ゾッとするほど澄んでいる。
それがどうしようもな綺麗で、見惚れてしまう。
「分かった」
不思議な強制力に導かれるまま、頷いていた。
首輪を軽く引く、その些細な動作で、俺たちの関係がはっきり変化したのが分かった。
「ふふ……いい子だね、千歳くん」
みさきちゃんは蕩けるように甘い声で言って、俺の頭を撫でる。
「この本みたいに、両脚を伸ばして座ってね」
みさきちゃんに言われるまま本と同じ体勢を取ると、みさきちゃんが俺の脚をまたいできた。尻をついて座っている俺を、膝立ちのみさきちゃんが見下ろしている。彼女の手には真っ赤なロープがある。
「これから、この縄で千歳くんを縛るんだよ」
みさきちゃんは縄肌を優しく撫でた。
「初めてだからドキドキするね。でも、絶対上手に縛ってあげる。千歳くんが私のものなんだって、ちゃんと分かるように……」
天使のような微笑みに、血のように赤い縄は不釣り合いに見えた。けれどなぜか、その不均衡が強烈なまでに美しく見える。
まるで彼女の前にかしずくのが、人生最大の喜びであるかのように――無意識のうちに、身体が歓喜に震えてしまう。
「両手を後ろに回して組んでくれる?」
「うん」
手を後ろに回し、右手で左肘を、左手で右肘を持つように組む。
みさきちゃんは俺の後ろに回って組み合わせを微調整して、「上手だね」と褒めてくれた。
「縄を通すね」
脇から、少し冷たい感触が入ってきた。とうとう縄が腕に通されたのだと分かった瞬間、背中がゾクゾクと震えた。
シュル、シュル……と縄が擦れる音がする。肌を縄が撫でていく。
「ぁ……っ!」
腕に巻かれた縄が、キュッと絞められた。
「痛い?」
「い、いや、痛くはないよ」
「そう、良かった」
少し腕をもぞつかせてみると、両手首のあたりに結び目が来ていた。後ろ手にしっかりと結び付けられているということだ。
「ふふ……動けないよね」
みさきちゃんがうっとりと言う。耳元で囁きながら、結び目を指で弄んでいる。
彼女が喜んでいる。その事実だけで、どうしようもなく身体が昂った。
「もう少しだけ、我慢していてね」
縄が二の腕の上に通され、正面へと回って来た。二周して、再び後ろでキュッと締められる。
「これね、『後手胸縄縛り』っていうみたい」
みさきちゃんは俺の後ろから身体を密着させ、正面に回った縄を指でなぞった。
乳首の少し上と少し下に縄が通っている。なんだか少し間抜けな光景で、みさきちゃんに見られるのが恥ずかしい。
「でも、女性用の縛り方とかなんじゃないかな? 胸があったら映える気がするけど……」
乳房を上下の縄で搾って強調する状態だったら、見た目にも美しい気がする。男の胸板を上下に絞ったところで、ただ乳首がぽつねんとあるだけで貧相だ。
「そんなことないよ。千歳くん、とっても素敵だよ」
耳元でみさきちゃんが囁く。
「それに……ココを弄ると、男の子でも女の子みたいになっちゃうんだって」
縄をなぞっていた指が、乳首に触れた。
「ッ……!?」
指の腹で、乳輪をくるくると撫でまわしてくる。
「気持ちいい……?」
「わ、分からないな……くすぐったいけど……」
「そっかぁ……じゃあ、もうちょっと弄ってみようね」
上下に通した縄で区切られた範囲を、さわさわと撫でる。乳輪よりも外側部分を優しく撫でていたかと思えば、乳首のあたりをぎゅっと指で押し込んでくる。
華奢な指で乳首をぐりぐりと押し込まれると、その反動か乳首がむくっと勃ちあがった。
「ぁは……乳首、おっきしちゃったねぇ……?」
耳元を熱っぽい吐息がくすぐった。
ピンと勃った乳首をわざと避けるように、その周囲ばかりを撫で、擦ってくる。
「身体、汗ばんできたみたい……肌が少し赤らんできて……縄に映えて、すっごくエッチ……自分でも、分かるよね……?」
ひそひそと、耳元で囁き続けられる。耳朶が敏感になってきて、みさきちゃんの呼吸ひとつでも身体が震えてしまう。
「乳首、触ってほしそうに一生懸命膨らんでるね……? なんだか可愛い……ふふっ」
「み……みさきちゃん……そこも……」
「そこ? なぁに? もしかして……おねだり、かな?」
どこか期待するような声。
優しく導くような囁き。
身じろぎすると、首輪がカチャリと音を立てた。
その音を聞いたとたん、頭の中で何かのスイッチが切り替わる感覚がした。
「乳首も……乳首も、触ってほしいんだ、みさきちゃんに……っ」
くすぐったいだけだと抑えこんでいた性感が、一気に膨れ上がったように感じた。
みさきちゃんの手も、吐息も、気持ちいい。
だからもっとしてほ���い。
そんな感情が、堰を切ったように湧き上がってくる。
「くすっ……いいよ。上手におねだりできたからぁ……いっぱい触ってあげるね」
不意に、みさきちゃんの指が俺の乳首を摘まんだ。
ためらいなく、強く、ぐりぐりと指の腹で押しつぶしてくる。
「ぉあっ……!? あ……待って、みさきちゃん……っ!」
「グリグリ……ぎゅーって……乳首弄ってあげる……これ、気持ちいいでしょ……?」
指先でピンと払われる。ピン、ピン、ピン……とリズミカルに弾かれ、乳輪ごと押し込むようにぎゅっと押さえつけられる。
「ぅ、あ……っ」
無意識のうちに声が出ている。
強めに弄られた乳首は真っ赤に腫れ、乳輪ごとぷっくりと隆起していた。
「乳首いじめられるの、気持ちいいよねぇ……?」
みさきちゃんは、唇を耳朶に押し付けるようにしながら囁いてくる。
「だって私、ちゃんと気付いてるよ? おちんちん、さっきから先走りでドロッドロになってるの……」
「……っ!!」
彼女の言う通りだった。
まだ少しも触れていないペニスはパンパンに勃起して、鈴口からダラダラとカウパーを垂らしている。
亀頭は物欲しげにぱくぱくと喘ぎ、腫れたように赤く膨らんでいた。
「乳首でいっぱい気持ちよくなっちゃってるね……? ふふっ……千歳くんのおっぱい、女の子になっちゃったね……?」
両手で乳首を摘まみ、くにくにと揉みしだいてくる。強めに引っ張られると、それだけでペニスがピクンと反応した。
みさきちゃんはペニスの露骨な反応を見て、嬉しそうな息を漏らす。
「ふふ……そろそろ、おちんちんもいい子いい子してあげないとね」
みさきちゃんは立ち上がり、俺の前へと回った。縄で縛る前のように、俺の脚をまたいで膝立ちになる。
「いっぱい頑張ったご褒美だよ……」
みさきちゃんは、細い指を肉丘に添えた。軽く広げると、クチュリという音と共に濡れそぼった粘膜が露わになる。
濃いピンク色に充血した秘部は、すでに過剰なほど愛液を滴らせていた。
「一緒に気持ちよくなろうね」
みさきちゃんは、俺の上半身を抱きしめた。そしてゆっくりと腰を下ろしていく。
「はぁ……ぁ……おちんちん、入ってくるよぉ……」
焦れるほど時間をかけて、肉茎が膣内に埋まっていく。
愛液が竿を伝い落ちていく、そのひと筋ひと筋の感覚さえ冴え冴えと分かるほどだ。
「ふふ……とってもエッチな顔してる……早くおまんこで気持ちよくなりたいんだね……?」
心底嬉しそうに、みさきちゃんが言う。
「乳首でいっぱい感じられるようになったご褒美だけど…………私を不安にさせたお仕置きもしないといけないから……千歳くんは腰動かしちゃダメだよ」
「え……!?」
「くす……っ、そんなに切なそうな顔しないで。私が、ちゃぁんと気持ち良くしてあげるから……」
とうとう肉棒全てがみさきちゃんの膣内に埋まりこんだ。
「はぁ……はぁっ……ふふ……おちんちん、熱くて気持ちいい……」
膣肉がペニスに絡みつき、優しく締め付けてくる。
ヒダがうねり、愛液を滲ませながら肉竿を撫で回している。
腰から下が溶けてしまいそうなほど気持ちいい。
「約束だよ……自分から腰動かしちゃダメって、ちゃんと覚えててね」
首輪をクンッと引っ張って、みさきちゃんが微笑む。
「分かった……」
「くすっ……いい子」
慈愛に満ちた微笑を浮かべたまま、みさきちゃんが腰を動かし始める。
「うぁ……っ!?」
「んっ……ん……っ……! はぁ……ナカでどんどん大きくなってる……」
リズミカルに腰を上下させるたびに、結合部から水音が鳴った。
先走りと愛液が掻き混ぜられ、泡立ち、飛び散っていく。
「ぁん……んっ……いつもより、おちんちんガチガチだよぉ……ふふっ……縄でぎゅぅって縛られて、嬉しいんだぁ……?」
大きな動きで抽送されると、全身が跳ねてベッドがギシギシと軋む。
身体のどこかが弾むたび、動くたびに縄が食い込んで、否応なしに存在を主張してくる。
縄の擦れる部分が熱い。その熱がなぜか、深い安心感を与えてくる。
みさきちゃんとどこまでもひとつに溶け合っていくような――そんな多幸感がある。
「お顔が蕩けてるよ……? ふふっ、喜んでくれて、嬉しい……」
「みさきちゃん……」
「でも……今なら、もっと気持ちよくなれるよね?」
「えっ?」
唐突に、みさきちゃんは両手で俺の乳首を引っ張り上げた。
「ふふっ、千歳くんのおっぱい、女の子になっちゃってるんだもんね……だから、こっちも弄ってあげないとね?」
ぎゅう、ぎゅう……っと乳輪ごと乳首をねじられる。胸板全体が引っ張られ、肌が縄に擦れる。
胸全体が敏感になっていて、ちょっとの刺激でも強烈な快感が生まれた。
「あは……とっても気持ちよさそう……おちんちん、私のナカでビクンビクンしてるよぉ……っ」
膣内でペニスが痛いほど勃起している。
肉壁を押し広げるように膨張し、亀頭が熱く張っていく感覚がする。
「このままだと、おっぱい弄りながらじゃないとイけなくなっちゃうかな……?」
きゅっ、きゅっ、と乳首をつねり、指ではじきながら、みさきちゃんが舌なめずりをする。
「私でしかイけない身体にするのも『縛る』ってことだよね……? それって、すっごく……興奮しちゃうなぁ……ふふふっ……」
腰使いはいよいよ激しくなっている。
亀頭に子宮口を押し付けるように腰をくねらせ、膣壁全体で肉竿を擦りたててくる。
根元から先端まで、貪るような動きで膣肉が収縮を繰り返している。
「みさきちゃん、俺、もう……っ」
「いいよ……私も、もうイっちゃいそう……っ」
愛液まみれの膣内が熱を孕み、膣穴から最奥までが痙攣し始めている。
絶頂が近い膣内で、容赦なくペニスを扱きたててくる。
「はぁっ、はぁっ……精液昇ってきてるぅ……んんっ、おちんちん、熱くなって……んん……っ!」
みさきちゃんは、射精寸前のペニス全体を絞るように結合部をしっかり密着させてきた。
「ふふっ……私とのエッチでしかイけない身体になっちゃえ……っ♪」
子宮口が亀頭に吸い付き、射精を煽る。
「あ、あっ、みさきちゃん……!」
快感が極限まで高まった瞬間、背中が大きく仰け反った。
「ふぁぁぁぁぁぁっ、んくぅぅぅぅ……っ!!」
みさきちゃんと同時に果てる。
射精を始めたペニスを、みさきちゃんの膣肉がわななきながら搾り上げてくる。
絶頂の証のように噴き出した愛液が下腹部を濡らす熱さを感じながら、二度、三度とみさきちゃんの膣内に精を吐き出した。
「あぁぁ……っ、すごいよぉ……おちんちん、ずぅっとビクビク暴れて……私のナカ、かき混ぜてる……」
みさきちゃん自身も身体を痙攣させながら、絶頂の余韻に浸っていた。
「そろそろ、縄を解いてあげないとね」
少し残念そうに言う。「長時間縛るのはよくないって書いてあったから」
自分を納得させるように呟きつつ、縄を名残惜しそうに撫でる。
白く華奢な手。細くて簡単に折れてしまいそうな手。
そんな手が、俺を縛り上げたんだ。
その事実が今さらながらに甘美に思えて、夢心地になってしまう。
「……どうしたの、千歳くん?」
みさきちゃんが、俺の視線に気付いて小首を傾げる。
全身が汗だくで、サラサラの髪の毛も頬に貼りついている。
白い肌は朱色に染まって、汗の香りを漂わせている。
快感で乱れ切った卑猥な姿でさえ、みさきちゃんはきれいで――可愛かった。
「みさきちゃんに見惚れてたんだ」
「ふぇっ……!? も、もう……またからかって……」
みさきちゃんは照れ隠しのようにぎゅっと抱きついてきた。
「わっ……」
「きゃっ!?」
そのまま後ろに倒れてしまう。
驚き顔を見合わせて、すぐにくすくすと笑い合った。
「ありがとう。私……今、すごく幸せ」
首輪を優しく撫でて、みさきちゃんが言った。
「俺の方こそ……大事にするよ、この首輪」
「うん。私の大切な存在って言う証だから……一生、ちゃんと付けててね」
「と……とりあえず、エッチの時だけでいいかな……」
さすがに常時首輪生活は、日常生活に支障が出そうだ。
「うん、それでもいいよ。今は、ね」
含みはるけれど、みさきちゃんは頷いてくれた。
「あのね……」
首輪を撫でていた手を止めて、みさきちゃんが俺の目を見つめてくる。
「どうしたの?」
瞳がキラキラと輝いていることに気付いて、下腹部が勝手にゾクリと震えた。
「私、今までSMプレイに興味なかったけど……千歳くんとなら、楽しそうかも」
みさきちゃんは、今までで一番可愛い笑顔を浮かべていた。
//
>写真をお借りしています
UnsplashのÖnder Örtelが撮影した写真
0 notes
Text
【許すことを強要する教育と、期待することについて】
自己整理も含めて駄文を書き連ねる。
ややネガティブな内容を含むので、読み返さないことを自分に勧める。
さて、許すということが日本では子供の頃から教えられてて、さも当然かのように喧嘩の結末が強要される。
決めつけのように見えるかもしれないが、自分はその結晶というか、蒸留後の水というか、絹ごし豆腐のような人間なので、許すことや、喧嘩両成敗の精神は存在していると強く感じる。
こんなことはないだろうか、小学生の頃、友達と殴り合うほどの喧嘩になった。片方は無視したと勘違いして殴りかかってきて、片方はただ殴られただけ。プロセスを見ても非は明らかだと思うものだが、小学生の頃言われた言葉の多くは違った。
「あなたも何が悪いところがあったんじゃないの?無視したって思われてるんだから」
といったものだ。
いやどう考えても殴る方が悪い。
別件にはなるが、ここ最近に元アイドルの浮気が発覚した。
別にゴシップには興味は無いのでなんとも思わなかったが、そこには浮気擁護派がいた。流石に当の本人でも浮気を肯定しないだろうに、ここでも喧嘩両成敗の"美しい"精神が如実に現れている。
非常に美しい。美しすぎて私には到底理解の及ばない世界だなと思ったものだった。
かなり前置きが長くなってしまった。
本題としては、今年さっそくイラッとしてしまうことがあった。
ただ、ふと俯瞰で見ると、
・○○を言ったやつ(Aさん)
・Aさんが○○って言ってたよと教えてきたやつ
この2名がいたことで、私の怒りの導火線に着火したわけだが、私の導火線はそう短くない。
喧嘩両成敗の精神も含めて、
自分も悪かったかもと振り返ってみよう。
結論、
自分は100%悪くない、相手が100%悪い。
ちなみに、相手方のどちらが悪いとかではなく同罪だと思った。
あゝ早速、喧嘩両成敗の気持ちは太陽系の端っこに飛んでしまったようだ。残念。
この結論に至った理由は大きく3つある。
まず1つ目、特に、後者が俯瞰で見るようなセリフを残していったから妙に腹が立ったから。
(むしろ後者の方が悪いのではという風潮があるけど、それは誤りだと思う。そもそも自分は前者を信頼して、話している。前者はその気持ちを簡単に踏み躙っている。)
(期待をするのは、勝手にこっちが期待をするからという某芦田さんがインタビューされていた時に答えていたが、あれも納得がいかない。人は誰かに期待しても良いと思う。これも喧嘩両成敗というか、それも自分が悪かったんだな、と思わせられる思考に陥る。そんなことはない。人は人に期待してもいい。)
仲悪くさせちゃったかも…みたいなことをつぶやくような悲劇のヒロインとはここでおさらばだ。そもそも言わなかったら始まらなかった戦火だが、このことについては謝りもせず、ただすみませんしかなかった。
社会人になってから感じるようになったのか、何がダメだと思っているのか認識を合わせる必要がある。がしかし、おそらく本質は分かってなさそうなのでもうよい。
繰り返すが、悲劇のヒロインになるくらいなら他の姿勢で表して欲しかった。
理由2つ目は返信が異常に遅かったことだ。
先程まで、何が悪いかわかっているのかという話があった中で即矛盾を呈するが、直ぐに返信して謝罪の意を示すことは必要だと思う。
そこで、なぜこちらが謝っている側の気持ちを組まなければならないのだろうか。
なかなか返信がなさそうだったので、どうやってことを鎮めようかと1度は考えた。次に飯に行く時はおごってくれよなって。1度はこのメッセージを送った。次の機会を生み出せたら許せるのではと思ったからだった。が、直ぐに消去した。
それは自分だけが得をしていて、その話に関係する方々に何も還元出来ていない。自分だけがその恩恵を享受するのはポリシーとして許せなかった。
自分への許せなさ
そして、相手方への許せなさ
丸23年とちょっと生きてきて、初めて誰かを許さないという判断をしてしまいそうだ。
まあ自然に離れていった人々もいることはさておき、意識的に離れようと思う瞬間に久々に相対した。
最後に3つめの理由は、
マジでごめん、などと本来謝罪の時に使うべきでは無い言葉を使用したことである。
謝罪の意を示す際に、どれだけ仲が良いかんけいであろうと使うべきでは無い。なぜなら心から謝っている気持ちが薄まった状態で伝わってしまうからだ。
日本語の特徴でもある形容詞や副詞はさておき、とにかく誠意ある言葉を使うべきだ。それが友達であっても。
正に親しき仲にも礼儀ありといったところか。
先程あげた前者も後者もこの点が非常に欠けていた。怒ってるやん、だと?怒っている側がさも悪いかのように、その気持ちは汲み取れなかったかのように書くのはお門違いも甚だしい。
自分がされて嫌なことは人にしないというのも日本教育でよく言われるセリフだが、なかなか浸透しないなあとこんな時に感じる。
立ち返って私は今回の件について、
前向きに許さな��という判断をしようと思う。
================
ここからは完全に余談だが、大きく2つのことを考えたり、感じた。
まず1つ目、鋼の錬金術師でのセリフ
「勘違いしないで、許しては無いのよ」
これはヒロインのキャラクターが、怪我をした敵キャラの怪我を治すシーンで言われた言葉だった。ここが大きく今日の私の判断を支えている。
許さなくてもいい。
許さなくてもよいが、関係性を無にするわけではない。そんな関係性も合っていいのではと思った。おきたことはどうしようもない。前に進むしかないと思った。
2点目、言葉ならなんとでも言えることと、日本語の発達。
今回の一見を経て感じたことがある。それは日本人の言葉のあやが増えすぎてしまったことだ。
ごめん、など日本語には感情を伝える言葉が存在するが、ピダハンという民族には感情を表現する語彙がない。
何をするかと言うと態度で示すのである。
謝るだけなら警察要らない。
あまり好きな言葉ではなかったが、余りにもラフな謝り方をされるとさすがに感じるものだ。
破天荒な1年が始まりそうな予感がしたが、怒りを感じるのは今年、これが最初で最後で良いと思った。
以上。
0 notes
Text
2023年、私たちを待ち受けているものとは?
刺激的で濃密な1年
アンティエ・リンデンブラット

オリジナル動画🔗:https://youtu.be/z8mF4yWjJmY
【和訳:ALAE PHOENICIS】
https://t.me/alaephoenicis
1. 時間がますます崩壊していく
2023年は、今年よりも時間が速く過ぎると感じるでしょう。私は今年でもすごい速く過ぎたと思っていますが、来年は更に加速します。2023年の年末になるときには、「うわ〜❗今年は何処へ行ってしまったんだ❔」と思うでしょう。あまりにも多くのことがあるからですが、それは後の項目で述べます。
この時間の加速は振動周波数が高くなることと関係しています。それは常に波を描いてやってくるのですが、次々とやって来るその速度が加速され、波と波の間も狭まっていきます。
そして「時間が線上に流れている」という感覚も、私たちの中で消滅していきます。これは、今年2022年に既に始まっていた傾向ですが、2023年にはもっと強くなります。それは私たちがますます「創造主」の意識に近づいているからで、なにより「多次元性」に覚醒めてきていて、線上に流れる時間というのが全く存在していない次元と繋がり出しているからです。つまり、「時間が線上に流れる次元」というのを私たちはまだ日常必要としているのですが、それが消滅し始めている今、同時にそうではない「時がない次元」と並行して体験し始めるということです。時のない次元では、常に「今」しか存在していません。
そのような方向感覚を失ったような感覚には慣れていないのは、今の状況では当然のことです。
起こっている状況を信頼することが大事で、ゆっくりとその感覚へと入っていきます。
2. 自分自身への違和感
このことは12月の動画でも一部扱いました。
人間というのは習慣の動物ですが、更に覚醒が進んでいくと、我々はそのエゴというある種のアイデンティティの中で消滅していき、創造主自身のような多次元的意識に覚醒めていきます。それと共に、不安・怯えといった感情が無くなっていったり、もしくは何かに対する行動の姿勢や、ものの見方が変化し、これまで現実だと認識していた・信じていた世界観が変わっていきます。
これまでの世界観は、自分に枠組みと安定を与えてくれていたし、ある程度は予測可能な世界でした。しかし、これが消え去ると、とりあえず私たちは不安を感じると共に、自分自身への違和感も出てきます。
実際にはここで、更に上層における秩序が再構築されると我々の視点も変化するので、物事をもっと高いところから眺めることが出来るようになっていきます。全てにはそれなりの秩序があり、これまで思っていたのとは全像が違っていたことが分かってきます。
「こんな自分は知らない」という感覚がまたもや起こってくるのは、これまで自分で思っていた「自分」は、隅々に渡って「実は自分ではなかった」ことが明らかになってくるからです。
それが、「エゴ・アイデンティティの崩壊」と関わってきます。
そしてそれこそ、この次元上昇プロセスが、突然に起こるわけではない、という理由の一つです。
数年前はまだ多くの人が「なるほど、ある朝起きたら5Dになっている訳ね」と信じていました。もしそうであるなら、私たちは完全に圧倒され、どうすれば良いのかわからなくなリ、混乱してしまうでしょう。そんなことをしても、誰のためにもなりません。
これは、2023年になると本格的にスピードアップしていくプロセスとなります。
3. 多方面において濃厚な1年
周波数とエネルギーの上昇について既に触れましたが、特に年の後半になると急激に増大します。それはこれまで本当に知られることのなかった人類全体の覚醒に影響を及ぼします。
次々と波がやって来る、間隔が短くなっていく、と言いましたが、その合間に私たちの心身が新しくやって来るエネルギーと融合していく時間もどんどん短くなっていきます。
私たちは非常に濃厚な感覚に挑まれるでしょう。
年の前半は、集中的浄化の時。個人と集団のレベル、また地球にも強烈な浄化が見られるでしょう。特に地球の浄化は地水火風すべての元素レベルで起こり、”彼女”のからだはより高い周波数へと持ち上げられます。
これと繋がっているのが、古い秩序、古い構造で、これらは崩壊します。年の前半に強くこれが見えてきます。
そして私たちは「革命、激変、ストライキ、暴動」...といったものを目にしますが、残念なことにこれらは常に平和的には済まされないでしょう。
反面、急速な発見、改変などがあり、これらは特に医科学・健康分野において起こる、とスピリットの世界が伝えてきています。つまり、これらの分野でも、とてもポジティブな「革命」が起きるようです。
物事は急速に流れていき、「顕現」ということも急速になります。そうなると、自分が何を欲しているのかという方向性を定めることと、自分の「想い・思考」を表現する能力が、尚更重要となってきます。
なぜなら、「思考」が「顕現」されるまでの間隔が、今もうすごく短くなってきているからです。これは重要です。
2023年は、全体に活発だといえます。活発で、大きく動かされる感覚になるでしょう。私たちは沢山のことを動かせるし、沢山のことを昇華させることが出来ます。
多くの人が「今年こそ前進したい、新しいことを始めたい」と思っていたのに、何かと弊害があって出来なかったことを、私は知ってます。これは2023年には間違い無く取り払われます。ものごとは大きく流れ、動き出します。
4. 地球の新しい周波数領域へ突入する私たち
私たちはこれから、新しい周波数領域へと足を踏み入れることになりますが、それを通す門となるのが今年の冬至です。つまり、私たちはこの門を通して新しい周波数に触れることになり、そうやって私たちはより高い周波数へと持ち上げられます。
ちょうど今、スピリットの世界から示されたのは「人類にとってこれまで体験したことのないもの」です。非常にスリリングです。
この新しい周波数、「波動」によって、私たちはより強く「創造主」の意識へと目覚め、「新地球に物理的場所」を創造・顕現してい来ます。
去年の時点から気づかれた方も多かったでしょうが、「自然の輝き」が変化していました。光のあふれる度合いが高まっていました。2023年はそのクリスタル的エネルギーは、より一層自然の中に見られ、感じられるようになります。私rたちに知覚可能なレベルへと、全てが生き生きと鮮明になり、エネルギーに満ちていきます。
5. コミュニティ
世界は突然に変わるのではなく、プロセスを経ていきますが、コミュニティの構築もそうです。生活共同体として形作られることもあれば、複数の人達と協力し合う何かであったりします。数年前からこの傾向は強まっていますが、2023年から走り出す...地面からキノコが出てくるような感じになります。
これらのコミュニティの中心に置かれるのはハート。ハートのクウォリティ、そしてハートの価値です。これは「新しいもの」であって、2023年には更に強く開花していきます。ということはつまり、心が通い合うもの同士、ソウルメイト同士が互いを見つけ合うようになります。もしかすると、既に出会っていて、2023年から協力しあって世界へ向けた新しいコミュニティを構築し、リードと責任を負うポジションや役割を担っていくのかも知れません。
新しい構造と秩序は、新しい地球の周波数がエネルギーとして利用され、物理的に顕現していきます。
ここで重要になってくるのは、私たちの「思考・意図の句案(言葉による表現)」が、人類全般の幸せに貢献するものであることで、この「思考・意図」にこもるパワーを駆使するようになります。
これも、非常にスリリングなテーマです。
6. 透視感覚や 特殊能力の強烈な覚醒
透視能力、これはいわゆる神通力のようなもので、視覚だけでなく、聴覚であったり、何かを感じるとか既知感だとか、これに関連した全く個人的な才能・能力が、2023年には強く拡張されていきます。
このような感覚が初めて生じる人もいれば、元からあった感覚が増強されます。こうして「自分が創造者である」という自覚が強まり、より開花されていきます。これは一つのプロセスとして、2023年に入ってから、というより今年の12月にはそれが始まります。
創造しているのは自分なのだ、という自覚はある程度あったかもですが、これ以降、「頭で理解している」のを超えて、自分自身の心と感情を以て、その自覚を体現するようになっていきます。
自分の意識が何を目指すのか、どのような思考を凝らすのか、そしてそれを「利用」することで、望む方向へと現実に変化をもたらす力が自分にあることを、認識するようになります。
7. 内面的・外面的な挑戦
2023年には個人のみならず、人類全体が挑まれることになりますが、この挑戦は、人類の覚醒、成長、そして何よりも必要とされている変化のためにはとてつもなく重要です。これは古い構造と秩序を溶解し、新たに創造するためです。
意識変化は私たちにとって実際、自らの観点を変えるためのチャンスとなり、これが挑戦ということなのです。
つまり、これまで弊害・障壁に感じられていたことは、「もっとしっかり見つめるべきこと」、「改めるべきこと」、「限界を広げること」なのだと促されているのだ、と気づきます。
ですから「挑戦」とは、土台「道標」であり、「もしもし、こっちだよ」とというお知らせなのです。そして、これまでの自分の観点を手放していくことで、これらの挑戦とも向き合いやすくなっていきます。
これは私たちの強さや、秘められた可能性をも指し示してくれていて、もっと成長して開花するための手助けとなってくれます。この「開花」というのが2023年の大きなテーマなのです。
8. ハートとマインドのシンクロナイゼーション
(シンクロナイゼーションとは、同期・同化させること)
皆さんも、心と頭の間で起こる葛藤をご存知のはず。この心とマインド(思考・精神)は、この時期に再び「一致」していきます。
これに伴い、私たちはどんどん、より「アバター(化身)」となっていく、つまり「神(としての)人」に近づいていきます。「神的な自己」というのが「人間的自己」と結びついて「統一体」となっていくと、日常生活や決断の仕方などが根本的に変化していきます。こうした様相も、私たちにとっては非常に未知なることです。
これ迄は、理性で操作・管理しようとしていたことを、私たちはもっと「心」の声を聞いて、直感で判断するようになり、そこに流れるエネルギーの波に乗るようになります。
怯えからくるコントロールへの執着などは、「自分は誰なのか」という心の声と統合・一致して「流れてくるもの」によって、溶かされていきます。
そうして、私たちは改めて「信頼」を学ぶと共に、自分の心に従うときには自分自身への信頼も高めるようになります。
自分たちは恣意的に何かに晒されているわけではない、何かが思いがけず起こるわけではない、そうではなくて自分で創造しているのだ、というこの「知っている」という感覚、自分が創造者であるという自覚がそこにはあるわけです。
この心の奥底で起こる覚醒は2023年、更に強くなり、私たちのハートが拡張することで、前述したハートのクウォリティ・ハートの価値といったものについて、ただ「語る」のではなく、もっとそれを「生きる」ことになります。
これによって、私たちは自分自身に対する理解と共感を深めるようになりますが、それは他人を理解し、他人への共感が深まることでもあるのです。すると「人と人との関わり合い方」への効果も体験するでしょう。
ここで開花されるのは「女性的な側面」です。徐々に、女神が私たち人類と地球の中へ戻ってきます。女性的なクウォリティと属性で、「他と共に流れる」ような様態、直感・心に従う、実際に「心を生きる」というのも女性的なものの一つです。
私たちは、これまでよりも物事を「やわらかく」体験するようになるでしょう。これまでは沢山の硬い構造・厳しさがそこに在るような感じしたが、心と頭の葛藤を超えて、「心」に従って生きるよようになると柔らかさを体験します。
更に素晴らしいのは、この同化によって心が開かれ、神的な子供の自分というのが強く覚醒めていきます。もっと発見したい、もっと遊びたい、クリエイティブになりたいし、クリエイトしたい... 私たちはそこにも、新しい価値を見出していくでしょう。子供の時の私たちにはまだあったのに、抑圧されてきたものです。
そうやって私たちは新しい目で世界を眺めるようになります。スピリットの世界が今、私にある例えをわたしてくれました。
多くのことが私たちには「当たり前」になってしまいました。そこに小川が流れていれば、「こんなのもう数え切れぬほど見たことあるし」となりますが、こうした「当たり前」になっていたものを、改めて眺めなおしてみるのです。私たちの「感覚」は強く覚醒し、これまで以上の感覚を駆使して眺めることになるからです。あなたは強く魅了されるでしょう。子供がそのように反応しますが、私たちは大人になる過程でそれを失ってきました。しかし、それが戻ってきます。
また、私たちはもっともっと「喜び」をもって行動するようになります。大人のしかつめらしさからではなく。
集中的に「今」を生きようとし、計画や結果・目的を掲げない、というのも「流れる」という様態を示してます。
内なる「子供」は当然、深い癒やしを得ます。だって、生活の中にやっと、自分自身を開花させることができる場所が得られるわけなので。
それはとても素晴らしいことです。
9. ソウルパーツを統合し、全体性へと導き戻す
これは2023年の大事なテーマですが、エネルギーはこのソウルパーツの統合をサポートしてくれます。
上述したように、新しい地球はある周波数に達しますが、これは調和と統合・全体性の周波数です。そして、そこに居る私たちはこの周波数を体現しているはずです。
しかしこの周波数は、私たちの魂が分裂したままで、統合して全体をなしていなければ、達することが出来ません。ですから、分裂していた魂のパーツを統合して全体性を取り戻すことが必須です。
魂のパーツは、自分の中で調和をもって統合されていなければなりません。これができていれば、自分の外側の人たちとも上手に調和していけます。
なぜなら、「傷ついている人は、他人を傷つける」からですが、この行為が最初に向けられるのは他人ではなく、自分自身に向けられます。
自分の魂に、まだ癒やされていない傷ついたパーツがあると、これが自分自身を何度も何度も傷つけてきて、これはとても痛みを伴います。
多くの人が、分裂したソウルパーツについては抽象的にしか想像ができないので、1月にはこのテーマの詳細を具体的に説明するセミナーを数回に渡って計画しています。統合プロセスや、その時の光と闇の関わり合いなどについて。
10. 新しい世代がリードする
このテーマは、夢で私に示されました。
ドローレス・キャノンという人、ご存じの方も居ると思います。彼女には新地球についての何冊もの著書があり、「三つの志願者の波」についても言及しています。つまり、この覚醒とアセンションに協力したくて地球への転生を願い出た魂たちのことです。
40−50代以上の人たちは長い間、エネルギー的に導く役割を担ってきました。この世代の人は、癒やしや変換(トランスフォーメーション)、そして覚醒を促し、「闇に光」を持ち込むのが課題でした。
夢で私に示されたのは、エネルギー的にはこれより次の世代がリードを担うということでした。これがドローレスが言っていた次の「志願者の波」で、20-25歳ぐらいの世代です。
2023年には、彼らの姿が更に目立ってきて、新地球に物理的に新しい声生命を吹き込み、物理的に顕現させていきます。
そうすることで、前世代の志願者たちをその役割から解放してくれます。どの「志願者の波」にも独特の課題がありました。私たち(40-50代以上)は、これまで長年、常に何らかの圧迫を感じたり、自分を犠牲にしたり我慢したりしなければならない感触の中にあり、楽ではありませんでした。それが急に軽くなることで、解放されたことを知ります。
この新しい世代の「志願者の波」は、とりわけ米国で目立ってきます。ここ数年、既に目立ってきています。つまり、多くの魂があの場所に集中的に転生してきているということです。ムーヴメントは米国で大きく動き出すでしょう。
11. グラウンディング&内側へのリトリートが基本
(リトリートとは、引きこもって静養する、というような意味が近いかと思います)
2023年は振動周波数がどんどん高まっていき、自分がそれと統合していく間隔も狭まっていきます。ですから「静養する」時間をとることは必須。これは非常に重要です。
やって来るエネルギーを、人間としての自分の肉体に統合しきれないと、まるっきり圧倒されてしまい、混乱し、方向感覚を失い...ひどい場合は「自分は気が狂ったのではないか」と感じたりします。あまりにも多くの変化が、自分の意識の中、人間としての生活の中で起こるからです。
グラウンディングに最適なのは自然と触れ合うことです。しかし、その場合、���本的に大事なのは「肉体」に留まることです。
オススメは、ヨガやスポーツなどで、身体を動かすこと。また、睡眠を沢山取り、静かな時間を持つことです。
私はここに「シンプリシティ(簡易・質素/単純性)」とメモってあります。生活を簡素にしましょう。どの部分をもっと簡略化できますか?何が最も大事なのかを知って、優先順位をつけること。
そして、外からの刺激・影響を徐々にカットしていって、ある意味「コンセントを抜く」のです。物理的な面だけでなく、自分のエネルギーの面でもそうします。それは「コンセントを抜く」イメージでやると良いです。
私たちのアンテナは、周囲の状況や、全ての人々、全ての別次元...あらゆるエネルギーと繋がっています。
ああ、もう一杯いっぱい、もうもちきれない、という気分になったときは、イメージワーキングをして、全てのコンセントを抜き、静寂な自然の中へ入っていったりするのが一番です。全てとの繋がりを解いて、自分自身にランディングして下さい。そうやって「統合すべきものを統合する」余裕を作ります。
あと、10項目ぐらいは述べられますが、これらが2023年に主に予想されることで、最も重要だと私が感じていることであり、スピリットの世界からも渡された情報です。
これ以降はまた、月々のメッセージでお伝えしていきます。
0 notes
Text
媛深湖
墓に手を合わせて顔を上げる。後ろを振り返れば、数ヶ月振りに会う恋人がそこに居た。
待ち合わせ場所をここに指定したのは、彼女の方だった。湖のほとり。知らなければ辿り着けないような、木々の波をぬった先にある。頭上に浮かぶ月と広がる雲が織りなす陰影は、まるで水の底に居るかのような錯覚を起こさせる。
ここはかつて 裏社会の寺か神社のような場所だったところ。表社会をつまはじきにされたはぐれ者や、無縁仏なんかがゴミのように投げ込まれていた場所だ。
僕が座り込んでいたのが、新しい墓の前だと気付いたのか、彼女は「何を祈っていたのかな」と呟いた。
「……それはまぁ、魂の安息だよ」
「ふふ。懺悔のようなものだね」
「ああ」
今 この場所は人魚の墓場になっている。
薬が無くなり救いを失った彼等は、狂い死ぬ際になるとまるで彷徨うようにここへやって来るらしかった。この数年に渡って、湖の水辺にまで辿り着けずに木の根へ倒れ伏して亡くなっている遺体が いくつも見つかった。
彼等は自分たちが死んだこと――――僕らヒトが思うような死を迎えたことには気付かず、未だ苦しみのさなかにあるのかもしれない。少なくとも死ぬ間際、人魚の秘薬に頼れなかった彼等はそう信じて死んでいったのだろう。死ぬということは何かの区切りではなく、肉体が動かなくなるだけの、苦痛の継続なのだと。
もし……本当にそうだとしたら、僕はそんな苦渋は到底飲み込みきれなさそうだ。
願わくば 死が彼等の思うようなものじゃなく ヒトが楽観的に考えたような、何の苦痛も感じない終焉でありますように。
「私も懺悔しなくてはいけないかな」
僕が隣に立つまで黙っていた彼女、散葉は、そのまま歩き出すことはせず、むしろ向き合って僕の顔を見据えてそう言った。夜の暗がりに金の双眸が猛禽類のごとく光る。温もりを感じる人となりに反して、彼女の目の輝きはいつも、どこか冷たい。それが好きでもあったし怖くもあった。
「……懺悔って顔じゃ、無いみたいだけど」
敵対するかのようなその動作に、否が応でも身構える
黒いマントと、あれから更に長く伸びた髪が まるでファントムのようだ。
――――その靡くマントの 内側から
妖精のような幼子が、姿を現わした。
「……ぇ、」
幼さに不相応な痩せ方と頭身、青ざめた肌と焦点の危うい虚ろな目
もつれたような黒髪の癖毛
一目見たら……、一目見ただけでは、酷く不健康で痛々しい要素でしか無いそれが、人形のように造型の中で溶けている。
その子の容姿は僕には全く似ていない。ただ、その両眼だけは、僕の娘と言い張って通用しそうな青色をしていた。
「この、子は……」
「名前は媛深湖。いま2歳、今年で3歳になるよ」
「な、に、2歳?」
とてもそうは見えない。見た目以上に、その立ち姿が。指先まで神経の通った両手の仕草、細い背を支えるしっかりとした足取り。
エミコ、という名前の響きの可愛らしい印象とは裏腹に 妖鬼じみた得体の知れなさがある。
どうしてこの場に、こんな子供を――――、いや
もし、その双眸が透けた血の色の滲む薄ピンクだったら。もし、このまま成長を遂げれば。酷くよく似た顔立ちを、僕は知っているんじゃないか。
誰の……子供なんだ。
この子の両親は誰だ?
本人の前で口にするのは憚られ、僕が口ごもると まるでそれを見透かしたかのように散葉は微笑んで、言った。
「君の娘だよ。青佑くん」
間違い無く私が、生みの親だ、と。
水中には「お母さん」「お父さん」という呼びかけは無かったそうだ。
性に奔放な人魚たちは誰と誰の子供なのか血縁を隠しはしなかったが、赤子はコミュニティ全体で育て、その後ある程度成長した子供は自分で誰の元につくかを決めたらしい。元はそれが「主人」と「愛子」の関係だ。
散葉は自分の父母の話を鳴瀬にした時、単語が全く通じずにカルチャーショックだったという。
学生時代、既にある程度補われていた鳴瀬のヒト知識は、身近に散葉や姫歌さんの存在があってこそだったのだろう。あいつは他の人魚より日本語が比較的通じている感触があったのは、僕の勘違いじゃ無かったってことだ。
思い返してみるに、当時の鳴瀬が僕をふざけてお父さんだのお母さんだのと呼んでいたのは、僕が世話を焼いたりお小言みたいな口出しをした時だったと思う。周囲には親子じゃなく夫婦か恋人同士みたいに見えていたし、実際あの時の僕らの関わりかたは 愛子と主人との関係に近かったのだ。
愛子と主人。
主従関係で擬似的な親子のようでいて、その実対等な関係。
共犯者であり、愛するだけのことを押しつけ合う、身勝手な関係。その身勝手をゆるしあう関係。
「愛子」のことを、水中の身分制度と記録されている書物もある。主人と愛子の関係を取ることで、仕組みを形成していたのだと。
けれどおそらく実態は違った。
彼等にとって愛子と主人は、ただの個人と個人で
同じ「愛子」と表されたとしても、決まった型など何一つ無かったんじゃないかと、今では思う。
だからきっと鳴瀬は、「お父さん」も「お母さん」も
恋人も友人も上下関係も師弟関係も 知らなかった。想いを向けるときよるべとなるような足場の全部、知らなかった。
双方向に通わせようと思ったら、そうした足場に一緒に立つしかないのに、……それをしなかったら 同じ気持ちなんて幻想が、まかり通るはずもない。心はみんな違うのだ。だから足場をもたない彼の愛は一方的なもので、彼の妹ともそれで成立していた。
僕らの関係は ヒトの愛情を鳴瀬が受け入れたいと、愛されようとしてくれたところから 崩れ始めた。
愛されたいと願うことによって愛していることを示すのは 死が救済、の強い信仰に支えられていた人魚にとって、その認識を根底から破壊されるような、恐ろしい意識の変革だったろう。
あいつは自分が愛していればそれでよかったのに、喪失をそのまま愛せないヒトの感覚を知ってしまった
僕らももう少しくらい鳴瀬に応えてやるべきだったのかもしれないと今更になって思う。お前が居なくなるよりも、苦しむ方が辛いよと 言ってやれれば、何か違っただろうか。だけどそれはできない相談なんだ、だって心は、感じ方はみんなそれぞれ違うんだ。
理解できない人魚の苦痛に 僕はどこまでも、冷酷になれた。
家までの道中、タクシーの車内で僕の膝に抱かれて泣くこともぐずることもなく凭れていたその子は、降りるとき散葉に促されて「ありがとうございました」と流暢な発声で礼を述べた。
どうしてもヒトの2歳児では無い、という風に、見てしまう。
これが人魚の子供なら、誰の血を継いでいるかは明らかだ。
「ただいま」
「おかえり。……媛深湖、ここがお家だよ」
「ただいま?」
「うん。おかえり」
笑いかけると、ぽかんと口を開けてふんわりした視線が僕の喉辺りまで上がってきた。かわいいな。
ばさりとマントを脱いだ散葉がのんびりとソファでくつろぎ始め、媛深湖もそこまで歩み寄っていって身体を丸めた。かわいい。急に家の中が華やかになった気がする。
この部屋から続くドアの向こうに、本当の父親が居る。――――本当の、などと考えるのは僕がヒトだからだろうか。おそらく戸籍上は散葉の言うとおり、僕と散葉の娘、ってことになっているんだろうけど。
戸籍よりは血縁、けれど情よりも血縁だとは、僕だって思いたくない。とはいえ……。
この子は、姫歌さんに似すぎている。
つまり、散葉が女性体である以上、相手は鳴瀬だ。あいつがそういうことを散葉に無理矢理強いるとは思えないが、けれど制御できなくなっていたらあり得ないとも言い切れない。もしくは逆に、散葉が鳴瀬を襲うことは簡単にできただろう。そう察して余りある状況を、この2年間目にし続けてきた。
最初のうち、鳴瀬と二人の暮らしは快適の一言に尽きた。家に居る間ほとんどの家事をやっておいてくれるし、外に出られなくても文句一つ言わない。基本的には一人で居たがるが、話し掛ければ穏やかに応えてくれて、笑い合うこともあった。
……だが、それは初めの数ヶ月の間の話だ。
残っていた分の薬を使い切ってしばらくすると、鳴瀬は突然物を落としたり、不意に意識が乖離したかのようにぼんやりすることが増えた。
ふとしたとき僕の方を見て、……目は合わなかった、そういう時鳴瀬は少し目線を下げた伏し目で僕の方を見ていて、何か迷うような確かめるような数秒の後、何もなく視線を逸らし、見詰めてくる前の動作の続きをした。
そうしてまもなく、苦痛に起き上がることもできなくなった。
寝室でじっと横になることさえ辛く、悶え続ける鳴瀬を見て、本当にこのまま死んでしまうんじゃないかと思ったし、……それでも死にはせず衰弱していく様子を追うごとに 彼を、彼等を救っていた薬を、無駄に浪費した文秋や娯楽に使った人間たちに、言いようもない感情を覚えた。
あの事件で彼等がしたことの罪の深さを、……姫歌さんが言っていたことの意味の重さを、
実際に目の当たりにすることで僕は ようやく、知った。
新しく薬が出来上がるまで、最短でも2年かかる。花が咲くまでの1年、作って試験し散葉から受け取るまでに1年。
それまでの間、苛まれ続けた身体が、どうなっているか
全く動かずに居たら筋肉も骨も取り返しがつかないほど弱ってしまう。どうにかして風呂やトイレや、特に無意味でも室内をうろつく程度の動作は介助しつつも行うよう、普段から習慣化させているが、起き上がった拍子に嘔吐や失禁することもあった。こんな姿、いくら僕にだって見られたくなかったろう。どんなに苦しんでいても、鳴瀬は相変わらず理知的でまだ思考までやられていなかったし、身を置かれた現実から逃げるようにたぐる指先で美しい絵を描くこともあった。��意に零れ出す歌声は美しかった。だから余計、その肉体が制御を失い何もできずに呻く症状の落差が痛々しく見え、余計、この先に待ち受ける狂気に彼が呑まれる時を想像して 恐ろしかった。
あの薬が、死という救いが人魚の尊厳を守っていた。
秘密警察で人魚を処刑対象として追う期間は3年。以前までその期間を、やけに短く打ち切るんだな、なんて思っていたけど。
今は、3年なんて 彼等が何の援助もなく、失踪した状態でよすがなく生き延びるのは、絶対に不可能な長さだと そう思う。
……それでも そのよすがとなれるなら、僕はどこまでも冷酷になれた
苦しんでいる鳴瀬の傍で、今も 彼が死なないよう閉じ込め続けている。
「散葉」
「はい」
「一つだけ聞きたい」
媛深湖がすやすやと眠っているのを視認して、抑えた声で問いかける。2歳だ。2年間。つまり僕と鳴瀬がここで暮らし始めた時には既に、この子は生まれる予定だった。
「……どうしてこの子のこと、今まで教えてくれなかった?鳴瀬は知ってるのか」
「りょーちゃんもこの子のことは知らない。伝えなかったのは、わからなかったから」
「……わからなかった?」
「この子が生きられるかどうか、わからなかったから」
「それでも、お前の子なら僕には無関係じゃ無いだろ。……生まれたことも知らないなんて、」
「青佑くん。私は貴方が思うよりずっと、倫理に欠けた者なんだ」
「 …、え?」
雲行きが怪しいことに気付いても、もう遅かった。もうとっくの昔に遅かったのを、――――突きつけられる。
「この子は実験体とするために生んだ。薬の試験に使うために」
―――――― 、
――――……、っ
思わず 言葉に、詰まった僕の 目を、……敵対するように見据えて
彼女はよどみなく告げる。
「この子の協力のおかげで、私たちの女神様はより良い薬を作り出すことができたよ。2歳と聞いて、ある程度察してはいなかったのかな、秘密警察のバフィくん」
「………………」
「今度来るときには、完成した薬を持って来られる。……この子にも、いずれ使える薬だよ。成長したら教えてあげないとね」
こいつ
こいつ、……
ふらふらとソファの背に手をついて、座り込む。こいつは自分で生んだ娘が、もし薬で死んだとしても、その可能性すら受け入れて、前��としてそのために、鳴瀬と行為に及んで妊娠して、子供を産んで、���てた。
育てて 今まで――――子供の身体を 使って、……
ああ、失念していた。彼女もまた、頭の先まで水の中に浸かっていた者だってことを。水槽の人魚たちに仕えていた、こちらは正真正銘、「仕えていた」者だったってことを。
「お前……絶対に、そんなこと、この子に、言うなよ」
「……言わないよ。軽蔑した?」
「……正直、今回は少し、キツい」
今更軽蔑なんてできない、と言ってしまうのは簡単だ。実際に僕は今散葉を軽蔑はしていない。
ただ、どうしようもなく思っただけだ。
どうしようも無いことに手を出して、ままならない思いをするのに 久しぶりに膝を折っただけだ。
「それでいいよ」
「……」
「軽蔑してくれたらいい。私の手元にこの子を置いておくべきじゃ無い。……だから今日は、この子を連れてきたんだ」
「――――どういうこと」
「媛深湖をここで暮らさせてほしい」
「…… 」ここで
僕が 引き取るって、ことか。
「もうすぐ幼稚園に通える年になるんだよ」
散葉が媛深湖の頭を撫でて優しい顔をする。まるで慈しんでいるような。実際そうなのだろう。心に偽りは無く愛していて、それを惜しみなく与えられて
だから実験体にできないとか、そういうことにはならないだけで。
「保育園でもいいな。私と青佑くん、共働きだから審査は通ると思うし、そこはお任せするけど。この子にとって私と居るより、青佑くんと居た方がきっといい。穏やかで、反抗できる、親と言える存在を、この子にはあげたい。守ってくれる存在を」
守るべき存在。子供は、社会において守られるべき存在のはずだ。
そうでなくても
安らかに瞼の伏せられた寝顔を見る 大切な、この部屋のドアの向こうに居る存在と、よく似た寝顔
それを抱きしめているのは恋の相手に選んだ、たった一人僕を掻き乱してくれる人
僕の 正義を支えるもの。
「わかった」
立ち上がり近付いて もう一度膝をつく。お姫さまの前に跪くような姿勢で、小さな子供の頭を撫でて「引き取るよ。僕の娘だ」しっかり金色の目を見詰め返すと、そう答えた。
この時、媛深湖が 僕にとって必ず、何よりも1番に守るべき存在になった。
『インサニティ』
0 notes
Text
やくしゃしょうかい。
こんにちは。カヌレです。本番が近づくにつれてドキドキワクワクしてます。前回トマトの話をしすぎたので、今回は真面目に役者紹介します。(敬称略)
握飯子
クオリアさん。カヌレの名付け親。いつもテンション高めで話しかけてくれて、私まで元気になれます。ちゃうかシナモロールの民の1人で、出会った初日にお互いのシナモングッズを見せ合う儀式をしたのも素敵な思い出。演技をするときにスイッチか入るところがめっちゃかっこいいです。クオリアさんの見せてくださる表情の1つひとつが全部大好きです。
杏仁アニー
アニーさん。めっちゃすごい方。多才すぎて尊敬を通り越して恐れ多いです。いつもたくさん話しかけてくれてありがとうございます。嬉しいです。役者をするアニーさんを入団してから初めて見たのですが、肺活量と表情がすごいうえに、常に向上心があるすごい先輩だなと感じ、心から尊敬し、憧れました。それに加えてスタッフでも活躍されていて、アニーさんはいつ寝ているのだろうか…。この謎はきっとちゃうかに伝わる七不思議のひとつだと思います。
田中かほ
ゆるあさん。かわいいオブかわいい。かわいくて、厳しくて、かっこよくて、こんなに魅力的な方には初めて出会いました。いつもかわいいって言ってくれるのですが、恥ずかしくてどんなリアクションをしたらいいか分かりません。私なんかよりゆるあさんの方が100億倍かわいいと思ってます。役者をする姿もチーフとして指揮する姿も、演劇に本気な姿勢がビシビシ伝わってきて、見ているこちらまで頑張ろうと思えるような、素敵な先輩です。
君安飛那太
コルクさん。舞台の上で見せる自然な笑顔が素敵な方。きっと日常生活のちょっとした1場面を演技に活かしていて、その積み重ねで日常には無いことも自然に演じられるすごい人なのだと思っています。PVの撮影や編集の技術があまりにもすごすぎて、キラキラ宝石箱みたいなPVを作れるなんて、めっちゃ尊敬してます。YouTubeで毎日PVを見て、公演へのワクワクを高めています。
坪井涼
ゴコさん。今公演のNO.1推し。かわいすぎてかわいすぎてゴコさんを表す言葉が愛おしい以外思いつかないです。そのかわいさをぜひみなさんの目で確認してほしいです。いつも私を見かけると手を振ってくれます。たくさんファンサありがとうございます。いつも休憩中話しかけてくれてありがとうございます。一切絡むシーンがなかったのに仲良くなれて嬉しいです。
一宮仁
ロキ。すごい才能を持ってる人。出会ってから1ヶ月ぐらいはずっと先輩だと思ってたし、こわい人だと思ってた。なんでかと言うと、話したことがなかったから。食わず嫌い的なやつですね。話してみると面白くて、笑顔が眩しい爽やか男子って感じの印象に変わりました。稽古終わりにおつかれって言ってくれたの、1日の疲れ吹き飛んだ。嬉しかった。空気清浄機みたいな人だと思います。
緒田舞里
まりお。眩しすぎない太陽みたいな人。まりおがいると場の雰囲気が明るくなるよね。なのに明るすぎて直視できない感じではなく、ぽかぽかあったかい陽だまりみたいな雰囲気を持ってると思います。いつも周りに気を使ってくれてるのに、それを感じさせないところが本当に素敵だと思う。明るい役が似合うけど、だからこそ、いつか違う1面も見てみたいな。
梅本潤
しあらさん。今回の公演で1番お世話になった方。しあらさんのおかげで役をなんとか形に出来ました。たくさん迷惑をかけてしまったけど、一緒に動きや役について考えてくださり、本当にありがとうございました。優しくて頼りがいがあるのに意外とあっさりしている1面もあって、何回話しても不思議な方だなと思います。いろいろなところに気配りが出来る素敵な先輩です。たまには無理せず、周りを気にせず自分のことだけ考えてほしくなるような、みんなを大切にしてくれる方だと思います。
えどいん
エドウィンさん。知れば知るほど不思議で深みのある方。独特の世界観でその場を自分のものに出来るなんて、誰にでもできる簡単なことじゃないです。本当にすごいです。でも何故かカードゲームは最弱で、大富豪でもババ抜きでも最下位だったのはもっと不思議です。リベンジマッチお待ちしてます。
ε
ベータさん。方向音痴ですぐ迷子になる私を救ってくれた方。ベータさんがいなければ私が芸術創造館に来るのに10年はかかっただろうし、家に帰るのに15年はかかったと思います。その節は本当にありがとうございました。すごく頼りがいがあって、きっと実家には弟妹が50人ぐらいいるんだと思います。お名前は理系なのにバリバリの文系らしいです。不思議ですね。気が合うって言ってもらえて嬉しかったです。
ふぉにゃ
フォーニャー。動作の1つひとつがかわいい人。私の髪をふわふわに巻いてくれる人。メイクに関する知識と技術が豊富で、やったことないとか言いながら完璧に出来る。さすがすぎる。役としての絡みはないけど、普段から仲良くしてくれる。すごく嬉しい。うちの大学に来た理由の半分は、大阪にUSJがあるかららしい。ハリーポッターが好きらしい。素敵だね。私はUSJの中ではスペース・ファンタジー・ザ・ライドが好きです。
亜臨界橋本濃度
ニトロさん。芸名が文系にはよく分からない方。いつもニトロさんの声量に圧倒されます。すごく背が高い。私と30cmも差があるらしい。この前段上げに登って私のことを見下ろしていたときは、超大型巨人に襲われるような恐怖を感じました。見た目とは裏腹に家庭的で、裁縫からアクセサリー作りまで出来る、すごく器用な方です。演技の引き出しが豊富で、方向性を見失った私の相談にたくさん乗ってくださり、本当にありがとうございました。
雑賀厚成
シドさん。大きいくまのお人形さんのような安心感のある方。かわいくて、天然で、面白いです。シドさんの代役が面白すぎて、演技に集中出来なかったことは数知れず。指からビームを出して、宇宙と交信してるらしいです。かっこいい声とかわいい動きのギャップで、みなさんもきっと心を鷲掴みにされるはず。ちなみに、私のいとこと高校時代の知り合いらしいです。どういうこと??
たぴおか太郎
ナスカ。いや、たぴ。呼び方が定まらない人。本当にすごい。センスがずば抜けすぎてて時代が追いつけない。声の出し方や動きを研究してる。真面目と書きたいところだけど、書いてほしいと言われるとやめとこうと思う。すごく包容力のある人だと思う。きっと前世は私のお母さんかお姉ちゃんだったのだろう。ちゃうかシナモロールの民として、たぴともシナモングッズを見せ合う儀式をした。楽しい。
岡崎仁美
私。トマトとオレンジジュースが好き。世間からずれていることに気づき始めたときにちゃうかに入り、最近はそうでもないと思っている。進む道と役の方向性は見失いやすいが、きっと本能とその時の気分のままに進んでしまうからだろう。初の役者にも関わらず今は緊張していないが、本番はきっと足がガクガクなのだろう。
水琴冬雪
ベガ。いつまで経っても掴みどころのない人。しっかりしていると思ったら意外とそうでもないし、そうでもないと思ったら意外としっかりしている。どっちなんだ。真面目な役からぶっ飛んだ役までこなせるのは本当にすごい。すぐふざける34期の手綱をにぎれる数少ない存在であることは間違いないが、ベガ自身もふざけるため、1度逸れた道を元に戻す人がいなくなる。どうしよう。
夕暮児
こたち。役に真摯な人。どんな役でも真剣に向き合って、100%の演技を120%に出来るところがすごいと思う。すごく優しい人。荷物がたくさんあって困っていたら半分持ってくれた。稽古始めたばかりで発声が上手く出来ずに困っていたら声を掛けてくれたし、アドバイスもしてくれた。ありがとう。そういう優しさをあたりまえみたいにくれるこたちは、心から優しい人だと思うし、尊敬してる。自分もそんな人になれるようにがんばりたいと思う。
佐々木モモ
コロネさん。きっとちゃうかのお母さんな方。毎回稽古で話しかけてくださった。すごく嬉しいです。もっともっと仲良くなりたい。かわいい衣装作っててめっちゃすごいです。いつもにこにこ笑顔で優しいけど、怒る演技は迫力があって、そのギャップにドキドキしちゃいますね。そばにいるとあったかい毛布に包まれてるみたいな、安らかな気持ちになれる、包容力のある優しい先輩です。
中津川つくも
つくもさん。カメレオン俳優ってこういうことなんだなと思わせてくれる方。今までに少なくとも保育園の先生とアイドルを経験してきてると思います。たぶん。動きの1つひとつが綺麗で計算し尽くされてるけど、それを自然に見せられる人なのだろうと思っています。いつも優しくしてくださって、本当にありがとうございます。でも1つだけ言わせてください。私は5歳児じゃないです。
黍
きびさん。アイデアがいっぱい詰まってる方。演出も脚本も役者も出来るすごい方。本チラのイラストが素敵過ぎました。きびさんの頭の中の引き出しはドラえもんの四次元ポケットぐらいあるのだと思います。アドバイスも的確で、自分が何をどうしたらいいのか分かりやすいです。すごいです。きびさんが私を今回の役に選んでくださったおかげで、推しがライブで役の名前を言ってくれた。最高のファンサもらえました。本当にありがとうございます。
アリリ・オルタネイト
イルル。笑顔が弾けるかわいい人。共演シーンがあったり、共通の趣味があったりして、今公演で1番仲良くなった人。ライブも一緒に行ってくれた。日本語ではなく関西弁と関西人としてのスキルを習得している。なぜ。ツッコミが完璧すぎて、生粋の関西人として負けている気がする。演技の面では、セリフを繰り返し練習していて、努力をあたりまえみたいに出来る人なんだと思う。すごい。私の役作りに付き合ってくれてありがとう。何か掴めた気がします。
すぺしゃるさんくす
宙稚勇貴
くうやさん。なんでも出来るスーパーマンみたいな方。ちゃうかに入ったのが遅かった私にいつも話しかけてくださったし、演技の相談にもたくさん乗ってくださって本当にありがとうございました。あっちでアドバイスしていたと思ったら、こっちでもアドバイスしてて、気付いたらキャスパの指導までしていて、タスク量の多さにびっくりします。果たしてくうやさんは何人いるのだろうか…。それとも分身の術…??
母によるとちゃうかに入ってから私は今まで見たことないぐらい楽しそうらしいです。こんなに幸せな環境にいれることが本当に嬉しいです。「ゴミたちの日」全力でがんばります!よろしくお願いします!以上、カヌレでした!
1 note
·
View note
Text
「演劇人コンクール2022」第一次上演審査 前半 総評
6月に行われた「演劇人コンクール2022」第一次上演審査、前半の総評を公開いたします。
* * * * *
前半選評
平田オリザ
例年通り、審査員長として審査の過程も含めて記しておく。
本年は、初夏の第一次上演審査と秋の最終上演審査に分かれるため、一次審査では最終上演審査に進む二団体を決めるための協議を行った。
前半週の課題戯曲、ケラリーノ・サンドロヴィッチ氏の『フローズン・ビーチ』は、本コンクールの二十年以上の歴史の中で、はじめて戦後生まれの作家の書いた作品である。これについては戯曲選定段階でも大きな議論になったが、私としては本作は、それだけの普遍性を持ち、コンクールにふさわしい作品だと考えて課題戯曲とした。
ただし、この戯曲を上演するには「バブル経済」という八十年代末の状況に対して、どう距離を置くかという視点が必要になる。いや、必要になるだろうと私は考えていた。
もしもこれが百年前に書かれた戯曲ならば、演出家は、その書かれた時代についてもっと注意深くなるだろう。しかし、まだ地続きの三十数年前の出来事については、意識的になることが難しかったのかとも感じた。
そのなかで、三村さんの演出は、俳優一人ひとりのせりふを、限られた時間の中で丹念に吟味し完成度の高い舞台となった。審査員は全員一致で三村さんを最終上演審査へと選んだ。
鈴木さんは本作を「好みではない」(文言は正確ではないかもしれない)とおっしゃっていた。しかし、指揮者のコンクールで抽選で選ばれた課題曲を「好き/嫌い」で取り組むことはしないだろう。演出家にも「得手/不得手」はある。不得手であっても、あるいは不得手だからこその何らかの策を見せていただきたかった。
一宮さんは、おそらくもっと技術のある方なのだろうが、どこか萎縮しているように見えた。
三橋さんもまた、小道具の使い方などが思いつきの域を出ておらず時間切れの感は否めなかった。
「バブル」との距離といった具体的な問題以前に、本作は純然たるコメディであって、オーソドックスに上演をすれば、とりあえず面白いという立て付けになっている。それは後半週の、きわめて抽象性の高い安部公房戯曲とは対照的な位置づけで、私としては、そのどちらが演出家の技量を見るのに適するのかという感心もあった。
もちろん、どちらにも一長一短があるが、本作で言えば、これをコメディとして演じないのならば、それはそれなりのロジックが必要だろう。三村さん以外の三作品は、いずれも、その点においても不満が残るものであった。
* * * * *
2022年、新しいコンクール
いしいみちこ
演劇人コンクール2022前半にご参加いただいた演出家の皆さま、お疲れさまでした。
今年から新しい形式となって、戸惑われたことも多かったと思います。十分な稽古を積んで臨むことができたこれまでと違い、1週間で戯曲を読み解き、演出プランを考え、たった1日の稽古で上演するというのは、なかなかにハードな形式です。それぞれ普段からどう演出やその手法に向き合っているかが試される場となったのではないでしょうか。しかしながら、戯曲を読み解くこと、舞台上に出現させたい独自のものを練り上げること、自分の中にあるイメージを俳優や技術スタッフへ渡す言葉を鍛えていくことは、演出家にとって必須の力でもあります。この新しい形式が、それぞれの力を試す場になり、学びの場にもなっていればと思います。役割として講評を書いてはいますが、一観客としての感想とお考えいただき、ご自分の方法論やこだわりは是非とも大切にしていただきたいです。
最後に、Covid-19感染拡大3年目の今年、様々な対策を施して有観客のコンクールを実施してくださったコンクール事務局及び江原河畔劇場の皆さまに、心より感謝申し上げます。
〇鈴木佳奈子氏(ORU)
まず、このようにテキストレジーをした意図が観客に伝わり難かった。全体を市子の夢として構成しようとしたと私は感じたが、それによって作品のカラーや主題が際立ったとは思えなかった。バブル経済期の日本人の狂乱、プリミティブな欲望、人の生命に対するなんとはなしの軽い扱い。これらを舞台上にどう出現させるのかがこの作品の生命線だと思うが、それが十分に達成される演出にはなっていなかったように思う。市子という人物の視点から構成するというのであれば、市子の偏向的価値観やものの見方、千津との関係・執着や、愛という人物への憎悪といったものを描き出すことができれば、市子に焦点化することが作品の再構成につながったかもしれない。途中、市子の高校生時代の「放火」について語る部分をリズムを刻んで歌うという演出があったが、そこにも主題との有機的なつながりは感じられなかった。鈴木氏の上演順は一���最初だったが、もし発表順序がもっと後だったら、つまり作品の内容について熟知した上で鑑賞したとしたら、違った見え方があったかもしれないと感じた。
〇一宮周平氏(PANCHETA)
舞台下手にバーカウンターがあるのが、昭和の泥臭さから抜けたバブル期の浮かれた空気感を醸し出しており、舞台美術として有効だと感じた。しかし、中央にいる千津が手に持っている電話がダイヤル式だったのは、南の島にレジャーランドを作ろうとする財力のある登場人物たちの背景とはマッチせず、ちぐはぐな印象を受けた。
課題となっている本戯曲の冒頭部分は、千津、市子、愛の認識のズレや感情の高まりによる微妙な会話のすれ違いが、掛け合い漫才的に展開することで笑いが生まれるように書かれているが、この「掛け合い漫才的」を成立させるための通底する無意味な明るさのようなものが、全体的に弱かったように思う。そのため観客は「この場面はきっと笑えるのだろう」と思いながら笑わないという不発感に終始することになった。中盤、音楽をかけて千津と市子が話す場面、照明を落として蠟燭を行き来させ、秘密を共有している二人を表す演出があったが、明かりによって時間的にも空間的にも区切られてしまい、萌の登場による曝露の衝撃やスリルがストレートに伝わってこなかった。戯曲に対する向き合い方は誠実なので、戯曲の持ち味を活かす読み解きが次の段階へつながる方途となるように思う。
〇三村聡氏(バングラ)
戯曲の言葉が俳優によって身体化されて、血の通った生き生きとした言葉として舞台上にあり、登場人物それぞれの特性までをも十分表現するものとなっていて群を抜いていた。同時多発に展開される会話も場のリアリティに貢献していた。戯曲のコミカルな側面を現出させるだけでなく登場人物の軽薄さ、悪意、狂気、及びそれとは真逆の愛らしさのようなものも同時に実現されていて、複眼的に人間を表現できていたと感じた。テキスト全てを上演するのではなく、演技やストーリーの進行をダブつかせる冗長な部分は潔くカットし、観客の想像力の歯車をスピード感をもって回し続ける選択には演出の力量を感じた。
一つ気になったのは、愛が引きこもるトイレが舞台上にあったことだ。舞台上にあることで愛が一度退場し、萌となって出てくることを観客に見せること、異化することが必要であるのかどうか疑問であった。また、トイレの位置が近いために、聴かれてはならないはずの会話が十分聞こえる声量で話されるという結果となり、リアリティを削ぐ形になったように思う。ただ、そういった部分を気にさせないほどの、スピード感、躍動感が一貫して舞台上にあったのは見事だった。
〇三橋亮太氏(譜面絵画/青年団演出部)
上演が始まる前から搬入口が開放され、外の景色を観客に見せていたのだが、その意味は何だろう。劇場という虚構の空間のなかに外の世界を取り入れるということは、2022年の現在とのなんらかのつながりを演出するのかと思った。1980年代のバブル期からその崩壊、最後には自然の営為によって経済も生活も海に沈むこの作品は、Covid-19感染拡大によって社会が頓挫している現代との共通点がある。その展開を期待したのだが最後までその部分の追及は感じられなかった。現実から虚構に入ったものの、終演の際に再度現実へ移行することもなく、外部を取り込むという演出が宙に浮いたまま放置されたような気分になってしまったのは私だけだろうか。舞台美術として風船を床に置いて部屋や廊下の境界を作り、それを俳優が踏み荒らすという美術だったが、風船という素材が子供っぽさや可愛らしさを想起させ、この作品の持つ毒のようなものとマッチしないように感じてしまった。劇中、台詞の唱和や繰り返しが行われていたが、それによって観客になにを想起させようとしているのか私には理解できなかった。もし繰り返しや唱和を演出として取り入れるのであれば、もっと徹底してやっても良かったのではないか。台詞をもっとテンポアップし、間をうまく使ったら繰り返しや唱和の意図や効果が見えて来たのかもしれない。
* * * * *
「読むだけでおもしろい戯曲を演出することのむずかしさについて考えさせられました。」
志賀玲子
課題戯曲『フローズン・ビーチ』は、読み物として読むだけでも、頭の中で登場人物たちの会話が炸裂して、強迫神経症的な独特の世界が急ピッチに展開していく面白さがある。舞台はカリブ海と大西洋の間にある小さな島の海辺に建てられた3階建ての別荘で、課題となった第一場は、バブル景気直前の、1987年夏の深夜という設定である。
上演審査にあたって、私は戯曲を読んで上演に臨んだので、あらかじめ、自分なりの戯曲世界が頭の中に立ちあがっていた。何が起きるか、何が話されるかは知った上で4人の演出家の作品を拝見することは、演出とはどういう仕事なのか、大変よくわかる機会となり、興味深い体験であった。
鈴木佳奈子さんの演出作品は、冒頭から意表をつかれた。<コレオグラフィー・モンタージュ>と鈴木氏によって名付けられた自身の作劇法なのか、戯曲に書かれた会話劇は始まらず、抽象的な空間で、切り取られた台詞の断片による、前後の脈略のないイメージショットのような世界が展開された。市子のエキセントリックさを中心にすえるというアイデアは興味深いが、課題戯曲の物語が観客に伝わらないことを承知の上で、このように大胆に翻案する意図は何か。具体的な物語を抽象化するならば、なるほどと思わせる明確さで戯曲の世界観や感覚を示してほしかった。
一宮周平さんの演出作品は、私の脳内劇場よりも、残念ながら全般的に平板に感じられた。劇の冒頭、物語の序章としての不穏な予感がうすく、これから始まる世界への期待感、緊張感がかきたてられない。会話の応酬による<うねり>が弱いため笑いのツボが流れてしまい、登場人物それぞれの奇妙さ、異常さが立ち上がってこなかった。会話劇のスピード感やリズム感は、戯曲の解釈によって様々に設定可能であるとは思うが、今回の一宮さんの解釈におけるそれらは的確だったろうか?
三橋亮太さんの演出作品は、戯曲冒頭のト書きにある空間設定と前後(手前と奥)が逆転した部屋の配置で上演された。戯曲では奥にある設定のバルコニーとベッドを観客の眼前に、下手設定のトイレを中央奥に置くことによって実現したかった戯曲解釈、演出効果がわからなかった。カラフルな風船でバルコニーらしいエリアをつくり、バランスボールを椅子として使い、登場人物が風船をふくらませしぼませる。風船が何かのシンボル(まもなく始まるバブル景気?)のように使われているのだが、その効果と帰結点が見えてこなかった。小さなアイデアが演出の鍵となっていくことはあると思うが、その取捨選択はもう少し厳密にする必要があるのではないか。
三村聡さんの演出作品は、見終わって素直に「おもしろかった!」と口をついて出るものだった。会話のスピード、間合い、ニュアンスのすべてが丁寧に検証され、ひとつの台詞に次の台詞が確実に積み重なる。台詞の連なりには、俳優の言外の表情や態度、行動が加味され、なぜこの人物がこんなことを言うのか、いちいち腑に落ち、その結果、戯曲の面白さ、不穏さがしっかりと現前した。優れた舞踊が超絶的な技巧をもってしても、あたかも特別なことは何もやっていないかのごとく自然で軽やかであるように、三村演出は緻密に自然で、粋な会話劇に仕上がっていた。俳優歴の長い三村さんのキャリアが存分に生かされた演出であった。
* * * * *
演出家のやるべきこと
中島諒人
今回の演劇人コンクールは、今までとは異なるルールとなった。演出家による俳優の演技造形のみが審査の対象であり、その造形も一つの芝居の全体ではなく一場面のみ。芝居は終わりから逆算して構成する部分が大きいから、芝居全体の構成というよりは現場の交通整理力の巧拙が審査の対象になってしまうのではないかと危惧した。また照明、音響、衣装などについては、基本的にアプローチができない。演出家の力量は、この方法によって本当に測れるのだろうか。
とはいえ、シーンの方向性を演出家が現場の皆に示し、俳優と意思疎通して演技を作っていくのは芝居づくりの土台であり、それがあってスタッフワークの他の要素も決まってくる。何もない裸の空間で場面を作ることから、芝居づくりの全てが始まる。そういう意味で今回の審査方法は、現場の作業手順に沿ったものと言える。
演劇の言葉は、一見朗らかに会話が進んでいても、そこに必ず悪意や企みが潜んでいる。演劇は関係を扱うもので、つまるところその場にいる者のマウントの取り合いの様を描いている。見えない力のつばぜり合いのような応酬を、あるいは場面に外からかかっている時代や社会の力を見つけなければならない*1。一週目課題戯曲『フローズン・ビーチ』では、テンポの良い邪気のない会話が展開しているように思える。その中に差別や憎しみ、苛立ちの連鎖を見つけることができたか。この発掘のような作業は、通常次の二つのステップを行ったり来たりしながら深められる。
初めの段階は演出家が一人で読む。繰り返し読み、最後から逆算して考える中、一人ひとりの登場人物の全体展開の中での役割と人物像が見えてくる。登場人物の芝居始めでの状態(物語の前提)を見定め、展開について不可解なところは仮説を立て、関わりの中で変化する言葉や行為の推移を見定めようとする。(演出家による読解から見立ての段階)
次の段階は、この作業を俳優とともに、彼らの語る言葉や動きの中でていねいに繰り返し、先の見立てを確認し修正し深めていく。全体の流れと各人の機能を俳優に示し、適宜俳優に指示を与えてそれぞれの登場人物の性格を少しずつ際立たせていく。この過程を通じて、登場人物個々の性質、各人の言葉や行為の連鎖が少しずつ明瞭に見えてくる。平板に見えていた関係が急激に立体化してくる瞬間である。俳優も自分の役の性質や変化について発見があり、演出家にも発見がある。双方でその発見を共有しながら、俳優は言葉や行為の調子を自覚的に選び、試す。演出家は、俳優の試みについてコメントしていくことで共同作業が深まっていく。生まれかけている関係をいっそう浮かび上がらせるために、音楽やセットの使い方を工夫することも必要となる。(繰り返してやってみて、演出家と俳優がともに発見する段階)(ここで台本上の納得できないこと、わからないことをはっきりさせ、それへの回答を用意しなければならない*2。)
この二つを繰り返すことが、作品作りを深めるために不可欠だと私は考えている(もちろん演出家と俳優の関係の中で、共同作業のあり方も変わる)。今回のコンクールの時間の制約の中、このような作業がどこまでできるかというと、ほんの入口の入口程度のことであったろう。しかし、三村さんの作品からは上に書いたようなプロセスの痕跡、演出家と俳優の共同作業と発見のイキイキとした過程をつぶさに感じることができた*3。
*1 『フローズン・ビーチ』に漂う苛立ち・投げやりな感覚はバブル経済の無根拠な盛り上がりに由来するものだが、そのことを踏まえている上演はなかったように思う。この戯曲はバブル経済と人間の関係を見つめようとしている。もし今この作品を上演するなら、その事象に何らか触れることが不可欠だと私は思う。その手並みに演出家の技量やセンスが問われることになるだろう。それは一週間の準備期間だからできなかったということではなく、コンクールの場である以上、演出家としてやるべきことだ。
*2 もう一つ具体的な話になるが、家の主の一人である愛が初登場し、無断で国際電話をかけている来訪者・千津と目が合う場面。家人がいないことをいいことに高額な国際電話をかけている無礼についての二人の交錯する心情に意識を払えている上演もなかったと思う。回答を見つけることよりも、わからないことを見つけるほうが難しい。あるいは、高額になってしまう国際電話の緊張感を、スカイプやズームに慣れたみなさんは知らなかったということだろうか。
*3 審査の場でも触れたが、「カニバビロン」をめぐる騒ぎが、直前のやり取りに起因する愛の市子へのムカツキから生まれていることが感じられたのは、三村さんの上演だけだった。そう解釈しなければいけないというのではない、そのようにやりとりがビビッドになることが肝心なのだ。発見がある稽古は楽しい。一つの発見は次の発見を生む。だから演劇はやめられない。
1 note
·
View note
Photo
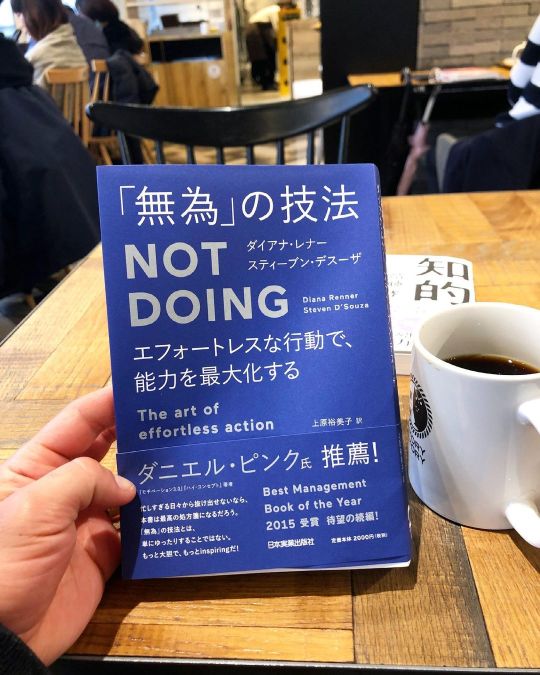
#読書 #無為の技法 一年前に読んだ本のメモが途中だったので再読。 去年読んだときの印象は��く残っていなかったけど 今読むと内容の深みがとても腑に落ちてくる。 この数ヶ月、緊急事態宣言のおかげで 心穏やかに、執着を手放して、ゆとりある時間を過ごせてるおかげだと思います🙏✨ #読書メモ #大切なのは水ではなく流れだよ風が動物たちが鳥たちが虫たちがそして人季節天気石や大地やたくさんの色が川になって流れている #しないということは不安や無気力や決断力のなさから生じる行動の欠如ではない押すことでもなければ引くことでもない逆らわず委ねてともに歩いてみるそうすることで力みがとれ自分がかかわっている状況に対して意識が開く #やらないよりやる方がいいに決まっているという発想は私たちを翻弄し疲弊させる #無為でいるためには自分は他者の力が作用する世界にいるということを理解する必要がある私たちに必要なのは岸にしがみつこうとする手を放し取り巻く世界の自然なエネルギーに乗ってみることだ #私たちに必要なのは身構えず無理に押し通そうとせずエフォートレスに受け入れていくことではないだろうか #必死になればなるほど心身の視野が狭くなり柔軟ではなくなるサイドブレーキを入れたまま運転しているようなものであのタスクこのタスクと頻繁に切り替えながら進めていくと何かを完遂した満足感が薄れていく機能障害に陥りがち #しなければならないの同義語は執着 #人と時間との関係は誰がその時間を所有しているのかという基準で左右される #仕事の複雑さに対してスピード勝負で解決することについてその最大の悲劇は自分と同じ時速で動いていないものを認識できなくなることだ #機械的だけれどボヤけた時間感覚で生きているうちに大切な人との距離が開いてしまうのだ #未来を考えるから不安になるのではない未来をコントロールしたいと思うから不安になるのだ #自分の役割に執着しているとそれをアイデンティティと同一視してしまうことがあり役割と自分自身を区別できなくなると人は役割以外の自分を犠牲にして仕事に過剰にのめり込みやすい #目的もビジョンもなくただ忙しくしている機能不全な状態を多忙馬鹿シンドロームと呼ぶ #著書ティール組織は今もビジネス用語に製造の比喩が色濃く残る印象を指摘している機械の比喩表現を用いることは組織とそこで働く人々を非人間的にし入換や交換可能な部品として扱う要らなくなったら捨てるモノと化す #複雑で不確実な現代社会に求められるリーダーシップとはリーダーとしての我を出さずクリエイティブキャパシティのための余地を差し出すことではないだろうか #行動しないコントロールしない介入しないリーダーがしない無為を選んだ結果としてそれ以外のメンバーの創造的な活動が開く #あがこうとせず単なる許容でもなく逃げたい直したい突き進みたいという欲望も超えてただ完結した瞬間として純粋に在ること #私たちは行動することに執着している少しでも自分の存在を主張し少しでも忙しくしていようと駆け回ることで自分の内側で聞こえる声を締め出している #自分自身の声が聞こえていれば他人の人生に対する意識も芽生える #待っているときに自然と生じる感情はふだん私たちが何を気にしているかということの表れだ無視せず認識し向き合ってみると発見がある #しっかり握りしめることで人は強くいられると思う人もいるが手を放すことが人を強くすることもある #抵抗をやめすべてを掌握したい欲求を手放せば新しい可能性を信じてオープンに向き合うことができる自分の力ではどうにもならないと受け入れるとそこに自由の感覚が生じる #手放さなければならないことを知っているかどうかいつ手放すか知っているかどうかそれが創造的ブレイクスルーの鍵だ #私がしていることを私は知らない私が向かっている方向を私は知らないけれどこの道を行かねばならないことはわかっている行き着く先がどこであるとしても #あなたがすべきことはあなたの仕事をすることであり結果を出すことではない結果のために働いてはいけないただ漫然としていてもいけない自分としっかり向き合い自分をなすべきことをする他の何かに執着はしない成功にも失敗にも心を乱さない平穏な心こそ真のヨガである #この世で最も柔らかいものがこの世で最も堅きものを押し流し超えていく #レガシー思考とは決断や行動の際には必ず未来の世代と環境と持続可能性を考慮に入れるよき祖先となることと過去に行われたことから学びそれを踏まえて失敗の繰り返しを防ぎこれまで語られたストーリーを守りながら新しいページを加えていくよき子孫の両者の視点を併せ持つこと https://www.instagram.com/p/CPaU_nQLq5a/?utm_medium=tumblr
#読書#無為の技法#読書メモ#大切なのは水ではなく流れだよ風が動物たちが鳥たちが虫たちがそして人季節天気石や大地やたくさんの色が川になって流れている#しないということは不安や無気力や決断力のなさから生じる行動の欠如ではない押すことでもなければ引くことでもない逆らわず委ねてともに歩いてみるそうすることで力みがとれ自分#やらないよりやる方がいいに決まっているという発想は私たちを翻弄し疲弊させる#無為でいるためには自分は他者の力が作用する世界にいるということを理解する必要がある私たちに必要なのは岸にしがみつこうとする手を放し取り巻く世界の自然なエネルギーに乗っ#私たちに必要なのは身構えず無理に押し通そうとせずエフォートレスに受け入れていくことではないだろうか#必死になればなるほど心身の視野が狭くなり柔軟ではなくなるサイドブレーキを入れたまま運転しているようなものであのタスクこのタスクと頻繁に切り替えながら進めていくと何かを#しなければならないの同義語は執着#人と時間との関係は誰がその時間を所有しているのかという基準で左右される#仕事の複雑さに対してスピード勝負で解決することについてその最大の悲劇は自分と同じ時速で動いていないものを認識できなくなることだ#機械的だけれどボヤけた時間感覚で生きているうちに大切な人との距離が開いてしまうのだ#未来を考えるから不安になるのではない未来をコントロールしたいと思うから不安になるのだ#自分の役割に執着しているとそれをアイデンティティと同一視してしまうことがあり役割と自分自身を区別できなくなると人は役割以外の自分を犠牲にして仕事に過剰にのめり込みやす#目的もビジョンもなくただ忙しくしている機能不全な状態を多忙馬鹿シンドロームと呼ぶ#著書ティール組織は今もビジネス用語に製造の比喩が色濃く残る印象を指摘している機械の比喩表現を用いることは組織とそこで働く人々を非人間的にし入換や交換可能な部品として扱#複雑で不確実な現代社会に求められるリーダーシップとはリーダーとしての我を出さずクリエイティブキャパシティのための余地を差し出すことではないだろうか#行動しないコントロールしない介入しないリーダーがしない無為を選んだ結果としてそれ以外のメンバーの創造的な活動が開く#あがこうとせず単なる許容でもなく逃げたい直したい突き進みたいという欲望も超えてただ完結した瞬間として純粋に在ること#私たちは行動することに執着している少しでも自分の存在を主張し少しでも忙しくしていようと駆け回ることで自分の内側で聞こえる声を締め出している#自分自身の声が聞こえていれば他人の人生に対する意識も芽生える#待っているときに自然と生じる感情はふだん私たちが何を気にしているかということの表れだ無視せず認識し向き合ってみると発見がある#しっかり握りしめることで人は強くいられると思う人もいるが手を放すことが人を強くすることもある#抵抗をやめすべてを掌握したい欲求を手放せば新しい可能性を信じてオープンに向き合うことができる自分の力ではどうにもならないと受け入れるとそこに自由の感覚が生じる#手放さなければならないことを知っているかどうかいつ手放すか知っているかどうかそれが創造的ブレイクスルーの鍵だ#私がしていることを私は知らない私が向かっている方向を私は知らないけれどこの道を行かねばならないことはわかっている行き着く先がどこであるとしても#あなたがすべきことはあなたの仕事をすることであり結果を出すことではない結果のために働いてはいけないただ漫然としていてもいけない自分としっかり向き合い自分をなすべきこと#この世で最も柔らかいものがこの世で最も堅きものを押し流し超えていく#レガシー思考とは決断や行動の際には必ず未来の世代と環境と持続可能性を考慮に入れるよき祖先となることと過去に行われたことから学びそれを踏まえて失敗の繰り返しを防ぎこれま
23 notes
·
View notes
Text
馬鹿げてる。
何でなったこともない、男性の体で生きたことがない経験したことがないのに自分は男だと確信をもってそう思えるのかわからない。
ジェンダーアイデンティティなんていうのは心理的な枠組みであって、心の中のものだ。それを身体という自分自身を形作る表面に放出したところで性別は変わらない。あなたの臓器や骨格や体内の水分量や臓器の脂肪分なども含めた性差は変わらない。性別は心で感じているものが全てで体を蔑ろにしたセルフIDの考え方が浸透しきっているから性別を変えられる、異性になって生きていくことはできると思い込んでしまう。そんなの間違いだ。心は体じゃない。今の社会は境界のないイメージの世界だとわたしは思う。何でもかんでも共感し合い、感受性も何もかも同じチャンネルを共有しているように思い込む。イメージの中で私たちは他者と共存していると思い込み、イメージの中の他者に怒り悲しみ絆を感じている。そのことを無視している。自分の境界も希薄であり、窮屈である。自分の感じているものの違和感や苦しみの正体を知ろうとせず、それを全て心の中に感じているぼんやりした何かやあるいは不安や疎外感から、原因を直接性別のせいだと思い込もうとする。それを形成する性役割やその生きづらさや生きにくさが
実体としての臓器や遺伝子を含めた身体があるのに、男性的女性的といった社会から要求される性役割やそれに応じた女性像男性像に従うことが苦痛である場合、逆の性別になれば解決できるだとか自分は望まない体で生まれてきてしまった異性なのだと感じ取り、そうして異性として扱われたり自認を尊重されることでその人がようやく安心感をえたり救われるという社会ってどうなのだろう?
自分の感じるジェンダーやジェンダー表現が噛み合わない、ジェンダー表現を受け入れない社会に苦悩することもあるだろうが、そもそも
しかし、そうした適合することに拒否感を覚えたり自身のジェンダー表現を受け入れようとしない社会をひもとくとそこにはミソジニーと女性差別、ホモソーシャリティの問題が基盤に存在する。男性主観で男性の感じ方のみが正しい社会の中で、女性がそうした差別の実態や構造にアクセスすることは難しい。
また、感じ方だけが全てであり、それを直接今感じている原因であるかのように
そもそもまず異性のジェンダー表現は身体性別に等しいものと見なすことは全くの間違いだ。
本当の性別人々が生きにくい枠組みがすでにこの社会に存在していて、その人たちが旧的な枠組みから外れた新しいトランス ジェンダーという枠組みを用意することも正しいと思えない。
なぜならばトランスジェンダーの人々は結局異性のジェンダー規範を再生産しているだけでジェンダー規範を強化しているからだ。
性役割をただ異性のものに交換しているだけ。その性役割というのは搾取や支配を正当化する構造であり、性役割そのものがそうした支配と隷属の関係と、それらの歴史を見えなくする蓋のようなものである。それらが差別であると認識されず、差別を受けている女性という当事者が軽んじられ、差別を受けていることや男たちは間違っていると告発するだけで「それはあなたの思い込みだ」「そんな言い方はないんじゃないか」「男性への差別だ」と言われる。トランス差別だ!を唱える人たちもこれと全く同じだ。
性の多様性だとかいっているけれど全く多様ではない。
異性の性役割やジェンダーに適合したいのに社会が云々、孤独だ孤立しているトランス差別だ云々と唱えている人たちをみていると、本当に無神経でさすが男だと言いたくなる。あの人たちはなぜセクシーな女性的な振る舞いがしたいのだろう。それが差別的な記号であると知らないからだ。そのような記号を踏襲した女性ヒロインやそれが好きな物なら尊重してあげようよと言っているのも男だ。それは女からしたら差別なのだ。それを求められ、そのような記号的な存在とみなされ、男にとって快い範囲内の振る舞いやあからさまな蔑視や使い捨ての性対象として私たち女は男に用いられてきたからだ。いまだに女性は金にがめつい、イケメンには股を開く、性犯罪加害者でもイケメンなら無罪だというような蔑視は至るところで見受けられる。女性差別を主張する女性は醜い年増で若い女に嫉妬している。男側に視野を広げて男性も辛いですよね、という配慮や優しさが無いと賢い女ではない。至るところで私たち女性は無知だという設定で上から目線の説教を食らわされたり事あるごとにマンスプレイニングを食らう。鬱病で苦しい時病院に行った時ほとんど話も聞かず、怪しい治療のセールスをされたり「その程度のことで苦しいのか」という対応をされる。女性の性犯罪被害の話や性的対象とみなされる苦痛を訴えても、怒りを直接語ると感情的だと嘲笑される。女性の痛みに対して医療は鈍感であり、医療の性差が考慮され研究されるようになったの。男が女性に対して接する時の親切の中にも、見下しや蔑視感情がある。自分の気持ちを満たしたいための感情の吐口である場合や、ただ女と話したい、気分良くなりたいという感情があることもしばしばだ。それは女性にしかわからない感覚だが、それは思い込みだ、繊細すぎる、病院に行ったほうがいいなどと言われる。常に女性の感受性はずれがあるも��という前提があり、気に食わないものをただ非難したいだけだとか、イケメンなら許すんだろうなどという偏見を飛ばされる。女性はしたたかで計算高く、高飛車で、あるいは男をたぶらかし、コケティッシュな振る舞いで翻弄するファムファタール的な記号は都合よく従ってくれる、暴力によって屈服させられることが可能な男からしたら、許容する範囲でワガママに振るまう可愛い女(でも自分がいなければ生きられない弱い存在)は素晴らしい存在なのである。長くファッションではそのような被虐的な立場であることを喜ぶように見せる観念が女性ジェンダー服に染み込んでいる。それは男ウケのいい服装として堂々としている。胸元だけ穴が���いていたりオフショルダーだったり、肩だけ透けていたり、ホットパンツだったり。コルセット風ワンピースやボディハーネスだったりの類もそうだ。そうした適度に『扇情的』な要素を含んだ服が女性を縛り付ける価値観であることをかわいさで覆い隠している。女性は展示品である。自分の個性を表明するために、わざわざそのような隷属的な価値観の服装を可愛いもので個性的で自分らしく生きることを肯定してくれるものと思わされている。逆に自分の個性や癒しや自己表現が自身の才能や能力やバックボーンなどに由来するものではなく、ファッションやメイクなどの装飾でしか自信を得られない。それは全て女性が装飾、それも男目線で構築された女性を支配するための記号で作られた価値に沿っていなくては人間以下であると社会的に定められていることと同義である。私たちは差別のプールに浸かりながら、自らその水を自分たちで再生産するよう、プールから出られないように仕向けられている。
しかし、私の見たところトランスパーソンの自認女性はそうした扇情的な(男から見て)服装やロングヘアだったりといいったホットな女性像をまといたがる。そうした扇情的な服などを女性のみがきることを許された服だという思い込みがあるのか?そうした性的な意味も含めて男から見た男の価値観に沿った魅力に満ちた女性こそが本当の女性であるという発想があるからなのではないだろうか。つまり、かれらもまた同じように女性を固定化された家父長制に都合のいい支配の記号だけを抽出した存在として、表面だけを女性とみなしているのである。また、トランスパーソンの自認女性は完全な女性だと支持している人々にとっても女性とは着飾る生き物であり、性的魅力に溢れた姿が正しい女性の姿で、女性というのはファッションやロングヘアであるとみなしているからだ。そのような女性像はメディアや創作、映画にも氾濫している。しかしそうした表現こそが女性差別で女性憎悪だと公然と言われることがない。ドラマでは高飛車でヒステリックな金持ちの女性は面白おかしく描かれ、舌足らずで幼稚でワガママな女性が男性を振り回す。いつも考えが足りなくて幼く、考えが足りずに失敗を繰り返す。それすらも可愛さの中に収納される。ハニートラップをしかける女性や財産目当てで玉の輿を狙うしたたかな女性キャラクターや、マウントを取ることを生きがいにしている女性や、素顔を隠して女性は足りない方がいいという発想がある。逆に馬鹿な方がいい、男の前で馬鹿を演じている女性はしたたかで賢いという想像を生身の女性たちが演じている。そうしたあざとい女性を同性がいやがったり、逆にあざとさをうまく演出する女性を同性が素晴らしいと支持することもある。世の中は腐っている。それはアニメの中でも同じだ。女子学生の制服の胸や股間の線が生地から浮き上がった絵が普通に存在し、それらが表現の自由というマジックワードによって擁護される。そうした絵がどれほど女性の尊厳を害するものであるかそうした表現が表現として成立していることは正しいのか?女性が怒りを語るとそのような絵を描いている人たちの仕事をフェミニストは軽視しているだ、絵に込められた思いを馬鹿にしているだ、いやなら見るな、絵に人権はないことを理解していないだと男たちは反発する。そしてお決まりのお気持ちだお気持ちだの連呼である。女性が差別を発信するだけで嫌がらせの対象となる。個人情報をばら撒かれる。執拗に自分の納得できるデータを出せと要求され、粘着される。馬鹿フェミだキチフェミとよばれ、精神病院に行けと言われる。性犯罪と結びつけるな、被害者を自分の主張のために利用するなんておぞましい。やっぱりおんなの敵は女だと性犯罪被害に遭わない立場からものをいう。アニメの中では女性たちが胸の大きさを比べて嫉妬し合う様子が当たり前にベタなネタとして描かれる。お互いの体型で嫉妬し合い、体重で一喜一憂し、潰そうとしていて、承認欲求の塊で、知性がない存在のように描かれる。痴漢被害を告発した女性や夫のDVで苦しんでいたり、妻が家事全てをやるべきという価値観から夫の世話や片付けをしないことや全ての尻拭いを無償でさせられている妻がSNSで怒りを投稿すれば女性器呼ばわりされて『マンカスゴキブリ』『専業主婦は寄生虫』『養ってもらっている分際で文句を言うな』というコメントが相次ぐ。挙句発言者の女性アカウントの顔や他の日常の投稿なども掲示板で晒されて品評される。アイドルをプロデュースするゲームには女子小学生や中学生のアイドルまでいる。女性差別的な価値観は当たり前に蔓延し現実の女性もアニメキャラクターのように属性化された存在として分類されている。自分の「需要」を理解してあざとく振る舞う女性は喜ばれる。男性の立場になって発言する弁えられるエマワトソンのようなフェミニストが真のフェミニストとして讃えられ、そしてそれ以外の男に奪われた権利を取り戻そうとする女性は女性の敵で足りない存在で、恋人も結婚もできない負け組で嫉妬している哀れな存在だと笑っている。けれど、そうした表明をしないだけで男は皆そのような幻想の中の女の姿やステレオタイプで女は足りない存在なのだというふうにこの社会が決めた通りに女を人間以下の存在と見做しているし、自分が単に不快になった時に突然黙ってみたり突然不快な態度をとって女性に機嫌を取らせようとしたり、女性が差別を語るとその発想や発言は間違いだと自動的に決めつけて笑ったり、女性が間違っているという前提で呆れた態度を発露する。社会的にも優位な立場であることは知覚している。アニメの中にはなんでも男の主人公に頼って甘える幼馴染がいて、すぐキレるのに短絡的な発想で失敗ばかりを繰り返し、生意気な態度をとっても結局は愛情の裏返しなだけで、突飛で無理くりな理由をつけて幼稚な発想で女性キャラクターたちは男性主人公が自分に好意を持つように迫る。女性たちに生理はなく、妊娠や流産や死産や中絶、同性愛者や性犯罪被害者は存在しない。また、そのような露骨な差別に満ちたキャラクターやなんでもいうことを聞いてくれる服従が約束された二次元の女性たちはその設定だけでも差別の結晶である。また、そのようなコンテンツは女性憎悪を招く。アニメやドラマや映画のように女性とは未熟で感情をコントロールできず、男に守ってもらわなくては生きていけない寄生虫で感情的な生き物だというふうに学ぶのだ。反発しても結局主人公を愛し主人公のことを必要とする女性キャラクターの存在は男がいなければ自力では生きていけないのだ。けれど、男にとってみればそうした女性は当然のようにコントロール可能な対象である。女性の隷属や無条件的な男に対する同意や賞賛や感謝を前提とし、そうした精神的ケアも含めた男にとって都合のいい存在であるとみなした関係性の構築をより強化する。社会的に蔓延している女性をコントロール可能な対象とする価値観がまた濃縮されるのだ。ストーカーが絶えないのも好意があるのにわざと反発して主人公を女性が創作物に多く、女性がコントロール可能な存在として描かれ女性をコントロール可能な対象として物扱いする社会だからこそ憎悪犯罪が絶えないのだ。アニメやドラマ、その制作者たちも当然女性を商品として扱っている。演じる女性の尊厳ではなく、キャラクターのことも女性を生きている人間としてみなさなち。実体のある尊厳のある人間ではなく、胸や尻や脚や扇情的なキャラクターと言ったようにバラバラの属性として分断し切断している。妊孕性でさえ性的なパーツである。実際アダルト業界では膣内射精やいやがる実の娘や生意気な上司を無理やり強姦して膣内に射精したり監禁して輪姦すると言った内容のビデオがシリーズ化され、レイプや盗撮や女子高校生がジャンルとして存在されている。酔わせてレイプしたり、女性に写真をばら撒くと脅すリベンジポルノが題材になることも知っている。トランスパーソンの自認女性は性犯罪被害の危険があるから身体女性と共闘できるはずで分かち合うことができるというのは大嘘だ。実際女性は身体が女性であるから差別をされ妊孕性でさえ性欲や征服欲を満たす存在として性的な利用価値を見出され、女性の恐怖心や絶望に陥れる様を見て楽しむ映像が出回っていて、盗撮映像がインターネット上で売り買いされ、身体が女性であるがために感情ケアを当然のように男たちは自分の周囲の女性に無言で求めてくる。性犯罪被害者の人権は皆無だ。電車には乗ることができない。酒を呑んで酔って自分を誤魔化して乗り切っても駅構内でぶつかられるし街中で空いた道を歩いていても後ろから突き飛ばされたりすれ違い様にジロジロと体型や顔を見られる。その苦痛やそれらが全て差別から派生した女性憎悪が引き金になっていることなどを告発しても思い込みだ自意識過剰だお気持ちだと言われる。女性が結婚するとキャリアが絶たれることや不利な状況に追いやられることが覆い隠され、家事などを無賃でこなすことをもとめられ、体調不良だろうとなんでも家事を妻任せだ。会社の上司や友人にはしないのに、妻の話を遮ったり妻がつわりで寝込んでいても平気で食事を作るよう要求して起こしたり名もなき家事を全て妻にやらせるのだ。そうした夫の無関心には女性差別が根底に存在する。私の父が家族共用パソコンでそうした履歴やビデオを保存し、家族写真のフォルダの中にさえ女性を強姦しているビデオの画像を保存していたように、言わないだけで多くの父親が女性の家族を疎ましい存在として邪険に扱いながらも精神的なケアを求めている。妻の都合や感情に対する配慮どころかそれすらも夫の視界にはない。それ以下の存在で、都合のいい時にプレゼントをわたしたり愛を伝えたりすればいいと思っているか、勝手に些細なことで怒っているんだと自分を哀れんでいたりするのだ。妻は同意なく自分の好きなタイミングで体に触れてもいい存在で、同意を得る必要さえないと思っている。選択の権利も余地も最初からない。私が同級生から性的な加害を受けた数日後も父は女子高生逆ナンパというタイトルの動画を見ていた。
トランスパーソンの自認女性と身体女性は全く違うどころか、女性であると認識し、女性になろうとして行っているメイクや服装、女性的と社会でみとめられた振る舞いをすること自体が女性への差別なのである。また、身体男性であることで意見や主張を間違っているものと咎められたり懲罰されてきたことから意見を話すことを恐れずにすんできた。直接的な感情の発露を認められてきた。また、身体男性として生きた経験は女性差別の蓄積でもある。もし単に性別違和があるならそれは脳の病気だ。しかし、性別は変えられる(実際は臓器に性差があるからそんなことは絶対に不可能だが)という幻想は徹底的に粉砕するべきだ。性別役割が徹底した社会の中にいきぐるしさがある人が自身をトランスジェンダーだと思うのならそれはこの社会が間違っているだけ、ともいえない。それは家父長制の影響とその本流から細分化した支流を含めた差別の複雑さや複合的な差別を無視したことになる。トランスパーソンの身体男たちは男だと。家父長制の中で優遇されてきたのだから、女性をコントロール可能な対象とみなす文化も当然疑問なく受け入れることができ、現在だって感情的な女性としての規範的な金型に沿わない女性を懲罰し、暴力で支配することや暴力をちらつかせることがどれだけ女性に『効き目』があるかも彼らは理解している。女性差別に染まっていない人間はいない。男は誰でも女性差別に対して無関心でいることや無関心でも生きていける立場を守られている。ケア要��として努めることを要求している時点でトランスジェンダーの人々は被差別対象ではない。好きな格好をしているだけで偏見の目で見られるなんて言う甘っちょろい苦痛なんかではない。それを人によって感じ方が違うから苦痛に客観的な視点や重さはない、どの人も守られるべきだと言う主張で、差別のもたらす弊害や女性の死を曖昧にするな。誤魔化そうとするな。お前らの感情なんかで私たちは消されてしまう存在ではない。共生という耳障りのいい言葉を使って侵襲しようとするな。お前たちにとって心地よい共生の中に私のような性犯罪被害者など存ないのだろう。反吐が出る、何が共闘だ。感じ方なんていう個人によって尺度の違うものなんかで、実在している差別の重みは消えない。お前らの感受性や視野にもその基礎や道徳観の根にあるものは家父長制を培養した憎悪が刻まれている。男としてどれほど優遇されているか?それなのに自分は弱者だと思い込むのは傲慢だ。そして優位性に基づいた感覚で女を裁量するな。女を名乗るな、女を奪うな。彼らの枠組みを保護することは自分を女性と認めない女性を懲罰的に見つめる視点や暴力性を沸騰させるだけだ。そうして守ろうとして配慮して譲ってやればやるほどヒロイズムに浸ってシス女性には私たちの苦しみなんてわからないだなんだと悲劇ぶるだけだ。女性憎悪に満ちた社会に対抗するために女性はどれほど傷ついても戦うことを強いられる。その中で死を選ばず生きることがどれほど過酷か。女性憎悪は解決されたものであるとみなし、露骨な差別以外は全てを除外し、女性の性犯罪被害そのものを例外視し、コントロール可能な対象とみなされ発言も全てを男より劣った亜流の存在とみなされ、花柄やハートや心配りや親切といった女性ならではの発想や特性をことあるごとに求められ制限されてきた私たち女性を別席に置いてきた男たちから、全てを奪い返さなくてはいけない。家父長制のその首を切り落として、私たちが生きる権利を取り戻しにいかないといけない。時計の針を逆回しにすることはいつでもできる。男たちこそ変われ!と言って何もしないでいるくせに男が少し平等だなんだとポーズをとっただけで理解してくださってありがとうございますと尻尾を振って理解してくれる男性を立派だと神聖視して救世主のように扱って応援するのはやめるべきだ。男の言葉を持ち上げるのも男こそ正統であるという思い込みによるものだ。その価値観こそ家父長制が作り出した女を支配下に置くことを許してきた足枷である。足枷をありがたがるのをやめよう。男が変わっているならとっくにこの世は変わっている。それでもこの世は変わっていなかった。そいつらは性風俗店で女を買い、スマホで女を虐待するビデオを見ることもできれば妻を無賃で搾取していながらそれを当たり前と思っている男たちだ。彼らは性風俗で溢れかえる繁華街や日々女性が殺されるニュースを見ても物騒な世の中になったとしか思わないし、それを見てもなんとも思わず素通りすることができる。そして電車の中では大股を開いて座り、大学進学は優遇され、高く設定された合格点に届かず志望校に行けなかった優秀な女性よりも劣った成績で進学し、妊孕性がないために就職や昇進も過大評価されている。男は無条件的にできて当たり前で成果を出せばそれは傘増しされる。女性の人権を奪ってあぐらをかいている男を見ながら男の認証や同意を求めようとするな。家父長制を処刑台に送り込まなければ私たちは殺され続けることを忘れてはいけない。差別を長らえさせることとは、私たちの今ある現実を無視することだ。
12 notes
·
View notes