#エミール・クラウスとベルギーの印象派
Photo
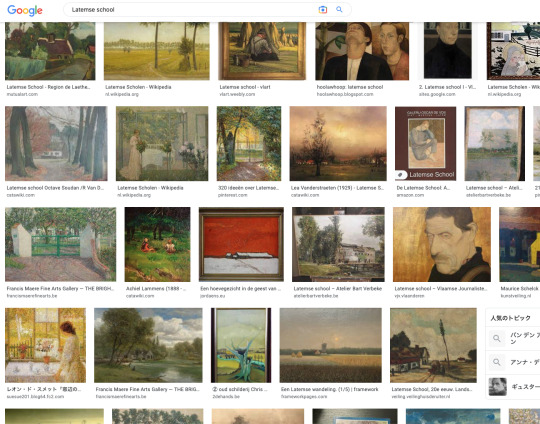
ラーテム派 Latemse school, Latemse Scholen
Latemse school - Google 画像検索
Arts Flanders Japan フランダースの光:ベルギーの美しい村を描いて
19世紀末から20世紀初頭にラーテム村に集った芸術家たちは、その美しい風景と素朴な村人をモデルに数多くの作品を制作しました。彼らは「ラーテム派」と呼ばれ、ベルギー美術史において重要な役割を果たすことになります
ラーテム派は各々の作風こそ個性的なものですが、その根底に共通するのは村人や画家同士の交流を通して見出した心の解放でした。人物や自然を素直な視点をもって表現する、思想にとらわれない自由な感覚こそがラーテム村の芸術の魅力といえるでしょう。
ラーテム村の精神的支柱で象徴主義の彫刻家ジョルジュ・ミンヌ、印象派の影響を受けた光り輝く絵画様式リュミニスムの代表エミール・クラウス、表現主義をベルギーに持ち込んだギュスターヴ・ド・スメットやフリッツ・ヴァン・デン・ベルグ、そしてベルギーへ留学してクラウスに師事した日本人画家・太田喜二郎と児島虎次郎など
0 notes
Text
『ヨーロッパにおける自由主義の歴史』ヴォルフガング・グラッスルの書評
Wolfgang Grassl, “Review of Histoire du liberalisme en Europe,” The Quarterly Journal of Austrian Economics 11, No. 1 (2008): 69–75.
アメリカ学界で教育されるとおりの自由主義思想の標準的歴史によれば、この伝統はギリシア哲学に太古のルーツをもち、ジョン・ロックとアダム・スミス、アメリカ合衆国建国の父らに継続され、十九世紀にイギリスで本領を発揮し、そのとき多かれ少なかれ自由市場経済思想の最後に接した(そこでオーストリア学派村の長が特別な言及を受けてはならない)。それは概して英語圏の伝統であり、経済的パースペクティブに牛耳られた。テーマより時系列で秩序付けられた自由主義についての書籍ではこの還元主義的な歪曲が一層甚だしく、英語の出版物ではほぼ普遍的である。この都合の宜しい(政治的に役立つ)虚構に抗して、マリー・ロスバードとラルフ・レイコ、その他の学者たちは、まことに天晴れ、スコラ学の思想と十七世紀から十八世紀までのフランスとドイツ、そしてイタリアとスペインの思想家、英語圏ではあまり知られていない人物たちから来た重要な衝撃を認識することで挑戦した。今、最も注目すべき概論が、もう一撃、そのみっちり印刷された千四二七ページの重い一冊を加えた。
フィリップ・ネモ教授(パリ経営管理のESCP-EAPヨーロッパ学校)とジャン・プティト教授(社会科学高等研究院とエコール・ポリテクニーク)の指導の下、二〇〇一年から二〇〇五年までの期間にパリで、ヨーロッパ自由主義史についての一連のセミナーが開かれた。八国から集まった三十六人の研究者が三十八本の論文を提出し、これがフランス語原文かフランス語翻訳によってこの書籍で出版された。記事は六部に配列され、自由主義思想の起源と、フランスとイタリア、ドイツ、オーストリア他ヨーロッパ諸国(スペインとポルトガル、ネーデルラント、スウェーデン)での自由主義を扱っている。繰り広げられる著者と主題の幅は、他の出版物からも学ばれうる事柄よりは、典型的ではないことがらに集中する非常に選択的なレビューを必要としている。
編集者は広く一般に信じられている神話の誤りをすっぱ抜く導入を寄稿した。神話とはすなわち、アングロサクソン思想家は自由主義の歴史で特権的な役割を担った。自由主義理念はとにかく人権と民主制の要求の副産物であった。あるいは、人権思想は専らロック派の伝統に根ざしていた。実際には、自由主義思想とはもっと古い醸造のものであり、ギリシア‐ローマの政治的法的伝統とユダヤ‐キリスト教の道徳価値観の中世的総合から生じていた。自由主義の血統書は比類なくヨーロッパ的であるけれども、この大量の思想は「メタ政治的」スタンスを呈し、ゆえに「非常に多様な文化的伝統と文明で採用可能であり、国家がその主権的規制的機能をどう行使してよいかの詳細に関してはかなり中立的である」。骨子は「交易論的自己組織の動態が維持されること」(p. 14)である。ここでのミーゼス的な言用語は紛らわしい――市場を「エコシステム」と見せ、市場参加者の自発性を複雑性の事例とする理念はハイエク派のビンテージである。カント派伝統を、その人格的自由と法の支配、――カントの成句で人間の「非社交的社交性」と表現されるとおりの――多元主義の尊重のゆえに包含することで、編集者はその書籍の全寄稿論文に対する標準を定める。カントはアメリカ・リバタリアン界隈では――おそらく、少なからずは彼の後の追随者ジョン・ロールズのせいで――典型的には「劣った」自由主義者であるとみなされ、彼の権利の強調にもかかわらず、確かにリバタリアンではない。しかしそれは、この書籍は現行のアメリカン・カテゴリーには従わないということである。
この書籍への寄稿において、百人を優に超える個々の思想家が少なくとも或る程度の詳しさで討論される。強調点とアプローチ、意見の相違はもちろんかなりのものであり、これがまとめを寄り合い仕事にしている。しかし、彼ら自由主義者が何を考えたかより、むしろどう考えたかのメタレベルから、鳥の目からこの伝統を見るべきであるとしたら、ヨーロッパ自由主義の多数派の立場の特徴としては、以下の共通点が浮上する。
1 「リベラル」とは歴史的な意味で理解されており、自由の発展に好意的である人々をいう――どんな形容詞(「古典的」)や新語(「リバタリアニズム」)もなしで、まったく申し訳なさそうな素振りを見せ���い。
2 経済的な行動とその他の社会的な側面の間に区別を設けず、ゆえに「財政的」自由主義者(あるいはアメリカ語での「保守主義者」)と「社会的」自由主義者を区別しない。自由とは実際に分割不可能であると扱われる。
3 自由主義思想は多様なヨーロッパ諸国で発達し、社会と文化、政治的境遇の多様性によって深く形成された。イタリアとドイツがまだ国民国家ではなかった十九世紀最初の六十年においては、これらの国々では自由主義者とは法の支配に根ざす国民国家のビジョンに動機付けられた統一運動の最前線にいた。ヨーロッパの多様性はまた自由主義者をしてこの多様性それ自体の維持を主要目標に動機付けさせた。したがって、ヴィルヘルム・フォン・フンボルトならびバンジャマン・コンスタンとアントニオ・ロズミーニ、ベネデット・クローチェ、ホセ・オルテガ・イ・ガセトにとって、自由とは生産と消費、貿易で停まるべきものではなかった。それはまた人格的自由と文化の自由にも相当すべきものである。この背景に照らせば、ドイツとイタリアの自由主義がつねにロックとスミスの「消極的自由」よりも「積極的自由」への強い意向をもっていたことが容易に分かる。
4 自由主義は、ハイエクが強調したとおり(p. 1119)、保守主義と社会主義に並ぶ、政治哲学の三つの古典的立場のうちの一つである。互いに寄り添うことはないが、自由主義思想家はしばしば他の陣営から理念を吸収し、彼らの思想がそれらの方向に引き寄せられることを経験した。
5 自由主義はしばしば過剰に権力を得たカトリック教会への反対の立場をとった。ヨーロッパ自由主義が全般的には人文学的や世俗的であると分類されうるのはこうして説明される。にもかかわらず、カトリック思想家は自由主義思想の発達にプロテスタントなどと同じだけ多く貢献してきた。
6 ヨーロッパ自由主義の発達に対しての(イギリスではなく)アメリカ思想の影響は相対的に地味であり、ピエール・サミュエル・デュポン・ド・ヌムールとアレクシ・ド・トクヴィル、近年の(せいぜい限界的な衝撃の)「リバタリアン」運動とのわずかな繋がりしかなかった。
7 アメリカ保守主義界隈で生まれた啓蒙(特にフランス啓蒙)の見解とは対照的にも、啓蒙思想のほとんどは、人権と、企業と貿易の自由を強調することで自由主義的なのであった。「レッセフェール」の標語の普及者アンヌ=ロベール=ジャック・テュルゴは、スミスと先数世代の自由主義経済思想に強い影響を及ぼす、需要ベース価格理論と市場価格に代わる「自然」価格のような、手に余るほどの多くの理念を導入しただけではなかった。彼はルイ十四世の財務総監として、また政府支出を削減し、ギルド体制を解体し、財産への単一税を導入し、国内穀物交易の制限を廃止した。
8 経済的自由は完全な人間的自由にとって十分条件ではなく必要条件である。相対的に自由な市場は全体主義政権の下でも継続するかもしれないが、自由社会は少なくとも経済的自由を保障しなければ決して可能ではない。したがって自由主義理想は「単なる」経済的自由以上を要求する。個人的権利を要し、この権利を守る法の支配を要し、個人的尊厳の価値を養う文化において、この種のすべてを要するのである。この図は抽象的で還元主義的なホモ・エコノミクスのモデルとはまったく異なっている。実際、(ジョン・スチュアート・ミルに代わる)非経済的擁護が優勢なのはヨーロッパ自由主義の特徴である。
9 もしも自由主義が包括的に理解されるならば、狭い着想の下には入らなかった多くの思想家が含まれるだろう。意見の多元主義と宗教的寛容、個人的責任を提唱した十六世紀と十七世紀の思想家――ミシェル・ド・モンテーニュとフーゴ・グロティウス、ピエール・ベール――は、真理を軽蔑したからではなく、前世紀のカール・ポパーのように、異なる見解の入場が真理の発見に良いチャンスを与えると信じたから、この意味での自由主義者である。
10 自由は民主主義とは、あからさまな反対関係ではなくとも、少なくとも緊張関係にある。幾人かの自由主義者(早期功利主義者、またフライブルク学派)は確かに民主主義の提唱者だったけれども、まず平等主義的で多数主義的なタイプではなかった。それと自由主義理想との両立可能性に懐疑的な、少なくとも同じだけ強い伝統が存在した(ギゾとロワイエ=コラール、コンスタン、トクヴィル、パレート、オルテガ・イ・ガセト、ハイエク)。
オーストリア学派は主にオーストリアにおける自由主義の部に(ヨーク・ギド・フルスマンとフィリップ・ネモ、ジャン・プティト、ロベール・ナドー、ジャン=ピエール・デュピュイ、ダリオ・アンティセリ、ヨセフ・シマ、ロベルタ・モドゥーニョの寄稿で)現れるが、ミハエル・ヴォルフゲムットの記事「ドイツ自由主義に対するオーストリア学派の影響力」にも現れる。フルスマンの寄稿論文はオーストリア経済思想をもっと古いスコラ学派実在論哲学と啓蒙改革主義の伝統に埋め込むが、多文化多言語オーストリア=ハンガリー帝国の特別な挑戦にどう反応したかをも示している。プティトの論文「ハイエクの市場秩序自動組織化理論」はこの書籍で最も異常である。本書に寄稿される他の彼の論文が自由主義の歴史に捧げられているのとは異なり、この理論的論文は「見えざる手」の形式的モデルと進化的ゲーム理論の繋がりを確立する。その議論は明晰で容認可能だが、ゲーム理論モデルがハイエクの市場過程(と様式認識)理論に投げかける光はそれほど明らかではない。モドゥーニョの論文「オーストリア人とアメリカ人リバタリアンの対話」は本書にはややそぐわない。これは概ね、かたや自然法に基礎付けられるとおりの権利と価値の理解、かたや帰結主義的倫理理論、以上についてのアメリカ内の対話を記述している。この討論はその主唱者の幾人かの起源を除けばヨーロッパ自由主義の歴史とほとんど関わりがない。しかしながらこの文脈で最も興味深いのは、ハイエクのフランス理性主義者の「偽の自由主義」に対するイギリス経験主義者の「真の自由主義」嗜好――「人間理性への蔑み」を露呈する選好(pp. 1302f.)――についての、ロスバードとレイコの批判に言及するところである。自由の根底に関するこの論争――人間の無知か人間の本性か――はアメリカ・リバタリアン自家製の論点であるように思われるかもしれないが、実際にはヨーロッパ自由主義思想の発散性の要素に基づいているのである。
本書の主な功績は、伝統的にはこの伝統の文脈には置かれていなかったか祖国の外ではあまり知られていなかった、自由主義史上の人物に当てられるスポットライトにあるかもしれない。ヴィルフレド・パレートを含む自由主義の歴史は少ないが、彼は理論的作品においてもジャーナリストとしても保護主義と社会主義の熱心な反対者であった、とはいえ晩年の社会学著作物では自由主義思想を放棄した(フィリップ・シュタイナー)。イギリス穀物法に抗するリチャード・コブデンの成功裏の闘争に気づいている自由主義研究者は少ないが、この法律は一八四六年に廃止されたし、その一世紀前にはフランスでは似た闘争が先例を作っており、ケネーとテュルゴが自由貿易を提唱していた(フィリップ・シュタイナー)。ほとんどの歴史書はフンボルトにドイツ自由主義思想の始まりを許すが、彼が十八世紀末の「新ドイツ自然法学派」に影響を受けていたことや、ヤーコプ・モーヴィヨンのことを知っているのはわずかであろう(ラルフ・レイコ)。十九世紀イタリア人司祭ルイジ・タパレッリ・ダツェーリョとアントニオ・ロズミーニを耳にしたことがある学者は神学の外では少ないが、彼らはともに自由の哲学者であり、カトリック教人格主義の基礎を設えた。(パオロ・エリティエ)スカンジナビアの外側では、十八世紀自由主義政治家、聖職者兼著述家アンデルス・キデニウスを知る者は少ないが、彼は当時スウェーデンの一部であったフィンランドに生まれ、啓蒙の男で、自由な貿易と産業、自由出版、国家影響力の削減を提唱した(ヨハン・ノルベルク)。フランス人哲学者エティエンヌ・ボノ・コンディヤック神父に気づいている経済学者は少ないが、彼はレッセフェール経済学を支持しながら、スミスの片意地に間違った労働費用説ではなく効用と稀少性に価値を基礎付けた(アラン・ローラン)。リバタリアンはフレデリック・バスティアの作品を継承したベルギー系経済学者ギュスターヴ・ド・モリナリの名に馴染み深いかもしれないが、彼が現在アナルコ資本主義と呼ばれているものを一八四九年の時点ですでに整合的に提唱していたことを知る者は少ない(ミシェル・ルテ)。この書籍が輝かせるヨーロッパ自由主義思想の歴史の虹は実に広く鮮やかである。
この書籍のたった一つの大きな弱点はイギリス伝統の排除にある。編集者は「一般的には非自由主義的とみなされる国々」に集中したいとのことでこれを正当化する(p. 1397)。しかしこれは真実か? スイスとネーデルラント、当時の他の国々(たとえばグリュンダーツァイト期のオーストリア=ハンガリーはおろか、ワイマール共和国期のドイツ)は、同時代のイギリスと同率かそれに近い法の支配と民主的諸制度、自由主義経済政策、社会的寛容を市民に差し出していなかったか? 大陸諸国はほぼすべてがイギリスより先に奴隷制を廃止していなかったか? パリのセミナーが大陸の伝統に焦点を当てたいのは難なく理解できるし、この伝統はフランス人研究科にさえあまり知られていなかったものだ。しかしそれは「最も独創的で最も深遠な理論的貢献は、アングロサクソン諸国ではなく、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスとカール・ポパー、フリードリヒ・アウグスト・ハイエク、マイケル・ポランニー、ハンナ・アーレント、ウォルター・オイケン、ピエロ・ゴベッティ、ブルーノ・レオーニらによって、大陸ヨーロッパから来た」(p. 11)という本書の前提とは整合しない。またもイギリスが、非常に恣意的な仕方で、ヨーロッパから知的に孤立したものとして提示される。決してそうではなかったのだ。イギリス自由主義者と大陸自由主義者の繋がりは甚大であった。アダム・スミスはグロティウスとカンティロン、コンドルセ、モンテスキューから引用したし、デュポン・ド・ヌムールと連絡を取っていた。テュルゴは他の誰よりも彼の経済的著述に影響した。ジョン・スチュアート・ミルはジャン=バティスト・セーの家に留まったし、またグロティウスとコンディヤック、シラー、とりわけフンボルトに影響された。逆の方向にドーバー海峡を渡った多数の影響が本書のページに見受けられる。実際、これらはほとんどイギリス自由主義思想の排除の正当化とは思われない。
他の批判点はほとんどすべて、特定の思想家たちの包含か排除かや、部分的な歴史の切り詰めに関わる。フィジオクラートの包含については良い議論が提出されるかもしれない。彼らの農業生産への執着、個人主義と私有財産、レッセフェール市場システム、自由貿易の提唱だ。しかし、この書籍で考察される最初のフランス人自由主義者が、知的多元主義を信奉したカント哲学者だったが或る点で自由主義に批判的だったシャルル・ルヌーヴィエである理由は、はっきりしない。ベルトラン・ド・ジュヴネルとジャック・リュエフのような英領力のある自由主義知識人はまったく言及されない。ついでに、バンジャマン・コンスタンとスタール夫人はジャン=シャルル=レオナール・シスモンド・ド・シスモンディら「グループ・ド・コペ」のメンバーと同じくスイス生まれであった(フランスではなかった)けれども、生涯の多くをフランスで過ごしたといっていい。実際、本書で言及されなかったアンリ・フレデリック・アルミエルとデニ・ド・ルージュモンのような自由主義思想家とフライジン運動を加えるならば、スイス自由主義伝統への言及は正当化されるだろう。またも、包含と排除は自由主義の着想に依存する。クローチェの有名な区別によれば、リベリズモ(すなわち、功利主義心理学に基づく経済的自由)の伝統か、それとももっと包括的なリベラリズモ(すなわち、倫理的ビジョンに基づくもっと包括的な社会的自由)の伝統か。
この書籍での各章の焦点は個々の主唱者か、自由主義思想家の集団であるから、「大局」はなかなか現れない。しかしこれは欠陥というよりは長所である。というのも自由主義思想とは継続的な事業であり、満ち欠けするのは実際の政治への影響力だけだからである。余所からの鼓吹の有り無しにかかわらず、似た議論が発達したとはいえ、或る期間に重大な発明が持ち込まれた。たとえば、ミーゼスの一九二二年の『社会主義』は社会主義批判の哲学的社会的思想の長い伝統に立脚する。けれどもそれは新しい議論を持ち込みもした――経済効率の議論だ。すなわち、社会主義は需給の(動的)バランスを唯一許す自由な価格形成を妨げる。
多数の著者の寄稿からなるこの長さの書籍は不可避的に多くの疑問を呼び起こす。アクトン卿をイギリスの家系に連ねる議論はほとんどないから、彼はドイツの自由主義伝統に数え入れられるべきか、イタリアか、それとも超民族的カトリック教の伝統か? ノルベルト・ボッビオの「自由社会主義」は本当に依然として自由主義の部分なのか? アンジェロ・トザートの包含に十分な理由はあるのか? 自由主義に対するシスモンディの曖昧な態度は包含を正当化するか?
また、幾人かの著者の良い判断に関する疑問もある。ヨセフ・シマは「チェコ人と『オーストリア人』の理想」で、オーストリア学派のチェコ人メンバー、フランティシェク・チュヘルとカレル・エングリシュに言及する。しかし彼は、自由主義政策を放棄したかどで非難されるヴァツラフ・クラウスからしか自由主義の政治的影響を許さない。実は、十九世紀のボヘミアには畏敬すべき自由主義の潮流があった。もっと度量が大きく、経済的にもそこまで狭くない見解が、プラハ哲学者兼司祭ベルナルド・ボルツァーノの自由主義的な側面であったかもしれない。それはボルツァーノの後の同僚にして、その価値論においてカール・メンガーとオイゲン・フォン・ベーム=バヴェルクの主観的限界的理念を社会ダーウィニズムと結合しようと試みた、クリスティアン・フォン・エーレンフェルスを含めるかもしれない。それは、その国民主義政策よりも哲学的著述のゆえに、チェコスロバキア初代大統領トマーシュ・マサリクまで拡張さえするかもしれない。
セミナーのプレゼンテーションとして予想されなければならないとおり、幾つかの寄稿は他のより大なる重みと高い品質をもつ。幾つかは単なる立場の要約や引用の選集で、他のは正真正銘分析的である。千四二七ページもの書籍はどうやら名前の索引を許さなかったらしいが、これは本の末尾の広範な目次で部分的に償われている欠落である。けれども自由主義思想の貢献者の幾人かの欠落は際立っている。オランダ人人文学者デジデリウス・エラスムスとアイルランド系フランス人経済学者リチャード・カンティロン、ドイツ人歴史家兼詩人フリードリヒ・フォン・シラー、スペイン人外交官兼歴史家サルヴァドール・デ・マダリアーガ、フランス人文芸批評家エミール・ファゲ、ドイツ人牧師兼政治家フリードリヒ・ナウマン、ハンガリー系イギリス人化学者兼哲学者マイケル・ポランニー、フランス人社会学者レーモン・アーロンはその名のわずかな孤立的存在を除けば議論の日の目を見ない。
この書籍はまたヨーロッパ自由主義史の興味深い事実を確認する。低地帯は十八世紀からの商業と草分け的な自由貿易提唱における指導的な役割にもかかわらず、重大な自由主義思想家をグロティウスしか輩出しなかった。唯一の例外は十九世紀オランダ人歴史家兼政治家、ヨハン・ルドルフ・トルベッケであろうが、彼は本書では言及されない。ネーデルラントの貢献は自由主義の思想――あるいはその政治的組織――を二十世紀のかなり及び腰の現象に見せる。
後書きとして、本書は哲学者バリー・スミスの論文「生命の意味と文明の測定」を特集する。その主な主張いわく、生命の意味は人生に「日常を超える」一定の形式を与えることからなる(p. 1406)。この成功の標準は公的で客観的に測定可能ではなければならない(学界の出版物のリスト、発明者の特許、あるいは作曲家に生産された楽譜)。そしたら、諸個人に対して彼ら自身の計画に従い、かくて意味ある人生に至ることを許す際に、自由主義社会秩序は他のいずれよりも優れている。しかしスミスの純粋に形式的な基準は十分だろうか? テロリストは確かに世界を変形し、人生に明瞭な形式を刻み込み、純粋には私的でない測定可能な「意味」を成し遂げることができる。そのような「意味」の創造を容易くする文明は他より優れているのやら。倫理的推理の長い歴史は、メタ倫理学は決して価値と規則の実質的倫理学に成り代わることができないと示している。
それにもかかわらず、貴重な本書の多くの論文は自由主義思想史の関心を発達させ、ひいてはおそらく自由主義秩序の優越を信じるための、十分な理由を差し出している。これまでのほとんどすべての自由主義史は長調でしか主唱者を紹介しなかった。本書は――フランソワ・ギゾとヴィルフレド・パレートのような「右寄り」自由主義者からグイド・カロジェーロとヴィルヘルム・レプケのような「左寄り自由主義者」まで――短調で同じように並べられる多くの声をまとめて持ってくる点にかけて独特である。もちろん、ドクトリネールな拘束具を適用せずに「自由の政党」すべてを包含するようなもっと包括的な自由主義の観念は、この概念を無差別に拡張することにより、結局はこの伝統を平凡化する危険のせいで不利に働くに違いない。本書が示すとおり、自由主義思想の市民はほぼ全員がその物差しの両極のようなカテゴリー化を超えている。実際、自由な諸個人が妨害されずに彼ら自身の計画を追及するという理想は不可分のものなのである。たとえ本書が知性史を体系的作品というよりは選集にしてしまうとしても、まさしくそのような包括的な見解が、どうしても必要とされてきたのだった。願わくは、その長さにもかまわず、この書籍が英訳でも利用可能にならんことを。疑いなく、本書は自由主義思想の歴史と本性に関するアメリカ学界他の捻じ曲がった見解を払いのけてくれる。
0 notes